6 / 15
第2章:記憶螺旋~MEMORL DORL~
Ⅱ
しおりを挟む
翌日もその翌日も、ずっとヒヨリは会いにきた。
彼女はそのたびに地上のものを持ってきてくれた。童話や花やぬいぐるみ、それに地上で使われているという色々なカードも。
「これ、鍵なの。扉の鍵。これを機械に通すと扉が開くのよ」
「こんなにうすっぺらいんだな」
「昔は鉄の棒みたいなの、使ってたの。今もそういうの使ってる人もいるけど」
そういえばこの部屋には扉がない。外と唯一行き来できるのは、いつもヒヨリがやってくるあの天窓だけだ。
「この鍵で、いつも天窓を開けてるのか?」
「あそこは鍵なんてないわ。手で開けるの。コツが必要だけど」
そしてヒヨリは話してくれる。いつものように、地上の様々なことを。
ぼくは地上のことを何も知らない。だからヒヨリは教えてくれる。
ぼくたちのような人間が地上にはいっぱいいて、学校というところもあって、そして人型の機械、ヒューマノイドとかいうものが普及しているのだと。
「人間はその機械がないとやっていけないの」
昔はなんでも自分でやっていたけれど、最近はもうそんなことは考えられないのだそうだ。
どことなく哀しそうに、ヒヨリは言う。
「きみも、その機械を使ってるの?」
「うちは研究所よ。その機械を造る専門の場所なの。だから人よりもいっぱい接触してるわ。オギ知ってるでしょ、あたしのお兄ちゃん。歳はすごく離れてるんだけど、お兄ちゃんは博士なの。いつも機械ばかり造ってるわ」
「オギ」
ぼくは思わず反芻する。
また、その名前だ。
いやそうな顔になっていたのだろう、隣に座っていたヒヨリはぼくを見て首をかしげた。
「どうしてそんな顔、するの?」
「オギに呼ばれるとヒヨリはいつもいなくなる」
するとヒヨリはびっくりして沈黙してしまった。
「───あたしがくると嬉しい? いなくなると哀しい?」
やがてそっとたずねた声は、どこか震えているようだった。気の強い声しか聞いたことがなかったから、ぼくも驚いた。
「だってぼくはヒヨリを待ってるんだ。いつも」
ぼくがそう言うと、ヒヨリはくしゃっと顔を歪めた。
どうしてそんな哀しそうな顔をするのか、ぼくには分からなかった。
それで、前にヒヨリが持ってきた本にあったように、彼女を抱き寄せてみた。
泣いている女の子は、こうするとホッとするんだ。そう書いてあったから。
でもヒヨリはますます泣いた。
「ぼく、謝る?」
謝ったほうが泣きやむんだろうか。
けれどヒヨリはぼくの胸にしがみつき、かぶりを振った。小さな声で何か言ったけれど、聞こえなかった。
ぼくとヒヨリはしばらく離れなかった。
ヒヨリはぼくの胸に顔をうずめたまま動こうとしなかったし、何よりもぼくが彼女を離したくなかった。
「気持ちいいな、ヒヨリは」
ぼくはヒヨリを初めて抱いた。だから、彼女がこんなにあたたかでやわらかいことに気がつかなかったんだ。
ぼくより年上なのにぼくより小さな、ヒヨリの身体。
「あたしがあなたにとって悪い存在だとしたら?」
突然顔を上げて、泣き濡れた顔で彼女は言った。自分自身を責めているような、瞳の色だった。
「それでもあたしを待っててくれるの? これからも、ずっと?」
「どうしてヒヨリが悪い存在なんだ」
ぼくには分からない。
「だってぼくの生活はみんなヒヨリがなきゃいけない」
───ああ、この言葉は違う。
これでは通じない。
彼女に通じない。
でもヒヨリ以外の誰とも喋ったことのないぼくには、それ以上今のこの気持ちを言い表すことができなかった。
ピイッとまた電話が鳴った。ヒヨリがまた保留スイッチを押す。
「じゃあ───」
おずおずと言ったヒヨリの身体が、ふわりと離れかけた。
行ってしまう……!
ぼくは思わずその細い腕をつかんでいた。ひっぱり寄せ、自分でも知らないうちにくちづけていた。
「───!」
腕の中でヒヨリが震えた。ぼくは何度も何度もキスをくり返した。
「胸が痛いんだ」
くり返しながら、ぼくは救いを乞う。
「胸が膨れ上がりそうで痛いんだ。そんな気がする。こんなことは初めてだ、これは何なの? 教えて、ヒヨリ」
「それは、」
ヒヨリは震えながら言った。ぼくの目をしっかり見上げて怯えたように教えてくれた。
「持っちゃいけないものよ。あなたはそんなもの持っちゃいけない」
「どうして?」
「その気持ちを持っていると、殺されるから」
「───その、気持ち……?」
「ナキ。自分で考えて。───どうしてあなたは、あたしにキスしたの」
小さな声。
ヒヨリ───恥ずかしがって、いる?
ぼくは答えた。
「したかったから」
「だから、それはどうして? あたしに他にどんな気持ちを持ってるか教えて」
「抱きたい。守りたい。からかいたい。怒鳴られたい。叱られたい。触れたい」
言葉ごとにヒヨリの顔が赤らんでいく。しまいにはぼくの瞳から視線を外し、床に落としてしまう。
「怒ったのか」
「違う。……それって、恋だわ」
コイ───。
ぼくが、ヒヨリを、好きだということ。
ああ、それで胸が膨れそうになるんだ。痛む気がするんだ。それなら納得できる。
ぼくは、確かにヒヨリのことが好きだから。
ヒヨリとずっと一緒にいること───それが、ぼくの、夢だから。
彼女はそのたびに地上のものを持ってきてくれた。童話や花やぬいぐるみ、それに地上で使われているという色々なカードも。
「これ、鍵なの。扉の鍵。これを機械に通すと扉が開くのよ」
「こんなにうすっぺらいんだな」
「昔は鉄の棒みたいなの、使ってたの。今もそういうの使ってる人もいるけど」
そういえばこの部屋には扉がない。外と唯一行き来できるのは、いつもヒヨリがやってくるあの天窓だけだ。
「この鍵で、いつも天窓を開けてるのか?」
「あそこは鍵なんてないわ。手で開けるの。コツが必要だけど」
そしてヒヨリは話してくれる。いつものように、地上の様々なことを。
ぼくは地上のことを何も知らない。だからヒヨリは教えてくれる。
ぼくたちのような人間が地上にはいっぱいいて、学校というところもあって、そして人型の機械、ヒューマノイドとかいうものが普及しているのだと。
「人間はその機械がないとやっていけないの」
昔はなんでも自分でやっていたけれど、最近はもうそんなことは考えられないのだそうだ。
どことなく哀しそうに、ヒヨリは言う。
「きみも、その機械を使ってるの?」
「うちは研究所よ。その機械を造る専門の場所なの。だから人よりもいっぱい接触してるわ。オギ知ってるでしょ、あたしのお兄ちゃん。歳はすごく離れてるんだけど、お兄ちゃんは博士なの。いつも機械ばかり造ってるわ」
「オギ」
ぼくは思わず反芻する。
また、その名前だ。
いやそうな顔になっていたのだろう、隣に座っていたヒヨリはぼくを見て首をかしげた。
「どうしてそんな顔、するの?」
「オギに呼ばれるとヒヨリはいつもいなくなる」
するとヒヨリはびっくりして沈黙してしまった。
「───あたしがくると嬉しい? いなくなると哀しい?」
やがてそっとたずねた声は、どこか震えているようだった。気の強い声しか聞いたことがなかったから、ぼくも驚いた。
「だってぼくはヒヨリを待ってるんだ。いつも」
ぼくがそう言うと、ヒヨリはくしゃっと顔を歪めた。
どうしてそんな哀しそうな顔をするのか、ぼくには分からなかった。
それで、前にヒヨリが持ってきた本にあったように、彼女を抱き寄せてみた。
泣いている女の子は、こうするとホッとするんだ。そう書いてあったから。
でもヒヨリはますます泣いた。
「ぼく、謝る?」
謝ったほうが泣きやむんだろうか。
けれどヒヨリはぼくの胸にしがみつき、かぶりを振った。小さな声で何か言ったけれど、聞こえなかった。
ぼくとヒヨリはしばらく離れなかった。
ヒヨリはぼくの胸に顔をうずめたまま動こうとしなかったし、何よりもぼくが彼女を離したくなかった。
「気持ちいいな、ヒヨリは」
ぼくはヒヨリを初めて抱いた。だから、彼女がこんなにあたたかでやわらかいことに気がつかなかったんだ。
ぼくより年上なのにぼくより小さな、ヒヨリの身体。
「あたしがあなたにとって悪い存在だとしたら?」
突然顔を上げて、泣き濡れた顔で彼女は言った。自分自身を責めているような、瞳の色だった。
「それでもあたしを待っててくれるの? これからも、ずっと?」
「どうしてヒヨリが悪い存在なんだ」
ぼくには分からない。
「だってぼくの生活はみんなヒヨリがなきゃいけない」
───ああ、この言葉は違う。
これでは通じない。
彼女に通じない。
でもヒヨリ以外の誰とも喋ったことのないぼくには、それ以上今のこの気持ちを言い表すことができなかった。
ピイッとまた電話が鳴った。ヒヨリがまた保留スイッチを押す。
「じゃあ───」
おずおずと言ったヒヨリの身体が、ふわりと離れかけた。
行ってしまう……!
ぼくは思わずその細い腕をつかんでいた。ひっぱり寄せ、自分でも知らないうちにくちづけていた。
「───!」
腕の中でヒヨリが震えた。ぼくは何度も何度もキスをくり返した。
「胸が痛いんだ」
くり返しながら、ぼくは救いを乞う。
「胸が膨れ上がりそうで痛いんだ。そんな気がする。こんなことは初めてだ、これは何なの? 教えて、ヒヨリ」
「それは、」
ヒヨリは震えながら言った。ぼくの目をしっかり見上げて怯えたように教えてくれた。
「持っちゃいけないものよ。あなたはそんなもの持っちゃいけない」
「どうして?」
「その気持ちを持っていると、殺されるから」
「───その、気持ち……?」
「ナキ。自分で考えて。───どうしてあなたは、あたしにキスしたの」
小さな声。
ヒヨリ───恥ずかしがって、いる?
ぼくは答えた。
「したかったから」
「だから、それはどうして? あたしに他にどんな気持ちを持ってるか教えて」
「抱きたい。守りたい。からかいたい。怒鳴られたい。叱られたい。触れたい」
言葉ごとにヒヨリの顔が赤らんでいく。しまいにはぼくの瞳から視線を外し、床に落としてしまう。
「怒ったのか」
「違う。……それって、恋だわ」
コイ───。
ぼくが、ヒヨリを、好きだということ。
ああ、それで胸が膨れそうになるんだ。痛む気がするんだ。それなら納得できる。
ぼくは、確かにヒヨリのことが好きだから。
ヒヨリとずっと一緒にいること───それが、ぼくの、夢だから。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


カラー・マン
上杉 裕泉 (Yusen Uesugi)
SF
とある金曜日の夕方のこと。週末のゴルフの予定を楽しみにする朝倉祐二外務省長官のもとに、一人の対外惑星大使が現れる。その女性――水野は、ウルサゴ人と適切な関係を築くため、彼らの身にまとう色を覚えろと言う。朝倉は、機械の力と特訓により見違えるように色を見分けることのができるようになり、ついに親睦パーティーへと乗り込むのだが……




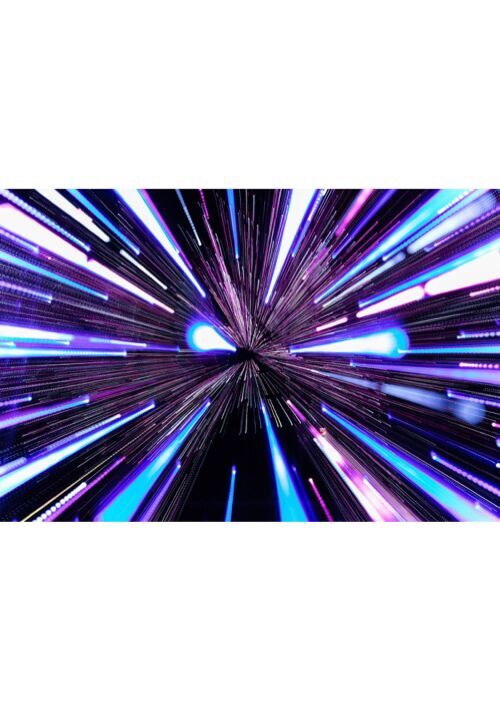
【総集編】未来予測短編集
Grisly
SF
⭐︎登録お願いします。未来はこうなる!
当たったら恐ろしい、未来予測達。
SF短編小説。ショートショート集。
これだけ出せば
1つは当たるかも知れません笑

鉄籠の中の愛
百合桜餅
SF
巨大な鉄の壁で覆われた『都市』にて暮らすリアラとアスカは、様々な場所を漁って物を得て暮らす『漁り屋』だった。
彼女たちは都市の中央に位置する『タワー』に移送される謎の存在に目を付け、ソレの奪取に奇跡的に成功する。
仰々しい箱を開き、中を確かめるとそこには……人。
いや、人に似た何か。AI搭載型最新ヒューマノイドがそこには居た。
ヒューマノイド……彼女には、名前が付けられた。
『アイ』
リアラとアスカ、そしてアイの傍には、そろりそろりと、
破滅の足音が近づいていた。
※過激な表現や設定があるかも。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















