お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

絆の輪舞曲〜ロンド〜
Ⅶ.a
児童書・童話
キャラクター構成
主人公:水谷 陽太(みずたに ようた)
- 年齢:30歳
- 職業:小説家
- 性格:おっとりしていて感受性豊かだが、少々抜けているところもある。
- 背景:幼少期に両親を失い、叔母の家で育つ。小説家としては成功しているが、人付き合いが苦手。
ヒロイン:白石 瑠奈(しらいし るな)
- 年齢:28歳
- 職業:刑事
- 性格:強気で頭の回転が速いが、情に厚く家族思い。
- 背景:警察一家に生まれ育ち、父親の影響で刑事の道を選ぶ。兄が失踪しており、その謎を追っている。
親友:鈴木 健太(すずき けんた)
- 年齢:30歳
- 職業:弁護士
- 性格:冷静で理知的だが、友人思いの一面も持つ。
- 背景:大学時代から陽太の親友。過去に大きな挫折を経験し、そこから立ち直った経緯がある。
謎の人物:黒崎 直人(くろさき なおと)
- 年齢:35歳
- 職業:実業家
- 性格:冷酷で謎めいているが、実は深い孤独を抱えている。
- 背景:成功した実業家だが、その裏には多くの謎と秘密が隠されている。瑠奈の兄の失踪にも関与している可能性がある。
水谷陽太は、小説家としての成功を手にしながらも、幼少期のトラウマと向き合う日々を送っていた。そんな彼の前に現れたのは、刑事の白石瑠奈。瑠奈は失踪した兄の行方を追う中で、陽太の小説に隠された手がかりに気付く。二人は次第に友情と信頼を深め、共に真相を探り始める。
一方で、陽太の親友で弁護士の鈴木健太もまた、過去の挫折から立ち直り、二人をサポートする。しかし、彼らの前には冷酷な実業家、黒崎直人が立ちはだかる。黒崎は自身の目的のために、様々な手段を駆使して二人を翻弄する。
サスペンスフルな展開の中で明かされる真実、そしてそれぞれの絆が試される瞬間。笑いあり、涙ありの壮大なサクセスストーリーが、読者を待っている。絆と運命に導かれた物語、「絆の輪舞曲(ロンド)」で、あなたも彼らの冒険に参加してみませんか?

山姥(やまんば)
野松 彦秋
児童書・童話
小学校5年生の仲良し3人組の、テッカ(佐上哲也)、カッチ(野田克彦)、ナオケン(犬塚直哉)。
実は3人とも、同じクラスの女委員長の松本いずみに片思いをしている。
小学校の宿泊研修を楽しみにしていた4人。ある日、宿泊研修の目的地が3枚の御札の昔話が生まれた山である事が分かる。
しかも、10年前自分達の学校の先輩がその山で失踪していた事実がわかる。
行方不明者3名のうち、一人だけ帰って来た先輩がいるという事を知り、興味本位でその人に会いに行く事を思いつく3人。
3人の意中の女の子、委員長松本いずみもその計画に興味を持ち、4人はその先輩に会いに行く事にする。
それが、恐怖の夏休みの始まりであった。
山姥が実在し、4人に危険が迫る。
4人は、信頼する大人達に助けを求めるが、その結果大事な人を失う事に、状況はどんどん悪くなる。
山姥の執拗な追跡に、彼らは生き残る事が出来るのか!

オレの師匠は職人バカ。~ル・リーデル宝石工房物語~
若松だんご
児童書・童話
街の中心からやや外れたところにある、「ル・リーデル宝石工房」
この工房には、新進気鋭の若い師匠とその弟子の二人が暮らしていた。
南の国で修行してきたという師匠の腕は決して悪くないのだが、街の人からの評価は、「地味。センスがない」。
仕事の依頼もなく、注文を受けることもない工房は常に貧乏で、薄い塩味豆だけスープしか食べられない。
「決めた!! この石を使って、一世一代の宝石を作り上げる!!」
貧乏に耐えかねた師匠が取り出したのは、先代が遺したエメラルドの原石。
「これ、使うのか?」
期待と不安の混じった目で石と師匠を見る弟子のグリュウ。
この石には無限の可能性が秘められてる。
興奮気味に話す師匠に戸惑うグリュウ。
石は本当に素晴らしいのか? クズ石じゃないのか? 大丈夫なのか?
――でも、完成するのがすっげえ楽しみ。
石に没頭すれば、周囲が全く見えなくなる職人バカな師匠と、それをフォローする弟子の小さな物語


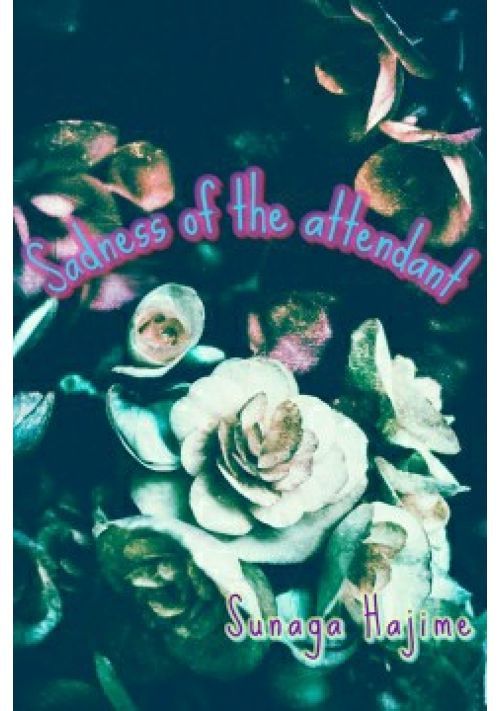
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

おっとりドンの童歌
花田 一劫
児童書・童話
いつもおっとりしているドン(道明寺僚) が、通学途中で暴走車に引かれてしまった。
意識を失い気が付くと、この世では見たことのない奇妙な部屋の中。
「どこ。どこ。ここはどこ?」と自問していたら、こっちに雀が近づいて来た。
なんと、その雀は歌をうたい狂ったように踊って(跳ねて)いた。
「チュン。チュン。はあ~。らっせーら。らっせいら。らせらせ、らせーら。」と。
その雀が言うことには、ドンが死んだことを(津軽弁や古いギャグを交えて)伝えに来た者だという。
道明寺が下の世界を覗くと、テレビのドラマで観た昔話の風景のようだった。
その中には、自分と瓜二つのドン助や同級生の瓜二つのハナちゃん、ヤーミ、イート、ヨウカイ、カトッぺがいた。
みんながいる村では、ヌエという妖怪がいた。
ヌエとは、顔は鬼、身体は熊、虎の手や足をもち、何とシッポの先に大蛇の頭がついてあり、人を食べる恐ろしい妖怪のことだった。
ある時、ハナちゃんがヌエに攫われて、ドン助とヤーミがヌエを退治に行くことになるが、天界からドラマを観るように楽しんで鑑賞していた道明寺だったが、道明寺の体は消え、意識はドン助の体と同化していった。
ドン助とヤーミは、ハナちゃんを救出できたのか?恐ろしいヌエは退治できたのか?

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















