8 / 10
8.誰かではない
しおりを挟む
アラームではなく、着信音で目が覚めた。枕元へと手を伸ばすが、明るくなった画面に着信を示すものは何もない。
「百瀬、ケータイ、鳴ってる」
ベッドの上から声をかければ、丸まっていた背中が一瞬で伸びる。「すみません!」と床に転がっていたスマートフォンを手に取り、その場で正座する。あまりにも素早い動きに驚いていると、
「お世話になっております」
百瀬が仕事の表情になった。取引先だろうか。土曜日なのに? 訝しんでいると、今度は百瀬のカバンから振動音が響く。
百瀬が口パクで「社用です」と伝えてくる。外ポケットに入っていたそれを取り出せば、画面には木崎の名前が出ていた。
「……おはようございます。津島です。すみません、百瀬はべつの電話に出ていて」
「――今から会社に来るよう伝えて」
「何かトラブルですか」
「来ればわかる」
そう言うと木崎は一方的に通話を終了させた。こちらの都合など確かめもせず。
「来ればわかるって……」
自分も行くべきだろうか。内容がわからないので判断できない。
「津島さん」
通話を終えた百瀬が、声に緊張を滲ませる。
「ファンゲームの中村さんからだったんですけど」
半分以上ライトが落とされたフロアを歩く。新入社員研修や株主総会の準備などが重なるこの時期、休日出勤するのは人事部と総務部がほとんどだ。その奥に三課の島がある。百瀬と二人で木崎の席へと向かえば、挨拶もなく簡潔に状況を説明される。
「配送中にグッズの一部が破損した」
「配送トラブルですか」
「そうだ。使った業者が悪かった。うちの指定業者じゃない。案内はどうなってる?」
搬入には指定業者を使ってもらい、営業所から一括で運び入れることになっている。
「案内には記載してありますが」
「確認は入れなかったのか」
被せるように尋ねられ、言葉に詰まる。ほかの企業を含め、そこまでの確認はしていない。だが、ファンゲームはイベント自体が初参加だ。それを踏まえた上でのフォローが必要だったということだろう。
「――す」
「すみません。自分が言うべきでした」
俺が頭を下げるより早く、百瀬が大きな体を勢いよく曲げた。確かに百瀬なら言う機会はあっただろう。ファンゲームからの連絡は常に百瀬宛てだった。でも、きっとそれは俺のせいでもある。
「すみません。俺が確認するべきでした」
求められていなくても、担当者であることに変わりはない。それなのに俺は、相手の都合に合わせるだけで自分からは動かず、必要なフォローを見逃した。
「起きたことは仕方ない。大事なのは明日のイベントをどうするか。破損は三分の一程度らしい」
「無事なのは三分の二……。と言っても、ファンゲームさんはもともとの数量が少ないですよね。いっそゲームの景品として使うのは……無理ですよね。物販情報出てますし」
「物販として見込んだ利益もゼロになるしな」
「破損したものは使えないですよね。品質にはこだわっているでしょうし」
「そうだな」
目の前を過ぎていく会話。聞くことしかできない自分。このトラブルをどうすべきか考えなくてはならないのに、言葉は何も出てこない。
中村さんが相談したのは木崎と百瀬で、木崎が呼んだのは百瀬で。俺は初めから頼りにされてすらいない。俺がここにいることを望むひとなんて誰もいないし、俺の意見なんて必要ないのかもしれない。
でも、だからといって投げ出していいわけじゃない。与えられるのを、誰かの答えを待っているからダメなんだ。ここにいる意味は自分で作るしかない。
そっと息を吸い込み、考えを組み立てる。品質へのこだわり。リアリティの追及。明日までに取れる手段。うちだからできること。うちにしかできないこと……。
「――うちで補修しましょう」
「補修?」
「破損を活かした補修にするんです。修理スペースで行うのは可能ですよね。それに」
「津島」
説明を遮った木崎が電話へと視線を向ける。
「中村さん、説得しろ。責任は俺が取る」
デザインから販売まで全工程を自社で行っているところだ。誰かの手が入ることをよくは思わないだろう。でも、それだけこだわる意味は百瀬が教えてくれた。
「――やってみます」
信頼には届かなくても。誰かの意見ではない、自分の言葉で今度こそ伝えたい。それが今の俺にできる『津島にしかできないこと』だと思うから。
呼び出し音は二回で途切れる。名前を告げれば、中村さんの声がわずかに強張った。期待していた相手ではないというのが伝わってくる。それでも、もう逃げたくない。
「破損した商材ですが、弊社で補修させていただけないでしょうか」
「補修程度でどうにかなる問題では」
「補修はあくまでケガなどの事故を防ぐためのものです」
「それではうちの商品として出せません」
「ええ、『ファンゲームのグッズを弊社が補修したもの』になります。ですが、今回のグッズであれば、リアリティの追及という方向になるのではないでしょうか」
「今回の……」
「はい、今回のゲームの特性です。それと、補修分についてはこちらですべて買い取り致します。修理スペースの宣伝になりますので」
「――なるほど」
表情は見えない。吹き出しを確かめることはできない。それでも伝わってくる。中村さんがこちらの言葉を真剣に受け止めてくれているのが。見えるかどうかじゃない。大事なのは、相手をわかりたいと思うかどうかだ。
「どうでしょうか」
「わかりました。……本物のゾンビらしく仕上げてくださいね」
通話が切れると同時、肩から力が抜ける。早く報告しなくては、と顔を上げれば、二人とも電話中だった。ちょうど受話器を置いた百瀬と目が合う。
「お疲れ様です。担当者にはもう連絡済みです」
「え?」
「津島さんが話し始めたタイミングで『関係各所に連絡しろ』って課長が。津島さんなら説得できるって、確信していたみたいです」
木崎へと視線を向ければ、業務中にしては珍しく口元が笑ったように見えた。
押し慣れた自動販売機のボタンに触れる。木崎に「コーヒー買ってきて」と言われ、百瀬と休憩室に来た。二人で、とわざわざ付け足したのは「休憩しろ」という意味だろう。
「あれ、津島じゃん」
「お疲れ様です」
ガラス扉を開いたのは総務の畑中先輩だった。百瀬も「お疲れ様です」と挨拶する。
「そっちも休日出勤なの?」
隣の自動販売機に立ち、振り向くことなく尋ねられる。
「もう解決しましたが、ちょっとトラブルがありまして」
「そうなんだ」
話を振ってきたわりに興味のなさそうな相槌だった。早くコーヒーできないかな。百瀬の手にある紙コップはまだひとつだ。
「津島、優秀だもんな」
そんな、と答えるより早く言葉が続く。
「詳しく説明しなくても理解できるし、言いたいこと汲み取るのが早いし、ほんと手のかからない後輩だったわ」
褒めてはいない。声に滲むのはそんな温かな感情ではない。吹き出しなんて見なくてもわかる。
「畑中さんの教え方がよかったからですよ」
ランプが灯るのと同時に扉を開け、百瀬に手渡せば、空気を読んだのか「先に戻りますね」と出ていく。
新しくセットされた紙コップにコーヒーはまだ落ちてこない。
「頭の中見られてるみたいで、気持ち悪かったけど」
わずかに変化した声。顔を向ければ、今日初めて目が合い、吹き出しが作られる。
――なんでお前なんだよ。
「まー、もしそんな能力あったら、三課に行ってたのは俺だったかもな」
明るく笑いを含ませた声だが、目は笑っていない。頭上には『俺が企画に行きたかったのに』と浮かんでいる。
「津島は企画、行きたかったの?」
射貫くような視線を向けられ、言葉が喉に詰まる。自分で望んだわけじゃなかった。企画に行きたいなんて思ったこともなかった。
「行きたくなかったのに選ばれちゃった?」
――どうして自分なのかと思った。経験はない。企画は通らない。取引先の信頼も得られない。ちっとも自分には合っていない。ずっと苦しいだけで、いいことなんてひとつもなかった。
「そんな苦しそうな顔するならさ、今からでも俺と変わる? 津島も総務に戻りたいんじゃない?」
総務に戻ったら、きっとこの苦しさからは逃れられる。周りの望む自分になれる。上手く立ち回れる。三課のみんなもそれを望んでいるのかもしれない。――でも、俺はもう「誰か」の望む自分でいたくない。
俺がいたいと思う場所は俺が決める。
「いえ、僕は」
「それはできないな」
声が重なると同時、風が流れてくる。木崎は注ぎ終わっていたコーヒーを取り出し、俺に手渡した。指先からじわりと熱が滲み込む。
「俺が津島を手放すつもりないから」
「津島のことすごく買ってるんですね。……もともと知り合いだった、とか?」
木崎が着任したのはこの四月で、俺以外は企画に関係のある部署から集められている。何か理由があると考えるのは自然なことだった。出身大学なんて調べればすぐにわかる。木崎は躊躇いなく「そうだけど」と答えた。
「なんだ、そういうことか」
畑中先輩が木崎ではなく、俺を見る。
「――ズルいな」
落とされた言葉に、吹き出しを見ることすらできない。重りを沈められたかのように体が動かなくなる。否定なんてできない。他人ができないことをできてしまう自分は――心が読めてしまう俺は、ずっと「ズル」をしている。ズルをして信頼をもらい、ズルをして関係を築き、ズルをして自分を作っている。
「ズルい、か。俺が会長の孫だっていうのもズルだと思う?」
「それは」
「能力、家柄、環境……『普通』じゃない、というのが『ズル』だとして、それだけで全部うまくいくとでも?」
木崎は表情を変えることなく、淡々と言葉を紡いでいく。
「特別な何かを持っていても、ただ持っているだけで特別になれるわけじゃない。今の俺があるのは、俺が動いた結果だし、今の君も、君が今までやってきた結果だろう。津島が今三課にいるのだって、俺と知り合いだったというだけじゃない」
「じゃあ、津島を選んだ理由は何ですか」
「津島ほど周りが見えるやつを俺は知らない」
表情も声も変わらないのに。木崎の言葉が、俺の内側に熱を広げ、重りを掬い取る。
「一緒に働いたことがある人間なら、知ってると思ったけど」
君は違うの? 落とされた言葉に、畑中先輩は何も答えなかった。
「百瀬、ケータイ、鳴ってる」
ベッドの上から声をかければ、丸まっていた背中が一瞬で伸びる。「すみません!」と床に転がっていたスマートフォンを手に取り、その場で正座する。あまりにも素早い動きに驚いていると、
「お世話になっております」
百瀬が仕事の表情になった。取引先だろうか。土曜日なのに? 訝しんでいると、今度は百瀬のカバンから振動音が響く。
百瀬が口パクで「社用です」と伝えてくる。外ポケットに入っていたそれを取り出せば、画面には木崎の名前が出ていた。
「……おはようございます。津島です。すみません、百瀬はべつの電話に出ていて」
「――今から会社に来るよう伝えて」
「何かトラブルですか」
「来ればわかる」
そう言うと木崎は一方的に通話を終了させた。こちらの都合など確かめもせず。
「来ればわかるって……」
自分も行くべきだろうか。内容がわからないので判断できない。
「津島さん」
通話を終えた百瀬が、声に緊張を滲ませる。
「ファンゲームの中村さんからだったんですけど」
半分以上ライトが落とされたフロアを歩く。新入社員研修や株主総会の準備などが重なるこの時期、休日出勤するのは人事部と総務部がほとんどだ。その奥に三課の島がある。百瀬と二人で木崎の席へと向かえば、挨拶もなく簡潔に状況を説明される。
「配送中にグッズの一部が破損した」
「配送トラブルですか」
「そうだ。使った業者が悪かった。うちの指定業者じゃない。案内はどうなってる?」
搬入には指定業者を使ってもらい、営業所から一括で運び入れることになっている。
「案内には記載してありますが」
「確認は入れなかったのか」
被せるように尋ねられ、言葉に詰まる。ほかの企業を含め、そこまでの確認はしていない。だが、ファンゲームはイベント自体が初参加だ。それを踏まえた上でのフォローが必要だったということだろう。
「――す」
「すみません。自分が言うべきでした」
俺が頭を下げるより早く、百瀬が大きな体を勢いよく曲げた。確かに百瀬なら言う機会はあっただろう。ファンゲームからの連絡は常に百瀬宛てだった。でも、きっとそれは俺のせいでもある。
「すみません。俺が確認するべきでした」
求められていなくても、担当者であることに変わりはない。それなのに俺は、相手の都合に合わせるだけで自分からは動かず、必要なフォローを見逃した。
「起きたことは仕方ない。大事なのは明日のイベントをどうするか。破損は三分の一程度らしい」
「無事なのは三分の二……。と言っても、ファンゲームさんはもともとの数量が少ないですよね。いっそゲームの景品として使うのは……無理ですよね。物販情報出てますし」
「物販として見込んだ利益もゼロになるしな」
「破損したものは使えないですよね。品質にはこだわっているでしょうし」
「そうだな」
目の前を過ぎていく会話。聞くことしかできない自分。このトラブルをどうすべきか考えなくてはならないのに、言葉は何も出てこない。
中村さんが相談したのは木崎と百瀬で、木崎が呼んだのは百瀬で。俺は初めから頼りにされてすらいない。俺がここにいることを望むひとなんて誰もいないし、俺の意見なんて必要ないのかもしれない。
でも、だからといって投げ出していいわけじゃない。与えられるのを、誰かの答えを待っているからダメなんだ。ここにいる意味は自分で作るしかない。
そっと息を吸い込み、考えを組み立てる。品質へのこだわり。リアリティの追及。明日までに取れる手段。うちだからできること。うちにしかできないこと……。
「――うちで補修しましょう」
「補修?」
「破損を活かした補修にするんです。修理スペースで行うのは可能ですよね。それに」
「津島」
説明を遮った木崎が電話へと視線を向ける。
「中村さん、説得しろ。責任は俺が取る」
デザインから販売まで全工程を自社で行っているところだ。誰かの手が入ることをよくは思わないだろう。でも、それだけこだわる意味は百瀬が教えてくれた。
「――やってみます」
信頼には届かなくても。誰かの意見ではない、自分の言葉で今度こそ伝えたい。それが今の俺にできる『津島にしかできないこと』だと思うから。
呼び出し音は二回で途切れる。名前を告げれば、中村さんの声がわずかに強張った。期待していた相手ではないというのが伝わってくる。それでも、もう逃げたくない。
「破損した商材ですが、弊社で補修させていただけないでしょうか」
「補修程度でどうにかなる問題では」
「補修はあくまでケガなどの事故を防ぐためのものです」
「それではうちの商品として出せません」
「ええ、『ファンゲームのグッズを弊社が補修したもの』になります。ですが、今回のグッズであれば、リアリティの追及という方向になるのではないでしょうか」
「今回の……」
「はい、今回のゲームの特性です。それと、補修分についてはこちらですべて買い取り致します。修理スペースの宣伝になりますので」
「――なるほど」
表情は見えない。吹き出しを確かめることはできない。それでも伝わってくる。中村さんがこちらの言葉を真剣に受け止めてくれているのが。見えるかどうかじゃない。大事なのは、相手をわかりたいと思うかどうかだ。
「どうでしょうか」
「わかりました。……本物のゾンビらしく仕上げてくださいね」
通話が切れると同時、肩から力が抜ける。早く報告しなくては、と顔を上げれば、二人とも電話中だった。ちょうど受話器を置いた百瀬と目が合う。
「お疲れ様です。担当者にはもう連絡済みです」
「え?」
「津島さんが話し始めたタイミングで『関係各所に連絡しろ』って課長が。津島さんなら説得できるって、確信していたみたいです」
木崎へと視線を向ければ、業務中にしては珍しく口元が笑ったように見えた。
押し慣れた自動販売機のボタンに触れる。木崎に「コーヒー買ってきて」と言われ、百瀬と休憩室に来た。二人で、とわざわざ付け足したのは「休憩しろ」という意味だろう。
「あれ、津島じゃん」
「お疲れ様です」
ガラス扉を開いたのは総務の畑中先輩だった。百瀬も「お疲れ様です」と挨拶する。
「そっちも休日出勤なの?」
隣の自動販売機に立ち、振り向くことなく尋ねられる。
「もう解決しましたが、ちょっとトラブルがありまして」
「そうなんだ」
話を振ってきたわりに興味のなさそうな相槌だった。早くコーヒーできないかな。百瀬の手にある紙コップはまだひとつだ。
「津島、優秀だもんな」
そんな、と答えるより早く言葉が続く。
「詳しく説明しなくても理解できるし、言いたいこと汲み取るのが早いし、ほんと手のかからない後輩だったわ」
褒めてはいない。声に滲むのはそんな温かな感情ではない。吹き出しなんて見なくてもわかる。
「畑中さんの教え方がよかったからですよ」
ランプが灯るのと同時に扉を開け、百瀬に手渡せば、空気を読んだのか「先に戻りますね」と出ていく。
新しくセットされた紙コップにコーヒーはまだ落ちてこない。
「頭の中見られてるみたいで、気持ち悪かったけど」
わずかに変化した声。顔を向ければ、今日初めて目が合い、吹き出しが作られる。
――なんでお前なんだよ。
「まー、もしそんな能力あったら、三課に行ってたのは俺だったかもな」
明るく笑いを含ませた声だが、目は笑っていない。頭上には『俺が企画に行きたかったのに』と浮かんでいる。
「津島は企画、行きたかったの?」
射貫くような視線を向けられ、言葉が喉に詰まる。自分で望んだわけじゃなかった。企画に行きたいなんて思ったこともなかった。
「行きたくなかったのに選ばれちゃった?」
――どうして自分なのかと思った。経験はない。企画は通らない。取引先の信頼も得られない。ちっとも自分には合っていない。ずっと苦しいだけで、いいことなんてひとつもなかった。
「そんな苦しそうな顔するならさ、今からでも俺と変わる? 津島も総務に戻りたいんじゃない?」
総務に戻ったら、きっとこの苦しさからは逃れられる。周りの望む自分になれる。上手く立ち回れる。三課のみんなもそれを望んでいるのかもしれない。――でも、俺はもう「誰か」の望む自分でいたくない。
俺がいたいと思う場所は俺が決める。
「いえ、僕は」
「それはできないな」
声が重なると同時、風が流れてくる。木崎は注ぎ終わっていたコーヒーを取り出し、俺に手渡した。指先からじわりと熱が滲み込む。
「俺が津島を手放すつもりないから」
「津島のことすごく買ってるんですね。……もともと知り合いだった、とか?」
木崎が着任したのはこの四月で、俺以外は企画に関係のある部署から集められている。何か理由があると考えるのは自然なことだった。出身大学なんて調べればすぐにわかる。木崎は躊躇いなく「そうだけど」と答えた。
「なんだ、そういうことか」
畑中先輩が木崎ではなく、俺を見る。
「――ズルいな」
落とされた言葉に、吹き出しを見ることすらできない。重りを沈められたかのように体が動かなくなる。否定なんてできない。他人ができないことをできてしまう自分は――心が読めてしまう俺は、ずっと「ズル」をしている。ズルをして信頼をもらい、ズルをして関係を築き、ズルをして自分を作っている。
「ズルい、か。俺が会長の孫だっていうのもズルだと思う?」
「それは」
「能力、家柄、環境……『普通』じゃない、というのが『ズル』だとして、それだけで全部うまくいくとでも?」
木崎は表情を変えることなく、淡々と言葉を紡いでいく。
「特別な何かを持っていても、ただ持っているだけで特別になれるわけじゃない。今の俺があるのは、俺が動いた結果だし、今の君も、君が今までやってきた結果だろう。津島が今三課にいるのだって、俺と知り合いだったというだけじゃない」
「じゃあ、津島を選んだ理由は何ですか」
「津島ほど周りが見えるやつを俺は知らない」
表情も声も変わらないのに。木崎の言葉が、俺の内側に熱を広げ、重りを掬い取る。
「一緒に働いたことがある人間なら、知ってると思ったけど」
君は違うの? 落とされた言葉に、畑中先輩は何も答えなかった。
11
お気に入りに追加
16
あなたにおすすめの小説



愛なんかなかった
拓海のり
BL
直樹は振られた女の結婚式で磯崎に会った。その後、会社の接待で饗応の相手に使われた直樹は女性に性欲を感じなくなった。ある日そういう嗜好の男が行くバーで磯崎に再会する。
リーマン、俺様傲慢攻め×流され受け。総受け。三万字ちょいのお話です。
※ 傲慢俺様攻めです。合わない方は即閉じお願いします。

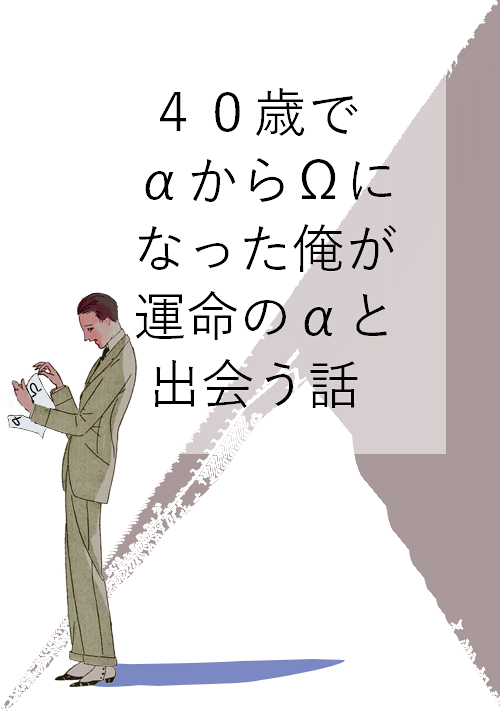
40歳でαからΩになった俺が運命のαに出会う話
深山恐竜
BL
αとして40年間生きてきた俺は、ある日『突発性Ω化症候群』と診断され、Ωになった。俺は今更Ωとしての人生を受け入れられず、Ωであることを隠して生きることを決めた。
しかし、運命のαである久慈充と出会ったことで俺の生活は一変した。久慈は俺が経営する会社を買収し、俺にΩとしての義務を迫るが、俺には嘘偽りなくαとして生きた40年間と、矜持があるんだ!
(18歳α×42歳Ω)
オメガバース設定をお借りしています。妊娠出産有り。
(ムーンライトノベルズ様にも掲載中)


【完結】スーツ男子の歩き方
SAI
BL
イベント会社勤務の羽山は接待が続いて胃を壊しながらも働いていた。そんな中、4年付き合っていた彼女にも振られてしまう。
胃は痛い、彼女にも振られた。そんな羽山の家に通って会社の後輩である高見がご飯を作ってくれるようになり……。
ノンケ社会人羽山が恋愛と性欲の迷路に迷い込みます。そして辿り着いた答えは。
後半から性描写が増えます。
本編 スーツ男子の歩き方 30話
サイドストーリー 7話
順次投稿していきます。
※サイドストーリーはリバカップルの話になります。
※性描写が入る部分には☆をつけてあります。
10/18 サイドストーリー2 亨の場合の投稿を開始しました。全5話の予定です。

【完結】遍く、歪んだ花たちに。
古都まとい
BL
職場の部下 和泉周(いずみしゅう)は、はっきり言って根暗でオタクっぽい。目にかかる長い前髪に、覇気のない視線を隠す黒縁眼鏡。仕事ぶりは可もなく不可もなく。そう、凡人の中の凡人である。
和泉の直属の上司である村谷(むらや)はある日、ひょんなことから繁華街のホストクラブへと連れて行かれてしまう。そこで出会ったNo.1ホスト天音(あまね)には、どこか和泉の面影があって――。
「先輩、僕のこと何も知っちゃいないくせに」
No.1ホスト部下×堅物上司の現代BL。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















