2 / 10
2.春の記憶
しおりを挟む
玩具、映像音楽、ビデオゲーム、アミューズメント分野を扱うエンタテインメント総合商社であるうちの会社が、自動車産業を中心に事業を拡大する国内トップ企業、木崎グループの傘下に入ったのは一年前。
以来、親会社(俺たちは本社と呼んでいる)から社員が出向してくるようになった。人事の吉川部長もその一人だ。こんな形で木崎との繋がりができてしまうとは思わなかったが、直接関わるようなことはないだろう――そう思っていた、のに。
「津島」
企画三課に異動になって二週間。感情の見えない木崎の声を聞くのは何度目だろうか。机の前に立った瞬間、書類を差し出される。
「やり直し」
視線はディスプレイに固定されたまま、こちらを見ようともしない。目が合ったところで吹き出しすら見えないのはわかっているが。
三課は商品のプロモーション活動である、イベントの企画や運営を行うために新設された。玩具を扱う一課とそれ以外を扱う二課、それぞれでやっていたことだが、一緒にすることで業務の効率化と今までにない企画を打ち出すのが目的だ。そのために木崎から全員に課されたのが、週一回の企画提出だった。
企画書を返されたのはこれで三度目。初めは素直に受け取っていたが、もうどこを直せばいいのかわからない。周りはみな経験者で、全く違う業務にいたのは自分だけ。「面倒な後輩」にならないよう質問は最小限にし、できるだけ心を読むことにしている。それなのに「木崎課長次第だから」と明確な答えを誰も示してはくれない。
――なんで、こいつだけ見えないんだ。
心さえ読めればこんなのすぐ終わるのに。
「もう少し具体的に教えていただけませんか」
笑顔を崩さぬよう「謙虚で素直な部下」として接すれば、木崎がわかりやすくため息を落とした。
思わず手にしていた紙に皺が寄る。上司にため息をつかれたことなど一度もない。いつでも俺は「仕事のできる部下」で「手のかからない後輩」だった。どうして、よりによって木崎だけ見えないのか。お前なんかいなくてもうまくやれている、そう見せつけてやりたいのに。沸き立つ苦さを押し込め、もう一度口を開く。
「どこがいけないのか教えてください」
切れ長の目も高い鼻も薄い唇も変わらない。六年も経ったとは思えないほどそのままだ。けれど、全く知らない、他人に見上げられている気がした。
「企画の内容に問題はない」
予想外の言葉に面食らう。だったら、なぜ。
「俺は誰が書いても同じものなんていらない」
向けられた視線の温度がすっと下がった、気がした。
「これは『津島にしかできないこと』じゃないだろう」
それは、と反論しかけたが「もうひとつ」と先に言葉を落とされる。
「この企画、津島は誰のために書いたんだ?」
一瞬の迷いを木崎は見逃さない。答えを探す間もなく、視線を外される。「以上だ」パソコンのディスプレイに向き直った木崎はもうこちらを見ない。誰のためって、会社のためだろうが。そもそもお前が毎週提出するように言ったから、提出しているだけなのに。
――これは『津島にしかできないこと』じゃないだろう。
感情の見えない顔。温度のない声。初めて会ったかのような態度。けれど目の前の男が、自分の知っている木崎なのだと突き付けられた気がした。
――朝陽は?
耳の奥で蘇ってしまった優しい声が、閉じ込めてきた記憶を無遠慮に揺らす。
俺が木崎と出会ったのは、七年前。
大学入学から一か月経ち、桜の樹は緑色に覆われていた。午前の講義が終わり、向かったのは学食ではなく部室棟。映画研究サークルの部室に鍵はかかっていなかった。誰かいるのだろうか。大画面のテレビ、革張りのソファ、本やDVDの並ぶ棚。ぐるりと見渡すが、人影は見えない。鍵を締め忘れただけか。ホッと息をついた、そのとき。
「んー……」
突然聞こえた声にビクッと肩が跳ねた。
棚の影から誰かが這い出てくる。なんでそんなところに、という疑問には「ここ日当たり良くて気持ちいーんだよ」と欠伸交じりの言葉が答えをくれた。
棚と壁の間、ひと一人座れるほどの隙間に陽だまりができている。春とはいえ、まだ長袖が必要な気温だ。暖かい場所を求めてしまう気持ちはわからないでもない。でも、床で、しかも座って寝るか? 猫みたいだな。
「で、だれ?」
大きく伸びをしながら立ち上がると、自分よりも頭ひとつ背が高い。部屋着とも言えるラフな格好なのに不思議とダサくない。ふわりと柔らかな髪は肩に触れるか触れないかの長さで、切れ長の目が前髪の隙間から覗く。
「経済学部一年の津島です」
「下の名前は?」
「朝陽です」
間髪入れず尋ねられ、反射で答えてしまう。
「朝陽ね。俺は四年の木崎。新歓とかパスしちゃったから知らないよな」
こっちには名前を尋ねておいて、自分は名字だけかよ。と思わなくはなかったけど、柔らかな日差しの中で笑った顔が、なぜか泣き出す前のように見え、何も言えなくなった。
細められた瞳から視線を上に向ける。もうクセみたいなものだ。目が合ったら確かめずにはいられない。
――キレイ、というか、可愛いな。
は? 並んだ文字を読み取った俺は、意味を理解するまでの数秒、固まる。
「ん? どした?」
緩く傾けられた顔。柔らかな眼差しに混じる温度。なんで、と言葉にはならず、視線を再び宙へ向ける。
――すっげー好みなんだけど。一目惚れってあるんだな。
見てしまったことを後悔したが、もう遅い。
「具合でも悪い?」と、木崎が手を伸ばしてくる。距離を取るより先に指が触れ、自分でも驚くほど強く振り払っていた。
「っ、あ、……失礼しますっ」
振り返ることなく、部室を飛び出す。
騒ぐ心臓を抱えたまま階段を駆け下りる。
好意を向けられることには慣れているはずだった。見た目だけでなく、相手の望むように動けるのだからモテて当然。俺自身はアリかナシかを考えるだけでいい。主導権は常に自分にあって、距離を詰めるのも置くのも自分次第。
けれど、さっきはそれを考える暇も、笑顔で躱す余裕もなかった。木崎は「初対面の距離」というものが全くない相手だったのだ。
「なんなんだ、あいつ……」
相手の表情や空気を読まないやつは嫌いだ。できるだけ関わりたくない。それなのに、今まで飲み会にすら参加していなかった木崎が、頻繁に顔を出すようになった。
しかも俺の姿を見つけると「朝陽」と必ず寄ってくる。周りは「いつの間に仲良くなったんだよ」と不思議そうだったが、好きな映画を観るだけの緩いサークルなので他人の事情に深く突っ込むやつはいない。
「これどう?」
窓際に寄せた机の前で、木崎がスマートフォンをこちらに向ける。
「どうって……」
机に肘を置き、しゃがんだ姿勢の木崎に見上げられる。目の前に『今日も会えるなんてラッキー』と書かれた吹き出しが浮かぶ。
アリかナシかでいえばナシに決まっていて、告白されたら即お断りだけど、何も言われていない時点で振ることはできない。それとなく察してもらいたいと思うが、そんな繊細な神経を木崎が持ち合わせているわけはなく。
ほかの先輩たちと同じように「愛想のいい後輩」「気の利く後輩」として接しようとするのだが、木崎は俺が引こうとする線をあっさり超え、距離を詰めてくる。それならば、と木崎の望む姿とは違う自分を作り、距離を置こうと思ったのだが。
――朝陽は何が好きなのかな。
木崎が浮かべるのは俺自身のことばかりで、俺にどうしてほしいというのは見せない。望む姿がわからないから反対に振る舞うこともできない。それは今まで当たり前に「作って」きた俺を、とても落ち着かない心地にさせた。
はあ、とため息とともに視線を落とせば、「ん?」と顔を傾けた木崎と再び目が合う。思いがけず優しい眼差しを向けられ、心臓が跳ねた。今まで誰と目が合っても何ともなかったのに。どうして、今。なんで、木崎に。
「こういうの、好きじゃない?」
揺れ始めた心臓に気づかないふりをして、画面へと意識を向ければ、先週から公開になった映画の予告映像が流れている。好きじゃない、って言えばいい。それで会話は終わる。それなのに揺れる鼓動の大きさが、嘘をつくために必要なものを奪っていく。表情も声も作れず、掠れた言葉だけが落ちた。
「……好き、だけど」
言ってしまってから体温が勝手に上がりだす。映画に対する答えにすぎないのに。
「よし、じゃあ、土曜日は?」
立ち上がった木崎がスマートフォンを操作する。
「なんか予定ある?」
「ないけど」
早く会話を終わらせたくて、反射的に答えてしまう。アルバイトは平日と日曜日に設定していて、土曜日はなるべく空けるようにしている。スケジュールを確認するまでもない。
「おっけ。じゃあ、この十一時の回でいい?」
映画館の上映スケジュールを見せられ、目が合いそうになったので、急いで頭を下げる。
「駅前に十時半? でいっか」
頷いたことになってしまったのだと気づき、「なんで」と返せば、「あ、早い? 午後でもいいけど、お昼食べたら眠くなるかもだし」と笑って言われる。
思わず視界に入れてしまった吹き出しには『初デートだ』と文字が並んでいた。デートって、ただ映画観に行くだけじゃん。と思ってしまった時点で、自分でも行く気になっているのだと気づく。行くとも行かないとも言わないうちに「じゃあ土曜日に」と木崎は部室を出ていった。「お前、何しに来たんだよ」と周りに笑われても構うことなく。
悔しいことに、木崎と映画を観るのは楽しかった。待ち合わせの時点で『可愛い』と並んだ文字に戸惑ったが、『楽しい』や『嬉しいな』と明るい感想が並べば悪い気はしない。
距離が近いとか、もっと空気を読めとか思うことは色々あるし、そこが嫌いなのに、作るべき自分がわからないからか、わからないならいいやと開き直ってしまったからか、いつもより深く息が吸える気がした。「どう見られているか」を考えなくていい相手は、木崎が初めてだった。
「朝陽? 飲まないの?」
木崎と出かけるようになって一か月が経つ。映画を観終わった後は、お昼を食べる前でも後でも、必ずと言っていいほどカフェに寄る。感想言いたいじゃん、と木崎が言ったのが始まりだが、今では感想を話している時間の方が短い。
湯気の消えたカップへ、ため息を落とす。
木崎といると冷めるのが早い気がする。
「アイスコーヒーは好きだけど、冷めたコーヒーは好きじゃないんだよ」
「なら、初めからアイス頼めばいいじゃん」
「アイスよりホットが好きなの」
「へーえ」
木崎がストローを咥えたまま、おかしそうに笑う。
「そろそろ帰る?」
木崎の視線を追えば、ガラス越しに見える駅前の景色は夕陽に染まっていた。今日は午後二時からの回だったので、もう六時近い。
コーヒーはまだ三分の一ほど残っている。
「朝陽」
顔を上げれば「もーらい」と、カップを奪われた。冷めたコーヒーなんて美味しくないのに。一気飲みした木崎は笑って言う。
「ごちそうさま」
切れ長の目が三日月を描く。瞬間、きゅっと胸が鳴った。苦しさに似たこの感覚が「嫌い」でできていないことに、俺はもう気づいている。「ん?」と傾けられた顔に、「朝陽」と笑って呼ぶ声に、浮かんだ文句が一瞬で消えてしまう理由にも。それなのに。
――また今度かな。
見えた文字にイラっとする。強引なくらい勝手に約束を取り付けるくせに、最後の一歩は踏み込まない。今度、今度って、いつになったら、こいつは……。
「朝陽?」
気づけば、立ち上がりかけた木崎の腕を掴んでいた。
「……えっと、ご飯食べて帰らない?」
掴まれた腕を振り払うことなく、木崎は少し考えるような表情を見せる。吹き出しを確かめたくても微妙に目が合わない。
木崎に想われている自信はある。断られるなんて思ってもない。けれど返事はなかなか聞こえず、不安が膨らみ始める。
「この後なにか用事あった? それなら別に無理しなくていいよ」
パッと手を離し、早口で告げる。カップとグラスを載せたトレイを持ち上げ、木崎の顔を見ないようにして返却口へ持っていく。
タイミングが悪かっただけだろう。今日は用事があるとか、日が悪いとか、そういうことだろう。お前が何も言わないから、こっちから誘ってやったのに。なんだよ。
トレイを片付け、出入り口へと向かえば、先に出ていた木崎が振り返る。
「朝陽」
カフェと外灯の明かりに挟まれ、木崎の顔がよく見えた。頭上の吹き出しも。
「ご飯、朝陽の部屋ならいいよ」
ご飯食べて帰らない? という問いの答えがどうして、俺の部屋なら、となるのか。返事として正しくないだろ。自分の部屋に誘わないで俺の部屋っていうのも図々しい。言葉はぐるぐる回るが声にはならない。見えてしまった文字が頭の大部分を占めていた。
「……俺、料理できないからな」
「いいよ、そんなの」
眉を寄せて答えれば、春の空気みたいな柔らかさで微笑まれる。甘さと落ち着かなさが一気に膨らみ、刻まれる鼓動はどんどんテンポを上げていく。
「とりあえず駅だな」
くるりと方向転換した木崎に、とても自然に手を取られる。冷たい、と思ったのは一瞬で、肌を伝わる温度はゆっくりと上がっていく。隣よりもわずかに後ろを歩きながら、視線を頭上に向けた。今はもう見えない言葉を反芻させ、きゅっと唇を噛む。
――朝陽が好きだ。
「顔緩んでるぞ」
追加の缶ビールとともに言ってやれば、木崎は「ありがと」と受け取りながらさらに頬を緩める。
「だって嬉しいもん」
「もん、って」
「初めてじゃん。部屋に呼んでくれたの」
「……呼んではない」
一人暮らしの部屋は狭い。ベッドとローテーブルの隙間に並んで座れば、触れていなくても相手の動きが伝わってくる。
ビールの空き缶、食べかけのピザにポテト。テーブルには、一人では見られない光景が広がる。だからだろうか。自分の部屋なのに、ちっとも落ち着かない。たった一人増えただけで空気が薄い気がする。
木崎は受け取った缶を開けずに、テーブルに置いた。乾いた音が部屋に響き、BGM代わりのテレビの音が遠くなる。
「朝陽」
耳が音を拾うよりも先、肌に触れた空気が揺れる。吐き出された息に混じるビールの香りと熱。ほんの少し顔を動かせば触れてしまう。見なくてもわかる。わかるから、動けない。両手に握り締めたままのコーラのペットボトルから水滴が滲む。
「いつもさ、俺が誘うばっかりだったからさ、嬉しかった」
うん、とも。そう、とも言えず。ただ静かに呼吸することしかできない。
「朝陽も、俺といたいって思ってくれたのかなって」
薄く開けている窓からは夜の匂いが流れ込み、冷たい風がカーテンを揺らす。「涼しい」と「寒い」の間みたいな温度。それなのにちっとも体温は下がらず、体の熱を強く意識させられる。
「朝陽」
木崎の指がうなじに触れ、体が小さく跳ねる。思わず顔を向ければ、視界が木崎の顔で埋まる。頭上なんて確かめる隙もない。熱を帯びた視線と柔らかな表情を向けられ、呼吸が止まった。
「好きだよ」
とっくに知っていた。ずっと気づいていた。「やっと言ったか」って笑ってやろうかとすら思っていた。それなのに。木崎の口から、木崎の声で伝えられて、喉が詰まった。
細められた瞳が距離を詰める言葉を待っている。うなじで遊ぶ指が力を込めるタイミングを窺っている。木崎の全部が俺の言葉を待っていた。言わなくてもわかるだろ、とか。言う必要なくない? とか。逃げ出そうとする心を捕まえに来る。
「……俺も」
音になったかわからないくらいの小ささで答えれば、ふわりと綻んだ顔が一瞬にして距離を消した。
学生時代の淡い思い出。あんな別れ方さえしなければ、それで終われたのに。
以来、親会社(俺たちは本社と呼んでいる)から社員が出向してくるようになった。人事の吉川部長もその一人だ。こんな形で木崎との繋がりができてしまうとは思わなかったが、直接関わるようなことはないだろう――そう思っていた、のに。
「津島」
企画三課に異動になって二週間。感情の見えない木崎の声を聞くのは何度目だろうか。机の前に立った瞬間、書類を差し出される。
「やり直し」
視線はディスプレイに固定されたまま、こちらを見ようともしない。目が合ったところで吹き出しすら見えないのはわかっているが。
三課は商品のプロモーション活動である、イベントの企画や運営を行うために新設された。玩具を扱う一課とそれ以外を扱う二課、それぞれでやっていたことだが、一緒にすることで業務の効率化と今までにない企画を打ち出すのが目的だ。そのために木崎から全員に課されたのが、週一回の企画提出だった。
企画書を返されたのはこれで三度目。初めは素直に受け取っていたが、もうどこを直せばいいのかわからない。周りはみな経験者で、全く違う業務にいたのは自分だけ。「面倒な後輩」にならないよう質問は最小限にし、できるだけ心を読むことにしている。それなのに「木崎課長次第だから」と明確な答えを誰も示してはくれない。
――なんで、こいつだけ見えないんだ。
心さえ読めればこんなのすぐ終わるのに。
「もう少し具体的に教えていただけませんか」
笑顔を崩さぬよう「謙虚で素直な部下」として接すれば、木崎がわかりやすくため息を落とした。
思わず手にしていた紙に皺が寄る。上司にため息をつかれたことなど一度もない。いつでも俺は「仕事のできる部下」で「手のかからない後輩」だった。どうして、よりによって木崎だけ見えないのか。お前なんかいなくてもうまくやれている、そう見せつけてやりたいのに。沸き立つ苦さを押し込め、もう一度口を開く。
「どこがいけないのか教えてください」
切れ長の目も高い鼻も薄い唇も変わらない。六年も経ったとは思えないほどそのままだ。けれど、全く知らない、他人に見上げられている気がした。
「企画の内容に問題はない」
予想外の言葉に面食らう。だったら、なぜ。
「俺は誰が書いても同じものなんていらない」
向けられた視線の温度がすっと下がった、気がした。
「これは『津島にしかできないこと』じゃないだろう」
それは、と反論しかけたが「もうひとつ」と先に言葉を落とされる。
「この企画、津島は誰のために書いたんだ?」
一瞬の迷いを木崎は見逃さない。答えを探す間もなく、視線を外される。「以上だ」パソコンのディスプレイに向き直った木崎はもうこちらを見ない。誰のためって、会社のためだろうが。そもそもお前が毎週提出するように言ったから、提出しているだけなのに。
――これは『津島にしかできないこと』じゃないだろう。
感情の見えない顔。温度のない声。初めて会ったかのような態度。けれど目の前の男が、自分の知っている木崎なのだと突き付けられた気がした。
――朝陽は?
耳の奥で蘇ってしまった優しい声が、閉じ込めてきた記憶を無遠慮に揺らす。
俺が木崎と出会ったのは、七年前。
大学入学から一か月経ち、桜の樹は緑色に覆われていた。午前の講義が終わり、向かったのは学食ではなく部室棟。映画研究サークルの部室に鍵はかかっていなかった。誰かいるのだろうか。大画面のテレビ、革張りのソファ、本やDVDの並ぶ棚。ぐるりと見渡すが、人影は見えない。鍵を締め忘れただけか。ホッと息をついた、そのとき。
「んー……」
突然聞こえた声にビクッと肩が跳ねた。
棚の影から誰かが這い出てくる。なんでそんなところに、という疑問には「ここ日当たり良くて気持ちいーんだよ」と欠伸交じりの言葉が答えをくれた。
棚と壁の間、ひと一人座れるほどの隙間に陽だまりができている。春とはいえ、まだ長袖が必要な気温だ。暖かい場所を求めてしまう気持ちはわからないでもない。でも、床で、しかも座って寝るか? 猫みたいだな。
「で、だれ?」
大きく伸びをしながら立ち上がると、自分よりも頭ひとつ背が高い。部屋着とも言えるラフな格好なのに不思議とダサくない。ふわりと柔らかな髪は肩に触れるか触れないかの長さで、切れ長の目が前髪の隙間から覗く。
「経済学部一年の津島です」
「下の名前は?」
「朝陽です」
間髪入れず尋ねられ、反射で答えてしまう。
「朝陽ね。俺は四年の木崎。新歓とかパスしちゃったから知らないよな」
こっちには名前を尋ねておいて、自分は名字だけかよ。と思わなくはなかったけど、柔らかな日差しの中で笑った顔が、なぜか泣き出す前のように見え、何も言えなくなった。
細められた瞳から視線を上に向ける。もうクセみたいなものだ。目が合ったら確かめずにはいられない。
――キレイ、というか、可愛いな。
は? 並んだ文字を読み取った俺は、意味を理解するまでの数秒、固まる。
「ん? どした?」
緩く傾けられた顔。柔らかな眼差しに混じる温度。なんで、と言葉にはならず、視線を再び宙へ向ける。
――すっげー好みなんだけど。一目惚れってあるんだな。
見てしまったことを後悔したが、もう遅い。
「具合でも悪い?」と、木崎が手を伸ばしてくる。距離を取るより先に指が触れ、自分でも驚くほど強く振り払っていた。
「っ、あ、……失礼しますっ」
振り返ることなく、部室を飛び出す。
騒ぐ心臓を抱えたまま階段を駆け下りる。
好意を向けられることには慣れているはずだった。見た目だけでなく、相手の望むように動けるのだからモテて当然。俺自身はアリかナシかを考えるだけでいい。主導権は常に自分にあって、距離を詰めるのも置くのも自分次第。
けれど、さっきはそれを考える暇も、笑顔で躱す余裕もなかった。木崎は「初対面の距離」というものが全くない相手だったのだ。
「なんなんだ、あいつ……」
相手の表情や空気を読まないやつは嫌いだ。できるだけ関わりたくない。それなのに、今まで飲み会にすら参加していなかった木崎が、頻繁に顔を出すようになった。
しかも俺の姿を見つけると「朝陽」と必ず寄ってくる。周りは「いつの間に仲良くなったんだよ」と不思議そうだったが、好きな映画を観るだけの緩いサークルなので他人の事情に深く突っ込むやつはいない。
「これどう?」
窓際に寄せた机の前で、木崎がスマートフォンをこちらに向ける。
「どうって……」
机に肘を置き、しゃがんだ姿勢の木崎に見上げられる。目の前に『今日も会えるなんてラッキー』と書かれた吹き出しが浮かぶ。
アリかナシかでいえばナシに決まっていて、告白されたら即お断りだけど、何も言われていない時点で振ることはできない。それとなく察してもらいたいと思うが、そんな繊細な神経を木崎が持ち合わせているわけはなく。
ほかの先輩たちと同じように「愛想のいい後輩」「気の利く後輩」として接しようとするのだが、木崎は俺が引こうとする線をあっさり超え、距離を詰めてくる。それならば、と木崎の望む姿とは違う自分を作り、距離を置こうと思ったのだが。
――朝陽は何が好きなのかな。
木崎が浮かべるのは俺自身のことばかりで、俺にどうしてほしいというのは見せない。望む姿がわからないから反対に振る舞うこともできない。それは今まで当たり前に「作って」きた俺を、とても落ち着かない心地にさせた。
はあ、とため息とともに視線を落とせば、「ん?」と顔を傾けた木崎と再び目が合う。思いがけず優しい眼差しを向けられ、心臓が跳ねた。今まで誰と目が合っても何ともなかったのに。どうして、今。なんで、木崎に。
「こういうの、好きじゃない?」
揺れ始めた心臓に気づかないふりをして、画面へと意識を向ければ、先週から公開になった映画の予告映像が流れている。好きじゃない、って言えばいい。それで会話は終わる。それなのに揺れる鼓動の大きさが、嘘をつくために必要なものを奪っていく。表情も声も作れず、掠れた言葉だけが落ちた。
「……好き、だけど」
言ってしまってから体温が勝手に上がりだす。映画に対する答えにすぎないのに。
「よし、じゃあ、土曜日は?」
立ち上がった木崎がスマートフォンを操作する。
「なんか予定ある?」
「ないけど」
早く会話を終わらせたくて、反射的に答えてしまう。アルバイトは平日と日曜日に設定していて、土曜日はなるべく空けるようにしている。スケジュールを確認するまでもない。
「おっけ。じゃあ、この十一時の回でいい?」
映画館の上映スケジュールを見せられ、目が合いそうになったので、急いで頭を下げる。
「駅前に十時半? でいっか」
頷いたことになってしまったのだと気づき、「なんで」と返せば、「あ、早い? 午後でもいいけど、お昼食べたら眠くなるかもだし」と笑って言われる。
思わず視界に入れてしまった吹き出しには『初デートだ』と文字が並んでいた。デートって、ただ映画観に行くだけじゃん。と思ってしまった時点で、自分でも行く気になっているのだと気づく。行くとも行かないとも言わないうちに「じゃあ土曜日に」と木崎は部室を出ていった。「お前、何しに来たんだよ」と周りに笑われても構うことなく。
悔しいことに、木崎と映画を観るのは楽しかった。待ち合わせの時点で『可愛い』と並んだ文字に戸惑ったが、『楽しい』や『嬉しいな』と明るい感想が並べば悪い気はしない。
距離が近いとか、もっと空気を読めとか思うことは色々あるし、そこが嫌いなのに、作るべき自分がわからないからか、わからないならいいやと開き直ってしまったからか、いつもより深く息が吸える気がした。「どう見られているか」を考えなくていい相手は、木崎が初めてだった。
「朝陽? 飲まないの?」
木崎と出かけるようになって一か月が経つ。映画を観終わった後は、お昼を食べる前でも後でも、必ずと言っていいほどカフェに寄る。感想言いたいじゃん、と木崎が言ったのが始まりだが、今では感想を話している時間の方が短い。
湯気の消えたカップへ、ため息を落とす。
木崎といると冷めるのが早い気がする。
「アイスコーヒーは好きだけど、冷めたコーヒーは好きじゃないんだよ」
「なら、初めからアイス頼めばいいじゃん」
「アイスよりホットが好きなの」
「へーえ」
木崎がストローを咥えたまま、おかしそうに笑う。
「そろそろ帰る?」
木崎の視線を追えば、ガラス越しに見える駅前の景色は夕陽に染まっていた。今日は午後二時からの回だったので、もう六時近い。
コーヒーはまだ三分の一ほど残っている。
「朝陽」
顔を上げれば「もーらい」と、カップを奪われた。冷めたコーヒーなんて美味しくないのに。一気飲みした木崎は笑って言う。
「ごちそうさま」
切れ長の目が三日月を描く。瞬間、きゅっと胸が鳴った。苦しさに似たこの感覚が「嫌い」でできていないことに、俺はもう気づいている。「ん?」と傾けられた顔に、「朝陽」と笑って呼ぶ声に、浮かんだ文句が一瞬で消えてしまう理由にも。それなのに。
――また今度かな。
見えた文字にイラっとする。強引なくらい勝手に約束を取り付けるくせに、最後の一歩は踏み込まない。今度、今度って、いつになったら、こいつは……。
「朝陽?」
気づけば、立ち上がりかけた木崎の腕を掴んでいた。
「……えっと、ご飯食べて帰らない?」
掴まれた腕を振り払うことなく、木崎は少し考えるような表情を見せる。吹き出しを確かめたくても微妙に目が合わない。
木崎に想われている自信はある。断られるなんて思ってもない。けれど返事はなかなか聞こえず、不安が膨らみ始める。
「この後なにか用事あった? それなら別に無理しなくていいよ」
パッと手を離し、早口で告げる。カップとグラスを載せたトレイを持ち上げ、木崎の顔を見ないようにして返却口へ持っていく。
タイミングが悪かっただけだろう。今日は用事があるとか、日が悪いとか、そういうことだろう。お前が何も言わないから、こっちから誘ってやったのに。なんだよ。
トレイを片付け、出入り口へと向かえば、先に出ていた木崎が振り返る。
「朝陽」
カフェと外灯の明かりに挟まれ、木崎の顔がよく見えた。頭上の吹き出しも。
「ご飯、朝陽の部屋ならいいよ」
ご飯食べて帰らない? という問いの答えがどうして、俺の部屋なら、となるのか。返事として正しくないだろ。自分の部屋に誘わないで俺の部屋っていうのも図々しい。言葉はぐるぐる回るが声にはならない。見えてしまった文字が頭の大部分を占めていた。
「……俺、料理できないからな」
「いいよ、そんなの」
眉を寄せて答えれば、春の空気みたいな柔らかさで微笑まれる。甘さと落ち着かなさが一気に膨らみ、刻まれる鼓動はどんどんテンポを上げていく。
「とりあえず駅だな」
くるりと方向転換した木崎に、とても自然に手を取られる。冷たい、と思ったのは一瞬で、肌を伝わる温度はゆっくりと上がっていく。隣よりもわずかに後ろを歩きながら、視線を頭上に向けた。今はもう見えない言葉を反芻させ、きゅっと唇を噛む。
――朝陽が好きだ。
「顔緩んでるぞ」
追加の缶ビールとともに言ってやれば、木崎は「ありがと」と受け取りながらさらに頬を緩める。
「だって嬉しいもん」
「もん、って」
「初めてじゃん。部屋に呼んでくれたの」
「……呼んではない」
一人暮らしの部屋は狭い。ベッドとローテーブルの隙間に並んで座れば、触れていなくても相手の動きが伝わってくる。
ビールの空き缶、食べかけのピザにポテト。テーブルには、一人では見られない光景が広がる。だからだろうか。自分の部屋なのに、ちっとも落ち着かない。たった一人増えただけで空気が薄い気がする。
木崎は受け取った缶を開けずに、テーブルに置いた。乾いた音が部屋に響き、BGM代わりのテレビの音が遠くなる。
「朝陽」
耳が音を拾うよりも先、肌に触れた空気が揺れる。吐き出された息に混じるビールの香りと熱。ほんの少し顔を動かせば触れてしまう。見なくてもわかる。わかるから、動けない。両手に握り締めたままのコーラのペットボトルから水滴が滲む。
「いつもさ、俺が誘うばっかりだったからさ、嬉しかった」
うん、とも。そう、とも言えず。ただ静かに呼吸することしかできない。
「朝陽も、俺といたいって思ってくれたのかなって」
薄く開けている窓からは夜の匂いが流れ込み、冷たい風がカーテンを揺らす。「涼しい」と「寒い」の間みたいな温度。それなのにちっとも体温は下がらず、体の熱を強く意識させられる。
「朝陽」
木崎の指がうなじに触れ、体が小さく跳ねる。思わず顔を向ければ、視界が木崎の顔で埋まる。頭上なんて確かめる隙もない。熱を帯びた視線と柔らかな表情を向けられ、呼吸が止まった。
「好きだよ」
とっくに知っていた。ずっと気づいていた。「やっと言ったか」って笑ってやろうかとすら思っていた。それなのに。木崎の口から、木崎の声で伝えられて、喉が詰まった。
細められた瞳が距離を詰める言葉を待っている。うなじで遊ぶ指が力を込めるタイミングを窺っている。木崎の全部が俺の言葉を待っていた。言わなくてもわかるだろ、とか。言う必要なくない? とか。逃げ出そうとする心を捕まえに来る。
「……俺も」
音になったかわからないくらいの小ささで答えれば、ふわりと綻んだ顔が一瞬にして距離を消した。
学生時代の淡い思い出。あんな別れ方さえしなければ、それで終われたのに。
11
お気に入りに追加
18
あなたにおすすめの小説


林檎買ってきて
hamapito
BL
#創作BL版深夜の60分一本勝負
お題「林檎」「頬」 で書いたものです(*´▽`*)
*社会人同士のカップルのおはなし*
――林檎買ってきて。
二週間ぶりに会えるというのに、メッセージはそれだけだった。

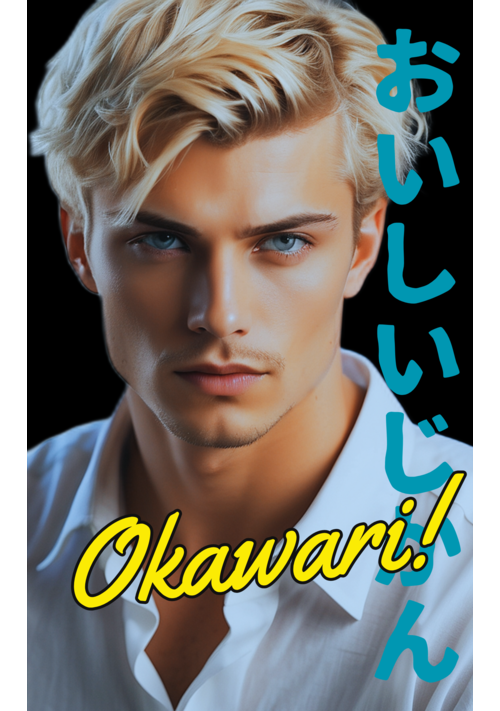
おかわり
ストロングベリー
BL
恐ろしいほどの美貌と絶品の料理で人気のカフェバーのオーナー【ヒューゴ】は、晴れて恋人になった【透】においしい料理と愛情を注ぐ日々。
男性経験のない透とは、時間をかけてゆっくり愛し合うつもりでいたが……透は意外にも積極的で、性来Dominantなヒューゴを夜ごとに刺激してくる。
「おいしいじかん」の続編、両思いになった2人の愛し合う姿をぜひ♡


林檎買ってきて*同棲編*
hamapito
BL
『林檎買ってきて』https://www.alphapolis.co.jp/novel/382671364/488697419のふたりのその後
――林檎買ってきて。
そんなメッセージを受け取ってからもうすぐ一年。
付き合って一年半、互いに部屋の合鍵を持ち合い、週末に泊まるのも当たり前になった。
家族以外に弱っているところを見られても大丈夫だと思えた相手は初めてで。俺としては自然な流れだと思ったのだが。
相手は違ったらしい――??


【完結】義兄に十年片想いしているけれど、もう諦めます
夏ノ宮萄玄
BL
オレには、親の再婚によってできた義兄がいる。彼に対しオレが長年抱き続けてきた想いとは。
――どうしてオレは、この不毛な恋心を捨て去ることができないのだろう。
懊悩する義弟の桧理(かいり)に訪れた終わり。
義兄×義弟。美形で穏やかな社会人義兄と、つい先日まで高校生だった少しマイナス思考の義弟の話。短編小説です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















