お気に入りに追加
218
あなたにおすすめの小説

婚約破棄された竜好き令嬢は黒竜様に溺愛される。残念ですが、守護竜を捨てたこの国は滅亡するようですよ
水無瀬
ファンタジー
竜が好きで、三度のご飯より竜研究に没頭していた侯爵令嬢の私は、婚約者の王太子から婚約破棄を突きつけられる。
それだけでなく、この国をずっと守護してきた黒竜様を捨てると言うの。
黒竜様のことをずっと研究してきた私も、見せしめとして処刑されてしまうらしいです。
叶うなら、死ぬ前に一度でいいから黒竜様に会ってみたかったな。
ですが、私は知らなかった。
黒竜様はずっと私のそばで、私を見守ってくれていたのだ。
残念ですが、守護竜を捨てたこの国は滅亡するようですよ?

【完結】もう…我慢しなくても良いですよね?
アノマロカリス
ファンタジー
マーテルリア・フローレンス公爵令嬢は、幼い頃から自国の第一王子との婚約が決まっていて幼少の頃から厳しい教育を施されていた。
泣き言は許されず、笑みを浮かべる事も許されず、お茶会にすら参加させて貰えずに常に完璧な淑女を求められて教育をされて来た。
16歳の成人の義を過ぎてから王子との婚約発表の場で、事あろうことか王子は聖女に選ばれたという男爵令嬢を連れて来て私との婚約を破棄して、男爵令嬢と婚約する事を選んだ。
マーテルリアの幼少からの血の滲むような努力は、一瞬で崩壊してしまった。
あぁ、今迄の苦労は一体なんの為に…
もう…我慢しなくても良いですよね?
この物語は、「虐げられる生活を曽祖母の秘術でざまぁして差し上げますわ!」の続編です。
前作の登場人物達も多数登場する予定です。
マーテルリアのイラストを変更致しました。
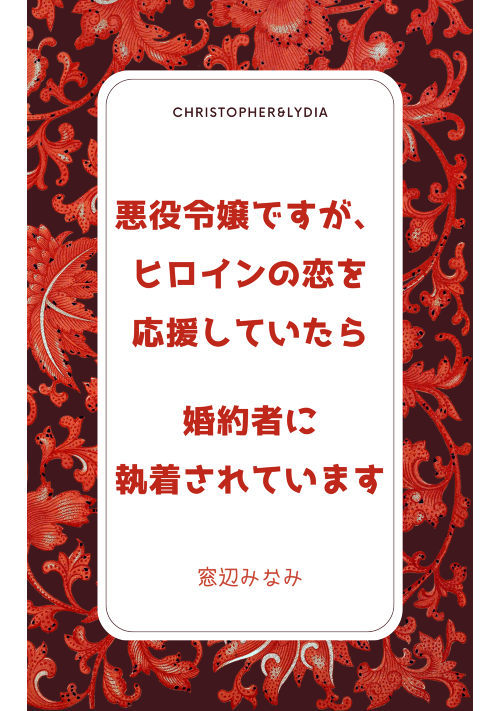
悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています
窓辺ミナミ
ファンタジー
悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。
シナリオ通りなら、死ぬ運命。
だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!
騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!
というわけで、私、悪役やりません!
来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。
あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!
気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。
悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

どうも、死んだはずの悪役令嬢です。
西藤島 みや
ファンタジー
ある夏の夜。公爵令嬢のアシュレイは王宮殿の舞踏会で、婚約者のルディ皇子にいつも通り罵声を浴びせられていた。
皇子の罵声のせいで、男にだらしなく浪費家と思われて王宮殿の使用人どころか通っている学園でも遠巻きにされているアシュレイ。
アシュレイの誕生日だというのに、エスコートすら放棄して、皇子づきのメイドのミュシャに気を遣うよう求めてくる皇子と取り巻き達に、呆れるばかり。
「幼馴染みだかなんだかしらないけれど、もう限界だわ。あの人達に罰があたればいいのに」
こっそり呟いた瞬間、
《願いを聞き届けてあげるよ!》
何故か全くの別人になってしまっていたアシュレイ。目の前で、アシュレイが倒れて意識不明になるのを見ることになる。
「よくも、義妹にこんなことを!皇子、婚約はなかったことにしてもらいます!」
義父と義兄はアシュレイが状況を理解する前に、アシュレイの体を持ち去ってしまう。
今までミュシャを崇めてアシュレイを冷遇してきた取り巻き達は、次々と不幸に巻き込まれてゆき…ついには、ミュシャや皇子まで…
ひたすら一人づつざまあされていくのを、呆然と見守ることになってしまった公爵令嬢と、怒り心頭の義父と義兄の物語。
はたしてアシュレイは元に戻れるのか?
剣と魔法と妖精の住む世界の、まあまあよくあるざまあメインの物語です。
ざまあが書きたかった。それだけです。

とまどいの花嫁は、夫から逃げられない
椎名さえら
恋愛
エラは、親が決めた婚約者からずっと冷淡に扱われ
初夜、夫は愛人の家へと行った。
戦争が起こり、夫は戦地へと赴いた。
「無事に戻ってきたら、お前とは離婚する」
と言い置いて。
やっと戦争が終わった後、エラのもとへ戻ってきた夫に
彼女は強い違和感を感じる。
夫はすっかり改心し、エラとは離婚しないと言い張り
突然彼女を溺愛し始めたからだ
______________________
✴︎舞台のイメージはイギリス近代(ゆるゆる設定)
✴︎誤字脱字は優しくスルーしていただけると幸いです
✴︎なろうさんにも投稿しています
私の勝手なBGMは、懐かしすぎるけど鬼束ちひろ『月光』←名曲すぎ

君のためだと言われても、少しも嬉しくありません
みみぢあん
恋愛
子爵家の令嬢マリオンの婚約者、アルフレッド卿が王族の護衛で隣国へ行くが、任期がながびき帰国できなくなり婚約を解消することになった。 すぐにノエル卿と2度目の婚約が決まったが、結婚を目前にして家庭の事情で2人は…… 暗い流れがつづきます。 ざまぁでスカッ… とされたい方には不向きのお話です。ご注意を😓

悪役令息の婚約者になりまして
どくりんご
恋愛
婚約者に出逢って一秒。
前世の記憶を思い出した。それと同時にこの世界が小説の中だということに気づいた。
その中で、目の前のこの人は悪役、つまり悪役令息だということも同時にわかった。
彼がヒロインに恋をしてしまうことを知っていても思いは止められない。
この思い、どうすれば良いの?

記憶喪失になった嫌われ悪女は心を入れ替える事にした
結城芙由奈@コミカライズ発売中
ファンタジー
池で溺れて死にかけた私は意識を取り戻した時、全ての記憶を失っていた。それと同時に自分が周囲の人々から陰で悪女と呼ばれ、嫌われている事を知る。どうせ記憶喪失になったなら今から心を入れ替えて生きていこう。そして私はさらに衝撃の事実を知る事になる―。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















