3 / 13
3. 虫の知らせ
しおりを挟む
慶応3年(1867年)の秋。
京都の町は秋風に揺れる紅葉の彩りに染まっていた。
坂本龍馬は二条城の一室にて、冷たい茶を前にして独り佇んでいた。
彼の心には、これまでの努力と決意が揺らぐ思いがあった。
龍馬は長州藩と薩摩藩の同盟を実現し、徳川幕府を倒すための道筋を作り上げた。
しかし、その道がどこに繋がるのか。
彼の頭の中には、血と闘争による変革の後に残る荒廃した日本の姿が浮かんでいた。
「まっことこれでえいがか……」
龍馬は頭を抱え、呟いた。
彼は仲間たちの顔を思い浮かべた。
西郷隆盛、高杉晋作、中岡慎太郎、陸奥宗光……そして、かつて対立していた新撰組の志士たち。
彼らは皆、新しい時代のために命を賭けていた。
しかし、龍馬の心は次第に重くなっていった。
彼は血で血を洗うような変革に疑問を抱いていたのだ。
その夜、龍馬は筆をとった。
それは西郷隆盛宛のもので、龍馬がこれ以上の倒幕運動に関与しない旨を伝えるものであった。
本来直接会って話すべきことを手紙で伝えることを謝罪した上で、近代化によって日本人としての誇りを失っていく国の行く末への危機感と、武士道の精神を忘れるべきではないという龍馬の思いを手紙に認めた。
一方で、西郷隆盛もまた龍馬の迷いに日に日に共感することが多くなっていた。
彼は元々保守的な一面があり、明治政府の急激な近代化改革に反発するようになり、龍馬からの手紙に返事こそ出さなかったもののその後は武士道の精神を重んじる動きを取っていた。
◆
「時代は繰り返される。頭では分かっちゅうつもりじゃったけんど……」
「龍馬さん?」
「いや、なんちゃあ無いき。今日のところは稽古は終わりじゃ。腹減っちゅうろ、夕飯の準備じゃ」
こうして、仁は龍馬の寺に住み込みで稽古をする日々を送るようになった。
最初の数ヶ月は、剣術の基本を徹底的に学ぶ日々であった。
毎朝早くから日が沈むまで、木刀を握りしめ、ひたすら型を繰り返す。
龍馬は一つ一つの動作に対し丁寧に指導し、その意義を説いた。
「仁、剣はただ振るうだけではいかんがぜよ。一刀一刀に命を賭ける覚悟を剣に込めるがじゃ」
仁はその言葉を胸に刻みながら、黙々と稽古を続けた。
徐々に彼の動きは洗練されていき、筋力も増していった。
ある日龍馬は、仁との稽古の合間にふと笑みを浮かべ、昔の友人のことを話し始めた。
「仁、ちぃと休憩じゃ。……おまん、西郷隆盛ち知っちゅうがかえ?」
「あの薩摩藩のですか?」
龍馬は頷き、仁は興味津々で耳を傾けた。
龍馬は懐かしき思い出を手繰り寄せるように、少し遠くを見つめていた。
「西郷どん……あん人はほんっにでかい漢やった。心も体もな。初めて会うたがは、江戸の薩摩屋敷やったがぜよ。儂らは初めは敵同士んようなもんやったけんど、話をしゆううちに意気投合して、いつん間にか友になっちょった」
「どのようなお話をされたので?」
「西郷どんとは、国んことをよう話したがよ。あん人は心から日本の未来を思っちょった。儂も同じ気持ちやったけんど、方法がちぃと違うた。西郷どんは、まずは薩摩を強くせんといかん言いよった。けんど儂は、こん国全体が一つにならんちいかんと思うちょったがじゃ」
龍馬はしばし言葉を止め、仁の目を見つめた。
「仁。儂らは、互いを理解し合うて、互いの考えを尊重し合いよった。西郷どんは、ほんに優しい男じゃった。いつも人んことを思いやって、自分んことは後回しにするような奴じゃった」
仁は静かに龍馬の話を聞いていた。
「ある日、西郷どんが儂に言うたがよ。『龍馬、君が思う日本はどんな国や?』って。儂は『自由で平和な国じゃ。誰もが笑うて暮らせる国じゃ』って。西郷どんはそん時、にっこり笑うて『そいがいっちばんやな』ち言うたがよ」
龍馬の瞳には懐かしさが宿っていた。
「要は何が言いたいち言うと、武士道は剣術だけやないがぜ。一番大事ながは、人を思いやる心やちいうことぜよ」
仁は深く頷いた。
腕を磨くのみが武士道ではないという龍馬の言葉が強く心に響いた。
龍馬は微笑みながら、仁の肩を軽く叩いた。
「仁、儂がおまんを立派な侍に育てちゃるき」
そう言って、仁と龍馬は再び稽古に戻った。
仁はその言葉を胸に、今よりさらに努力を続ける決意を新たにした。
しかし、龍馬の心には少し暗い靄がかかっていた。
何故、今になって西郷隆盛との思い出話を仁にしようと思ったのか。
確かに武士道の精神を伝えかったというのも事実だが、何かの虫の知らせのような気がしていた。
この日を境に、龍馬は夢にうなされるようになった。
京都の町は秋風に揺れる紅葉の彩りに染まっていた。
坂本龍馬は二条城の一室にて、冷たい茶を前にして独り佇んでいた。
彼の心には、これまでの努力と決意が揺らぐ思いがあった。
龍馬は長州藩と薩摩藩の同盟を実現し、徳川幕府を倒すための道筋を作り上げた。
しかし、その道がどこに繋がるのか。
彼の頭の中には、血と闘争による変革の後に残る荒廃した日本の姿が浮かんでいた。
「まっことこれでえいがか……」
龍馬は頭を抱え、呟いた。
彼は仲間たちの顔を思い浮かべた。
西郷隆盛、高杉晋作、中岡慎太郎、陸奥宗光……そして、かつて対立していた新撰組の志士たち。
彼らは皆、新しい時代のために命を賭けていた。
しかし、龍馬の心は次第に重くなっていった。
彼は血で血を洗うような変革に疑問を抱いていたのだ。
その夜、龍馬は筆をとった。
それは西郷隆盛宛のもので、龍馬がこれ以上の倒幕運動に関与しない旨を伝えるものであった。
本来直接会って話すべきことを手紙で伝えることを謝罪した上で、近代化によって日本人としての誇りを失っていく国の行く末への危機感と、武士道の精神を忘れるべきではないという龍馬の思いを手紙に認めた。
一方で、西郷隆盛もまた龍馬の迷いに日に日に共感することが多くなっていた。
彼は元々保守的な一面があり、明治政府の急激な近代化改革に反発するようになり、龍馬からの手紙に返事こそ出さなかったもののその後は武士道の精神を重んじる動きを取っていた。
◆
「時代は繰り返される。頭では分かっちゅうつもりじゃったけんど……」
「龍馬さん?」
「いや、なんちゃあ無いき。今日のところは稽古は終わりじゃ。腹減っちゅうろ、夕飯の準備じゃ」
こうして、仁は龍馬の寺に住み込みで稽古をする日々を送るようになった。
最初の数ヶ月は、剣術の基本を徹底的に学ぶ日々であった。
毎朝早くから日が沈むまで、木刀を握りしめ、ひたすら型を繰り返す。
龍馬は一つ一つの動作に対し丁寧に指導し、その意義を説いた。
「仁、剣はただ振るうだけではいかんがぜよ。一刀一刀に命を賭ける覚悟を剣に込めるがじゃ」
仁はその言葉を胸に刻みながら、黙々と稽古を続けた。
徐々に彼の動きは洗練されていき、筋力も増していった。
ある日龍馬は、仁との稽古の合間にふと笑みを浮かべ、昔の友人のことを話し始めた。
「仁、ちぃと休憩じゃ。……おまん、西郷隆盛ち知っちゅうがかえ?」
「あの薩摩藩のですか?」
龍馬は頷き、仁は興味津々で耳を傾けた。
龍馬は懐かしき思い出を手繰り寄せるように、少し遠くを見つめていた。
「西郷どん……あん人はほんっにでかい漢やった。心も体もな。初めて会うたがは、江戸の薩摩屋敷やったがぜよ。儂らは初めは敵同士んようなもんやったけんど、話をしゆううちに意気投合して、いつん間にか友になっちょった」
「どのようなお話をされたので?」
「西郷どんとは、国んことをよう話したがよ。あん人は心から日本の未来を思っちょった。儂も同じ気持ちやったけんど、方法がちぃと違うた。西郷どんは、まずは薩摩を強くせんといかん言いよった。けんど儂は、こん国全体が一つにならんちいかんと思うちょったがじゃ」
龍馬はしばし言葉を止め、仁の目を見つめた。
「仁。儂らは、互いを理解し合うて、互いの考えを尊重し合いよった。西郷どんは、ほんに優しい男じゃった。いつも人んことを思いやって、自分んことは後回しにするような奴じゃった」
仁は静かに龍馬の話を聞いていた。
「ある日、西郷どんが儂に言うたがよ。『龍馬、君が思う日本はどんな国や?』って。儂は『自由で平和な国じゃ。誰もが笑うて暮らせる国じゃ』って。西郷どんはそん時、にっこり笑うて『そいがいっちばんやな』ち言うたがよ」
龍馬の瞳には懐かしさが宿っていた。
「要は何が言いたいち言うと、武士道は剣術だけやないがぜ。一番大事ながは、人を思いやる心やちいうことぜよ」
仁は深く頷いた。
腕を磨くのみが武士道ではないという龍馬の言葉が強く心に響いた。
龍馬は微笑みながら、仁の肩を軽く叩いた。
「仁、儂がおまんを立派な侍に育てちゃるき」
そう言って、仁と龍馬は再び稽古に戻った。
仁はその言葉を胸に、今よりさらに努力を続ける決意を新たにした。
しかし、龍馬の心には少し暗い靄がかかっていた。
何故、今になって西郷隆盛との思い出話を仁にしようと思ったのか。
確かに武士道の精神を伝えかったというのも事実だが、何かの虫の知らせのような気がしていた。
この日を境に、龍馬は夢にうなされるようになった。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説
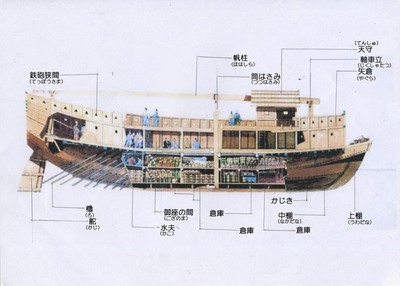


鬼嫁物語
楠乃小玉
歴史・時代
織田信長家臣筆頭である佐久間信盛の弟、佐久間左京亮(さきょうのすけ)。
自由奔放な兄に加え、きっつい嫁に振り回され、
フラフラになりながらも必死に生き延びようとする彼にはたして
未来はあるのか?

紫苑の誠
卯月さくら
歴史・時代
あなたの生きる理由になりたい。
これは、心を閉ざし復讐に生きる一人の少女と、誠の旗印のもと、自分の信念を最後まで貫いて散っていった幕末の志士の物語。
※外部サイト「エブリスタ」で自身が投稿した小説を独自に加筆修正したものを投稿しています。

犬鍋
戸部家尊
歴史・時代
江戸時代後期、伊那川藩では飢饉や貧困により民は困窮の極みにあった。
藩士加賀十四郎は友人たちと光流寺へ墓参りに行く。
そこで歴代藩主の墓の前で切腹している男を発見する。
「まさか、この男は……殿なのか?」
※戯曲形式ですので一部読みづらい点があるかと思います。

ぼくの言の葉がきみに舞う
ユーリ(佐伯瑠璃)
歴史・時代
常世には常葉という妹がいた。
妹は戊辰戦争で土方の小姓市村鉄之助に扮して箱館戦争に加わった。
その妹を陰から守っていたのが、兄である常世だ。
妹を守るために身につけたたくさんの術。しかしもうそれも必要ない。
常葉は土方と生きることを決めたからだ。
常世は妹の常葉に代わって市村鉄之助になり変わり、土方の遺品を持って東京は日野へ。
遺品の全てをを届けたら、異国にでも渡ろうか。
妹を守るという支えをなくした常世は、半ば人生を諦めかけていた。
そんな時に噂に聞いた残党狩りに遭遇する。
狩られようとしていたのは元新選組隊士の十羽(とわ)という女だった。残党狩りのやり口と、十羽が妹と重なって反射的に助け出す。
「自分の人生を生きなさい」
「俺の、人生……」
これは、常世と十羽の旅恋物語である。
※小説家になろう、カクヨムにも投稿しています。

夜に咲く花
増黒 豊
歴史・時代
2017年に書いたものの改稿版を掲載します。
幕末を駆け抜けた新撰組。
その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。
よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~
恩地玖
歴史・時代
位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。
一体、これまで成してきたことは何だったのか。
医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















