1 / 33
<第一話・裂>
しおりを挟む
しゃん、しゃん、しゃん。
鈴の音が規則的に、断続的に響き渡る。あれはなんという道具だっただろうか、と篠崎秋乃は思った。神社かお寺か、そのへんの行事で見たことがあるような気がするがよく覚えていない。学校で勉強したかもしれないが、生憎秋乃は授業は基本寝ているかサボっているかのどちらかである。秋乃の高校の生徒は誰も彼もそんなものだった。元々偏差値の低い、やる気のない子供ばかり集まるのだから仕方のないことかもしれないが。
――ああ、よくわかんないけど、でも。やばいんだよね、これ。
出来が良くない頭でも、現状のまずさは十二分に分かるのだ。姉に連れられて、面白半分に“此処”に来てしまった自分は確かに不謹慎であったのかもしれない。それこそ、この地で失踪した人間の死体でも見つかったら一躍有名人じゃないか、なんて二人でおおはしゃぎしていたのは事実だ。それが悪いことであったというのなら素直に謝罪しよう。でも。
だからって、こんな。こんなよくわからない目に遭わせられなければいけないほど、いけないことをしてしまっただろうか。
ただ此処に来て、彼らと少し話をした、それだけの筈である。死体を探しているとか、失踪者がいたんじゃないかとか、姉はどうか知らないが少なくとも秋乃はそんな話も口にしていない。というか、村のお祭りが楽しすぎて、途中からそんな目的さえ忘れていたというのが正しい。それが何故、こんな松明の明かりしか見えないような真っ暗な場所で――両手両足を広げて、棒に貼り付けられなければいけないのだろうか。
これではまるで、十字架に磔られたどこぞの神様のようだ。
いや、十字架ならもう少しマシな姿であったことだろう。棒は十時ではなく、バッテン印のように組まれている。手足はその棒の端にそれぞれくくりつけられているため、両手両足を大きく広げて、それもかなり引っ張られる形で固定されている状態だった。身動きするたび縄が食い込むし、ぎちぎちに伸ばされた関節が痛くてしょうがない。この時点で十分拷問だというのに――これがまだ、始まりでしかないことは嫌でも理解できる状況だ。
怪しい白装束の集団が、大量の鈴をつけた棒を規則的に地面に打ち付け、鳴らし続けている。
それに合わせて、やや耳に痛い――不協和音のような笛の音が、延々と奏者によって奏でられている。真っ黒な増えだ。尺八とか、そういうものに似ているようにも見えるが、残念ながら勉強をサボり続けてきた秋乃にその正体がわかるはずもない。ひょっとしたら、一般では流通していない、この地域特有の楽器か何かであるのかもしれなかった。
此処が何処であるのかも、わからない。
目覚めたらこの場所にいた。恐らく屋内であろうということはわかるが、それだけだ。自分が眠ってからどれほどの時間が過ぎたかも定かではない。多少トイレに行きたくなっているので、それなりに時間は経過したものと予想できるけども。
――これ、まるでホラゲーじゃん。なんなのこれ。何が始まるっていうの。
そういえば、姉はどうしたのだろうか。同じ部屋で眠っていたはずなのだが、彼女は無事なのか。あるいは、彼女もまた何処かで捕まっているのだろうか。
もし無事ならば、助けに来て欲しい。あれでも姉は、学生時代柔道部に所属していたはず。こんな白装束のよくわからん連中なんて簡単になぎ倒せるはずなのだ。今の自分に出来ることは、姉がどうにか助けてくれることを信じて待つだけである。それがたとえ、儚い望みでしかないのだとしても、だ。
「籤を」
真正面で鈴を振っていた、頭に金ピカの冠をつけたいかにも偉そうな男性が、低く威厳のある声でそう宣言した。瞬間、鈴の音も笛の音もぴたりと止まる。そしてその偉い人のところに、従者らしき白装束の一人が四角い木の箱を持ってきた。箱には、しめ縄のようなものが巻かれている。いかにも神聖なものであると言わんばかりだ。
冠をつけた男性は何事かの呪文を唱えつつ、箱の中にそっと手を差し入れた。そして、一枚の折りたたまれた白い紙を取り出し――読み上げる。
「此度の文字は……“裂《れつ》”」
紙は、それなりに大きなものだった。彼が紙を広げて全員に見せたことで、秋乃にもそこに書かれたものがしっかりと目に入ることになる。
筆で書かれた――恐らくは相当達筆というものなのだろう。その文字は“引き裂く”とかの“裂”という字だった。不吉なことに黒ではなく、まるで血のような真っ赤な文字で記されている。嫌な予感に、心臓が跳ね上がった。その文字が一体何なのか、何を意味するのか、秋乃の頭は既に想像することを拒んでいる。
――や、やだ。やだよ。何するの、ねえ。
大量の白装束達がわらわらと現れた。縛り付けられた秋乃の前に、綺麗に列を成して並ぶ。そして、一番前の者は何か台座のようなものを掲げていた。
そこに置かれていたのは、この場に非常に相応しくない、現代的な道具。――あれは、ペンチというもの、ではなかろうか。
「それでは皆様、一本ずつ、“引き裂いて”いきましょう」
偉い人が、声をかけた。それと同時に、秋乃の後ろから現れた白装束が、秋乃の両足首に手をかける。何をするのかと思ったら、靴と靴下を脱がし始めたではないか。秋乃は暴れるが、両手両足をがっちり固定されたこの状況ではどうにもならない。
「しかし、人間の体は思いのほか頑丈なものです。最終的に“引き裂き”になれば、ある程度の“切れ込み”を入れても構いません。包丁もご用意しておりますので、ご希望の方は儀式の折に申し出てください。指が終わったら、次は腕と足になります。こちらは機械で巻き取る準備もございます」
理解して、しまった。自分がこれから、どのような目に遭うのかということを。
――やだ、やだやだやだ!なんでよ、なんであたしがそんあの!
本当に恐ろしい時、人は声も出せなくなるのだと知った。悲鳴を上げて助けを呼びたいのに、喉は凍りついたように音を発してくれる気配がない。暴れようにも、ぎしぎしと縄をきしませ、ますます関節を痛めただけに終わった。何もかもがわからない。何故自分が、このような拷問めいた目に遭うことを強要されているのかも。
――助けて……助けてお姉ちゃん!助けてよ、誰か、誰か!
再び鳴り出す、鈴の音、笛の音、得体の知れぬ呪文の声。
白装束の一人が、ペンチを持って近づいてくるのを――秋乃はただ、絶望的な目で見つめる他なかった。
***
「あーもうくっそ!マジむっかつく!ちょっとイケメンだからっていい気になってんなアホー!!」
堂島美園は叫ぶと、パソコン横のデスクに思い切り缶ビールを叩きつけた。若干残っていた中身が溢れた気配があったが、今は無視の無視である。後で面倒になることはわかっていたが、酔いが回った頭では今すぐどうにかしようという気持ちは微塵も起こらなかった。一人ビール祭でも開催しなければやっていられない。それほどまでに、今日の出来事は美園にとって屈辱的だったのだ。
藍里大学のオカルト研究サークル、“怪奇現象研究クラブ”。記者に憧れ、同時に不思議な現象に興味を持っていた美園がそのサークルを選ぶのは必然的であったと言える。大学一年生の時は勉強が忙しすぎて、どこのサークルに入る余裕もなかったが、二年生になった今年からは違うのだ。必修科目の類もかなり目処が立っているし、今年からはもっと好きなことに邁進できるはず。美園は今年の春、意気揚々と怪奇現象研究クラブの門を叩いたメンバーだった。実際、自分達の学部の生徒なら、二年生からサークル所属を希望する者も少なくないのである。
他にも小さなオカルト研究サークルはあったが、此処が一番大手で人数も多かった。同時に、部長の新倉焔がインテリ系イケメンで、かなり美園の好みなタイプであったというのもある。二つ年上だが、年下にも見えるような童顔でありすらっと細身である、というのも高いポイントだった。現金かもしれないが、美園も二十歳の女である。そろそろ彼氏が欲しい、なんて野望を抱くのも別段おかしなことではないはずだ。
ちなみに美園、現在彼氏いない歴三年である。高校生の時に付き合っていた男とは、ちょっと人に説明したくないくらいひどい別れ方をしてしまっていた。焔ならきっと大丈夫だろう、という魂胆もあってのチョイスである。彼に現在彼女がいないという情報もガッチリとゲットしていたから尚更だ。
――くっそ、だからってさあ……あんな言い方することないじゃん!
そう、そのはず、だったのだが。
蓋を開けてみれば、焔はとんでもない毒舌男だった。美園が調べてきた怪奇現象の研究レポートを、“自分の足で取材もせず、よくこの程度の内容を自信満々に出して来れたものだな”と鼻で笑って見せたのである。文化祭では、怪奇現象クラブも研究成果を発表することになっている。研究成果を纏めた新聞も出す。この程度では発表に組み込むことも記事に取り入れることも到底不可能だ、ゼロからやり直せ――彼はちらっと見ただけで、あっさりと一刀両断してきたのだった。
確かに、実際に取材には行っていない。それでもネットと図書館でかなりの情報は取り入れたし、自分にしてはかなり大真面目に話をまとめたつもりだったというのに――何も、あそこまできつい言い方をしなくてもいいではないか。
聞けば、あれが焔の通常運転なのだという。彼はオカルト研究に関しては一切の妥協がないと有名だったのだそうだ。ついでに、女性に関しても同様で、あれだけのイケメンなのにカノジョの影が一切見えないのだという。実は同性愛者なんじゃないの、なんて噂がうっかり立つほどである。彼にアタックして撃沈どころか粉砕された女性は数多く存在するのだとか、なんとか。
――私だってさあ!頑張ったんだからさあ!ちょっとは認めてくれてもいいじゃないのさあ!
ああ、一人暮らしで良かった、と心底思う。多少荒れていても、それを誰かに見咎められるということがないのだから。
――今に見てろよお……!すっごいレポート出して、鼻を明かしてやるんだから!
美園は真っ暗な部屋で、ひたすらパソコンと向かい合っていた。取材をするにせよ、場所やら噂やらにアタリはつけなければいけない。何でもいいから、面白そうな話が落ちてやしないかどうか。
そう、動機など、そんな程度だったのである。
美園がとある大型掲示板を覗こうと思った、その理由なんてものは。
鈴の音が規則的に、断続的に響き渡る。あれはなんという道具だっただろうか、と篠崎秋乃は思った。神社かお寺か、そのへんの行事で見たことがあるような気がするがよく覚えていない。学校で勉強したかもしれないが、生憎秋乃は授業は基本寝ているかサボっているかのどちらかである。秋乃の高校の生徒は誰も彼もそんなものだった。元々偏差値の低い、やる気のない子供ばかり集まるのだから仕方のないことかもしれないが。
――ああ、よくわかんないけど、でも。やばいんだよね、これ。
出来が良くない頭でも、現状のまずさは十二分に分かるのだ。姉に連れられて、面白半分に“此処”に来てしまった自分は確かに不謹慎であったのかもしれない。それこそ、この地で失踪した人間の死体でも見つかったら一躍有名人じゃないか、なんて二人でおおはしゃぎしていたのは事実だ。それが悪いことであったというのなら素直に謝罪しよう。でも。
だからって、こんな。こんなよくわからない目に遭わせられなければいけないほど、いけないことをしてしまっただろうか。
ただ此処に来て、彼らと少し話をした、それだけの筈である。死体を探しているとか、失踪者がいたんじゃないかとか、姉はどうか知らないが少なくとも秋乃はそんな話も口にしていない。というか、村のお祭りが楽しすぎて、途中からそんな目的さえ忘れていたというのが正しい。それが何故、こんな松明の明かりしか見えないような真っ暗な場所で――両手両足を広げて、棒に貼り付けられなければいけないのだろうか。
これではまるで、十字架に磔られたどこぞの神様のようだ。
いや、十字架ならもう少しマシな姿であったことだろう。棒は十時ではなく、バッテン印のように組まれている。手足はその棒の端にそれぞれくくりつけられているため、両手両足を大きく広げて、それもかなり引っ張られる形で固定されている状態だった。身動きするたび縄が食い込むし、ぎちぎちに伸ばされた関節が痛くてしょうがない。この時点で十分拷問だというのに――これがまだ、始まりでしかないことは嫌でも理解できる状況だ。
怪しい白装束の集団が、大量の鈴をつけた棒を規則的に地面に打ち付け、鳴らし続けている。
それに合わせて、やや耳に痛い――不協和音のような笛の音が、延々と奏者によって奏でられている。真っ黒な増えだ。尺八とか、そういうものに似ているようにも見えるが、残念ながら勉強をサボり続けてきた秋乃にその正体がわかるはずもない。ひょっとしたら、一般では流通していない、この地域特有の楽器か何かであるのかもしれなかった。
此処が何処であるのかも、わからない。
目覚めたらこの場所にいた。恐らく屋内であろうということはわかるが、それだけだ。自分が眠ってからどれほどの時間が過ぎたかも定かではない。多少トイレに行きたくなっているので、それなりに時間は経過したものと予想できるけども。
――これ、まるでホラゲーじゃん。なんなのこれ。何が始まるっていうの。
そういえば、姉はどうしたのだろうか。同じ部屋で眠っていたはずなのだが、彼女は無事なのか。あるいは、彼女もまた何処かで捕まっているのだろうか。
もし無事ならば、助けに来て欲しい。あれでも姉は、学生時代柔道部に所属していたはず。こんな白装束のよくわからん連中なんて簡単になぎ倒せるはずなのだ。今の自分に出来ることは、姉がどうにか助けてくれることを信じて待つだけである。それがたとえ、儚い望みでしかないのだとしても、だ。
「籤を」
真正面で鈴を振っていた、頭に金ピカの冠をつけたいかにも偉そうな男性が、低く威厳のある声でそう宣言した。瞬間、鈴の音も笛の音もぴたりと止まる。そしてその偉い人のところに、従者らしき白装束の一人が四角い木の箱を持ってきた。箱には、しめ縄のようなものが巻かれている。いかにも神聖なものであると言わんばかりだ。
冠をつけた男性は何事かの呪文を唱えつつ、箱の中にそっと手を差し入れた。そして、一枚の折りたたまれた白い紙を取り出し――読み上げる。
「此度の文字は……“裂《れつ》”」
紙は、それなりに大きなものだった。彼が紙を広げて全員に見せたことで、秋乃にもそこに書かれたものがしっかりと目に入ることになる。
筆で書かれた――恐らくは相当達筆というものなのだろう。その文字は“引き裂く”とかの“裂”という字だった。不吉なことに黒ではなく、まるで血のような真っ赤な文字で記されている。嫌な予感に、心臓が跳ね上がった。その文字が一体何なのか、何を意味するのか、秋乃の頭は既に想像することを拒んでいる。
――や、やだ。やだよ。何するの、ねえ。
大量の白装束達がわらわらと現れた。縛り付けられた秋乃の前に、綺麗に列を成して並ぶ。そして、一番前の者は何か台座のようなものを掲げていた。
そこに置かれていたのは、この場に非常に相応しくない、現代的な道具。――あれは、ペンチというもの、ではなかろうか。
「それでは皆様、一本ずつ、“引き裂いて”いきましょう」
偉い人が、声をかけた。それと同時に、秋乃の後ろから現れた白装束が、秋乃の両足首に手をかける。何をするのかと思ったら、靴と靴下を脱がし始めたではないか。秋乃は暴れるが、両手両足をがっちり固定されたこの状況ではどうにもならない。
「しかし、人間の体は思いのほか頑丈なものです。最終的に“引き裂き”になれば、ある程度の“切れ込み”を入れても構いません。包丁もご用意しておりますので、ご希望の方は儀式の折に申し出てください。指が終わったら、次は腕と足になります。こちらは機械で巻き取る準備もございます」
理解して、しまった。自分がこれから、どのような目に遭うのかということを。
――やだ、やだやだやだ!なんでよ、なんであたしがそんあの!
本当に恐ろしい時、人は声も出せなくなるのだと知った。悲鳴を上げて助けを呼びたいのに、喉は凍りついたように音を発してくれる気配がない。暴れようにも、ぎしぎしと縄をきしませ、ますます関節を痛めただけに終わった。何もかもがわからない。何故自分が、このような拷問めいた目に遭うことを強要されているのかも。
――助けて……助けてお姉ちゃん!助けてよ、誰か、誰か!
再び鳴り出す、鈴の音、笛の音、得体の知れぬ呪文の声。
白装束の一人が、ペンチを持って近づいてくるのを――秋乃はただ、絶望的な目で見つめる他なかった。
***
「あーもうくっそ!マジむっかつく!ちょっとイケメンだからっていい気になってんなアホー!!」
堂島美園は叫ぶと、パソコン横のデスクに思い切り缶ビールを叩きつけた。若干残っていた中身が溢れた気配があったが、今は無視の無視である。後で面倒になることはわかっていたが、酔いが回った頭では今すぐどうにかしようという気持ちは微塵も起こらなかった。一人ビール祭でも開催しなければやっていられない。それほどまでに、今日の出来事は美園にとって屈辱的だったのだ。
藍里大学のオカルト研究サークル、“怪奇現象研究クラブ”。記者に憧れ、同時に不思議な現象に興味を持っていた美園がそのサークルを選ぶのは必然的であったと言える。大学一年生の時は勉強が忙しすぎて、どこのサークルに入る余裕もなかったが、二年生になった今年からは違うのだ。必修科目の類もかなり目処が立っているし、今年からはもっと好きなことに邁進できるはず。美園は今年の春、意気揚々と怪奇現象研究クラブの門を叩いたメンバーだった。実際、自分達の学部の生徒なら、二年生からサークル所属を希望する者も少なくないのである。
他にも小さなオカルト研究サークルはあったが、此処が一番大手で人数も多かった。同時に、部長の新倉焔がインテリ系イケメンで、かなり美園の好みなタイプであったというのもある。二つ年上だが、年下にも見えるような童顔でありすらっと細身である、というのも高いポイントだった。現金かもしれないが、美園も二十歳の女である。そろそろ彼氏が欲しい、なんて野望を抱くのも別段おかしなことではないはずだ。
ちなみに美園、現在彼氏いない歴三年である。高校生の時に付き合っていた男とは、ちょっと人に説明したくないくらいひどい別れ方をしてしまっていた。焔ならきっと大丈夫だろう、という魂胆もあってのチョイスである。彼に現在彼女がいないという情報もガッチリとゲットしていたから尚更だ。
――くっそ、だからってさあ……あんな言い方することないじゃん!
そう、そのはず、だったのだが。
蓋を開けてみれば、焔はとんでもない毒舌男だった。美園が調べてきた怪奇現象の研究レポートを、“自分の足で取材もせず、よくこの程度の内容を自信満々に出して来れたものだな”と鼻で笑って見せたのである。文化祭では、怪奇現象クラブも研究成果を発表することになっている。研究成果を纏めた新聞も出す。この程度では発表に組み込むことも記事に取り入れることも到底不可能だ、ゼロからやり直せ――彼はちらっと見ただけで、あっさりと一刀両断してきたのだった。
確かに、実際に取材には行っていない。それでもネットと図書館でかなりの情報は取り入れたし、自分にしてはかなり大真面目に話をまとめたつもりだったというのに――何も、あそこまできつい言い方をしなくてもいいではないか。
聞けば、あれが焔の通常運転なのだという。彼はオカルト研究に関しては一切の妥協がないと有名だったのだそうだ。ついでに、女性に関しても同様で、あれだけのイケメンなのにカノジョの影が一切見えないのだという。実は同性愛者なんじゃないの、なんて噂がうっかり立つほどである。彼にアタックして撃沈どころか粉砕された女性は数多く存在するのだとか、なんとか。
――私だってさあ!頑張ったんだからさあ!ちょっとは認めてくれてもいいじゃないのさあ!
ああ、一人暮らしで良かった、と心底思う。多少荒れていても、それを誰かに見咎められるということがないのだから。
――今に見てろよお……!すっごいレポート出して、鼻を明かしてやるんだから!
美園は真っ暗な部屋で、ひたすらパソコンと向かい合っていた。取材をするにせよ、場所やら噂やらにアタリはつけなければいけない。何でもいいから、面白そうな話が落ちてやしないかどうか。
そう、動機など、そんな程度だったのである。
美園がとある大型掲示板を覗こうと思った、その理由なんてものは。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

ジャクタ様と四十九人の生贄
はじめアキラ
ホラー
「知らなくても無理ないね。大人の間じゃ結構大騒ぎになってるの。……なんかね、禁域に入った馬鹿がいて、何かとんでもないことをやらかしてくれたんじゃないかって」
T県T群尺汰村。
人口数百人程度のこののどかな村で、事件が発生した。禁域とされている移転前の尺汰村、通称・旧尺汰村に東京から来た動画配信者たちが踏込んで、不自然な死に方をしたというのだ。
怯える大人達、不安がる子供達。
やがて恐れていたことが現実になる。村の守り神である“ジャクタ様”を祀る御堂家が、目覚めてしまったジャクタ様を封印するための儀式を始めたのだ。
結界に閉ざされた村で、必要な生贄は四十九人。怪物が放たれた箱庭の中、四十九人が死ぬまで惨劇は終わらない。
尺汰村分校に通う女子高校生の平塚花林と、男子小学生の弟・平塚亜林もまた、その儀式に巻き込まれることになり……。



最終死発電車
真霜ナオ
ホラー
バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。
直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。
外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。
生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。
「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!


追っかけ
山吹
ホラー
小説を書いてみよう!という流れになって友達にどんなジャンルにしたらいいか聞いたらホラーがいいと言われたので生まれた作品です。ご愛読ありがとうございました。先生の次回作にご期待ください。
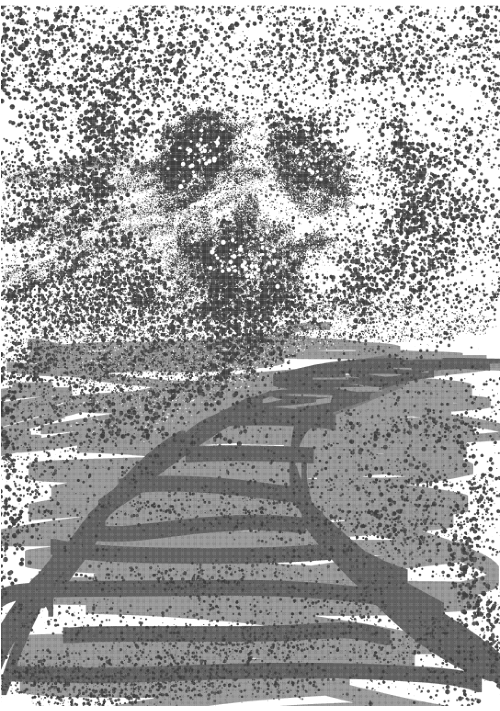

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















