24 / 26
第24話 今に至る二つの失敗
しおりを挟む
人と他人は完全に分かり合う事は出来ない。
どんなに素晴らしい絵画、物語、そして教えを見ても百人が百人同じ反応をするとは限らないのだ。
応供はその事実を転移前からよく理解していた。 星と運命の女神の教えをいくら説いたとしても完璧に伝え、理解させるのは至難の業と言っていい。
応供は無意識に拳を握って閉じる。 思い出したからだ。
初めて人を殺した時の事を。 アレは小学生の頃だった。
ズヴィオーズ様から力を授かり見るもの全てが変わった時、応供は脳内にのみ存在する女神の威光をどうにか現実に反映させようと必死に知恵を絞っている時だ。
幼く、拙い応供には上手い方法が思い浮かばずに取り敢えず、記憶力を頼りに絵を描いてみたのだ。
自分の画力では女神様の美しさを1%も表現できないが、少しでもと行動したのだが――
隣の席にいた子供に邪魔をされた。 バラエティー番組に歪んだ形で感化され、他人を笑いものにしてクラスで一定の地位を獲得し、自身が他よりも上等と錯覚した愚かな生き物だった。
正直、自分の事は割とどうでもよかったのだが、拙いとはいえ女神様を象った絵を破り捨てたのは看過できなかった。 ミュリエルの父親と同じように謝罪させようとしたが、女神様の素晴らしさを欠片も理解できない愚かな脳みそに非を認めるといった行為は断じて許容できなかったようだ。
その為、謝るまで殴りつけたのだが、周囲に止められてしまった。
応供は自らの正当性を周囲に説明したが、誰も彼も――応供の両親ですら彼の考えを理解できなかったのだ。 それどころか暴力はいけない事だ、お前が悪い、やりすぎだと話を聞く気がない。
その時に子供心に応供は悟った。 こいつ等は結局、目に見える事しか信じないのだろうと。
誰も応供の世界を理解しない。 理解しようともしない。
殴ったクラスメイトの親にはお前の所為で俺の息子は障害を一生抱える事になったどうしてくれると詰られた。
――この世界では正しい事を正しいと叫んでも理解されない。
何故なら正しさの定義が個々人で異なるからだ。
応供は目の前で怒鳴り散らす大人に自らの正当性を正面から説いたが、返って来たのは拳による一撃だ。 そこは納得できた。 彼等は身内を傷つけられて怒っている。
救いようがない生き物を生み出したという欠陥はあるが、その怒りは正当なものだ。
だから素直に殴られていたのだが、彼等は救いようのない生き物の生産元という事をすっかり忘れていた。 あろう事かそいつらも女神様の事を馬鹿にしたのだ。
だから応供は目の前の知能が存在せず、猿のように喚く事しか出来ない生き物達を殴り殺した。
女神様から賜った力を以ってすれば小学生でも大の大人を正面から殴り殺すなど朝飯前だ。
やはり女神様のお力は素晴らしい。 だが、猿以下の産廃でも一応は人間とカテゴライズされる生き物を殺すのは不味かった。
面倒事になるのは応供にも理解できたので、彼はその日にこれまでの日常と別れを告げたのだ。
――その事件は応供に大きな学びを与えた。
他人を信じさせるには目に見える物で信じさせねばならない。
つまりは女神様の素晴らしさを他人に理解させる為には変換作業が必要になる。
だから彼は自らに与えられた力を磨き、他者に施す事で女神様の素晴らしさ、そして信奉する事がいかに得なのかを伝えたのだ。 こうして生まれたのが星運教。
最初は上手く行っていた。
人が増え、女神ズヴィオーズの素晴らしさを間接的ではあるが、理解し始めた者も現れる。
組織の運営としてもそこそこ以上に上手く行っていた。
――だが、ここで応供は新しい失敗を経験、気付きを得る。
出る杭は打たれる。
よく聞く言葉だが、彼の二度目の失敗を表現するのにこれ以上のものはなかった。
応供はこの時点で他人に干渉し、その才能を開花させる術を身に付けていたのだ。
異能力と呼ばれる才能を。
それはその力を以前から操り、独占していた者達からすれば非常に目障りだったようだ。
こうして闘いの日々が始まった。 彼の尊厳を踏み躙ろうとする者達に応供は持てる力の全てを使って抗う。
次第に他者を傷つける術に長け、破壊する術に通ずるようになった。
戦いの日々の果てが応供の今だ。 応供はこの世界に流れ着いてからもずっと考えていた。
自分は何をしくじったのだろうかと。
彼が把握している失敗の要因は大きく二つ。
他人とは完璧に分かり合えない。 出る杭は打たれる。
この二つを念頭に置いて動かなければならない。
同じ失敗を繰り返すのは愚か者の行為。 応供は自身が完璧だとは思っていない。
だが、女神から力を賜った身としては彼女に恥じない自分でありたい。
――だから――
「さぁ、俺の手を取ってください。 俺はただ、教えを通して皆で幸せになりたいだけなんですよ」
目の前にいる疑念でいっぱいの村人に手を差し伸べる。
村人――確かオムという男は差し出された応供の手を見て迷うような素振りを見せた。
表情から半信半疑と言ったところだろう。 頭から疑っているにもかかわらず信が半分なのはそれだけ加護がないという事が彼にとってのコンプレックスであった事を意味する。
信じられない。 でも本当なら是非とも欲しい。
基本的にこの世界で得られる加護は生まれつきだ。 後から手に入れる事も可能ではあるが、誰でも容易という訳には行かない。 そうでなければオムもとっくに何かしらの加護を得ているはずだ。
「ほ、本当なんだな!?」
「はい、嘘ではありません。 そこまで深く考える必要はありませんよ。 気軽に試すだけでもいかがですか? あなたがするのは同意して俺の手を掴むだけ、難しい事ではありませんよ」
「わ、分かった。 う、嘘だったら許さないからな!?」
「えぇ、お好きにどうぞ」
オムは応供の手を掴む。 これでいい。
応供はこの世界に存在するステータスという仕組みを短時間でかなり深い部分まで理解していた。
同時に自身がどの程度の権限を持つ存在なのかも。
だから、こんな事も簡単にできてしまう。 オムの中に応供の力が流れ込んでいく。
スキル欄に阿羅漢の加護が入り、対応したステータスが爆発的に上昇する。
「お、おぉ……」
オムが自身に漲る力とスキル欄に追加された加護を見て歓喜の涙を流す。
応供は笑顔を絶やさない。 オムは応供の手を握ったまま跪いた。
意識しての行動ではなく、自然とそうなったのだ。
「ありがとう。 ありがとうございます」
長年のコンプレックスが解消され歓喜の涙を流しながら感謝を口にするオムに応供は――
「いえいえ、こちらこそありがとうございます」
――そう返した。
どんなに素晴らしい絵画、物語、そして教えを見ても百人が百人同じ反応をするとは限らないのだ。
応供はその事実を転移前からよく理解していた。 星と運命の女神の教えをいくら説いたとしても完璧に伝え、理解させるのは至難の業と言っていい。
応供は無意識に拳を握って閉じる。 思い出したからだ。
初めて人を殺した時の事を。 アレは小学生の頃だった。
ズヴィオーズ様から力を授かり見るもの全てが変わった時、応供は脳内にのみ存在する女神の威光をどうにか現実に反映させようと必死に知恵を絞っている時だ。
幼く、拙い応供には上手い方法が思い浮かばずに取り敢えず、記憶力を頼りに絵を描いてみたのだ。
自分の画力では女神様の美しさを1%も表現できないが、少しでもと行動したのだが――
隣の席にいた子供に邪魔をされた。 バラエティー番組に歪んだ形で感化され、他人を笑いものにしてクラスで一定の地位を獲得し、自身が他よりも上等と錯覚した愚かな生き物だった。
正直、自分の事は割とどうでもよかったのだが、拙いとはいえ女神様を象った絵を破り捨てたのは看過できなかった。 ミュリエルの父親と同じように謝罪させようとしたが、女神様の素晴らしさを欠片も理解できない愚かな脳みそに非を認めるといった行為は断じて許容できなかったようだ。
その為、謝るまで殴りつけたのだが、周囲に止められてしまった。
応供は自らの正当性を周囲に説明したが、誰も彼も――応供の両親ですら彼の考えを理解できなかったのだ。 それどころか暴力はいけない事だ、お前が悪い、やりすぎだと話を聞く気がない。
その時に子供心に応供は悟った。 こいつ等は結局、目に見える事しか信じないのだろうと。
誰も応供の世界を理解しない。 理解しようともしない。
殴ったクラスメイトの親にはお前の所為で俺の息子は障害を一生抱える事になったどうしてくれると詰られた。
――この世界では正しい事を正しいと叫んでも理解されない。
何故なら正しさの定義が個々人で異なるからだ。
応供は目の前で怒鳴り散らす大人に自らの正当性を正面から説いたが、返って来たのは拳による一撃だ。 そこは納得できた。 彼等は身内を傷つけられて怒っている。
救いようがない生き物を生み出したという欠陥はあるが、その怒りは正当なものだ。
だから素直に殴られていたのだが、彼等は救いようのない生き物の生産元という事をすっかり忘れていた。 あろう事かそいつらも女神様の事を馬鹿にしたのだ。
だから応供は目の前の知能が存在せず、猿のように喚く事しか出来ない生き物達を殴り殺した。
女神様から賜った力を以ってすれば小学生でも大の大人を正面から殴り殺すなど朝飯前だ。
やはり女神様のお力は素晴らしい。 だが、猿以下の産廃でも一応は人間とカテゴライズされる生き物を殺すのは不味かった。
面倒事になるのは応供にも理解できたので、彼はその日にこれまでの日常と別れを告げたのだ。
――その事件は応供に大きな学びを与えた。
他人を信じさせるには目に見える物で信じさせねばならない。
つまりは女神様の素晴らしさを他人に理解させる為には変換作業が必要になる。
だから彼は自らに与えられた力を磨き、他者に施す事で女神様の素晴らしさ、そして信奉する事がいかに得なのかを伝えたのだ。 こうして生まれたのが星運教。
最初は上手く行っていた。
人が増え、女神ズヴィオーズの素晴らしさを間接的ではあるが、理解し始めた者も現れる。
組織の運営としてもそこそこ以上に上手く行っていた。
――だが、ここで応供は新しい失敗を経験、気付きを得る。
出る杭は打たれる。
よく聞く言葉だが、彼の二度目の失敗を表現するのにこれ以上のものはなかった。
応供はこの時点で他人に干渉し、その才能を開花させる術を身に付けていたのだ。
異能力と呼ばれる才能を。
それはその力を以前から操り、独占していた者達からすれば非常に目障りだったようだ。
こうして闘いの日々が始まった。 彼の尊厳を踏み躙ろうとする者達に応供は持てる力の全てを使って抗う。
次第に他者を傷つける術に長け、破壊する術に通ずるようになった。
戦いの日々の果てが応供の今だ。 応供はこの世界に流れ着いてからもずっと考えていた。
自分は何をしくじったのだろうかと。
彼が把握している失敗の要因は大きく二つ。
他人とは完璧に分かり合えない。 出る杭は打たれる。
この二つを念頭に置いて動かなければならない。
同じ失敗を繰り返すのは愚か者の行為。 応供は自身が完璧だとは思っていない。
だが、女神から力を賜った身としては彼女に恥じない自分でありたい。
――だから――
「さぁ、俺の手を取ってください。 俺はただ、教えを通して皆で幸せになりたいだけなんですよ」
目の前にいる疑念でいっぱいの村人に手を差し伸べる。
村人――確かオムという男は差し出された応供の手を見て迷うような素振りを見せた。
表情から半信半疑と言ったところだろう。 頭から疑っているにもかかわらず信が半分なのはそれだけ加護がないという事が彼にとってのコンプレックスであった事を意味する。
信じられない。 でも本当なら是非とも欲しい。
基本的にこの世界で得られる加護は生まれつきだ。 後から手に入れる事も可能ではあるが、誰でも容易という訳には行かない。 そうでなければオムもとっくに何かしらの加護を得ているはずだ。
「ほ、本当なんだな!?」
「はい、嘘ではありません。 そこまで深く考える必要はありませんよ。 気軽に試すだけでもいかがですか? あなたがするのは同意して俺の手を掴むだけ、難しい事ではありませんよ」
「わ、分かった。 う、嘘だったら許さないからな!?」
「えぇ、お好きにどうぞ」
オムは応供の手を掴む。 これでいい。
応供はこの世界に存在するステータスという仕組みを短時間でかなり深い部分まで理解していた。
同時に自身がどの程度の権限を持つ存在なのかも。
だから、こんな事も簡単にできてしまう。 オムの中に応供の力が流れ込んでいく。
スキル欄に阿羅漢の加護が入り、対応したステータスが爆発的に上昇する。
「お、おぉ……」
オムが自身に漲る力とスキル欄に追加された加護を見て歓喜の涙を流す。
応供は笑顔を絶やさない。 オムは応供の手を握ったまま跪いた。
意識しての行動ではなく、自然とそうなったのだ。
「ありがとう。 ありがとうございます」
長年のコンプレックスが解消され歓喜の涙を流しながら感謝を口にするオムに応供は――
「いえいえ、こちらこそありがとうございます」
――そう返した。
0
お気に入りに追加
12
あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

日本帝国陸海軍 混成異世界根拠地隊
北鴨梨
ファンタジー
太平洋戦争も終盤に近付いた1944(昭和19)年末、日本海軍が特攻作戦のため終結させた南方の小規模な空母機動部隊、北方の輸送兼対潜掃討部隊、小笠原増援輸送部隊が突如として消失し、異世界へ転移した。米軍相手には苦戦続きの彼らが、航空戦力と火力、機動力を生かして他を圧倒し、図らずも異世界最強の軍隊となってしまい、その情勢に大きく関わって引っ掻き回すことになる。

明智さんちの旦那さんたちR
明智 颯茄
恋愛
あの小高い丘の上に建つ大きなお屋敷には、一風変わった夫婦が住んでいる。それは、妻一人に夫十人のいわゆる逆ハーレム婚だ。
奥さんは何かと大変かと思いきやそうではないらしい。旦那さんたちは全員神がかりな美しさを持つイケメンで、奥さんはニヤケ放題らしい。
ほのぼのとしながらも、複数婚が巻き起こすおかしな日常が満載。
*BL描写あり
毎週月曜日と隔週の日曜日お休みします。

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。

ギャルい女神と超絶チート同盟〜女神に贔屓されまくった結果、主人公クラスなチート持ち達の同盟リーダーとなってしまったんだが〜
平明神
ファンタジー
ユーゴ・タカトー。
それは、女神の「推し」になった男。
見た目ギャルな女神ユーラウリアの色仕掛けに負け、何度も異世界を救ってきた彼に新たに下った女神のお願いは、転生や転移した者達を探すこと。
彼が出会っていく者たちは、アニメやラノベの主人公を張れるほど強くて魅力的。だけど、みんなチート的な能力や武器を持つ濃いキャラで、なかなか一筋縄ではいかない者ばかり。
彼らと仲間になって同盟を組んだユーゴは、やがて彼らと共に様々な異世界を巻き込む大きな事件に関わっていく。
その過程で、彼はリーダーシップを発揮し、新たな力を開花させていくのだった!
女神から貰ったバラエティー豊かなチート能力とチートアイテムを駆使するユーゴは、どこへ行ってもみんなの度肝を抜きまくる!
さらに、彼にはもともと特殊な能力があるようで……?
英雄、聖女、魔王、人魚、侍、巫女、お嬢様、変身ヒーロー、巨大ロボット、歌姫、メイド、追放、ざまあ───
なんでもありの異世界アベンジャーズ!
女神の使徒と異世界チートな英雄たちとの絆が紡ぐ、運命の物語、ここに開幕!
※毎週、月、水、金曜日更新
※感想やお気に入り登録をして頂けますと、作者のモチベーションがあがり、エタることなくもっと面白い話が作れます。
※追放要素、ざまあ要素は第二章からです。
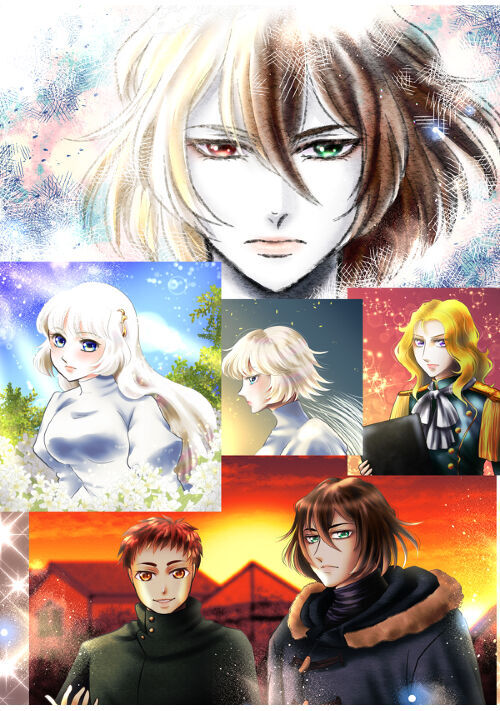
アストルムクロニカ-箱庭幻想譚-(挿し絵有り)
くまのこ
ファンタジー
これは、此処ではない場所と今ではない時代の御伽話。
滅びゆく世界から逃れてきた放浪者たちと、楽園に住む者たち。
二つの異なる世界が混じり合い新しい世界が生まれた。
そこで起きる、数多の国や文明の興亡と、それを眺める者たちの物語。
「彼」が目覚めたのは見知らぬ村の老夫婦の家だった。
過去の記憶を持たぬ「彼」は「フェリクス」と名付けられた。
優しい老夫婦から息子同然に可愛がられ、彼は村で平穏な生活を送っていた。
しかし、身に覚えのない罪を着せられたことを切っ掛けに村を出たフェリクスを待っていたのは、想像もしていなかった悲しみと、苦難の道だった。
自らが何者かを探るフェリクスが、信頼できる仲間と愛する人を得て、真実に辿り着くまで。
完結済み。ハッピーエンドです。
※7話以降でサブタイトルに「◆」が付いているものは、主人公以外のキャラクター視点のエピソードです※
※詳細なバトル描写などが出てくる可能性がある為、保険としてR-15設定しました※
※昔から脳内で温めていた世界観を形にしてみることにしました※
※あくまで御伽話です※
※固有名詞や人名などは、現代日本でも分かりやすいように翻訳したものもありますので御了承ください※
※この作品は「ノベルアッププラス」様、「カクヨム」様、「小説家になろう」様でも掲載しています※

スキル【アイテムコピー】を駆使して金貨のお風呂に入りたい
兎屋亀吉
ファンタジー
異世界転生にあたって、神様から提示されたスキルは4つ。1.【剣術】2.【火魔法】3.【アイテムボックス】4.【アイテムコピー】。これらのスキルの中から、選ぶことのできるスキルは一つだけ。さて、僕は何を選ぶべきか。タイトルで答え出てた。

前世の記憶で異世界を発展させます!~のんびり開発で世界最強~
櫻木零
ファンタジー
20XX年。特にこれといった長所もない主人公『朝比奈陽翔』は二人の幼なじみと充実した毎日をおくっていた。しかしある日、朝起きてみるとそこは異世界だった!?異世界アリストタパスでは陽翔はグランと名付けられ、生活をおくっていた。陽翔として住んでいた日本より生活水準が低く、人々は充実した生活をおくっていたが元の日本の暮らしを知っている陽翔は耐えられなかった。「生活水準が低いなら前世の知識で発展させよう!」グランは異世界にはなかったものをチートともいえる能力をつかい世に送り出していく。そんなこの物語はまあまあ地頭のいい少年グランの異世界建国?冒険譚である。小説家になろう様、カクヨム様、ノベマ様、ツギクル様でも掲載させていただいております。そちらもよろしくお願いします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















