6 / 8
5、転
転
しおりを挟む
電車に揺られながら、私は先ほど録音した東雲との会話を聞いていた。
全く、なんと無様なやりとりであることか。東雲脅迫用として録音したものだが、こんな内容、誰にも聞かせられない。そんなもん、私が犯人だと自白するも同然である。まさか東雲由紀乃があれほどできる女だとは思わなかった。私のトリックを見破り、私の言葉の隙を巧みについて論理的に私を苦しめた。彼女の決死の覚悟は、私を道連れにすることに成功していた。教師と生徒という関係でなかったなら私は敗北を喫していただろう。
なんとも腹が立つのは、自身のいやらしさである。圧倒的な劣勢に立たされておきながら自身の優位を誇張するために東雲の教師としての矜持をずたずたにしてしまった。
東雲の歯痒そうな顔。
破滅を悟った時の息遣い。
それでもなお抗い続けた瞳。
東雲は、これからも教師として生きていけるのだろうか。
少なくとも、私と彼女との関係は壊れた。
彼女は良い教師であった。
彼女は単に勉強を教えることだけに飽き足りる教師ではなかった。
彼女は大学入試で問われる以上のことを私たちに教えようとしていた。
本来なら、もっともっと多くの生徒に寄り添い、導く存在だった。
そんな彼女がもし、教師をやめてしまったら——。
東雲の、今にも泣きだしそうな顔が脳裏によみがえる。
彼女は何と戦っていたのか。
彼女は何故私と戦うことを選んだのか。
私の犯行を暴いてどうしようと思ったのか。
素直に私が反省すると思ったのか?
する訳がない、第一、もう手遅れだ。
私の犯行を暴いて彼女に何か得することがあったか?
お互いが傷を負っただけではないか、彼女に至っては致命傷だ。
そんなこと、最初から分かっていたことではないか。
それほどまでに彼女は愚かだったのか?
それとも、そんなことも分からない私が阿呆なのか?
もういい、考えるのはよそう、もう終わった話だ。
電車の窓から見える夕焼け空は、どこか淀んでいた。
*
最終下校時刻を過ぎて久しい保健室。養護教諭の白石に差し出されたココアを、ベッドに腰掛けたまま由紀乃は口をつけずに見つめている。
「少しは気持ち、落ち着いたかな?」
白石は由紀乃の隣に腰掛け、顔色を伺う。
しかし由紀乃は力なく首を横に振る。
「そっか」そう言って、白石は視線を由紀乃から外す。
気持ちが全く収まらない。
椚田の犯行を暴くことができず大敗を喫した記憶は由紀乃の心の奥深くに突き刺さっていた。
純粋に悔しかった。年下の、高校生男子に言い負かされ、馬鹿にされ、教師失格の烙印を押され、挙句の果てには脅迫まがいの行為まで受けた。それを思い出すだけで、涙が止まらなくなった。
「私、もう教師としてやっていけません」
涙声で、由紀乃がそう零す。
「明日から、どんな顔で生徒の前に立てばいいのか分かりません」
白石は、黙って由紀乃の頭を自身の胸に抱きよせた。そうして由紀乃の頭を撫でる。白石の胸に顔をうずめるようにして、由紀乃は咽び泣く。
「私が馬鹿でした、生徒を疑ってはいけないって、誰もが知ってることなのに、私は、自分が正しいって思って、でも、結果は……っ!」
そこまでしか、言葉にできなかった。
悔しくてたまらない。自分の愚かしさが。
「どうして自分は間違っているって思うの?」
由紀乃の頭を撫でていた白石が、ぽつりとそう尋ねる。
由紀乃は呻く。
「だって…」
結果はこの様で。
「私と椚田くんの関係は、もうボロボロで——」
「それは現在の状況だよね?」
「そう、ですけど」
何を、言おうとしているのだ、白石は。
由紀乃はそっと視線を上げる。
「前にも聞いたけどさ、由紀乃ちゃんは、どうして椚田さんの犯行を暴きたかったの?」
「それは…」
話がしたかった。
純粋に、これまでのこと、これからのこと。
「話がしたかったんだよね?」
そうだ、話しがしたかったのだ。
それがいつのまにか、犯行を暴く暴かれないの勝負になっていた。
勝つか負けるかの戦いとなれば、お互いが傷つくのは当然ではないか。
「椚田さんのトリックの秘密を教える時、実は躊躇したんだよね、こうなる可能性も、見えていたから」
「え?」
「椚田さんと話をするのに、本当に彼の秘密を暴く必要があったのか、考えていたんだよね」
由紀乃は訥々と話す白石の顔を見つめている。
「必要は、なかったのかもしれないね、今まで何もしてやれなくてごめんと謝って、これからは何でも相談して欲しいと伝え、ついでに今、松山さんがすごく傷ついていることも話して、これからのことを話して」
必要のないことだった、必要のないことをしたから傷ついた。
そっか、私って本当に、馬鹿だなぁ。
由紀乃は俯き、自嘲する。
「でもね、私だったら、暴くね」
「え⁉」憧れの教師の思わぬ一言に、由紀乃は身を起こし、再度その顔を見る。綺麗な眼差しで、何を言ってるのだこの人は。
「必要はないのかもしれない、でも、暴かないと、生徒も『こいつは一体どこまで知っていながら話してるんだ』と余計不審に思う。だって彼、自分のトリックに絶大な自信があったろうからね。彼のトリックを暴かないことには、『単に怪しいからって理由で疑ってるんだろうな』って思われるだろう。なんにせよ、ノイズが多い。自分は君の全てを知っている、知ってなお、こうして話したいんだ、そう思わせたい。由紀乃ちゃんも、そうだったんじゃないの?」
そうだ。
そうだった。
「でも、結果は」
結果は、最悪な形で——。
「失敗しちゃった、だね」
失敗しちゃった、そんな可愛いもんじゃない。
だって…
「私と椚田くんの関係はもう壊れちゃったんだよ!失敗なんて言葉で済ませられないよ!」
教師という仕事は人の人生を大きく左右する仕事である。大きな責任が伴う。
失敗は許されない。
「大丈夫だよ」
由紀乃の頭を撫でながら、白石は言う。
「壊れちゃったのなら、また作ればいいんだよ、今度はもっと頑丈にね」
何食わぬ顔で、白石は言う。
「失敗は、してもいいんだよ。諦めない限りその失敗はいつか成功に結び付くんだよ」
聞き覚えがある言葉、
そうだ、それは由紀乃が松山へ送った言葉でもあった。
生徒には偉そうにそう言っておいて、自分はこの様、情けない。
「でも、私は教師で、失敗の重みが」
「そんなの関係ない」
「えっ」
「教師だからとか、関係ないよ、働く人は皆なんらかの責任を負っている。どうして教師だけ特別扱いするのか、私には分からない」
由紀乃は表情を曇らせた。確かにそうだ。世間では教師を聖職者と呼ぶが、教師も人間である。それはもう、どうあがいても人間で、況してや聖人ばかりが採用される訳ではない。
「でも、世の中はそんな理屈、認めてくれませんよ」
「いいよ、私が認める」
なんという暴論。一介の養護教諭が何を言う。
「し、白石先生のその、自分は正しいっていう自信はどこから来るんですか?」
「別に自信なんてないよ、ただ、誰かの言う理屈と自分の中の理屈、正しいなと思った方を信じるようにしているだけだよ。由紀乃ちゃんも、そうじゃないの?」
そう聞かれて、ハッとする。
世間一般の正しさは理解しているつもりだった、それでも、なんとなくだけど、それではいけないと思ったから、由紀乃は椚田と対峙することを選んだのだ。
「でも、その結果がこれですよ。やっぱり世間一般の言うことが正しかったってことですよ」
「どこに主眼を置くかだよ、『犯人探しをしてはいけない』『生徒を疑ってはいけない』こう言った教えはね、生徒を守ると同時に由紀乃ちゃんを守る教えでもあったんだよ。こういった問題は難しいからね、誰でも上手に対応できる訳じゃない。今の由紀乃ちゃんみたいに傷を負う人も少なくないし、時には事が学校全体の問題となって、自分以外の教師にまで負担を強いることがある。そうした余計な傷口を広げないための教えでもあるんだよ。根底にあるのはことなかれ主義だと思うけどね」
悪戯っぽく白石が笑う。それから、少し真剣な顔で——。
「由紀乃ちゃんは、誰を守りたかったの?」
誰を、守りたかったのか。
椚田を、彼が過ちを抱えたまま人生を歩まないように、助けたかった。
自分を守りたかった訳では、決してない。
生徒のためなら、自分はどうなってもいいと思った。
でも、言葉では何とでも言えたが、実際の傷は、深くて、痛くて。
そんな由紀乃の弱い心を見透かすように、白石は由紀乃の手を取った。
「一人で戦うのは、辛いよね、だから、言わせてほしい」
白石は、由紀乃の目を見つめた。
「由紀乃ちゃんはまちがってない。私は由紀乃ちゃんの味方だよ。」
道理なんて、どうでもよくなった。
自分が正しいのか、そうでないのか、分からない。
しかし、それは由紀乃の心がずっと欲していた言葉で、
訳も分からず、白石の胸に顔を埋め、声に出して泣いた。
*
私は今まで誰かと恋仲になったことなどないが、男女の関係性というものはもっと時間をかけて育まれるものではないだろうか。
小学校高学年の頃、初恋をした。
小学生基準なのでよく分からないが、相対的に可愛い部類であった。
しかし当時の私にとっては絶対的に可愛かった。
そりゃもう、現在絶対的に可愛い早瀬さんを前にしたら月とゾウガメ程の差はあるが、ピカピカの小学生とイケイケの高校生を比べる方がナンセンスである。本気で比べようものならそれはもう恐ろしい変態である。
何はともあれ私はゾウガメに恋をした。
可愛いなぁ可愛いなぁと毎日見ていた。
可愛いなぁ可愛いなぁと見ているうちに、卒業式を迎えた。
彼女は進学校へと進み、以来、姿を見たことがない。
中学1年生の頃、恋をした。
クラスの8割はポニーテールであったが、中学生基準で相対的に可愛い部類のポニーテールであった。
そんなミシシッピアカミミガメに恋をした。
可愛いなぁ可愛いなぁと思って揺れるポニーテールを毎日見ていた。
可愛いなぁ可愛いなぁと見ているうちに、ミシシッピアカミミガメは別の男と付き合い出した。
彼女は彼氏の意向に従い髪型を変え、以来彼女のポニーテールは見ていない。
中学2年生の頃、恋をした。
彼女は長く美しい黒髪をたなびかせ、多くの男どもを魅了した。
その絶対的な美しさたるや比肩するものなし。後5年すれば絶対的に可愛い早瀬さんもあの領域に至るだろう。
そんな土星に恋をした。
美しいなぁ美しいなぁとなびく黒髪を毎週見ていた。
美しいなぁ美しいなぁと見ているうちに放送は終了した。
第二期が放送される予定は今のところない。
中学3年生の頃、恋をした。
中学3年生ともなると幼き日のように女子を純粋な目で見ることはできない。
彼女は中学生基準で相対的に健康的な美脚を有していた。
そんなアオウミガメに恋をした。
いい肉付きをしているなぁいい肉付きをしているなぁと毎日見ていた。
いい肉付きをしているなぁいい肉付きをしているなぁと毎日見ているうちにまたもや卒業式を迎えた。
以来彼女の美脚は見ていない。
要するに、男女の関係を築き上げるには恐ろしい程の年月を有要する者だと思われる。それだというのに。
「おじゃましまーす」
出会って1週間も経たぬうちに、絶対的に可愛い早瀬さん、襲来。
*
お金のかからないデートプラン休日編ということで、絶対的に可愛い彼女が提案したのがこの休日おしかけ勉強会である。
昼食代も浮いて(親が買った食材でやり過ごすため)、成績も良くなり、親からの好感度も稼げる素晴らしいデートプランであり、私はかねてよりそのようなデートをしてみたいと切に願っていた。それをこのような絶対的に可愛い早瀬さんと行うことができるのだから、椚田一族の中でもこれ程の幸福を掴んだものはいなかろうと思われる、のだが、その恐ろしい程に早い距離の縮め方に私は動揺を隠せない。
動揺を隠せないのは私の家族一同もそうであった。
女の子の後輩がうちに来て、一緒に勉強をする、ということは昨日のうちに伝えており、急遽部屋を片付け準備は万端であったのだが、絶対的に可愛い早瀬さんの絶対的な可愛さを前に玄関で出迎えた私の母親は開口一番「えっ?」と漏らした。ついで自身の部屋から出てきた兄も絶対的に可愛い早瀬さんを見るや「えっ?」と漏らした。親子揃って失礼極まりないが、私も兄がこれ程までに絶対的に可愛い存在を家に招き入れようものなら「えっ?」といって固まることだろう。
本日の彼女は白地のシャツの上にキャメルのカーディガンを羽織り、下はダメージを受けていないジーンズという大人びた風貌をしていた。ギャル装束で来られたらどうしようかと思ったが、常識人なようで安心した。しかし溢れ出る絶対的な可愛さは抑えられない。
「えっ?」と固まる母と兄を残して私は階段を上り絶対的に可愛い早瀬さんを自室に案内した。
「わぁ、ここが先輩の部屋なんですね、片付いていますね、素敵です」
片付けたんだよ、君が来るから。
入って左側には手前から本棚、ベッド、右側には手前から勉強机、クローゼット、中央には今回のためにセッティングした脚の短い木製のテーブルがある。窓は扉の反対側。以上参考にされたし、覚える必要はなし。
「鞄、どこに置いたらいいでしょうか?」絶対的に可愛い早瀬さんが遠慮がちに尋ねる。私は勉強机を指さし、そこに荷物を置くよう伝えた。
「ここで、先輩はいつも勉強しているんですね」私の勉強机を見て絶対的に可愛い早瀬さんは謎の感慨に耽る。
「すごい、先輩、棚にノートがずらぁーって並んでますね」
「うん、高校入った時から使い終わったノートはここに置くようにしているんだ」
「すごい!先輩が2年生の時のノート、見てもいいですか?」私は勉強机の棚から幾つかノートを手に取る。
「ありがとうございます、え?わぁすごい、先輩、無地のノートを使ってるんですか?すごいです、字も綺麗。」
私の高2の頃のノートを見て、絶対的に可愛い早瀬さんが目をキラキラさせる。なにがそんなにすごいんだろう。
「先輩、どの教科もこの、無地のノートを使ってるんですか?」
「うん、まぁね、レイアウトが自由にできるから好きなんだ。」
「確かに文字の大きさも自由に調整出来て、ポップで見ていて楽しいですね。いつから無地のノートを使ってるんですか?」
「高校受験のあたりかな、勉強も苦手で、授業もよく分かっていなかったんだけど、兄がこのノートを使ったノートの取り方を教えてくれて、以来これを使ってる。」
「へぇ、なるほど、罫線の入ったノートはそれ以来一度も買ってないんですか?」
「うん、このノートに慣れちゃったしね」
「そうなんですか、私も真似してみたいです。どこで買ってるんですか?」
「駅近くの文房具屋で僕は買ってるかな」
「あぁ、あそこですか。よろしければ今度買う時ご一緒させてください」
「うん、別にいいけれど」
たかがノートの何がすごいのか、彼女は目をキラキラさせて私のノートを見ている。
「さてと、そろそろ勉強しましょうか。分からない所、教えてくださいね?」
そう言って彼女は勉強道具を取り出した。
彼女は英語の問題集と参考書をテーブルの上に並べる。
私は数学の問題集とノートを取り出した。当然無地である。
絶対的に可愛い早瀬さんが家に来て、どんなイベントが起こるのかと思いきや、意外と普通に勉強する流れに移った。
今日はのんびりした時間が過ごせそうだと思い、問題集とノートをテーブルの上に置いた時、壁際でゴンっとなる音が聞えた。壁の向こうは、兄の部屋である。
これは——。
私は自室を抜け出し、兄の部屋へ急行する。兄の部屋の扉を開くと、兄は壁にヤモリが如く張り付いていた。
「なんだよ、部屋入る時はノックしろって言っただろ。親しき仲にも礼儀ありって言葉を知らないのか?」何食わぬ顔で兄はそう返す。
「いや、何してるんだよ」
「見て分かんねぇか?壁に張り付いてるんだよ。そういうトレーニングだ」
絶対嘘だ。
「いや、あの、やめてくれないかな?恥ずかしい兄ちゃんがいるって思われる」
「俺が自分の部屋で何しようが俺の勝手だろ、お茶目な兄ちゃんだと紹介しとけ」
「いや、無理、てかそれ絶対僕らの会話を盗み聞こうとしてるでしょ?」
「は?なわけねぇだろ。トレーニングって言ってんだろ?それともなんだ?こんな白昼堂々兄に何か聞かれちゃまずいことでもしようってのか?この変態が!」
「なっそんなわけないだろ!」
「だったら俺に構うな、去れ」
そう言って兄は、いかに壁との密着率を上げようかとブツブツ言いだした。
あれが東雲と同じ教師だとはとてもじゃないが思えない。
兄の説得に失敗した私はとぼとぼと自室に帰る。
「どうしたんですか、先輩」先ほどの私と兄との会話が聞こえていたのか、少しトーンを落としてヒソヒソと絶対的に可愛い早瀬さんが聞いてくる。そのヒソヒソ声も可愛い。
「別に、なんでもないよ」
「なんか、変態って言われていませんでした?」
「兄から見たらなんでも変態に見えるんだよ」
「そ、それは、お気の毒ですね」そう言って絶対的に可愛い苦笑いを浮かべる。
「うん、まぁね」
さて、勉強に取り掛かろう、再度そう思った矢先、ぎゅいぃぃぃぃぃんという音が階下から聞こえる。
私は部屋を飛び出して階段を降り、リビングの扉を開ける。
なんと母さんがドリルを手に持ったまま脚立に足をかけている。
「母さん、何してるの?」
「あぁ司、あんたの部屋、この辺よね?」
「そうだけど、え、何してるの?」
「見て分からない?穴を開けるのよ」
「え?なんで?やめようよ母さん、絶対やめた方がいいよ!取り返しがつかなくなるよ?」
母さんはしばらく私を見つめた。
温かい眼差しだった。
「司」不意に名を呼ばれる。
「何?」
「私はね、あんたが一時の気の迷いで、取り返しのつかない大きな過ちを犯さないか、そっちの方が心配だよ」
「え?何を言ってるの母さん?」
「それに比べたら床の穴の一つや二つ!なんてことないね!」
そう言って母さんはぎゅいぃぃぃぃんとドリルを回し天井に突き付けた。
ドリルはどんどん回転し天井に潜っていく。上階から「いやぁああああ!」という悲鳴が聞こえる。絶対的に可愛い早瀬さんの声だ!
私は急いで階段を駆け上がり自室へ向かう。ちょうど私の部屋から絶対的に可愛い早瀬さんが飛び出してきた。
「先輩!何かが!地面から!」
そう言って彼女は私に抱きつく。
すると隣の部屋から兄が飛び出してきて絶対的に可愛い早瀬さんと抱き合う私を見るなり
「このド変態が!」と叫んだ。
兄のその声を受けて「ド変態?ド変態はどこ⁉」と母さんがドリルを回しながら階段を上がって来た。
回転するドリルを見るなり絶対的に可愛い早瀬さんは半狂乱になり「いやぁ!いやぁ!」とより一層私にしがみついた。
「司!あんた!白昼堂々イチャイチャと女と抱き合って!受験はどうするの?今がとっても大切な時期だって分かってるの?恋愛に現を抜かしてる場合⁉」
「いや、だから勉強しようとしてたじゃん!」
「馬鹿野郎、そんな可愛い女の子を前にして勉強なんてできる訳ないだろう」
え?お前本当に教師?と耳を疑った。
「司、あんたとその子、どういう関係、どこまでやったの?正直に言いなさい、じゃないと」
ぎゅいぃぃぃぃんという音がけたたましく鳴る。
「いやぁあ!私たちまだ何もしてません!本当です!信じてください!」
涙を流しながら絶対的に可愛い早瀬さんが訴える。
「とりあえず、二人ともくっつきすぎだ、離れようか」
そう言って兄が私と絶対的に可愛い早瀬さんの間を割く。
「よし、私はその子の相手をするからあんたは司をお願い。」
母さんがそう言うや、兄は私を羽交い絞めにして彼の部屋に連行した。
「早瀬さん!」
「先輩」消え入りそうな声で絶対的に可愛い早瀬さんが私の名を呼ぶ。
「よし、あんたはこっちに来なさい、下手なことすると——」
ぎゅいぃぃぃぃん
「ひっ!」
絶対的に可愛い早瀬さんは抵抗する様子もなく母さんに連れていかれた。
え?何だこの展開は?
夢オチとかそういうのだろう、そう信じたくてならなかった。
まさか、こんな化け物どもと同じ家に住んでいただなんて、信じられる訳ないだろう。
*
「ここは俺の部屋だ、郷に入っては郷に従え、よってお前は俺に逆らえない、俺の言っていること、分かるか?」
私を自室に連れ込んだ兄は出入り口を塞ぐようにドアの前に立ち、正座させられている私を見下ろしてそう言った。
「いや、それなら一刻も早くこんな部屋出て行きたいんだけど」
私は抗議の意を込めて右手を掲げる。
「認めぬ」
憤然と一蹴された。なんという暴君だ。
「いいか、司、兄より優れた弟はいない、俺の言っていること、分かるか?」
1ミリも分からぬ。
「僕が身長を抜かしたこと、まだ根に持ってるの?」
分からぬなりに答えると、兄はドンっと壁を殴る。
「その話はするな」
理不尽極まりない。
「いいか、お前は馬鹿だから、教えておいてやる。お前はあの子に騙されている。あれは罠だ。あんな可愛い子がお前のことを好きになるはずないだろ、常識的に考えたら分かるはずだ」
ひどく偉そうに、兄は言った。
私はムッとした。確かに絶対的に可愛い早瀬さんが私に近づいて来たことは怪しすぎる、何か裏があるはずだと私は常々疑っている。しかし、いざそれを他人に指摘されると非常に腹立たしい。ましてやこんな何も分からぬ兄に。
「別に好きか嫌いかは関係ないだろ、一緒に勉強しようって話になっただけだ」
「他所でやれよ」
ぐぅの音も出ない。理想のデートプランである休日おしかけ勉強会という甘い響きに惑わされ、絶対的に可愛い早瀬さんを自宅に招いてしまったその心の裏で、私の家族に、私に友達がいるんだということを、ましてや絶対的に可愛い女友達がいるのだということを自慢したい気持ちがあったことは否定できない。
しかしそのちっぽけな虚栄心が今、私たちを脅かしている。
階下ではぎゅいぃぃぃぃんという回転音と「いやぁ」「助けてください」という絶対的に可愛い悲鳴が立ち上ってくる。非常にまずい。こんな兄ほっといて早く絶対的に可愛い早瀬さんを助けに行きたいものだが、眼前の傲慢男がそれを許さない。
「だいたいお前、なんで金髪なんだよ?なんでギャル?もうそこでわかんじゃん罠だって、ツツモタセってやつだよ、後でいかつい兄ちゃんがやって来て俺の女に手を出した云云かんぬん言ってくるんだよ、なぁ、やめとけ?あきらめろ?」
「僕たちは別に、一緒に勉強しようとしてただけだ」
「馬鹿、金髪ギャルが勉強なんてするはずがないだろ」
大変不遜な発言を漏らす。
本当に、東雲と同じ教師とは思えない発言。
東雲が言葉の端に気を配り、選びに選んで発言し、それ故に見せた苦悩の顔。
そんな東雲の負った傷など知らぬとばかりに爆弾発言を連発する兄に、私は怒りを覚えていた。
「本当に教師の発言とは思えないな」
私の発言に兄はピクリと眉を動かした。
「司、お前、あの子とどこまでやった?本当にやましいことはしてないって胸張って言えるか?あ?」
プライドを刺激されたのか、より一層高圧的になる。
しかし、私たちは本当になにもしていない。
そもそも出会って一週間も経っていない。
何をいやらしい妄想を膨らませているのか知らないが、私たちにやましい事なんて一つもない。恥ずべきことなど一つも——。
不意に、絶対的に可愛い早瀬さんに苺パフェをあーんしたことを思い出す。
全身に緊張が走る。
あれは、あれは非常に恥ずかしいことではないか?
それを私たちは出会った初日にした。
あの時に感じた一歩間違えれば拷問かと錯覚する恥ずかしさを思い出した。
私の顔に、ふつふつと汗が浮かぶ。
「おいどうした司、顔色悪いぞ?本当にやましいことなんてないんだよな?」
やましい?やましいこと?
やましいことってなんだ?定義が、定義が分からない。
あーんはやましいことなのか?
「ま、安心しろ、変態で小心者のお前のために、今母さんがあの子の化けの皮を剥いでいる。お前たちの関係も全部、洗いざらい話すだろうよ」
ニヤニヤと、兄が笑う。
ぎゅいぃぃぃぃんと音が鳴る度に、絶対的に可愛い早瀬さんの悲鳴が上がる。
彼女は今、何を考えているのだろうか。
もし、彼女が私の犯行を暴く証拠を求め、私に近づいていたとしたら、うまく私の懐に入り込んだと思っていたところ、相手の母親に急遽命を脅かされる。
相当パニックに陥るだろう。自分の身のためになら、本当のことを話すだろう。そういう意味では、私があれ程知りたがっていた彼女の正体という真実を知るまたとないチャンスである。
しかし、本当に私に好意を抱いているだけだったら?
憧れの先輩の家にお邪魔し、一緒に勉強しながら穏やかな時間の中で愛を育む、あわよくば家族公認の関係になれればと思っていただろう。ところがそんな幻想はヒステリーを起こしたモンスターペアレントによって打ち砕かれる。
訳も分からず命を脅かされ、例え誤解が解けたとしてもこれ程簡単に暴走する危険な家族を持つ家の男と今後も関りを持ちたいと思うだろうか。
例えば、好きになった相手がやくざの令嬢であったら?私はそれでもその手を取るだろうか。
「やめてください!話を聞いてください!」
階下で絶対的に可愛い早瀬さんが懸命に訴えている。
兄はニヤニヤと嗜虐的な笑みを浮かべている。絶対的に可愛い早瀬さんの苦悩の表情を思い浮かべているのだろう。どっちが変態だ。
兄の愉悦の表情を見て察するに、兄は私に嫉妬している。私が、絶対的に可愛い早瀬さんと恋仲だと思っているから。弟に先を越されただけでなく、その相手が絶対的に可愛いから。
絶対的に可愛い早瀬さんと付き合ったからとはいえ、私の価値が上がる訳ではない。誰と付き合おうが、私は私である。ただ、兄はいかに可愛い彼女と付き合うかが己の幸福度を上げてくれると考えているのだろう。兄もまた、面食いに捕らわれし哀れな奴隷であった。
故に、絶対的に可愛い早瀬さんが私と付き合うことで、私が自分より幸福になると錯覚し、それが許せないのだ。だからこそこうして、私と絶対的に可愛い早瀬さんとの関係をぶち壊そうとしているのだ。なんとも狭量なモンスターである。悔しさに拳を強く握る。
「こんなことしたって、意味なんてない、自分が何をしているのか分かってるのか?」私は挑むように兄を睨む。
「哀れな弟を助けることができる。親切な家族を持ったことに感謝しろ」
「誰も頼んでない!」
「頼まれてもないのにこうして手を焼いてやってるんだ、感謝しろ」
その横柄な態度に感情が逆撫でられる。
「教えている生徒に対しても、そんな態度をとっているのか」
「家族サービスだ、感謝しろ」
何を言っても感謝を強要される返しに歯噛みが抑えられない。こんな無駄な押し問答をしている間にも母のドリルという脅威は絶対的に可愛い早瀬さんに刻一刻と近づきつつある。
兄の言う通り、絶対的に可愛い早瀬さんが罠であるという可能性は散々考えた。疑心暗鬼に陥り、未だに真っすぐな気持ちで彼女を見ることができない。傷つくことが怖かった。傷つくよりかは今まで通りただ見ているだけの方が良いのではと思えた。
しかし私は知っている。
いや、全国の草食人間が知っている。
見ているだけでは何も得ることができないのだと。
ましてや、こんな形で終わるのをただ見ているだけだなんて、耐えられる訳がない。
高校3年生の頃、恋をした。
彼女は絶対的な可愛さでマウントを取ることを得意とした。
そんなお月様に恋をした。
絶対的に可愛いなぁ絶対的に可愛いなぁと毎日見ていた。
絶対的に可愛いなぁ絶対的に可愛いなぁと毎日見ているうちに母親にドリルで穴をあけられた。
以来彼女の姿は見ていない。
そんな悲しい感傷に浸りたくない!
彼女の正体は二の次だ。今私がするべきは彼女の下へ駆けつけ、彼女のヒーローとなることだ。
「うぉぉぉぉ!」
私は腹の底から雄たけびをあげて兄に向って突進した。
ドンっと兄の背中がドアに打ち付けられる。
私の身長は兄よりも高い、体当たりの効果は絶大であった。
兄が怯んだすきに私はドアノブに手を伸ばす。
その時、にゅっと兄の腕が伸びてきて、私の首をホールドする。
「かっ⁉」
私の顔が兄の腰に押し付けられる。
抵抗すべく重心を上げようとした所、私の首をホールドしたまま兄が身体をねじって後ろに倒れこむ。引き込まれるように私も倒れこんだ。
何が起こっているのか分からないまま首が絞められる。
首の拘束を剥そうと両手で兄の腕を掴む。
まさか兄にフロントチョークをかけられるとは思ってもいなかったが、兄に格闘技の経験はない。素人のテクニックである、苦しさこそあれ、完全に極められてはいない。とはいえ、一瞬でも気を抜いてはいけない危険な状態であることに変わりはなかった。
体力の消耗戦、それでもこっちは意識を手放す、下手をすれば窒息死する危険性を突き付けられているため、否が応でも諦める訳にはいかない。
私は必死に抗い続けた。
兄は「兄より優れた弟はいないぃぃぃぃ」と謎の呪文を唱え、拘束に力を籠める。
拘束を外そうとする私と締め落とそうとする兄の膠着状態が続く。
ふと、階段を上がってくる足音が聞こえる。その足音は、階段を上がりきると、私の部屋へと入って行った。そしてすぐに出て来たかと思うと、私たちが格闘している兄の部屋の扉の前に立った。
「は…早瀬、さん?」
声を絞り出し、扉の奥に呼びかける。
しばらく待っても返事はない、しかし、そこに誰かがいるのは確かである。
「早瀬さん!」もう一度、彼女の名前を呼ぶ。
首を絞める力が強まる。息が苦しい。
「先輩」
扉の奥から、絶対的に可愛い声が返ってくる。
その声音は、どこか震えている。
「ごめんなさい」
脈絡もなく、彼女が謝る。
何を謝っているのだ。
君が謝ることなど、一つもないではないか。
悪いのは全部私の家族で。
なんだ、なんだこの状況は!
「さようなら」
震えた声で、彼女はそう告げる。
泣いているのか、よく分からない。
さようならって、どういうことだ。
そのまま足音は階段を下りていき、玄関の扉の開く音が遠くに聞こえた。
抵抗する力が抜けていく。
途端に息が苦しくなる。
意識が薄れていく。
なんなんだこの状況は。
なんでこうなった。
悪い夢だよな。
こんなの、リアリティーがなさすぎる。
この現代日本のどこにドリルを用いて息子から彼女を引き剥そうとする母親がいる?
どこに本気で弟を締め落とす兄がいる?
おかしい、何かがおかしい。
こんな展開、誰が認める?
認められるわけがないだろう。
絶対的に可愛い早瀬さんの笑顔が脳裏に浮かぶ。
そしてその姿は、薄れゆく意識と共に霧散していった。
*
休みが明けて、新しい週が始まる。
今日も松山は休みだと、朝礼で東雲が言う。
私と目が合うと、きまり悪そうに視線を逸らした。
チクリと胸が痛む。
私と東雲との関係がこじれたのは、彼女が私を疑ったからなのか、それとも、私が彼女を傷つけたからなのか。
いいや、その事を考えるのはもう止そうと決めたではないか。
今更、どうすることもできない。それに——。
今は、そんなことを考えている余裕はない。
授業が始まっても、まるで集中できる気がしない。
こんな大事な時期に女に現を抜かしてどうするのかと母は言ったが、皮肉なことに、まさにその彼女を失ったことで、現在私は授業に集中できていない。
できる訳がない。
私の胸にまでドリルで穴を開けられたかのように、その穴からそれまで感じていた温かさやらが漏れ出て行った。
彼女が去ってから、メッセージアプリで連絡を取ろうとしたものの、「すみません」と返事があったきり、返事がない。
なにが、すみませんなのか。
絶対的に可愛い早瀬さんは恐ろしい魔女であった。彼女と知り合ったのは先週の火曜日である。それは関係を築くには、あまりにも短い期間である。お互いの中に、深い絆など、生じるはずがない。にもかかわらず、私は彼女のことを考えずにはいられない。恐ろしい女である。
これで、良かったのかもしれない。
偽りのラブレター事件の謎を紐解くのは、もしかしたら彼女かもしれないと思っていた。彼女の言動の一つ一つに何度心臓が止まりかけたか数えることができない。彼女に見つめられると、心の奥まで見透かされているような気持になり、このまま隠し通すことはできないと感じていた。
しかし私の心配は杞憂に終わり、彼女の方から離れていった。
これ以上彼女に関わらない限り、私の安全は保障される。
残り少ないスクールライフを、平和に暮らせるのだ。
松山を陥れて、東雲を傷つけてまでしてようやく手に入れた平穏な日常を、守り通すことができるのだ。
それ以上、望むのは、業が深すぎる。
これで良かったのだ。
彼女はよく分からない女性だった。絶対的に可愛いだけなのだが、その絶対的な可愛さ故に、彼女は怪しさを全身に纏っていた。
何もしていないのに、謎の女と称される不憫な彼女、思えばいつだって彼女は疑われてきた。松山にも疑われ、私にも疑われ、私の家族にも疑われた。絶対的に可愛い、ただそれだけの理由で。
「私、誰かとデートするのも初めてで、先輩が誘ってくれてすごく嬉しかったです。」
初めて彼女と会った日、彼女はそう言った。
嘘だと思った。
何を演技めいたことを、そう思った。
絶対的に可愛い彼女がこれまで男に声をかけられたことがないだなんて、あり得ないと思った。
しかし、彼女にも選ぶ権利がある。
声を掛けられたことは、あるのだろう。しかし、彼女が好意を寄せた相手に声を掛けられたことは、果たしてあったのだろうか。
ましてや彼女が想いを寄せた相手が、私のように、疑心暗鬼に陥る腑抜けばかりであったとしたら?
彼女の絶対的に可愛い笑顔を思い出す。
胸が熱を帯びる。
あの笑顔は、本当に偽物だったのか?
いや、本物か、偽物かだなんて、この際関係ない。
彼女がどう思っていたかも、関係ない。
彼女と過ごした一週間にも満たない日々を思い出す。
心臓に悪いことも沢山あった。
頭を悩ませることも沢山あった。
そもそも純真な心で彼女を見たことは一度もなかった。
常に狼狽し、疑心暗鬼に捕らわれて、
それでも、
彼女の本質がどうであれ、彼女と過ごした時間、私は幸せだったのだ。
その真意がどうであれ、彼女がかけてくれた言葉の一つ一つが、私に温もりを与えてくれていた。
絶対的な可愛さにではない、
早瀬涼香に、恋をしてしまっていた。
全く、なんと無様なやりとりであることか。東雲脅迫用として録音したものだが、こんな内容、誰にも聞かせられない。そんなもん、私が犯人だと自白するも同然である。まさか東雲由紀乃があれほどできる女だとは思わなかった。私のトリックを見破り、私の言葉の隙を巧みについて論理的に私を苦しめた。彼女の決死の覚悟は、私を道連れにすることに成功していた。教師と生徒という関係でなかったなら私は敗北を喫していただろう。
なんとも腹が立つのは、自身のいやらしさである。圧倒的な劣勢に立たされておきながら自身の優位を誇張するために東雲の教師としての矜持をずたずたにしてしまった。
東雲の歯痒そうな顔。
破滅を悟った時の息遣い。
それでもなお抗い続けた瞳。
東雲は、これからも教師として生きていけるのだろうか。
少なくとも、私と彼女との関係は壊れた。
彼女は良い教師であった。
彼女は単に勉強を教えることだけに飽き足りる教師ではなかった。
彼女は大学入試で問われる以上のことを私たちに教えようとしていた。
本来なら、もっともっと多くの生徒に寄り添い、導く存在だった。
そんな彼女がもし、教師をやめてしまったら——。
東雲の、今にも泣きだしそうな顔が脳裏によみがえる。
彼女は何と戦っていたのか。
彼女は何故私と戦うことを選んだのか。
私の犯行を暴いてどうしようと思ったのか。
素直に私が反省すると思ったのか?
する訳がない、第一、もう手遅れだ。
私の犯行を暴いて彼女に何か得することがあったか?
お互いが傷を負っただけではないか、彼女に至っては致命傷だ。
そんなこと、最初から分かっていたことではないか。
それほどまでに彼女は愚かだったのか?
それとも、そんなことも分からない私が阿呆なのか?
もういい、考えるのはよそう、もう終わった話だ。
電車の窓から見える夕焼け空は、どこか淀んでいた。
*
最終下校時刻を過ぎて久しい保健室。養護教諭の白石に差し出されたココアを、ベッドに腰掛けたまま由紀乃は口をつけずに見つめている。
「少しは気持ち、落ち着いたかな?」
白石は由紀乃の隣に腰掛け、顔色を伺う。
しかし由紀乃は力なく首を横に振る。
「そっか」そう言って、白石は視線を由紀乃から外す。
気持ちが全く収まらない。
椚田の犯行を暴くことができず大敗を喫した記憶は由紀乃の心の奥深くに突き刺さっていた。
純粋に悔しかった。年下の、高校生男子に言い負かされ、馬鹿にされ、教師失格の烙印を押され、挙句の果てには脅迫まがいの行為まで受けた。それを思い出すだけで、涙が止まらなくなった。
「私、もう教師としてやっていけません」
涙声で、由紀乃がそう零す。
「明日から、どんな顔で生徒の前に立てばいいのか分かりません」
白石は、黙って由紀乃の頭を自身の胸に抱きよせた。そうして由紀乃の頭を撫でる。白石の胸に顔をうずめるようにして、由紀乃は咽び泣く。
「私が馬鹿でした、生徒を疑ってはいけないって、誰もが知ってることなのに、私は、自分が正しいって思って、でも、結果は……っ!」
そこまでしか、言葉にできなかった。
悔しくてたまらない。自分の愚かしさが。
「どうして自分は間違っているって思うの?」
由紀乃の頭を撫でていた白石が、ぽつりとそう尋ねる。
由紀乃は呻く。
「だって…」
結果はこの様で。
「私と椚田くんの関係は、もうボロボロで——」
「それは現在の状況だよね?」
「そう、ですけど」
何を、言おうとしているのだ、白石は。
由紀乃はそっと視線を上げる。
「前にも聞いたけどさ、由紀乃ちゃんは、どうして椚田さんの犯行を暴きたかったの?」
「それは…」
話がしたかった。
純粋に、これまでのこと、これからのこと。
「話がしたかったんだよね?」
そうだ、話しがしたかったのだ。
それがいつのまにか、犯行を暴く暴かれないの勝負になっていた。
勝つか負けるかの戦いとなれば、お互いが傷つくのは当然ではないか。
「椚田さんのトリックの秘密を教える時、実は躊躇したんだよね、こうなる可能性も、見えていたから」
「え?」
「椚田さんと話をするのに、本当に彼の秘密を暴く必要があったのか、考えていたんだよね」
由紀乃は訥々と話す白石の顔を見つめている。
「必要は、なかったのかもしれないね、今まで何もしてやれなくてごめんと謝って、これからは何でも相談して欲しいと伝え、ついでに今、松山さんがすごく傷ついていることも話して、これからのことを話して」
必要のないことだった、必要のないことをしたから傷ついた。
そっか、私って本当に、馬鹿だなぁ。
由紀乃は俯き、自嘲する。
「でもね、私だったら、暴くね」
「え⁉」憧れの教師の思わぬ一言に、由紀乃は身を起こし、再度その顔を見る。綺麗な眼差しで、何を言ってるのだこの人は。
「必要はないのかもしれない、でも、暴かないと、生徒も『こいつは一体どこまで知っていながら話してるんだ』と余計不審に思う。だって彼、自分のトリックに絶大な自信があったろうからね。彼のトリックを暴かないことには、『単に怪しいからって理由で疑ってるんだろうな』って思われるだろう。なんにせよ、ノイズが多い。自分は君の全てを知っている、知ってなお、こうして話したいんだ、そう思わせたい。由紀乃ちゃんも、そうだったんじゃないの?」
そうだ。
そうだった。
「でも、結果は」
結果は、最悪な形で——。
「失敗しちゃった、だね」
失敗しちゃった、そんな可愛いもんじゃない。
だって…
「私と椚田くんの関係はもう壊れちゃったんだよ!失敗なんて言葉で済ませられないよ!」
教師という仕事は人の人生を大きく左右する仕事である。大きな責任が伴う。
失敗は許されない。
「大丈夫だよ」
由紀乃の頭を撫でながら、白石は言う。
「壊れちゃったのなら、また作ればいいんだよ、今度はもっと頑丈にね」
何食わぬ顔で、白石は言う。
「失敗は、してもいいんだよ。諦めない限りその失敗はいつか成功に結び付くんだよ」
聞き覚えがある言葉、
そうだ、それは由紀乃が松山へ送った言葉でもあった。
生徒には偉そうにそう言っておいて、自分はこの様、情けない。
「でも、私は教師で、失敗の重みが」
「そんなの関係ない」
「えっ」
「教師だからとか、関係ないよ、働く人は皆なんらかの責任を負っている。どうして教師だけ特別扱いするのか、私には分からない」
由紀乃は表情を曇らせた。確かにそうだ。世間では教師を聖職者と呼ぶが、教師も人間である。それはもう、どうあがいても人間で、況してや聖人ばかりが採用される訳ではない。
「でも、世の中はそんな理屈、認めてくれませんよ」
「いいよ、私が認める」
なんという暴論。一介の養護教諭が何を言う。
「し、白石先生のその、自分は正しいっていう自信はどこから来るんですか?」
「別に自信なんてないよ、ただ、誰かの言う理屈と自分の中の理屈、正しいなと思った方を信じるようにしているだけだよ。由紀乃ちゃんも、そうじゃないの?」
そう聞かれて、ハッとする。
世間一般の正しさは理解しているつもりだった、それでも、なんとなくだけど、それではいけないと思ったから、由紀乃は椚田と対峙することを選んだのだ。
「でも、その結果がこれですよ。やっぱり世間一般の言うことが正しかったってことですよ」
「どこに主眼を置くかだよ、『犯人探しをしてはいけない』『生徒を疑ってはいけない』こう言った教えはね、生徒を守ると同時に由紀乃ちゃんを守る教えでもあったんだよ。こういった問題は難しいからね、誰でも上手に対応できる訳じゃない。今の由紀乃ちゃんみたいに傷を負う人も少なくないし、時には事が学校全体の問題となって、自分以外の教師にまで負担を強いることがある。そうした余計な傷口を広げないための教えでもあるんだよ。根底にあるのはことなかれ主義だと思うけどね」
悪戯っぽく白石が笑う。それから、少し真剣な顔で——。
「由紀乃ちゃんは、誰を守りたかったの?」
誰を、守りたかったのか。
椚田を、彼が過ちを抱えたまま人生を歩まないように、助けたかった。
自分を守りたかった訳では、決してない。
生徒のためなら、自分はどうなってもいいと思った。
でも、言葉では何とでも言えたが、実際の傷は、深くて、痛くて。
そんな由紀乃の弱い心を見透かすように、白石は由紀乃の手を取った。
「一人で戦うのは、辛いよね、だから、言わせてほしい」
白石は、由紀乃の目を見つめた。
「由紀乃ちゃんはまちがってない。私は由紀乃ちゃんの味方だよ。」
道理なんて、どうでもよくなった。
自分が正しいのか、そうでないのか、分からない。
しかし、それは由紀乃の心がずっと欲していた言葉で、
訳も分からず、白石の胸に顔を埋め、声に出して泣いた。
*
私は今まで誰かと恋仲になったことなどないが、男女の関係性というものはもっと時間をかけて育まれるものではないだろうか。
小学校高学年の頃、初恋をした。
小学生基準なのでよく分からないが、相対的に可愛い部類であった。
しかし当時の私にとっては絶対的に可愛かった。
そりゃもう、現在絶対的に可愛い早瀬さんを前にしたら月とゾウガメ程の差はあるが、ピカピカの小学生とイケイケの高校生を比べる方がナンセンスである。本気で比べようものならそれはもう恐ろしい変態である。
何はともあれ私はゾウガメに恋をした。
可愛いなぁ可愛いなぁと毎日見ていた。
可愛いなぁ可愛いなぁと見ているうちに、卒業式を迎えた。
彼女は進学校へと進み、以来、姿を見たことがない。
中学1年生の頃、恋をした。
クラスの8割はポニーテールであったが、中学生基準で相対的に可愛い部類のポニーテールであった。
そんなミシシッピアカミミガメに恋をした。
可愛いなぁ可愛いなぁと思って揺れるポニーテールを毎日見ていた。
可愛いなぁ可愛いなぁと見ているうちに、ミシシッピアカミミガメは別の男と付き合い出した。
彼女は彼氏の意向に従い髪型を変え、以来彼女のポニーテールは見ていない。
中学2年生の頃、恋をした。
彼女は長く美しい黒髪をたなびかせ、多くの男どもを魅了した。
その絶対的な美しさたるや比肩するものなし。後5年すれば絶対的に可愛い早瀬さんもあの領域に至るだろう。
そんな土星に恋をした。
美しいなぁ美しいなぁとなびく黒髪を毎週見ていた。
美しいなぁ美しいなぁと見ているうちに放送は終了した。
第二期が放送される予定は今のところない。
中学3年生の頃、恋をした。
中学3年生ともなると幼き日のように女子を純粋な目で見ることはできない。
彼女は中学生基準で相対的に健康的な美脚を有していた。
そんなアオウミガメに恋をした。
いい肉付きをしているなぁいい肉付きをしているなぁと毎日見ていた。
いい肉付きをしているなぁいい肉付きをしているなぁと毎日見ているうちにまたもや卒業式を迎えた。
以来彼女の美脚は見ていない。
要するに、男女の関係を築き上げるには恐ろしい程の年月を有要する者だと思われる。それだというのに。
「おじゃましまーす」
出会って1週間も経たぬうちに、絶対的に可愛い早瀬さん、襲来。
*
お金のかからないデートプラン休日編ということで、絶対的に可愛い彼女が提案したのがこの休日おしかけ勉強会である。
昼食代も浮いて(親が買った食材でやり過ごすため)、成績も良くなり、親からの好感度も稼げる素晴らしいデートプランであり、私はかねてよりそのようなデートをしてみたいと切に願っていた。それをこのような絶対的に可愛い早瀬さんと行うことができるのだから、椚田一族の中でもこれ程の幸福を掴んだものはいなかろうと思われる、のだが、その恐ろしい程に早い距離の縮め方に私は動揺を隠せない。
動揺を隠せないのは私の家族一同もそうであった。
女の子の後輩がうちに来て、一緒に勉強をする、ということは昨日のうちに伝えており、急遽部屋を片付け準備は万端であったのだが、絶対的に可愛い早瀬さんの絶対的な可愛さを前に玄関で出迎えた私の母親は開口一番「えっ?」と漏らした。ついで自身の部屋から出てきた兄も絶対的に可愛い早瀬さんを見るや「えっ?」と漏らした。親子揃って失礼極まりないが、私も兄がこれ程までに絶対的に可愛い存在を家に招き入れようものなら「えっ?」といって固まることだろう。
本日の彼女は白地のシャツの上にキャメルのカーディガンを羽織り、下はダメージを受けていないジーンズという大人びた風貌をしていた。ギャル装束で来られたらどうしようかと思ったが、常識人なようで安心した。しかし溢れ出る絶対的な可愛さは抑えられない。
「えっ?」と固まる母と兄を残して私は階段を上り絶対的に可愛い早瀬さんを自室に案内した。
「わぁ、ここが先輩の部屋なんですね、片付いていますね、素敵です」
片付けたんだよ、君が来るから。
入って左側には手前から本棚、ベッド、右側には手前から勉強机、クローゼット、中央には今回のためにセッティングした脚の短い木製のテーブルがある。窓は扉の反対側。以上参考にされたし、覚える必要はなし。
「鞄、どこに置いたらいいでしょうか?」絶対的に可愛い早瀬さんが遠慮がちに尋ねる。私は勉強机を指さし、そこに荷物を置くよう伝えた。
「ここで、先輩はいつも勉強しているんですね」私の勉強机を見て絶対的に可愛い早瀬さんは謎の感慨に耽る。
「すごい、先輩、棚にノートがずらぁーって並んでますね」
「うん、高校入った時から使い終わったノートはここに置くようにしているんだ」
「すごい!先輩が2年生の時のノート、見てもいいですか?」私は勉強机の棚から幾つかノートを手に取る。
「ありがとうございます、え?わぁすごい、先輩、無地のノートを使ってるんですか?すごいです、字も綺麗。」
私の高2の頃のノートを見て、絶対的に可愛い早瀬さんが目をキラキラさせる。なにがそんなにすごいんだろう。
「先輩、どの教科もこの、無地のノートを使ってるんですか?」
「うん、まぁね、レイアウトが自由にできるから好きなんだ。」
「確かに文字の大きさも自由に調整出来て、ポップで見ていて楽しいですね。いつから無地のノートを使ってるんですか?」
「高校受験のあたりかな、勉強も苦手で、授業もよく分かっていなかったんだけど、兄がこのノートを使ったノートの取り方を教えてくれて、以来これを使ってる。」
「へぇ、なるほど、罫線の入ったノートはそれ以来一度も買ってないんですか?」
「うん、このノートに慣れちゃったしね」
「そうなんですか、私も真似してみたいです。どこで買ってるんですか?」
「駅近くの文房具屋で僕は買ってるかな」
「あぁ、あそこですか。よろしければ今度買う時ご一緒させてください」
「うん、別にいいけれど」
たかがノートの何がすごいのか、彼女は目をキラキラさせて私のノートを見ている。
「さてと、そろそろ勉強しましょうか。分からない所、教えてくださいね?」
そう言って彼女は勉強道具を取り出した。
彼女は英語の問題集と参考書をテーブルの上に並べる。
私は数学の問題集とノートを取り出した。当然無地である。
絶対的に可愛い早瀬さんが家に来て、どんなイベントが起こるのかと思いきや、意外と普通に勉強する流れに移った。
今日はのんびりした時間が過ごせそうだと思い、問題集とノートをテーブルの上に置いた時、壁際でゴンっとなる音が聞えた。壁の向こうは、兄の部屋である。
これは——。
私は自室を抜け出し、兄の部屋へ急行する。兄の部屋の扉を開くと、兄は壁にヤモリが如く張り付いていた。
「なんだよ、部屋入る時はノックしろって言っただろ。親しき仲にも礼儀ありって言葉を知らないのか?」何食わぬ顔で兄はそう返す。
「いや、何してるんだよ」
「見て分かんねぇか?壁に張り付いてるんだよ。そういうトレーニングだ」
絶対嘘だ。
「いや、あの、やめてくれないかな?恥ずかしい兄ちゃんがいるって思われる」
「俺が自分の部屋で何しようが俺の勝手だろ、お茶目な兄ちゃんだと紹介しとけ」
「いや、無理、てかそれ絶対僕らの会話を盗み聞こうとしてるでしょ?」
「は?なわけねぇだろ。トレーニングって言ってんだろ?それともなんだ?こんな白昼堂々兄に何か聞かれちゃまずいことでもしようってのか?この変態が!」
「なっそんなわけないだろ!」
「だったら俺に構うな、去れ」
そう言って兄は、いかに壁との密着率を上げようかとブツブツ言いだした。
あれが東雲と同じ教師だとはとてもじゃないが思えない。
兄の説得に失敗した私はとぼとぼと自室に帰る。
「どうしたんですか、先輩」先ほどの私と兄との会話が聞こえていたのか、少しトーンを落としてヒソヒソと絶対的に可愛い早瀬さんが聞いてくる。そのヒソヒソ声も可愛い。
「別に、なんでもないよ」
「なんか、変態って言われていませんでした?」
「兄から見たらなんでも変態に見えるんだよ」
「そ、それは、お気の毒ですね」そう言って絶対的に可愛い苦笑いを浮かべる。
「うん、まぁね」
さて、勉強に取り掛かろう、再度そう思った矢先、ぎゅいぃぃぃぃぃんという音が階下から聞こえる。
私は部屋を飛び出して階段を降り、リビングの扉を開ける。
なんと母さんがドリルを手に持ったまま脚立に足をかけている。
「母さん、何してるの?」
「あぁ司、あんたの部屋、この辺よね?」
「そうだけど、え、何してるの?」
「見て分からない?穴を開けるのよ」
「え?なんで?やめようよ母さん、絶対やめた方がいいよ!取り返しがつかなくなるよ?」
母さんはしばらく私を見つめた。
温かい眼差しだった。
「司」不意に名を呼ばれる。
「何?」
「私はね、あんたが一時の気の迷いで、取り返しのつかない大きな過ちを犯さないか、そっちの方が心配だよ」
「え?何を言ってるの母さん?」
「それに比べたら床の穴の一つや二つ!なんてことないね!」
そう言って母さんはぎゅいぃぃぃぃんとドリルを回し天井に突き付けた。
ドリルはどんどん回転し天井に潜っていく。上階から「いやぁああああ!」という悲鳴が聞こえる。絶対的に可愛い早瀬さんの声だ!
私は急いで階段を駆け上がり自室へ向かう。ちょうど私の部屋から絶対的に可愛い早瀬さんが飛び出してきた。
「先輩!何かが!地面から!」
そう言って彼女は私に抱きつく。
すると隣の部屋から兄が飛び出してきて絶対的に可愛い早瀬さんと抱き合う私を見るなり
「このド変態が!」と叫んだ。
兄のその声を受けて「ド変態?ド変態はどこ⁉」と母さんがドリルを回しながら階段を上がって来た。
回転するドリルを見るなり絶対的に可愛い早瀬さんは半狂乱になり「いやぁ!いやぁ!」とより一層私にしがみついた。
「司!あんた!白昼堂々イチャイチャと女と抱き合って!受験はどうするの?今がとっても大切な時期だって分かってるの?恋愛に現を抜かしてる場合⁉」
「いや、だから勉強しようとしてたじゃん!」
「馬鹿野郎、そんな可愛い女の子を前にして勉強なんてできる訳ないだろう」
え?お前本当に教師?と耳を疑った。
「司、あんたとその子、どういう関係、どこまでやったの?正直に言いなさい、じゃないと」
ぎゅいぃぃぃぃんという音がけたたましく鳴る。
「いやぁあ!私たちまだ何もしてません!本当です!信じてください!」
涙を流しながら絶対的に可愛い早瀬さんが訴える。
「とりあえず、二人ともくっつきすぎだ、離れようか」
そう言って兄が私と絶対的に可愛い早瀬さんの間を割く。
「よし、私はその子の相手をするからあんたは司をお願い。」
母さんがそう言うや、兄は私を羽交い絞めにして彼の部屋に連行した。
「早瀬さん!」
「先輩」消え入りそうな声で絶対的に可愛い早瀬さんが私の名を呼ぶ。
「よし、あんたはこっちに来なさい、下手なことすると——」
ぎゅいぃぃぃぃん
「ひっ!」
絶対的に可愛い早瀬さんは抵抗する様子もなく母さんに連れていかれた。
え?何だこの展開は?
夢オチとかそういうのだろう、そう信じたくてならなかった。
まさか、こんな化け物どもと同じ家に住んでいただなんて、信じられる訳ないだろう。
*
「ここは俺の部屋だ、郷に入っては郷に従え、よってお前は俺に逆らえない、俺の言っていること、分かるか?」
私を自室に連れ込んだ兄は出入り口を塞ぐようにドアの前に立ち、正座させられている私を見下ろしてそう言った。
「いや、それなら一刻も早くこんな部屋出て行きたいんだけど」
私は抗議の意を込めて右手を掲げる。
「認めぬ」
憤然と一蹴された。なんという暴君だ。
「いいか、司、兄より優れた弟はいない、俺の言っていること、分かるか?」
1ミリも分からぬ。
「僕が身長を抜かしたこと、まだ根に持ってるの?」
分からぬなりに答えると、兄はドンっと壁を殴る。
「その話はするな」
理不尽極まりない。
「いいか、お前は馬鹿だから、教えておいてやる。お前はあの子に騙されている。あれは罠だ。あんな可愛い子がお前のことを好きになるはずないだろ、常識的に考えたら分かるはずだ」
ひどく偉そうに、兄は言った。
私はムッとした。確かに絶対的に可愛い早瀬さんが私に近づいて来たことは怪しすぎる、何か裏があるはずだと私は常々疑っている。しかし、いざそれを他人に指摘されると非常に腹立たしい。ましてやこんな何も分からぬ兄に。
「別に好きか嫌いかは関係ないだろ、一緒に勉強しようって話になっただけだ」
「他所でやれよ」
ぐぅの音も出ない。理想のデートプランである休日おしかけ勉強会という甘い響きに惑わされ、絶対的に可愛い早瀬さんを自宅に招いてしまったその心の裏で、私の家族に、私に友達がいるんだということを、ましてや絶対的に可愛い女友達がいるのだということを自慢したい気持ちがあったことは否定できない。
しかしそのちっぽけな虚栄心が今、私たちを脅かしている。
階下ではぎゅいぃぃぃぃんという回転音と「いやぁ」「助けてください」という絶対的に可愛い悲鳴が立ち上ってくる。非常にまずい。こんな兄ほっといて早く絶対的に可愛い早瀬さんを助けに行きたいものだが、眼前の傲慢男がそれを許さない。
「だいたいお前、なんで金髪なんだよ?なんでギャル?もうそこでわかんじゃん罠だって、ツツモタセってやつだよ、後でいかつい兄ちゃんがやって来て俺の女に手を出した云云かんぬん言ってくるんだよ、なぁ、やめとけ?あきらめろ?」
「僕たちは別に、一緒に勉強しようとしてただけだ」
「馬鹿、金髪ギャルが勉強なんてするはずがないだろ」
大変不遜な発言を漏らす。
本当に、東雲と同じ教師とは思えない発言。
東雲が言葉の端に気を配り、選びに選んで発言し、それ故に見せた苦悩の顔。
そんな東雲の負った傷など知らぬとばかりに爆弾発言を連発する兄に、私は怒りを覚えていた。
「本当に教師の発言とは思えないな」
私の発言に兄はピクリと眉を動かした。
「司、お前、あの子とどこまでやった?本当にやましいことはしてないって胸張って言えるか?あ?」
プライドを刺激されたのか、より一層高圧的になる。
しかし、私たちは本当になにもしていない。
そもそも出会って一週間も経っていない。
何をいやらしい妄想を膨らませているのか知らないが、私たちにやましい事なんて一つもない。恥ずべきことなど一つも——。
不意に、絶対的に可愛い早瀬さんに苺パフェをあーんしたことを思い出す。
全身に緊張が走る。
あれは、あれは非常に恥ずかしいことではないか?
それを私たちは出会った初日にした。
あの時に感じた一歩間違えれば拷問かと錯覚する恥ずかしさを思い出した。
私の顔に、ふつふつと汗が浮かぶ。
「おいどうした司、顔色悪いぞ?本当にやましいことなんてないんだよな?」
やましい?やましいこと?
やましいことってなんだ?定義が、定義が分からない。
あーんはやましいことなのか?
「ま、安心しろ、変態で小心者のお前のために、今母さんがあの子の化けの皮を剥いでいる。お前たちの関係も全部、洗いざらい話すだろうよ」
ニヤニヤと、兄が笑う。
ぎゅいぃぃぃぃんと音が鳴る度に、絶対的に可愛い早瀬さんの悲鳴が上がる。
彼女は今、何を考えているのだろうか。
もし、彼女が私の犯行を暴く証拠を求め、私に近づいていたとしたら、うまく私の懐に入り込んだと思っていたところ、相手の母親に急遽命を脅かされる。
相当パニックに陥るだろう。自分の身のためになら、本当のことを話すだろう。そういう意味では、私があれ程知りたがっていた彼女の正体という真実を知るまたとないチャンスである。
しかし、本当に私に好意を抱いているだけだったら?
憧れの先輩の家にお邪魔し、一緒に勉強しながら穏やかな時間の中で愛を育む、あわよくば家族公認の関係になれればと思っていただろう。ところがそんな幻想はヒステリーを起こしたモンスターペアレントによって打ち砕かれる。
訳も分からず命を脅かされ、例え誤解が解けたとしてもこれ程簡単に暴走する危険な家族を持つ家の男と今後も関りを持ちたいと思うだろうか。
例えば、好きになった相手がやくざの令嬢であったら?私はそれでもその手を取るだろうか。
「やめてください!話を聞いてください!」
階下で絶対的に可愛い早瀬さんが懸命に訴えている。
兄はニヤニヤと嗜虐的な笑みを浮かべている。絶対的に可愛い早瀬さんの苦悩の表情を思い浮かべているのだろう。どっちが変態だ。
兄の愉悦の表情を見て察するに、兄は私に嫉妬している。私が、絶対的に可愛い早瀬さんと恋仲だと思っているから。弟に先を越されただけでなく、その相手が絶対的に可愛いから。
絶対的に可愛い早瀬さんと付き合ったからとはいえ、私の価値が上がる訳ではない。誰と付き合おうが、私は私である。ただ、兄はいかに可愛い彼女と付き合うかが己の幸福度を上げてくれると考えているのだろう。兄もまた、面食いに捕らわれし哀れな奴隷であった。
故に、絶対的に可愛い早瀬さんが私と付き合うことで、私が自分より幸福になると錯覚し、それが許せないのだ。だからこそこうして、私と絶対的に可愛い早瀬さんとの関係をぶち壊そうとしているのだ。なんとも狭量なモンスターである。悔しさに拳を強く握る。
「こんなことしたって、意味なんてない、自分が何をしているのか分かってるのか?」私は挑むように兄を睨む。
「哀れな弟を助けることができる。親切な家族を持ったことに感謝しろ」
「誰も頼んでない!」
「頼まれてもないのにこうして手を焼いてやってるんだ、感謝しろ」
その横柄な態度に感情が逆撫でられる。
「教えている生徒に対しても、そんな態度をとっているのか」
「家族サービスだ、感謝しろ」
何を言っても感謝を強要される返しに歯噛みが抑えられない。こんな無駄な押し問答をしている間にも母のドリルという脅威は絶対的に可愛い早瀬さんに刻一刻と近づきつつある。
兄の言う通り、絶対的に可愛い早瀬さんが罠であるという可能性は散々考えた。疑心暗鬼に陥り、未だに真っすぐな気持ちで彼女を見ることができない。傷つくことが怖かった。傷つくよりかは今まで通りただ見ているだけの方が良いのではと思えた。
しかし私は知っている。
いや、全国の草食人間が知っている。
見ているだけでは何も得ることができないのだと。
ましてや、こんな形で終わるのをただ見ているだけだなんて、耐えられる訳がない。
高校3年生の頃、恋をした。
彼女は絶対的な可愛さでマウントを取ることを得意とした。
そんなお月様に恋をした。
絶対的に可愛いなぁ絶対的に可愛いなぁと毎日見ていた。
絶対的に可愛いなぁ絶対的に可愛いなぁと毎日見ているうちに母親にドリルで穴をあけられた。
以来彼女の姿は見ていない。
そんな悲しい感傷に浸りたくない!
彼女の正体は二の次だ。今私がするべきは彼女の下へ駆けつけ、彼女のヒーローとなることだ。
「うぉぉぉぉ!」
私は腹の底から雄たけびをあげて兄に向って突進した。
ドンっと兄の背中がドアに打ち付けられる。
私の身長は兄よりも高い、体当たりの効果は絶大であった。
兄が怯んだすきに私はドアノブに手を伸ばす。
その時、にゅっと兄の腕が伸びてきて、私の首をホールドする。
「かっ⁉」
私の顔が兄の腰に押し付けられる。
抵抗すべく重心を上げようとした所、私の首をホールドしたまま兄が身体をねじって後ろに倒れこむ。引き込まれるように私も倒れこんだ。
何が起こっているのか分からないまま首が絞められる。
首の拘束を剥そうと両手で兄の腕を掴む。
まさか兄にフロントチョークをかけられるとは思ってもいなかったが、兄に格闘技の経験はない。素人のテクニックである、苦しさこそあれ、完全に極められてはいない。とはいえ、一瞬でも気を抜いてはいけない危険な状態であることに変わりはなかった。
体力の消耗戦、それでもこっちは意識を手放す、下手をすれば窒息死する危険性を突き付けられているため、否が応でも諦める訳にはいかない。
私は必死に抗い続けた。
兄は「兄より優れた弟はいないぃぃぃぃ」と謎の呪文を唱え、拘束に力を籠める。
拘束を外そうとする私と締め落とそうとする兄の膠着状態が続く。
ふと、階段を上がってくる足音が聞こえる。その足音は、階段を上がりきると、私の部屋へと入って行った。そしてすぐに出て来たかと思うと、私たちが格闘している兄の部屋の扉の前に立った。
「は…早瀬、さん?」
声を絞り出し、扉の奥に呼びかける。
しばらく待っても返事はない、しかし、そこに誰かがいるのは確かである。
「早瀬さん!」もう一度、彼女の名前を呼ぶ。
首を絞める力が強まる。息が苦しい。
「先輩」
扉の奥から、絶対的に可愛い声が返ってくる。
その声音は、どこか震えている。
「ごめんなさい」
脈絡もなく、彼女が謝る。
何を謝っているのだ。
君が謝ることなど、一つもないではないか。
悪いのは全部私の家族で。
なんだ、なんだこの状況は!
「さようなら」
震えた声で、彼女はそう告げる。
泣いているのか、よく分からない。
さようならって、どういうことだ。
そのまま足音は階段を下りていき、玄関の扉の開く音が遠くに聞こえた。
抵抗する力が抜けていく。
途端に息が苦しくなる。
意識が薄れていく。
なんなんだこの状況は。
なんでこうなった。
悪い夢だよな。
こんなの、リアリティーがなさすぎる。
この現代日本のどこにドリルを用いて息子から彼女を引き剥そうとする母親がいる?
どこに本気で弟を締め落とす兄がいる?
おかしい、何かがおかしい。
こんな展開、誰が認める?
認められるわけがないだろう。
絶対的に可愛い早瀬さんの笑顔が脳裏に浮かぶ。
そしてその姿は、薄れゆく意識と共に霧散していった。
*
休みが明けて、新しい週が始まる。
今日も松山は休みだと、朝礼で東雲が言う。
私と目が合うと、きまり悪そうに視線を逸らした。
チクリと胸が痛む。
私と東雲との関係がこじれたのは、彼女が私を疑ったからなのか、それとも、私が彼女を傷つけたからなのか。
いいや、その事を考えるのはもう止そうと決めたではないか。
今更、どうすることもできない。それに——。
今は、そんなことを考えている余裕はない。
授業が始まっても、まるで集中できる気がしない。
こんな大事な時期に女に現を抜かしてどうするのかと母は言ったが、皮肉なことに、まさにその彼女を失ったことで、現在私は授業に集中できていない。
できる訳がない。
私の胸にまでドリルで穴を開けられたかのように、その穴からそれまで感じていた温かさやらが漏れ出て行った。
彼女が去ってから、メッセージアプリで連絡を取ろうとしたものの、「すみません」と返事があったきり、返事がない。
なにが、すみませんなのか。
絶対的に可愛い早瀬さんは恐ろしい魔女であった。彼女と知り合ったのは先週の火曜日である。それは関係を築くには、あまりにも短い期間である。お互いの中に、深い絆など、生じるはずがない。にもかかわらず、私は彼女のことを考えずにはいられない。恐ろしい女である。
これで、良かったのかもしれない。
偽りのラブレター事件の謎を紐解くのは、もしかしたら彼女かもしれないと思っていた。彼女の言動の一つ一つに何度心臓が止まりかけたか数えることができない。彼女に見つめられると、心の奥まで見透かされているような気持になり、このまま隠し通すことはできないと感じていた。
しかし私の心配は杞憂に終わり、彼女の方から離れていった。
これ以上彼女に関わらない限り、私の安全は保障される。
残り少ないスクールライフを、平和に暮らせるのだ。
松山を陥れて、東雲を傷つけてまでしてようやく手に入れた平穏な日常を、守り通すことができるのだ。
それ以上、望むのは、業が深すぎる。
これで良かったのだ。
彼女はよく分からない女性だった。絶対的に可愛いだけなのだが、その絶対的な可愛さ故に、彼女は怪しさを全身に纏っていた。
何もしていないのに、謎の女と称される不憫な彼女、思えばいつだって彼女は疑われてきた。松山にも疑われ、私にも疑われ、私の家族にも疑われた。絶対的に可愛い、ただそれだけの理由で。
「私、誰かとデートするのも初めてで、先輩が誘ってくれてすごく嬉しかったです。」
初めて彼女と会った日、彼女はそう言った。
嘘だと思った。
何を演技めいたことを、そう思った。
絶対的に可愛い彼女がこれまで男に声をかけられたことがないだなんて、あり得ないと思った。
しかし、彼女にも選ぶ権利がある。
声を掛けられたことは、あるのだろう。しかし、彼女が好意を寄せた相手に声を掛けられたことは、果たしてあったのだろうか。
ましてや彼女が想いを寄せた相手が、私のように、疑心暗鬼に陥る腑抜けばかりであったとしたら?
彼女の絶対的に可愛い笑顔を思い出す。
胸が熱を帯びる。
あの笑顔は、本当に偽物だったのか?
いや、本物か、偽物かだなんて、この際関係ない。
彼女がどう思っていたかも、関係ない。
彼女と過ごした一週間にも満たない日々を思い出す。
心臓に悪いことも沢山あった。
頭を悩ませることも沢山あった。
そもそも純真な心で彼女を見たことは一度もなかった。
常に狼狽し、疑心暗鬼に捕らわれて、
それでも、
彼女の本質がどうであれ、彼女と過ごした時間、私は幸せだったのだ。
その真意がどうであれ、彼女がかけてくれた言葉の一つ一つが、私に温もりを与えてくれていた。
絶対的な可愛さにではない、
早瀬涼香に、恋をしてしまっていた。
1
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

「南風の頃に」~ノダケンとその仲間達~
kitamitio
青春
合格するはずのなかった札幌の超難関高に入学してしまった野球少年の野田賢治は、野球部員たちの執拗な勧誘を逃れ陸上部に入部する。北海道の海沿いの田舎町で育った彼は仲間たちの優秀さに引け目を感じる生活を送っていたが、長年続けて来た野球との違いに戸惑いながらも陸上競技にのめりこんでいく。「自主自律」を校訓とする私服の学校に敢えて詰襟の学生服を着ていくことで自分自身の存在を主張しようとしていた野田賢治。それでも新しい仲間が広がっていく中で少しずつ変わっていくものがあった。そして、隠していた野田賢治自身の過去について少しずつ知らされていく……。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち
ヒロワークス
ライト文芸
女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。
クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。
それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。
そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!
その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。
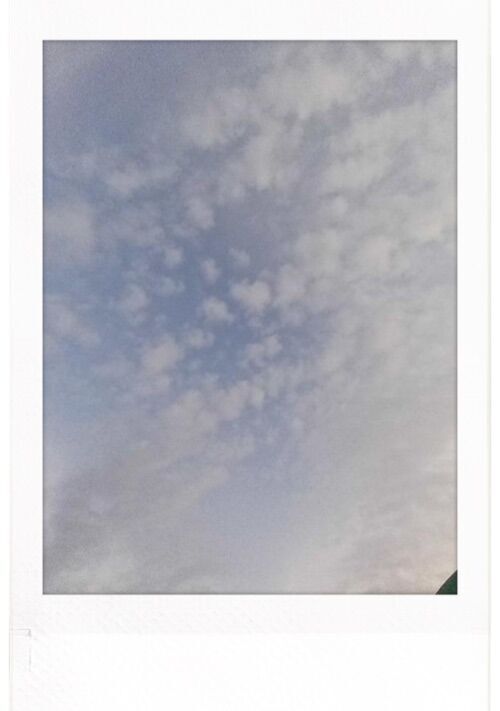
ファンファーレ!
ほしのことば
青春
♡完結まで毎日投稿♡
高校2年生の初夏、ユキは余命1年だと申告された。思えば、今まで「なんとなく」で生きてきた人生。延命治療も勧められたが、ユキは治療はせず、残りの人生を全力で生きることを決意した。
友情・恋愛・行事・学業…。
今まで適当にこなしてきただけの毎日を全力で過ごすことで、ユキの「生」に関する気持ちは段々と動いていく。
主人公のユキの心情を軸に、ユキが全力で生きることで起きる周りの心情の変化も描く。
誰もが感じたことのある青春時代の悩みや感動が、きっとあなたの心に寄り添う作品。

切り札の男
古野ジョン
青春
野球への未練から、毎日のようにバッティングセンターに通う高校一年生の久保雄大。
ある日、野球部のマネージャーだという滝川まなに野球部に入るよう頼まれる。
理由を聞くと、「三年の兄をプロ野球選手にするため、少しでも大会で勝ち上がりたい」のだという。
そんな簡単にプロ野球に入れるわけがない。そう思った久保は、つい彼女と口論してしまう。
その結果、「兄の球を打ってみろ」とけしかけられてしまった。
彼はその挑発に乗ってしまうが……
小説家になろう・カクヨム・ハーメルンにも掲載しています。

28メートル先のキミへ
佑佳
青春
弓道部の友達の応援をしに大会に来た青磁。
女子個人の最後の一矢を放ったのは、とても美しい引き方をした人。
その一矢で、彼女の優勝が決まったのがわかると、青磁は溜め息のように独り言を漏らした。
「かっ、けぇー……」
はい、自覚なしの一目惚れをしました。
何も持っていない(自己評価)・僕、佐々井青磁は、唯一無二を持ち孤高に輝き続ける永澤さんを知りたくなった。
でも、声をかける勇気すら持っていないって気が付いた。
これでいいのかよ? ん?
ハンディキャップと共に生きる先に、青磁は何を手にするか。
クスッと笑えてたまーーにシリアス、そんな、『佑佳』を始めた最初の完結物語を大幅改稿リメイクでお披露目です!

文化研究部
ポリ 外丸
青春
高校入学を控えた5人の中学生の物語。中学時代少々難があった5人が偶々集まり、高校入学と共に新しく部を作ろうとする。しかし、創部を前にいくつかの問題が襲い掛かってくることになる。
※カクヨム、ノベルアップ+、ノベルバ、小説家になろうにも投稿しています。

乙男女じぇねれーしょん
ムラハチ
青春
見知らぬ街でセーラー服を着るはめになったほぼニートのおじさんが、『乙男女《おつとめ》じぇねれーしょん』というアイドルグループに加入し、神戸を舞台に事件に巻き込まれながらトップアイドルを目指す青春群像劇! 怪しいおじさん達の周りで巻き起こる少女誘拐事件、そして消えた3億円の行方は……。
小説家になろうは現在休止中。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















