お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説

壬生狼の戦姫
天羽ヒフミ
歴史・時代
──曰く、新撰組には「壬生狼の戦姫」と言われるほどの強い女性がいたと言う。
土方歳三には最期まで想いを告げられなかった許嫁がいた。名を君菊。幼馴染であり、歳三の良き理解者であった。だが彼女は喧嘩がとんでもなく強く美しい女性だった。そんな彼女にはある秘密があって──?
激動の時代、誠を貫いた新撰組の歴史と土方歳三の愛と人生、そして君菊の人生を描いたおはなし。
参考・引用文献
土方歳三 新撰組の組織者<増補新版>新撰組結成150年
図説 新撰組 横田淳
新撰組・池田屋事件顛末記 冨成博

仇討ちの娘
サクラ近衛将監
歴史・時代
父の仇を追う姉弟と従者、しかしながらその行く手には暗雲が広がる。藩の闇が仇討ちを様々に妨害するが、仇討の成否や如何に?娘をヒロインとして思わぬ人物が手助けをしてくれることになる。
毎週木曜日22時の投稿を目指します。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。


蛙の半兵衛泣き笑い
藍染 迅
歴史・時代
長屋住まいの浪人川津半兵衛は普段は気の弱いお人よし。大工、左官にも喧嘩に負けるが、何故か人に慕われる。
ある日隣の幼女おきせが、不意に姿を消した。どうやら人買いにさらわれたらしい。
夜に入って降り出した雨。半兵衛は単身人買い一味が潜む荒れ寺へと乗り込む。
褌裸に菅の笠。腰に差したるは鮫革柄の小太刀一振り。
雨が降ったら誰にも負けぬ。古流剣術蛟流が飛沫を巻き上げる。
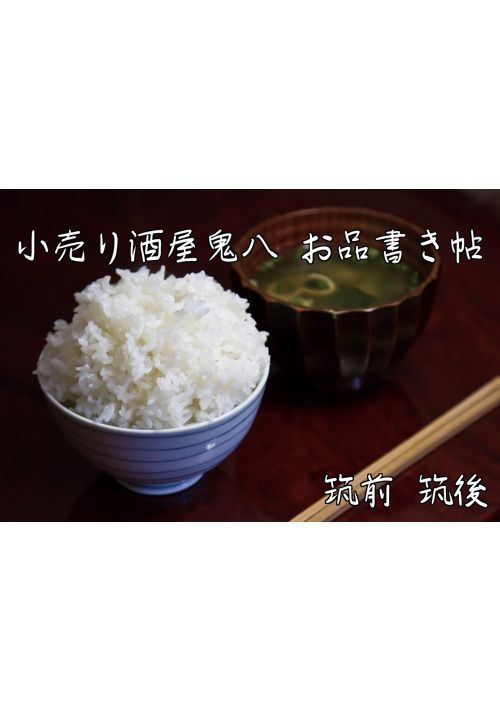
【受賞作】小売り酒屋鬼八 人情お品書き帖
筑前助広
歴史・時代
幸せとちょっぴりの切なさを感じるお品書き帖です――
野州夜須藩の城下・蔵前町に、昼は小売り酒屋、夜は居酒屋を営む鬼八という店がある。父娘二人で切り盛りするその店に、六蔵という料理人が現れ――。
アルファポリス歴史時代小説大賞特別賞「狼の裔」、同最終候補「天暗の星」ともリンクする、「夜須藩もの」人情ストーリー。


播磨守江戸人情小噺 お家存続の悲願
戸沢一平
歴史・時代
南町奉行池田播磨守頼方《いけだはりまのかみよりまさ》が下す裁断についての、江戸市民たちの評判がすこぶる良い。大見得を切って正義を振りかざすような派手さは無いのだが、胸にジンと染みる温情をサラリと加える加減が玄人好みなのだと、うるさ型の江戸っ子たちはいう。
池田播磨守頼方は、遠山の金さんこと遠山景元の後任の町奉行だ。あの、国定忠治に死罪を申し渡した鬼の奉行として恐れられていた。しかし、池田が下す裁断は、人情味に溢れる名裁断として江戸市民たちの評判を呼んでいく。
幕府勘定役組頭の奥田源右衛門《おくだげんえもん》が殺された。深夜に、屋敷で首を刺されていたのだ。下手人はどうも、奥田が毎夜のように招いていた女のようだ。奥田は女好きとして有名で、その筋の女を買うことが少なくない。
その関係の殺しとも思われたが、調べが進むと、お役目に関わる事情が浮上して来た。
町奉行池田播磨守は、どうやって犯人を追い詰めるのか。そして、どのような裁断を下すのか。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















