6 / 9
6 嘘
しおりを挟む
荷の積み込みを手伝いながら、高鵬は夜襲のことが気になって仕方がなかった。
あまりに時が悪過ぎはしないか。こちらが払暁の急襲を考えていた直前に敵軍の夜襲があるなど、彼には、偶然ではあり得ないことのように思えた。
楊然が情報を漏らしたとは考えられないだろうか。
それまで失敗らしい失敗のなかった偉い軍師さまがしくじったというのも、高鵬に、そのような疑いの気持ちを強くさせた。
だが、たまたまということもある。彼にはあり得ないことに思えたが、それでも絶対にない、というわけではない。敵にも、いろいろと攻め方を考える偉い軍師さまがいるのかも知れない。
そう考えれば、結論を出すには、まだ早いような気もしてきた。
作業の合間に休息を取っていると、林の陰から手招きする人間が見えた。巧みにほかの兵からは死角になり、高鵬からしか見えないようにその人間は立っていた。
見覚えがあった。あの銭を受け取った朝に、楊然と何やら話していたやけに背の高い男だ。
無視をするわけにもいかず、仕方なく手招きに応じると、あの時とは違って、長身の男は笑顔だった。
気味が悪い。
高鵬は、嫌な予感がした。
「伍長さん、でしたよね」
辺りを憚るその小声は、楊然とは異なり、どこかの地方を感じさせるような訛りを持っていなかった。
「そうだが……」
高鵬の声は、自然に警戒の色が濃くなった。
「伍長さんもよろしく頼みますよ」
「何をよろしくせよというのだ」
「惚けてもらっちゃあ、困りますよ。楊然からちゃんと聞いているんでしょ」
「何も聞いておらん」
少しだけだが、撥ね付けるような強い声を出してみた。
「おいおい、こちらが優しく言っている間に、認めた方が利口ってものだ。私の懐から出た銭が、伍長さんに渡ったという事実があるのだからな」
「……」
急に口調をぞんざいにするのも、恐らく交渉術のうちだろうが、高鵬にはどう対処して良いのか、ますます分からなかった。
「伍長さんにも頼みがある。この軍の行き先が知りたい」
「そんなことは知らん」
「おいおい」
「いや、本当に知らんのだ。惚けているわけではない」
知っていたら、自分は答えるつもりなのか、と彼は自分の言ったことに驚いた。
「ふん。楊然も知らないと言っていたからな。とりあえずは信じよう。私のことは彭浩と呼んでくれ。また顔を出す。その時に聞かせてもらおう」
「おい」
引き止めようとしたが、あっと言う間に彭浩は、木々が作る陰に溶けていった。
困ったことになった。
しかし、これで楊然のことははっきりした。
兵站を整えるのが意外に早く終わった。再出発までにほんの少しだが間ができた。
楊然に対してはわだかまりがあったが、いつものように五人は談笑していた。
高鵬は、楊然にどう対処すべきか、結論を得られないでいた。上官に報告するのか。しかし、それでは自分が銭を受け取ったことまで明るみに出る。いまさら、あの時は咄嗟でわけが分からなかった、などという言いわけは通らないだろう。あるいは、このまま黙認するのか。だがそれでは、また過日の夜襲のような恐ろしいことが起きるはずだ。では、楊然に直接問い質すか。いや、楊然の言うことを信じる気持ちになれないのだから、意味はない。
そのような思案を巡らせながらの談笑だった。
そこへ、同じ分隊の方翼という伍長から急に呼び出された。方翼とは挨拶をする程度だ。
ついて行くと伍長ばかりが何人も待っていた。どうやら面白い話ではなさそうだ。
「自分だけ勝手なことをされては困る」
方翼が、しかし穏やかな口調でまずはそう言った。
「……」
高鵬は、表情が変わるのを自覚した。同時に手の平に銭の感触が蘇った。
「飯のことだ」
顔を知っているだけの伍長が、険しい顔で吐き捨てるように言った。
「……」
一瞬、安堵が高鵬を包みそうになったが、次の瞬間には、不安がその上からさらに彼を覆って、やはり言葉が出てこない。何のことを言われているのかまるで分からなかった。
「部下と飯を分け合っているそうだな」
険しい顔のままで、同じ男が言った。
「……ああ」
やっとの思いで、そう返事をしたが、この状況と飯を分け合ったことが、高鵬の中ではどうしてもつながらない。
「そんなにいい格好をしたいのか」
また別の人間が、激しい口調でそう言ったが、逆光でその顔は真っ黒になり、誰であるか彼には判別できなかった。
それが合図であったかのように、伍長たちは口々に怒鳴り始めた。
部下たちが食事の際に険しい目を向けるとか、命令に対して不平を言うようになったとか、戦闘中に足を引っかけられたとか、直属の上官である分隊長が部下の掌握について嫌味を言ったとか……。
その主張が徐々に飯のことから離れていくのに反比例して、高鵬を囲む伍長たちの輪が狭まってきた。にじり寄る者たちの足が、おのおの砂煙を立てる。大勢の足が、砂煙を膨らませながら近づいてくる。
あまりに時が悪過ぎはしないか。こちらが払暁の急襲を考えていた直前に敵軍の夜襲があるなど、彼には、偶然ではあり得ないことのように思えた。
楊然が情報を漏らしたとは考えられないだろうか。
それまで失敗らしい失敗のなかった偉い軍師さまがしくじったというのも、高鵬に、そのような疑いの気持ちを強くさせた。
だが、たまたまということもある。彼にはあり得ないことに思えたが、それでも絶対にない、というわけではない。敵にも、いろいろと攻め方を考える偉い軍師さまがいるのかも知れない。
そう考えれば、結論を出すには、まだ早いような気もしてきた。
作業の合間に休息を取っていると、林の陰から手招きする人間が見えた。巧みにほかの兵からは死角になり、高鵬からしか見えないようにその人間は立っていた。
見覚えがあった。あの銭を受け取った朝に、楊然と何やら話していたやけに背の高い男だ。
無視をするわけにもいかず、仕方なく手招きに応じると、あの時とは違って、長身の男は笑顔だった。
気味が悪い。
高鵬は、嫌な予感がした。
「伍長さん、でしたよね」
辺りを憚るその小声は、楊然とは異なり、どこかの地方を感じさせるような訛りを持っていなかった。
「そうだが……」
高鵬の声は、自然に警戒の色が濃くなった。
「伍長さんもよろしく頼みますよ」
「何をよろしくせよというのだ」
「惚けてもらっちゃあ、困りますよ。楊然からちゃんと聞いているんでしょ」
「何も聞いておらん」
少しだけだが、撥ね付けるような強い声を出してみた。
「おいおい、こちらが優しく言っている間に、認めた方が利口ってものだ。私の懐から出た銭が、伍長さんに渡ったという事実があるのだからな」
「……」
急に口調をぞんざいにするのも、恐らく交渉術のうちだろうが、高鵬にはどう対処して良いのか、ますます分からなかった。
「伍長さんにも頼みがある。この軍の行き先が知りたい」
「そんなことは知らん」
「おいおい」
「いや、本当に知らんのだ。惚けているわけではない」
知っていたら、自分は答えるつもりなのか、と彼は自分の言ったことに驚いた。
「ふん。楊然も知らないと言っていたからな。とりあえずは信じよう。私のことは彭浩と呼んでくれ。また顔を出す。その時に聞かせてもらおう」
「おい」
引き止めようとしたが、あっと言う間に彭浩は、木々が作る陰に溶けていった。
困ったことになった。
しかし、これで楊然のことははっきりした。
兵站を整えるのが意外に早く終わった。再出発までにほんの少しだが間ができた。
楊然に対してはわだかまりがあったが、いつものように五人は談笑していた。
高鵬は、楊然にどう対処すべきか、結論を得られないでいた。上官に報告するのか。しかし、それでは自分が銭を受け取ったことまで明るみに出る。いまさら、あの時は咄嗟でわけが分からなかった、などという言いわけは通らないだろう。あるいは、このまま黙認するのか。だがそれでは、また過日の夜襲のような恐ろしいことが起きるはずだ。では、楊然に直接問い質すか。いや、楊然の言うことを信じる気持ちになれないのだから、意味はない。
そのような思案を巡らせながらの談笑だった。
そこへ、同じ分隊の方翼という伍長から急に呼び出された。方翼とは挨拶をする程度だ。
ついて行くと伍長ばかりが何人も待っていた。どうやら面白い話ではなさそうだ。
「自分だけ勝手なことをされては困る」
方翼が、しかし穏やかな口調でまずはそう言った。
「……」
高鵬は、表情が変わるのを自覚した。同時に手の平に銭の感触が蘇った。
「飯のことだ」
顔を知っているだけの伍長が、険しい顔で吐き捨てるように言った。
「……」
一瞬、安堵が高鵬を包みそうになったが、次の瞬間には、不安がその上からさらに彼を覆って、やはり言葉が出てこない。何のことを言われているのかまるで分からなかった。
「部下と飯を分け合っているそうだな」
険しい顔のままで、同じ男が言った。
「……ああ」
やっとの思いで、そう返事をしたが、この状況と飯を分け合ったことが、高鵬の中ではどうしてもつながらない。
「そんなにいい格好をしたいのか」
また別の人間が、激しい口調でそう言ったが、逆光でその顔は真っ黒になり、誰であるか彼には判別できなかった。
それが合図であったかのように、伍長たちは口々に怒鳴り始めた。
部下たちが食事の際に険しい目を向けるとか、命令に対して不平を言うようになったとか、戦闘中に足を引っかけられたとか、直属の上官である分隊長が部下の掌握について嫌味を言ったとか……。
その主張が徐々に飯のことから離れていくのに反比例して、高鵬を囲む伍長たちの輪が狭まってきた。にじり寄る者たちの足が、おのおの砂煙を立てる。大勢の足が、砂煙を膨らませながら近づいてくる。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

劉縯
橘誠治
歴史・時代
古代中国・後漢王朝の始祖、光武帝の兄・劉縯(りゅうえん)の短編小説です。
もともとは彼の方が皇帝に近い立場でしたが、様々な理由からそれはかなわず…それを正史『後漢書』に肉付けする形で描いていきたいと思っています。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
歴史小説家では宮城谷昌光さんや司馬遼太郎さんが好きです。
歴史上の人物のことを知るにはやっぱり物語がある方が覚えやすい。
上記のお二人の他にもいろんな作家さんや、大和和紀さんの「あさきゆめみし」に代表される漫画家さんにぼくもたくさんお世話になりました。
ぼくは特に古代中国史が好きなので題材はそこに求めることが多いですが、その恩返しの気持ちも込めて、自分もいろんな人に、あまり詳しく知られていない歴史上の人物について物語を通して伝えてゆきたい。
そんな風に思いながら書いています。
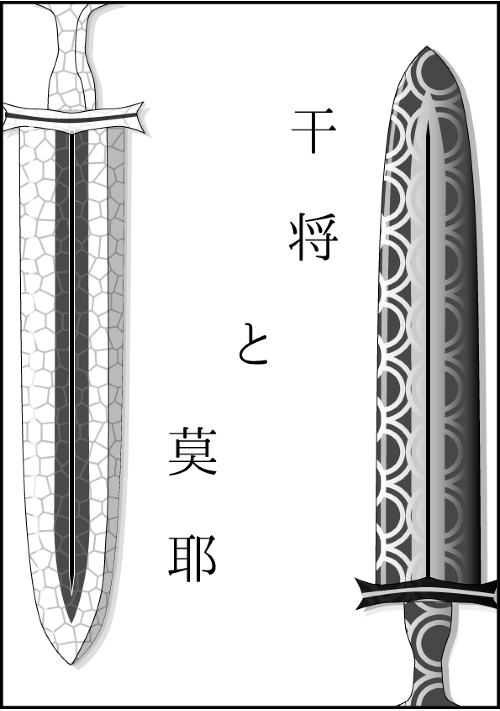

要塞少女
水城洋臣
歴史・時代
蛮族に包囲され孤立した城を守り抜いた指揮官は、十四歳の少女であった。
三国時代を統一によって終わらせた西晋王朝の末期。
かつて南中と呼ばれた寧州で、蛮族の反乱によって孤立した州城。今は国中が内紛の只中にあり援軍も望めない。絶体絶命と思われた城を救ったのは、名将である父から兵法・武芸を学んだ弱冠十四歳の少女・李秀であった……。
かの『三國志』で、劉備たちが治めた蜀の地。そんな蜀漢が滅びた後、蜀がどんな歴史を辿ったのか。
東晋時代に編纂された史書『華陽國志』(巴蜀の地方史)に記された史実を元にした伝奇フィクションです。


東洋大快人伝
三文山而
歴史・時代
薩長同盟に尽力し、自由民権運動で活躍した都道府県といえば、有名どころでは高知県、マイナーどころでは福岡県だった。
特に頭山満という人物は自由民権運動で板垣退助・植木枝盛の率いる土佐勢と主導権を奪い合い、伊藤博文・桂太郎といった明治の元勲たちを脅えさせ、大政翼賛会に真っ向から嫌がらせをして東条英機に手も足も出させなかった。
ここにあるのはそんな彼の生涯とその周辺を描くことで、幕末から昭和までの日本近代史を裏面から語る話である。
なろう・アルファポリス・カクヨム・マグネットに同一内容のものを投稿します。

信忠 ~“奇妙”と呼ばれた男~
佐倉伸哉
歴史・時代
その男は、幼名を“奇妙丸”という。人の名前につけるような単語ではないが、名付けた父親が父親だけに仕方がないと思われた。
父親の名前は、織田信長。その男の名は――織田信忠。
稀代の英邁を父に持ち、その父から『天下の儀も御与奪なさるべき旨』と認められた。しかし、彼は父と同じ日に命を落としてしまう。
明智勢が本能寺に殺到し、信忠は京から脱出する事も可能だった。それなのに、どうして彼はそれを選ばなかったのか? その決断の裏には、彼の辿って来た道が関係していた――。
◇この作品は『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n9394ie/)』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/16818093085367901420)』でも同時掲載しています◇

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)
三矢由巳
歴史・時代
時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。
佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。
幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。
ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。
又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。
海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。
一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。
事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。
果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。
シロの鼻が真実を追い詰める!
別サイトで発表した作品のR15版です。

戯作者になりたい ――物書き若様辻蔵之介覚え書――
加賀美優
歴史・時代
小普請の辻蔵之介は戯作者を目指しているが、どうもうまくいかない。持ち込んでも、書肆に断られてしまう。役目もなく苦しい立場に置かれた蔵之介は、友人の紹介で、町の騒動を解決していくのであるが、それが意外な大事件につながっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















