11 / 12
出発
しおりを挟む
「おはようございます」
日付が変わって、いつもより三十分早く出社した。誰よりも早く出社したかった。オフィスに入ると権藤課長がすでに仕事を始めていた。
「おはよう。今日はずいぶん早いね」
「はい。権藤課長。ちょっとお話があります」
こういう話は心理的に先手を打ちたかったので、ちょっと勢いをつけて言った。
「あっ。わかった。外がいい?」
「中でけっこうです」
わたしがそう言うと、権藤課長は立ち上がり、会議室へ歩き出した。会議室へ入ると、権藤課長は無言でわたしが切り出すのを待っていた。わたしはかおりから預かった会社宛の封書を机の上に差し出した。
「かおりからです」
「うん」
権藤課長は神妙な顔つきになった。
「郵便で送られてきました」
「もう顔を見せないということか」
権藤課長はひとりごとのようにつぶやいた。
「上野さん宛の封書も入っていました。わたしが直接渡します」
「婚約者にもそういうことか。仕事のことで悩んでいたのかな。彼女は常にハイレベルのものを自分に課していたから、疲れちゃったのかな。辞めるというより、少し休んでから出てくるというやり方もあったはず。完璧を求め過ぎちゃったのかなあ」
権藤課長は残念そうに肩を落としていた。そういう姿を見ていると心苦しかった。真実を知るわたしにとって、人をだますことと同じことだ。『申しわけありません』わたしは心の中でそうつぶやいた。
「亜仁場さん。さみしいでしょう。親しかったからね。あっさりと、去られちゃったね。つらいと思ったら、少し休んでいいよ」
権藤課長のわたしに対するおもいやりだと思った。
「大丈夫です。会社で仕事をしている方が気が紛れます」
「無理しなくてもいいよ。つらいと思ったら休んでいいから」
権藤課長はそう言って、立ち上がって、会議室を出た。しばらくして、わたしも会議室を出た。上野さんが出社したら、かおりからのメッセージをすぐに渡したかった。わたしは自分の席で待った。とにかく渡さないと、仕事が手につかない。パソコンのメールをチェックしていると、その姿が視界に入った。
「上野さん。おはようございます」
「あっ。おはよう。どうしたの、そんなあらたまって」
「ちょっと、お話があります」
「えっ。なに」
「かおりのことです」
わたしは小声で言った。
「えっ」
上野さんは急に真顔になった。少し凍りついたようにも見えた。上野さんは席に座らず、バッグを置くとすぐにオフィスの外に出た。わたしは後に続いた。上野さんとわたしは会社のエントランスをくぐって、人通りの少ない歩道で足を止めた。
「それで、かおりがどうしたって?」
上野さんは興奮していた。圧倒されそうだった。
「これです。郵便で送られてきました」
わたしは恐る恐る手紙を差し出した。上野さんはひったくるように手紙をつかんだ。そして、封を切った。上野さんが手紙を読んでいる間、わたしはうつむいていた。どんなことが書いてあるのか、想像するといたたまれない気持ちがあふれてきた。上野さんの手が少し震えているのがわかる。わたしはどうしたらいいんだろう。そんなわたしの気持ちを見透かしたように、上野さんは読み終えると、言った。
「郵便で送ってきたって、どういうこと? 亜仁場さんになんで。なんで、俺には直接送ってこないんだ。住所は? どこから出していた?」
口調はきつかった。
「はい。住所はありませんでした。なぜわたしになのか……」
わたしは歯切れが悪かった。
「婚約者より、友人か。まあ、そういうことか。自分を見つめ直したいって、どういうことだ。こんな形をとらなくてもできるはずだ。かおりらしくない」
上野さんは口調も目も怒っていた。ほんとうのことを書けないかおりにとって、苦し紛れの内容になってしまうのは避けられない。上野さんが納得できる内容を書けるわけがない。予想はしていたけれど、婚約寸前までいっていた人とこんな形になってしまうなんて、わたしもせつなくなった。
上野さんの赤ちゃんかもしれないのに……。そんなことを思ったら、急に涙があふれてきた。
「ごめん。亜仁場さんを責めているつもりじゃないんだ。ただ、納得できなかっただけなんだ。どうしても整理がつかないんだ。君にも何にも説明がないんだろ」
上野さんの悔しさが伝わってくる。わたしが別の意味で悲しんでいることを、上野さんは気づくはずもなかった。
「どういったことで自分を見つめ直したいのか、その前に相談してくれてもいいじゃないか。亜仁場さんもそう思わない?」
「ええ」
わたしもこのまま嘘を通さなければならない。かおりとの約束を守るために嘘を守らなくてはならない。……でも、すべてを守れるだろうか。上野さんの表情を見て、強く感じた。
「会社も無断欠勤で退社ということか」
「会社宛のメッセージは権藤課長に渡しました」
「辞表も郵便ということか。それにしても、俺はかおりのことをよくわからなかったということか。かおりの一部しか知らなかったということか。たぶんそうだ」
上野さんはそう言うと、オフィスへ戻って行った。わたしは大声で言い訳したい。事実をありのままに伝えたい。かおりはそんな人じゃない。ひとつの不明な事実があって、それが原因で結果的に嘘をつかなければならなかっただけだ。でもそれを言うと、特定の人が深く傷つく。とても深く傷つくから、嘘のオブラートで包むしかなかった。わたしもオフィスに戻った。しばらくして、始業時間になった。権藤課長はいなかった。上司に報告しているのだろうか。上野さんは怒ったままの表情で、メールをチェックしている。
いたたまれない雰囲気の中で一日は終わった。
自宅のリビングに座っていてもくつろげない。胸にぽっかり穴があいたように、心にもからだにも力が入らない状態だ。悪いことをしたような後味の悪さ。事情を知らない人から見れば、実際に悪いことをしていることになるだろう。
プルルルッ。プルルルッ。
「はい」
「あさり? 木村です」
「あー。征治さん」
びっくりした。征治さんから電話があるなんてめずらしいことだった。
「あさり。ちょっと旅に出ることにしたんだ」
「えっ。旅? どこへ?」
「ロシアへ」
「ひとりで?」
「そうだよ」
「でも、急じゃない。どうして、急にロシアへ行くの?」
「昔の友だちに会いに行こうと思ってさ。あさりとしばらく会えなくなると思ってさ。その前に会いたいと思って、電話したんだ」
「みんないなくなっちゃう。わたしどうしたらいいの」
かおりの次は征治さんがいなくなる。わたしと近い人たちがいなくなってしまう。さみしさが胸の奥からこみ上げてきた。
「みんなって、どうしたの。何かあったの」
「うん。公私ともにすごく仲のよかった友だちがいたんだけど、わたしの前からいなくなっちゃったの。それで、次は征治さんでしょ。わたしどうしたらいいの。親しい人たちがみんないなくなっちゃうじゃない」
「みんなって、ふたりじゃない」
「それが重要なの。わたしにとって大きな意味があるのに、征治さんわかってない」
わたしはさみしさ、悲しさ、むなしさが入り混じって、声を荒らげてしまった。
「あさり。ごめん。そんなつもりで言ったわけじゃないけれど、あやまるよ。とにかく会おうよ。電話だと正確に伝わらないし、誤解されちゃうから、とにかく会おうよ」
「征治さん。声を荒らげてしまって、ごめんなさい」
わたしと征治さんは会う約束をして、電話を切った。わたしはリビングに大の字になった。みんないなくなってしまう。なんでこんなことになるんだろう。普段の行いが悪いのかな。わたしだけが取り残され、時間の中で止まっている感じがした。みんな、先に進んでしまって、そのうち後ろ姿も見えなくなる。いっそうの孤独感がわたしを襲った。
目を覚ましてみると、夜明けが近かった。電話を切った後、そのまま眠ってしまったらしい。
「太陽が昇る。一日が始まる。わたしの一日。みんなの一日」
ひとりでいるのがさみしくて、ひとりごとを自分に聞かせた。
「おはようございます」
出社して、いつものようにオフィスに入った。いつものように入ったけれど、いつもの雰囲気ではなかった。かおりが会社を辞めることが周知されたのだろうか。ちょっと重苦しい雰囲気だった。上野さんはすでに出社していたけれど、何かが覆い被さったように、その周りの空気を重くしていた。その空気が、オフィス内を満たしていくようだった。
「亜仁場さん。おはよう」
望月さんが声をかけてきた。望月さんの目配せで、わたしたちはオフィスから出た。
「亜仁場さん。鈴木さん辞めることになったんだって」
「はい」
「無断欠勤が続いたから、無理もないけれど、なんでこんなことになったの。上野さんには相談したのかなあ」
「いえ。わたしがメッセージを封書で渡しました」
「そうなの。婚約者に対して、そんなのあり? 妊娠してるんじゃなかったの?」
そうか、望月さんはかおりの妊娠を疑っていた。この前に聞かれたときは、同性の勘は侮れないと思って、嘘を言えなかった。今は状況が違う。かおりが産むと決心した以上、かおりの名誉を守りたい。妊娠していると言ったら、みんなに伝わってしまう。ここだけの話の九十九パーセントは外に漏れることになると聞いた。今は、絶対に広めるわけにはいかない。
「違ったみたいです」
「えっ。だって、あのおなかは普通じゃなかったじゃない。食べ過ぎとか、そういうわけじゃないでしょう」
望月さんは疑いの目でわたしの顔を見た。いたたまれないわたしと、かおりの名誉を守りたいわたしがそこにいた。
「もしかして、流産しちゃったの? そのショックが尾を引いてるんでしょ。それで、会社にも出てこれなくなったんじゃないの」
「いえ。違います」
「でも、原因がはっきりしないんでしょ」
望月さんは疑問を抱いたまま、オフィスに戻った。望月さんは誤解している。誤解してもしょうがない。まわりの人たちも誤解しているのだろうか。
「鈴木さん。けっこうキャリアしてたのに、張り切り過ぎて疲れちゃったのかな。上野さんも聞かされていなかったみたいだ」
「ほんとに」
廊下ですれ違った人たちの会話が耳に入った。こういった内容の話は伝達が早い。仕事の通達より早く社内を駆け抜けていく。こうして、かおりの不名誉な退社理由だけが知れ渡ることになる。わたしではどうにもならない。
このような社内の雰囲気とわたしの気持ちが週末まで続いた。
土曜日の朝になった。征治さんと会うことになっている。いつもと違うのは、相談したいことがあって、わたしが会いに行くのではない。征治さんからのアプローチで会いに行くのだ。かおりのいない社内の雰囲気を引きずっていて、晴れない日々が続いたけれど、征治さんと会えることで、心の中にあかりがポッと灯るようだった。
新宿駅西口、ショッピングビル一階にある大きなガラスがエントランスに広がる見通しのいい喫茶店。約束の時間より五分早く着いたとき、征治さんがガラス越しに手を振ってくれた。
「あさり。悪いね」
「えっ。なんで」
「僕の言い訳を聞くために来てくれたからね。貴重な時間を割いてね」
「水くさい言い方ね。会えて嬉しい。電話くれてありがとう。そう言いたいの。とりあえずね。でもね、その言い訳にわたしが納得しなかったら撤回するよ」
「はははっ。先手を取られたな」
「こうでも言っておかないと、今のわたしは耐えられそうもないからね。電話でも言ったでしょ」
わたしたちはコーヒーを注文した。征治さんが息を深く吸い込んで、ゆっくり吐いた。
「突然だったかな」
「それはそうよ。征治さんは前から計画してたことでしょう。聞かされた方はなんの前触れもないから、びっくりするわよ」
「確かに行きたい気持ちはずっとあった。それはほんとうだ。でもね。それをいつにしようかと決めたのは、最近なんだ。あさりに電話する一週間前に決めたんだ。隠してたことになるのかな。でも、決心したのは最近だから、隠したことにはならないでしょ。まあ、そういうことにしといて」
まわりくどいいい方だった。でも、征治さんらしかった。
「まあ。許す」
わざと言ってみた。
「前にも話したことがあるよね。格闘技をやっていたことがあったときのこと」
「うん。憶えてる」
「そのときの友だちのところに行くんだ。故郷に似た空を探しに、いっしょに日本をまわったロシアの友だち。事情があって住むところを変えていたらしいが、ちょっと落ち着いたということで、連絡をもらったんだ。以前から、僕が行きたいと言っていたので、憶えていてくれたんだよ」
「じゃあ。一週間とか、二週間で帰ってくるんでしょう」
「長期になりそうなんだ。いろいろあって話がしたいし、いっしょに活動したいことがあって期間が決められないんだよ」
「活動ってなんなの」
「彼が育った地域をゆっくり見てみたい。彼の考え方がどのように形成されたかを知りたい。例えば、空を見るときの感情の表れ。一日の太陽の終わりを目に焼き付けようとすること」
わたしは思い出した。その話は征治さんから聞いたことがある。そのときは聞き流していた。わたしにとっては世間話のひとつだと思っていた。征治さんにとっては根が深い出来事だったんだ。
「そんなに大切なことなの」
「大切かどうか。聞かれても、はっきりと答えることができない。答えるのが嫌じゃなくて、よくわからないということだよ。事実を知りたいということだよ。彼は深い悲しみを持っていた。深い悲しみを持っていたが、希望も持っていた。ちょうど天秤で釣り合うような感情かな。交戦状態で日々の暮らしが危機にさらされているときでも、なんとか生きて、平和で穏やかな日々を取り戻したい。悲しい状況であっても、希望を語ることは忘れなかった。そのときの彼の目は輝いていたよ。透明だった。希望っていうのは、つくるものなんだと、教えられた気がしたんだ。」
「それって、男の友情なのかな」
「友情だけではない気がする。女の人から見たら、そう見えるかもね」
「征治さんの事務所はどうするの」
「僕の事務所で働いている人がいたでしょ。その人も資格を持っているんだ。事務所の名称は変わるけれど、その場所で行政書士事務所を開くことになっている。開拓した顧客がまわりにいるから、引き継いでもらうことにしたよ」
「さみしくなっちゃうね」
「ごめん」
「ごめんって、誰に謝っているの。わたしにだったら、わたしに相談しなかったこと。怒りたい。ずるいよ。去る人は、いつも自分勝手。勝手に決めて、報告して終わりでしょ。残される人は、その事実を受け止めることしかできないでしょ。その事実に参加することができない。ずるいよ。わたしのことどう思っていたの」
そこまで言うと、急に悲しくなってきた。征治さんを快く送り出すつもりで来たのに、涙をこらえることができなかった。
「あさり」
しばらく、沈黙が続いた。わたしが泣いている間、征治さんはうつむいていた。何かを言いたそうだった。
「あさり。友だちの話を聞かせてくれないか。いなくなった友だちの話」
征治さんが口を開いた。
「うん」
「仲よかったんでしょ」
「うん」
「その友だちと僕がいなくなっちゃうことが耐えられないんだよね」
わたしの心はまさにそうだった。
「みんないなくなっちゃう。みんなわたしから離れていく」
「話すのがつらかったら、話さなくてもいいよ」
ふと見上げると、征治さんはわたしを見つめていた。目の表情はやわらかかった。
「聞いてくれる」
「うん」
それから一時間くらい、わたしはかおりのことを征治さんに話した。私生活でも会社にいても何でも話せる友だちだったことを、ありのままを話した。
「親友であり、よりどころ、今の生活にとって必要な人だったのかな」
征治さんがぽつりと言った。
「そうなの。でも、急にいなくなっちゃった」
「自分でも迷っているんだよ」
「迷ってるって? かおりは自分で決めたんだよ」
「表向きはそう見えるよ。産むと決めたことはね。それがその時点で一番の選択肢だった。多少の迷いはあるけれど、将来に向かって一番の選択肢だった」
「多少の迷いって、産むと決めたのはかおりだよ。わたしはそこまでは言えなかったよ。友だちとしても、同じ女としても言えなかった。最終的にはかおりが決めたけどね」
「最終的に決めたのはかおりちゃんだよ。でも、迷いがあるからひとりになって考える時間が欲しかったのじゃないかな。何か引っかかるものがあって、今は言えないか、わからないからひとりになって考えたい。ということ」
「そうなのかなあ。ちょっとわからない」
「あさりに連絡するっていうことでしょ。連絡があったら、何かが前進したっていうことだよ」
「なかったら?」
「ないというより、何かあったら連絡があるよ」
「そうかな」
征治さんの話の半分は理解できた。残りの半分は友だちとして、納得できなかった。
「あさりとかおりちゃんって、いい友だちなんだよね。僕も会ってみたい気がする」
「ほんと」
わたしはうれしかった。仲のいい友だちと会ってみたいと言ってくれるだけで、なぜかうれしかった。
「出発は二週間後なんだ」
「えっ。もうすぐじゃない」
「決めたら、早い方がいいと思ってね」
「行っちゃうのか。ひとりになっちゃうな。連絡先は? 連絡するにはどうしたらいいの」
「はっきりとした場所が定まらないからね。何かあったら連絡するよ」
「それじゃ、かおりといっしょじゃない。みんな自分勝手だよね」
「先はどうなるかわからない。人生は推定だよ。推定しながら生きている。推定があるからワクワクして楽しいのかもしれないね。僕も自分推定しながら生きていくよ。あさりもあさり推定だよ。世の中、わからないことだらけだよ。実際に見ることができることって、限られるよね。よほど意識しないと視界は広がらない。意識し過ぎても疲れちゃうしね。だから、推定しながら力を抜いていこうよ」
「推定ばかりじゃ、何もわからないでしょ。確定しないとどこへ行っていいかわからないでしょ」
「確定したら、そこで止まっちゃうよ。この世でも、あの世でも、確定するものじゃないからね。終着点はないような気がする。クルクル回っているような感じ。推定しながら、よりよいところを求めていくような感じ」
「それで満たされるの? 確定しなくちゃ、つかめるものがないような気がする」
「そんなことはないよ。そこで止まっちゃうより、続いている方が希望はあるよ。そう思ったほうが楽しいよ」
「楽しいか……。今のわたしにとって、それがいいかもね。そう思わないと、さみしいしね」
「あまり思いつめないでよ。希望は持てるよ。持った方がいいよ。そうすれば、あさりはかおりちゃんにだって会えるだろうし、僕にも会えるよ。そんな気がするな」
「まあ、そういうことにしておくね」
わたしはちょっと気が楽になった。征治さんと話ができてよかった。
わたしたちは喫茶店を出て、しばらく歩いた。
「征治さん。わたしと征治さんの関係って、なんだろうね。友だちかな」
「友だち? うーん。もっと、いい感じ」
「いい感じ?」
「うん。今は」
「今は」
「そう。先はわからないよ。推定だよ。ははっ」
「もう。まじめに聞いているのに」
ふと見ると、征治さんの横顔がうれしそうな表情をしていた。その表情に触れて、わたしの気持ちがちょっと楽になった気がした。
「思い出は大切にしなよ。それ以上に、未来も大切にしなよ。そんな人になれれば、その人に会った人たちは、みんな楽しくなれるよ。そんなあさりになって欲しいな」
「うん」
心の隙間にやわらかな風がゆっくり通り過ぎた。よどんでいた何かが流れていった。街の風景も目にやさしく映った。
一週間が過ぎた。いつもより十分早く出社した。気持ちが浮足立っていたからだ。
「おはようございます」
「おはよう」
権藤課長はすでに出社していた。
「ありがとうございました」
わたしは辞表を提出した。
「どうした」
権藤課長はちょっと驚いたようにわたしを見た。
「お世話になりました」
「鈴木さんの件か。それとも仕事上で悩んでいたの」
「いえ違います。自立します。少し甘えていました」
素直な気持ちだった。
「ヘアカラーの企画の件、中心メンバーになってもらおうと思っていたのに、どうしたの」
「周りを見過ぎて、合わせていたところがありました。見つめ直して、自分を鍛えたいんです」
「ここでもいいじゃないか」
「新しい環境で、まっさらにしたいんです」
「もう少し、時間をおいてからでもいいよ」
「ありがとうございます。でも、決めました」
権藤課長の言葉はありがたかったけれど、わたしは心に決めていた。
「うん。仮に預かっておくよ。一週間僕のところでね」
権藤課長はポンとわたしの肩をたたいて微笑んでくれた。その気持ちを考慮して、わたしは否定しなかった。否定はしなかったけれど、自分でも不思議なくらい決意を固めていた。かおりのいない職場はいつも通りビジネスの時間が流れていた。わたしがいなくなっても何日か経てばいつも通りの時間が流れていくだろう。征治さんの話を聞いているうちに、わたしは強い人間になりたくなった。それも芯の強い人間になってみたかった。まっさらな環境に、まっさらな自分を放り込んでみたい。素直に思った。
わたしはパソコンに向かって、データの整理を始めた。心に決めたからには、少しでも早く次の行動に移りたかった。今まで甘えていた部分があった。受け身で待っていた部分があった。今までは、それはそれで楽しかった。これからは、征治さんが言っていたように、推定で生きていこう。目先の距離ではなくて、もっと先の目線で見ていこうと思う。何があるかわからない方が楽しそうだし、夢もふくらみそうな気がする。
「いい表情してるね」
わたしがファクシミリで送っているときに、望月さんが声をかけてきた。
「あっ。どうも」
「ふっきれたの」
「えっ。かおりのことですか」
「そう」
「彼女も悩んだみたいだし、私もこれからだと思ってます」
「そうなの。いいことじゃない。上野さんはまだみたいね」
「上野さんはそうでしょうね」
上野さんは元気がない。かおりの失踪当時よりも、退社が決まってからの方が元気がない。それは無理もない。わたしにも責任がある。上野さんの顔を見ると、真実を打ち明けたくなる。すれ違うだけで心が痛い。ただ、上野さんがほんとうのことを知ったとしても、悩みは消えない。消えないどころかよけいに苦しめてしまうことになる。絶対になる。上野さん。ごめんなさい。いつかは、きっと……。いつも、心でつぶやいている。
「亜仁場さんはこれからなんだから、がんばりな」
「はい。ありがとうございます」
望月さんも心配してくれていた。かおりがいなくなって、わたしは落ち込んでいた。事情がわかっていても、当たり前のように存在した親友がいないなんて、考えたこともなかったし、想像もできなかったからだ。体験してみないとわからないさみしさだった。そんな落ち込みようのわたしを望月さんは心配してくれていた。同性としていたわってくれた。社員旅行で望月さんのことが少しわかったし、望月さんもわたしのことを少しは理解してくれたのかもしれない。普段の仕事向きの顔ではほんとうの姿を知ることは難しい。社員旅行というイレギュラーな設定は人と人との関係を再発見するいい機会だった。
その日は、晴れ晴れしい気分で仕事を終えた。
次の日も、また次の日も同じような気分で一日が終わった。
「権藤課長」
辞表提出の日から一週間過ぎた、朝だった。
「亜仁場さん。わかっているよ」
権藤課長はわたしを会議室に促がした。
「権藤課長。わたし気持ちが変わりません」
「わかっているよ。最近の亜仁場さんを見ているとそう感じたんだ。前の君だったら、説得の余地はありそうだったが、最近は違うね。目の表情が違う。明確な意思をもって、行動しているように見えた。内容はよくわからないけれど、鈴木さんのことがきっかけになったんだろう。今までとは違う何かを感じた。だから、これからの君に期待したい。ほんとうのことを言えば、ここに残って力を発揮して欲しいところだが、君の意思を尊重するよ」
「ありがとうございます」
わたしは胸が熱くなった。そこまで思っていてくれた権藤課長に申しわけない気持ちも湧き上がった。
「離れていくのがさみしいな。でも、君のことを思ったら、がんばれ亜仁場。ありがとう。そういうことだ」
「はい」
「早い方がいいんだろう。仕事は僕が引き継ぐよ」
「ありがとうございます」
それ以上言えなかった。わたしの心が見透かされていたような気がした。きっと、今までもこんな感じで、わたしの心を読み取りながら仕事の指示をしていたのだろう。恵まれていた仕事場だったと、あらためて思った。
退社日は一週間後に決まった。最後の終業時刻まで精一杯やろうと思った。
五日前、四日前、三日前、二日前、一日前……。
「お世話になりました」
お世話になったひとりひとりにあいさつをして別れを告げた。権藤課長はさみしそうだったけれど、わたしの次の人生を後押しするかのように、背中を押して送り出してくれた。最後の職場を振り返ってみた。みんな笑顔で送り出してくれた。にっこり顔の望月さんもいた。みんなありがとうございました。
「最後なんだから、お見送りしたっていいでしょ」
征治さんの旅立ちの日だ。最初、征治さんにお見送りのことを告げたら、丁重に断られた。でも、強引にわたしの意思を通した。次の人生の始まりだから、そう簡単には引き下がらないことにしたのだった。
「わかった。わかった。何度言っても強情だな。昔のあさりじゃないな。なんとなくそんな気がする」
「そんなのどうだっていいじゃない」
空港のロビーにはたくさんの顔が行き交っている。笑った顔、涙顔、緊張顔、うつむき顔……。出迎えた人や見送った人が、それぞれの表情で、それぞれのドラマの一場面をつくっている。そんなドラマがロビーにはあふれている。わたしと征治さんもドラマのクライマックスを迎えようとしている。
「行っちゃう人はいいよね。飛行機に乗ったら終わりでしょ。わたしは来た道を戻らなきゃいけないしね」
「飛行機に乗ったら終わり? そんなことはないよ。これから始まるんだよ」
「征治さんから見たらそうかもね。わたしから見たら、終わりなの」
「僕から見たらそうなるか。じゃあ、僕から見たらでいいよ。僕から見たら、始まりということでね。でも、始まりといっても、先はわからないからね。明確な目標に向かって行くわけじゃないから、どう展開するかわからないよ。すべては推定で進んでいくよ」
「推定か。まあ、そうでしょうね。わたしもこれからどうなるのか、わからないし、決められないしね」
「お互いさま。僕とあさりは同じだよ」
「同じ? なんか違うような感じがする。でも、まあいいか。明るく送りたいしね」
飛行機の便がアナウンスされている。征治さんが乗る便もボードに表示されている。出発の時刻も迫ってくる。
「今日は有給休暇をとったの?」
「えっ。まあね」
わたしが会社を辞めたこと。征治さんには言っていなかった。よけいな心配事を持って行かせたくなかったからだ。征治さんに相談したら、どう答えてくれるかなと思ったこともあったけれど、今回は自分で決めることにした。次の人生は自分で決める。その始まりだからだ。
「居場所がはっきりしたら、連絡してね。絶対連絡してね」
「そうだね」
肯定とも否定ともとれる曖昧なニュアンスで征治さんは答えた。わたしは征治さんの目を見た。征治さんを信じて、肯定の意味で受け止めることにした。
「いつかは戻ってくるんでしょ」
「そうだね」
「いつ戻るかはわからないんだよね」
「そうだね」
「そうだね。ばっかりじゃない」
「そうだね。はははっ」
「もう。まじめに答えてよ」
「あさりはどうしてるかなあ」
「わたし? 気になる?」
「まあね」
「わからない。白紙の状態だからね」
「そうか。もしひとりでいたなら、彼女にしようかな」
「えっ。何て言ったの」
空港内の搭乗アナウンスの声と征治さんの声が重なってよく聞き取れなかった。何て言ったのだろう。ひとりでなんとかなんとか……。ひとりでいるなっていうことかな。よけいなお世話。そのうちに、彼氏をつくってみせるから。征治さんが帰ってくる頃にはね。
「なんでもない。ひとりごと」
「もうすぐ、時間だね」
征治さんの便のアナウンスが流れた。出発ロビーにさみしさが漂った。
「ありがとうね」
この言葉を言ったとたん、涙が自然とあふれてきた。涙が止まらない。
「あさりも元気でね」
征治さんの表情が見えない。
ドアを開けて、リビングの床に座った。シーンと静まり返った部屋の中、空っぽになったわたしを置いた。かおりや征治さんがいなくなって、心がちょっと空っぽ。この部屋からスタートしたいろんな出来事はリセットされた。何かが終わった。何が終わったのかは考えない。考えたくない。かおりは連絡してくれるかな? 征治さんは戻ってくるかな? 待っていればいいのだろうか。
いや、待つだけじゃさみしいし、つまらない。この部屋から何かをスタートさせたい。スタートしなくちゃ、つまらない。スタートする。わたし推定。推定でいいから、動き出したい。
何気に郵便物をチェックした。
「ネクステージ」
「ネクステージ?」
あっ。そうか。結婚相談所だ。渋谷で声をかけられた結婚相談所だ。封を切ってみると、説明のコピーと直筆のメッセージがあった。
『ピッタリのお相手が見つかりました。お電話ください。待っています。しあわせになりましょ』
不思議な存在感で、ニコニコ顔の女性スタッフが頭に浮かんだ。きっとあの人だ。人柄が伝わってきそうな、やわらかな文体だ。でも、まあ、もういいの。電話しない。これからのわたしは、今始まったばかりだからね。自分で始める。
「今日も、何ごとも起こりませんように」
これまでのわたしはこれが口癖だったよなあ。これからのわたしはね。
「明日も、いいことがありますように」
ふと目を上げたら、オレンジ色の光がわたしに注がれた。夕日だ。征治さんが言っていた夕日の意味がわかった。そんな気がした。
日付が変わって、いつもより三十分早く出社した。誰よりも早く出社したかった。オフィスに入ると権藤課長がすでに仕事を始めていた。
「おはよう。今日はずいぶん早いね」
「はい。権藤課長。ちょっとお話があります」
こういう話は心理的に先手を打ちたかったので、ちょっと勢いをつけて言った。
「あっ。わかった。外がいい?」
「中でけっこうです」
わたしがそう言うと、権藤課長は立ち上がり、会議室へ歩き出した。会議室へ入ると、権藤課長は無言でわたしが切り出すのを待っていた。わたしはかおりから預かった会社宛の封書を机の上に差し出した。
「かおりからです」
「うん」
権藤課長は神妙な顔つきになった。
「郵便で送られてきました」
「もう顔を見せないということか」
権藤課長はひとりごとのようにつぶやいた。
「上野さん宛の封書も入っていました。わたしが直接渡します」
「婚約者にもそういうことか。仕事のことで悩んでいたのかな。彼女は常にハイレベルのものを自分に課していたから、疲れちゃったのかな。辞めるというより、少し休んでから出てくるというやり方もあったはず。完璧を求め過ぎちゃったのかなあ」
権藤課長は残念そうに肩を落としていた。そういう姿を見ていると心苦しかった。真実を知るわたしにとって、人をだますことと同じことだ。『申しわけありません』わたしは心の中でそうつぶやいた。
「亜仁場さん。さみしいでしょう。親しかったからね。あっさりと、去られちゃったね。つらいと思ったら、少し休んでいいよ」
権藤課長のわたしに対するおもいやりだと思った。
「大丈夫です。会社で仕事をしている方が気が紛れます」
「無理しなくてもいいよ。つらいと思ったら休んでいいから」
権藤課長はそう言って、立ち上がって、会議室を出た。しばらくして、わたしも会議室を出た。上野さんが出社したら、かおりからのメッセージをすぐに渡したかった。わたしは自分の席で待った。とにかく渡さないと、仕事が手につかない。パソコンのメールをチェックしていると、その姿が視界に入った。
「上野さん。おはようございます」
「あっ。おはよう。どうしたの、そんなあらたまって」
「ちょっと、お話があります」
「えっ。なに」
「かおりのことです」
わたしは小声で言った。
「えっ」
上野さんは急に真顔になった。少し凍りついたようにも見えた。上野さんは席に座らず、バッグを置くとすぐにオフィスの外に出た。わたしは後に続いた。上野さんとわたしは会社のエントランスをくぐって、人通りの少ない歩道で足を止めた。
「それで、かおりがどうしたって?」
上野さんは興奮していた。圧倒されそうだった。
「これです。郵便で送られてきました」
わたしは恐る恐る手紙を差し出した。上野さんはひったくるように手紙をつかんだ。そして、封を切った。上野さんが手紙を読んでいる間、わたしはうつむいていた。どんなことが書いてあるのか、想像するといたたまれない気持ちがあふれてきた。上野さんの手が少し震えているのがわかる。わたしはどうしたらいいんだろう。そんなわたしの気持ちを見透かしたように、上野さんは読み終えると、言った。
「郵便で送ってきたって、どういうこと? 亜仁場さんになんで。なんで、俺には直接送ってこないんだ。住所は? どこから出していた?」
口調はきつかった。
「はい。住所はありませんでした。なぜわたしになのか……」
わたしは歯切れが悪かった。
「婚約者より、友人か。まあ、そういうことか。自分を見つめ直したいって、どういうことだ。こんな形をとらなくてもできるはずだ。かおりらしくない」
上野さんは口調も目も怒っていた。ほんとうのことを書けないかおりにとって、苦し紛れの内容になってしまうのは避けられない。上野さんが納得できる内容を書けるわけがない。予想はしていたけれど、婚約寸前までいっていた人とこんな形になってしまうなんて、わたしもせつなくなった。
上野さんの赤ちゃんかもしれないのに……。そんなことを思ったら、急に涙があふれてきた。
「ごめん。亜仁場さんを責めているつもりじゃないんだ。ただ、納得できなかっただけなんだ。どうしても整理がつかないんだ。君にも何にも説明がないんだろ」
上野さんの悔しさが伝わってくる。わたしが別の意味で悲しんでいることを、上野さんは気づくはずもなかった。
「どういったことで自分を見つめ直したいのか、その前に相談してくれてもいいじゃないか。亜仁場さんもそう思わない?」
「ええ」
わたしもこのまま嘘を通さなければならない。かおりとの約束を守るために嘘を守らなくてはならない。……でも、すべてを守れるだろうか。上野さんの表情を見て、強く感じた。
「会社も無断欠勤で退社ということか」
「会社宛のメッセージは権藤課長に渡しました」
「辞表も郵便ということか。それにしても、俺はかおりのことをよくわからなかったということか。かおりの一部しか知らなかったということか。たぶんそうだ」
上野さんはそう言うと、オフィスへ戻って行った。わたしは大声で言い訳したい。事実をありのままに伝えたい。かおりはそんな人じゃない。ひとつの不明な事実があって、それが原因で結果的に嘘をつかなければならなかっただけだ。でもそれを言うと、特定の人が深く傷つく。とても深く傷つくから、嘘のオブラートで包むしかなかった。わたしもオフィスに戻った。しばらくして、始業時間になった。権藤課長はいなかった。上司に報告しているのだろうか。上野さんは怒ったままの表情で、メールをチェックしている。
いたたまれない雰囲気の中で一日は終わった。
自宅のリビングに座っていてもくつろげない。胸にぽっかり穴があいたように、心にもからだにも力が入らない状態だ。悪いことをしたような後味の悪さ。事情を知らない人から見れば、実際に悪いことをしていることになるだろう。
プルルルッ。プルルルッ。
「はい」
「あさり? 木村です」
「あー。征治さん」
びっくりした。征治さんから電話があるなんてめずらしいことだった。
「あさり。ちょっと旅に出ることにしたんだ」
「えっ。旅? どこへ?」
「ロシアへ」
「ひとりで?」
「そうだよ」
「でも、急じゃない。どうして、急にロシアへ行くの?」
「昔の友だちに会いに行こうと思ってさ。あさりとしばらく会えなくなると思ってさ。その前に会いたいと思って、電話したんだ」
「みんないなくなっちゃう。わたしどうしたらいいの」
かおりの次は征治さんがいなくなる。わたしと近い人たちがいなくなってしまう。さみしさが胸の奥からこみ上げてきた。
「みんなって、どうしたの。何かあったの」
「うん。公私ともにすごく仲のよかった友だちがいたんだけど、わたしの前からいなくなっちゃったの。それで、次は征治さんでしょ。わたしどうしたらいいの。親しい人たちがみんないなくなっちゃうじゃない」
「みんなって、ふたりじゃない」
「それが重要なの。わたしにとって大きな意味があるのに、征治さんわかってない」
わたしはさみしさ、悲しさ、むなしさが入り混じって、声を荒らげてしまった。
「あさり。ごめん。そんなつもりで言ったわけじゃないけれど、あやまるよ。とにかく会おうよ。電話だと正確に伝わらないし、誤解されちゃうから、とにかく会おうよ」
「征治さん。声を荒らげてしまって、ごめんなさい」
わたしと征治さんは会う約束をして、電話を切った。わたしはリビングに大の字になった。みんないなくなってしまう。なんでこんなことになるんだろう。普段の行いが悪いのかな。わたしだけが取り残され、時間の中で止まっている感じがした。みんな、先に進んでしまって、そのうち後ろ姿も見えなくなる。いっそうの孤独感がわたしを襲った。
目を覚ましてみると、夜明けが近かった。電話を切った後、そのまま眠ってしまったらしい。
「太陽が昇る。一日が始まる。わたしの一日。みんなの一日」
ひとりでいるのがさみしくて、ひとりごとを自分に聞かせた。
「おはようございます」
出社して、いつものようにオフィスに入った。いつものように入ったけれど、いつもの雰囲気ではなかった。かおりが会社を辞めることが周知されたのだろうか。ちょっと重苦しい雰囲気だった。上野さんはすでに出社していたけれど、何かが覆い被さったように、その周りの空気を重くしていた。その空気が、オフィス内を満たしていくようだった。
「亜仁場さん。おはよう」
望月さんが声をかけてきた。望月さんの目配せで、わたしたちはオフィスから出た。
「亜仁場さん。鈴木さん辞めることになったんだって」
「はい」
「無断欠勤が続いたから、無理もないけれど、なんでこんなことになったの。上野さんには相談したのかなあ」
「いえ。わたしがメッセージを封書で渡しました」
「そうなの。婚約者に対して、そんなのあり? 妊娠してるんじゃなかったの?」
そうか、望月さんはかおりの妊娠を疑っていた。この前に聞かれたときは、同性の勘は侮れないと思って、嘘を言えなかった。今は状況が違う。かおりが産むと決心した以上、かおりの名誉を守りたい。妊娠していると言ったら、みんなに伝わってしまう。ここだけの話の九十九パーセントは外に漏れることになると聞いた。今は、絶対に広めるわけにはいかない。
「違ったみたいです」
「えっ。だって、あのおなかは普通じゃなかったじゃない。食べ過ぎとか、そういうわけじゃないでしょう」
望月さんは疑いの目でわたしの顔を見た。いたたまれないわたしと、かおりの名誉を守りたいわたしがそこにいた。
「もしかして、流産しちゃったの? そのショックが尾を引いてるんでしょ。それで、会社にも出てこれなくなったんじゃないの」
「いえ。違います」
「でも、原因がはっきりしないんでしょ」
望月さんは疑問を抱いたまま、オフィスに戻った。望月さんは誤解している。誤解してもしょうがない。まわりの人たちも誤解しているのだろうか。
「鈴木さん。けっこうキャリアしてたのに、張り切り過ぎて疲れちゃったのかな。上野さんも聞かされていなかったみたいだ」
「ほんとに」
廊下ですれ違った人たちの会話が耳に入った。こういった内容の話は伝達が早い。仕事の通達より早く社内を駆け抜けていく。こうして、かおりの不名誉な退社理由だけが知れ渡ることになる。わたしではどうにもならない。
このような社内の雰囲気とわたしの気持ちが週末まで続いた。
土曜日の朝になった。征治さんと会うことになっている。いつもと違うのは、相談したいことがあって、わたしが会いに行くのではない。征治さんからのアプローチで会いに行くのだ。かおりのいない社内の雰囲気を引きずっていて、晴れない日々が続いたけれど、征治さんと会えることで、心の中にあかりがポッと灯るようだった。
新宿駅西口、ショッピングビル一階にある大きなガラスがエントランスに広がる見通しのいい喫茶店。約束の時間より五分早く着いたとき、征治さんがガラス越しに手を振ってくれた。
「あさり。悪いね」
「えっ。なんで」
「僕の言い訳を聞くために来てくれたからね。貴重な時間を割いてね」
「水くさい言い方ね。会えて嬉しい。電話くれてありがとう。そう言いたいの。とりあえずね。でもね、その言い訳にわたしが納得しなかったら撤回するよ」
「はははっ。先手を取られたな」
「こうでも言っておかないと、今のわたしは耐えられそうもないからね。電話でも言ったでしょ」
わたしたちはコーヒーを注文した。征治さんが息を深く吸い込んで、ゆっくり吐いた。
「突然だったかな」
「それはそうよ。征治さんは前から計画してたことでしょう。聞かされた方はなんの前触れもないから、びっくりするわよ」
「確かに行きたい気持ちはずっとあった。それはほんとうだ。でもね。それをいつにしようかと決めたのは、最近なんだ。あさりに電話する一週間前に決めたんだ。隠してたことになるのかな。でも、決心したのは最近だから、隠したことにはならないでしょ。まあ、そういうことにしといて」
まわりくどいいい方だった。でも、征治さんらしかった。
「まあ。許す」
わざと言ってみた。
「前にも話したことがあるよね。格闘技をやっていたことがあったときのこと」
「うん。憶えてる」
「そのときの友だちのところに行くんだ。故郷に似た空を探しに、いっしょに日本をまわったロシアの友だち。事情があって住むところを変えていたらしいが、ちょっと落ち着いたということで、連絡をもらったんだ。以前から、僕が行きたいと言っていたので、憶えていてくれたんだよ」
「じゃあ。一週間とか、二週間で帰ってくるんでしょう」
「長期になりそうなんだ。いろいろあって話がしたいし、いっしょに活動したいことがあって期間が決められないんだよ」
「活動ってなんなの」
「彼が育った地域をゆっくり見てみたい。彼の考え方がどのように形成されたかを知りたい。例えば、空を見るときの感情の表れ。一日の太陽の終わりを目に焼き付けようとすること」
わたしは思い出した。その話は征治さんから聞いたことがある。そのときは聞き流していた。わたしにとっては世間話のひとつだと思っていた。征治さんにとっては根が深い出来事だったんだ。
「そんなに大切なことなの」
「大切かどうか。聞かれても、はっきりと答えることができない。答えるのが嫌じゃなくて、よくわからないということだよ。事実を知りたいということだよ。彼は深い悲しみを持っていた。深い悲しみを持っていたが、希望も持っていた。ちょうど天秤で釣り合うような感情かな。交戦状態で日々の暮らしが危機にさらされているときでも、なんとか生きて、平和で穏やかな日々を取り戻したい。悲しい状況であっても、希望を語ることは忘れなかった。そのときの彼の目は輝いていたよ。透明だった。希望っていうのは、つくるものなんだと、教えられた気がしたんだ。」
「それって、男の友情なのかな」
「友情だけではない気がする。女の人から見たら、そう見えるかもね」
「征治さんの事務所はどうするの」
「僕の事務所で働いている人がいたでしょ。その人も資格を持っているんだ。事務所の名称は変わるけれど、その場所で行政書士事務所を開くことになっている。開拓した顧客がまわりにいるから、引き継いでもらうことにしたよ」
「さみしくなっちゃうね」
「ごめん」
「ごめんって、誰に謝っているの。わたしにだったら、わたしに相談しなかったこと。怒りたい。ずるいよ。去る人は、いつも自分勝手。勝手に決めて、報告して終わりでしょ。残される人は、その事実を受け止めることしかできないでしょ。その事実に参加することができない。ずるいよ。わたしのことどう思っていたの」
そこまで言うと、急に悲しくなってきた。征治さんを快く送り出すつもりで来たのに、涙をこらえることができなかった。
「あさり」
しばらく、沈黙が続いた。わたしが泣いている間、征治さんはうつむいていた。何かを言いたそうだった。
「あさり。友だちの話を聞かせてくれないか。いなくなった友だちの話」
征治さんが口を開いた。
「うん」
「仲よかったんでしょ」
「うん」
「その友だちと僕がいなくなっちゃうことが耐えられないんだよね」
わたしの心はまさにそうだった。
「みんないなくなっちゃう。みんなわたしから離れていく」
「話すのがつらかったら、話さなくてもいいよ」
ふと見上げると、征治さんはわたしを見つめていた。目の表情はやわらかかった。
「聞いてくれる」
「うん」
それから一時間くらい、わたしはかおりのことを征治さんに話した。私生活でも会社にいても何でも話せる友だちだったことを、ありのままを話した。
「親友であり、よりどころ、今の生活にとって必要な人だったのかな」
征治さんがぽつりと言った。
「そうなの。でも、急にいなくなっちゃった」
「自分でも迷っているんだよ」
「迷ってるって? かおりは自分で決めたんだよ」
「表向きはそう見えるよ。産むと決めたことはね。それがその時点で一番の選択肢だった。多少の迷いはあるけれど、将来に向かって一番の選択肢だった」
「多少の迷いって、産むと決めたのはかおりだよ。わたしはそこまでは言えなかったよ。友だちとしても、同じ女としても言えなかった。最終的にはかおりが決めたけどね」
「最終的に決めたのはかおりちゃんだよ。でも、迷いがあるからひとりになって考える時間が欲しかったのじゃないかな。何か引っかかるものがあって、今は言えないか、わからないからひとりになって考えたい。ということ」
「そうなのかなあ。ちょっとわからない」
「あさりに連絡するっていうことでしょ。連絡があったら、何かが前進したっていうことだよ」
「なかったら?」
「ないというより、何かあったら連絡があるよ」
「そうかな」
征治さんの話の半分は理解できた。残りの半分は友だちとして、納得できなかった。
「あさりとかおりちゃんって、いい友だちなんだよね。僕も会ってみたい気がする」
「ほんと」
わたしはうれしかった。仲のいい友だちと会ってみたいと言ってくれるだけで、なぜかうれしかった。
「出発は二週間後なんだ」
「えっ。もうすぐじゃない」
「決めたら、早い方がいいと思ってね」
「行っちゃうのか。ひとりになっちゃうな。連絡先は? 連絡するにはどうしたらいいの」
「はっきりとした場所が定まらないからね。何かあったら連絡するよ」
「それじゃ、かおりといっしょじゃない。みんな自分勝手だよね」
「先はどうなるかわからない。人生は推定だよ。推定しながら生きている。推定があるからワクワクして楽しいのかもしれないね。僕も自分推定しながら生きていくよ。あさりもあさり推定だよ。世の中、わからないことだらけだよ。実際に見ることができることって、限られるよね。よほど意識しないと視界は広がらない。意識し過ぎても疲れちゃうしね。だから、推定しながら力を抜いていこうよ」
「推定ばかりじゃ、何もわからないでしょ。確定しないとどこへ行っていいかわからないでしょ」
「確定したら、そこで止まっちゃうよ。この世でも、あの世でも、確定するものじゃないからね。終着点はないような気がする。クルクル回っているような感じ。推定しながら、よりよいところを求めていくような感じ」
「それで満たされるの? 確定しなくちゃ、つかめるものがないような気がする」
「そんなことはないよ。そこで止まっちゃうより、続いている方が希望はあるよ。そう思ったほうが楽しいよ」
「楽しいか……。今のわたしにとって、それがいいかもね。そう思わないと、さみしいしね」
「あまり思いつめないでよ。希望は持てるよ。持った方がいいよ。そうすれば、あさりはかおりちゃんにだって会えるだろうし、僕にも会えるよ。そんな気がするな」
「まあ、そういうことにしておくね」
わたしはちょっと気が楽になった。征治さんと話ができてよかった。
わたしたちは喫茶店を出て、しばらく歩いた。
「征治さん。わたしと征治さんの関係って、なんだろうね。友だちかな」
「友だち? うーん。もっと、いい感じ」
「いい感じ?」
「うん。今は」
「今は」
「そう。先はわからないよ。推定だよ。ははっ」
「もう。まじめに聞いているのに」
ふと見ると、征治さんの横顔がうれしそうな表情をしていた。その表情に触れて、わたしの気持ちがちょっと楽になった気がした。
「思い出は大切にしなよ。それ以上に、未来も大切にしなよ。そんな人になれれば、その人に会った人たちは、みんな楽しくなれるよ。そんなあさりになって欲しいな」
「うん」
心の隙間にやわらかな風がゆっくり通り過ぎた。よどんでいた何かが流れていった。街の風景も目にやさしく映った。
一週間が過ぎた。いつもより十分早く出社した。気持ちが浮足立っていたからだ。
「おはようございます」
「おはよう」
権藤課長はすでに出社していた。
「ありがとうございました」
わたしは辞表を提出した。
「どうした」
権藤課長はちょっと驚いたようにわたしを見た。
「お世話になりました」
「鈴木さんの件か。それとも仕事上で悩んでいたの」
「いえ違います。自立します。少し甘えていました」
素直な気持ちだった。
「ヘアカラーの企画の件、中心メンバーになってもらおうと思っていたのに、どうしたの」
「周りを見過ぎて、合わせていたところがありました。見つめ直して、自分を鍛えたいんです」
「ここでもいいじゃないか」
「新しい環境で、まっさらにしたいんです」
「もう少し、時間をおいてからでもいいよ」
「ありがとうございます。でも、決めました」
権藤課長の言葉はありがたかったけれど、わたしは心に決めていた。
「うん。仮に預かっておくよ。一週間僕のところでね」
権藤課長はポンとわたしの肩をたたいて微笑んでくれた。その気持ちを考慮して、わたしは否定しなかった。否定はしなかったけれど、自分でも不思議なくらい決意を固めていた。かおりのいない職場はいつも通りビジネスの時間が流れていた。わたしがいなくなっても何日か経てばいつも通りの時間が流れていくだろう。征治さんの話を聞いているうちに、わたしは強い人間になりたくなった。それも芯の強い人間になってみたかった。まっさらな環境に、まっさらな自分を放り込んでみたい。素直に思った。
わたしはパソコンに向かって、データの整理を始めた。心に決めたからには、少しでも早く次の行動に移りたかった。今まで甘えていた部分があった。受け身で待っていた部分があった。今までは、それはそれで楽しかった。これからは、征治さんが言っていたように、推定で生きていこう。目先の距離ではなくて、もっと先の目線で見ていこうと思う。何があるかわからない方が楽しそうだし、夢もふくらみそうな気がする。
「いい表情してるね」
わたしがファクシミリで送っているときに、望月さんが声をかけてきた。
「あっ。どうも」
「ふっきれたの」
「えっ。かおりのことですか」
「そう」
「彼女も悩んだみたいだし、私もこれからだと思ってます」
「そうなの。いいことじゃない。上野さんはまだみたいね」
「上野さんはそうでしょうね」
上野さんは元気がない。かおりの失踪当時よりも、退社が決まってからの方が元気がない。それは無理もない。わたしにも責任がある。上野さんの顔を見ると、真実を打ち明けたくなる。すれ違うだけで心が痛い。ただ、上野さんがほんとうのことを知ったとしても、悩みは消えない。消えないどころかよけいに苦しめてしまうことになる。絶対になる。上野さん。ごめんなさい。いつかは、きっと……。いつも、心でつぶやいている。
「亜仁場さんはこれからなんだから、がんばりな」
「はい。ありがとうございます」
望月さんも心配してくれていた。かおりがいなくなって、わたしは落ち込んでいた。事情がわかっていても、当たり前のように存在した親友がいないなんて、考えたこともなかったし、想像もできなかったからだ。体験してみないとわからないさみしさだった。そんな落ち込みようのわたしを望月さんは心配してくれていた。同性としていたわってくれた。社員旅行で望月さんのことが少しわかったし、望月さんもわたしのことを少しは理解してくれたのかもしれない。普段の仕事向きの顔ではほんとうの姿を知ることは難しい。社員旅行というイレギュラーな設定は人と人との関係を再発見するいい機会だった。
その日は、晴れ晴れしい気分で仕事を終えた。
次の日も、また次の日も同じような気分で一日が終わった。
「権藤課長」
辞表提出の日から一週間過ぎた、朝だった。
「亜仁場さん。わかっているよ」
権藤課長はわたしを会議室に促がした。
「権藤課長。わたし気持ちが変わりません」
「わかっているよ。最近の亜仁場さんを見ているとそう感じたんだ。前の君だったら、説得の余地はありそうだったが、最近は違うね。目の表情が違う。明確な意思をもって、行動しているように見えた。内容はよくわからないけれど、鈴木さんのことがきっかけになったんだろう。今までとは違う何かを感じた。だから、これからの君に期待したい。ほんとうのことを言えば、ここに残って力を発揮して欲しいところだが、君の意思を尊重するよ」
「ありがとうございます」
わたしは胸が熱くなった。そこまで思っていてくれた権藤課長に申しわけない気持ちも湧き上がった。
「離れていくのがさみしいな。でも、君のことを思ったら、がんばれ亜仁場。ありがとう。そういうことだ」
「はい」
「早い方がいいんだろう。仕事は僕が引き継ぐよ」
「ありがとうございます」
それ以上言えなかった。わたしの心が見透かされていたような気がした。きっと、今までもこんな感じで、わたしの心を読み取りながら仕事の指示をしていたのだろう。恵まれていた仕事場だったと、あらためて思った。
退社日は一週間後に決まった。最後の終業時刻まで精一杯やろうと思った。
五日前、四日前、三日前、二日前、一日前……。
「お世話になりました」
お世話になったひとりひとりにあいさつをして別れを告げた。権藤課長はさみしそうだったけれど、わたしの次の人生を後押しするかのように、背中を押して送り出してくれた。最後の職場を振り返ってみた。みんな笑顔で送り出してくれた。にっこり顔の望月さんもいた。みんなありがとうございました。
「最後なんだから、お見送りしたっていいでしょ」
征治さんの旅立ちの日だ。最初、征治さんにお見送りのことを告げたら、丁重に断られた。でも、強引にわたしの意思を通した。次の人生の始まりだから、そう簡単には引き下がらないことにしたのだった。
「わかった。わかった。何度言っても強情だな。昔のあさりじゃないな。なんとなくそんな気がする」
「そんなのどうだっていいじゃない」
空港のロビーにはたくさんの顔が行き交っている。笑った顔、涙顔、緊張顔、うつむき顔……。出迎えた人や見送った人が、それぞれの表情で、それぞれのドラマの一場面をつくっている。そんなドラマがロビーにはあふれている。わたしと征治さんもドラマのクライマックスを迎えようとしている。
「行っちゃう人はいいよね。飛行機に乗ったら終わりでしょ。わたしは来た道を戻らなきゃいけないしね」
「飛行機に乗ったら終わり? そんなことはないよ。これから始まるんだよ」
「征治さんから見たらそうかもね。わたしから見たら、終わりなの」
「僕から見たらそうなるか。じゃあ、僕から見たらでいいよ。僕から見たら、始まりということでね。でも、始まりといっても、先はわからないからね。明確な目標に向かって行くわけじゃないから、どう展開するかわからないよ。すべては推定で進んでいくよ」
「推定か。まあ、そうでしょうね。わたしもこれからどうなるのか、わからないし、決められないしね」
「お互いさま。僕とあさりは同じだよ」
「同じ? なんか違うような感じがする。でも、まあいいか。明るく送りたいしね」
飛行機の便がアナウンスされている。征治さんが乗る便もボードに表示されている。出発の時刻も迫ってくる。
「今日は有給休暇をとったの?」
「えっ。まあね」
わたしが会社を辞めたこと。征治さんには言っていなかった。よけいな心配事を持って行かせたくなかったからだ。征治さんに相談したら、どう答えてくれるかなと思ったこともあったけれど、今回は自分で決めることにした。次の人生は自分で決める。その始まりだからだ。
「居場所がはっきりしたら、連絡してね。絶対連絡してね」
「そうだね」
肯定とも否定ともとれる曖昧なニュアンスで征治さんは答えた。わたしは征治さんの目を見た。征治さんを信じて、肯定の意味で受け止めることにした。
「いつかは戻ってくるんでしょ」
「そうだね」
「いつ戻るかはわからないんだよね」
「そうだね」
「そうだね。ばっかりじゃない」
「そうだね。はははっ」
「もう。まじめに答えてよ」
「あさりはどうしてるかなあ」
「わたし? 気になる?」
「まあね」
「わからない。白紙の状態だからね」
「そうか。もしひとりでいたなら、彼女にしようかな」
「えっ。何て言ったの」
空港内の搭乗アナウンスの声と征治さんの声が重なってよく聞き取れなかった。何て言ったのだろう。ひとりでなんとかなんとか……。ひとりでいるなっていうことかな。よけいなお世話。そのうちに、彼氏をつくってみせるから。征治さんが帰ってくる頃にはね。
「なんでもない。ひとりごと」
「もうすぐ、時間だね」
征治さんの便のアナウンスが流れた。出発ロビーにさみしさが漂った。
「ありがとうね」
この言葉を言ったとたん、涙が自然とあふれてきた。涙が止まらない。
「あさりも元気でね」
征治さんの表情が見えない。
ドアを開けて、リビングの床に座った。シーンと静まり返った部屋の中、空っぽになったわたしを置いた。かおりや征治さんがいなくなって、心がちょっと空っぽ。この部屋からスタートしたいろんな出来事はリセットされた。何かが終わった。何が終わったのかは考えない。考えたくない。かおりは連絡してくれるかな? 征治さんは戻ってくるかな? 待っていればいいのだろうか。
いや、待つだけじゃさみしいし、つまらない。この部屋から何かをスタートさせたい。スタートしなくちゃ、つまらない。スタートする。わたし推定。推定でいいから、動き出したい。
何気に郵便物をチェックした。
「ネクステージ」
「ネクステージ?」
あっ。そうか。結婚相談所だ。渋谷で声をかけられた結婚相談所だ。封を切ってみると、説明のコピーと直筆のメッセージがあった。
『ピッタリのお相手が見つかりました。お電話ください。待っています。しあわせになりましょ』
不思議な存在感で、ニコニコ顔の女性スタッフが頭に浮かんだ。きっとあの人だ。人柄が伝わってきそうな、やわらかな文体だ。でも、まあ、もういいの。電話しない。これからのわたしは、今始まったばかりだからね。自分で始める。
「今日も、何ごとも起こりませんように」
これまでのわたしはこれが口癖だったよなあ。これからのわたしはね。
「明日も、いいことがありますように」
ふと目を上げたら、オレンジ色の光がわたしに注がれた。夕日だ。征治さんが言っていた夕日の意味がわかった。そんな気がした。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説


『脆弱能力巫女の古代女王「卑弥呼たん」門真市ニコニコ商店街に転生す!』
M‐赤井翼
現代文学
赤井です。
今回は、いつもの「ニコニコ商店街」と「こども食堂」を舞台に「邪馬台国」から「女王 卑弥呼たん」がなつ&陽菜の「こっくりさん」で召喚!
令和の世では「卑弥呼たんの特殊の能力」の「予言」も「天気予知」も「雨乞い能力」もスマホや水道の前には「過去の遺物」(´・ω・`)ショボーン。
こども食堂で「自信」を持って提供した「卑弥呼たん」にとっての最高のご馳走「塩むすび」も子供達からは「不評」…( ノД`)シクシク…。
でも、「女王 卑弥呼たん」はくじけない!
「元女王」としてのプライドをもって現代っ子に果敢にチャレンジ!
いつぞや、みんなの人気者に!
そんな「卑弥呼たん」になじんだ、こども食堂の人気者「陽葵ちゃん」に迫る魔の手…。
「陽葵ちゃん」が危機に陥った時、「古代女王 卑弥呼たん」に「怒りの電流」が流れる!
歴史マニア「赤井翼」の思う、「邪馬台国」と「卑弥呼」を思う存分に書かせてもらった「魏志倭人伝」、「古事記」、「日本書記」に「ごめんなさい!」の一作!
「歴史歪曲」と言わずに、「諸説あり」の「ひとつ」と思って「ゆるーく」読んでやってください!
もちろん最後は「ハッピーエンド」はお約束!
では、全11チャプターの「短期集中連載」ですのでよーろーひーこー!
(⋈◍>◡<◍)。✧♡

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。



遅れてきた先生
kitamitio
現代文学
中学校の卒業が義務教育を終えるということにはどんな意味があるのだろう。
大学を卒業したが教員採用試験に合格できないまま、何年もの間臨時採用教師として中学校に勤務する北田道生。「正規」の先生たち以上にいろんな学校のいろんな先生達や、いろんな生徒達に接することで見えてきた「中学校のあるべき姿」に思いを深めていく主人公の生き方を描いています。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
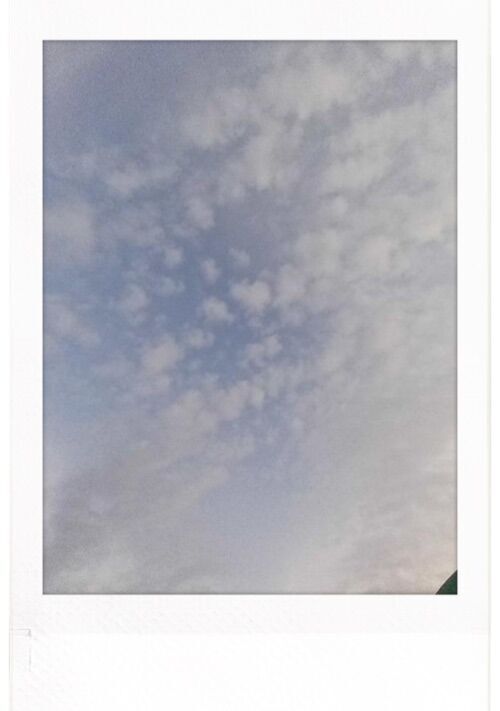
ファンファーレ!
ほしのことば
青春
♡完結まで毎日投稿♡
高校2年生の初夏、ユキは余命1年だと申告された。思えば、今まで「なんとなく」で生きてきた人生。延命治療も勧められたが、ユキは治療はせず、残りの人生を全力で生きることを決意した。
友情・恋愛・行事・学業…。
今まで適当にこなしてきただけの毎日を全力で過ごすことで、ユキの「生」に関する気持ちは段々と動いていく。
主人公のユキの心情を軸に、ユキが全力で生きることで起きる周りの心情の変化も描く。
誰もが感じたことのある青春時代の悩みや感動が、きっとあなたの心に寄り添う作品。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















