7 / 12
結婚なんて
しおりを挟む
翌朝、電話で起こされた。かおりからだった。
「あさり、きのうどこに行っていたの。電話をかけ続けていたんだけどつながらなくて、朝早いけどごめんね」
「えっ。あー」
わたしは半分眠っていた。ふと、時計を見ると五時だ。
「たいへんなのよ。今日、商社マンとデートなんだけど、上野さんが今日も会いたいって言ってきたの。きのうはデートしたのよ。今日は、用事があるって言ったんだけど、いつもと違ってしつこいの。だから、あさり、アリバイづくりに協力してよ」
かおりはちょっといらだった様子だった。
「あー。えっ。かおり、だから言ったじゃない。つじつまが合わなくなるって」
わたしは、少しずつ目が覚めてきた。
「今は、それどころじゃないから。とにかくお願い」
「もう。上野さん、きっと気づき始めているのよ」
「そのことはあとで考えるから、とにかくお願い」
「どうすればいいの」
わたしは、気が進まなかった。でも、もう少し眠りたかったので、そのように返答した。
「あさりも今日どこかへ出かけてよ。それか、電話が鳴っても出ないでね。電話に出たら、あさりが家にいることがばれちゃうからね」
「それって、拘束状態じゃない」
「それより、かおりの携帯にかかってくるでしょ」
「わたしの携帯は切っておくから大丈夫」
「だから、お願い。今度、おごるから」
「とりあえず、わかった。でも、どう対処するかはわたしに決めさせて」
電話を切った。わたしは、完全に目が覚めてしまった。頭が少しずつ回転し始め、かおりの頼みを受けてしまったことを後悔した。泥沼にはまっていきそうで、気が重い。きのうは楽しい一日だった。今日はねー……。もやもやした気持ちを振り払いたかったので、ベッドから飛び起きた。空を見たら、晴れそうだった。
「出かけよう」
自分に向けて、そう言った。
着替えて、顔を洗って、カーテンを開けた。休日にこんなに早く起きることはめったにない。旅行に行くときぐらいだ。窓を開け、外を見た。道路に車がない。平日だったら、車が数珠つなぎで、排気ガスも途切れないのに、今日は空気が澄んでいるような錯覚に陥った。空気を意識的に吸い込んだ。いや、錯覚じゃない。普段とは違う味がする。早起きして、得した気分になった。そこには、うれしい自分がいた。
音が少ない日曜日の朝は、わたしを落ち着かせてくれる。テーブルの上にあった雑誌を手に取った。定期的に雑誌は買うようにしている。一冊はファッション雑誌、もう一冊は住まいの雑誌。ファッションについては、仕事柄、最新の情報をキャッチするために半分はパブリックな気持ちで買っている。個人的に流行に興味はあるけれど、流行のすべてを身につけようとは思わないから、プライベートな気持ちは半分だけ。住まいについては、結婚している友だちの家に遊びに行ったときに興味を持った。一戸建やマンションに住んでいて、内装やインテリアに凝っている人たちが何人かいる。そのこだわりに憧れるものがあって、わたしだったらこうしようと夢がふくらむ対象になっているから、その参考資料として買っているのだ。ただ、仕事のある平日は、ゆっくり読むための時間がなかなかとれない。休日は、雑誌がゆっくり読める、わたしを取り戻すための時間だ。
ファッション雑誌に目をやると、表紙の渋谷特集の文字が飛び込んできた。渋谷……最近は行っていない。学生時代は、渋谷とか原宿、たまに銀座かな。渋谷は、わたしより若い世代の街だと思っているから、意識の枠から外していた。雑誌の表紙は、定番になっているモデルが笑っている写真。笑顔に渋谷。なんとなく決めた。今日は渋谷にしよう。そう思うと時間がもったいないので、朝食を簡単につくって、出かける準備をするために、気持ちに弾みをつけた。
ひと通りの準備を終えて、玄関ドアに鍵をかける頃には、かおりに朝早く起こされたもやもや感はすっかり消え、休日モードのわたしに戻っていた。最寄り駅から地下鉄に乗った。それなりの数の人たちが乗っていて、座れなかったので、戸袋に寄りかかった。車内広告を見た。車内広告を見て思うことがある。字が小さい広告が多いこと。相当近づかないとわからないものがあるし、視力の弱い人たちは読めないだろう。そのうえ、広告紙を挟んで留める金具に隠れてしまって読めないものもある。読みたいと思っても読めないし、広告主にとってもアピールする内容が伝わらないだろう。紙面のレイアウトやデザインが優先になっているからかもしれない。隠れている文字を当てる国語のクイズじゃないんだから、工夫が欲しい。けっこう、見てるんだから。
地下鉄に乗っている人たちに押し出されて、渋谷駅に着いた。やはり人波がすごい。波にまかせて、そのまま流されてしまった方が楽かもしれない。わたしは、特に目的としている場所もなかったので、波に乗って街に出た。まわりも見てもわたしより若い人たちが多い。高校生、中学生、中には小学校の中高学年のようなグループもいた。どこにでもいるような人たちともいえるけれど、ここは密度が濃そうだ。駅前から坂を登り、少し行くと間口の狭いたくさんのビルがぎっしり建ち並んでいた。駅前の現代的な建物に比べて、古いつくりのビルたちだ。これらが、征治さんが言うとこの雑居ビルなのかな。歩きながらビルに目をやると、どのビルもお店や会社が入っている。ほとんど空きがない。中には歩道の上まで、PR看板が陣取っている。視線を上げた、どこかで見たような、聞いたような文字列が視界に入った。
『ネクステージ』。ネクステージ? わたしの頭の中で、その文字列が分析された。五秒、十秒、そうだ! 『ネクステージ』だ! かおりが言っていた『ネクステージ』だ! ここかあ、と思いながら足を止めた。わたしは、看板を見ながら、かおりの顔を思い浮かべていると、背中をなでるようなやわらかい風が吹いたかと思うと、耳元に人の気配を感じた。振り返ると、五十歳くらいの女性がニコニコと微笑んでいた。
「ちょっと、いらっしゃい」
その女性が、さらに微笑みながら言った。
「いえ。なんでもないんです」
わたしは、瞬間的にネクステージのスタッフだと感じ、関わりたくなかったので、否定的に反応した。
「いいのよ。そんなに深く考えないで。ちょっと、おばさんの話しを聞いてよ」
その女性は、柔和な感じを崩さないまま言った。
「いえ。わたしはそんなつもりで……」
わたしは、その女性の仏様みたいなやわらかな表情を見て、強く断る気持ちが萎え始めていた。
「あなたが抱いている気持ち、わたしはわかっているから、ちょっと来てよ」
「えっ」
わたしは、ネクステージに興味があるわけではないけれど、その女性の不思議な存在感を無視できなくなり、気がつくと心が反応していた。その女性の背中に誘導されながら、奥にあるエレベーターの入口に向かった。十五秒くらいして扉が開き、ふたりは乗った。
「渋谷にはよくいらっしゃるの」
その女性が、口を開いた。
「学生時代は来ていましたが、今はあんまり」
「そう」
エレベーターは七階で止まった。扉が開き、正面にネクステージのプレートが見えた。その女性は、わたしを招くようにドアを開けた。薄いピンク系の壁紙が目に飛び込んだ。ピンクのもつやわらかな雰囲気が部屋全体に広がって、あたたかさと安心感を与えてくれた。業務内容よりも事務所のつくりに興味を持った。かおりが言っていたように、銀行のカウンターブースの雰囲気だ。三つのカウンターがあった。三つとも埋まっていた。かおりが来たときも、すべて埋まっていたようなことを言っていたかな。
「ちょっと、待ってね」
やわらかな表情を保ったまま、女性が言った。
なんで、ついてきたのだろうという気持ちと、妙にやわらかいその表情に身を委ねている安心感とが入り混じって、不思議な感覚で時の経つのを待っていた。五分くらいして、カウンターのひとつが空いた。真ん中のカウンターに座っていた二十代前半の女性が立ち上がって、帰ろうとしていた。出口に向かうため、わたしの方に歩いてきたが、その表情は明るかった。安心感を与えられたような明るさだった。しばらくして、わたしは真ん中のカウンターに案内された。もといたスタッフに代わって、わたしをここまで誘導してきた女性が担当者として目の前に座った。
「こんにちは」
女性スタッフがにっこり微笑んだ。
「どうも」
わたしは、少し不安になった。
「わたしたちの看板に目を留めてくれてありがとう。心配しないでね。いかがわしい会社じゃないから」
「はい」
「独身ですね。結婚には興味を持っていらっしゃるんでしょ」
「いえ。まだそこまでは」
「いいのよ。すぐでなくても。ちょっとでも興味を持った瞬間から、始まっているのよ」
「始まっている?」
「そうなの。結婚という文字や言葉に少しでも反応したときから、結婚について意識し始めたということなのよ。結婚したいとか、したくないとかは、その次の意識のパターンなのよ。だから、あなたが看板に目を留めたことは、人として、女性として自然なことなの」
「ええ」
わたしは、半分納得して、半分理解できなかった。というよりも、意識が追いついていなかった。
「お勤めですか」
「はい」
「お友だちの中で、結婚している方はいらっしゃる?」
「はい」
「そうですか。まわりの人たちがみなさん独身であるなら、意識しなかったことが、身近な誰かが結婚して、生活パターンが変化する様子を見たときから、気持ちが変化する人たちが多いのよ。特に女性の場合はね。憧れとか理想とか、ときには嫉妬という形で芽生えるの。結婚したくない人でも、避けては通れない気持ちの変化みたいなものなの」
「はー」
少し理解できたけれども、認めたくない気持ちが三割ほど残った。
「あなたの気持ちの中で整理がつかないのは当然よ。人から言われて、結婚ということについて今すぐ真剣に考えなければならない問題でもないし、そういう気持ちがはっきり出てくるまで待てばいいという人もいることは確か。でも、あなたのように気づき始めている人にとっては、いい機会なの。チャンスでもあるの。今抱いている気持ちに無理やりフタを閉めてしまうと、歪んだ形で表われてくることもあるから。例えば、嫉妬とかね。とにかく自分に正直になることが、自分を大切にすることだからね」
「ここは、結婚相談所ですよね」
「まあ、案内所に近いわね。旅行したときに立ち寄る観光案内所みたいなものかな。旅先で聞きたいことがあったら、誰でも気軽に立ち寄るでしょ。そういうようなところだから安心してちょうだい」
「えー」
わたしは、説明内容にちょっと違和感があったけれど、女性スタッフが漂わせるやわらかな空気と、かおりが入会した動機を無視できなかったので、席を立とうとは思わなかった。
「大丈夫よ。誰もが抱いている気持ちを再確認するだけのことだから、安心してね。それでは、ちょっといいかしら。あなた、ぱっと見たところ、華美に飾る人じゃないわね。化粧もナチュラルであって、それが似合うのよ。自然体の中に気品があるのよね」
「そうですか」
かおりが言っていたように、いきなり本題には入らない。いろいろなタイプの人が来るから、百戦錬磨なのだろう。人を嫌な気分にさせない。
「好きなタイプでも嫌いなタイプでもいいから、こういう人がいいとか嫌だとか、明確に思うことってあるかしら」
「自己中心的な人は嫌ですね。思いやりのない人も。好きなタイプはこれといって、はっきりしたものはありません。気が合えばいいという感じです」
なんか、わたし、誘導尋問にはまっているのかなと思いつつ、答えていた。
「お歳は、いくつ」
「二十八です」
「今が旬ね。でも、まだまだこれからよ。輝いているときだから、大事にしなくちゃ。あといくつかお聞きしていいかしら」
「ええ」
そのあと、わたしはいくつかの質問に答えた。自分の簡単なプロフィール、趣味、ライフスタイル、相手の希望条件など。そして、女性スタッフは、相談システムの概要をひと通り説明してくれた。
「本日はお疲れさまでした。あなたのことがわかって、わたしもうれしいです。お役に立てることがあるかと思います。あまり肩に力を入れずに頑張っていきましょう。わたしが力になりますから、安心してください」
「はい」
最初から最後まで、相手のペースで押し切られたような感じだった。強い力で押し切られたというよりも、やわらかなじゅうたんの上で、背中を押されながら歩かされた感じだ。エレベーターを降りて、渋谷の街に立ったとき、足もとに浮遊感が漂った。時計を見ると、ここに最初に立ったときから一時間経っていた。あっという間の時間だったが、どっと疲れた。少し休みたい気分だったので、歩きながら喫茶店を探した。
五分くらい歩いて、間口はそれほどでもないが、その割に窓の大きな店を見つけた。ドアを開けると、ダークブラウンの色が効いたシックな雰囲気を漂わせていた。窓側の席が空いていたので、そこに座った。コーヒーを注文し、背もたれに寄りかかり、窓の外を見た。ネクステージに行ったことを少し後悔していた。なんで行ったんだろう。看板の前で立ち止まらなければよかった。女性に声をかけられても無視すればよかった。結婚する気もないし、誰かを紹介されても困るのはわたし。それに、彼女や彼氏のいない人が行くところだ。彼女や彼氏……。ふと、わたしはどうなんだろうと考えていた。付き合っているといえるのかな……今のわたし。どっちなんだろう。それは、わたしが決めること? わたしと誰かが決めること? 今の心境とネクステージに行ったことが、わたしの中でうまく融合できずに葛藤していた。
頭の中がリセットできないまま、視線をテーブルに落とすと、耳元に言葉が入ってきた。横を見ると、OLらしい女性がふたり、話し込んでいた。
「何年付き合ってたんだっけ」
「二年弱」
「二年弱? あっという間ね」
「いろいろ考えたけど、決めちゃった」
「ピッタリの人がいて、よかったね」
「最初は好きなタイプじゃなかったんだけど、ズルズルきちゃって、突然プロポーズされちゃったの。彼、転勤が決まったみたいで、押し切られた感じかな。どうしてもわたしを連れて行くって。わたしのこと、ほんとうはどう思っているのかわからなくて悩んだこともあった。彼がわたしのことほんとうに好きなのか、転勤が決まったから焦ったのかわからないまま進んじゃった」
「えっ。じゃあ、後悔しているの」
「ううん。後悔じゃなくて、これでいいのかなって。いっしょになれば、うまくやっていけそうだから、ベストじゃないけどベターな選択」
「そう」
「かなはどうなのよ」
「付き合っている人はいるけどね。ゆかより長いよ。三年くらい。お互い、付いたり離れたりの感じよ」
「プロポーズの雰囲気はないの?」
「さあ」
「あれば、どうするの。応じるの」
「わからない。待っているのとは違うのよ。わたしからどうしてもこの人だっていう気持ちもないしね。わたし、彼氏がいなかった時期があって、焦ったことがあってね。誰でもいいから紹介してよって言いまくっていた。それで紹介されたのが今の彼氏なのよ」
「そう」
「緊急措置的な彼氏かも」
「でも、続いてるってことは、合っているんじゃない」
「そうかもしれない。でもさあ、もっといい人がいるかもしれないじゃない。そう思うとさあ、まだまだこれからでしょ」
「かなは贅沢かもね。あはは」
ふたりの会話は続いていた。このふたりとわたしもどこにでもいるような女性像なのかなと、ふと考えた。ネクステージの女性スタッフが言っていたように、結婚したいとか、したくないとかは別にして、結婚については避けて通れない問題なのかなと。このふたりの会話に出てきた、焦りの気持ちと、これでいいのかなっていう気持ち。わたしにも焦りはあるかもしれない。これでいいのかなっていう気持ちはわからない。というより、その立場に立っていないから、理解できない。
わたしの中に、何かもやもやした感情が膨れ上がり、座っている自分にもどかしさを感じてきたので、席を立って街に出ることにした。店を出て、洋服でも見ようと駅方向に歩き出した。こんな気分で歩いていると、通り過ぎる風景が無機質にわたしに飛び込んでくるような威圧感になり、いっそうの孤独を誘った。駅に近づくにつれて、人波のうねりが大きくなり、街の不規則な音が一段と強くなった。
人波に身を任せていると、わたしの歩幅に合わせるかのように、か細い声がした。聞き取れなかったので、無視していると、再びか細い声。また無視していると、トーンが上がって「あのー」という声がした。気になって振り返ってみると、細身の大学生のような男性が緊張した面持ちで歩いていた。目と目が合って、わたしにも緊張感が伝染してきたので、無視して歩き出そうとすると、その男性が小走りになったので、わたしは怖くなって動けなくなってしまった。
「あのー」
か細い声が、わたしに向かった。
「なんですか。わたしに何か」
わたしは言葉を返したくなかったけれど、また追ってきそうなので、そう言った。
「怪しいものではありません。何かの勧誘でもありません」
「わたし、急いでいますので」
「待ってください」
「さようなら」
わたしは、気味が悪かったので、前を向いて走り出した。
「待ってください」
その男性は、わたしを追い抜きながら言った。
「やめてください」
逃げたい。逃げられない。そんな気持ちがそう言わせた。そして、動けなくなった。
「すみません。怖がらないでください。そんな気持ちじゃないんです。ちょっと話をしたかったんです。僕の理想形だったんで」
「わたしには関係ないことですよね」
「僕が描いていた理想なんです。ちょっと話ができませんか」
その男性は、目に力を入れながら言った。わたしは嫌だった。でも、どこまでも追ってきそうな雰囲気がその男性にはあった。
「少しだけなら」
わたしはあきらめた。少しでも話氏を聞けば開放されるだろう。そんな気持ちだった。
「ありがとうございます。近くの喫茶店でいいですか」
その男性は満面の笑みで歩き出した。わたしは、後悔の気持ちがじわじわと高まりながらも、その男性の背中に付いて行った。まわりをきょろきょろしながら歩いているところを見ると、ここにはそんなに来ていないのだろうし、ナンパにも慣れているようではなかった。とわたしは予想した。わたしたちはしばらく歩いて、喫茶に入った。そして、適当なところに座った。ふたりは向かい合う状態になった。でも、男性は視線をテーブルに落としたまま、何もしゃべらない。わたしは、何のためにここにいるのだろうと思い始めた。やっぱり、来るんじゃなかった。席を立とうと思って、わたしから声をかけた。
「あのー、用がないなら帰ります」
するとその男性が
「すみません。ちょっと待ってください。緊張してるんです。タイプなんです」
「それだけですか。特に用がないなら帰りますけど」
わたしは、ここにいる時間が無駄に思えてきて、そう言った。
「いやっ。えーと。じつは、結婚前提に付き合ってくれませんか」
男性がそう言って、わたしは驚いた。
「なんでそういうことを言うんですか。初めて会ってから、時間も経ってもいないのに、そんなこと言われても困ります」
「唐突ですが、僕はそういう気持ちなんです。会った瞬間から。だから、行かないでください」
「あなたのことも何も知らないし、わたしの事情も知らないのに、よくそういうこと言えますね」
わたしは、少々腹が立った。
「あー。あー」
男性は泣きそうになった。
「落ち着いてください」
なんでわたしがこんな目に合わなければならないのと思いながらも、ここで泣かれたら、いやだったので、わたしは口調をやわらげた。
「すみません。慣れていないのです。歩いていて、理想の人が目の前に現われたので、どうしても話氏をしてみたかったのです」
「あなたは学生さん」
「そうです。春に東京に来たばかりで、人も街もよくわかりません」
男性はようやく落ち着いてきたようだった。
「わたしも上京組だから、あなたの気持ちも少しはわかるわ。見かけは、おとなしそうね。女性ともあまり話したことはないでしょう。それなのにナンパする度胸はあるわけ」
「あなたを見たときから胸がドキドキでした。度胸があるわけではありません。でも、どうしても手に入れたかったというか……」
「手に入れたい? わたしものじゃないんだから。それに、学生さんでしょ。まだまだこれからなのに、そう簡単に結婚という文字を使っちゃダメよ。これからたくさんの人とめぐりあうかもしれないじゃない。今はそういう気持ちでも、人は気が変わるから、慎重に考えないと。まあ、慎重に考えていくのは難しいけどね」
わたしは、説教のつもりで言ったわけじゃなかった。
「そうでしょうか。まだ、甘いのでしょうか」
「甘いというよりも、まだこれからいろんなことに出会うでしょう。人とか、街とかもそう。今がすべてじゃないっていうことよ。わたしが言いたいのは」
「友だちとしてもダメですか」
「学校にも同世代の人たちがたくさんいるでしょ。きっと見つかるわよ。その方が、話が合うわよ」
しばらく、沈黙が続いた。言い過ぎたかなと思いつつも、わたしは友だちになるのも気が進まなかった。
「あのう、僕、チャットでしかあまり話せないんです」
「チャット? パソコン上での会話ね」
「そうです」
「チャットでしか話せない? チャットで話すことは悪いことじゃないわよね」
「チャットでのやりとりはできるのです。キーを打つスピードも自信があります。でも、実際に会って人と話すのが苦手です」
「パソコンの文字だとニュアンスが伝わらないしね。しばらく、チャットをやめちゃったら」
わたしは、軽く言ったつもりだった。
「僕にとって大切なんです。今の僕にとって」
男性の口調は少し強くなった。
「ごめんね。否定するつもりじゃないのよ。ちょっとの間、やめてみたらと思って、そう言ったのよ。」
わたしは、こういうタイプの人の扱いには慣れていないので、言葉を選ぶのに苦労した。
「やめる生活は考えられないです」
「わたしは、人と直接話すのが基本なの。一期一会というには大げさかもしれないけれど、会って話している瞬間を大切にしたいのよ。次はいつ話せるかわからないし、話せないまま時間が過ぎていくかもしれないでしょ。あなたと話している今もそうよ。たまたま会って話している。次はもうないでしょう」
「えっ。もうなしですか」
男性はキッとにらみ返してきた。その瞬間、わたしはまずいと思った。こういうタイプは予想がつかない。言い方に気をつけなくちゃ。
「人から聞いた話でこういうのがあるの。クローンという言葉があるじゃない。羊とか、人間とか。DNAからクローンを生成して、生物のコピーをつくっていこうという試み。実際につくられた例もあるわよね。ただ、遺伝子に組み込まれた本能部分は少ししかないらしくて、学習や知能を中心に行動している高等動物については、実際にコピーできるのは、外形と行動パターンの一部なんですって。わたしは、それを聞いてから、人との出会いを大切にしようと思ったの。同じ人間はありえない。一期一会を大切にしようとね」
わたしは、征治さんから聞いたことを思い出した。
「はい。それだったら、僕との付き合いも考えてくれませんか」
「それとこれとは……」
わたしは、慣れない例え話をして失敗した。つかみどころのない人は苦手だ。そして、疲れた。
「一期一会が大切なら、僕とのことも考えてください」
「あなたは、ずうずうしいのか、度胸があるのか。見た目はか弱そうなのに。わたしにも都合があるからね。強引過ぎるんじゃない。わたしに付き合っている人がいるかどうかも聞かないで」
「日曜日にひとりなんで、彼氏はいないものだと思ってました」
「ずいぶん単純に考えるのね」
わたしは、複雑な心境だった。勝手に決め付けられて、湧き起こる反発する気持ちと、付き合っている人の気配を感じさせないわたしの何かが拮抗している心理状態。そんな中途半端な感情が続いた。
「住所だけでもダメですか」
「わたしは身持ちが固いの。わかってちょうだい」
ほんとうは強引に断りたかった。でも、こういうタイプは何をするのか予想がつかないから、やんわりと幕を引きたかった。
「僕のこと嫌いなんですね」
「そんなに自分を追いつめないでよ。学生さんでしょ。いろんな人とめぐり会う機会がこれからたくさんあるわよ。わたしと出会ったこともそのひとつ。まだ決め付けない方がいいわよ」
わたしは、席を立って、レジで代金を払った。振り返ると、男性は席に座ったままだが、少し微笑んでいるように見えた。よかった。あなたは、まだまだこれからよ……心の中でつぶやいて、お店を出た。そして、駅へ向かう途中のデパートで食材を買って、渋谷を後にした。
家に着く頃には陽が暮れていた。ドアを開け、食材をテーブルに置いて、ソファに腰を預けた。寄りかかって、天井を見ながら、一息ついた。今日は面白い一日だった。目的があったわけじゃなく、ただ歩いていただけなのに、少しは意味があったような時間だった。まあ、こんな日もいいかなと感じていたわたしだった。そもそも、かおりの電話で始まったことだ。ふと、電話を見ると誰かから留守電にメッセージが入っていた。上野さんかな。不安な気持ちで、再生してみると征治さんからだった。きのうのお礼の電話だった。シンプルな言葉だったけれど、うれしかった。束縛されない、こういう関係もいいかなって、思った瞬間だった。
「あさり、きのうどこに行っていたの。電話をかけ続けていたんだけどつながらなくて、朝早いけどごめんね」
「えっ。あー」
わたしは半分眠っていた。ふと、時計を見ると五時だ。
「たいへんなのよ。今日、商社マンとデートなんだけど、上野さんが今日も会いたいって言ってきたの。きのうはデートしたのよ。今日は、用事があるって言ったんだけど、いつもと違ってしつこいの。だから、あさり、アリバイづくりに協力してよ」
かおりはちょっといらだった様子だった。
「あー。えっ。かおり、だから言ったじゃない。つじつまが合わなくなるって」
わたしは、少しずつ目が覚めてきた。
「今は、それどころじゃないから。とにかくお願い」
「もう。上野さん、きっと気づき始めているのよ」
「そのことはあとで考えるから、とにかくお願い」
「どうすればいいの」
わたしは、気が進まなかった。でも、もう少し眠りたかったので、そのように返答した。
「あさりも今日どこかへ出かけてよ。それか、電話が鳴っても出ないでね。電話に出たら、あさりが家にいることがばれちゃうからね」
「それって、拘束状態じゃない」
「それより、かおりの携帯にかかってくるでしょ」
「わたしの携帯は切っておくから大丈夫」
「だから、お願い。今度、おごるから」
「とりあえず、わかった。でも、どう対処するかはわたしに決めさせて」
電話を切った。わたしは、完全に目が覚めてしまった。頭が少しずつ回転し始め、かおりの頼みを受けてしまったことを後悔した。泥沼にはまっていきそうで、気が重い。きのうは楽しい一日だった。今日はねー……。もやもやした気持ちを振り払いたかったので、ベッドから飛び起きた。空を見たら、晴れそうだった。
「出かけよう」
自分に向けて、そう言った。
着替えて、顔を洗って、カーテンを開けた。休日にこんなに早く起きることはめったにない。旅行に行くときぐらいだ。窓を開け、外を見た。道路に車がない。平日だったら、車が数珠つなぎで、排気ガスも途切れないのに、今日は空気が澄んでいるような錯覚に陥った。空気を意識的に吸い込んだ。いや、錯覚じゃない。普段とは違う味がする。早起きして、得した気分になった。そこには、うれしい自分がいた。
音が少ない日曜日の朝は、わたしを落ち着かせてくれる。テーブルの上にあった雑誌を手に取った。定期的に雑誌は買うようにしている。一冊はファッション雑誌、もう一冊は住まいの雑誌。ファッションについては、仕事柄、最新の情報をキャッチするために半分はパブリックな気持ちで買っている。個人的に流行に興味はあるけれど、流行のすべてを身につけようとは思わないから、プライベートな気持ちは半分だけ。住まいについては、結婚している友だちの家に遊びに行ったときに興味を持った。一戸建やマンションに住んでいて、内装やインテリアに凝っている人たちが何人かいる。そのこだわりに憧れるものがあって、わたしだったらこうしようと夢がふくらむ対象になっているから、その参考資料として買っているのだ。ただ、仕事のある平日は、ゆっくり読むための時間がなかなかとれない。休日は、雑誌がゆっくり読める、わたしを取り戻すための時間だ。
ファッション雑誌に目をやると、表紙の渋谷特集の文字が飛び込んできた。渋谷……最近は行っていない。学生時代は、渋谷とか原宿、たまに銀座かな。渋谷は、わたしより若い世代の街だと思っているから、意識の枠から外していた。雑誌の表紙は、定番になっているモデルが笑っている写真。笑顔に渋谷。なんとなく決めた。今日は渋谷にしよう。そう思うと時間がもったいないので、朝食を簡単につくって、出かける準備をするために、気持ちに弾みをつけた。
ひと通りの準備を終えて、玄関ドアに鍵をかける頃には、かおりに朝早く起こされたもやもや感はすっかり消え、休日モードのわたしに戻っていた。最寄り駅から地下鉄に乗った。それなりの数の人たちが乗っていて、座れなかったので、戸袋に寄りかかった。車内広告を見た。車内広告を見て思うことがある。字が小さい広告が多いこと。相当近づかないとわからないものがあるし、視力の弱い人たちは読めないだろう。そのうえ、広告紙を挟んで留める金具に隠れてしまって読めないものもある。読みたいと思っても読めないし、広告主にとってもアピールする内容が伝わらないだろう。紙面のレイアウトやデザインが優先になっているからかもしれない。隠れている文字を当てる国語のクイズじゃないんだから、工夫が欲しい。けっこう、見てるんだから。
地下鉄に乗っている人たちに押し出されて、渋谷駅に着いた。やはり人波がすごい。波にまかせて、そのまま流されてしまった方が楽かもしれない。わたしは、特に目的としている場所もなかったので、波に乗って街に出た。まわりも見てもわたしより若い人たちが多い。高校生、中学生、中には小学校の中高学年のようなグループもいた。どこにでもいるような人たちともいえるけれど、ここは密度が濃そうだ。駅前から坂を登り、少し行くと間口の狭いたくさんのビルがぎっしり建ち並んでいた。駅前の現代的な建物に比べて、古いつくりのビルたちだ。これらが、征治さんが言うとこの雑居ビルなのかな。歩きながらビルに目をやると、どのビルもお店や会社が入っている。ほとんど空きがない。中には歩道の上まで、PR看板が陣取っている。視線を上げた、どこかで見たような、聞いたような文字列が視界に入った。
『ネクステージ』。ネクステージ? わたしの頭の中で、その文字列が分析された。五秒、十秒、そうだ! 『ネクステージ』だ! かおりが言っていた『ネクステージ』だ! ここかあ、と思いながら足を止めた。わたしは、看板を見ながら、かおりの顔を思い浮かべていると、背中をなでるようなやわらかい風が吹いたかと思うと、耳元に人の気配を感じた。振り返ると、五十歳くらいの女性がニコニコと微笑んでいた。
「ちょっと、いらっしゃい」
その女性が、さらに微笑みながら言った。
「いえ。なんでもないんです」
わたしは、瞬間的にネクステージのスタッフだと感じ、関わりたくなかったので、否定的に反応した。
「いいのよ。そんなに深く考えないで。ちょっと、おばさんの話しを聞いてよ」
その女性は、柔和な感じを崩さないまま言った。
「いえ。わたしはそんなつもりで……」
わたしは、その女性の仏様みたいなやわらかな表情を見て、強く断る気持ちが萎え始めていた。
「あなたが抱いている気持ち、わたしはわかっているから、ちょっと来てよ」
「えっ」
わたしは、ネクステージに興味があるわけではないけれど、その女性の不思議な存在感を無視できなくなり、気がつくと心が反応していた。その女性の背中に誘導されながら、奥にあるエレベーターの入口に向かった。十五秒くらいして扉が開き、ふたりは乗った。
「渋谷にはよくいらっしゃるの」
その女性が、口を開いた。
「学生時代は来ていましたが、今はあんまり」
「そう」
エレベーターは七階で止まった。扉が開き、正面にネクステージのプレートが見えた。その女性は、わたしを招くようにドアを開けた。薄いピンク系の壁紙が目に飛び込んだ。ピンクのもつやわらかな雰囲気が部屋全体に広がって、あたたかさと安心感を与えてくれた。業務内容よりも事務所のつくりに興味を持った。かおりが言っていたように、銀行のカウンターブースの雰囲気だ。三つのカウンターがあった。三つとも埋まっていた。かおりが来たときも、すべて埋まっていたようなことを言っていたかな。
「ちょっと、待ってね」
やわらかな表情を保ったまま、女性が言った。
なんで、ついてきたのだろうという気持ちと、妙にやわらかいその表情に身を委ねている安心感とが入り混じって、不思議な感覚で時の経つのを待っていた。五分くらいして、カウンターのひとつが空いた。真ん中のカウンターに座っていた二十代前半の女性が立ち上がって、帰ろうとしていた。出口に向かうため、わたしの方に歩いてきたが、その表情は明るかった。安心感を与えられたような明るさだった。しばらくして、わたしは真ん中のカウンターに案内された。もといたスタッフに代わって、わたしをここまで誘導してきた女性が担当者として目の前に座った。
「こんにちは」
女性スタッフがにっこり微笑んだ。
「どうも」
わたしは、少し不安になった。
「わたしたちの看板に目を留めてくれてありがとう。心配しないでね。いかがわしい会社じゃないから」
「はい」
「独身ですね。結婚には興味を持っていらっしゃるんでしょ」
「いえ。まだそこまでは」
「いいのよ。すぐでなくても。ちょっとでも興味を持った瞬間から、始まっているのよ」
「始まっている?」
「そうなの。結婚という文字や言葉に少しでも反応したときから、結婚について意識し始めたということなのよ。結婚したいとか、したくないとかは、その次の意識のパターンなのよ。だから、あなたが看板に目を留めたことは、人として、女性として自然なことなの」
「ええ」
わたしは、半分納得して、半分理解できなかった。というよりも、意識が追いついていなかった。
「お勤めですか」
「はい」
「お友だちの中で、結婚している方はいらっしゃる?」
「はい」
「そうですか。まわりの人たちがみなさん独身であるなら、意識しなかったことが、身近な誰かが結婚して、生活パターンが変化する様子を見たときから、気持ちが変化する人たちが多いのよ。特に女性の場合はね。憧れとか理想とか、ときには嫉妬という形で芽生えるの。結婚したくない人でも、避けては通れない気持ちの変化みたいなものなの」
「はー」
少し理解できたけれども、認めたくない気持ちが三割ほど残った。
「あなたの気持ちの中で整理がつかないのは当然よ。人から言われて、結婚ということについて今すぐ真剣に考えなければならない問題でもないし、そういう気持ちがはっきり出てくるまで待てばいいという人もいることは確か。でも、あなたのように気づき始めている人にとっては、いい機会なの。チャンスでもあるの。今抱いている気持ちに無理やりフタを閉めてしまうと、歪んだ形で表われてくることもあるから。例えば、嫉妬とかね。とにかく自分に正直になることが、自分を大切にすることだからね」
「ここは、結婚相談所ですよね」
「まあ、案内所に近いわね。旅行したときに立ち寄る観光案内所みたいなものかな。旅先で聞きたいことがあったら、誰でも気軽に立ち寄るでしょ。そういうようなところだから安心してちょうだい」
「えー」
わたしは、説明内容にちょっと違和感があったけれど、女性スタッフが漂わせるやわらかな空気と、かおりが入会した動機を無視できなかったので、席を立とうとは思わなかった。
「大丈夫よ。誰もが抱いている気持ちを再確認するだけのことだから、安心してね。それでは、ちょっといいかしら。あなた、ぱっと見たところ、華美に飾る人じゃないわね。化粧もナチュラルであって、それが似合うのよ。自然体の中に気品があるのよね」
「そうですか」
かおりが言っていたように、いきなり本題には入らない。いろいろなタイプの人が来るから、百戦錬磨なのだろう。人を嫌な気分にさせない。
「好きなタイプでも嫌いなタイプでもいいから、こういう人がいいとか嫌だとか、明確に思うことってあるかしら」
「自己中心的な人は嫌ですね。思いやりのない人も。好きなタイプはこれといって、はっきりしたものはありません。気が合えばいいという感じです」
なんか、わたし、誘導尋問にはまっているのかなと思いつつ、答えていた。
「お歳は、いくつ」
「二十八です」
「今が旬ね。でも、まだまだこれからよ。輝いているときだから、大事にしなくちゃ。あといくつかお聞きしていいかしら」
「ええ」
そのあと、わたしはいくつかの質問に答えた。自分の簡単なプロフィール、趣味、ライフスタイル、相手の希望条件など。そして、女性スタッフは、相談システムの概要をひと通り説明してくれた。
「本日はお疲れさまでした。あなたのことがわかって、わたしもうれしいです。お役に立てることがあるかと思います。あまり肩に力を入れずに頑張っていきましょう。わたしが力になりますから、安心してください」
「はい」
最初から最後まで、相手のペースで押し切られたような感じだった。強い力で押し切られたというよりも、やわらかなじゅうたんの上で、背中を押されながら歩かされた感じだ。エレベーターを降りて、渋谷の街に立ったとき、足もとに浮遊感が漂った。時計を見ると、ここに最初に立ったときから一時間経っていた。あっという間の時間だったが、どっと疲れた。少し休みたい気分だったので、歩きながら喫茶店を探した。
五分くらい歩いて、間口はそれほどでもないが、その割に窓の大きな店を見つけた。ドアを開けると、ダークブラウンの色が効いたシックな雰囲気を漂わせていた。窓側の席が空いていたので、そこに座った。コーヒーを注文し、背もたれに寄りかかり、窓の外を見た。ネクステージに行ったことを少し後悔していた。なんで行ったんだろう。看板の前で立ち止まらなければよかった。女性に声をかけられても無視すればよかった。結婚する気もないし、誰かを紹介されても困るのはわたし。それに、彼女や彼氏のいない人が行くところだ。彼女や彼氏……。ふと、わたしはどうなんだろうと考えていた。付き合っているといえるのかな……今のわたし。どっちなんだろう。それは、わたしが決めること? わたしと誰かが決めること? 今の心境とネクステージに行ったことが、わたしの中でうまく融合できずに葛藤していた。
頭の中がリセットできないまま、視線をテーブルに落とすと、耳元に言葉が入ってきた。横を見ると、OLらしい女性がふたり、話し込んでいた。
「何年付き合ってたんだっけ」
「二年弱」
「二年弱? あっという間ね」
「いろいろ考えたけど、決めちゃった」
「ピッタリの人がいて、よかったね」
「最初は好きなタイプじゃなかったんだけど、ズルズルきちゃって、突然プロポーズされちゃったの。彼、転勤が決まったみたいで、押し切られた感じかな。どうしてもわたしを連れて行くって。わたしのこと、ほんとうはどう思っているのかわからなくて悩んだこともあった。彼がわたしのことほんとうに好きなのか、転勤が決まったから焦ったのかわからないまま進んじゃった」
「えっ。じゃあ、後悔しているの」
「ううん。後悔じゃなくて、これでいいのかなって。いっしょになれば、うまくやっていけそうだから、ベストじゃないけどベターな選択」
「そう」
「かなはどうなのよ」
「付き合っている人はいるけどね。ゆかより長いよ。三年くらい。お互い、付いたり離れたりの感じよ」
「プロポーズの雰囲気はないの?」
「さあ」
「あれば、どうするの。応じるの」
「わからない。待っているのとは違うのよ。わたしからどうしてもこの人だっていう気持ちもないしね。わたし、彼氏がいなかった時期があって、焦ったことがあってね。誰でもいいから紹介してよって言いまくっていた。それで紹介されたのが今の彼氏なのよ」
「そう」
「緊急措置的な彼氏かも」
「でも、続いてるってことは、合っているんじゃない」
「そうかもしれない。でもさあ、もっといい人がいるかもしれないじゃない。そう思うとさあ、まだまだこれからでしょ」
「かなは贅沢かもね。あはは」
ふたりの会話は続いていた。このふたりとわたしもどこにでもいるような女性像なのかなと、ふと考えた。ネクステージの女性スタッフが言っていたように、結婚したいとか、したくないとかは別にして、結婚については避けて通れない問題なのかなと。このふたりの会話に出てきた、焦りの気持ちと、これでいいのかなっていう気持ち。わたしにも焦りはあるかもしれない。これでいいのかなっていう気持ちはわからない。というより、その立場に立っていないから、理解できない。
わたしの中に、何かもやもやした感情が膨れ上がり、座っている自分にもどかしさを感じてきたので、席を立って街に出ることにした。店を出て、洋服でも見ようと駅方向に歩き出した。こんな気分で歩いていると、通り過ぎる風景が無機質にわたしに飛び込んでくるような威圧感になり、いっそうの孤独を誘った。駅に近づくにつれて、人波のうねりが大きくなり、街の不規則な音が一段と強くなった。
人波に身を任せていると、わたしの歩幅に合わせるかのように、か細い声がした。聞き取れなかったので、無視していると、再びか細い声。また無視していると、トーンが上がって「あのー」という声がした。気になって振り返ってみると、細身の大学生のような男性が緊張した面持ちで歩いていた。目と目が合って、わたしにも緊張感が伝染してきたので、無視して歩き出そうとすると、その男性が小走りになったので、わたしは怖くなって動けなくなってしまった。
「あのー」
か細い声が、わたしに向かった。
「なんですか。わたしに何か」
わたしは言葉を返したくなかったけれど、また追ってきそうなので、そう言った。
「怪しいものではありません。何かの勧誘でもありません」
「わたし、急いでいますので」
「待ってください」
「さようなら」
わたしは、気味が悪かったので、前を向いて走り出した。
「待ってください」
その男性は、わたしを追い抜きながら言った。
「やめてください」
逃げたい。逃げられない。そんな気持ちがそう言わせた。そして、動けなくなった。
「すみません。怖がらないでください。そんな気持ちじゃないんです。ちょっと話をしたかったんです。僕の理想形だったんで」
「わたしには関係ないことですよね」
「僕が描いていた理想なんです。ちょっと話ができませんか」
その男性は、目に力を入れながら言った。わたしは嫌だった。でも、どこまでも追ってきそうな雰囲気がその男性にはあった。
「少しだけなら」
わたしはあきらめた。少しでも話氏を聞けば開放されるだろう。そんな気持ちだった。
「ありがとうございます。近くの喫茶店でいいですか」
その男性は満面の笑みで歩き出した。わたしは、後悔の気持ちがじわじわと高まりながらも、その男性の背中に付いて行った。まわりをきょろきょろしながら歩いているところを見ると、ここにはそんなに来ていないのだろうし、ナンパにも慣れているようではなかった。とわたしは予想した。わたしたちはしばらく歩いて、喫茶に入った。そして、適当なところに座った。ふたりは向かい合う状態になった。でも、男性は視線をテーブルに落としたまま、何もしゃべらない。わたしは、何のためにここにいるのだろうと思い始めた。やっぱり、来るんじゃなかった。席を立とうと思って、わたしから声をかけた。
「あのー、用がないなら帰ります」
するとその男性が
「すみません。ちょっと待ってください。緊張してるんです。タイプなんです」
「それだけですか。特に用がないなら帰りますけど」
わたしは、ここにいる時間が無駄に思えてきて、そう言った。
「いやっ。えーと。じつは、結婚前提に付き合ってくれませんか」
男性がそう言って、わたしは驚いた。
「なんでそういうことを言うんですか。初めて会ってから、時間も経ってもいないのに、そんなこと言われても困ります」
「唐突ですが、僕はそういう気持ちなんです。会った瞬間から。だから、行かないでください」
「あなたのことも何も知らないし、わたしの事情も知らないのに、よくそういうこと言えますね」
わたしは、少々腹が立った。
「あー。あー」
男性は泣きそうになった。
「落ち着いてください」
なんでわたしがこんな目に合わなければならないのと思いながらも、ここで泣かれたら、いやだったので、わたしは口調をやわらげた。
「すみません。慣れていないのです。歩いていて、理想の人が目の前に現われたので、どうしても話氏をしてみたかったのです」
「あなたは学生さん」
「そうです。春に東京に来たばかりで、人も街もよくわかりません」
男性はようやく落ち着いてきたようだった。
「わたしも上京組だから、あなたの気持ちも少しはわかるわ。見かけは、おとなしそうね。女性ともあまり話したことはないでしょう。それなのにナンパする度胸はあるわけ」
「あなたを見たときから胸がドキドキでした。度胸があるわけではありません。でも、どうしても手に入れたかったというか……」
「手に入れたい? わたしものじゃないんだから。それに、学生さんでしょ。まだまだこれからなのに、そう簡単に結婚という文字を使っちゃダメよ。これからたくさんの人とめぐりあうかもしれないじゃない。今はそういう気持ちでも、人は気が変わるから、慎重に考えないと。まあ、慎重に考えていくのは難しいけどね」
わたしは、説教のつもりで言ったわけじゃなかった。
「そうでしょうか。まだ、甘いのでしょうか」
「甘いというよりも、まだこれからいろんなことに出会うでしょう。人とか、街とかもそう。今がすべてじゃないっていうことよ。わたしが言いたいのは」
「友だちとしてもダメですか」
「学校にも同世代の人たちがたくさんいるでしょ。きっと見つかるわよ。その方が、話が合うわよ」
しばらく、沈黙が続いた。言い過ぎたかなと思いつつも、わたしは友だちになるのも気が進まなかった。
「あのう、僕、チャットでしかあまり話せないんです」
「チャット? パソコン上での会話ね」
「そうです」
「チャットでしか話せない? チャットで話すことは悪いことじゃないわよね」
「チャットでのやりとりはできるのです。キーを打つスピードも自信があります。でも、実際に会って人と話すのが苦手です」
「パソコンの文字だとニュアンスが伝わらないしね。しばらく、チャットをやめちゃったら」
わたしは、軽く言ったつもりだった。
「僕にとって大切なんです。今の僕にとって」
男性の口調は少し強くなった。
「ごめんね。否定するつもりじゃないのよ。ちょっとの間、やめてみたらと思って、そう言ったのよ。」
わたしは、こういうタイプの人の扱いには慣れていないので、言葉を選ぶのに苦労した。
「やめる生活は考えられないです」
「わたしは、人と直接話すのが基本なの。一期一会というには大げさかもしれないけれど、会って話している瞬間を大切にしたいのよ。次はいつ話せるかわからないし、話せないまま時間が過ぎていくかもしれないでしょ。あなたと話している今もそうよ。たまたま会って話している。次はもうないでしょう」
「えっ。もうなしですか」
男性はキッとにらみ返してきた。その瞬間、わたしはまずいと思った。こういうタイプは予想がつかない。言い方に気をつけなくちゃ。
「人から聞いた話でこういうのがあるの。クローンという言葉があるじゃない。羊とか、人間とか。DNAからクローンを生成して、生物のコピーをつくっていこうという試み。実際につくられた例もあるわよね。ただ、遺伝子に組み込まれた本能部分は少ししかないらしくて、学習や知能を中心に行動している高等動物については、実際にコピーできるのは、外形と行動パターンの一部なんですって。わたしは、それを聞いてから、人との出会いを大切にしようと思ったの。同じ人間はありえない。一期一会を大切にしようとね」
わたしは、征治さんから聞いたことを思い出した。
「はい。それだったら、僕との付き合いも考えてくれませんか」
「それとこれとは……」
わたしは、慣れない例え話をして失敗した。つかみどころのない人は苦手だ。そして、疲れた。
「一期一会が大切なら、僕とのことも考えてください」
「あなたは、ずうずうしいのか、度胸があるのか。見た目はか弱そうなのに。わたしにも都合があるからね。強引過ぎるんじゃない。わたしに付き合っている人がいるかどうかも聞かないで」
「日曜日にひとりなんで、彼氏はいないものだと思ってました」
「ずいぶん単純に考えるのね」
わたしは、複雑な心境だった。勝手に決め付けられて、湧き起こる反発する気持ちと、付き合っている人の気配を感じさせないわたしの何かが拮抗している心理状態。そんな中途半端な感情が続いた。
「住所だけでもダメですか」
「わたしは身持ちが固いの。わかってちょうだい」
ほんとうは強引に断りたかった。でも、こういうタイプは何をするのか予想がつかないから、やんわりと幕を引きたかった。
「僕のこと嫌いなんですね」
「そんなに自分を追いつめないでよ。学生さんでしょ。いろんな人とめぐり会う機会がこれからたくさんあるわよ。わたしと出会ったこともそのひとつ。まだ決め付けない方がいいわよ」
わたしは、席を立って、レジで代金を払った。振り返ると、男性は席に座ったままだが、少し微笑んでいるように見えた。よかった。あなたは、まだまだこれからよ……心の中でつぶやいて、お店を出た。そして、駅へ向かう途中のデパートで食材を買って、渋谷を後にした。
家に着く頃には陽が暮れていた。ドアを開け、食材をテーブルに置いて、ソファに腰を預けた。寄りかかって、天井を見ながら、一息ついた。今日は面白い一日だった。目的があったわけじゃなく、ただ歩いていただけなのに、少しは意味があったような時間だった。まあ、こんな日もいいかなと感じていたわたしだった。そもそも、かおりの電話で始まったことだ。ふと、電話を見ると誰かから留守電にメッセージが入っていた。上野さんかな。不安な気持ちで、再生してみると征治さんからだった。きのうのお礼の電話だった。シンプルな言葉だったけれど、うれしかった。束縛されない、こういう関係もいいかなって、思った瞬間だった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説


『脆弱能力巫女の古代女王「卑弥呼たん」門真市ニコニコ商店街に転生す!』
M‐赤井翼
現代文学
赤井です。
今回は、いつもの「ニコニコ商店街」と「こども食堂」を舞台に「邪馬台国」から「女王 卑弥呼たん」がなつ&陽菜の「こっくりさん」で召喚!
令和の世では「卑弥呼たんの特殊の能力」の「予言」も「天気予知」も「雨乞い能力」もスマホや水道の前には「過去の遺物」(´・ω・`)ショボーン。
こども食堂で「自信」を持って提供した「卑弥呼たん」にとっての最高のご馳走「塩むすび」も子供達からは「不評」…( ノД`)シクシク…。
でも、「女王 卑弥呼たん」はくじけない!
「元女王」としてのプライドをもって現代っ子に果敢にチャレンジ!
いつぞや、みんなの人気者に!
そんな「卑弥呼たん」になじんだ、こども食堂の人気者「陽葵ちゃん」に迫る魔の手…。
「陽葵ちゃん」が危機に陥った時、「古代女王 卑弥呼たん」に「怒りの電流」が流れる!
歴史マニア「赤井翼」の思う、「邪馬台国」と「卑弥呼」を思う存分に書かせてもらった「魏志倭人伝」、「古事記」、「日本書記」に「ごめんなさい!」の一作!
「歴史歪曲」と言わずに、「諸説あり」の「ひとつ」と思って「ゆるーく」読んでやってください!
もちろん最後は「ハッピーエンド」はお約束!
では、全11チャプターの「短期集中連載」ですのでよーろーひーこー!
(⋈◍>◡<◍)。✧♡


サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

遅れてきた先生
kitamitio
現代文学
中学校の卒業が義務教育を終えるということにはどんな意味があるのだろう。
大学を卒業したが教員採用試験に合格できないまま、何年もの間臨時採用教師として中学校に勤務する北田道生。「正規」の先生たち以上にいろんな学校のいろんな先生達や、いろんな生徒達に接することで見えてきた「中学校のあるべき姿」に思いを深めていく主人公の生き方を描いています。


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
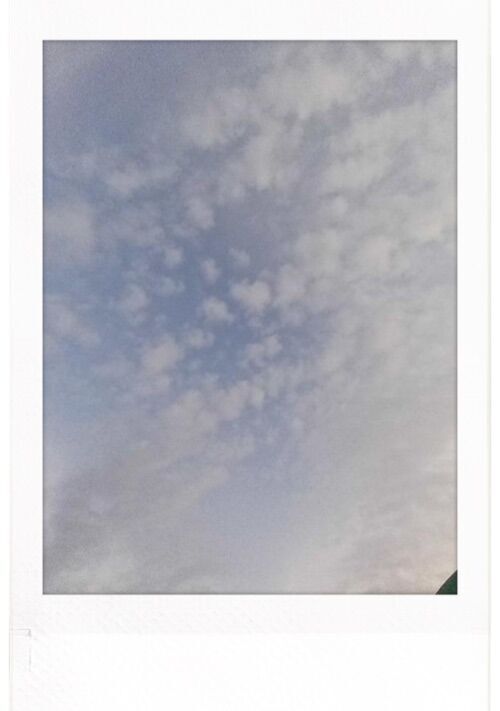
ファンファーレ!
ほしのことば
青春
♡完結まで毎日投稿♡
高校2年生の初夏、ユキは余命1年だと申告された。思えば、今まで「なんとなく」で生きてきた人生。延命治療も勧められたが、ユキは治療はせず、残りの人生を全力で生きることを決意した。
友情・恋愛・行事・学業…。
今まで適当にこなしてきただけの毎日を全力で過ごすことで、ユキの「生」に関する気持ちは段々と動いていく。
主人公のユキの心情を軸に、ユキが全力で生きることで起きる周りの心情の変化も描く。
誰もが感じたことのある青春時代の悩みや感動が、きっとあなたの心に寄り添う作品。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















