10 / 32
第3章 ポワティエの戦い
開戦
しおりを挟む
それから三日後、エドワードは再び軍を率いてボルドーを出立し、パリを横目にオルレアンを通過、ロワール川流域に沿って進んだ。キャロラインはボルドーにとどまり、ニールはエドワードの軍の最後方を進んでいる。
エドワードはいつものように、黒い甲冑を着込んでいる。特別製の黒い鎧は、日の光を浴びて、鈍い光沢を放っていた。その後ろを、五千人にも上る兵士たちが突き従う。
「報告します! ジャン二世は昨日早朝にパリを出立、こちらへ向かっている模様です」
エドワードがその伝令を受けたのは、一三五六年九月十三日のことであった。ニールの指揮の下、スパイをパリに潜ませてあった理由の一つは、この情報を得るためである。エドワードは直ちに、ロワール川流域から南下し、ボルドー方面に向かった。
エドワードが率いる兵は約五千。スパイの報告によれば、ジャン二世率いるフランス軍は約二万。まともに戦っては勝ち目が無いと、イングランドの兵たちの心は焦っていた。
伝令を受けてから五日が経ったが、エドワード軍は相変わらずゆっくりした行進で、急ぐ気配が無い。焦れたチャンドスは、エドワードに直接進言した。
「殿下、もう少し急ぎませんと、フランス軍に追いつかれますぞ」
「案ずるな、チャンドス。今回は、すでに父上に援軍を頼んである」
もともと一連の略奪は、ジャン二世をパリから引きずり出すのが目的だった。引きずり出しても勝てないというのでは意味が無い。
エドワードはパリとボルドーとの中間地点でジャン二世の軍を待ち受ける。ジャン二世がパリから南下し、エドワードの軍と戦闘に入ったところで、北の港町カレーから上陸した国王エドワード三世の軍が背後より襲い掛かり、ジャン二世を挟み撃ちにする。そういう作戦だったのである。慌てる必要など、微塵もなかった。
エドワードの軍は作戦に従い、ゆっくりと南下した。血気にはやったジャン二世の軍は、この機会に憎き黒太子を殲滅せんと、エドワードの軍を猛追する。
「殿下、一大事です!」
後ろから、今度はウォリック伯が馬を飛ばしてやってくる。
エドワードは思わず苦笑した。やれやれ、どうしてこう慌て者が多いのか。今回はすべて計画通りに進んでいるというのに……。
「国王陛下の軍が、シャルル=ド=ブロワの軍と交戦状態に入りました!」
その報せに、エドワードの心臓は喉の辺りまで飛び上がった。
「なんだと!」
叫びが出たのは、報せを聞いてから三秒後のことだった。シャルル=ド=ブロワ、いわゆるブロワ伯は親フランス派で知られており、イングランドに友好的でないことは予想していたが、まさかこのようなときに足止めに来るとは。
フランスを侮りすぎていたかもしれない。もし作戦が読まれていたのであれば、カレーの近くに領土を持つブロワ伯にフランスが話を持ちかけたとしても、不思議ではなかった。
国王軍が北で足止めされているとなれば、ここへの援軍は期待できない。となれば、独軍でフランス軍と戦わねばならないことになる。エドワードの決断は早かった。
「いかん。全軍、ボルドーに戻る。急げ!」
エドワードは言うが早いか、馬の手綱をしごいた。周りの者たちが、慌ててそれに倣う。遅れれば追いつかれるが、急ぎすぎると軍の隊列が崩れる。そこを急襲されれば、ひとたまりも無い。ここが大将の難しいところであった。
それでもエドワード軍は、可能な限りの速さで、ボルドーへと進み始めた。
しかし、血気盛ん――ニールに言わせれば猪突猛進――なフランス軍は、獲物を逃がすことはなかった。もともと騎兵の割合はフランスの方が多かったこともあって、翌日の昼ごろには、フランス軍は間近にまで迫ってきた。
「殿下、無理です。フランス軍に追いつかれます」
狼に追われる子羊のように青ざめた顔で、ウォリック伯が言った。
「やむをえん、ここでジャン二世を迎え撃つ。全軍、防衛態勢に移れ」
「ここで戦うのですか?」
「うむ。父上の助けがなくとも、勝てぬ戦いではない。必ず勝つ、と言えなくなっただけのことよ」
エドワードのそのセリフは、部下を安心させるためのリップサービスではなく、彼自身そう信じ込んでのことだった。彼は戦争の計画段階においては、必ず勝てると言えるだけの用意をしてから戦いに望むことを信条としていた。しかし、計画通りに行かなかったとしても、勝てる自信がなくなるわけではないのである。むしろ、戦術家としての彼の血は、このようなときにほど沸き立ってくるものであると言えた。彼に言わせれば、「必ず勝てる戦いなどつまらない」のだから。
「今回は数的に不利ゆえ、向こうはかさにかかって攻めてくるだろう。こちらは防衛一色の構えでよい。障害物を築き、穴を掘れ」
「しかし、今からでは間に合いません! 敵はもうすぐそこまで」
「掘れるだけでいい、とにかく少しでも弓兵のために時間を稼ぐ必要があるのだ」
エドワードの理想は、クレシーのときと同じように、落とし穴を多数作り、弓兵の前に柵を設けることであった。しかし、事前に下調べしていた前回と違い、今回は急にここポワティエを戦場と決めたため、時間に余裕が無い。
最初、彼が目をつけたのは、河であった。河を背後にして戦えば、後ろから襲われる心配はないし、味方の逃亡も防げる。兵も死ぬ気で戦うだろう。
しかし、味方の逃亡を防ぐということは、いざというとき逃亡できないということである。負けた場合、全滅もありうる。戦えば必ず勝つというような騎士物語の夢想とは無縁のエドワードは、そのような態勢をとることを好まなかった。
焦るエドワードに、近づく人馬があった。グライーである。その顔には、いまだ不敵な笑みが浮かんでいた。この局面で笑えるとは、臆病者で無いのは確かなようだった。
「殿下、ずいぶんと困ってるようじゃねえか」
「グライーか、見ての通りだ。おまえにも奮戦してもらわねばならぬ、頼むぞ」
「ああ、それは任しとけ。しかし、もう少し楽に戦える方法があるぜ」
「ん? なんだ?」
「ここからほんの少し行ったところに、森林と沼地がある。森林と沼地を後背と側面に背負って戦えば、挟撃の危険がなく、防衛にはもってこいの地形だと思うが、どうだね」
グライーの言葉を聞き、エドワードの顔に喜色が躍り出た。幼い頃からフランス西部で遊びまわっていたグライーにとっては、このあたりは自分の庭みたいなものだった。
「おお、それは本当か!」
沼地や密生した森林であれば、軍としての整然とした行動はできなくとも、いざというとき散り散りになって逃げることができる。挟撃を防ぎつつ逃亡の余地を残しておくには、もってこいの地形であった。
「負けちゃ戦利品が手に入らねえからな、嘘はいわねえよ」
「よし、案内を頼む」
「ついてきな」
くるりと背を向けるグライー。それを追おうとするエドワードに、チャンドスが耳打ちした。
「殿下、あのような者の言うことを信用なされるので?」
「信用して裏切られれば、負ける。しかし信用しなければ、やはり負ける。ならば信じるしかあるまい。案ずるな、あの男の性格からして、フランスの王族どもが策を託す相手のようには思えんよ」
確かにチャンドスが疑うのも無理はない。素行面において、グライーは怪しい。エドワードに味方するようになって一年と経っていないし、土壇場で裏切られる可能性は充分にある。
しかし、土壇場で裏切るつもりならば、この戦いを土壇場にしなければいいだけのことだ。ああいう男は、こちらが勝っている限りは裏切らない。
もともとがフランスからの刺客だという可能性も、なくはない。しかし、怪しい者を刺客とするには、雇う側も度胸を決めなくてはならないのである。もしジャン二世が、グライーのような者にこの大局を任せるほどの器量人であるならば、負けてもやむをえないではないか。第一、数の面では相手が三倍以上であり、普通に戦えば負ける相手なのである。
軍勢を引き連れて、イングランド王太子エドワードとブーシュ伯グライーをそれぞれ背に乗せた二頭の軍馬が先頭を行く。やがて彼らは、グライーが言った通りの場所に着いた。
「おお、これは素晴らしい」
エドワードは思わず感嘆の声をあげた。森林や沼地は、馬が最も苦手とするところであり、ここを通っての進軍は考えづらい。エドワードは森林を背後に、左手を沼地として戦うことに決めた。
さらに都合のいいことに、背丈の低い樹木が、まるで生垣のように一列に並んでいた。自然に生えたものか誰かが手を入れたものかわからないが、これを利用しない手は無い。エドワードは、そこの樹木の後ろに本陣を置くことにした。
「右手には、今までの略奪品を荷車ごと山積みにせよ。一時的にでも突撃を防げれば、それでよい。隊列は、横線陣。ソールズベリ伯には右翼の指揮をお願いしたい。ウォリック伯は左翼に。騎士はそれぞれ下馬して、弓兵の援護を頼む」
「承知しました」
ソールズベリ伯とウォリック伯が、それぞれの陣へと向かう。彼らが去ってから、エドワードはグライーを呼び止めた。
「グライーの軍は、右翼のソールズベリ伯の陣に入ってくれ。それと……」
エドワードはグライーに、何事か作戦を授けた。それを聞くと、グライーはにやりと笑った。
「なるほど、面白いな。しかし、俺みたいな若造にそんな大役を任せちまってもいいのかい?」
「若いことは、なんら恥じることではない。人間の寿命は五十年、長く持っても八十年がいいところだ。四十になるまで活躍の機会がないとなれば、それだけ活躍できる期間が短くなる。それは優秀な人間にとっても国にとっても不幸なことだと思わんか」
彼が人間にだけあえて「優秀な」という形容詞をつけたのは、無能な人間はすぐ退場してもらいたいという隠れた悪意を表すものであった。もっとも、本当に無能な人間には、それが示す意味すらわからないであろうが。
「優秀な人間が年をとって無能になることはあっても、無能な人間が年をとってから優秀になることはないものだ」
彼は独語した。それは若さゆえの思い上がりであったろうか。しかし、年長の人間にはそれだけ多くの機会が与えられていたことを思えば、それは必ずしも彼一人の思い込みというわけではなさそうであった。
それからグライーは右翼へと去る。エドワードはふと、ニールのことを思い出した。今回、ニールはウォリック伯の陣に入っている。ニールは現状を見て、勝率はどれくらいと予言するだろうか。
「極めて厳しいでしょうね。ひいき目に見て二十パーセントといったところでしょうか」
そんなことを言うニールの顔が目に浮かぶようだった。兵力差だけで言えば、こちらが勝つ可能性はゼロ。しかし先ほどの策が当たれば、勝てなくは無い。さらに自分の指揮能力がジャン二世より勝っていれば、勝てる見込みはさらに増えるだろう。
それでも、勝率は良くて二割か。フランス軍がクレシーのときと同じように、ひたすら突撃を繰り返してくれればよいが、彼らもそこまで馬鹿ではあるまい。
それにしても、これほどまでに絶望的な状況の中で、震えるほどの昂揚感が身体の中から湧き上がってくるのはなぜだろう。今までどの戦いでも、これほどまでの興奮はなかった。はじめて、勝てるかどうかわからない戦に直面したからか。
そんなことを考えているうちに、フランス軍は視界に入る距離にまで近づいてきた。土煙を巻き上げながら、人馬が着々と近づいてくるのが見える。衝突まで、五分とかからないだろう。エドワードは固唾を呑みながら、そのときを待った。
報告によれば、フランス軍の先陣はクレルモン将軍が率いる傭兵隊五千、続いてシャルル王太子が率いる歩兵隊が四千。それに続くオルレアン公の軍勢が四千、最後にジャン二世の本隊が七千人で総勢二万という、圧倒的な兵士数であった。単純にイングランドの四倍である。
ただ、エドワードにとって不審なのは、その隊列である。横に広がる隊列なのはいいとして、それが四列並ぶというのはどういうことか。これでは、後ろの兵は遊軍となってしまう。
仮に、先陣が疲れると同時に後陣と入れ替わるための隊列だとしても、それを実際に行うには、軍団長にはもちろん、小隊長クラスにも高度な指揮能力が求められる。後退中に混乱が生じれば、敵に攻撃の隙を与えてしまうからだ。
すでに敵の四倍という兵力面での優位を確保しているフランス軍が、そのような危険を冒す必要があるのだろうか。あるいは、単にジャン二世が用兵を知らぬだけなのかもしれない。いずれにせよ、すぐにわかることだ。
接近中のフランス軍が、勢いを弱める気配を見せた。フランス軍はクレシーの教訓を生かしたか、騎兵はほとんど下馬しており、歩兵が中心となっている。こうなると騎馬のように、勢いがついて止まらないということもない。イングランドの弓兵の射程外でいったん隊列を整え、そこから整然と突撃を図る気だろう。
そうはさせじと、エドワードが事前に伝えてあった第一の指令を、左翼のウォリック伯が実行に移した。すなわち、偽装撤退である。逃走する素振りを見せて、突撃を誘う。
勢いに乗ったクレルモン将軍率いる傭兵隊は、これを好機と見て、突撃を開始した。
「矢を射よ!」
エドワードの掛け声に応じ、イングランドの誇る三千の長弓隊が、一斉にフランス軍に矢を射た。長弓から放たれた矢は、芸術的なまでにきれいな曲線を描いて、フランス軍へと吸い込まれてゆく。
エドワードはいつものように、黒い甲冑を着込んでいる。特別製の黒い鎧は、日の光を浴びて、鈍い光沢を放っていた。その後ろを、五千人にも上る兵士たちが突き従う。
「報告します! ジャン二世は昨日早朝にパリを出立、こちらへ向かっている模様です」
エドワードがその伝令を受けたのは、一三五六年九月十三日のことであった。ニールの指揮の下、スパイをパリに潜ませてあった理由の一つは、この情報を得るためである。エドワードは直ちに、ロワール川流域から南下し、ボルドー方面に向かった。
エドワードが率いる兵は約五千。スパイの報告によれば、ジャン二世率いるフランス軍は約二万。まともに戦っては勝ち目が無いと、イングランドの兵たちの心は焦っていた。
伝令を受けてから五日が経ったが、エドワード軍は相変わらずゆっくりした行進で、急ぐ気配が無い。焦れたチャンドスは、エドワードに直接進言した。
「殿下、もう少し急ぎませんと、フランス軍に追いつかれますぞ」
「案ずるな、チャンドス。今回は、すでに父上に援軍を頼んである」
もともと一連の略奪は、ジャン二世をパリから引きずり出すのが目的だった。引きずり出しても勝てないというのでは意味が無い。
エドワードはパリとボルドーとの中間地点でジャン二世の軍を待ち受ける。ジャン二世がパリから南下し、エドワードの軍と戦闘に入ったところで、北の港町カレーから上陸した国王エドワード三世の軍が背後より襲い掛かり、ジャン二世を挟み撃ちにする。そういう作戦だったのである。慌てる必要など、微塵もなかった。
エドワードの軍は作戦に従い、ゆっくりと南下した。血気にはやったジャン二世の軍は、この機会に憎き黒太子を殲滅せんと、エドワードの軍を猛追する。
「殿下、一大事です!」
後ろから、今度はウォリック伯が馬を飛ばしてやってくる。
エドワードは思わず苦笑した。やれやれ、どうしてこう慌て者が多いのか。今回はすべて計画通りに進んでいるというのに……。
「国王陛下の軍が、シャルル=ド=ブロワの軍と交戦状態に入りました!」
その報せに、エドワードの心臓は喉の辺りまで飛び上がった。
「なんだと!」
叫びが出たのは、報せを聞いてから三秒後のことだった。シャルル=ド=ブロワ、いわゆるブロワ伯は親フランス派で知られており、イングランドに友好的でないことは予想していたが、まさかこのようなときに足止めに来るとは。
フランスを侮りすぎていたかもしれない。もし作戦が読まれていたのであれば、カレーの近くに領土を持つブロワ伯にフランスが話を持ちかけたとしても、不思議ではなかった。
国王軍が北で足止めされているとなれば、ここへの援軍は期待できない。となれば、独軍でフランス軍と戦わねばならないことになる。エドワードの決断は早かった。
「いかん。全軍、ボルドーに戻る。急げ!」
エドワードは言うが早いか、馬の手綱をしごいた。周りの者たちが、慌ててそれに倣う。遅れれば追いつかれるが、急ぎすぎると軍の隊列が崩れる。そこを急襲されれば、ひとたまりも無い。ここが大将の難しいところであった。
それでもエドワード軍は、可能な限りの速さで、ボルドーへと進み始めた。
しかし、血気盛ん――ニールに言わせれば猪突猛進――なフランス軍は、獲物を逃がすことはなかった。もともと騎兵の割合はフランスの方が多かったこともあって、翌日の昼ごろには、フランス軍は間近にまで迫ってきた。
「殿下、無理です。フランス軍に追いつかれます」
狼に追われる子羊のように青ざめた顔で、ウォリック伯が言った。
「やむをえん、ここでジャン二世を迎え撃つ。全軍、防衛態勢に移れ」
「ここで戦うのですか?」
「うむ。父上の助けがなくとも、勝てぬ戦いではない。必ず勝つ、と言えなくなっただけのことよ」
エドワードのそのセリフは、部下を安心させるためのリップサービスではなく、彼自身そう信じ込んでのことだった。彼は戦争の計画段階においては、必ず勝てると言えるだけの用意をしてから戦いに望むことを信条としていた。しかし、計画通りに行かなかったとしても、勝てる自信がなくなるわけではないのである。むしろ、戦術家としての彼の血は、このようなときにほど沸き立ってくるものであると言えた。彼に言わせれば、「必ず勝てる戦いなどつまらない」のだから。
「今回は数的に不利ゆえ、向こうはかさにかかって攻めてくるだろう。こちらは防衛一色の構えでよい。障害物を築き、穴を掘れ」
「しかし、今からでは間に合いません! 敵はもうすぐそこまで」
「掘れるだけでいい、とにかく少しでも弓兵のために時間を稼ぐ必要があるのだ」
エドワードの理想は、クレシーのときと同じように、落とし穴を多数作り、弓兵の前に柵を設けることであった。しかし、事前に下調べしていた前回と違い、今回は急にここポワティエを戦場と決めたため、時間に余裕が無い。
最初、彼が目をつけたのは、河であった。河を背後にして戦えば、後ろから襲われる心配はないし、味方の逃亡も防げる。兵も死ぬ気で戦うだろう。
しかし、味方の逃亡を防ぐということは、いざというとき逃亡できないということである。負けた場合、全滅もありうる。戦えば必ず勝つというような騎士物語の夢想とは無縁のエドワードは、そのような態勢をとることを好まなかった。
焦るエドワードに、近づく人馬があった。グライーである。その顔には、いまだ不敵な笑みが浮かんでいた。この局面で笑えるとは、臆病者で無いのは確かなようだった。
「殿下、ずいぶんと困ってるようじゃねえか」
「グライーか、見ての通りだ。おまえにも奮戦してもらわねばならぬ、頼むぞ」
「ああ、それは任しとけ。しかし、もう少し楽に戦える方法があるぜ」
「ん? なんだ?」
「ここからほんの少し行ったところに、森林と沼地がある。森林と沼地を後背と側面に背負って戦えば、挟撃の危険がなく、防衛にはもってこいの地形だと思うが、どうだね」
グライーの言葉を聞き、エドワードの顔に喜色が躍り出た。幼い頃からフランス西部で遊びまわっていたグライーにとっては、このあたりは自分の庭みたいなものだった。
「おお、それは本当か!」
沼地や密生した森林であれば、軍としての整然とした行動はできなくとも、いざというとき散り散りになって逃げることができる。挟撃を防ぎつつ逃亡の余地を残しておくには、もってこいの地形であった。
「負けちゃ戦利品が手に入らねえからな、嘘はいわねえよ」
「よし、案内を頼む」
「ついてきな」
くるりと背を向けるグライー。それを追おうとするエドワードに、チャンドスが耳打ちした。
「殿下、あのような者の言うことを信用なされるので?」
「信用して裏切られれば、負ける。しかし信用しなければ、やはり負ける。ならば信じるしかあるまい。案ずるな、あの男の性格からして、フランスの王族どもが策を託す相手のようには思えんよ」
確かにチャンドスが疑うのも無理はない。素行面において、グライーは怪しい。エドワードに味方するようになって一年と経っていないし、土壇場で裏切られる可能性は充分にある。
しかし、土壇場で裏切るつもりならば、この戦いを土壇場にしなければいいだけのことだ。ああいう男は、こちらが勝っている限りは裏切らない。
もともとがフランスからの刺客だという可能性も、なくはない。しかし、怪しい者を刺客とするには、雇う側も度胸を決めなくてはならないのである。もしジャン二世が、グライーのような者にこの大局を任せるほどの器量人であるならば、負けてもやむをえないではないか。第一、数の面では相手が三倍以上であり、普通に戦えば負ける相手なのである。
軍勢を引き連れて、イングランド王太子エドワードとブーシュ伯グライーをそれぞれ背に乗せた二頭の軍馬が先頭を行く。やがて彼らは、グライーが言った通りの場所に着いた。
「おお、これは素晴らしい」
エドワードは思わず感嘆の声をあげた。森林や沼地は、馬が最も苦手とするところであり、ここを通っての進軍は考えづらい。エドワードは森林を背後に、左手を沼地として戦うことに決めた。
さらに都合のいいことに、背丈の低い樹木が、まるで生垣のように一列に並んでいた。自然に生えたものか誰かが手を入れたものかわからないが、これを利用しない手は無い。エドワードは、そこの樹木の後ろに本陣を置くことにした。
「右手には、今までの略奪品を荷車ごと山積みにせよ。一時的にでも突撃を防げれば、それでよい。隊列は、横線陣。ソールズベリ伯には右翼の指揮をお願いしたい。ウォリック伯は左翼に。騎士はそれぞれ下馬して、弓兵の援護を頼む」
「承知しました」
ソールズベリ伯とウォリック伯が、それぞれの陣へと向かう。彼らが去ってから、エドワードはグライーを呼び止めた。
「グライーの軍は、右翼のソールズベリ伯の陣に入ってくれ。それと……」
エドワードはグライーに、何事か作戦を授けた。それを聞くと、グライーはにやりと笑った。
「なるほど、面白いな。しかし、俺みたいな若造にそんな大役を任せちまってもいいのかい?」
「若いことは、なんら恥じることではない。人間の寿命は五十年、長く持っても八十年がいいところだ。四十になるまで活躍の機会がないとなれば、それだけ活躍できる期間が短くなる。それは優秀な人間にとっても国にとっても不幸なことだと思わんか」
彼が人間にだけあえて「優秀な」という形容詞をつけたのは、無能な人間はすぐ退場してもらいたいという隠れた悪意を表すものであった。もっとも、本当に無能な人間には、それが示す意味すらわからないであろうが。
「優秀な人間が年をとって無能になることはあっても、無能な人間が年をとってから優秀になることはないものだ」
彼は独語した。それは若さゆえの思い上がりであったろうか。しかし、年長の人間にはそれだけ多くの機会が与えられていたことを思えば、それは必ずしも彼一人の思い込みというわけではなさそうであった。
それからグライーは右翼へと去る。エドワードはふと、ニールのことを思い出した。今回、ニールはウォリック伯の陣に入っている。ニールは現状を見て、勝率はどれくらいと予言するだろうか。
「極めて厳しいでしょうね。ひいき目に見て二十パーセントといったところでしょうか」
そんなことを言うニールの顔が目に浮かぶようだった。兵力差だけで言えば、こちらが勝つ可能性はゼロ。しかし先ほどの策が当たれば、勝てなくは無い。さらに自分の指揮能力がジャン二世より勝っていれば、勝てる見込みはさらに増えるだろう。
それでも、勝率は良くて二割か。フランス軍がクレシーのときと同じように、ひたすら突撃を繰り返してくれればよいが、彼らもそこまで馬鹿ではあるまい。
それにしても、これほどまでに絶望的な状況の中で、震えるほどの昂揚感が身体の中から湧き上がってくるのはなぜだろう。今までどの戦いでも、これほどまでの興奮はなかった。はじめて、勝てるかどうかわからない戦に直面したからか。
そんなことを考えているうちに、フランス軍は視界に入る距離にまで近づいてきた。土煙を巻き上げながら、人馬が着々と近づいてくるのが見える。衝突まで、五分とかからないだろう。エドワードは固唾を呑みながら、そのときを待った。
報告によれば、フランス軍の先陣はクレルモン将軍が率いる傭兵隊五千、続いてシャルル王太子が率いる歩兵隊が四千。それに続くオルレアン公の軍勢が四千、最後にジャン二世の本隊が七千人で総勢二万という、圧倒的な兵士数であった。単純にイングランドの四倍である。
ただ、エドワードにとって不審なのは、その隊列である。横に広がる隊列なのはいいとして、それが四列並ぶというのはどういうことか。これでは、後ろの兵は遊軍となってしまう。
仮に、先陣が疲れると同時に後陣と入れ替わるための隊列だとしても、それを実際に行うには、軍団長にはもちろん、小隊長クラスにも高度な指揮能力が求められる。後退中に混乱が生じれば、敵に攻撃の隙を与えてしまうからだ。
すでに敵の四倍という兵力面での優位を確保しているフランス軍が、そのような危険を冒す必要があるのだろうか。あるいは、単にジャン二世が用兵を知らぬだけなのかもしれない。いずれにせよ、すぐにわかることだ。
接近中のフランス軍が、勢いを弱める気配を見せた。フランス軍はクレシーの教訓を生かしたか、騎兵はほとんど下馬しており、歩兵が中心となっている。こうなると騎馬のように、勢いがついて止まらないということもない。イングランドの弓兵の射程外でいったん隊列を整え、そこから整然と突撃を図る気だろう。
そうはさせじと、エドワードが事前に伝えてあった第一の指令を、左翼のウォリック伯が実行に移した。すなわち、偽装撤退である。逃走する素振りを見せて、突撃を誘う。
勢いに乗ったクレルモン将軍率いる傭兵隊は、これを好機と見て、突撃を開始した。
「矢を射よ!」
エドワードの掛け声に応じ、イングランドの誇る三千の長弓隊が、一斉にフランス軍に矢を射た。長弓から放たれた矢は、芸術的なまでにきれいな曲線を描いて、フランス軍へと吸い込まれてゆく。
0
お気に入りに追加
19
あなたにおすすめの小説

陸のくじら侍 -元禄の竜-
陸 理明
歴史・時代
元禄時代、江戸に「くじら侍」と呼ばれた男がいた。かつて武士であるにも関わらず鯨漁に没頭し、そして誰も知らない理由で江戸に流れてきた赤銅色の大男――権藤伊佐馬という。海の巨獣との命を削る凄絶な戦いの果てに会得した正確無比な投げ銛術と、苛烈なまでの剛剣の使い手でもある伊佐馬は、南町奉行所の戦闘狂の美貌の同心・青碕伯之進とともに江戸の悪を討ちつつ、日がな一日ずっと釣りをして生きていくだけの暮らしを続けていた……

座頭の石《ざとうのいし》
とおのかげふみ
歴史・時代
盲目の男『石』は、《つる》という女性と二人で旅を続けている。
旅の途中で出会った女性《よし》と娘の《たえ》の親子。
二人と懇意になり、町に留まることにした二人。
その町は、尾張藩の代官、和久家の管理下にあったが、実質的には一人のヤクザが支配していた。
《タノヤスケゴロウ》表向き商人を装うこの男に目を付けられてしまった石。
町は幕府からの大事業の河川工事の真っ只中。
棟梁を務める《さだよし》は、《よし》に執着する《スケゴロウ》と対立を深めていく。
和久家の跡取り問題が引き金となり《スケゴロウ》は、子分の《やキり》の忠告にも耳を貸さず、暴走し始める。
それは、《さだよし》や《よし》の親子、そして、《つる》がいる集落を破壊するということだった。
その事を知った石は、《つる》を、《よし》親子を、そして町で出会った人々を守るために、たった一人で立ち向かう。


思い出のチョコレートエッグ
ライヒェル
恋愛
失恋傷心旅行に出た花音は、思い出の地、オランダでの出会いをきっかけに、ワーキングホリデー制度を利用し、ドイツの首都、ベルリンに1年限定で住むことを決意する。
慣れない海外生活に戸惑い、異国ならではの苦労もするが、やがて、日々の生活がリズムに乗り始めたころ、とてつもなく魅力的な男性と出会う。
秘密の多い彼との恋愛、彼を取り巻く複雑な人間関係、初めて経験するセレブの世界。
主人公、花音の人生パズルが、紆余曲折を経て、ついに最後のピースがぴったりはまり完成するまでを追う、胸キュン&溺愛系ラブストーリーです。
* ドイツ在住の作者がお届けする、ヨーロッパを舞台にした、喜怒哀楽満載のラブストーリー。
* 外国での生活や、外国人との恋愛の様子をリアルに感じて、主人公の日々を間近に見ているような気分になれる内容となっています。
* 実在する場所と人物を一部モデルにした、リアリティ感の溢れる長編小説です。
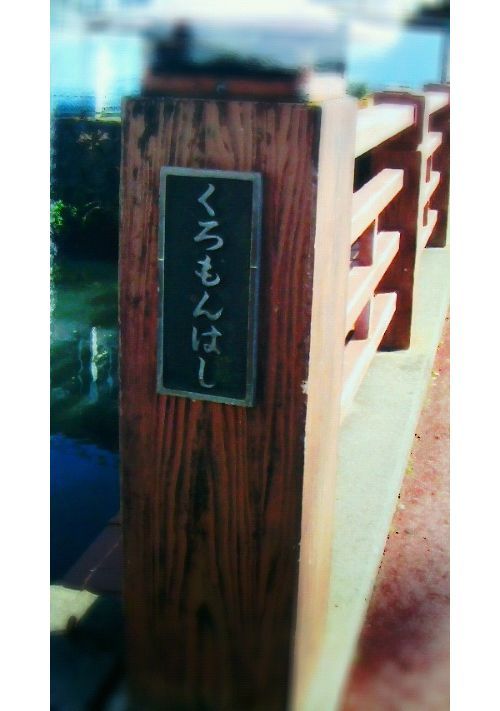
肥後の春を待ち望む
尾方佐羽
歴史・時代
秀吉の天下統一が目前になった天正の頃、肥後(熊本)の国主になった佐々成政に対して国人たちが次から次へと反旗を翻した。それを先導した国人の筆頭格が隈部親永(くまべちかなが)である。彼はなぜ、島津も退くほどの強大な敵に立ち向かったのか。国人たちはどのように戦ったのか。そして、九州人ながら秀吉に従い国人衆とあいまみえることになった若き立花統虎(宗茂)の胸中は……。

わが友ヒトラー
名無ナナシ
歴史・時代
史上最悪の独裁者として名高いアドルフ・ヒトラー
そんな彼にも青春を共にする者がいた
一九〇〇年代のドイツ
二人の青春物語
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC6CwMDVM6o7OygoFC3RdKng
参考・引用
彡(゜)(゜)「ワイはアドルフ・ヒトラー。将来の大芸術家や」(5ch)
アドルフ・ヒトラーの青春(三交社)

天暗の星~念真流寂滅抄~
筑前助広
歴史・時代
「人を斬らねば、私は生きられぬのか……」
江戸の泰平も豊熟の極みに達し、腐敗臭を放ちだした頃。
夜須藩御手先役見習い・平山清記は、自らの役目に疑問を覚えながらも、主君を守る太刀として藩法を破る無頼漢を斬る日々を過ごしていた。
そんなある日、清記は父の悌蔵に命じられ、中老・奥寺大和の剣術指南役になる。そこで出会った、運命の女。そして、友。青春の暁光を迎えようとしていた清記に、天暗の宿星が微笑む――。
寂滅の秘剣・落鳳。幾代を重ね、生き血を啜って生まれし、一族の魔剣よ。願いを訊き給へ。能うならば、我が業罪が一殺多生にならん事を。
アルファポリス第一回歴史時代小説大賞特別賞「狼の裔」に続く、もう一つの念真流物語!
※この物語はフィクションです。実在の人物・団体・地名とは一切関係ありません。
※この物語は、「巷説江戸演義」と題した筑前筑後オリジナル作品企画の作品群です。舞台は江戸時代ですが、オリジナル解釈の江戸時代ですので、史実とは違う部分も多数ございますので、どうぞご注意ください。また、作中には実際の地名が登場しますが、実在のものとは違いますので、併せてご注意ください。

狐侍こんこんちき
月芝
歴史・時代
母は出戻り幽霊。居候はしゃべる猫。
父は何の因果か輪廻の輪からはずされて、地獄の官吏についている。
そんな九坂家は由緒正しいおんぼろ道場を営んでいるが、
門弟なんぞはひとりもいやしない。
寄りつくのはもっぱら妙ちきりんな連中ばかり。
かような家を継いでしまった藤士郎は、狐面にていつも背を丸めている青瓢箪。
のんびりした性格にて、覇気に乏しく、およそ武士らしくない。
おかげでせっかくの剣の腕も宝の持ち腐れ。
もっぱら魚をさばいたり、薪を割るのに役立っているが、そんな暮らしも案外悪くない。
けれどもある日のこと。
自宅兼道場の前にて倒れている子どもを拾ったことから、奇妙な縁が動きだす。
脇差しの付喪神を助けたことから、世にも奇妙な仇討ち騒動に関わることになった藤士郎。
こんこんちきちき、こんちきちん。
家内安全、無病息災、心願成就にて妖縁奇縁が来来。
巻き起こる騒動の数々。
これを解決するために奔走する狐侍の奇々怪々なお江戸物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















