36 / 39
七章 珠玉の疵
四
しおりを挟む
包囲されて十日が経った。王翦は決然と腰を据え、こちらが立ち枯れるのを待っている。処々方々で民は蜂起しているようだが、その殆どが秦の別動隊に潰されている。王翦の包囲網は微塵の隙もない。熊啓が拠る、蘄は完全に孤立したと言っていい。だが、不思議と心は乱れていなかった。まだ光輝は残されている。
「備蓄は以って、あと一ヶ月という所でしょうか」
補佐役の宋辰が沈思を隠さず、執務室として使っている、官衙の一室に入ってきた。
「そうか」
薄暗い執務室の中で、燭台の炎が、ゆらゆらと揺れている。
「大王。このままでは最悪の情況に陥ってしまいます」
文机の前に端座する、熊啓は静かに瞼を開いた。
彼が語る最悪の情況とは、備蓄を食い尽し、飢餓が蔓延することだ。
「民が互いの肉を食らい合う事態だけは、絶対に避けなくてはなりません」
「婉曲な言い回しはやめろ。お前は降伏を望んでいるのだろ」
宋辰が深く息を吐く。
「降伏しましょう、大王。最早、我等に勝ち目はありません」
宋辰の必死の訴えにも、熊啓の決意は揺らがず、心は凪いだ状態を保っていた。
「我等は抗秦の旗を掲げ続けた。王翦が降伏を承諾すると思えん」
「しかし、無辜の民の命は」
「甘い幻想を抱くのはやめろ。秦は牙を剥いた者には、一切の容赦はしない。敗けも降伏も結末は同じこと。五万の義勇兵と三万の無辜の民は皆殺しにされる」
闇の中で薄暗く浮かび上がる、宋辰の双眸が怯懦の色を明滅させた。
「生き残りたければ、我等は王翦に勝つしか道は残されていない」
宋辰は蒼白い唇を震わせ、逃げるように執務室を後にした。
「我等は勝つしかない」
熊啓は己に言い聞かせるように、同じ言葉を繰り返した。
そして、勝利の鍵は黒き竜が握っている。
膠着状態が続き、十五日目の深更。事件は起こった。
「大王!」
汗明が杖をばたつかせて、執務室に駆け込んできた。
尋常ならざる事態であることは、額に玉のような汗を浮かべた、汗明の周章ぶりを見れば分かる。
「何事だ?」
「宋辰が数人の手勢を率いて、城門前に押しかけています」
「何だと」
熊啓は夜着の裾を払い、衝立に掛けてある、剣に手を伸ばした。
その時である。城市の方で歓声が上がった。次いで聞こえてくるのは、門が開く音。
熊啓と汗明は、刹那の間、顔を見合わせた。
「汗明!直ぐに兵士を叩き起こしてくれ!敵が雪崩れこんでくるぞ!」
「御意」
汗明は杖を鳴らし、執務室から飛び出て行った。
(くそ!宋辰に意識を向けておくべきだったか)
懼れに歪んだ、宋辰の顔が脳裏を翳めていく。怯懦に憑りつかれた者は、たとえ優秀な者であっても、往々にして保身に走る。
熊啓は大童で具足を纏うと、数人の麾下を引き連れ、歩墻へと出た。暁の光線が地上に降り注ぎ、白を帯びる大地には、すでに甲土が満ちている。鳶色の旒が林立し、軍旅斧鉞を鳴らしながら、迫ってきている。再び歓声が上がる。橋が鈍い音を立てて、降りていく。
右尹の宋辰という者が間者を通して、此方との接触を図ってきた。
宋辰が寄越した書簡には、こう認められていた。城門を内側から開門する故、降伏を承諾し、身柄を保障して欲しいと。
王翦は書簡を受け取ると、直ぐに返事を認め、間者を宋辰の元へと送った。勿怪の幸いとはこのことであった。宋辰は約束の刻限通りに、城門を開門させた。王翦は軍を進撃させ、蔪の城内に秦兵達が次々に雪崩込んでいく。城内に侵入してしまえば、流れは完全に此方のものである。
楚を裏切った宋辰は、数人の手勢を連れ、秦へ降った。
彼は王翦の前に膝をつくと、憚りもせず秦への忠誠を誓った。
「李信」
合図一つで、李信は抜刀する。
白刃が鶺鴒の尾が如く弧を描く。
宋辰の首が舞う。それを見た数人の手勢は、悲鳴を上げ、逃れようとしたが、間断なく放たれる、李信の凶刃に全員が斃れた。
「下衆が」
眼許を半月型にした、王翦が満足げに唸る。
「間もなく昌平君の首もあがってくるだろう」
蘄の城内は混迷を極めていた。まともな訓練を受けていない、義勇兵共は、戦いの術を心得ている、秦兵に成す術もなく討たれていく。
本当の意味で、己の軍人としての人生が終焉を迎える。宿敵を討ち果たし、疵一つない功績を手に入れた。己にとって、至高の宝玉に勝るほど価値のあるものだ。加えて、燕と楚を平定したことによって、己の名は天下統一の最大の功労者として深く青史に名を刻むだろう。軍人として上官であった白起と並ぶ元勲となる。完全無欠を求め続けた王翦は、永きに亘る人生で初めて満たされる。
悦びで総身が瘧のように震えた。
(これで完璧な形で人生を終えることができる)
満腔の笑みを湛えた時、王翦の周囲を固める十万の兵の中から、歓声に近いものが上がった。
思わず身を乗り出し、前方を見入る。麾下が熊啓の首級を上げたのかもしれない。しかし、直ぐに違和感を覚える。それは歓声というには、あまりにも緊迫したものだった。
「将軍!」
李信が叫んだ。
東の方角に砂塵。凄まじい勢いで駆けてくる。彼我の差は二里。
「敵襲!」
誰が叫んだ。
だが、その間にも濛々と立ち込める砂塵を切り払い、瞬く間に突如現れた敵は距離を詰めてくる。
中空に漂う塵芥が晴れる。そして、黄金の陽光に照らされる竜旗を王翦は見た。漆黒の流星が、軌跡を描きながら突っ込んでくる。
全身に戦慄が走る。
(莫迦な)
思考が停止する。
「将軍!」
李信の己を呼ばわる声で、我に返る。
「迎撃準備を」
狼狽しながら、指揮刀を振るう。だが、判断が半呼吸遅れた。
左翼の横腹に、黒の一団が、錐状の陣形で突っ込んだ。大地が揺れる。
響めきが走る。数としては、恐らくたいした数ではない。それでも、あの男が率いる数百騎は時に、万兵に値する攻撃力を誇る。
縦に伸びた騎馬隊を歩兵達が周囲を囲み、馬の脚を止めようとするが、騎馬隊は勢いを保ったまま、中軍に肉薄してくる。
決死の突撃―。
(刺し違えるつもりか。項燕)
間近に迫った項の旗。そして、あの男と視界が交錯する。
項燕の眼が、竜眼のように神々しく輝いていた。そして、思い知る。奴は天に生かされたことを。
黒き戎衣を纏う竜が不敵に笑ったのを見た。
彼我の差、歩数にして二十。両者を阻むのは厚い肉の壁。辿りつくことはできない。
不意の襲撃に浮足立ったが、項燕率いる三百騎には、肉薄を許すまいと麾下が群がっている。
(今度こそ、貴様の息の根を止めてやる)
王翦は闘志で内に蟠る怯懦を弾いた。気炎が揚がる。
その時である。蘄から吶喊が響いた。
視線を薙ぐ。楚の旌旗。そして、千ほどの騎馬隊が、城門前に蝟集する、秦兵を蹴散らして、疾風の如く駆けて来る。
「昌平君か」
あろうことか楚王を僭称した、熊啓が自ら千騎を率いて討って出てきた。李信の言葉が蘇る。
「昌平君は何かを待っているのではないでしょうか?」
王翦は唇を噛む。
(昌平君は項燕を待っていたのか)
新たな衝撃が先頭に走る。所詮は千三百の攻撃を受けているに過ぎない。だが、何なのだ。この凄味は。
「王翦‼」
項燕の破鐘のような雄叫びが戦場に轟いた。視線を転じる。
群がる兵士の隙間から見える、項燕の姿。
項燕の手には装填済みの弩があった。照準が光線となって、王翦の心の臓を捉えた。
項燕は弩の懸刀(引き金)を引いた。箭槽に装填された箭が放たれる。
箭は風を裂き、蝟集する兵の隙間を縫って、一直線に王翦の元へ向かっていく。
王翦は矛を構えた。だが、放たれた箭は矛の柄を砕く。
(わしの勝ちだ。王翦)
刹那である。肌を刺す強烈な闘志を感じた。
「李信‼」
王翦は叫んだ。
背後に影のように控えた李信は剣を抜き放ち、王翦の胸を貫かんとする、箭をすんでの所で叩き斬った。
身を翻し、李信は剣を捨て、王翦の腰にある佩剣を抜き去った。
馬肚を蹴る。王翦の剣は、項燕に砕かれた矛を溶かし、百煉鋼で鍛えられた優れた剣である。不純物を一切含まない刃は、老いてなお、鋼のような肉体を持つ、項燕の肉を容易く断つ。
李信は単騎で、項燕の元へと駆けた。指呼の間。
項燕が鋭い牙を覗かせた。吐息から火焔が漏れている。
「項燕‼」
「李信‼」
気魄が稲妻となり、宙で衝突する。
項燕は剣を抜く。王翦はまだ若き猛虎という切り札を隠していた。
肚の底から、残りの生気を振り絞る。
王翦に残しておくべき力だった。だが、眼前の敵は全身全霊の力で迎い討たなければならないと直感が告げる。
武威が衝突し、砂塵が巻き上がる。白刃が交錯する。
斬ったのは李信の眼光の尾。疾風となった、李信が躱す。
低い体勢で剣を薙いで来る。受ける。
鉄華が散った。剣の刃が砕けた。
見上げた空。砂煙は晴れていた。遥か上空に李信は跳躍していた。
重なる日輪。
縦の閃光が走った。
鮮血が視界を覆う。
同時に漲っていた力が、天へと還っていく。
「李信!項燕の首を奪れ!」
狂気に満ちた、王翦の咆哮に近い声が迫って来る。
戦場の時は止まっていた。李信は地に仰臥する。項燕を見下ろしていた。
「やるな。若造」
項燕は血で真っ赤に染まった、歯を剥き出しにして笑った。袈裟から血が溢れだしている。一刻も命は保ないだろう。だが、眼の前の男は、直前に迫る死を感じさせないほどに、清々しい笑貌を見せた。
「どうした?わしの首を奪らないのか」
項燕の声は驚くほど澄んでいた。
「死ぬのが怖くないのか?あんた」
「もう充分に生きた。最期に力を振り絞り、お前と戦った。王翦の首を奪れなんだのは悔しいが。王翦ではなく、お前に首を奪られるのなら、まぁよかろう」
項燕は血を吐き出し、遠い眼で空を見上げた。
「何している!早く項燕の首を寄越せ」
王翦が金切り声を上げて、煽り立てくる。
「ったく。戦人同士の語らいに茶々を入れるとは、奴もとんだ無粋者じゃ」
力なく笑った、項燕から命が消えていくのを感じる。
「あの男はあんたの屍に凌辱の限りを尽くすだろう。あんたの一族にも危害が及ぶ」
「分かっておるわ。だから、息子達や孫は遠くに逃がしておる」
「そうか」
李信は返り血に濡れた、剣の刃を項燕の喉元へ。
「それでいい」
敵も味方も動きを止め、二人の戦人が生み出す静謐に注視している。
項燕は、
「主よ。わしは役目を果たせなかったようだ」と天に向かって告げ、静かに瞼を閉じた。
剣尖が項燕の喉元に触れる。柄を握りしめる。
一拍の間、
「やめだ」
李信は剣を払った。
「おい」
項燕の麾下を呼ばわる。
「連れていけ」
呼ばれた麾下は困惑している。
「どういうつもりだ。わしはもう死ぬ」
細く瞼を開いた、項燕の顔色は死人そのものであった。
「俺はあんたのおかげで強くなれた。死に場所くらいは与えてやる。だから、静かに死んでいけ。あんたは本当の意味で英雄だったよ。王翦などに辱めを受けていいような男ではない」
王翦の喧しい奇声は耳に入っていたが、李信はそしらぬ顔を貫いた。
「お前が罰を受ける」
李信は苦笑し、首を竦める。
「まぁ、どうにかなるさ」
「感謝する‥‥。小僧」
もう項燕は笑えてすらいなかった。
「行け。じじい」
麾下の一人が下馬し、瀕死の項燕を担ぐ。
「何をしている!李信!」
王翦の叫声が迫ってくる。
今や百ほどに減った、項燕の麾下が一塊となり、馬首を返す。
「項燕を逃がすな!」
李信と項燕のやりとりを呆然と眺めていた、兵士達は王翦の喝に弾かれたように動き出す。
瞬間。
「道を空けろ!今、英雄が逝こうとしている。奴の誇り高き死を阻もうとする者は、この李信が叩き斬る!」
李信は声を張り上げた。炎雷の如き武威に打たれ、兵士達は静止した。
「さらばだ。楚の英雄よ」
巨大な影が地を走った。空を見上げる。
李信には見えた。蒼空を遊弋し、悲し気な声で咆哮する黒竜の姿が。
「備蓄は以って、あと一ヶ月という所でしょうか」
補佐役の宋辰が沈思を隠さず、執務室として使っている、官衙の一室に入ってきた。
「そうか」
薄暗い執務室の中で、燭台の炎が、ゆらゆらと揺れている。
「大王。このままでは最悪の情況に陥ってしまいます」
文机の前に端座する、熊啓は静かに瞼を開いた。
彼が語る最悪の情況とは、備蓄を食い尽し、飢餓が蔓延することだ。
「民が互いの肉を食らい合う事態だけは、絶対に避けなくてはなりません」
「婉曲な言い回しはやめろ。お前は降伏を望んでいるのだろ」
宋辰が深く息を吐く。
「降伏しましょう、大王。最早、我等に勝ち目はありません」
宋辰の必死の訴えにも、熊啓の決意は揺らがず、心は凪いだ状態を保っていた。
「我等は抗秦の旗を掲げ続けた。王翦が降伏を承諾すると思えん」
「しかし、無辜の民の命は」
「甘い幻想を抱くのはやめろ。秦は牙を剥いた者には、一切の容赦はしない。敗けも降伏も結末は同じこと。五万の義勇兵と三万の無辜の民は皆殺しにされる」
闇の中で薄暗く浮かび上がる、宋辰の双眸が怯懦の色を明滅させた。
「生き残りたければ、我等は王翦に勝つしか道は残されていない」
宋辰は蒼白い唇を震わせ、逃げるように執務室を後にした。
「我等は勝つしかない」
熊啓は己に言い聞かせるように、同じ言葉を繰り返した。
そして、勝利の鍵は黒き竜が握っている。
膠着状態が続き、十五日目の深更。事件は起こった。
「大王!」
汗明が杖をばたつかせて、執務室に駆け込んできた。
尋常ならざる事態であることは、額に玉のような汗を浮かべた、汗明の周章ぶりを見れば分かる。
「何事だ?」
「宋辰が数人の手勢を率いて、城門前に押しかけています」
「何だと」
熊啓は夜着の裾を払い、衝立に掛けてある、剣に手を伸ばした。
その時である。城市の方で歓声が上がった。次いで聞こえてくるのは、門が開く音。
熊啓と汗明は、刹那の間、顔を見合わせた。
「汗明!直ぐに兵士を叩き起こしてくれ!敵が雪崩れこんでくるぞ!」
「御意」
汗明は杖を鳴らし、執務室から飛び出て行った。
(くそ!宋辰に意識を向けておくべきだったか)
懼れに歪んだ、宋辰の顔が脳裏を翳めていく。怯懦に憑りつかれた者は、たとえ優秀な者であっても、往々にして保身に走る。
熊啓は大童で具足を纏うと、数人の麾下を引き連れ、歩墻へと出た。暁の光線が地上に降り注ぎ、白を帯びる大地には、すでに甲土が満ちている。鳶色の旒が林立し、軍旅斧鉞を鳴らしながら、迫ってきている。再び歓声が上がる。橋が鈍い音を立てて、降りていく。
右尹の宋辰という者が間者を通して、此方との接触を図ってきた。
宋辰が寄越した書簡には、こう認められていた。城門を内側から開門する故、降伏を承諾し、身柄を保障して欲しいと。
王翦は書簡を受け取ると、直ぐに返事を認め、間者を宋辰の元へと送った。勿怪の幸いとはこのことであった。宋辰は約束の刻限通りに、城門を開門させた。王翦は軍を進撃させ、蔪の城内に秦兵達が次々に雪崩込んでいく。城内に侵入してしまえば、流れは完全に此方のものである。
楚を裏切った宋辰は、数人の手勢を連れ、秦へ降った。
彼は王翦の前に膝をつくと、憚りもせず秦への忠誠を誓った。
「李信」
合図一つで、李信は抜刀する。
白刃が鶺鴒の尾が如く弧を描く。
宋辰の首が舞う。それを見た数人の手勢は、悲鳴を上げ、逃れようとしたが、間断なく放たれる、李信の凶刃に全員が斃れた。
「下衆が」
眼許を半月型にした、王翦が満足げに唸る。
「間もなく昌平君の首もあがってくるだろう」
蘄の城内は混迷を極めていた。まともな訓練を受けていない、義勇兵共は、戦いの術を心得ている、秦兵に成す術もなく討たれていく。
本当の意味で、己の軍人としての人生が終焉を迎える。宿敵を討ち果たし、疵一つない功績を手に入れた。己にとって、至高の宝玉に勝るほど価値のあるものだ。加えて、燕と楚を平定したことによって、己の名は天下統一の最大の功労者として深く青史に名を刻むだろう。軍人として上官であった白起と並ぶ元勲となる。完全無欠を求め続けた王翦は、永きに亘る人生で初めて満たされる。
悦びで総身が瘧のように震えた。
(これで完璧な形で人生を終えることができる)
満腔の笑みを湛えた時、王翦の周囲を固める十万の兵の中から、歓声に近いものが上がった。
思わず身を乗り出し、前方を見入る。麾下が熊啓の首級を上げたのかもしれない。しかし、直ぐに違和感を覚える。それは歓声というには、あまりにも緊迫したものだった。
「将軍!」
李信が叫んだ。
東の方角に砂塵。凄まじい勢いで駆けてくる。彼我の差は二里。
「敵襲!」
誰が叫んだ。
だが、その間にも濛々と立ち込める砂塵を切り払い、瞬く間に突如現れた敵は距離を詰めてくる。
中空に漂う塵芥が晴れる。そして、黄金の陽光に照らされる竜旗を王翦は見た。漆黒の流星が、軌跡を描きながら突っ込んでくる。
全身に戦慄が走る。
(莫迦な)
思考が停止する。
「将軍!」
李信の己を呼ばわる声で、我に返る。
「迎撃準備を」
狼狽しながら、指揮刀を振るう。だが、判断が半呼吸遅れた。
左翼の横腹に、黒の一団が、錐状の陣形で突っ込んだ。大地が揺れる。
響めきが走る。数としては、恐らくたいした数ではない。それでも、あの男が率いる数百騎は時に、万兵に値する攻撃力を誇る。
縦に伸びた騎馬隊を歩兵達が周囲を囲み、馬の脚を止めようとするが、騎馬隊は勢いを保ったまま、中軍に肉薄してくる。
決死の突撃―。
(刺し違えるつもりか。項燕)
間近に迫った項の旗。そして、あの男と視界が交錯する。
項燕の眼が、竜眼のように神々しく輝いていた。そして、思い知る。奴は天に生かされたことを。
黒き戎衣を纏う竜が不敵に笑ったのを見た。
彼我の差、歩数にして二十。両者を阻むのは厚い肉の壁。辿りつくことはできない。
不意の襲撃に浮足立ったが、項燕率いる三百騎には、肉薄を許すまいと麾下が群がっている。
(今度こそ、貴様の息の根を止めてやる)
王翦は闘志で内に蟠る怯懦を弾いた。気炎が揚がる。
その時である。蘄から吶喊が響いた。
視線を薙ぐ。楚の旌旗。そして、千ほどの騎馬隊が、城門前に蝟集する、秦兵を蹴散らして、疾風の如く駆けて来る。
「昌平君か」
あろうことか楚王を僭称した、熊啓が自ら千騎を率いて討って出てきた。李信の言葉が蘇る。
「昌平君は何かを待っているのではないでしょうか?」
王翦は唇を噛む。
(昌平君は項燕を待っていたのか)
新たな衝撃が先頭に走る。所詮は千三百の攻撃を受けているに過ぎない。だが、何なのだ。この凄味は。
「王翦‼」
項燕の破鐘のような雄叫びが戦場に轟いた。視線を転じる。
群がる兵士の隙間から見える、項燕の姿。
項燕の手には装填済みの弩があった。照準が光線となって、王翦の心の臓を捉えた。
項燕は弩の懸刀(引き金)を引いた。箭槽に装填された箭が放たれる。
箭は風を裂き、蝟集する兵の隙間を縫って、一直線に王翦の元へ向かっていく。
王翦は矛を構えた。だが、放たれた箭は矛の柄を砕く。
(わしの勝ちだ。王翦)
刹那である。肌を刺す強烈な闘志を感じた。
「李信‼」
王翦は叫んだ。
背後に影のように控えた李信は剣を抜き放ち、王翦の胸を貫かんとする、箭をすんでの所で叩き斬った。
身を翻し、李信は剣を捨て、王翦の腰にある佩剣を抜き去った。
馬肚を蹴る。王翦の剣は、項燕に砕かれた矛を溶かし、百煉鋼で鍛えられた優れた剣である。不純物を一切含まない刃は、老いてなお、鋼のような肉体を持つ、項燕の肉を容易く断つ。
李信は単騎で、項燕の元へと駆けた。指呼の間。
項燕が鋭い牙を覗かせた。吐息から火焔が漏れている。
「項燕‼」
「李信‼」
気魄が稲妻となり、宙で衝突する。
項燕は剣を抜く。王翦はまだ若き猛虎という切り札を隠していた。
肚の底から、残りの生気を振り絞る。
王翦に残しておくべき力だった。だが、眼前の敵は全身全霊の力で迎い討たなければならないと直感が告げる。
武威が衝突し、砂塵が巻き上がる。白刃が交錯する。
斬ったのは李信の眼光の尾。疾風となった、李信が躱す。
低い体勢で剣を薙いで来る。受ける。
鉄華が散った。剣の刃が砕けた。
見上げた空。砂煙は晴れていた。遥か上空に李信は跳躍していた。
重なる日輪。
縦の閃光が走った。
鮮血が視界を覆う。
同時に漲っていた力が、天へと還っていく。
「李信!項燕の首を奪れ!」
狂気に満ちた、王翦の咆哮に近い声が迫って来る。
戦場の時は止まっていた。李信は地に仰臥する。項燕を見下ろしていた。
「やるな。若造」
項燕は血で真っ赤に染まった、歯を剥き出しにして笑った。袈裟から血が溢れだしている。一刻も命は保ないだろう。だが、眼の前の男は、直前に迫る死を感じさせないほどに、清々しい笑貌を見せた。
「どうした?わしの首を奪らないのか」
項燕の声は驚くほど澄んでいた。
「死ぬのが怖くないのか?あんた」
「もう充分に生きた。最期に力を振り絞り、お前と戦った。王翦の首を奪れなんだのは悔しいが。王翦ではなく、お前に首を奪られるのなら、まぁよかろう」
項燕は血を吐き出し、遠い眼で空を見上げた。
「何している!早く項燕の首を寄越せ」
王翦が金切り声を上げて、煽り立てくる。
「ったく。戦人同士の語らいに茶々を入れるとは、奴もとんだ無粋者じゃ」
力なく笑った、項燕から命が消えていくのを感じる。
「あの男はあんたの屍に凌辱の限りを尽くすだろう。あんたの一族にも危害が及ぶ」
「分かっておるわ。だから、息子達や孫は遠くに逃がしておる」
「そうか」
李信は返り血に濡れた、剣の刃を項燕の喉元へ。
「それでいい」
敵も味方も動きを止め、二人の戦人が生み出す静謐に注視している。
項燕は、
「主よ。わしは役目を果たせなかったようだ」と天に向かって告げ、静かに瞼を閉じた。
剣尖が項燕の喉元に触れる。柄を握りしめる。
一拍の間、
「やめだ」
李信は剣を払った。
「おい」
項燕の麾下を呼ばわる。
「連れていけ」
呼ばれた麾下は困惑している。
「どういうつもりだ。わしはもう死ぬ」
細く瞼を開いた、項燕の顔色は死人そのものであった。
「俺はあんたのおかげで強くなれた。死に場所くらいは与えてやる。だから、静かに死んでいけ。あんたは本当の意味で英雄だったよ。王翦などに辱めを受けていいような男ではない」
王翦の喧しい奇声は耳に入っていたが、李信はそしらぬ顔を貫いた。
「お前が罰を受ける」
李信は苦笑し、首を竦める。
「まぁ、どうにかなるさ」
「感謝する‥‥。小僧」
もう項燕は笑えてすらいなかった。
「行け。じじい」
麾下の一人が下馬し、瀕死の項燕を担ぐ。
「何をしている!李信!」
王翦の叫声が迫ってくる。
今や百ほどに減った、項燕の麾下が一塊となり、馬首を返す。
「項燕を逃がすな!」
李信と項燕のやりとりを呆然と眺めていた、兵士達は王翦の喝に弾かれたように動き出す。
瞬間。
「道を空けろ!今、英雄が逝こうとしている。奴の誇り高き死を阻もうとする者は、この李信が叩き斬る!」
李信は声を張り上げた。炎雷の如き武威に打たれ、兵士達は静止した。
「さらばだ。楚の英雄よ」
巨大な影が地を走った。空を見上げる。
李信には見えた。蒼空を遊弋し、悲し気な声で咆哮する黒竜の姿が。
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

本能のままに
揚羽
歴史・時代
1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった
もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!
※更新は不定期になると思います。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――
黒鯛の刺身♪
歴史・時代
戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。
一般には武田勝頼と記されることが多い。
……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。
信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。
つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。
一介の後見人の立場でしかない。
織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。
……これは、そんな悲運の名将のお話である。
【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵
【注意】……武田贔屓のお話です。
所説あります。
あくまでも一つのお話としてお楽しみください。
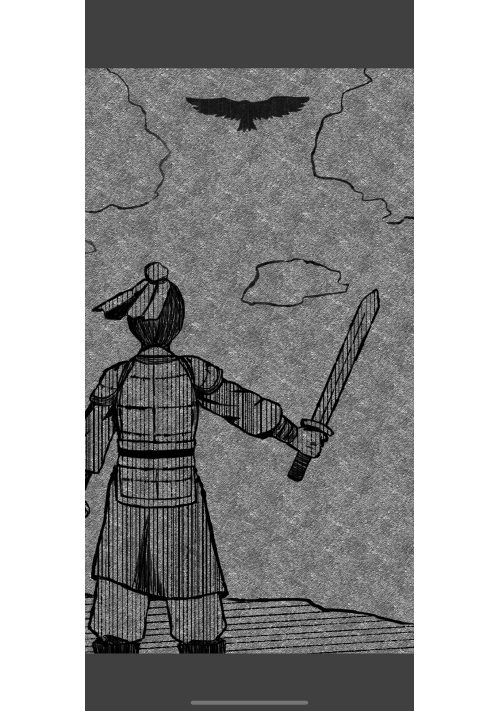
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

旧式戦艦はつせ
古井論理
歴史・時代
真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

幕府海軍戦艦大和
みらいつりびと
歴史・時代
IF歴史SF短編です。全3話。
ときに西暦1853年、江戸湾にぽんぽんぽんと蒸気機関を響かせて黒船が来航したが、徳川幕府はそんなものへっちゃらだった。征夷大将軍徳川家定は余裕綽々としていた。
「大和に迎撃させよ!」と命令した。
戦艦大和が横須賀基地から出撃し、46センチ三連装砲を黒船に向けた……。

池田戦記ー池田恒興・青年編ー信長が最も愛した漢
林走涼司(はばしり りょうじ)
歴史・時代
天文5年(1536)尾張国の侍長屋で、産声を上げた池田勝三郎は、戦で重傷を負い余命を待つだけの父、利恒と、勝三郎を生んだばかりの母、お福を囲んで、今後の身の振り方を決めるため利恒の兄、滝川一勝、上役の森寺秀勝が額を付き合わせている。
利恒の上司、森寺秀勝の提案は、お福に、主、織田信秀の嫡男吉法師の乳母になることだった……。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















