10 / 39
三章 陰火
二
しおりを挟む
払暁の光線が、寝室に差し込む。まんじりもせず迎えた朝。王翦は具足を鳴らし、牀から起き上がる。全身の筋を伸ばす。筋は音を立ててほぐれていく。呻くほどの痛みが総身に走る。無理もない。齢六十五歳を越え、躰の至る所にガタが来ている。この時代ででは大往生である。
躰を伸ばしていると、館の外の方で、馬車が駆ける音が聞こえた。それもかなりの数と推測できる。耳を澄ませる。すると馬蹄の響きは、館の前で止まった。
(このような時間に客人か)
隠棲した今、息子の王賁以外に、王翦を訪ねるものなどいなかった。門前雀羅とは良く言ったもので、軍人時代には、王翦に阿諛追従する文官共がひっきりなしに門を叩いたものだが。
廊下を走る、下男の慌ただしい足音が響く。
「旦那様!」
勢いよく寝室に入った、下男は土気色の顔を向けた。
「何があった?」
ただならぬ気配を感じる。
「それがー」
下男は慄きながら、早朝の来訪者の名を告げた。
王翦は瞠目し、暫しの間、自失した。だが、老齢にして、研がれた刀のように鋭い思考の持ち主である王翦は、
「承知した。鄭重におもてなしせよ」
と泰然と告げ、他の下男に武冠(武官の冠)を持ってくるように命じた。
装いを改めた王翦は、客間の下座で座し、客人を静かに待っていた。
戸が開き、「王翦将軍」と己を呼ばわる、凛とした声が響いた。
(相変わらずこの御方の声はよく透る)
王翦は跪拝し、深く面を下げた。客人が上座に座す。
「面を上げてくれ。王翦将軍」
君主に対して、許しがなければ、臣下は直視も直言もできない。
王翦はゆっくりと面を上げ、秦王こと嬴政を双眼で捉えた。
「お久しゅうございます。大王様」
秦王政は鋭い眼許に、穏やかな皺を刻んだ。
「息災であったか。王翦」
「はい。この通りでございます」
王翦は相好を崩し、服の袖をはためかせた。
王翦はつらつらと壮年期の秦王の姿を眺めた。風姿には明晰の光が満ちている。
豊かな耳翼は、彼が口許を弛める度に震える。
王翦は秦王政の父、荘襄王の容貌も知っているが、まるで似ていない。荘襄王は柔和な顔立ちの男であった。蒲柳をうかがわせ、君主というより、詩人や楽人に近い気配を纏っていた。
秦王政の母である太后と私通していた、呂不韋が彼の実父というのは、真なのかもしれない。三十半ばに達した秦王政の容貌は、相邦として辣腕を振るっていた、壮年期の呂不韋と瓜二つであった。
だが、瞳の奥に宿る猜疑の影は、遥かに嬴政の方が濃く禍々しい。幾星霜と続く戦乱を憎み、純粋に万民の幸せを願い天下統一を宿願に掲げた、純朴であった頃の王の姿は、今はない。
何が純粋であった少年王を変えたのか。恐らく彼を、猜疑心に憑りつかれた怪物に変えたのは人であろう。弟の成蟜、母である太后の反乱。そして、太后と情夫である嫪毐の謀反には、実父と噂される、呂不韋も関与していた。つまり、嬴政は身内に裏切り続けられてきた。戦乱の世に、骨肉相食む情況は、珍しいことではない。
しかし、肉親の裏切りが、確実に、嬴政の何かを変えた。人の醜悪さを知ったのか。君主とは孤独なものなのだろう。一度は軍人の極みに至った己であるが、君主の孤独は理解できない。
ともあれ純朴であった少年王の転化を残念に思っていない訳ではない。だが、時間と経験は普遍のもので、必ず人に変化を与える。過去の経験値が、今の嬴政を創り上げ、少なからず軍人として仕えた己も、彼の積み重ねた経験値の中にあるのだと思うと、こんなものだと割り切ることができる。これから若き秦王が如何に変化してゆくか。老いさき短い己の知る所ではない。
「御光臨頂き感佩の至りでございます。して、来意を御尋ねしても」
王翦は猜疑心の塊である、秦王政に柔和な笑みを浮かべ尋ねた。
秦王政の眼許から感情が引いていく。長嘆息の後、彼はおもむろに床に額を擦りつけた。
これには、海千山千の王翦も驚いた。
「大王様!何を!」
慌てて膝行で、頭を垂れる、秦王政の躰を支えた。
「孤はそなたに謝罪しなくてはならない」
面を上げた秦王政の苦い表情からは、焦燥と怒りが窺えた。
「謝罪とは?」
「荊の討伐を任せた李信と蒙恬が敗けた」
荊とは楚のことをさす。
秦王政が婉曲に楚の名称を避けたのは、父王である荘襄王の諱が子楚であるからである。
(なるほど。やはりか)
この時点で、秦王政が秘める心算を看破した。
「それはー。俄かに信じ難い話ですな。李信、蒙恬両将軍は共に勇猛果敢で、私の知る所、斜陽にある楚に彼等を撃ち破るほどの将校がいるとは思えませんが」
事実、項燕が退役してからというもの、楚には柱石といえる軍人は一人もいない。
元来、楚は公室や貴族の力が強い、旧態依然とした国である。長大な領土を有していながらも、新興の国である秦に、大きく差をつけられたのは、旧来の陋習に囚われ、時代の変遷に合わせて、時流の波に乗ることができなかったことにある。
その点、秦では公室、貴族が力を持つ、封建制度の撤廃を推し進め、法による統治を国是とし、外国人を排斥せず登用し、実力主義による論功行賞を確立させた。秦では功績なきものに、禄を食ませることはしない。極論、奴隷でも手柄を上げれば、極官へと登り詰めることができるのである。秦の強さの根底は、封建制の撤廃を推進したことにあるといっても過言ではない。
王翦自身も生え抜きの軍人であり、実力と積み重ねた功績のみで、大将軍にまで登った。李信、蒙恬の両名も同様で、まだ若いが幾度も死線を潜り抜けてきた、千軍万馬の将である。項燕以外の楚の将を思い起こしてみるが、李信、蒙恬を撃ち破れるほどの将の名は上がってこない。
「昌平君、昌文君が叛旗を翻した」
秦王政は苦虫を噛み潰したような顔で言った。眇めた巨眼の奥では、憤怒の烈火が灯っている。
「何と」
隠棲してからというもの、世の情勢をあえて耳に入らないようにしている。宿敵が戦場を去ってから、全てがどうでもよくなったのだ。
両名は共に、長く王を丞相として輔け、彼自身全幅の信頼を置いていたことは、傍目からでも感じていた。だが、両名とも、楚の公子である。祖国の危急が、叛心の萌芽を芽吹かせたのか。これで李信と蒙恬が敗れた理由も明瞭になってきた。恐らく昌平君、昌文君の軍に背後を衝かれたのであろう。
「孤は出陣前に、そなたと李信に問うたな。荊を攻め奪るのにどれほどの兵力が必要かと」
「ええ」
「そなたは、六十万は必要だと答えた。対して李信は二十万で充分だと言ってのけた」
李信は直近の功があった。僅か数千の兵を率いて、秦王政に荊軻という刺客を差し向けた、燕の太子丹を易水で破り、捕縛することに成功している。
当時の問答の様子を回顧する。
「王翦も耄碌したものだ。老いは人を脆弱に変えるな。それに比べ、李信には果敢さと気概が溢れておる」
王翦は秦王政の心ない発言に、大いに気色ばんだのを覚えている。
王翦が六十万と明確な数字を出したのは、老いでも弱腰になった訳でもない。この問答が成された時は、項燕の所在も曖昧模糊としていたし、幾ら斜陽の国であっても、楚には長大な領土があり、練度は低くとも六十万を超える兵卒がいる。王翦からすれば李信の言は、秦王政に阿る為だけの血気に逸った主張と言えた。
李信は時得顔に軽侮を添えた眼で、鼻白む王翦を見遣った。慷慨し理路整然と、李信の主張に反駁するも、秦王政は李信に楚討伐の任を託した。後に王翦は項燕の退役を知り、自身も軍から退くことを決意した。
「孤が間違っていた。結果、二十万の軍勢は覆滅。昌文君は戦死したが、昌平君は三日三晩遁走する、秦軍を追い、七人の将校を殺した」
秦王政が腰に巻く、佩玉が乾いた音を立てる。
握りしめられた拳からは、血が滴っている。
李信の自信に満ちた表情が、恐怖に歪んだ様を想像すると、胸をすくものがある。しかし、それだけのことだ。たとえ、秦王政自ら出向き、謝意を述べられたとしても、もう一度戦場に立とうとは思わない。
「大王様。私は一度、戦場を離れてしまったのです。隠棲の地で安逸を貪るだけの老骨に、一軍を率いることはできませぬ」
「天下統一は目前に迫っている。だが、宿願を南の荊が阻んでいる。孤は宿願を成就させる為にも、一刻も早く荊を滅ぼしたい。憎き荊を伐てるのは、無限の軍略を有する、王翦将軍―。そなたしかいない」
秦王政は怨顔を向け、強く王翦の皺だらけの手を握った。だが、心に揺らぎはない。
「この老い耄れに、大王様の扶翼が務まるとは、到底思えませぬ」
王翦はするりと、秦王政の桎梏から逃れた。
瞬間、秦王政からたちのぼる不敵な気配を感じた。
「王翦将軍。一つ言い忘れていたことがある」
先ほどまで沈んでいた、秦王政の口調には力が蘇っている。
「はて、何でしょう」
「李信、蒙恬を破ったのは、昌平君一人の力ではない」
「それはつまりー」
「昌平君の動きに呼応した男がいる」
王翦は瞠目し、生唾を呑んだ。心臓が早鐘を打っている。
「王翦将軍―。項燕が戦場に戻ってきた」
曲がった背筋が自然に伸び、総身の細胞が快哉を上げた。
「これでも戦場に戻らぬか?次の戦必ず項燕は出てくるぞ」
胸の奥に不要なものとしまいこんだ闘志が蜷局を巻いて、四肢の先にまで沁みわたっていく。
「大王様も意地の悪いことをなされる」
秦王政は破顔し、唇の隙間から鋭利な犬歯を覗かせた。
「将軍。すでに軍人の眼に戻っているぞ」
躰を伸ばしていると、館の外の方で、馬車が駆ける音が聞こえた。それもかなりの数と推測できる。耳を澄ませる。すると馬蹄の響きは、館の前で止まった。
(このような時間に客人か)
隠棲した今、息子の王賁以外に、王翦を訪ねるものなどいなかった。門前雀羅とは良く言ったもので、軍人時代には、王翦に阿諛追従する文官共がひっきりなしに門を叩いたものだが。
廊下を走る、下男の慌ただしい足音が響く。
「旦那様!」
勢いよく寝室に入った、下男は土気色の顔を向けた。
「何があった?」
ただならぬ気配を感じる。
「それがー」
下男は慄きながら、早朝の来訪者の名を告げた。
王翦は瞠目し、暫しの間、自失した。だが、老齢にして、研がれた刀のように鋭い思考の持ち主である王翦は、
「承知した。鄭重におもてなしせよ」
と泰然と告げ、他の下男に武冠(武官の冠)を持ってくるように命じた。
装いを改めた王翦は、客間の下座で座し、客人を静かに待っていた。
戸が開き、「王翦将軍」と己を呼ばわる、凛とした声が響いた。
(相変わらずこの御方の声はよく透る)
王翦は跪拝し、深く面を下げた。客人が上座に座す。
「面を上げてくれ。王翦将軍」
君主に対して、許しがなければ、臣下は直視も直言もできない。
王翦はゆっくりと面を上げ、秦王こと嬴政を双眼で捉えた。
「お久しゅうございます。大王様」
秦王政は鋭い眼許に、穏やかな皺を刻んだ。
「息災であったか。王翦」
「はい。この通りでございます」
王翦は相好を崩し、服の袖をはためかせた。
王翦はつらつらと壮年期の秦王の姿を眺めた。風姿には明晰の光が満ちている。
豊かな耳翼は、彼が口許を弛める度に震える。
王翦は秦王政の父、荘襄王の容貌も知っているが、まるで似ていない。荘襄王は柔和な顔立ちの男であった。蒲柳をうかがわせ、君主というより、詩人や楽人に近い気配を纏っていた。
秦王政の母である太后と私通していた、呂不韋が彼の実父というのは、真なのかもしれない。三十半ばに達した秦王政の容貌は、相邦として辣腕を振るっていた、壮年期の呂不韋と瓜二つであった。
だが、瞳の奥に宿る猜疑の影は、遥かに嬴政の方が濃く禍々しい。幾星霜と続く戦乱を憎み、純粋に万民の幸せを願い天下統一を宿願に掲げた、純朴であった頃の王の姿は、今はない。
何が純粋であった少年王を変えたのか。恐らく彼を、猜疑心に憑りつかれた怪物に変えたのは人であろう。弟の成蟜、母である太后の反乱。そして、太后と情夫である嫪毐の謀反には、実父と噂される、呂不韋も関与していた。つまり、嬴政は身内に裏切り続けられてきた。戦乱の世に、骨肉相食む情況は、珍しいことではない。
しかし、肉親の裏切りが、確実に、嬴政の何かを変えた。人の醜悪さを知ったのか。君主とは孤独なものなのだろう。一度は軍人の極みに至った己であるが、君主の孤独は理解できない。
ともあれ純朴であった少年王の転化を残念に思っていない訳ではない。だが、時間と経験は普遍のもので、必ず人に変化を与える。過去の経験値が、今の嬴政を創り上げ、少なからず軍人として仕えた己も、彼の積み重ねた経験値の中にあるのだと思うと、こんなものだと割り切ることができる。これから若き秦王が如何に変化してゆくか。老いさき短い己の知る所ではない。
「御光臨頂き感佩の至りでございます。して、来意を御尋ねしても」
王翦は猜疑心の塊である、秦王政に柔和な笑みを浮かべ尋ねた。
秦王政の眼許から感情が引いていく。長嘆息の後、彼はおもむろに床に額を擦りつけた。
これには、海千山千の王翦も驚いた。
「大王様!何を!」
慌てて膝行で、頭を垂れる、秦王政の躰を支えた。
「孤はそなたに謝罪しなくてはならない」
面を上げた秦王政の苦い表情からは、焦燥と怒りが窺えた。
「謝罪とは?」
「荊の討伐を任せた李信と蒙恬が敗けた」
荊とは楚のことをさす。
秦王政が婉曲に楚の名称を避けたのは、父王である荘襄王の諱が子楚であるからである。
(なるほど。やはりか)
この時点で、秦王政が秘める心算を看破した。
「それはー。俄かに信じ難い話ですな。李信、蒙恬両将軍は共に勇猛果敢で、私の知る所、斜陽にある楚に彼等を撃ち破るほどの将校がいるとは思えませんが」
事実、項燕が退役してからというもの、楚には柱石といえる軍人は一人もいない。
元来、楚は公室や貴族の力が強い、旧態依然とした国である。長大な領土を有していながらも、新興の国である秦に、大きく差をつけられたのは、旧来の陋習に囚われ、時代の変遷に合わせて、時流の波に乗ることができなかったことにある。
その点、秦では公室、貴族が力を持つ、封建制度の撤廃を推し進め、法による統治を国是とし、外国人を排斥せず登用し、実力主義による論功行賞を確立させた。秦では功績なきものに、禄を食ませることはしない。極論、奴隷でも手柄を上げれば、極官へと登り詰めることができるのである。秦の強さの根底は、封建制の撤廃を推進したことにあるといっても過言ではない。
王翦自身も生え抜きの軍人であり、実力と積み重ねた功績のみで、大将軍にまで登った。李信、蒙恬の両名も同様で、まだ若いが幾度も死線を潜り抜けてきた、千軍万馬の将である。項燕以外の楚の将を思い起こしてみるが、李信、蒙恬を撃ち破れるほどの将の名は上がってこない。
「昌平君、昌文君が叛旗を翻した」
秦王政は苦虫を噛み潰したような顔で言った。眇めた巨眼の奥では、憤怒の烈火が灯っている。
「何と」
隠棲してからというもの、世の情勢をあえて耳に入らないようにしている。宿敵が戦場を去ってから、全てがどうでもよくなったのだ。
両名は共に、長く王を丞相として輔け、彼自身全幅の信頼を置いていたことは、傍目からでも感じていた。だが、両名とも、楚の公子である。祖国の危急が、叛心の萌芽を芽吹かせたのか。これで李信と蒙恬が敗れた理由も明瞭になってきた。恐らく昌平君、昌文君の軍に背後を衝かれたのであろう。
「孤は出陣前に、そなたと李信に問うたな。荊を攻め奪るのにどれほどの兵力が必要かと」
「ええ」
「そなたは、六十万は必要だと答えた。対して李信は二十万で充分だと言ってのけた」
李信は直近の功があった。僅か数千の兵を率いて、秦王政に荊軻という刺客を差し向けた、燕の太子丹を易水で破り、捕縛することに成功している。
当時の問答の様子を回顧する。
「王翦も耄碌したものだ。老いは人を脆弱に変えるな。それに比べ、李信には果敢さと気概が溢れておる」
王翦は秦王政の心ない発言に、大いに気色ばんだのを覚えている。
王翦が六十万と明確な数字を出したのは、老いでも弱腰になった訳でもない。この問答が成された時は、項燕の所在も曖昧模糊としていたし、幾ら斜陽の国であっても、楚には長大な領土があり、練度は低くとも六十万を超える兵卒がいる。王翦からすれば李信の言は、秦王政に阿る為だけの血気に逸った主張と言えた。
李信は時得顔に軽侮を添えた眼で、鼻白む王翦を見遣った。慷慨し理路整然と、李信の主張に反駁するも、秦王政は李信に楚討伐の任を託した。後に王翦は項燕の退役を知り、自身も軍から退くことを決意した。
「孤が間違っていた。結果、二十万の軍勢は覆滅。昌文君は戦死したが、昌平君は三日三晩遁走する、秦軍を追い、七人の将校を殺した」
秦王政が腰に巻く、佩玉が乾いた音を立てる。
握りしめられた拳からは、血が滴っている。
李信の自信に満ちた表情が、恐怖に歪んだ様を想像すると、胸をすくものがある。しかし、それだけのことだ。たとえ、秦王政自ら出向き、謝意を述べられたとしても、もう一度戦場に立とうとは思わない。
「大王様。私は一度、戦場を離れてしまったのです。隠棲の地で安逸を貪るだけの老骨に、一軍を率いることはできませぬ」
「天下統一は目前に迫っている。だが、宿願を南の荊が阻んでいる。孤は宿願を成就させる為にも、一刻も早く荊を滅ぼしたい。憎き荊を伐てるのは、無限の軍略を有する、王翦将軍―。そなたしかいない」
秦王政は怨顔を向け、強く王翦の皺だらけの手を握った。だが、心に揺らぎはない。
「この老い耄れに、大王様の扶翼が務まるとは、到底思えませぬ」
王翦はするりと、秦王政の桎梏から逃れた。
瞬間、秦王政からたちのぼる不敵な気配を感じた。
「王翦将軍。一つ言い忘れていたことがある」
先ほどまで沈んでいた、秦王政の口調には力が蘇っている。
「はて、何でしょう」
「李信、蒙恬を破ったのは、昌平君一人の力ではない」
「それはつまりー」
「昌平君の動きに呼応した男がいる」
王翦は瞠目し、生唾を呑んだ。心臓が早鐘を打っている。
「王翦将軍―。項燕が戦場に戻ってきた」
曲がった背筋が自然に伸び、総身の細胞が快哉を上げた。
「これでも戦場に戻らぬか?次の戦必ず項燕は出てくるぞ」
胸の奥に不要なものとしまいこんだ闘志が蜷局を巻いて、四肢の先にまで沁みわたっていく。
「大王様も意地の悪いことをなされる」
秦王政は破顔し、唇の隙間から鋭利な犬歯を覗かせた。
「将軍。すでに軍人の眼に戻っているぞ」
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

本能のままに
揚羽
歴史・時代
1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった
もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!
※更新は不定期になると思います。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――
黒鯛の刺身♪
歴史・時代
戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。
一般には武田勝頼と記されることが多い。
……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。
信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。
つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。
一介の後見人の立場でしかない。
織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。
……これは、そんな悲運の名将のお話である。
【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵
【注意】……武田贔屓のお話です。
所説あります。
あくまでも一つのお話としてお楽しみください。
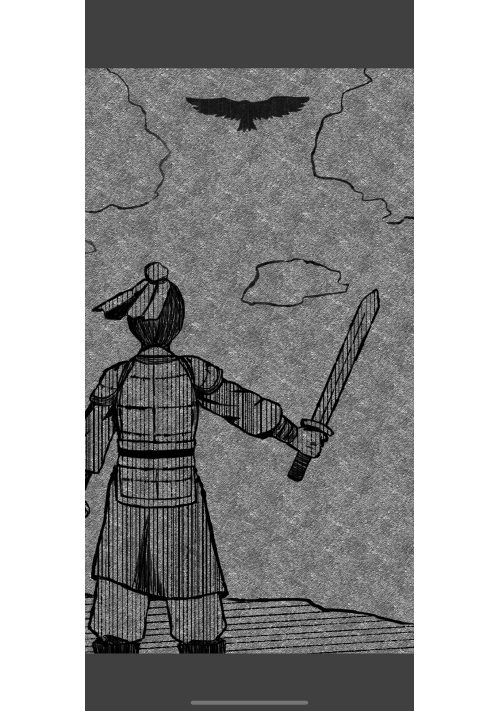
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

旧式戦艦はつせ
古井論理
歴史・時代
真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

幕府海軍戦艦大和
みらいつりびと
歴史・時代
IF歴史SF短編です。全3話。
ときに西暦1853年、江戸湾にぽんぽんぽんと蒸気機関を響かせて黒船が来航したが、徳川幕府はそんなものへっちゃらだった。征夷大将軍徳川家定は余裕綽々としていた。
「大和に迎撃させよ!」と命令した。
戦艦大和が横須賀基地から出撃し、46センチ三連装砲を黒船に向けた……。


猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~
橋本洋一
歴史・時代
この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。
記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。
これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語
※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















