5 / 16
第五章
第五章
しおりを挟むわたしが忍んで半年ほども通い蓐中を求めた家は、國体道路傍の警固神社近く、大名と呼ばれる有明行燈な盛り場の外れになる、隅に寄った奥まったところにあって少し寂然とした気もなくはない場所にあった。
鳥渡、博多の通めかして此の盛り場について述べてみよう。
大名は福岡市中央区の町名で、九州最大の繁華街のひとつ天神の西隣の辺りである。現在は流行の衣料を飾る店や飲食店、玄人筋や狼連などが陽が昇るころまで三斗の酒に浸る房に、雑居ビルが夥しく所在する一方、かつてからの居宅も残っている。細い路地が入り組むところも相俟って、天神とは異なった独特の雰囲気を持つ地域である。江戸時代、福岡城の内堀に面して家老や大組など藩政の重臣たちが居住しており、大組に相当する家臣を「大名」と呼んだことに地名はちなんでいる。いまの区域の地下には「肥前堀」と「紺屋町堀」といった遺構が残っており、往時は福岡城から那珂川にまで伸びていた。
明治時代になると其辺に櫛比していた楊弓場や銘酒屋の類が後に中洲という歓楽街を形成した。中洲には福岡病院(九州大学病院の前身)や博多電灯会社、福岡電話局などが開設される。明治七年には常設の芝居小屋が設立され、三十年代には次々と劇場が建てられた。
さらに大正初期からは活動写真館が続々と立てられて街は発展する。大正十四年には玉屋デパートが開業した。一方、明治三十年からは券番(検番。芸妓と客を取り持つ事務所)が複数設立され、大正時代初期になるとカフェーやバーも増えた。浜新地や南新地などでは白昼、下地っ子に稽古をつける師匠の音締を伴奏に茶音頭や黒髪といった長唄地唄が風に乗って流れる様は趣あるものだが、通行人が悉く袖を引かれて帽子を奪われるようになっては当局も黙っていられなくなる。警察の取締りが厳しくなって、如何わしい店は車の通る表通りから路地の内へと引込まされた。
街の形勢の裏表、時勢に伴う盛衰の変はあるものの目貫処には銀行や郵便局、湯屋に寄席、活動写真館などが軒を並べ、新しくできた大通りにはタクシーの輻輳と屋台と呼ばれる夜店の賑わいが溢れた。大東亜とも太平洋とも呼び名がある戦争の福岡大空襲では、南新地の一部を除く中洲全域が罹災したものの、その年の末からは映画館や劇場などが復活。券番も再開するに伴いスナックやキャバレーも激増した。また赤線、青線といった身の寄せ処がなく、星の流れに身を占う女たちが春を鬻ぐ場所も現れた。その名残りで性風俗や特殊浴場と呼ばれる店や末社たちの姿が、現在の南新地には立ち並んでいる。
お京という姿は現代的であっても、まるで島田や丸髷を結った時代の幻影を纏う風情の女と出遭ったのは、そんな場所近くの夜店屋台であった。
わたしが街を散策する方面を天神の西へと替えて、街外れの際に住むお京の家で週に三、四日を憩うようになってすでに半歳。暦は初夏になるのを知らせ、昼間は暑気に汗ばむほどであった。
わたしが福岡に暫く滞在するに当たっては荷物を預かって貰うだけでなく、必要なときには寝床の用意もしてくれる奇特な宅が筑前前原という、佐賀県寄りの糸島という地にあり、そこから女の処へ遠道を往復したが、初めのころに比べるとだんだんと苦にならなくなった。福岡市営の地下鉄と相互乗換えをして唐津へと続く筑肥線で通うことも、習慣になってしまえば意識より身体が先に動くようになって、こと煩わしいとはおもわない。
其のうち乗客の雑沓する時間や区間が、日によって違うことも明になるもの。之を避けさえすれば、遠道だけにゆっくり本を読んだりして行くことも出来るのである。元来わたしは電車の内での読書は余りしない性質だが、新聞や雑誌など読むには手ごろな時間であった。
天神の驛に着くと大名まで散歩の途すがら、独り者生活に必要なもの、とくに鑵詰といった簡易な食料品などを三日毎には買っていた。ついでと女に贈る土産物をもしばしば買ったが,此事が往訪すること僅にして二重の効果を収めた。安直な食べ物ばかりを買うのみならず、上着やシャツで取れかかった釦の繕いを願ったりすると、いよいよにお京はわたしを独身との確信を深めたのである。ならば頻繁に遊びに行っても一向不審はないとなろう。また芝居や活動を観ることもなく、行く処がないというようにもおもう筈がない。それらについて言い訳をせずとも自然にうまく行ったのだが、金の出処については疑いをかけられはしまいかと場所柄だけにそれとなく質問をしてみた。すると女は其晩払うものさえ払ってくれさえすれば、他の事などてんで考えていないと云う様子であった。
「遣う人は随分と遣うわ。まる一ト月くらい居続けしたお客もあったわね」
「ほう。ここにかい。無用心じゃないか」
わたしは驚いた顔をして見せた。
「警察へ届けなくってもいいのか?吉原や飛田なんぞだと直に届けると云うぞ」
「此の土地でも、家によっちゃあ、するかも知れないわ」
「その居続けた客は何者だったね?泥棒か、それとも極道者か」
「呉服屋さんだったわ。とうとう店の檀那さんが来て連れて帰ったけれど」
「なるほど。勘定の持ち逃げってやつか」
「そうでしょう」
「おれは大丈夫だよ。其方は」
わたしの言葉に、女はどちらでも構わないという顔で聞き返しもしなかった。
然しわたしの職業については、お京はとうから勝手に決めているらしい。前に店の方まで出向いたとき、古風な和の設えの部屋に通されたが、そこの襖には半紙四つ切程の大きさで復刻された浮世絵の美人画が張り混ぜにしてあった。其の中には歌麿の鮑取り、豊信の入浴美女といった艶気のある絵が見れたので委しく説明してやったことがある。
又、お京が別の客と部屋に入ってるときに、応接室風の待機部屋で手慰みに置いてあった紙片にペン先を流し、春画もどきの猥雑な戯画を描いているのをチラと見て、てっきり其の手の出版物に係わる業の男とおもったようだ。次に来るとき何か描いたものを持って来てほしいと言い出すので、かつての仕事で残したものの中から裸婦画のいくつかを請われるままに一度持って行くと、ここに至るまでわたしの職業について言わず語らずと決められたようになった。
お京の胸のうちで悪銭の出処がそうと明瞭になったようで、すると態度は一層打ち解けて、いつしか全く客扱いではなくなった。
日蔭に住む女達が世を忍ぶ後暗い男に対するとき、恐れもせず嫌いもせず必ず親密と愛憐との心情を起こす事は、夥多の実例に徴して深く説明するに及ぶまい。鴨川の芸妓は幕吏に追われる志士を救い、寒驛の酌婦は関所破りの博徒に旅のお足を恵むのを辞さなかった。トスカは逃竄の貧士に食を与え、三千歳は無頼の徒に恋愛の真情を捧げて悔いはなかった。
ともあれ、此れに於いてわたしの憂慮するところは女の家付近で、若しくは通う電車の中で顔見知りと出くわすことである。此の他の人達には何処で会おうと一向に差閊はない。謹厳な人達からは若年の頃より相容れぬ、見限られた身である。全くのところ憚る心配はなかった。
面倒なのは操觚の士である。昔を知る儕輩なんぞ偏頗に世間の秤を鞠躬如なまで気に病み、毛色が違う者を揣摩憶測で面白可笑しく噂をして陥れようとする。わたしが夜竊に大名の辺で遊ぶを探知したなら、何事を吹聴するやらだ。
しかし、それもよしとしよう。只独恐る可きは別にあったが、それは此の話とは関係ないので省かせてもらう。但し、わたしは毎夜電車の乗り降りから遊里に入り込んで夜店が賑わう表通りはだけでなく、路地の小径でさえも前後左右に気を配って歩かなければならない事情があった。正に世を忍ぶ隠密者という面を持っていたというのを覚えていただければ可である。
続
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

今日の授業は保健体育
にのみや朱乃
恋愛
(性的描写あり)
僕は家庭教師として、高校三年生のユキの家に行った。
その日はちょうどユキ以外には誰もいなかった。
ユキは勉強したくない、科目を変えようと言う。ユキが提案した科目とは。
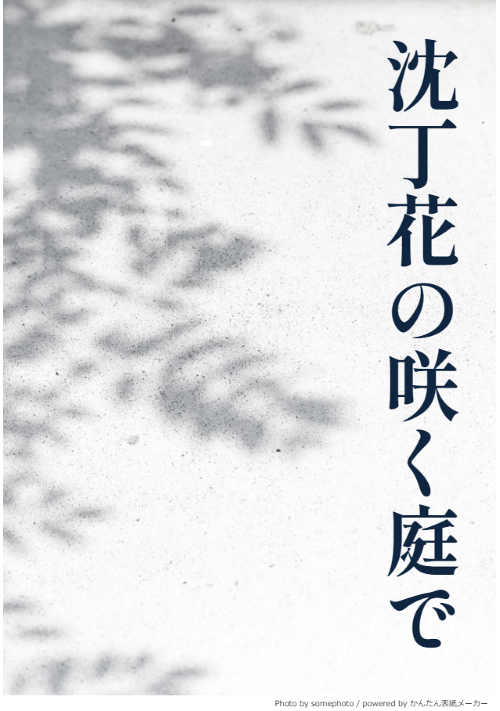

後悔と快感の中で
なつき
エッセイ・ノンフィクション
後悔してる私
快感に溺れてしまってる私
なつきの体験談かも知れないです
もしもあの人達がこれを読んだらどうしよう
もっと後悔して
もっと溺れてしまうかも
※感想を聞かせてもらえたらうれしいです


パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?
すずなり。
恋愛
ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。
「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」
家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。
「私は母親じゃない・・・!」
そう言って家を飛び出した。
夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。
「何があった?送ってく。」
それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。
「俺と・・・結婚してほしい。」
「!?」
突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。
かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。
そんな彼に、私は想いを返したい。
「俺に・・・全てを見せて。」
苦手意識の強かった『営み』。
彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。
「いあぁぁぁっ・・!!」
「感じやすいんだな・・・。」
※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。
※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。
それではお楽しみください。すずなり。

黒庭 ~閉ざされた真実~
五十嵐 昌人
ホラー
未解決の迷宮入りした”ある事件”に対して異常な執着を示した若い刑事が
担当を願い出たまでは良かったが調べていく内に、とんでもない事実が
発覚して危険に身を投じる事となる。閉ざされた真実とは一体何なのか?
事件は無事に解決できるのか!?
そこも見所となっておりますので完結までお付き合い下さる事を願って
おります。ヒリヒリ感を増していく展開と毒素を含む内容となっており
ますので苦手な方は御遠慮ください。
2022年12月1~31日までTwitterと連動企画します!
詳しくは近況ボードにて確認下さい。
皆様、今年も後1ヶ月と少しですが宜しくお願いします!
お気に入り登録&感想(短くてもOKです)も、お待ちしております♪
*毎年(節目)、読み返してみると好きなキャラが変わったり、感じ方
や受け取り方も違ってくる内容となっております。

六華 snow crystal 2
なごみ
現代文学
雪の街、札幌を舞台にした医療系純愛小説。part 2
彩矢に翻弄されながらも、いつまでも忘れられずに想い続ける遼介の苦悩。
そんな遼介を支えながらも、報われない恋を諦められない有紀。
そんな有紀に、インテリでイケメンの薬剤師、谷 修ニから突然のプロポーズ。
二人の仲に遼介の心も複雑に揺れる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















