11 / 15
シャネイたち2
しおりを挟む
「ドーリ、サビー!」
二人が木から降てゆくと、隠れていた少年たちとリミーが駆け寄ってきた。
「どうだった?」
「もう大丈夫なの?」
「やつらはいなくなった?」
抱きついてくるリミーの頭を撫でて、ドーリは皆に安心させるようにうなずきかけた。
「大丈夫だよ。あいつらはいっちまった。もう大丈夫さ」
「俺たちは怖くなかったよ。な、フーラ」
「な、ギムシ」
「でもリミーったら、一番怖がりなんだもの」
「そうそう、ナミンだって泣かないでじっとしていたのにな」
この中で一番小さなナミンが、こくこくと得意気にうなずいてみせる。
「よせよ、お前ら。リミーは女の子なんだからな」
少年たちのリーダーであるサビーが言った。
「そうさ。それにこの子はね、たくさんつらいことがあったんだから……」
ぎゅっとしがみつて離れない少女の頭を、ドーリはやさしく撫でつける。
「思い出しちまったのかい?怖い記憶を」
少女がこくりと小さくうなずく。
「大丈夫。もう大丈夫だよ。あたしがついてる。あいつらはいっちまったんだ。もう来ないから」
「ドーリ、もしかして、リミーは兄さんのことを……」
言いかけたサビーは、口に指をあて首を振るドーリを見て、黙ってうなずいた。
「ねえ、サビー、兵隊を見たんでしょ?どうだった?」
「どうだった?怖そうだった?あいつら」
「やっぱりでっけえ武器とか持ってたんだろ?」
「あ、ああ……」
少年たちがサビーを取り囲んで質問をあびせる。サビーは、困ったようにただうなずくだけだった。まるで彼は、なにか心にかかる考え事でもあるように、ぼんやりと視線をさまよわせていた。
「さ、もう戻ろうか。もうじき暗くなるよ」
リミーが落ち着くのを待ってから、ドーリはそうきりだした。
「村へ戻って夕御飯だ。でもお前たち、母さんたちにしかられて飯ぬきになっても泣くんじゃないよ」
「いいもん。そうしたらドーリの家に食べにいくから」
「そうそう、ドーリのご飯たべるー」
「馬鹿いってんじゃないよ。あたしだって、炊事の途中できちまったんだから、オダーマに怒られてあたしも飯ぬきかもしれないよ」
危険が去ったことで緊張もなくなり、丘を下る少年たちはドーリと並んで歩きながら、楽しそうに笑い合っていた。
「嘘だあ。オダーマは怒らないよ。だってオダーマはやさしいもの」
「そうさ。それにオダーマはドーリが大好きだから。きっと怒らないよ」
「愛しあってるんだもんねえ」
「こら。こどものくせに、なんとまあ生意気なことをいう」
ドーリは笑いながら少年たちの頭を小突くふりをした。キャアと声を上げる少年たち。ふとリミーが振り返ると、サビーは一人うつむきかげんに少年たちのあとを歩いていた。その手には使うことなく済んだ愛用の弓がぶらさがっている。
「……とにかく、みんなの母さんたちにはあたしから言っといてやるよ。ジャリア兵を見にいったなんていったら大目玉だろうから、ちょっと丘に遊びに行って遅くなったとでもしておこうかね」
ジャリアの一隊が通りすぎた街道には、軍馬が通った蹄のあとがまだ生々しく残っていた。そこをはしゃぎながら横切る少年たちから、ドーリはふと街道の先に目を移した。もちろんジャリア兵の姿などは、もうその流旗の一片すらも見つけられない。すっかり暗くなった夕闇のなか、街道の先はただ黒々とした森が広がるばかりだった。
「ドーリ」
少年たちは街道を渡って村へと続く丘を登っていたが、ドーリがその声に振り向いたとき、サビーは街道の真ん中で足を止め、ぽつんとそこに立っていた。
「おや、なんだい?あんた、まだそんなところにいたのかい」
「ああ……」
「早くお行きよ。ほら、あの子らはもう村へ着いちまうよ」
「う……うん」
うつむいたまま曖昧な返事をする少年の様子に、ドーリは首をかしげた。
「なんだい、元気ないね。ジャリア王子を弓矢で狙おうかってあんたが。もしかして、さっきのあたしの話をまだ気にしているのかい?だったらもう忘れていいよ。そんなに考え込むことじゃ……」
「違うんだ……」
少年は首を振り、なにか言いたそうにこちらを見た。
「あの……さ、ドーリ」
「うん?どうしたんだい?」
「ちょっと、話すことがあるから……」
普段は明るく快活な少年が、今は奇妙ににおずおずとしている。ドーリはふと眉を寄せた。
「ドーリー、早くー」
「あんたたち、先に村に帰っといで。あたしらもすぐ行くから」
丘の上から手を振る少年たちにそう言うと、ドーリはサビーに目をやった。少年は意を決したように口を開いた。
「ドーリ……あの、オダーマを呼んでくるように言ってよ」
「なんだって?」
「いや、オダーマでなくてもいい。サダルでも……そうだラビでもいい。とにかく大人の男を来させてよ」
「いいよ……分かった」
ドーリは少年の様子から、これがただごとではないと悟ると、もう一度丘の上の子供たちに声をかけた。
「お待ち。トルーク、あんたみんなを村まで送っていったら、ちょっとあたしの家に行って、オダーマに伝えとくれ。ちょっと遅くなるからって」
「分かったー」
丘の上からトルークが手を振った。
「それから……、そうだね、ラビに、すぐにここに来るように言っておくれ」
「ドーリ、ここじゃなくて、赤石の水車小屋のあたりがいい」
横からサビーが言うのにうなずき、ドーリは言いなおした。
「トルーク。ラビに赤石の水車小屋にすぐ来るように言っておくれ」
「分かったよー。オダーマには遅くなるって、ラビには来るようにって言うよ」
少年たちが村の方へ消えてゆくのを見送り、ドーリはサビーに向き直った。
「さて……話してちょうだい。どうやらなにかあるようだけど?」
「ああ……そうなんだ。もしかしたら、だけど……」
サビーはうなずき、その顔をまっすぐ年長のシャネイに向けた。
「隣村……南のレンゼー村のリンジたちを知ってるよね」
「ああ、あの悪ガキども。あんたらとよく一緒になって遊んでたね。それがどうかおしかい?」
「うん。水車小屋まで歩きながら話すよ。すぐにラビが来るだろうから」
「いいよ。そうしよう」
二人はさきほどジャリア兵の一隊が消えていった方向へ、街道を歩きはじめた。
人間にすればかなりの早足で歩きながら、サビーは事の次第を語りだした。
「今日のこと、つまり、ジャリア兵と、うまくすれば王子を殺そうという計画は、ただの遊びじゃなくて、けっこう本気だったんだよ」
「ああ……それで?」
「それで、俺たち……俺とトルーク、そしてレンゼー村のリンジたち、どっちがうまくやるかを競争していたんだ……」
「なるほどね。ということは、レンゼー村の悪ガキどもも、あんたたちみたいに無茶なことをするってわけかい?」
「ああ、やると思う。あいつらの方がずっと人数多いし……、俺たちは、俺とトルーク以外は、ただおまけにくっついてきただけだけど、あっちはもっと大がかりみたいなんだ。この前会ったときにちょっと教えてくれたけど、リンジは『俺たちは強力な長弓を作ったんだぜ。こいつなら鎧だって貫通できる。見てろよ。必ず残虐王子の首をとってやる』って言っていた。なんだか向こうは村の大人も何人かそれに協力しているみたい」
「まったく、なんてことだろう……」
ドーリは苦々しくつぶやいた。
「馬鹿なことを……、もし誰かか止めなかったら……」
「それにそろそろ、ジャリア軍がレンゼー村の近くを通るころだよ」
「それでラビを呼びに……」
「うん、オダーマでもいいけど、ラビの方が危険なこととかに慣れてるでしょう?もしレンゼー村がジャリア兵に襲われたりしたら……」
ドーリは立ち止まり、表情を険しくして少年を見た。
「あんた。ここからすぐお帰り。話してくれたからもう怒りはしないよ。でもここまでだ。レンゼー村へはラビに行ってもらう」
「そんな。いやだよ」
「駄目だ。もし、本当に村が危険な状態だったら、どうするんだい」
「大丈夫だよ。俺もう子供じゃないよ。弓だって使えるし、剣だって少しは……」 「サビー」
ドーリは声を強めたが、少年は臆することなく言った。
「ドーリ。俺は行くよ」
「サビー……」
「俺はもう子どもじゃない。自分の命は自分で守るし、その責任ももう自分でとるよ」
そう言った少年の顔を、ドーリはじっと見つめた。
「それに、俺はいかなくちゃ。リンジたちは友達だよ。あいつらだって、みんな、仲間のためを思ってやろうとしているんだ。俺だってそうだ。でも、さっきドーリの話を聞いて、俺は分かったよ。こんなやり方では何も変わらないって」
「サビー……お前」
少年はうなずいた。その目の光は強く、まっすぐにドーリに向けられていた。
「だから……俺はリンジたちをとめなくちゃ。今から走っていけば、もしかしたら間に合うかも知れない。リンジたちには俺から言わなくちゃ駄目なんだ。あいつらのやろうとしていることも、俺のやろうとしたことも、それは本当に危険なことで、全部の村に関わる大変なことなんだって。俺から言わなくちゃ……」
「そう……そうだね。そうかもしれない」
それまでただのいたずら好きの子どもだった少年が、にわかに大人になりつつあったことを、ドーリは初めて知った。ほんの数年前はもっとずっと小さかったのに、今では背丈はドーリとほとんど変わらない。普段はやんちゃで、よく笑うその顔は、今はまるで青年のように引き締まって見える。
「それにさ……」
落ち着いた笑顔とともに、サビーは言った。
「もしかしたら、リンジたちも今頃、俺みたいに誰かに止められて、こっぴどく怒られているかもしれないしね」
「ああ、そうだね。そうだったら、ただの取り越し苦労ってもんだ」
二人は顔を見合わせて笑った。
街道を南に少しゆくと、川べりの小さな水車小屋がある。近隣のいくつかのシャネイ村が、粉挽きのために使用する共同の小屋だ。二人が小屋の前で待つと、ほどなくしてこちらに駆け寄ってきたのは、同じ村の青年、ラビだった。
「ラビ、早かったね」
相当なスピードで走ってきたのか、シャネイの若者は何度か息をついてうなずいた。
「夕食中だったが、ほっぽらかして走ってきた。ドーリが大急ぎで呼んでいると、子供らが言うのでな」
女や年寄りの多い彼らの村では、ラビは一番頼れる若者だった。すらりと背が高く、力持ちで機転もきく。かつては自警団で剣を習っていたこともある。彼にとって、村長オダーマの妻であるドーリは、ほとんど家族にも近い存在であった。
「どうした?ドーリ、何があった」
「すまないねえ、ラビ。急がせちまって。カナリは驚いてなかったかい」
「大丈夫さ。俺の嫁は勇気がある。慌てて飛び出そうとする俺に……ほら、こうして水筒と、もしものための短剣、包帯やら薬草なんかを持たせてくれたよ」
若者は腰に縛りつけた皮袋を見せた。
「それにしても、子供たちが大騒ぎで村に帰ってきたので、みんな仰天してオダーマの所に駆け込んでいるぞ。しかも、オダーマの家にドーリがいないので、みんな何があったのかと心配している」
「あら、いやだ。あの子たちったら、そんな大げさな。オダーマは何か言っていた?」
「いや、オダーマはまず皆を落ちつかせて、ドーリの言うとおり、俺に様子を見に行かせようと言った。皆が慌てることはまだ何も起こっていないと。それで俺に向かって、ドーリとサビーを頼む、自分は村長の責任があるゆえ、村を離れられない。何かあったときはすぐ対処できるようにしておくから、二人をくれぐれも頼むと」
「さすがはオダーマ」
ドーリは満足そうにうなずいた。
「あたしが見込んだ男だわ。それでこそ。それじゃあ、村の方はまず安心ね」
「ねえ、ドーリ。こんな所に立ち止まっていても仕方ないよ。歩きながら話そう。早くレンゼー村へ行かないと」
「おお、そうだ。そうだね。行こう」
「レンゼー村へ?いったい何があったんだ?」
ラビが眉をひそめた。その長い耳がピンと立つ。
「まさか、さっき通りすぎたジャリア軍の一隊となにか関係があるのか?」
「そうさ」
ドーリがうなずく。
「もしかしたら……大変なことが起こるかも知れないんだよ。まだ分からないけど。とにかく、行こう。ラビ、あんたが先頭にたって」
「わかった。レンゼー村だな」
ラビを先頭に、三人は街道を走り出した。
夕闇に包まれた街道の周りには、黒々とした森や山々が広がっている。このあたりにはいくつものシャネイ村が隣接しており、リンゼー村は彼らの足なら走ってほんの半刻ほどの距離であった。
「なるほど……そういう、ことか」
少年とドーリから話を聞いたラビは、顔つきを険しくした。
「それはまずい。俺は知ってる。あの黒竜王子を。一度ラハインの宮廷に小麦を届けに行ったとき、俺は近くであの王子の顔を見た」
街道の印石がかろうじて見えるくらいの夕闇の中を、三人は軽やかな足どりで走り抜けてゆく。シャネイの視力はとても強く、夜闇の中であっても、地面の石ころも、突き出した木々の枝も、はっきりと見分けられる。
「あの王子の目……なにも映さない、まるで感情のない目。あの目が、俺は心底恐ろしかった。特に俺たちシャネイを見る目つきは、とうてい人間を見る目つきとは思えなかったよ。言葉の通じぬ動物を見るような、蔑みも越した冷たい目つき。まるで道端の石ころでも見るように俺を見た、あの目を見たとき……俺は知ったのだ。残虐王子という名は、決して大げさなものではないのだと。あの王子からすれば、きっと俺たちを殺すことなどには何も意味を持たない。豚や猪を殺すように奴らは我々を狩り、殺してゆくだろうと」
「そういえば、たしか、あんたの妹と両親も……」
「ああ、前の村で殺された。あのときも王子の配下の部隊が通りかかって、ちょっとしたことで奴らの怒りをかい、戦いになり、そして……村は壊滅した。生き残ったのは老人とほんの数人の女子供だけだった」
前をゆくラビの声がかすかに震えるのを、サビーは聞いた。
「いけない……いくら子どもたちのすることとはいえ。あいつらは決して容赦しない。早く……早く止めないと」
「いやだよ。リンジたちが、みんな兵隊にやられちゃうなんて。そしたら俺……俺……」
「サビー。まだそうと決まったわけじゃないよ。あんたも言っただろう。あの悪ガキどもも、お前みたいに今頃は誰かに止められて、こっぴどく叱られているかもしれないって。あたしたちが村に着いてみたら何も起こっておらず、レンゼーの人たちが笑いながら、よく来たねって、みやげにに白パンでもくれて、あったかい豆のスープをごちそうしてくれるかもしれないよ。そうさ。なにも……なにも起こっていないよ、きっと……ね」
ドーリの言葉は、自分自身に言い聞かせるようなつぶやきに変わった。夜の街道を走る三人の足取りは、なにかに急かされるように、しだいに速くなっていった。
「村はもうすぐだ。あの橋を渡れば……」
遠くに小さな光が見えはじめていた。川の向こうにレンゼー村はある。
「あっ」
「な、なんだあれは」
サビーとラビが同時に声を上げた。
「あれは……」
ドーリも息を呑んだようにつぶやいた。
村の明かりとおぼしき光が、しだいに大きくなっていた。
その光は、ひとつ、ふたつ、みっつと、見る間に増えてゆく。
三人は橋の手前で立ち止まっていた。
「あれは……火だ!」
ラビが叫んだ。
「まさか。まさか……」
ドーリが口の中でつぶやく。
村が燃えている。
耳を澄ますと、村の方向からはごうごうという炎の音が聞こえ、それに混じって、なにかが起きているらしい喧騒の空気が伝わってくる。
いったい何が起こっているというのか。三人は言葉を失って立ち尽くした。
黒い夜空に燃えさかる火柱が上がる。
「あっ、お待ち。サビー!」
ドーリが止めるまもなく、少年は村に向かって走り出していた。
「ラビ、サビーをとめて!」
二人のシャネイは少年の後を追って、赤々とした炎に包まれつつある橋の向こうへ走り出した。
それより少しまえ……
街道をゆくフェルス王子と四十五人隊の一行は、一定の速度を保ちながら粛々と行軍していた。
ときは夕暮れどき。しばらくは両側を丘に挟まれた狭い道が続くことから、隊列は横三列となり、その中ほどに王子を守る長い隊形をとっている。隊列を組む一人一人の騎士は、兜の面頬を下ろし、槍を手に、無機質なほどの不気味な静かさで巧みに馬を操る。その様子はまるで、機械仕掛けの軍隊のようであった。
「異常ありません」
先行させていた斥候の騎士の報告を受け、馬上の王子はゆったりとうなずいた。王子の後ろには巨漢のザージーンの乗る馬が影のように付き従う。
「どうやら、今回はシャネイどもはおとなしいようですな」
馬を寄せてきたのは、副官のジルト・ステイクだった。
「あの低能なサルたちも、少しは利口になったということですかな」
「さあ、どうかな」
王子は意味ありげに言うと、街道の彼方へ目を向けた。
しだいに暗さを増してゆく黄昏の空。丘の向こうに沈みゆく、夕日の最後の残照とともに、王子と騎士たちは馬を歩ませる。
「フェルス殿下」
しんがりをつとめていた副隊長、ノーマス・ハインが報告に来た。
「どうした」
「は、すでにお気づきになっているかとも思いますが……」
若き副隊長は面頬を上げると、馬上から街道の両脇に目をやった。
「どうも静かすぎます」
「そうだな」
「いつもであれば、シャネイどもが街道わきから隊列を見物しているはず。この辺りは奴らの村が点在していますから」
「確かにな」
副隊長の言葉をうけ、王子も鋭い視線を道の左右に向けた。
ジャリアの首都ラハインから南部へ下る街道は他にもあるが、丘陵地帯を迂回せずにすむこのルートが時間的には一番ロスが少ない。周囲に多くのシャネイ村の存在するこの辺りでは、これまでにも街道を下るジャリアの兵隊、商隊などが襲撃を受ける事件が何度かあった。数年前から取り締まりを厳しくしたこともあり、ここ最近では目立った被害は少なくなってきていたが、それでもやはりジャリア兵士がこの街道を通りかかると、両脇の丘の上には居並んだシャネイたちが、とくに何も仕掛けてくるわけではないが、ただじっとこちらを見張っているということが常だったのだ。
「かえって怪しむべき静けさという気もします。行軍速度を少し速めれば、日が暮れる前にはこの地帯を抜けられますが」
「的確な判断だな、ノーマス。お前ももう立派な副隊長か」
「おそれいります」
若い騎士は嬉しそうに笑顔を見せた。
「よかろう。ではお前に任せる。先頭に立て。しんがりは別のものに任せよう」
「はっ」
「では、行軍速度二から三へ。同時に第二種警戒!」
ノーマスの発した命令が、隊列全体へと伝わってゆく。
「行軍二から三へ。第二種警戒」
「了解」
後尾で伝令確認の流旗が上がると、先頭の列からゆるやかに速度を上げはじめる。面頬を上げていたものは下ろし、隊の外側のものは距離をややせばめて密集する。相当に訓練されなければ出来ない動きである。
「ザージーン、兜をとれ」
王子が命じると、ザージーンは黙ってヘルムを脱いだ。頭髪を剃りあげ、浅黒い肌をした顔があらわになる。
「そのまま、できるだけ俺の馬に近づいていろ」
男は無表情のまま、言われたとおり、その巨体を乗せた馬を器用に操って、王子の馬のすぐ後に続いた。その剥き出しのいかつい顔は、大きな体躯と相まって、統一された鎧兜姿の隊列でひどく目立った。
「よし」
王子は満足そうにうすく笑いをうかべた。
速度を上げた隊列は街道を進んでいった。騎士たちの警戒をよそに、周囲にはまったく異変の予兆はなく、ただ静かで、暮れなずむ空のもとを、馬蹄の音が規則正しく響いてゆく。
街道はしだいに両側から丘に挟み込まれるようにして狭まり、さらに視界が悪くなった。ここを抜ければ丘陵地帯も終わり、ぐっと道はひらけてくるはずである。
隊列を組む騎士たちは、引き続き警戒をしつつ進んでゆくが、その緊張がいくらか惰性に変わった頃だったろうか。
突然、ガッという、石矢が鎧に当たる音とともに、王子のすぐそばの騎士が声を上げた。
「わあっ」
「どうしたっ!」
ひゅん
ひゅん
続けざまに、矢が空気を切り裂く音がいくつも鳴った。
「敵か?」
「弓だぞ!」
何本もの矢が兜や鎧にはね返され、そのうちのいくつかが馬に突き刺さった。つんざくようないななきが、静寂を破って辺りに響き渡る。
「これは長弓だぞ。気をつけろ。鎧にも突き刺さる」
「落ちつけ!隊列を崩すな。王子殿下をお守りしろ!」
それぞれに叫びながらも、さすがに訓練されたジャリアの騎士たちは、そう大きな狂乱に陥ることはない。一瞬の狼狽から立ち直ると、すぐに隊列を立て直す。
「丘だ、両側の丘の上からだ」
「シャネイどもの攻撃だ」
「殿下。危険ですから、どうか馬上にお伏せください」
「うろたえるな。栄えある四十五人隊の勇敢な騎士たちよ。我らはジャリア軍でも精鋭中の精鋭ぞ。いかに夜目がきくシャネイとはいえ、しょせん数にも力にも足りぬ」
王子は馬上で微動だにせず、騎士たちを叱咤した。そのすぐ後ろにいるザージーンの顔を、ぴゅんと矢がかすめる。
「殿下、ご無事で!」
馬で走り寄ってきたノーマスが、王子を庇うように前に出た。
「どうやら、狙われているのは隊列の中央のみのようです」
「なるほど。つまり、やつらは俺を狙っているわけだな」
王子はにやりと笑った。
その間にも、ひゅんひゅんと、いくつもの矢が至近距離をかすめてゆく。夕闇の中でも目が利くのだろう、放たれた矢は驚くほど的確に王子を狙っているようだった。
「王子、どうか頭をお低く。ザージーンは後ろをお守りしろ!」
ザージーンの兜をかぶらぬ剥き出しの顔を見て、ノーマスは眉をひそめた。
「王子、ザージーンの兜を……。敵に御身の場所を教えましたか」
「ノーマス」
兜の奥で、王子はあやしく目を光らせた。
「我に危害をなさんとする野卑な民どもに、今一度、思い知らせてやるときだな」
「王子……」
むしろ穏やかですらある王子の声に、ノーマス・ハインは思わず息をのんだ。
「ここに近いシャネイ村はどこか」
「は、はっ。いちばん近いのは、レンゼー村かと。五百人以上の比較的大きな村で……」
「よかろう」
王子はすっと手をかざした。
「騎士たち、流旗を上げよ」
鋭い声が隊列に響きわたった。
「戦闘開始!シャネイどもの村へ。焼き払え。みなごろしだ」
二人が木から降てゆくと、隠れていた少年たちとリミーが駆け寄ってきた。
「どうだった?」
「もう大丈夫なの?」
「やつらはいなくなった?」
抱きついてくるリミーの頭を撫でて、ドーリは皆に安心させるようにうなずきかけた。
「大丈夫だよ。あいつらはいっちまった。もう大丈夫さ」
「俺たちは怖くなかったよ。な、フーラ」
「な、ギムシ」
「でもリミーったら、一番怖がりなんだもの」
「そうそう、ナミンだって泣かないでじっとしていたのにな」
この中で一番小さなナミンが、こくこくと得意気にうなずいてみせる。
「よせよ、お前ら。リミーは女の子なんだからな」
少年たちのリーダーであるサビーが言った。
「そうさ。それにこの子はね、たくさんつらいことがあったんだから……」
ぎゅっとしがみつて離れない少女の頭を、ドーリはやさしく撫でつける。
「思い出しちまったのかい?怖い記憶を」
少女がこくりと小さくうなずく。
「大丈夫。もう大丈夫だよ。あたしがついてる。あいつらはいっちまったんだ。もう来ないから」
「ドーリ、もしかして、リミーは兄さんのことを……」
言いかけたサビーは、口に指をあて首を振るドーリを見て、黙ってうなずいた。
「ねえ、サビー、兵隊を見たんでしょ?どうだった?」
「どうだった?怖そうだった?あいつら」
「やっぱりでっけえ武器とか持ってたんだろ?」
「あ、ああ……」
少年たちがサビーを取り囲んで質問をあびせる。サビーは、困ったようにただうなずくだけだった。まるで彼は、なにか心にかかる考え事でもあるように、ぼんやりと視線をさまよわせていた。
「さ、もう戻ろうか。もうじき暗くなるよ」
リミーが落ち着くのを待ってから、ドーリはそうきりだした。
「村へ戻って夕御飯だ。でもお前たち、母さんたちにしかられて飯ぬきになっても泣くんじゃないよ」
「いいもん。そうしたらドーリの家に食べにいくから」
「そうそう、ドーリのご飯たべるー」
「馬鹿いってんじゃないよ。あたしだって、炊事の途中できちまったんだから、オダーマに怒られてあたしも飯ぬきかもしれないよ」
危険が去ったことで緊張もなくなり、丘を下る少年たちはドーリと並んで歩きながら、楽しそうに笑い合っていた。
「嘘だあ。オダーマは怒らないよ。だってオダーマはやさしいもの」
「そうさ。それにオダーマはドーリが大好きだから。きっと怒らないよ」
「愛しあってるんだもんねえ」
「こら。こどものくせに、なんとまあ生意気なことをいう」
ドーリは笑いながら少年たちの頭を小突くふりをした。キャアと声を上げる少年たち。ふとリミーが振り返ると、サビーは一人うつむきかげんに少年たちのあとを歩いていた。その手には使うことなく済んだ愛用の弓がぶらさがっている。
「……とにかく、みんなの母さんたちにはあたしから言っといてやるよ。ジャリア兵を見にいったなんていったら大目玉だろうから、ちょっと丘に遊びに行って遅くなったとでもしておこうかね」
ジャリアの一隊が通りすぎた街道には、軍馬が通った蹄のあとがまだ生々しく残っていた。そこをはしゃぎながら横切る少年たちから、ドーリはふと街道の先に目を移した。もちろんジャリア兵の姿などは、もうその流旗の一片すらも見つけられない。すっかり暗くなった夕闇のなか、街道の先はただ黒々とした森が広がるばかりだった。
「ドーリ」
少年たちは街道を渡って村へと続く丘を登っていたが、ドーリがその声に振り向いたとき、サビーは街道の真ん中で足を止め、ぽつんとそこに立っていた。
「おや、なんだい?あんた、まだそんなところにいたのかい」
「ああ……」
「早くお行きよ。ほら、あの子らはもう村へ着いちまうよ」
「う……うん」
うつむいたまま曖昧な返事をする少年の様子に、ドーリは首をかしげた。
「なんだい、元気ないね。ジャリア王子を弓矢で狙おうかってあんたが。もしかして、さっきのあたしの話をまだ気にしているのかい?だったらもう忘れていいよ。そんなに考え込むことじゃ……」
「違うんだ……」
少年は首を振り、なにか言いたそうにこちらを見た。
「あの……さ、ドーリ」
「うん?どうしたんだい?」
「ちょっと、話すことがあるから……」
普段は明るく快活な少年が、今は奇妙ににおずおずとしている。ドーリはふと眉を寄せた。
「ドーリー、早くー」
「あんたたち、先に村に帰っといで。あたしらもすぐ行くから」
丘の上から手を振る少年たちにそう言うと、ドーリはサビーに目をやった。少年は意を決したように口を開いた。
「ドーリ……あの、オダーマを呼んでくるように言ってよ」
「なんだって?」
「いや、オダーマでなくてもいい。サダルでも……そうだラビでもいい。とにかく大人の男を来させてよ」
「いいよ……分かった」
ドーリは少年の様子から、これがただごとではないと悟ると、もう一度丘の上の子供たちに声をかけた。
「お待ち。トルーク、あんたみんなを村まで送っていったら、ちょっとあたしの家に行って、オダーマに伝えとくれ。ちょっと遅くなるからって」
「分かったー」
丘の上からトルークが手を振った。
「それから……、そうだね、ラビに、すぐにここに来るように言っておくれ」
「ドーリ、ここじゃなくて、赤石の水車小屋のあたりがいい」
横からサビーが言うのにうなずき、ドーリは言いなおした。
「トルーク。ラビに赤石の水車小屋にすぐ来るように言っておくれ」
「分かったよー。オダーマには遅くなるって、ラビには来るようにって言うよ」
少年たちが村の方へ消えてゆくのを見送り、ドーリはサビーに向き直った。
「さて……話してちょうだい。どうやらなにかあるようだけど?」
「ああ……そうなんだ。もしかしたら、だけど……」
サビーはうなずき、その顔をまっすぐ年長のシャネイに向けた。
「隣村……南のレンゼー村のリンジたちを知ってるよね」
「ああ、あの悪ガキども。あんたらとよく一緒になって遊んでたね。それがどうかおしかい?」
「うん。水車小屋まで歩きながら話すよ。すぐにラビが来るだろうから」
「いいよ。そうしよう」
二人はさきほどジャリア兵の一隊が消えていった方向へ、街道を歩きはじめた。
人間にすればかなりの早足で歩きながら、サビーは事の次第を語りだした。
「今日のこと、つまり、ジャリア兵と、うまくすれば王子を殺そうという計画は、ただの遊びじゃなくて、けっこう本気だったんだよ」
「ああ……それで?」
「それで、俺たち……俺とトルーク、そしてレンゼー村のリンジたち、どっちがうまくやるかを競争していたんだ……」
「なるほどね。ということは、レンゼー村の悪ガキどもも、あんたたちみたいに無茶なことをするってわけかい?」
「ああ、やると思う。あいつらの方がずっと人数多いし……、俺たちは、俺とトルーク以外は、ただおまけにくっついてきただけだけど、あっちはもっと大がかりみたいなんだ。この前会ったときにちょっと教えてくれたけど、リンジは『俺たちは強力な長弓を作ったんだぜ。こいつなら鎧だって貫通できる。見てろよ。必ず残虐王子の首をとってやる』って言っていた。なんだか向こうは村の大人も何人かそれに協力しているみたい」
「まったく、なんてことだろう……」
ドーリは苦々しくつぶやいた。
「馬鹿なことを……、もし誰かか止めなかったら……」
「それにそろそろ、ジャリア軍がレンゼー村の近くを通るころだよ」
「それでラビを呼びに……」
「うん、オダーマでもいいけど、ラビの方が危険なこととかに慣れてるでしょう?もしレンゼー村がジャリア兵に襲われたりしたら……」
ドーリは立ち止まり、表情を険しくして少年を見た。
「あんた。ここからすぐお帰り。話してくれたからもう怒りはしないよ。でもここまでだ。レンゼー村へはラビに行ってもらう」
「そんな。いやだよ」
「駄目だ。もし、本当に村が危険な状態だったら、どうするんだい」
「大丈夫だよ。俺もう子供じゃないよ。弓だって使えるし、剣だって少しは……」 「サビー」
ドーリは声を強めたが、少年は臆することなく言った。
「ドーリ。俺は行くよ」
「サビー……」
「俺はもう子どもじゃない。自分の命は自分で守るし、その責任ももう自分でとるよ」
そう言った少年の顔を、ドーリはじっと見つめた。
「それに、俺はいかなくちゃ。リンジたちは友達だよ。あいつらだって、みんな、仲間のためを思ってやろうとしているんだ。俺だってそうだ。でも、さっきドーリの話を聞いて、俺は分かったよ。こんなやり方では何も変わらないって」
「サビー……お前」
少年はうなずいた。その目の光は強く、まっすぐにドーリに向けられていた。
「だから……俺はリンジたちをとめなくちゃ。今から走っていけば、もしかしたら間に合うかも知れない。リンジたちには俺から言わなくちゃ駄目なんだ。あいつらのやろうとしていることも、俺のやろうとしたことも、それは本当に危険なことで、全部の村に関わる大変なことなんだって。俺から言わなくちゃ……」
「そう……そうだね。そうかもしれない」
それまでただのいたずら好きの子どもだった少年が、にわかに大人になりつつあったことを、ドーリは初めて知った。ほんの数年前はもっとずっと小さかったのに、今では背丈はドーリとほとんど変わらない。普段はやんちゃで、よく笑うその顔は、今はまるで青年のように引き締まって見える。
「それにさ……」
落ち着いた笑顔とともに、サビーは言った。
「もしかしたら、リンジたちも今頃、俺みたいに誰かに止められて、こっぴどく怒られているかもしれないしね」
「ああ、そうだね。そうだったら、ただの取り越し苦労ってもんだ」
二人は顔を見合わせて笑った。
街道を南に少しゆくと、川べりの小さな水車小屋がある。近隣のいくつかのシャネイ村が、粉挽きのために使用する共同の小屋だ。二人が小屋の前で待つと、ほどなくしてこちらに駆け寄ってきたのは、同じ村の青年、ラビだった。
「ラビ、早かったね」
相当なスピードで走ってきたのか、シャネイの若者は何度か息をついてうなずいた。
「夕食中だったが、ほっぽらかして走ってきた。ドーリが大急ぎで呼んでいると、子供らが言うのでな」
女や年寄りの多い彼らの村では、ラビは一番頼れる若者だった。すらりと背が高く、力持ちで機転もきく。かつては自警団で剣を習っていたこともある。彼にとって、村長オダーマの妻であるドーリは、ほとんど家族にも近い存在であった。
「どうした?ドーリ、何があった」
「すまないねえ、ラビ。急がせちまって。カナリは驚いてなかったかい」
「大丈夫さ。俺の嫁は勇気がある。慌てて飛び出そうとする俺に……ほら、こうして水筒と、もしものための短剣、包帯やら薬草なんかを持たせてくれたよ」
若者は腰に縛りつけた皮袋を見せた。
「それにしても、子供たちが大騒ぎで村に帰ってきたので、みんな仰天してオダーマの所に駆け込んでいるぞ。しかも、オダーマの家にドーリがいないので、みんな何があったのかと心配している」
「あら、いやだ。あの子たちったら、そんな大げさな。オダーマは何か言っていた?」
「いや、オダーマはまず皆を落ちつかせて、ドーリの言うとおり、俺に様子を見に行かせようと言った。皆が慌てることはまだ何も起こっていないと。それで俺に向かって、ドーリとサビーを頼む、自分は村長の責任があるゆえ、村を離れられない。何かあったときはすぐ対処できるようにしておくから、二人をくれぐれも頼むと」
「さすがはオダーマ」
ドーリは満足そうにうなずいた。
「あたしが見込んだ男だわ。それでこそ。それじゃあ、村の方はまず安心ね」
「ねえ、ドーリ。こんな所に立ち止まっていても仕方ないよ。歩きながら話そう。早くレンゼー村へ行かないと」
「おお、そうだ。そうだね。行こう」
「レンゼー村へ?いったい何があったんだ?」
ラビが眉をひそめた。その長い耳がピンと立つ。
「まさか、さっき通りすぎたジャリア軍の一隊となにか関係があるのか?」
「そうさ」
ドーリがうなずく。
「もしかしたら……大変なことが起こるかも知れないんだよ。まだ分からないけど。とにかく、行こう。ラビ、あんたが先頭にたって」
「わかった。レンゼー村だな」
ラビを先頭に、三人は街道を走り出した。
夕闇に包まれた街道の周りには、黒々とした森や山々が広がっている。このあたりにはいくつものシャネイ村が隣接しており、リンゼー村は彼らの足なら走ってほんの半刻ほどの距離であった。
「なるほど……そういう、ことか」
少年とドーリから話を聞いたラビは、顔つきを険しくした。
「それはまずい。俺は知ってる。あの黒竜王子を。一度ラハインの宮廷に小麦を届けに行ったとき、俺は近くであの王子の顔を見た」
街道の印石がかろうじて見えるくらいの夕闇の中を、三人は軽やかな足どりで走り抜けてゆく。シャネイの視力はとても強く、夜闇の中であっても、地面の石ころも、突き出した木々の枝も、はっきりと見分けられる。
「あの王子の目……なにも映さない、まるで感情のない目。あの目が、俺は心底恐ろしかった。特に俺たちシャネイを見る目つきは、とうてい人間を見る目つきとは思えなかったよ。言葉の通じぬ動物を見るような、蔑みも越した冷たい目つき。まるで道端の石ころでも見るように俺を見た、あの目を見たとき……俺は知ったのだ。残虐王子という名は、決して大げさなものではないのだと。あの王子からすれば、きっと俺たちを殺すことなどには何も意味を持たない。豚や猪を殺すように奴らは我々を狩り、殺してゆくだろうと」
「そういえば、たしか、あんたの妹と両親も……」
「ああ、前の村で殺された。あのときも王子の配下の部隊が通りかかって、ちょっとしたことで奴らの怒りをかい、戦いになり、そして……村は壊滅した。生き残ったのは老人とほんの数人の女子供だけだった」
前をゆくラビの声がかすかに震えるのを、サビーは聞いた。
「いけない……いくら子どもたちのすることとはいえ。あいつらは決して容赦しない。早く……早く止めないと」
「いやだよ。リンジたちが、みんな兵隊にやられちゃうなんて。そしたら俺……俺……」
「サビー。まだそうと決まったわけじゃないよ。あんたも言っただろう。あの悪ガキどもも、お前みたいに今頃は誰かに止められて、こっぴどく叱られているかもしれないって。あたしたちが村に着いてみたら何も起こっておらず、レンゼーの人たちが笑いながら、よく来たねって、みやげにに白パンでもくれて、あったかい豆のスープをごちそうしてくれるかもしれないよ。そうさ。なにも……なにも起こっていないよ、きっと……ね」
ドーリの言葉は、自分自身に言い聞かせるようなつぶやきに変わった。夜の街道を走る三人の足取りは、なにかに急かされるように、しだいに速くなっていった。
「村はもうすぐだ。あの橋を渡れば……」
遠くに小さな光が見えはじめていた。川の向こうにレンゼー村はある。
「あっ」
「な、なんだあれは」
サビーとラビが同時に声を上げた。
「あれは……」
ドーリも息を呑んだようにつぶやいた。
村の明かりとおぼしき光が、しだいに大きくなっていた。
その光は、ひとつ、ふたつ、みっつと、見る間に増えてゆく。
三人は橋の手前で立ち止まっていた。
「あれは……火だ!」
ラビが叫んだ。
「まさか。まさか……」
ドーリが口の中でつぶやく。
村が燃えている。
耳を澄ますと、村の方向からはごうごうという炎の音が聞こえ、それに混じって、なにかが起きているらしい喧騒の空気が伝わってくる。
いったい何が起こっているというのか。三人は言葉を失って立ち尽くした。
黒い夜空に燃えさかる火柱が上がる。
「あっ、お待ち。サビー!」
ドーリが止めるまもなく、少年は村に向かって走り出していた。
「ラビ、サビーをとめて!」
二人のシャネイは少年の後を追って、赤々とした炎に包まれつつある橋の向こうへ走り出した。
それより少しまえ……
街道をゆくフェルス王子と四十五人隊の一行は、一定の速度を保ちながら粛々と行軍していた。
ときは夕暮れどき。しばらくは両側を丘に挟まれた狭い道が続くことから、隊列は横三列となり、その中ほどに王子を守る長い隊形をとっている。隊列を組む一人一人の騎士は、兜の面頬を下ろし、槍を手に、無機質なほどの不気味な静かさで巧みに馬を操る。その様子はまるで、機械仕掛けの軍隊のようであった。
「異常ありません」
先行させていた斥候の騎士の報告を受け、馬上の王子はゆったりとうなずいた。王子の後ろには巨漢のザージーンの乗る馬が影のように付き従う。
「どうやら、今回はシャネイどもはおとなしいようですな」
馬を寄せてきたのは、副官のジルト・ステイクだった。
「あの低能なサルたちも、少しは利口になったということですかな」
「さあ、どうかな」
王子は意味ありげに言うと、街道の彼方へ目を向けた。
しだいに暗さを増してゆく黄昏の空。丘の向こうに沈みゆく、夕日の最後の残照とともに、王子と騎士たちは馬を歩ませる。
「フェルス殿下」
しんがりをつとめていた副隊長、ノーマス・ハインが報告に来た。
「どうした」
「は、すでにお気づきになっているかとも思いますが……」
若き副隊長は面頬を上げると、馬上から街道の両脇に目をやった。
「どうも静かすぎます」
「そうだな」
「いつもであれば、シャネイどもが街道わきから隊列を見物しているはず。この辺りは奴らの村が点在していますから」
「確かにな」
副隊長の言葉をうけ、王子も鋭い視線を道の左右に向けた。
ジャリアの首都ラハインから南部へ下る街道は他にもあるが、丘陵地帯を迂回せずにすむこのルートが時間的には一番ロスが少ない。周囲に多くのシャネイ村の存在するこの辺りでは、これまでにも街道を下るジャリアの兵隊、商隊などが襲撃を受ける事件が何度かあった。数年前から取り締まりを厳しくしたこともあり、ここ最近では目立った被害は少なくなってきていたが、それでもやはりジャリア兵士がこの街道を通りかかると、両脇の丘の上には居並んだシャネイたちが、とくに何も仕掛けてくるわけではないが、ただじっとこちらを見張っているということが常だったのだ。
「かえって怪しむべき静けさという気もします。行軍速度を少し速めれば、日が暮れる前にはこの地帯を抜けられますが」
「的確な判断だな、ノーマス。お前ももう立派な副隊長か」
「おそれいります」
若い騎士は嬉しそうに笑顔を見せた。
「よかろう。ではお前に任せる。先頭に立て。しんがりは別のものに任せよう」
「はっ」
「では、行軍速度二から三へ。同時に第二種警戒!」
ノーマスの発した命令が、隊列全体へと伝わってゆく。
「行軍二から三へ。第二種警戒」
「了解」
後尾で伝令確認の流旗が上がると、先頭の列からゆるやかに速度を上げはじめる。面頬を上げていたものは下ろし、隊の外側のものは距離をややせばめて密集する。相当に訓練されなければ出来ない動きである。
「ザージーン、兜をとれ」
王子が命じると、ザージーンは黙ってヘルムを脱いだ。頭髪を剃りあげ、浅黒い肌をした顔があらわになる。
「そのまま、できるだけ俺の馬に近づいていろ」
男は無表情のまま、言われたとおり、その巨体を乗せた馬を器用に操って、王子の馬のすぐ後に続いた。その剥き出しのいかつい顔は、大きな体躯と相まって、統一された鎧兜姿の隊列でひどく目立った。
「よし」
王子は満足そうにうすく笑いをうかべた。
速度を上げた隊列は街道を進んでいった。騎士たちの警戒をよそに、周囲にはまったく異変の予兆はなく、ただ静かで、暮れなずむ空のもとを、馬蹄の音が規則正しく響いてゆく。
街道はしだいに両側から丘に挟み込まれるようにして狭まり、さらに視界が悪くなった。ここを抜ければ丘陵地帯も終わり、ぐっと道はひらけてくるはずである。
隊列を組む騎士たちは、引き続き警戒をしつつ進んでゆくが、その緊張がいくらか惰性に変わった頃だったろうか。
突然、ガッという、石矢が鎧に当たる音とともに、王子のすぐそばの騎士が声を上げた。
「わあっ」
「どうしたっ!」
ひゅん
ひゅん
続けざまに、矢が空気を切り裂く音がいくつも鳴った。
「敵か?」
「弓だぞ!」
何本もの矢が兜や鎧にはね返され、そのうちのいくつかが馬に突き刺さった。つんざくようないななきが、静寂を破って辺りに響き渡る。
「これは長弓だぞ。気をつけろ。鎧にも突き刺さる」
「落ちつけ!隊列を崩すな。王子殿下をお守りしろ!」
それぞれに叫びながらも、さすがに訓練されたジャリアの騎士たちは、そう大きな狂乱に陥ることはない。一瞬の狼狽から立ち直ると、すぐに隊列を立て直す。
「丘だ、両側の丘の上からだ」
「シャネイどもの攻撃だ」
「殿下。危険ですから、どうか馬上にお伏せください」
「うろたえるな。栄えある四十五人隊の勇敢な騎士たちよ。我らはジャリア軍でも精鋭中の精鋭ぞ。いかに夜目がきくシャネイとはいえ、しょせん数にも力にも足りぬ」
王子は馬上で微動だにせず、騎士たちを叱咤した。そのすぐ後ろにいるザージーンの顔を、ぴゅんと矢がかすめる。
「殿下、ご無事で!」
馬で走り寄ってきたノーマスが、王子を庇うように前に出た。
「どうやら、狙われているのは隊列の中央のみのようです」
「なるほど。つまり、やつらは俺を狙っているわけだな」
王子はにやりと笑った。
その間にも、ひゅんひゅんと、いくつもの矢が至近距離をかすめてゆく。夕闇の中でも目が利くのだろう、放たれた矢は驚くほど的確に王子を狙っているようだった。
「王子、どうか頭をお低く。ザージーンは後ろをお守りしろ!」
ザージーンの兜をかぶらぬ剥き出しの顔を見て、ノーマスは眉をひそめた。
「王子、ザージーンの兜を……。敵に御身の場所を教えましたか」
「ノーマス」
兜の奥で、王子はあやしく目を光らせた。
「我に危害をなさんとする野卑な民どもに、今一度、思い知らせてやるときだな」
「王子……」
むしろ穏やかですらある王子の声に、ノーマス・ハインは思わず息をのんだ。
「ここに近いシャネイ村はどこか」
「は、はっ。いちばん近いのは、レンゼー村かと。五百人以上の比較的大きな村で……」
「よかろう」
王子はすっと手をかざした。
「騎士たち、流旗を上げよ」
鋭い声が隊列に響きわたった。
「戦闘開始!シャネイどもの村へ。焼き払え。みなごろしだ」
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説
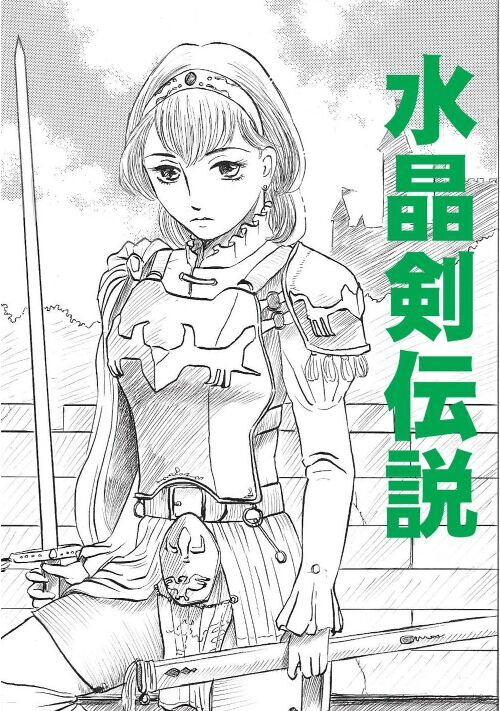
水晶剣伝説3~ウェルドスラーブへの出発
緑川らあず
ファンタジー
トレミリアの大剣技会で優勝を果たし、宮廷騎士となったレークは、遠征部隊の一員として友国ウェルドスラーブへと出発する。一方、相棒の美剣士アレンは、宮廷女官たちの教師となり、美しき王女と出会う。


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。


【完結】仰る通り、貴方の子ではありません
ユユ
恋愛
辛い悪阻と難産を経て産まれたのは
私に似た待望の男児だった。
なのに認められず、
不貞の濡れ衣を着せられ、
追い出されてしまった。
実家からも勘当され
息子と2人で生きていくことにした。
* 作り話です
* 暇つぶしにどうぞ
* 4万文字未満
* 完結保証付き
* 少し大人表現あり

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。


セクスカリバーをヌキました!
桂
ファンタジー
とある世界の森の奥地に真の勇者だけに抜けると言い伝えられている聖剣「セクスカリバー」が岩に刺さって存在していた。
国一番の剣士の少女ステラはセクスカリバーを抜くことに成功するが、セクスカリバーはステラの膣を鞘代わりにして収まってしまう。
ステラはセクスカリバーを抜けないまま武闘会に出場して……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















