12 / 18
愛しき思い出2
しおりを挟む
それからというもの、千尋はことあるごとに悠灯に絡んでいった。
はじめは絡まれることが鬱陶しくて、千尋を避けていたが、いくら邪険にしても付きまとう千尋に観念して相手をするようになった。
そうして2か月ほど経ったある日――――
放課後の夕方。
二人は一緒に帰るほどに親しくなっていた。
日が長くなり、16時になろうとしているのにまだ太陽は高い位置にあった。
夏も薫る7月の中旬あたりの事だった。
「今日もバイト?」
「うん」
「時々でもいいから、休めばいいのに…」
「そうも言ってられないよ」
前を向いて歩く二人にお互いの顔は見えない。
太陽が眩しくて息苦しさを感じ、悠灯は目を細めた。
「でも、就活もやってるんだろ。そのままじゃ本当に倒れるぞ」
確かに、就職活動は難航していた。
進学校である自分の高校は、高校で就職するような生徒は通わない。
そのため、高校に求人が来ない。自分でハローワークに通って就職先を探すしかなかった。
先生も専門外のため頼めない。
そもそも受験で生徒も先生もピリピリしている中でそんな厄介な生徒の面倒を見ようと思う人はいなかった。
でも、それを千尋に言っても心配してしまう。
付き合ってみて、千尋が本心から悠灯を心配していることは痛いほど伝わった。
ことあるごとに大丈夫なのか確認してくるし、今だってこうして言葉に出して悠灯を労わってくれる。
それだけで嬉しくて、申し訳ない気持ちでいっぱいなのに。
これ以上彼の気を揉むようなことを言いたくなかった。
「大丈夫だって……」
言った途端に、目の前がグラグラと揺れ出した。
さっきは太陽が高いせいで、息苦しさを感じていたと思ったが……。
どうやら違ったらしい。
立ち止まる悠灯に気づかず、千尋はそのまま歩き続けた。
千尋の背中が見えたと思った瞬間、立っていられなくなり悠灯は膝から崩れ落ちるように倒れた。
ドサリッと何かが倒れる音に振り向くと、千尋が駆け寄る。
「幾島…!幾島!!」
何度も何度も名前を呼ぶ千尋の声がくぐもって聞こえる。
驚いたような焦ったような顔が薄めにも確認できた。
(こんな必死な顔してても、綺麗なんだな…)
そうのんきに考えていたのも束の間、悠灯は意識を手放していた。
***
「…ここ、どこ?」
目を覚ますと、天井と蛍光灯が見えた。
今自分がどこにいるのかわからず、思わずそう呟いていた。
「悠灯っ!」
誰かに呼ばれ、声のする方に顔を向ける。
そこには心配そうに見つめる千尋の姿があった。
「良かった、本当に…。っていうか全然大丈夫じゃないじゃんか……」
千尋は悠灯の手を強く握り、そこに額を乗っけると弱弱しく呟いた。
千尋の手が温かくて、ほっとする。
「…ごめん」
シャーッと音がして、仕切られていたカーテンが開く。
悠灯たちより少し年上のうす水色の制服をきた青年がそこに立っていた。
着ている制服と持っているクリップファイルから、ここが病院だとわかった。
「あぁ、良かった起きたの。ただの過労だったから安心して。その点滴終わったら帰っていいから」
それだけ言うとまたカーテンを戻し、忙しそうに足早に去っていった。
ほっと一息ついたのも束の間、自分がバイトに行く途中だったことを思い出した。
「バイト!それに母さんにも連絡しなきゃ」
焦って起き上がろうとする悠灯を千尋は宥めると、強く体を押されベッドに戻された。
「大丈夫、どっちにも連絡しといたから。でも、お母さんは迎えに来れないみたいだから自分で帰ってきてほしいって言ってた」
その言葉にほっと息を漏らす。
何から何まで千尋にやらせてしまい申し訳なかった。
「ありがとう」
その言葉を聞いて、嬉しそうに目を細めて笑うと千尋は笑った。
その笑顔が直視できなくて、悠灯は目を逸らした。
顔がすごく熱くなって仕方なかった。
しばらくすると点滴が終わり、会計を済ませると病院を後にした。
外に出た瞬間ムッとした熱気が遅い、ジワリと体が汗で湿っていく。
もうすっかり宵闇に包まれていた。
時間を確認するともう8時近い。
千尋をこんな時間まで付き合わせてしまったことに今更ながら申し訳なくなった。
「ごめん、こんな遅くまで付き添ってもらって」
「いいんだよ、俺がしたくてしたことだから」
それにしたって、こんな夜遅くまで友人のために付き合ってくれるだろうか。
「都築って、友達思いなんだな」
「……ちがうよ」
立ち止まった千尋に悠灯も思わず歩みを止めた。
「え?」
「悠灯だから……。悠灯が相手だからするんだよ」
「それって、どういう」
「だからっ―――」
「俺、悠灯のこと好きだから」
信じられない言葉を聞いて自分の耳がおかしくなったのかと思った。
悠灯を見つめる強くまっすぐな瞳に視線が逸らせない。
心臓が止まるかと思った。
びっくりし過ぎて声もでない。
「好きな人のことだから、こんなにするんだよ。じゃなかったらここまでしない」
言い切る千尋になにも言葉が返せない。
驚いて立ち尽くしていると、千尋が近寄ってきた。
顔が熱くて仕方ない。
きっとすごく赤くなっている。
いつの間にか、千尋の顔が目の前まで来ていた。
頬に手が触れる。
それに小さくビクリと反応した。
「嫌だったら、殴ってでも止めてよ」
そういうと千尋は顔を悠灯に近づけた。
瞬間、唇に何か触れた。
「―――っ!」
それが千尋の唇だということにすぐに気づいた。
(キス…されてる)
はじめて行う行為に心臓が飛び跳ねる。
柔らかい感触が唇から伝わり、恥ずかしくて仕方ない。
唇同士が触れているだけなのに、どうしてこんなにドキドキするのか悠灯にはわからなかった。
10秒ほど経っただろうか。
千尋が顔を遠ざけ、瞬時に背けると帰る方向へ歩き出した。
「さ、帰るぞ!」
先導する千尋の背中を追いかけるように、悠灯も歩き出した。
しかし、千尋の顔を確認する勇気はなくて、横に並ぶことができず、後ろを一定の距離を保ちながら一緒に歩くのが精いっぱいだった。
それから、どうやって帰ったのか覚えていない。
ただ、いつの間にか家に着いていて心配する両親にうわごとのように返事をしたような気がする。
そして気づいたときには風呂に入り終わり、布団に入ったところで先ほどの出来事が鮮明に蘇った。
途端に顔から火が出るんじゃないかと思う程顔が熱くなる。
唇の指でなぞって、先ほどの感触を思い出す。
(どうして、どうして嫌じゃなかったんだ……)
自分自身のことがわからない。
ただただ、ずっと心臓がうるさくて仕方なかった。
はじめは絡まれることが鬱陶しくて、千尋を避けていたが、いくら邪険にしても付きまとう千尋に観念して相手をするようになった。
そうして2か月ほど経ったある日――――
放課後の夕方。
二人は一緒に帰るほどに親しくなっていた。
日が長くなり、16時になろうとしているのにまだ太陽は高い位置にあった。
夏も薫る7月の中旬あたりの事だった。
「今日もバイト?」
「うん」
「時々でもいいから、休めばいいのに…」
「そうも言ってられないよ」
前を向いて歩く二人にお互いの顔は見えない。
太陽が眩しくて息苦しさを感じ、悠灯は目を細めた。
「でも、就活もやってるんだろ。そのままじゃ本当に倒れるぞ」
確かに、就職活動は難航していた。
進学校である自分の高校は、高校で就職するような生徒は通わない。
そのため、高校に求人が来ない。自分でハローワークに通って就職先を探すしかなかった。
先生も専門外のため頼めない。
そもそも受験で生徒も先生もピリピリしている中でそんな厄介な生徒の面倒を見ようと思う人はいなかった。
でも、それを千尋に言っても心配してしまう。
付き合ってみて、千尋が本心から悠灯を心配していることは痛いほど伝わった。
ことあるごとに大丈夫なのか確認してくるし、今だってこうして言葉に出して悠灯を労わってくれる。
それだけで嬉しくて、申し訳ない気持ちでいっぱいなのに。
これ以上彼の気を揉むようなことを言いたくなかった。
「大丈夫だって……」
言った途端に、目の前がグラグラと揺れ出した。
さっきは太陽が高いせいで、息苦しさを感じていたと思ったが……。
どうやら違ったらしい。
立ち止まる悠灯に気づかず、千尋はそのまま歩き続けた。
千尋の背中が見えたと思った瞬間、立っていられなくなり悠灯は膝から崩れ落ちるように倒れた。
ドサリッと何かが倒れる音に振り向くと、千尋が駆け寄る。
「幾島…!幾島!!」
何度も何度も名前を呼ぶ千尋の声がくぐもって聞こえる。
驚いたような焦ったような顔が薄めにも確認できた。
(こんな必死な顔してても、綺麗なんだな…)
そうのんきに考えていたのも束の間、悠灯は意識を手放していた。
***
「…ここ、どこ?」
目を覚ますと、天井と蛍光灯が見えた。
今自分がどこにいるのかわからず、思わずそう呟いていた。
「悠灯っ!」
誰かに呼ばれ、声のする方に顔を向ける。
そこには心配そうに見つめる千尋の姿があった。
「良かった、本当に…。っていうか全然大丈夫じゃないじゃんか……」
千尋は悠灯の手を強く握り、そこに額を乗っけると弱弱しく呟いた。
千尋の手が温かくて、ほっとする。
「…ごめん」
シャーッと音がして、仕切られていたカーテンが開く。
悠灯たちより少し年上のうす水色の制服をきた青年がそこに立っていた。
着ている制服と持っているクリップファイルから、ここが病院だとわかった。
「あぁ、良かった起きたの。ただの過労だったから安心して。その点滴終わったら帰っていいから」
それだけ言うとまたカーテンを戻し、忙しそうに足早に去っていった。
ほっと一息ついたのも束の間、自分がバイトに行く途中だったことを思い出した。
「バイト!それに母さんにも連絡しなきゃ」
焦って起き上がろうとする悠灯を千尋は宥めると、強く体を押されベッドに戻された。
「大丈夫、どっちにも連絡しといたから。でも、お母さんは迎えに来れないみたいだから自分で帰ってきてほしいって言ってた」
その言葉にほっと息を漏らす。
何から何まで千尋にやらせてしまい申し訳なかった。
「ありがとう」
その言葉を聞いて、嬉しそうに目を細めて笑うと千尋は笑った。
その笑顔が直視できなくて、悠灯は目を逸らした。
顔がすごく熱くなって仕方なかった。
しばらくすると点滴が終わり、会計を済ませると病院を後にした。
外に出た瞬間ムッとした熱気が遅い、ジワリと体が汗で湿っていく。
もうすっかり宵闇に包まれていた。
時間を確認するともう8時近い。
千尋をこんな時間まで付き合わせてしまったことに今更ながら申し訳なくなった。
「ごめん、こんな遅くまで付き添ってもらって」
「いいんだよ、俺がしたくてしたことだから」
それにしたって、こんな夜遅くまで友人のために付き合ってくれるだろうか。
「都築って、友達思いなんだな」
「……ちがうよ」
立ち止まった千尋に悠灯も思わず歩みを止めた。
「え?」
「悠灯だから……。悠灯が相手だからするんだよ」
「それって、どういう」
「だからっ―――」
「俺、悠灯のこと好きだから」
信じられない言葉を聞いて自分の耳がおかしくなったのかと思った。
悠灯を見つめる強くまっすぐな瞳に視線が逸らせない。
心臓が止まるかと思った。
びっくりし過ぎて声もでない。
「好きな人のことだから、こんなにするんだよ。じゃなかったらここまでしない」
言い切る千尋になにも言葉が返せない。
驚いて立ち尽くしていると、千尋が近寄ってきた。
顔が熱くて仕方ない。
きっとすごく赤くなっている。
いつの間にか、千尋の顔が目の前まで来ていた。
頬に手が触れる。
それに小さくビクリと反応した。
「嫌だったら、殴ってでも止めてよ」
そういうと千尋は顔を悠灯に近づけた。
瞬間、唇に何か触れた。
「―――っ!」
それが千尋の唇だということにすぐに気づいた。
(キス…されてる)
はじめて行う行為に心臓が飛び跳ねる。
柔らかい感触が唇から伝わり、恥ずかしくて仕方ない。
唇同士が触れているだけなのに、どうしてこんなにドキドキするのか悠灯にはわからなかった。
10秒ほど経っただろうか。
千尋が顔を遠ざけ、瞬時に背けると帰る方向へ歩き出した。
「さ、帰るぞ!」
先導する千尋の背中を追いかけるように、悠灯も歩き出した。
しかし、千尋の顔を確認する勇気はなくて、横に並ぶことができず、後ろを一定の距離を保ちながら一緒に歩くのが精いっぱいだった。
それから、どうやって帰ったのか覚えていない。
ただ、いつの間にか家に着いていて心配する両親にうわごとのように返事をしたような気がする。
そして気づいたときには風呂に入り終わり、布団に入ったところで先ほどの出来事が鮮明に蘇った。
途端に顔から火が出るんじゃないかと思う程顔が熱くなる。
唇の指でなぞって、先ほどの感触を思い出す。
(どうして、どうして嫌じゃなかったんだ……)
自分自身のことがわからない。
ただただ、ずっと心臓がうるさくて仕方なかった。
0
お気に入りに追加
4
あなたにおすすめの小説


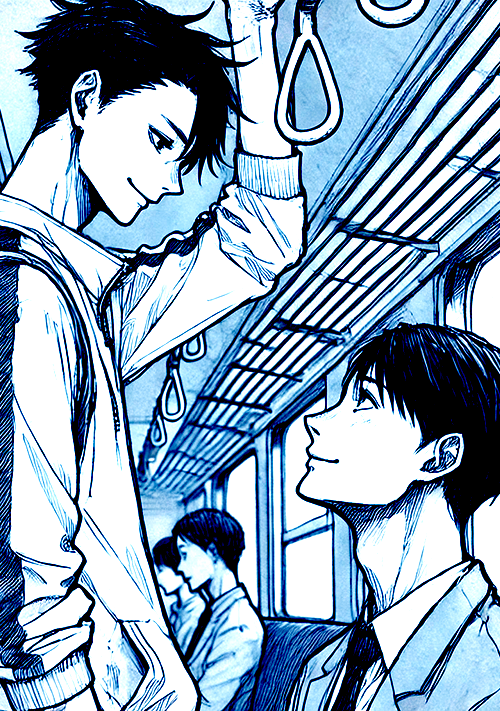
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……





紹介なんてされたくありません!
mahiro
BL
普通ならば「家族に紹介したい」と言われたら、嬉しいものなのだと思う。
けれど僕は男で目の前で平然と言ってのけたこの人物も男なわけで。
断りの言葉を言いかけた瞬間、来客を知らせるインターフォンが鳴り響き……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















