21 / 36
第三話 「くじら侍と修羅の兄妹」
岡っ引きの欣次
しおりを挟むいつまでもいつまでもやさしいと思うな
おまえのための俺じゃない
勘違いするなよ
仏の顔も三度までってのはあるんだよ
調子に乗らせた俺も悪いけど
調子に乗ったおまえが一番悪い!!
おまえのための俺じゃない
勘違いするなよ
仏の顔も三度までってのはあるんだよ
調子に乗らせた俺も悪いけど
調子に乗ったおまえが一番悪い!!
0
お気に入りに追加
15
あなたにおすすめの小説


くじら斗りゅう
陸 理明
歴史・時代
捕鯨によって空前の繁栄を謳歌する太地村を領内に有する紀伊新宮藩は、藩の財政を活性化させようと新しく藩直営の鯨方を立ち上げた。はぐれ者、あぶれ者、行き場のない若者をかき集めて作られた鵜殿の村には、もと武士でありながら捕鯨への情熱に満ちた権藤伊左馬という巨漢もいた。このままいけば新たな捕鯨の中心地となったであろう鵜殿であったが、ある嵐の日に突然現れた〈竜〉の如き巨大な生き物を獲ってしまったことから滅びへの運命を歩み始める…… これは、愛憎と欲望に翻弄される若き鯨猟夫たちの青春譚である。


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

晩夏の蝉
紫乃森統子
歴史・時代
当たり前の日々が崩れた、その日があった──。
まだほんの14歳の少年たちの日常を変えたのは、戊辰の戦火であった。
後に二本松少年隊と呼ばれた二本松藩の幼年兵、堀良輔と成田才次郎、木村丈太郎の三人の終着点。
※本作品は昭和16年発行の「二本松少年隊秘話」を主な参考にした史実ベースの創作作品です。
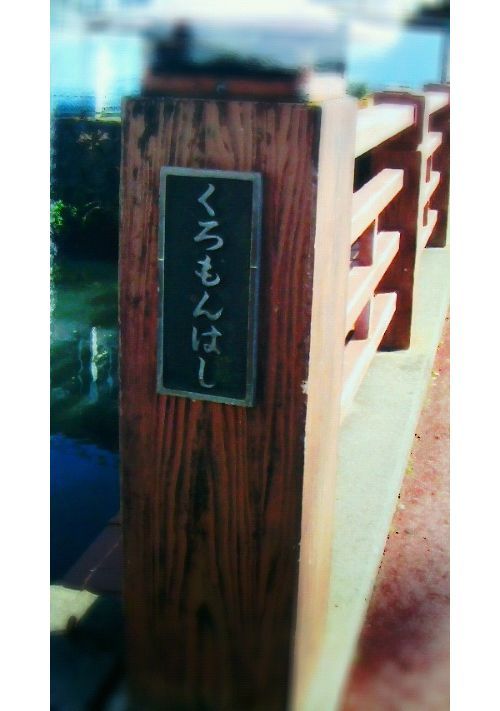
肥後の春を待ち望む
尾方佐羽
歴史・時代
秀吉の天下統一が目前になった天正の頃、肥後(熊本)の国主になった佐々成政に対して国人たちが次から次へと反旗を翻した。それを先導した国人の筆頭格が隈部親永(くまべちかなが)である。彼はなぜ、島津も退くほどの強大な敵に立ち向かったのか。国人たちはどのように戦ったのか。そして、九州人ながら秀吉に従い国人衆とあいまみえることになった若き立花統虎(宗茂)の胸中は……。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~
橋本洋一
歴史・時代
この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。
記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。
これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語
※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















