75 / 78
その後のお話① 初めての社交場
しおりを挟む
ロイド様と正式に婚約して、約二ヶ月後。ついに私の社交デビューの日がやって来た。
「母が懇意にしている伯爵家のご子息が叙勲され、それを祝うパーティーが伯爵邸で開かれるそうだ。我々も招かれているから、一緒に行こう、ミシェル」
「は、はいっ、ロイド様」
その話を聞いただけで、すでに私はカチコチに固まっていた。つ、ついに……ついに来てしまった……! この私が、初めて、ロイド様の婚約者として社交界の方々の前に顔を出すのだ。この私が。貴族のマナーもしきたりも何も学ばぬままに成長し、ようやく付け焼き刃のような猛勉強を始めたばかりの、私が。
つい最近まで、ハリントン公爵邸のただのメイドだった私が。この立派な公爵様の婚約者として、社交界の皆様の前に……!
ゴクリと生唾をのむ私を見て、ロイド様はクスリと笑うと、優しく私を抱きしめた。
「そんなに緊張しなくていい。国中の貴族が集まる王宮での夜会に参加するというような話ではないのだから。ただの内輪のパーティーだ。それに、君の隣には常に私がいる。君に不安な思いをさせたり、恥をかかせたりなどするものか」
「……ロイド様……」
顔を見上げると、ロイド様は慈しむように私の頬をそっと撫でる。
「大丈夫だ。この数ヶ月で、君は見違えるほど素敵なレディーになった。自信を持つといい。君はこの私を唯一骨抜きにした女性だぞ」
「~~~~っ!? ……あ、ありがとう、ございます……」
歯の浮くような台詞をサラリと言ってのけるロイド様の笑顔が眩しくて、私は真っ赤になった自分の頬を隠すように俯いた。
パーティー当日。今日はカーティスさんやアマンダさんもついてきてくれる予定だけれど、行き帰りの馬車は私たちとは別らしい。
早い時間から何人もの侍女たちによって、私は身支度を整えられていた。ドレスの後ろのリボンを結んでくれていたアマンダさんが、さっきからずっとクスクス笑っている。
「ふふ。ミシェル様ったら……。“婚約者同士でパーティーに参加する時には、互いの色を身にまとうものだ”と聞いていたから、旦那様が全身ピンク色の衣装を着ていくのだと思っていただなんて……。もう、なんだかツボに入っちゃって笑いが止まりませんわ」
「だ、だって、侍女がそう言ったから、てっきり……。よかったわ、必ずしも相手の髪の色の衣装を着るわけじゃないのね。私は自分が銀色のドレスを着ていくのだと思っていました」
「ふふふ……。全身ピンク色の旦那様が頭から離れないじゃないの。……あ、失礼しました。つい。油断すると以前の話し方に戻ってしまいますわ」
「私もです、アマンダさん」
私たちの会話を聞いていた周りの侍女たちも、クスクスと笑っている。私がロイド様の婚約者になってから、アマンダさんは私のことを「ミシェル様」と呼び、以前より丁寧な話し方に変わった。私は相変わらず「アマンダさん」と呼んではいるけれど、できるだけ“威厳”のある立ち居振る舞いをせねばと、自分なりに努力はしている。
「……とても素敵ですわ、ミシェル様。旦那様の瞳の色のドレス、よくお似合いです」
「あ、ありがとう」
アマンダさんにそう言われ、私は姿見の前に立った。鮮やかなサファイアブルーと白のグラデーションカラーのドレスは、品があってとても華やかだ。ロイド様は喜んでくださるだろうか。……まぁ、このドレスを選んだのはロイド様だから、どんなドレス姿で現れるのだろうワクワク、みたいな感情では待っていないと思うけど。
サイドだけ少し下ろしたアップスタイルに結ってもらった髪にも、首元にも、プラチナとダイアモンドの美しい装飾が施された。ドキドキしながらソファーに座っていると、やがてロイド様が私の様子を見に部屋に入ってきた。
「ミシェルの準備はできたか」
「はい、旦那様」
扉のところで侍女にそう確認し、私のそばまでやって来たロイド様は、立ち上がった私を見て目を見開く。そしてそのまま動かなくなった。
(わぁ……、ロイド様、なんて素敵なのかしら……)
そんなロイド様を見て、私は息を呑んだ。
普段と違うヘアセットにも、所々に金色の刺繍や装飾が施された濃茶のフォーマルな衣装姿にも、惚れ惚れしてしまう。この世にこんなにも素敵な男性が、他にいるのかしら。
「ロイド様……! すごく格好良いです……! あ、いえ、いつも素敵ですけど。……私なんだか、とっても胸がドキドキしてしまいます。今日は、よろしくお願いします」
胸の高鳴りのままにそう声をかけたけれど……、ロイド様はピクリとも動かない。形の良い唇を薄く開いたまま、私のことを穴があくほどジッと見つめている。私は少し不安になってきた。
「……ど、どこかおかしいでしょうか」
おそるおそるそう尋ねると、ロイド様はハッとしたように瞳を揺らし、そのまま横を向いてしまった。
そして口元を手で覆い、ボソリと言う。
「……すまない。君があまりにも……美しすぎて。言葉が出なかった」
「……へっ!?」
ロイド様のその言葉に、思わず変な声を上げてしまう。真っ赤になって狼狽える私に一歩近付いたロイド様が、耳元で甘く囁いた。
「最高に綺麗だ、ミシェル。君を誰の目にも触れさせたくなくなるほどに」
◇ ◇ ◇
「まぁ……! こちらが公爵閣下の大切な方ですの? なんて華やかで愛らしいのでしょう」
「ええ。ふふ。ようやく決めてくれましたわ。本当に生涯独身を貫くつもりなのかと落胆しておりましたけれど、こんなに可愛い婚約者ができましたのよ。ふふ。この子は社交にはまだ不慣れで、いろいろと勉強中ですの。とても頑張ってくれていますのよ。どうぞ、今後ともこのミシェル嬢を、よろしくお願いいたしますわね」
訪れた伯爵邸で、何人もの貴族の男性やご婦人からの挨拶を受ける。私の隣にピタリと立ち、嬉しそうに私を紹介してくれているのは、ロイド様……ではなく、ハリントン前公爵夫人。ロイド様のお母様だ。そして、楽しそうに話すご婦人たちと私の背後で、不機嫌をあらわにして立っているのが、ロイド様。カーティスさんとアマンダさんは、さらにその後方からこちらを静かに見守っている。
この伯爵邸へ到着してハリントン前公爵夫人と顔を合わせてからというもの、誰かから声をかけられるたびに、夫人はロイド様を押し退けて私の隣を陣取り、私を皆様に紹介してくれている。私をフォローしようというそのお優しい心遣いはひしひしと感じるし、大事にしてもらえているようで、とても嬉しい。……嬉しい、けれど……。
「……」
チラリと背後を振り返ると、ロイド様が母君の後頭部を、仏頂面でジトーッと睨みつけている。
(あぁ……、お、怒ってる……)
さっきから挨拶が終わって人が去るたびに「母上、ミシェルの紹介は私がします。婚約者は私なのですから。出しゃばらないでください」と前公爵夫人にきつめに言っているのに、それでもやはり新たな挨拶が始まると前公爵夫人はズイッと前に出て私の背に手を添え、嬉々として私の紹介を始めてくださるのだ。
「可愛いでしょう? ええ。本当に可愛いんですのよ。不慣れなことばかりなのに、とてもひたむきに頑張ってくれていて……。まさかロイドがこの歳になって、こんなにも素敵な婚約者に巡り会えるなんて。私も本当に予想外でしてね……ほほほ」
一生独身を貫きそうだった一人息子が婚約したことが、よほど嬉しくてたまらないらしい。ロイド様も以前「母は今“婚約者フィーバー”が来ている」と言っていた。
結局パーティーがお開きになる頃まで、ハリントン前公爵夫人は私たちの、いや、私のそばからほとんど離れなかったのだった。
ハリントンの屋敷に戻る馬車の中でようやく二人きりになると、向かいに座ったロイド様が深い深い溜息をついた。馬車がゆっくりと動き出す。
「お、お疲れ様でした、ロイド様。……その、つつがなく終わって、とても……」
「隣に座ってもいいか、ミシェル」
「は、はい」
疲れ切った低い声でそう尋ねてくるロイド様に返事をすると、彼は立ち上がり、私の隣に腰を下ろした。
ロイド様は私の腰にごく自然に手を回し、私をより一層そばへと引き寄せる。私の頬は、ロイド様の胸元へピタリとくっついた。
「ロイド様……っ」
「ようやく君を独占できる。……全く。母ときたら、まさかパーティーの間中君を手放さないとはな。呆れてしまった」
ブツブツとそんなことを言っているロイド様の唇が、私の髪に触れていて少しくすぐったい。けれど、こうして抱き寄せられるのが嬉しくて、とてもホッとして、私は抵抗することなくその胸に体を預けた。
「……ロイド様のお母様が、今までどれほど思い悩んでおられたのかがよく分かりました。私のような者でも、嫁いでくることをあんなにも喜んでくださって。今日も不慣れな私のことを、何度も優しくフォローしてくださっていました」
「……ああ。その通りだな。たしかに、母の気持ちは分かる。これまで心労をかけてきたのは、他ならぬこの私なのだから。……君にそう言われたら、もう母を責める気にはなれないな」
ロイド様はそう言うと、私の顔を覗き込むようにして言った。
「私のような者でも、などと言わないでくれ。ミシェルだからこそ、母はあんなにも喜んでいるんだ。素直でひたむきで、誠実な君だからこそ。私にとっても母にとっても、君は特別な女性なんだよ」
「ロ、ロイド様……」
今日のロイド様はどこまでも優しい。……いや、毎日優しいのだけど、私を見つめるロイド様の今日の視線は、いつもよりもずっとずっと熱くて甘い。そんな気がする。体が火照ってどうしようもない。
「……そんなに見つめないでください。どうしていいか分からなくなります」
たまらずそう言って目を逸らすと、ロイド様は私の顎に触れ、容赦なく自分の方へと視線を誘導する。
「今日の君の特別な美しさを、やっとこうしてゆっくり堪能できるんだ。気が済むまで見つめさせてくれ」
「……っ、」
間近できらめく青い瞳は深く澄んでいて、そしてとても色っぽかった。
その瞳が、ふいに私の視界を埋め尽くす。
(……っ!)
軽く触れるだけの口づけをすると、ロイド様は私の膝の下に片腕を通し、私の体をふわりと持ち上げた。
「っ! きゃ……っ!」
驚いて思わず彼の首にしがみつくと、私の体はロイド様の膝の上に下ろされた。
「ち……っ、近すぎます! ロイド様……っ」
激しく動揺した私は、思わず彼の胸を両手で押して距離をとろうとしてしまう。
けれどロイド様は私の背に手を回ししっかりと抱きしめ、それを許さなかった。
「馬車が揺れるから、口づけがしづらい。……ここにいてくれ」
「そ……っ! ……ん……っ」
真っ赤になった私が返事をする間もなく、私の唇はもう一度彼によって塞がれた。
屋敷に着くまでの間、頭がクラクラするほどの甘いキスが、何度も与えられたのだった。
ーーーーー end ーーーーー
「母が懇意にしている伯爵家のご子息が叙勲され、それを祝うパーティーが伯爵邸で開かれるそうだ。我々も招かれているから、一緒に行こう、ミシェル」
「は、はいっ、ロイド様」
その話を聞いただけで、すでに私はカチコチに固まっていた。つ、ついに……ついに来てしまった……! この私が、初めて、ロイド様の婚約者として社交界の方々の前に顔を出すのだ。この私が。貴族のマナーもしきたりも何も学ばぬままに成長し、ようやく付け焼き刃のような猛勉強を始めたばかりの、私が。
つい最近まで、ハリントン公爵邸のただのメイドだった私が。この立派な公爵様の婚約者として、社交界の皆様の前に……!
ゴクリと生唾をのむ私を見て、ロイド様はクスリと笑うと、優しく私を抱きしめた。
「そんなに緊張しなくていい。国中の貴族が集まる王宮での夜会に参加するというような話ではないのだから。ただの内輪のパーティーだ。それに、君の隣には常に私がいる。君に不安な思いをさせたり、恥をかかせたりなどするものか」
「……ロイド様……」
顔を見上げると、ロイド様は慈しむように私の頬をそっと撫でる。
「大丈夫だ。この数ヶ月で、君は見違えるほど素敵なレディーになった。自信を持つといい。君はこの私を唯一骨抜きにした女性だぞ」
「~~~~っ!? ……あ、ありがとう、ございます……」
歯の浮くような台詞をサラリと言ってのけるロイド様の笑顔が眩しくて、私は真っ赤になった自分の頬を隠すように俯いた。
パーティー当日。今日はカーティスさんやアマンダさんもついてきてくれる予定だけれど、行き帰りの馬車は私たちとは別らしい。
早い時間から何人もの侍女たちによって、私は身支度を整えられていた。ドレスの後ろのリボンを結んでくれていたアマンダさんが、さっきからずっとクスクス笑っている。
「ふふ。ミシェル様ったら……。“婚約者同士でパーティーに参加する時には、互いの色を身にまとうものだ”と聞いていたから、旦那様が全身ピンク色の衣装を着ていくのだと思っていただなんて……。もう、なんだかツボに入っちゃって笑いが止まりませんわ」
「だ、だって、侍女がそう言ったから、てっきり……。よかったわ、必ずしも相手の髪の色の衣装を着るわけじゃないのね。私は自分が銀色のドレスを着ていくのだと思っていました」
「ふふふ……。全身ピンク色の旦那様が頭から離れないじゃないの。……あ、失礼しました。つい。油断すると以前の話し方に戻ってしまいますわ」
「私もです、アマンダさん」
私たちの会話を聞いていた周りの侍女たちも、クスクスと笑っている。私がロイド様の婚約者になってから、アマンダさんは私のことを「ミシェル様」と呼び、以前より丁寧な話し方に変わった。私は相変わらず「アマンダさん」と呼んではいるけれど、できるだけ“威厳”のある立ち居振る舞いをせねばと、自分なりに努力はしている。
「……とても素敵ですわ、ミシェル様。旦那様の瞳の色のドレス、よくお似合いです」
「あ、ありがとう」
アマンダさんにそう言われ、私は姿見の前に立った。鮮やかなサファイアブルーと白のグラデーションカラーのドレスは、品があってとても華やかだ。ロイド様は喜んでくださるだろうか。……まぁ、このドレスを選んだのはロイド様だから、どんなドレス姿で現れるのだろうワクワク、みたいな感情では待っていないと思うけど。
サイドだけ少し下ろしたアップスタイルに結ってもらった髪にも、首元にも、プラチナとダイアモンドの美しい装飾が施された。ドキドキしながらソファーに座っていると、やがてロイド様が私の様子を見に部屋に入ってきた。
「ミシェルの準備はできたか」
「はい、旦那様」
扉のところで侍女にそう確認し、私のそばまでやって来たロイド様は、立ち上がった私を見て目を見開く。そしてそのまま動かなくなった。
(わぁ……、ロイド様、なんて素敵なのかしら……)
そんなロイド様を見て、私は息を呑んだ。
普段と違うヘアセットにも、所々に金色の刺繍や装飾が施された濃茶のフォーマルな衣装姿にも、惚れ惚れしてしまう。この世にこんなにも素敵な男性が、他にいるのかしら。
「ロイド様……! すごく格好良いです……! あ、いえ、いつも素敵ですけど。……私なんだか、とっても胸がドキドキしてしまいます。今日は、よろしくお願いします」
胸の高鳴りのままにそう声をかけたけれど……、ロイド様はピクリとも動かない。形の良い唇を薄く開いたまま、私のことを穴があくほどジッと見つめている。私は少し不安になってきた。
「……ど、どこかおかしいでしょうか」
おそるおそるそう尋ねると、ロイド様はハッとしたように瞳を揺らし、そのまま横を向いてしまった。
そして口元を手で覆い、ボソリと言う。
「……すまない。君があまりにも……美しすぎて。言葉が出なかった」
「……へっ!?」
ロイド様のその言葉に、思わず変な声を上げてしまう。真っ赤になって狼狽える私に一歩近付いたロイド様が、耳元で甘く囁いた。
「最高に綺麗だ、ミシェル。君を誰の目にも触れさせたくなくなるほどに」
◇ ◇ ◇
「まぁ……! こちらが公爵閣下の大切な方ですの? なんて華やかで愛らしいのでしょう」
「ええ。ふふ。ようやく決めてくれましたわ。本当に生涯独身を貫くつもりなのかと落胆しておりましたけれど、こんなに可愛い婚約者ができましたのよ。ふふ。この子は社交にはまだ不慣れで、いろいろと勉強中ですの。とても頑張ってくれていますのよ。どうぞ、今後ともこのミシェル嬢を、よろしくお願いいたしますわね」
訪れた伯爵邸で、何人もの貴族の男性やご婦人からの挨拶を受ける。私の隣にピタリと立ち、嬉しそうに私を紹介してくれているのは、ロイド様……ではなく、ハリントン前公爵夫人。ロイド様のお母様だ。そして、楽しそうに話すご婦人たちと私の背後で、不機嫌をあらわにして立っているのが、ロイド様。カーティスさんとアマンダさんは、さらにその後方からこちらを静かに見守っている。
この伯爵邸へ到着してハリントン前公爵夫人と顔を合わせてからというもの、誰かから声をかけられるたびに、夫人はロイド様を押し退けて私の隣を陣取り、私を皆様に紹介してくれている。私をフォローしようというそのお優しい心遣いはひしひしと感じるし、大事にしてもらえているようで、とても嬉しい。……嬉しい、けれど……。
「……」
チラリと背後を振り返ると、ロイド様が母君の後頭部を、仏頂面でジトーッと睨みつけている。
(あぁ……、お、怒ってる……)
さっきから挨拶が終わって人が去るたびに「母上、ミシェルの紹介は私がします。婚約者は私なのですから。出しゃばらないでください」と前公爵夫人にきつめに言っているのに、それでもやはり新たな挨拶が始まると前公爵夫人はズイッと前に出て私の背に手を添え、嬉々として私の紹介を始めてくださるのだ。
「可愛いでしょう? ええ。本当に可愛いんですのよ。不慣れなことばかりなのに、とてもひたむきに頑張ってくれていて……。まさかロイドがこの歳になって、こんなにも素敵な婚約者に巡り会えるなんて。私も本当に予想外でしてね……ほほほ」
一生独身を貫きそうだった一人息子が婚約したことが、よほど嬉しくてたまらないらしい。ロイド様も以前「母は今“婚約者フィーバー”が来ている」と言っていた。
結局パーティーがお開きになる頃まで、ハリントン前公爵夫人は私たちの、いや、私のそばからほとんど離れなかったのだった。
ハリントンの屋敷に戻る馬車の中でようやく二人きりになると、向かいに座ったロイド様が深い深い溜息をついた。馬車がゆっくりと動き出す。
「お、お疲れ様でした、ロイド様。……その、つつがなく終わって、とても……」
「隣に座ってもいいか、ミシェル」
「は、はい」
疲れ切った低い声でそう尋ねてくるロイド様に返事をすると、彼は立ち上がり、私の隣に腰を下ろした。
ロイド様は私の腰にごく自然に手を回し、私をより一層そばへと引き寄せる。私の頬は、ロイド様の胸元へピタリとくっついた。
「ロイド様……っ」
「ようやく君を独占できる。……全く。母ときたら、まさかパーティーの間中君を手放さないとはな。呆れてしまった」
ブツブツとそんなことを言っているロイド様の唇が、私の髪に触れていて少しくすぐったい。けれど、こうして抱き寄せられるのが嬉しくて、とてもホッとして、私は抵抗することなくその胸に体を預けた。
「……ロイド様のお母様が、今までどれほど思い悩んでおられたのかがよく分かりました。私のような者でも、嫁いでくることをあんなにも喜んでくださって。今日も不慣れな私のことを、何度も優しくフォローしてくださっていました」
「……ああ。その通りだな。たしかに、母の気持ちは分かる。これまで心労をかけてきたのは、他ならぬこの私なのだから。……君にそう言われたら、もう母を責める気にはなれないな」
ロイド様はそう言うと、私の顔を覗き込むようにして言った。
「私のような者でも、などと言わないでくれ。ミシェルだからこそ、母はあんなにも喜んでいるんだ。素直でひたむきで、誠実な君だからこそ。私にとっても母にとっても、君は特別な女性なんだよ」
「ロ、ロイド様……」
今日のロイド様はどこまでも優しい。……いや、毎日優しいのだけど、私を見つめるロイド様の今日の視線は、いつもよりもずっとずっと熱くて甘い。そんな気がする。体が火照ってどうしようもない。
「……そんなに見つめないでください。どうしていいか分からなくなります」
たまらずそう言って目を逸らすと、ロイド様は私の顎に触れ、容赦なく自分の方へと視線を誘導する。
「今日の君の特別な美しさを、やっとこうしてゆっくり堪能できるんだ。気が済むまで見つめさせてくれ」
「……っ、」
間近できらめく青い瞳は深く澄んでいて、そしてとても色っぽかった。
その瞳が、ふいに私の視界を埋め尽くす。
(……っ!)
軽く触れるだけの口づけをすると、ロイド様は私の膝の下に片腕を通し、私の体をふわりと持ち上げた。
「っ! きゃ……っ!」
驚いて思わず彼の首にしがみつくと、私の体はロイド様の膝の上に下ろされた。
「ち……っ、近すぎます! ロイド様……っ」
激しく動揺した私は、思わず彼の胸を両手で押して距離をとろうとしてしまう。
けれどロイド様は私の背に手を回ししっかりと抱きしめ、それを許さなかった。
「馬車が揺れるから、口づけがしづらい。……ここにいてくれ」
「そ……っ! ……ん……っ」
真っ赤になった私が返事をする間もなく、私の唇はもう一度彼によって塞がれた。
屋敷に着くまでの間、頭がクラクラするほどの甘いキスが、何度も与えられたのだった。
ーーーーー end ーーーーー
533
お気に入りに追加
2,009
あなたにおすすめの小説

初夜に大暴言を吐かれた伯爵夫人は、微笑みと共に我が道を行く ―旦那様、今更擦り寄られても困ります―
望月 或
恋愛
「お前の噂を聞いたぞ。毎夜町に出て男を求め、毎回違う男と朝までふしだらな行為に明け暮れているそうだな? その上糸目を付けず服や装飾品を買い漁り、多大な借金を背負っているとか……。そんな醜悪な女が俺の妻だとは非常に不愉快極まりない! 今後俺に話し掛けるな! 俺に一切関与するな! 同じ空気を吸ってるだけでとんでもなく不快だ……!!」
【王命】で決められた婚姻をし、ハイド・ランジニカ伯爵とオリービア・フレイグラント子爵令嬢の初夜は、彼のその暴言で始まった。
そして、それに返したオリービアの一言は、
「あらあら、まぁ」
の六文字だった。
屋敷に住まわせている、ハイドの愛人と噂されるユーカリや、その取巻きの使用人達の嫌がらせも何のその、オリービアは微笑みを絶やさず自分の道を突き進んでいく。
ユーカリだけを信じ心酔していたハイドだったが、オリービアが屋敷に来てから徐々に変化が表れ始めて……
※作者独自の世界観満載です。違和感を感じたら、「あぁ、こういう世界なんだな」と思って頂けたら有難いです……。

許婚と親友は両片思いだったので2人の仲を取り持つことにしました
結城芙由奈@12/27電子書籍配信中
恋愛
<2人の仲を応援するので、どうか私を嫌わないでください>
私には子供のころから決められた許嫁がいた。ある日、久しぶりに再会した親友を紹介した私は次第に2人がお互いを好きになっていく様子に気が付いた。どちらも私にとっては大切な存在。2人から邪魔者と思われ、嫌われたくはないので、私は全力で許嫁と親友の仲を取り持つ事を心に決めた。すると彼の評判が悪くなっていき、それまで冷たかった彼の態度が軟化してきて話は意外な展開に・・・?
※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています

里帰りをしていたら離婚届が送られてきたので今から様子を見に行ってきます
結城芙由奈@12/27電子書籍配信中
恋愛
<離婚届?納得いかないので今から内密に帰ります>
政略結婚で2年もの間「白い結婚」を続ける最中、妹の出産祝いで里帰りしていると突然届いた離婚届。あまりに理不尽で到底受け入れられないので内緒で帰ってみた結果・・・?
※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています

本日、私の大好きな幼馴染が大切な姉と結婚式を挙げます
結城芙由奈@12/27電子書籍配信中
恋愛
本日、私は大切な人達を2人同時に失います
<子供の頃から大好きだった幼馴染が恋する女性は私の5歳年上の姉でした。>
両親を亡くし、私を養ってくれた大切な姉に幸せになって貰いたい・・・そう願っていたのに姉は結婚を約束していた彼を事故で失ってしまった。悲しみに打ちひしがれる姉に寄り添う私の大好きな幼馴染。彼は決して私に振り向いてくれる事は無い。だから私は彼と姉が結ばれる事を願い、ついに2人は恋人同士になり、本日姉と幼馴染は結婚する。そしてそれは私が大切な2人を同時に失う日でもあった―。
※ 本編完結済。他視点での話、継続中。
※ 「カクヨム」「小説家になろう」にも掲載しています
※ 河口直人偏から少し大人向けの内容になります
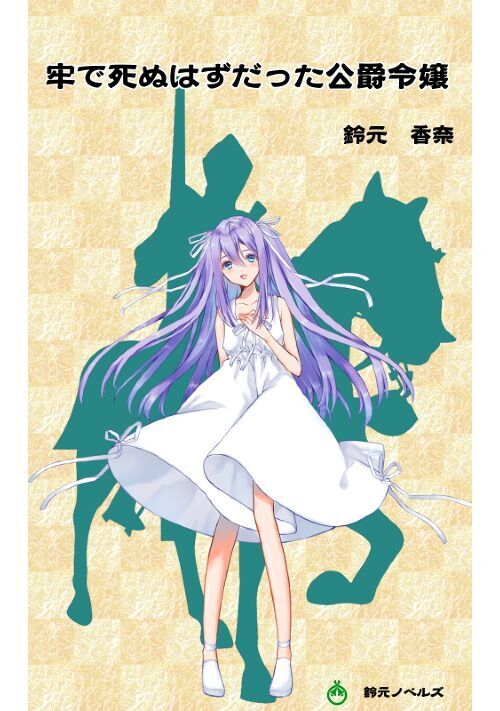
牢で死ぬはずだった公爵令嬢
鈴元 香奈
恋愛
婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。
表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。
小説家になろうさんにも投稿しています。

【完結】捨てられた双子のセカンドライフ
mazecco
ファンタジー
【第14回ファンタジー小説大賞 奨励賞受賞作】
王家の血を引きながらも、不吉の象徴とされる双子に生まれてしまったアーサーとモニカ。
父王から疎まれ、幼くして森に捨てられた二人だったが、身体能力が高いアーサーと魔法に適性のあるモニカは、力を合わせて厳しい環境を生き延びる。
やがて成長した二人は森を出て街で生活することを決意。
これはしあわせな第二の人生を送りたいと夢見た双子の物語。
冒険あり商売あり。
さまざまなことに挑戦しながら双子が日常生活?を楽しみます。
(話の流れは基本まったりしてますが、内容がハードな時もあります)

【完結】妖精姫と忘れられた恋~好きな人が結婚するみたいなので解放してあげようと思います~
塩羽間つづり
恋愛
お気に入り登録やエールいつもありがとうございます!
2.23完結しました!
ファルメリア王国の姫、メルティア・P・ファルメリアは、幼いころから恋をしていた。
相手は幼馴染ジーク・フォン・ランスト。
ローズの称号を賜る名門一族の次男だった。
幼いころの約束を信じ、いつかジークと結ばれると思っていたメルティアだが、ジークが結婚すると知り、メルティアの生活は一変する。
好きになってもらえるように慣れないお化粧をしたり、着飾ったりしてみたけれど反応はいまいち。
そしてだんだんと、メルティアは恋の邪魔をしているのは自分なのではないかと思いあたる。
それに気づいてから、メルティアはジークの幸せのためにジーク離れをはじめるのだが、思っていたようにはいかなくて……?
妖精が見えるお姫様と近衛騎士のすれ違う恋のお話
切なめ恋愛ファンタジー

【完結】長い眠りのその後で
maruko
恋愛
伯爵令嬢のアディルは王宮魔術師団の副団長サンディル・メイナードと結婚しました。
でも婚約してから婚姻まで一度も会えず、婚姻式でも、新居に向かう馬車の中でも目も合わせない旦那様。
いくら政略結婚でも幸せになりたいって思ってもいいでしょう?
このまま幸せになれるのかしらと思ってたら⋯⋯アレッ?旦那様が2人!!
どうして旦那様はずっと眠ってるの?
唖然としたけど強制的に旦那様の為に動かないと行けないみたい。
しょうがないアディル頑張りまーす!!
複雑な家庭環境で育って、醒めた目で世間を見ているアディルが幸せになるまでの物語です
全50話(2話分は登場人物と時系列の整理含む)
※他サイトでも投稿しております
ご都合主義、誤字脱字、未熟者ですが優しい目線で読んで頂けますと幸いです
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















