お気に入りに追加
12
あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

とある元令嬢の選択
こうじ
ファンタジー
アメリアは1年前まで公爵令嬢であり王太子の婚約者だった。しかし、ある日を境に一変した。今の彼女は小さな村で暮らすただの平民だ。そして、それは彼女が自ら下した選択であり結果だった。彼女は言う『今が1番幸せ』だ、と。何故貴族としての幸せよりも平民としての暮らしを決断したのか。そこには彼女しかわからない悩みがあった……。

【完結】義妹とやらが現れましたが認めません。〜断罪劇の次世代たち〜
福田 杜季
ファンタジー
侯爵令嬢のセシリアのもとに、ある日突然、義妹だという少女が現れた。
彼女はメリル。父親の友人であった彼女の父が不幸に見舞われ、親族に虐げられていたところを父が引き取ったらしい。
だがこの女、セシリアの父に欲しいものを買わせまくったり、人の婚約者に媚を打ったり、夜会で非常識な言動をくり返して顰蹙を買ったりと、どうしようもない。
「お義姉さま!」 . .
「姉などと呼ばないでください、メリルさん」
しかし、今はまだ辛抱のとき。
セシリアは来たるべき時へ向け、画策する。
──これは、20年前の断罪劇の続き。
喜劇がくり返されたとき、いま一度鉄槌は振り下ろされるのだ。
※ご指摘を受けて題名を変更しました。作者の見通しが甘くてご迷惑をおかけいたします。
旧題『義妹ができましたが大嫌いです。〜断罪劇の次世代たち〜』
※初投稿です。話に粗やご都合主義的な部分があるかもしれません。生あたたかい目で見守ってください。
※本編完結済みで、毎日1話ずつ投稿していきます。

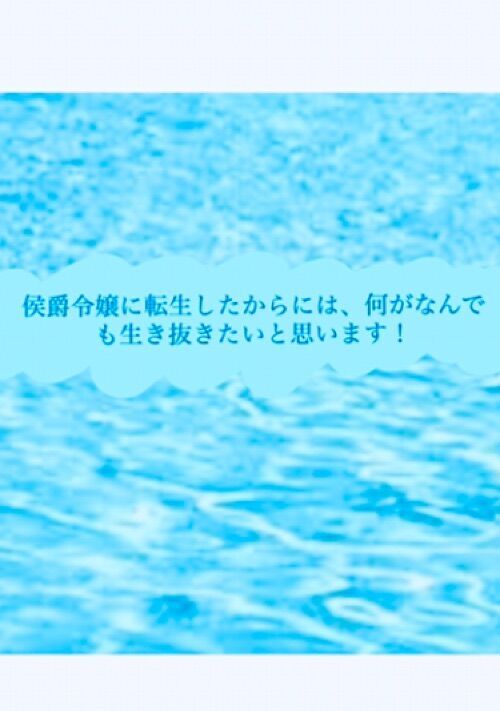
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」
音爽(ネソウ)
ファンタジー
容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。
本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。
しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。
*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

解呪の魔法しか使えないからとSランクパーティーから追放された俺は、呪いをかけられていた美少女ドラゴンを拾って最強へと至る
早見羽流
ファンタジー
「ロイ・クノール。お前はもう用無しだ」
解呪の魔法しか使えない初心者冒険者の俺は、呪いの宝箱を解呪した途端にSランクパーティーから追放され、ダンジョンの最深部へと蹴り落とされてしまう。
そこで出会ったのは封印された邪龍。解呪の能力を使って邪龍の封印を解くと、なんとそいつは美少女の姿になり、契約を結んで欲しいと頼んできた。
彼女は元は世界を守護する守護龍で、英雄や女神の陰謀によって邪龍に堕とされ封印されていたという。契約を結んだ俺は彼女を救うため、守護龍を封印し世界を牛耳っている女神や英雄の血を引く王家に立ち向かうことを誓ったのだった。
(1話2500字程度、1章まで完結保証です)

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















