5 / 61
夜空へ誓う
しおりを挟む
「旦那様」
屋敷に戻ると、女中のりよが真っ先に出て来た。
「どうなさったのですか? 釈放されたと聞きましたのにお戻りが随分と遅いので心配しておりました」
時刻はすでに夜四つに近かった。
新九郎は誤魔化すような作り笑顔を見せてから、
「ああ、すまぬ……その……少し考えを整理したくてな」
「また早月川ですか」
「ああ」
間違いではない。新九郎は頷いた。だが、辰之助と濃紺装束の者との斬り合いの件、そして大鳥家老の屋敷に寄ったことは言わなかった。
だが、りよの方から心配そうに言って来た。
「近頃、早月川の辺りは、まるで昔の笹川組のような者が現れて人を襲っていると聞いております。お気をつけくださいませ」
「ああ、わかった」
新九郎は履き物を脱いで式台に上がりながら、
「奈美はどうした?」
「ずっと心配して落ち着かぬ様子でございましたが、今日釈放されたと聞いて安心されたのか、もうお休みになられました」
「そうか。おりよにも心配かけたな、すまぬ」
「ええ。もし旦那さまに何かありましたら、と、私もずっと案じておりました」
そう言ったりよの目が潤み、行灯の灯に薄く光った。
新九郎は、思わずりよに触れたい衝動に駆られた。しかしぐっと自制して、
「釈放されたと言っても安心はできん。目付衆が調査をするそうだが、それを待っていても私は腹を切らされるだけであろう」
「え?」
りよは袖を目に当てた後に驚いた。
「詳しくは言えぬが……とても大きな力が私を陥れようとしているようだ」
「大きな力? どういうことでございましょうか」
りよは不思議そうに小首を傾げた。
「いずれわかる。とにかく、私の命、そしてこの黒須家は滅亡の淵に立たされている。それを防ぐ為、戻ったばかりだが、少し仮眠を取ったらすぐに鉢窪村に出掛ける。夜が空ける前にだ」
「すぐにですか? 慌ただしいことでございますね」
「仕方ない」
「お夜食はいかがなさいましょうか」
「いらぬ。外で少し食べて来た」
「では、明日の為に、むすびなど作っておきましょうか」
「それはありがたい。是非頼む」
新九郎は、強張っていた顔を緩ませた。
握り飯などはそもそも大した工夫のいらないものなのだが、りよの作る握り飯は不思議な旨さがあり、新九郎の好物であった。
「では、わたくしは準備をいたしますので、旦那様はお休みくださいませ」
「いつもすまぬな」
「いえ、とんでもございませぬ。わたくしの方こそ、旦那様に拾っていただけたのですから」
りよは、にこりと笑った。
りよは、元からいた女中ではない。
およそ一月前、新九郎が山回りから帰って来た夜道で、道端にうずくまっている町人風の女を見かけた。それがりよだった。声をかけると、城下へ向かっている途中に足を怪我してしまい、動けなくなってしまったと言う。家まで送ろう、と言うと、りよは家など無いと言う。
よくよく聞けば、りよは元々領内北方の港町、藤之津の小さな商家の一人娘であったが、商売が傾きかけていたところに両親が流行り病でなくなり、家が潰れてしまったと言う。
りよの父親は偏屈者であったので付き合いの深い親戚もおらず、りよは無一文で天涯孤独となってしまった。そこで、りよは城下に行けば何かしらの奉公の口があると思い、一人で城下へ向かった。
その途中で運が悪かったのか良かったのか、怪我をしてしまったところを新九郎に声をかけられたのであった。
新九郎はりよの事情を聞くと、自分の黒須家に女中に来ないかと言ってみた。ちょうどその頃、長年通いで来ていた下女が老齢の為にやめたいと申し出て来ていた。
黒須家は家禄を半分に減らされているとは言え、両親はなく、妹の奈美と二人だけである。女中一人を入れるぐらいの余裕はある。
りよが、新九郎の申し出を大喜びで受け入れたのは言うまでもなかった。
そして、新九郎は一刻半ほど仮眠を取った後、支度をして屋敷の裏口からまだ暗い夜空の下へと出た。
城から出て早月川に行った時はよく晴れた星月夜であったが、今は灰色の雲に覆われて月も星も見えなかった。
ーー雨が降るかもな。
新九郎は、雨気を孕んだ重い夜空を見上げて、万が一に備えて二刀の柄に柄袋をかけた。
その頃、家老大鳥順三郎は、ふとした胸騒ぎを覚えて目を覚ました。
上半身を起こし、薄闇の一点を睨むように見つめた。額から一筋の汗が垂れる。
しばらくすると立ち上がり、寝所の襖を開け、手を叩いて老爺の千吉を呼んだ。
「御用でございますか」
千吉は廊下の奥から静かに歩いて来て、順三郎の前に膝をついた。
「すまぬが、ひとっ走りして人を呼んで来てもらいたい」
順三郎はそう言い、呼ぶ人間の名を千吉に伝えた。
千吉は頷くと、すぐに屋敷を出て行った。
順三郎は廊下から縁側に出て、暗い夜空を睨むように見上げて呟いた。
「新兵衛よ……お前は守れなかったが……お前の息子だけは守ってみせるぞ、今度こそはな」
鉢窪村は、領内南東の山と山の間にあり、その名前の通り、すり鉢状の地形の中にある村であった。
高くはないが山を一つ越えて行かねばならないので、城下から歩いて行くと約一刻前後もかかる。遠い道である。
――小物成の控え……ちゃんと残してあればよいが。
新九郎は不安を感じ始めた。
鉢窪村の庄屋は祖先が元々戦国期に地侍であったので、苗字を許されており、今の当主は西川弥左衛門と言う。
四十手前で、祖先が武士であった為か、背は高く体格も良い。
だが性格は穏やかで礼儀正しく、旧知の新九郎が初めて役で来た当初は、言葉遣いもがらりと変えて、親切丁寧に村や仕事に関することを教えてくれた。
しかし一つ短所があり、粗忽者であった。
ちょっとした数を間違えたり、物をなくしたり、頼み事を忘れたりすることがよくある。
以前も、頼んでおいた書類をうっかり紛失してしまい、平謝りしてきた、と言うことがあった。
小物成帳の控えの作成は、習慣として続いてはいるが、残しておかなければならないと言う規則は無く曖昧であった。
それ故に、粗忽者の弥左衛門が紛失したりしていないか、新九郎は段々と心配になって来た。
あれこれ考えながら山を登っているうちに夜明けが訪れた。
だが、空は灰色の雲は広く垂れこめ、陽の光は薄かった。
そして峠を越え、朝露で草が濡れる林道を下って行くと、暗い朝靄の中に横たわっている鉢窪村が見えて来た。
すでに起きているのか、幾つかの民家から炊煙が立ち上っているのが見える。
鉢窪村に入ると、新九郎はすぐに西川弥左衛門の庄屋屋敷を訪ねた。
祖先がこの辺りを束ねていた地侍であっただけに、屋敷は武家屋敷のように大きく立派である。
訪いを入れると、まだ眠そうな顔をしている中年の下女が出て来た。
「まあ、これは黒須様。こんな早くから如何されましたか」
下女は驚きながら、新九郎を屋敷内に入れた。
「弥左衛門どのに急用があってな。このように朝早くからで申し訳ない。まだお休みであろう故、起こさずともよい。待たせていただく」
新九郎は、広い土間に入りながら言った。
「いえ、旦那さまはもう起きていらっしゃいます」
「なに? 随分と早いな」
「はい、いつもはまだ眠っておられるのですが、今日は珍しく夜が明ける前に起きて来られました」
「そうか。ならば事は早い」
「呼んでまいりますので、お待ちください」
下女は新九郎を客間に案内してから、そのまま弥左衛門に知らせに行った。
程なくして、弥左衛門が客間に現れて向かいに座った。
「これは新九郎さま、お早いですな。どうなさいましたか」
弥左衛門は新九郎を子供の頃から知っている。それゆえに、親しみを込めて名前で「新九郎さま」と呼び、新九郎もそれを許している。
早朝の突然の訪問だが、弥左衛門は特に驚いた様子もなく、にこにことした笑顔を見せた。
「ちと、深刻な事態が起きてな。弥左衛門どのに話があって参ったのだ」
「おや、深刻な事態とは」
眉をしかめる弥左衛門に、新九郎はこれまでの事情を話して聞かせた。
「と言うわけで、まずはそうだな。昨年の小物成帳の控えは取っておいているであろう。もしあれば見せてもらいたいのだが」
新九郎が言うと、弥左衛門は顔を青くして両手をつき、いきなり額を畳につけた。
「も、申し訳ございませぬ。実は、ちょうど次に新九郎様がお見えになったらお詫び申し上げようと思っていたのですが、あいにく、うちの下女が先日ごみと共に燃やしてしまったのでございます」
「ああっ……」
と、新九郎は思わず声を上げて目を閉じた。
心配が見事に当たってしまった。
「元はと言えば、私が手紙の下書きや必要のなくなった書類を燃やすよう命じていたところに、手違いで控えも混ぜてしまっていたのです。誠に申し訳ございませぬ。罰ならば受けまする」
畳に額を擦り付けて謝る弥左衛門を見て、新九郎は呻いた。
「ううむ、そうか……」
小物成の控えを紛失してしまった場合の罰則などない。
新九郎としては怒りたいところであったが、そこは堪えるしかなかった。
「では……他に何か、納入量がわかるような物はないか? 控えの下書きとか」
「下書き……他に……」
弥左衛門は顔を上げ、眉根を寄せて考え込んだが、
「申し訳ございませぬ、下書きなどはなく、他にも思い当たるようなものは……」
「ないか」
「はい。誠に申し訳ございませぬ」
弥左衛門は再び畳に額をすりつけた。
「これは困った」
新九郎は頭を抱えた。
しばし沈黙が流れた後、新九郎は弱り切った顔で、
「とりあえず、手間をかけるが共に城下まで来てもらえまいか?」
弥左衛門はぱっと顔を上げて、
「ええ。どこへでもお供いたします」
「すまぬな。その前に、村の様子など見せてもらえるかな。織機や作業の状況などを見てみたい」
「もちろんでございます、ご一緒いたします」
先祖代々からの屋敷であることと、地形の関係で、弥左衛門の庄屋屋敷だけが、微妙に村の中央から外れている。
新九郎は、弥左衛門と共に屋敷を出て、村の中央へ向かった。
すでに起きて炊事や作業をしている家々を回って見た。
どの家にも織機が一台あり、作業を中断したまま休んだと思われるところや、早めに朝食を済ませてまさにこれから作業をしようとしている若い娘などがいた。
しかし、特にこれと言って変わった様子はない。
「今月の量はいつもと変わらぬかな」
「ええ。権兵衛の妻が病で臥せっておりますので、その分少し少なくなるぐらいでございます」
「そうか」
新九郎はしばらく各家を見回った後、弥左衛門を振り返って、
「蔵を見せてくれるかな」
「ええ、ようございます」
村で収穫した青苧、各家で織った縮は、出来上がり次第、それぞれの蔵に入れて保管される。
蔵は、弥左衛門の庄屋屋敷の裏手にある。
二人は再び庄屋屋敷に戻り、裏手に回った。
弥左衛門が錠を開けて縮の蔵の中に案内する。
蔵の中は、四方の壁の上方に明かり取りの小窓があるが、まだ早朝である上に曇天であるので、薄暗くひんやりとしていた。
土蔵の壁に沿って、村人によって織られた縮がいくつも積み上げられている。
「新九郎さま、申し訳ございませぬが、朝の仕事がございますので、少し屋敷に戻らせていただいても構いませぬか? 城下へ行く準備もしなければなりませぬし」
弥左衛門が後ろから言った。
新九郎は振り返り、申し訳なさそうな顔をして、
「もちろんだ。時間を取らせてすまぬ」
「では。蔵の中はどうぞご自由にご検分くださいませ」
弥左衛門はそう言うと一礼し、蔵を出て行った。
――しかしこれは本当に困った。
新九郎は蔵の中を見回した。
最も新九郎の無実を証明できる効力を持つ小物成帳の控えがないのだ。
――とりあえず今月の見込み量を計算して……弥左衛門どのに共に来てもらって……それでどうするか。
新九郎は棚の側に寄り、積まれている縮を見ながら思案に耽った。
すると、突然背後でがたん、と音がした。
振り返ると、蔵の木戸が閉じられていた。次に、外から錠をかける音がした。
「どうした? 弥左衛門どの……何をする?」
新九郎は木戸に寄って声をかけた。
しかし、外から返答は無い。
「弥左衛門どの! 何故戸を閉める?」
新九郎は戸を叩いたが、やはり返事は無い。
何とかして戸を開けようとしたが、錠をかけられているのでびくともしない。閉じ込められてしまった。
――なんだ?
新九郎は顔色を変えた。
と、同時であった。
不審な剣気を感じて振り返ると、蔵の奥の暗がりの中から黒い人影が二つ、すうっと滑るように出て来た。
濃紺の上下に頭巾覆面姿である。
――蝙蝠やら燕とかか?
昨晩も三木辰之助が襲われているところに遭遇した。
近頃、夜闇の中で複数の藩士らを殺めて城下を騒がせている不審な連中である。
屋敷に戻ると、女中のりよが真っ先に出て来た。
「どうなさったのですか? 釈放されたと聞きましたのにお戻りが随分と遅いので心配しておりました」
時刻はすでに夜四つに近かった。
新九郎は誤魔化すような作り笑顔を見せてから、
「ああ、すまぬ……その……少し考えを整理したくてな」
「また早月川ですか」
「ああ」
間違いではない。新九郎は頷いた。だが、辰之助と濃紺装束の者との斬り合いの件、そして大鳥家老の屋敷に寄ったことは言わなかった。
だが、りよの方から心配そうに言って来た。
「近頃、早月川の辺りは、まるで昔の笹川組のような者が現れて人を襲っていると聞いております。お気をつけくださいませ」
「ああ、わかった」
新九郎は履き物を脱いで式台に上がりながら、
「奈美はどうした?」
「ずっと心配して落ち着かぬ様子でございましたが、今日釈放されたと聞いて安心されたのか、もうお休みになられました」
「そうか。おりよにも心配かけたな、すまぬ」
「ええ。もし旦那さまに何かありましたら、と、私もずっと案じておりました」
そう言ったりよの目が潤み、行灯の灯に薄く光った。
新九郎は、思わずりよに触れたい衝動に駆られた。しかしぐっと自制して、
「釈放されたと言っても安心はできん。目付衆が調査をするそうだが、それを待っていても私は腹を切らされるだけであろう」
「え?」
りよは袖を目に当てた後に驚いた。
「詳しくは言えぬが……とても大きな力が私を陥れようとしているようだ」
「大きな力? どういうことでございましょうか」
りよは不思議そうに小首を傾げた。
「いずれわかる。とにかく、私の命、そしてこの黒須家は滅亡の淵に立たされている。それを防ぐ為、戻ったばかりだが、少し仮眠を取ったらすぐに鉢窪村に出掛ける。夜が空ける前にだ」
「すぐにですか? 慌ただしいことでございますね」
「仕方ない」
「お夜食はいかがなさいましょうか」
「いらぬ。外で少し食べて来た」
「では、明日の為に、むすびなど作っておきましょうか」
「それはありがたい。是非頼む」
新九郎は、強張っていた顔を緩ませた。
握り飯などはそもそも大した工夫のいらないものなのだが、りよの作る握り飯は不思議な旨さがあり、新九郎の好物であった。
「では、わたくしは準備をいたしますので、旦那様はお休みくださいませ」
「いつもすまぬな」
「いえ、とんでもございませぬ。わたくしの方こそ、旦那様に拾っていただけたのですから」
りよは、にこりと笑った。
りよは、元からいた女中ではない。
およそ一月前、新九郎が山回りから帰って来た夜道で、道端にうずくまっている町人風の女を見かけた。それがりよだった。声をかけると、城下へ向かっている途中に足を怪我してしまい、動けなくなってしまったと言う。家まで送ろう、と言うと、りよは家など無いと言う。
よくよく聞けば、りよは元々領内北方の港町、藤之津の小さな商家の一人娘であったが、商売が傾きかけていたところに両親が流行り病でなくなり、家が潰れてしまったと言う。
りよの父親は偏屈者であったので付き合いの深い親戚もおらず、りよは無一文で天涯孤独となってしまった。そこで、りよは城下に行けば何かしらの奉公の口があると思い、一人で城下へ向かった。
その途中で運が悪かったのか良かったのか、怪我をしてしまったところを新九郎に声をかけられたのであった。
新九郎はりよの事情を聞くと、自分の黒須家に女中に来ないかと言ってみた。ちょうどその頃、長年通いで来ていた下女が老齢の為にやめたいと申し出て来ていた。
黒須家は家禄を半分に減らされているとは言え、両親はなく、妹の奈美と二人だけである。女中一人を入れるぐらいの余裕はある。
りよが、新九郎の申し出を大喜びで受け入れたのは言うまでもなかった。
そして、新九郎は一刻半ほど仮眠を取った後、支度をして屋敷の裏口からまだ暗い夜空の下へと出た。
城から出て早月川に行った時はよく晴れた星月夜であったが、今は灰色の雲に覆われて月も星も見えなかった。
ーー雨が降るかもな。
新九郎は、雨気を孕んだ重い夜空を見上げて、万が一に備えて二刀の柄に柄袋をかけた。
その頃、家老大鳥順三郎は、ふとした胸騒ぎを覚えて目を覚ました。
上半身を起こし、薄闇の一点を睨むように見つめた。額から一筋の汗が垂れる。
しばらくすると立ち上がり、寝所の襖を開け、手を叩いて老爺の千吉を呼んだ。
「御用でございますか」
千吉は廊下の奥から静かに歩いて来て、順三郎の前に膝をついた。
「すまぬが、ひとっ走りして人を呼んで来てもらいたい」
順三郎はそう言い、呼ぶ人間の名を千吉に伝えた。
千吉は頷くと、すぐに屋敷を出て行った。
順三郎は廊下から縁側に出て、暗い夜空を睨むように見上げて呟いた。
「新兵衛よ……お前は守れなかったが……お前の息子だけは守ってみせるぞ、今度こそはな」
鉢窪村は、領内南東の山と山の間にあり、その名前の通り、すり鉢状の地形の中にある村であった。
高くはないが山を一つ越えて行かねばならないので、城下から歩いて行くと約一刻前後もかかる。遠い道である。
――小物成の控え……ちゃんと残してあればよいが。
新九郎は不安を感じ始めた。
鉢窪村の庄屋は祖先が元々戦国期に地侍であったので、苗字を許されており、今の当主は西川弥左衛門と言う。
四十手前で、祖先が武士であった為か、背は高く体格も良い。
だが性格は穏やかで礼儀正しく、旧知の新九郎が初めて役で来た当初は、言葉遣いもがらりと変えて、親切丁寧に村や仕事に関することを教えてくれた。
しかし一つ短所があり、粗忽者であった。
ちょっとした数を間違えたり、物をなくしたり、頼み事を忘れたりすることがよくある。
以前も、頼んでおいた書類をうっかり紛失してしまい、平謝りしてきた、と言うことがあった。
小物成帳の控えの作成は、習慣として続いてはいるが、残しておかなければならないと言う規則は無く曖昧であった。
それ故に、粗忽者の弥左衛門が紛失したりしていないか、新九郎は段々と心配になって来た。
あれこれ考えながら山を登っているうちに夜明けが訪れた。
だが、空は灰色の雲は広く垂れこめ、陽の光は薄かった。
そして峠を越え、朝露で草が濡れる林道を下って行くと、暗い朝靄の中に横たわっている鉢窪村が見えて来た。
すでに起きているのか、幾つかの民家から炊煙が立ち上っているのが見える。
鉢窪村に入ると、新九郎はすぐに西川弥左衛門の庄屋屋敷を訪ねた。
祖先がこの辺りを束ねていた地侍であっただけに、屋敷は武家屋敷のように大きく立派である。
訪いを入れると、まだ眠そうな顔をしている中年の下女が出て来た。
「まあ、これは黒須様。こんな早くから如何されましたか」
下女は驚きながら、新九郎を屋敷内に入れた。
「弥左衛門どのに急用があってな。このように朝早くからで申し訳ない。まだお休みであろう故、起こさずともよい。待たせていただく」
新九郎は、広い土間に入りながら言った。
「いえ、旦那さまはもう起きていらっしゃいます」
「なに? 随分と早いな」
「はい、いつもはまだ眠っておられるのですが、今日は珍しく夜が明ける前に起きて来られました」
「そうか。ならば事は早い」
「呼んでまいりますので、お待ちください」
下女は新九郎を客間に案内してから、そのまま弥左衛門に知らせに行った。
程なくして、弥左衛門が客間に現れて向かいに座った。
「これは新九郎さま、お早いですな。どうなさいましたか」
弥左衛門は新九郎を子供の頃から知っている。それゆえに、親しみを込めて名前で「新九郎さま」と呼び、新九郎もそれを許している。
早朝の突然の訪問だが、弥左衛門は特に驚いた様子もなく、にこにことした笑顔を見せた。
「ちと、深刻な事態が起きてな。弥左衛門どのに話があって参ったのだ」
「おや、深刻な事態とは」
眉をしかめる弥左衛門に、新九郎はこれまでの事情を話して聞かせた。
「と言うわけで、まずはそうだな。昨年の小物成帳の控えは取っておいているであろう。もしあれば見せてもらいたいのだが」
新九郎が言うと、弥左衛門は顔を青くして両手をつき、いきなり額を畳につけた。
「も、申し訳ございませぬ。実は、ちょうど次に新九郎様がお見えになったらお詫び申し上げようと思っていたのですが、あいにく、うちの下女が先日ごみと共に燃やしてしまったのでございます」
「ああっ……」
と、新九郎は思わず声を上げて目を閉じた。
心配が見事に当たってしまった。
「元はと言えば、私が手紙の下書きや必要のなくなった書類を燃やすよう命じていたところに、手違いで控えも混ぜてしまっていたのです。誠に申し訳ございませぬ。罰ならば受けまする」
畳に額を擦り付けて謝る弥左衛門を見て、新九郎は呻いた。
「ううむ、そうか……」
小物成の控えを紛失してしまった場合の罰則などない。
新九郎としては怒りたいところであったが、そこは堪えるしかなかった。
「では……他に何か、納入量がわかるような物はないか? 控えの下書きとか」
「下書き……他に……」
弥左衛門は顔を上げ、眉根を寄せて考え込んだが、
「申し訳ございませぬ、下書きなどはなく、他にも思い当たるようなものは……」
「ないか」
「はい。誠に申し訳ございませぬ」
弥左衛門は再び畳に額をすりつけた。
「これは困った」
新九郎は頭を抱えた。
しばし沈黙が流れた後、新九郎は弱り切った顔で、
「とりあえず、手間をかけるが共に城下まで来てもらえまいか?」
弥左衛門はぱっと顔を上げて、
「ええ。どこへでもお供いたします」
「すまぬな。その前に、村の様子など見せてもらえるかな。織機や作業の状況などを見てみたい」
「もちろんでございます、ご一緒いたします」
先祖代々からの屋敷であることと、地形の関係で、弥左衛門の庄屋屋敷だけが、微妙に村の中央から外れている。
新九郎は、弥左衛門と共に屋敷を出て、村の中央へ向かった。
すでに起きて炊事や作業をしている家々を回って見た。
どの家にも織機が一台あり、作業を中断したまま休んだと思われるところや、早めに朝食を済ませてまさにこれから作業をしようとしている若い娘などがいた。
しかし、特にこれと言って変わった様子はない。
「今月の量はいつもと変わらぬかな」
「ええ。権兵衛の妻が病で臥せっておりますので、その分少し少なくなるぐらいでございます」
「そうか」
新九郎はしばらく各家を見回った後、弥左衛門を振り返って、
「蔵を見せてくれるかな」
「ええ、ようございます」
村で収穫した青苧、各家で織った縮は、出来上がり次第、それぞれの蔵に入れて保管される。
蔵は、弥左衛門の庄屋屋敷の裏手にある。
二人は再び庄屋屋敷に戻り、裏手に回った。
弥左衛門が錠を開けて縮の蔵の中に案内する。
蔵の中は、四方の壁の上方に明かり取りの小窓があるが、まだ早朝である上に曇天であるので、薄暗くひんやりとしていた。
土蔵の壁に沿って、村人によって織られた縮がいくつも積み上げられている。
「新九郎さま、申し訳ございませぬが、朝の仕事がございますので、少し屋敷に戻らせていただいても構いませぬか? 城下へ行く準備もしなければなりませぬし」
弥左衛門が後ろから言った。
新九郎は振り返り、申し訳なさそうな顔をして、
「もちろんだ。時間を取らせてすまぬ」
「では。蔵の中はどうぞご自由にご検分くださいませ」
弥左衛門はそう言うと一礼し、蔵を出て行った。
――しかしこれは本当に困った。
新九郎は蔵の中を見回した。
最も新九郎の無実を証明できる効力を持つ小物成帳の控えがないのだ。
――とりあえず今月の見込み量を計算して……弥左衛門どのに共に来てもらって……それでどうするか。
新九郎は棚の側に寄り、積まれている縮を見ながら思案に耽った。
すると、突然背後でがたん、と音がした。
振り返ると、蔵の木戸が閉じられていた。次に、外から錠をかける音がした。
「どうした? 弥左衛門どの……何をする?」
新九郎は木戸に寄って声をかけた。
しかし、外から返答は無い。
「弥左衛門どの! 何故戸を閉める?」
新九郎は戸を叩いたが、やはり返事は無い。
何とかして戸を開けようとしたが、錠をかけられているのでびくともしない。閉じ込められてしまった。
――なんだ?
新九郎は顔色を変えた。
と、同時であった。
不審な剣気を感じて振り返ると、蔵の奥の暗がりの中から黒い人影が二つ、すうっと滑るように出て来た。
濃紺の上下に頭巾覆面姿である。
――蝙蝠やら燕とかか?
昨晩も三木辰之助が襲われているところに遭遇した。
近頃、夜闇の中で複数の藩士らを殺めて城下を騒がせている不審な連中である。
1
お気に入りに追加
68
あなたにおすすめの小説

鬼を討つ〜徳川十六将・渡辺守綱記〜
八ケ代大輔
歴史・時代
徳川家康を天下に導いた十六人の家臣「徳川十六将」。そのうちの1人「槍の半蔵」と称され、服部半蔵と共に「両半蔵」と呼ばれた渡辺半蔵守綱の一代記。彼の祖先は酒天童子を倒した源頼光四天王の筆頭で鬼を斬ったとされる渡辺綱。徳川家康と同い歳の彼の人生は徳川家康と共に歩んだものでした。渡辺半蔵守綱の生涯を通して徳川家康が天下を取るまでの道のりを描く。表紙画像・すずき孔先生。

武田信玄の奇策・東北蝦夷地侵攻作戦ついに発動す!
沙羅双樹
歴史・時代
歴史的には、武田信玄は上洛途中で亡くなったとされていますが、もしも、信玄が健康そのもので、そして、上洛の前に、まずは東北と蝦夷地攻略を考えたら日本の歴史はどうなっていたでしょうか。この小説は、そんな「夢の信玄東北蝦夷地侵攻大作戦」です。
カクヨムで連載中の小説を加筆訂正してお届けします。
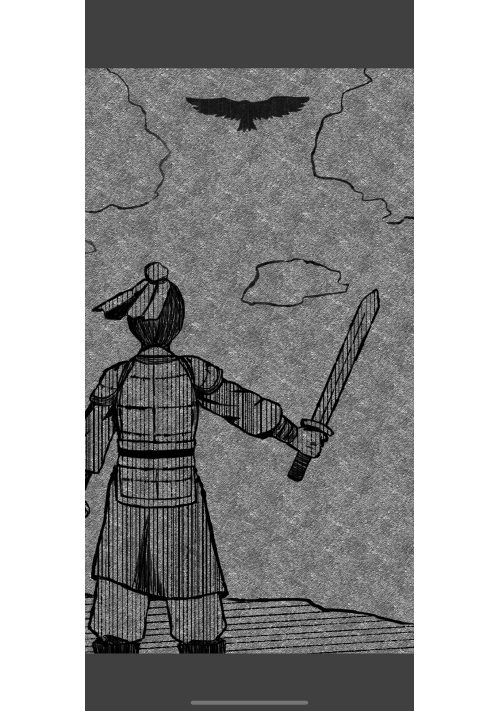
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

姫様、江戸を斬る 黒猫玉の御家騒動記
あこや(亜胡夜カイ)
歴史・時代
旧題:黒猫・玉、江戸を駆ける。~美弥姫初恋顛末~
つやつやの毛並みと緑の目がご自慢の黒猫・玉の飼い主は大名家の美弥姫様。この姫様、見目麗しいのにとんだはねかえりで新陰流・免許皆伝の腕前を誇る変わり者。その姫様が恋をしたらしい。もうすぐお輿入れだというのに。──男装の美弥姫が江戸の町を徘徊中、出会った二人の若侍、律と若。二人のお家騒動に自ら首を突っ込んだ姫の身に危険が迫る。そして初恋の行方は──
花のお江戸で美猫と姫様が大活躍!外題は~みやひめはつこいのてんまつ~
第6回歴史・時代小説大賞で大賞を頂きました!皆さまよりの応援、お励ましに心より御礼申し上げます。
有難うございました。
~お知らせ~現在、書籍化進行中でございます。21/9/16をもちまして、非公開とさせて頂きます。書籍化に関わる詳細は、以降近況ボードでご報告予定です。どうぞよろしくお願い致します。

腑抜けは要らない ~異国の美女と恋に落ち、腑抜けた皇子との縁を断ち切ることに成功した媛は、別の皇子と幸せを掴む~
夏笆(なつは)
歴史・時代
|今皇《いますめらぎ》の皇子である若竹と婚姻の約束をしていた|白朝《しろあさ》は、難破船に乗っていた異国の美女、|美鈴《みれい》に心奪われた挙句、白朝の父が白朝の為に建てた|花館《はなやかた》を勝手に美鈴に授けた若竹に見切りを付けるべく、父への直談判に臨む。
思いがけず、父だけでなく国の主要人物が揃う場で訴えることになり、青くなるも、白朝は無事、若竹との破談を勝ち取った。
しかしそこで言い渡されたのは、もうひとりの皇子である|石工《いしく》との婚姻。
石工に余り好かれていない自覚のある白朝は、その嫌がる顔を想像して慄くも、意外や意外、石工は白朝との縁談をすんなりと受け入れる。
その後も順調に石工との仲を育む白朝だが、若竹や美鈴に絡まれ、窃盗されと迷惑を被りながらも幸せになって行く。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

佐々木小次郎と名乗った男は四度死んだふりをした
迷熊井 泥(Make my day)
歴史・時代
巌流島で武蔵と戦ったあの佐々木小次郎は剣聖伊藤一刀斎に剣を学び、徳川家のため幕府を脅かす海賊を粛清し、たった一人で島津と戦い、豊臣秀頼の捜索に人生を捧げた公儀隠密だった。孤独に生きた宮本武蔵を理解し最も慕ったのもじつはこの佐々木小次郎を名乗った男だった。任務のために巌流島での決闘を演じ通算四度も死んだふりをした実在した超人剣士の物語である。

雨降って地固まる
江馬 百合子
歴史・時代
時は仮想戦国時代。
敵国の殿の元へ嫁ぐこととなった葵は、持ち前の明るさと聡明さで、様々な難局を乗り越えて行きます。頑なな彼の心の氷が溶ける日は来るのでしょうか。
「貴方様の苦しみが癒えることはないのかもしれません。
しかしながら、覚えておいてくださいませ。
私はずっと、貴方様のお側に居ります」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















