2 / 9
1話
1
しおりを挟む
小川が流れ、その上に小さな橋がかかっている。それを渡り、辺りを見渡す。春が終わり、初夏の羽音が、そこかしこから聞こえだしてきた。叢林の中を歩いていると、眼前に立派な日本家屋の豪邸が、堅牢にされどおしとやかに佇んでいた。
増 けい子は、門をくぐり、黒い扉の前に立った。扉を叩き、
「ごめんください」
と声を発した。応答は無い。そこで増けい子は思い出したーー勝手に入っていいことにである。
「お邪魔します」
一応、礼をして靴を揃え中に入った。廊下をまっすぐ進み以前に説明を受けた通り、奥の部屋まで向かった。すると、
「こっちじゃ」と声がしたので、増けい子は、声のほうの障子を開ける。そこには頬が痩せた青年がベッドの上で横になっていた。
増けい子は、姿勢をただし、
「今後、この家のお世話をさせていただく、増けい子と申します。よろしくお願いしま――」
「かたーい!」
すべてを言い終える前に強烈な一言が増けい子の耳に響いた。
「そんな堅苦しい挨拶、聞きたくないのう。――増けい子、ます、ます……おます! 今日からおますと呼ばせてもらおう!」
高笑いをしている坂井ホタルにあっけに取られたおますであった。
「あ、それから俺の事は、ホタルと呼び捨てにしてくれていいぞ」
「はあ」
と言われるがまま、おますは頷いた。
「ところでおますよ。その手に持っているのはなんだ?」
その一言でおますは思い出した。
「あ、これ……えっと、お、お届け物だそうです」
そう言って、ホタルにおますは持っていた物を手渡した。
「ランプ…いやランタンだな」
「えっと……この屋敷に入る前に、金髪の男性にこれを渡してくれと頼まれまして」
「先生からの魔法のアイテムか!」
*
「面接ってあなたがするんですね」
「うん。雇い主に任されていてね」
金髪オッドアイの男、ハーリーがコーヒーを啜っている。洒落たテラスのカフェで面接とは……マルチ商法の勧誘を受けているみたいだ。と心中で述べた。
「私は要するに、巷で有名な幽霊屋敷に住み込んで、家の管理をしろってことですか?」
「そそ。でも決まり事は守ってね」
おますは頷く。そして疑問を口にした。
「その……あまり信じられないのですけど、病弱な青年の幽霊がそこに住んでいるって……それって出会った時におっしゃっていた青年が幽霊だったってことですよね?」
「そうなんだよ~。恐いよね~」
ニコニコしたハーリーの顔から恐怖の恐の字も伺えなかった。
まずこの現代において、お化けや魔法といった非科学的な現象が起こっていると言われて、はい、そうですか……と信じるわけなどない。しかしだ、この説明を飲み込めば、住む所に加えてお給金までもらえるのだ。多少のことは受け入れていく――おますはそう考えながら、無理やり自分自身を納得させるよう努めた。
「大丈夫なんでしょうか?」
「ん? 無害だよ。まあ、男と一つ屋根の下っていうのは多少不安かしれないけど」
「そうじゃなくて……」
おますは祟られたりするのではといった不安を頭の中に浮かべるのであった。
「おもしろいことを考えるね。祟りなんて」
ギョッとおますは目を丸くした。どうして自分の考えたことがわかったのであろうかと……。
「僕は魔法使いだからね。君の心なんてお見通しさ」
おますは苦笑いをした。
「それに君は、こういったオカルト的なことを一般の人よりは信じる方じゃないのかい? 君の体質なり境遇的な部分で」
おますの眼が彼を睨みつけた。
「少し不幸なことが続いているだけでしょう。そんな人、世界に何人でもいるわ」
「そうだね。でもこの日本で戸籍をなくなっているなんて早々ありえないよ。まるで呪われているみたいだ」
おますは何も言い返せなかった。戸籍が紛失しているだけならまだしも、虚偽の申請やらなんやらと犯罪者扱いにされそうでもあった。
そんなこともあり、この自称魔法使いの言葉を信じ、おますは住み込みの仕事を受けることにした。その中身はやっぱり変なものであった。
「約束は守ります。あの時に渡された紙にかかれた内容はすべて覚えました」
「うん、頼むね。ではこれを――」
そういってハーリーは高さのある直方体の箱をおますの前に置いた。
「これは……」
「お察しの通り、約束事の一つ。〝月に一度、僕からの贈り物を渡す〟そう魔法のアイテムだ」
「そんなこと言って、魔法のアイテムでもなんでもないんでしょう?」
ハーリーはいたずらな笑みを浮かべる。
「彼がそう思っているのだから、それは魔法がかかっていなくても魔法のアイテムさ」
それはもうペテンだ……そんなことをしてもしバレたらどうするのか……その場にいる私が責められるではないか。おますは不服そうにアイスティーを飲む。
「だから〝僕と君の関係は知らない者同士〟という約束を書いていただろう?」
おますは黙した。まだ聞かなければならないことはたくさんあるのに、ハーリーが席を立った。
「さて、僕もそろそろ別の所に行かなくてはならないので」
と伝票を取った。
「では増さん、しっかり励んでくださいね」
カラリと氷が鳴り、何かに反射した太陽の光線がテラスに降り注いだ。一瞬、おますは目を塞ぎ、開いた時にはハーリーの姿はなかった。アイスティーを飲み干し、おますも店を出て、屋敷へと向かった。
*
「んーこれはどんな効果があると思う?」
ベットに座っているホタルは、ランタンの淵をなぞりながらおますに尋ねた。下手なことを言えないおますは苦笑いを浮かべ、
「どうなんでしょうね……」
濁す言い方しかできなかった。何の効果もないということをおますは知っている。知っているだけにそれを悟られずに接するのはなかなか難しい。
ホタルはおますの顔をじっと見つめた。その視線におますは嫌な汗をかく。ホタルは気づいてしまったのか? すると
「おますよ」
「はい……」
「信じてないな」
「はい?」
「先生のことだ。これをおますに預けた男性は、魔法使いということをだ」
「えっと……」
おますは反応に困った。
「無理もない。聡明かつ神秘的なお方だ。おますのような一般人には、そのすごさがわからなかったのであろう」
怪しくて、胡散臭いイメージはすごいのだけどな……と口にするのをおますは堪えた。
「そもそも、まだ俺と先生の出会いの話をしていなかったな」
といってホタルは語りだした。おますはそれを黙って聞いていた。そしてこの男がもうすでに亡くなっている事実が不意に頭をよぎり、戸惑う心が胸をざわつかせた。
「どうしたおます? 顔が青いぞ」
気づけば、ホタルは立ち上がっていておますの目の前にいた。
「え、あ、いや!」
びっくりして後ずさりし、腰が抜け、尻もちをつきそうになったところでおますの体がピタリと止まった。
「大丈夫か?」
とホタルがおますの手をしっかり握っていた。そのことを認識したおますは、
――ひゃッ! と叫び、ホタルに握られた手を無理やり振りほどいた。そしてドンと尻もちをついた。おますはホタルに触れれたことが逆に怖かった。この感情は無意識に大きな虫を掴んだ感覚に似ていた。
「おます……おぬし」
しまった……とおますは咄嗟の行動を悔いた。
「初心じゃのう」
「はい?」
思っていたのと違う発言だった。
「男に触れられただけで、その反応――かわゆい奴よ。まあまあ大丈夫じゃ。俺のタイプはもっとこうメリハリのある感じのセクシーな娘じゃ」
ホタルは咳払いをして
「だからお主のようなふくよかな体型は……」
は? ふくよかだと?――愛想笑いをするおますの瞼の奥の目が血走る。今度はホタルの顔が真っ青になった。ホタルは体型のことでおますをからかうのはやめておこうとこの時誓った。
「ところで、おますよ。お主の部屋へ案内するぞ」
話題を変え、ホタルは部屋を出るため障子を開けた。廊下を進み、縁側から見える日本庭園。その静かな荘厳さにおますは息を呑み、
「素敵」
とそうこぼした。
「そうじゃろ?」
ホタルが言ったと同時にカコンといった音が庭に響いた。足を止め、おますは音の方に顔を向けた。
「ししおどし……」
「おますを歓迎しているのかのう。手入れしてなくて、上手く動かない時があるんじゃが」
また廊下を左に折れた一番端の部屋。
「ここがおますの部屋じゃ」
「うわあ~」
障子を開けると、ほこりが舞った。
「汚くてすまぬな。そうじをして好きに使ってくれ、それから掃除用具は――」
言いかけてこじらせた咳をホタルはした。
「大丈夫ですか」
おますはホタルの肩を抱く。
「すまぬ。反対側に物置がある。そこから掃除用具があるから取って使ってくれ。晩飯は夜七時にお願いする。それから」
「もう大丈夫です。部屋で休んでいてください」
すまぬそう言ってホタルは部屋に向かった。おますは腕まくりし、
「さ、仕事だ!」と気合いを入れた。
増 けい子は、門をくぐり、黒い扉の前に立った。扉を叩き、
「ごめんください」
と声を発した。応答は無い。そこで増けい子は思い出したーー勝手に入っていいことにである。
「お邪魔します」
一応、礼をして靴を揃え中に入った。廊下をまっすぐ進み以前に説明を受けた通り、奥の部屋まで向かった。すると、
「こっちじゃ」と声がしたので、増けい子は、声のほうの障子を開ける。そこには頬が痩せた青年がベッドの上で横になっていた。
増けい子は、姿勢をただし、
「今後、この家のお世話をさせていただく、増けい子と申します。よろしくお願いしま――」
「かたーい!」
すべてを言い終える前に強烈な一言が増けい子の耳に響いた。
「そんな堅苦しい挨拶、聞きたくないのう。――増けい子、ます、ます……おます! 今日からおますと呼ばせてもらおう!」
高笑いをしている坂井ホタルにあっけに取られたおますであった。
「あ、それから俺の事は、ホタルと呼び捨てにしてくれていいぞ」
「はあ」
と言われるがまま、おますは頷いた。
「ところでおますよ。その手に持っているのはなんだ?」
その一言でおますは思い出した。
「あ、これ……えっと、お、お届け物だそうです」
そう言って、ホタルにおますは持っていた物を手渡した。
「ランプ…いやランタンだな」
「えっと……この屋敷に入る前に、金髪の男性にこれを渡してくれと頼まれまして」
「先生からの魔法のアイテムか!」
*
「面接ってあなたがするんですね」
「うん。雇い主に任されていてね」
金髪オッドアイの男、ハーリーがコーヒーを啜っている。洒落たテラスのカフェで面接とは……マルチ商法の勧誘を受けているみたいだ。と心中で述べた。
「私は要するに、巷で有名な幽霊屋敷に住み込んで、家の管理をしろってことですか?」
「そそ。でも決まり事は守ってね」
おますは頷く。そして疑問を口にした。
「その……あまり信じられないのですけど、病弱な青年の幽霊がそこに住んでいるって……それって出会った時におっしゃっていた青年が幽霊だったってことですよね?」
「そうなんだよ~。恐いよね~」
ニコニコしたハーリーの顔から恐怖の恐の字も伺えなかった。
まずこの現代において、お化けや魔法といった非科学的な現象が起こっていると言われて、はい、そうですか……と信じるわけなどない。しかしだ、この説明を飲み込めば、住む所に加えてお給金までもらえるのだ。多少のことは受け入れていく――おますはそう考えながら、無理やり自分自身を納得させるよう努めた。
「大丈夫なんでしょうか?」
「ん? 無害だよ。まあ、男と一つ屋根の下っていうのは多少不安かしれないけど」
「そうじゃなくて……」
おますは祟られたりするのではといった不安を頭の中に浮かべるのであった。
「おもしろいことを考えるね。祟りなんて」
ギョッとおますは目を丸くした。どうして自分の考えたことがわかったのであろうかと……。
「僕は魔法使いだからね。君の心なんてお見通しさ」
おますは苦笑いをした。
「それに君は、こういったオカルト的なことを一般の人よりは信じる方じゃないのかい? 君の体質なり境遇的な部分で」
おますの眼が彼を睨みつけた。
「少し不幸なことが続いているだけでしょう。そんな人、世界に何人でもいるわ」
「そうだね。でもこの日本で戸籍をなくなっているなんて早々ありえないよ。まるで呪われているみたいだ」
おますは何も言い返せなかった。戸籍が紛失しているだけならまだしも、虚偽の申請やらなんやらと犯罪者扱いにされそうでもあった。
そんなこともあり、この自称魔法使いの言葉を信じ、おますは住み込みの仕事を受けることにした。その中身はやっぱり変なものであった。
「約束は守ります。あの時に渡された紙にかかれた内容はすべて覚えました」
「うん、頼むね。ではこれを――」
そういってハーリーは高さのある直方体の箱をおますの前に置いた。
「これは……」
「お察しの通り、約束事の一つ。〝月に一度、僕からの贈り物を渡す〟そう魔法のアイテムだ」
「そんなこと言って、魔法のアイテムでもなんでもないんでしょう?」
ハーリーはいたずらな笑みを浮かべる。
「彼がそう思っているのだから、それは魔法がかかっていなくても魔法のアイテムさ」
それはもうペテンだ……そんなことをしてもしバレたらどうするのか……その場にいる私が責められるではないか。おますは不服そうにアイスティーを飲む。
「だから〝僕と君の関係は知らない者同士〟という約束を書いていただろう?」
おますは黙した。まだ聞かなければならないことはたくさんあるのに、ハーリーが席を立った。
「さて、僕もそろそろ別の所に行かなくてはならないので」
と伝票を取った。
「では増さん、しっかり励んでくださいね」
カラリと氷が鳴り、何かに反射した太陽の光線がテラスに降り注いだ。一瞬、おますは目を塞ぎ、開いた時にはハーリーの姿はなかった。アイスティーを飲み干し、おますも店を出て、屋敷へと向かった。
*
「んーこれはどんな効果があると思う?」
ベットに座っているホタルは、ランタンの淵をなぞりながらおますに尋ねた。下手なことを言えないおますは苦笑いを浮かべ、
「どうなんでしょうね……」
濁す言い方しかできなかった。何の効果もないということをおますは知っている。知っているだけにそれを悟られずに接するのはなかなか難しい。
ホタルはおますの顔をじっと見つめた。その視線におますは嫌な汗をかく。ホタルは気づいてしまったのか? すると
「おますよ」
「はい……」
「信じてないな」
「はい?」
「先生のことだ。これをおますに預けた男性は、魔法使いということをだ」
「えっと……」
おますは反応に困った。
「無理もない。聡明かつ神秘的なお方だ。おますのような一般人には、そのすごさがわからなかったのであろう」
怪しくて、胡散臭いイメージはすごいのだけどな……と口にするのをおますは堪えた。
「そもそも、まだ俺と先生の出会いの話をしていなかったな」
といってホタルは語りだした。おますはそれを黙って聞いていた。そしてこの男がもうすでに亡くなっている事実が不意に頭をよぎり、戸惑う心が胸をざわつかせた。
「どうしたおます? 顔が青いぞ」
気づけば、ホタルは立ち上がっていておますの目の前にいた。
「え、あ、いや!」
びっくりして後ずさりし、腰が抜け、尻もちをつきそうになったところでおますの体がピタリと止まった。
「大丈夫か?」
とホタルがおますの手をしっかり握っていた。そのことを認識したおますは、
――ひゃッ! と叫び、ホタルに握られた手を無理やり振りほどいた。そしてドンと尻もちをついた。おますはホタルに触れれたことが逆に怖かった。この感情は無意識に大きな虫を掴んだ感覚に似ていた。
「おます……おぬし」
しまった……とおますは咄嗟の行動を悔いた。
「初心じゃのう」
「はい?」
思っていたのと違う発言だった。
「男に触れられただけで、その反応――かわゆい奴よ。まあまあ大丈夫じゃ。俺のタイプはもっとこうメリハリのある感じのセクシーな娘じゃ」
ホタルは咳払いをして
「だからお主のようなふくよかな体型は……」
は? ふくよかだと?――愛想笑いをするおますの瞼の奥の目が血走る。今度はホタルの顔が真っ青になった。ホタルは体型のことでおますをからかうのはやめておこうとこの時誓った。
「ところで、おますよ。お主の部屋へ案内するぞ」
話題を変え、ホタルは部屋を出るため障子を開けた。廊下を進み、縁側から見える日本庭園。その静かな荘厳さにおますは息を呑み、
「素敵」
とそうこぼした。
「そうじゃろ?」
ホタルが言ったと同時にカコンといった音が庭に響いた。足を止め、おますは音の方に顔を向けた。
「ししおどし……」
「おますを歓迎しているのかのう。手入れしてなくて、上手く動かない時があるんじゃが」
また廊下を左に折れた一番端の部屋。
「ここがおますの部屋じゃ」
「うわあ~」
障子を開けると、ほこりが舞った。
「汚くてすまぬな。そうじをして好きに使ってくれ、それから掃除用具は――」
言いかけてこじらせた咳をホタルはした。
「大丈夫ですか」
おますはホタルの肩を抱く。
「すまぬ。反対側に物置がある。そこから掃除用具があるから取って使ってくれ。晩飯は夜七時にお願いする。それから」
「もう大丈夫です。部屋で休んでいてください」
すまぬそう言ってホタルは部屋に向かった。おますは腕まくりし、
「さ、仕事だ!」と気合いを入れた。
11
お気に入りに追加
48
あなたにおすすめの小説

作ろう! 女の子だけの町 ~未来の技術で少女に生まれ変わり、女の子達と楽園暮らし~
白井よもぎ
キャラ文芸
地元の企業に勤める会社員・安藤優也は、林の中で瀕死の未来人と遭遇した。
その未来人は絶滅の危機に瀕した未来を変える為、タイムマシンで現代にやってきたと言う。
しかし時間跳躍の事故により、彼は瀕死の重傷を負ってしまっていた。
自分の命が助からないと悟った未来人は、その場に居合わせた優也に、使命と未来の技術が全て詰まったロボットを託して息絶える。
奇しくも、人類の未来を委ねられた優也。
だが、優也は少女をこよなく愛する変態だった。
未来の技術を手に入れた優也は、その技術を用いて自らを少女へと生まれ変わらせ、不幸な環境で苦しんでいる少女達を勧誘しながら、女の子だけの楽園を作る。

終わった世界の蒸気屋すずさん
デバスズメ
キャラ文芸
遠い遠い昔、世界は終わり、それから長い長い時間がたちました。生き残った人間たちは、ほそぼそと命をつなげ、今となっては、それなりに平和な世界ができました。すずさんは、そんな世界で働く、蒸気屋さんです。
絵本のように穏やかな、終わった世界の物語。

野良インコと元飼主~山で高校生活送ります~
浅葱
ライト文芸
小学生の頃、不注意で逃がしてしまったオカメインコと山の中の高校で再会した少年。
男子高校生たちと生き物たちのわちゃわちゃ青春物語、ここに開幕!
オカメインコはおとなしく臆病だと言われているのに、再会したピー太は目つきも鋭く凶暴になっていた。
学校側に乞われて男子校の治安維持部隊をしているピー太。
ピー太、お前はいったいこの学校で何をやってるわけ?
頭がよすぎるのとサバイバル生活ですっかり強くなったオカメインコと、
なかなか背が伸びなくてちっちゃいとからかわれる高校生男子が織りなす物語です。
周りもなかなか個性的ですが、主人公以外にはBLっぽい内容もありますのでご注意ください。(主人公はBLになりません)
ハッピーエンドです。R15は保険です。
表紙の写真は写真ACさんからお借りしました。

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。

夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です
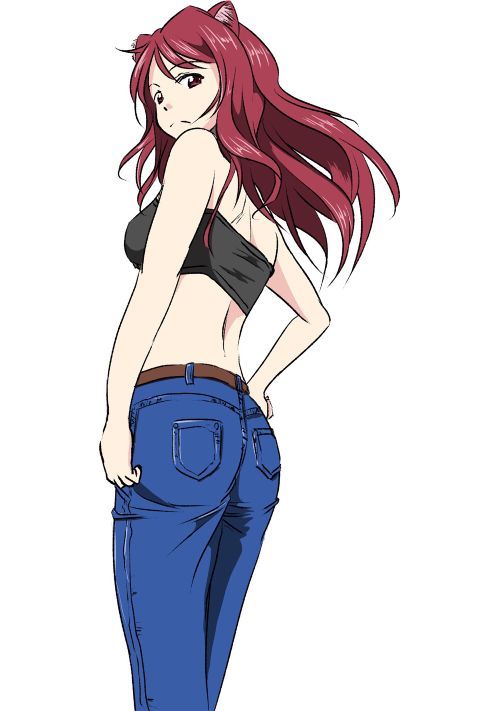
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















