18 / 39
第二章「江戸城の象」
第十話「天下人の貌」
しおりを挟む
曲者が観客に完全に紛れ込んでしまい困惑していた文蔵の耳に、万雷の拍手を掻き分けて一人の男の声が届いた。
「二列目十五番目の者、まだ拍手の場面では無い様だが、何故拍手をした? それに八列目三番目の者も、随分速やかに同調した様だが何か示し合わせでもあったのか?」
声の主は、八代将軍吉宗その人であった。
その声は落ち着いた様子で発されたもので、決して怒号ではない。だが、生半可な声をかき消すような拍手の中であっても、この場に居る全ての者の耳にはっきりと響いた。
指摘された者の周りがさっと開き、その姿が露わになる。今まで人込みで隠れていたのだが、何やら懐に手をやっている。怪しい事この上ない。
この光景を目の当たりにした文蔵は、将軍の力というものに恐れ入った。そして、何故家重が将軍に不適格だと評されているのかも理解した。
将軍の声は、それが例え静かに発された者であっても、言うなれば天下に轟くものでなければならない。そしてその声は天下に号令するものであるから、人々を動かす力が籠っていなければならないのだ。
これまでの将軍が全てこの様なものであったかは分からないが、当代将軍を知る者は、言語不明瞭な家重が将軍になる事を頼りなく思うであろう。これは、単なる権力争いや意地悪では無く、天下の安寧を思えばこそなのだ。
ともあれ、将軍の力により不逞の輩が明白になったのは好都合だ。文蔵は観客に紛れた侵入者に走り寄って行く。
「ええい、これまでだ。覚悟せい!」
人ごみに紛れ、隠密裏に事を運ぶことを計画していた侵入者は流石にそれは諦めた様だ。懐から手裏剣を数本取り出すと、一気にそれを投げつけた。
それはあまりにも素早く、文蔵といえども止める暇は無かった。速度といい、複数の手裏剣を同時に投擲する技量といい、生半な曲者ではない。
手裏剣が向かう先は八代将軍たる吉宗だ。
異常な事態に気付いていた文蔵や多羅尾も、この攻撃には間に合わず、とても間に割って入る事など出来ない。ましてや将軍の側に控える幕閣達は、攻撃に反応出来ていなかったので尚更だ。
隠し持っていた手裏剣であるためそれ程大きくはなく、殺傷力は低いはずだ。だが、辺りどころが悪ければ致命傷になり兼ねないし、毒が塗られていたならばかすり傷で死に至る。そして例えそうでなかったとしても、天下を統べる将軍が刺客から傷を負わされたと言う事自体が天下を揺るがす大事件だ。それも、仲には徳川家への反発を隠し持っているかもしれない大名達の前である。場合によっては戦国の世に逆戻りだ。
文蔵は御家人の子であるが、旅芸人に拾われて育ったため徳川に対する忠誠心はさほどない。だが、自分達の一座が日本各地を巡業できるのは、徳川の治世のおかげだという事は理解している。
その様な事を思った文蔵は、戦いの中ながら予想される未来に暗澹たる思いに包まれた。
だが、その直後予想もしなかった光景が文蔵の目の前に展開された。
吉宗は後ろに控えていた太刀持ちが持っていた宝刀に手を伸ばし、気合一閃襲い来る手裏剣を全て叩き落してしまった。抜刀の動作、手裏剣を捉えた太刀筋は文蔵の目にははっきりと見えず、残像しか映らなかった。
武芸好きとの噂は聞いていたが、予想を遥かに上回る腕前である。紀州藩の部屋住みであった頃ならいざ知らず、今は将軍としての政務で稽古の時間はあまりとれないはずだ。それにも関わらずこの技量、もしも徳川の血筋に生まれず市井の剣客として生きていたなら、柳生宗矩や宮本武蔵に並ぶ剣豪として名を馳せていたやも知れぬ。
「あ、あ……」
吉宗に手裏剣を放った刺客は、茫然自失立ち尽くした。当然だ、彼にとっては必殺の間合いだったし、殺せずともかすり傷を負わすだけで目的は果たす事が出来たはずだったのだ。もしも傷すら負わなかったとしても、無様に逃げたという評判が立っても天下に混乱が広まったのである。それがあの様に見事としか言いようのない対処をされてしまったのだ。逆に将軍の武家の棟梁としての名声は高まるであろう。
刺客の隙を見逃さず、すかさず文蔵は二人の刺客の頭を殴り飛ばす。正式な柔術の当身とは程遠い無骨な拳だが、喧嘩慣れしているだけあってその威力は十分だ。たちまち刺客達は白目をむいて倒れ伏した。
「服部! 他にもいるぞ!」
「なに?」
一息つく間も無く、多羅尾が警告の声を発した。文蔵が周りを見回すと、能舞台の上のシテが衣装の中から大型の苦無を取り出している。また、囃子方の何人かが楽器に仕込んでいた短刀を握っている。
「将軍は止めだ。狙うは、世子家重だ!」
「いかん、誰か止めろ!」
事態に気付いた文蔵は叫ぶが、それに反応する者はいない。家重に仕える田沼ら小姓は、将軍自らが臨席する事を憚ってそれ程数は多くない。また、田沼や大岡をはじめとする家重の部下は有能であるが、その本分は頭脳である。この点、武芸に長けた者を好んで身近に置く吉宗とは違う。田沼らはこの二転三転する修羅場に対応できず、主に危難が迫っているのに気付いていない。
家重が父吉宗の様に自ら刺客に対処できるとはとても思えず、良くて軽傷、悪ければ死すら有り得るだろう。
ただでさえ時期将軍の継承が揉めている所にその様な事があっては、確実に争いが激化して徳川家の安定した天下は揺らぐだろう。
今度こそ、惨劇が起きる事を文蔵は覚悟した。しかも、一方的に話しただけだが、多少は交流した相手に死が迫っている。
この事態を止められる人間は、誰もいないだろう。
そう、人間は……だ。
「な、何だこいつは!」
刺客と家重の間に割って入った者、それは人間では無く能舞台の横に待機していた象であった。象の巨体が割り込んだのだ。投擲された苦無は全て阻まれてしまった。しかも、象の皮膚は甲冑の様に硬い。苦無や短刀如きでは傷一つ負う事は無い。
「……!」
非現実的な光景に皆が唖然とする中、ただ一人家重は声にならない声を発した。そして、それに応える様に象はその長い鼻を差し伸べた。
「み、見ろ! 家重様が……」
「象の上に!」
家重は象の鼻の上を通り、その背に跨った。
象は家重の意思を反映する様にして刺客の方に向き直り、上に跨る家重は遥か高みから刺客どもを睥睨した。そして文蔵の方に指を向けた。
「……!」
「ははっ! 速やかにこ奴らを懲らしめ、この場を治めてご覧にいれます!」
家重は何も言わなかったが、文蔵には何が言いたいか理解出来た。
「皆! 協力してくれ!」
「はいよ!」
芸人という立場を弁えて、巳之吉一座は事態を見守っていたのだが、文蔵の声を契機に行動を開始する。
朱音は蛇を放って刺客の動きを封じ、巳之吉は馬に跨って刺客の一団に突っ込んで行く。
そして解き放たれた六尺の大イタチは刺客に襲い掛かる。イタチはその可愛らしい外見に反し、獰猛な性格とそれに見合った戦闘力を持った猛獣だ。日本に生息する小さなイタチやカワウソですら侮れぬ力を秘めている。それが人間と同じ大きさなのだ。とても短刀や苦無で対処できる相手ではない。たちまち無残な姿に変わっていく。大イタチは故郷では、鰐すら狩っていたのである。命があっただけでめっけものだ。
それでも刺客達は怯まずに、何とか少しでも戦果を上げようとして果敢に突っ込んで来るが、その行動は無駄に終わる。家重の前に文蔵が立ちはだかり、それ以上先に進もうとするのを防いだのだ。周囲にまだ観客の町人が居るので巻き添えを恐れて刀を抜く事は無いが、変幻自在の文蔵の蹴りは威力が十分だ。刺客達の足をへし折り、鳩尾を貫き、顎を叩き割った。
刺客達が制圧されたのは、あっという間の事であった。江戸城を警護する本来の侍たちは、将軍や幕閣の要人を守るのに精一杯で、戦ったのは文蔵達だけだ。刺客達を捕縛し終えた文蔵や巳之吉一座の一同は、家重の元に集まると、膝を着いて頭を垂れた。
家重は象に守られただけだし刺客を撃退したのは文蔵達だ。つまりは何もしていないと言える。だが、象に跨り町人達を睥睨し、指一つ動かす事無く敵を倒したその姿はまさに天下人の姿だ。また、いつもは生来の持病による痛みで引き攣った表情が、この時ばかりは穏やかになっている。象に跨るという非日常的な体験をしているためか、痛みが気になっていないのかもしれない。
そしてその顔立ちは、平素の家重からは考えられぬほど端正なものだった。痛みによる引き攣りが台無しにしていたのだが、これが本来の家重の顔なのだ。
日頃は家重の事を内心軽侮していた幕閣達も、本来の家重を目の当たりにして思わず平伏した。外見で判断してしまうのは本来推奨される事ではないが、その様な愚かさも人間の本質である。
威風堂々象に跨るその姿と、本来の端正な顔立ちを皆に晒した事、これらによってはじめて家重が将軍の後継者としての立場を確立したと言えるのかもしれない。
「服部よ、それに一座の者達よ、大儀であった。町人達に犠牲を出さずに場を治めた事、将軍として感謝するぞ」
家重は言葉を発せぬが、代わって将軍たる吉宗が労いの言葉をかけた。
まさか将軍直々に言葉をかけられると思っていなかった文蔵達は、驚きの表情で吉宗の方に向き直って頭を下げた。
文蔵は一応直参であるが、御家人で町方同心に過ぎない。将軍に声をかけられるなど本来あり得ない。また、巳之吉や朱音は芸人である。社会の最下層と言っても良い立場なのだ。
将軍家に対する忠義など持ち合わせていなかった文蔵達であるが、この時ばかりは晴れがましい気持ちが胸を満たしていた。
この日の町入能の出来事は、退城した名主衆の口から江戸中に広まった。
病弱で暗愚と噂されていた家重が天下人の器であった事もであるし、文蔵達の活躍もである。これによって文蔵の所属する北町奉行所の評判も上がり、文蔵を採用する事を思いついた稲生はほくほく顔だ。元勘定奉行らしく諸事に細かい稲生であったが、この時ばかりは機嫌良く大らかであった。
だが、良い事も有れば悪い事もある。
広まった噂には尾ひれがついて、文蔵が動物を操って刺客を撃退した事になっていた。
おかげで市中見廻りの時にあれが忍者同心の服部文蔵よとひそひそ話されてしまい、気恥ずかしい思いをしている。先輩の粟口には何かと叱責される事が増えてしまった。それに、これまでも文蔵の事を忍者の何たるかを心得ぬ者だと怒りを抱いていた伊賀や甲賀の本物の忍者達が、更に敵視して来ることになったのだ。
しばらくの間彼らと市中で遭遇するたび、舌打ちや嫌味を浴びせかけられて気まずい思いをしたのであった。
「二列目十五番目の者、まだ拍手の場面では無い様だが、何故拍手をした? それに八列目三番目の者も、随分速やかに同調した様だが何か示し合わせでもあったのか?」
声の主は、八代将軍吉宗その人であった。
その声は落ち着いた様子で発されたもので、決して怒号ではない。だが、生半可な声をかき消すような拍手の中であっても、この場に居る全ての者の耳にはっきりと響いた。
指摘された者の周りがさっと開き、その姿が露わになる。今まで人込みで隠れていたのだが、何やら懐に手をやっている。怪しい事この上ない。
この光景を目の当たりにした文蔵は、将軍の力というものに恐れ入った。そして、何故家重が将軍に不適格だと評されているのかも理解した。
将軍の声は、それが例え静かに発された者であっても、言うなれば天下に轟くものでなければならない。そしてその声は天下に号令するものであるから、人々を動かす力が籠っていなければならないのだ。
これまでの将軍が全てこの様なものであったかは分からないが、当代将軍を知る者は、言語不明瞭な家重が将軍になる事を頼りなく思うであろう。これは、単なる権力争いや意地悪では無く、天下の安寧を思えばこそなのだ。
ともあれ、将軍の力により不逞の輩が明白になったのは好都合だ。文蔵は観客に紛れた侵入者に走り寄って行く。
「ええい、これまでだ。覚悟せい!」
人ごみに紛れ、隠密裏に事を運ぶことを計画していた侵入者は流石にそれは諦めた様だ。懐から手裏剣を数本取り出すと、一気にそれを投げつけた。
それはあまりにも素早く、文蔵といえども止める暇は無かった。速度といい、複数の手裏剣を同時に投擲する技量といい、生半な曲者ではない。
手裏剣が向かう先は八代将軍たる吉宗だ。
異常な事態に気付いていた文蔵や多羅尾も、この攻撃には間に合わず、とても間に割って入る事など出来ない。ましてや将軍の側に控える幕閣達は、攻撃に反応出来ていなかったので尚更だ。
隠し持っていた手裏剣であるためそれ程大きくはなく、殺傷力は低いはずだ。だが、辺りどころが悪ければ致命傷になり兼ねないし、毒が塗られていたならばかすり傷で死に至る。そして例えそうでなかったとしても、天下を統べる将軍が刺客から傷を負わされたと言う事自体が天下を揺るがす大事件だ。それも、仲には徳川家への反発を隠し持っているかもしれない大名達の前である。場合によっては戦国の世に逆戻りだ。
文蔵は御家人の子であるが、旅芸人に拾われて育ったため徳川に対する忠誠心はさほどない。だが、自分達の一座が日本各地を巡業できるのは、徳川の治世のおかげだという事は理解している。
その様な事を思った文蔵は、戦いの中ながら予想される未来に暗澹たる思いに包まれた。
だが、その直後予想もしなかった光景が文蔵の目の前に展開された。
吉宗は後ろに控えていた太刀持ちが持っていた宝刀に手を伸ばし、気合一閃襲い来る手裏剣を全て叩き落してしまった。抜刀の動作、手裏剣を捉えた太刀筋は文蔵の目にははっきりと見えず、残像しか映らなかった。
武芸好きとの噂は聞いていたが、予想を遥かに上回る腕前である。紀州藩の部屋住みであった頃ならいざ知らず、今は将軍としての政務で稽古の時間はあまりとれないはずだ。それにも関わらずこの技量、もしも徳川の血筋に生まれず市井の剣客として生きていたなら、柳生宗矩や宮本武蔵に並ぶ剣豪として名を馳せていたやも知れぬ。
「あ、あ……」
吉宗に手裏剣を放った刺客は、茫然自失立ち尽くした。当然だ、彼にとっては必殺の間合いだったし、殺せずともかすり傷を負わすだけで目的は果たす事が出来たはずだったのだ。もしも傷すら負わなかったとしても、無様に逃げたという評判が立っても天下に混乱が広まったのである。それがあの様に見事としか言いようのない対処をされてしまったのだ。逆に将軍の武家の棟梁としての名声は高まるであろう。
刺客の隙を見逃さず、すかさず文蔵は二人の刺客の頭を殴り飛ばす。正式な柔術の当身とは程遠い無骨な拳だが、喧嘩慣れしているだけあってその威力は十分だ。たちまち刺客達は白目をむいて倒れ伏した。
「服部! 他にもいるぞ!」
「なに?」
一息つく間も無く、多羅尾が警告の声を発した。文蔵が周りを見回すと、能舞台の上のシテが衣装の中から大型の苦無を取り出している。また、囃子方の何人かが楽器に仕込んでいた短刀を握っている。
「将軍は止めだ。狙うは、世子家重だ!」
「いかん、誰か止めろ!」
事態に気付いた文蔵は叫ぶが、それに反応する者はいない。家重に仕える田沼ら小姓は、将軍自らが臨席する事を憚ってそれ程数は多くない。また、田沼や大岡をはじめとする家重の部下は有能であるが、その本分は頭脳である。この点、武芸に長けた者を好んで身近に置く吉宗とは違う。田沼らはこの二転三転する修羅場に対応できず、主に危難が迫っているのに気付いていない。
家重が父吉宗の様に自ら刺客に対処できるとはとても思えず、良くて軽傷、悪ければ死すら有り得るだろう。
ただでさえ時期将軍の継承が揉めている所にその様な事があっては、確実に争いが激化して徳川家の安定した天下は揺らぐだろう。
今度こそ、惨劇が起きる事を文蔵は覚悟した。しかも、一方的に話しただけだが、多少は交流した相手に死が迫っている。
この事態を止められる人間は、誰もいないだろう。
そう、人間は……だ。
「な、何だこいつは!」
刺客と家重の間に割って入った者、それは人間では無く能舞台の横に待機していた象であった。象の巨体が割り込んだのだ。投擲された苦無は全て阻まれてしまった。しかも、象の皮膚は甲冑の様に硬い。苦無や短刀如きでは傷一つ負う事は無い。
「……!」
非現実的な光景に皆が唖然とする中、ただ一人家重は声にならない声を発した。そして、それに応える様に象はその長い鼻を差し伸べた。
「み、見ろ! 家重様が……」
「象の上に!」
家重は象の鼻の上を通り、その背に跨った。
象は家重の意思を反映する様にして刺客の方に向き直り、上に跨る家重は遥か高みから刺客どもを睥睨した。そして文蔵の方に指を向けた。
「……!」
「ははっ! 速やかにこ奴らを懲らしめ、この場を治めてご覧にいれます!」
家重は何も言わなかったが、文蔵には何が言いたいか理解出来た。
「皆! 協力してくれ!」
「はいよ!」
芸人という立場を弁えて、巳之吉一座は事態を見守っていたのだが、文蔵の声を契機に行動を開始する。
朱音は蛇を放って刺客の動きを封じ、巳之吉は馬に跨って刺客の一団に突っ込んで行く。
そして解き放たれた六尺の大イタチは刺客に襲い掛かる。イタチはその可愛らしい外見に反し、獰猛な性格とそれに見合った戦闘力を持った猛獣だ。日本に生息する小さなイタチやカワウソですら侮れぬ力を秘めている。それが人間と同じ大きさなのだ。とても短刀や苦無で対処できる相手ではない。たちまち無残な姿に変わっていく。大イタチは故郷では、鰐すら狩っていたのである。命があっただけでめっけものだ。
それでも刺客達は怯まずに、何とか少しでも戦果を上げようとして果敢に突っ込んで来るが、その行動は無駄に終わる。家重の前に文蔵が立ちはだかり、それ以上先に進もうとするのを防いだのだ。周囲にまだ観客の町人が居るので巻き添えを恐れて刀を抜く事は無いが、変幻自在の文蔵の蹴りは威力が十分だ。刺客達の足をへし折り、鳩尾を貫き、顎を叩き割った。
刺客達が制圧されたのは、あっという間の事であった。江戸城を警護する本来の侍たちは、将軍や幕閣の要人を守るのに精一杯で、戦ったのは文蔵達だけだ。刺客達を捕縛し終えた文蔵や巳之吉一座の一同は、家重の元に集まると、膝を着いて頭を垂れた。
家重は象に守られただけだし刺客を撃退したのは文蔵達だ。つまりは何もしていないと言える。だが、象に跨り町人達を睥睨し、指一つ動かす事無く敵を倒したその姿はまさに天下人の姿だ。また、いつもは生来の持病による痛みで引き攣った表情が、この時ばかりは穏やかになっている。象に跨るという非日常的な体験をしているためか、痛みが気になっていないのかもしれない。
そしてその顔立ちは、平素の家重からは考えられぬほど端正なものだった。痛みによる引き攣りが台無しにしていたのだが、これが本来の家重の顔なのだ。
日頃は家重の事を内心軽侮していた幕閣達も、本来の家重を目の当たりにして思わず平伏した。外見で判断してしまうのは本来推奨される事ではないが、その様な愚かさも人間の本質である。
威風堂々象に跨るその姿と、本来の端正な顔立ちを皆に晒した事、これらによってはじめて家重が将軍の後継者としての立場を確立したと言えるのかもしれない。
「服部よ、それに一座の者達よ、大儀であった。町人達に犠牲を出さずに場を治めた事、将軍として感謝するぞ」
家重は言葉を発せぬが、代わって将軍たる吉宗が労いの言葉をかけた。
まさか将軍直々に言葉をかけられると思っていなかった文蔵達は、驚きの表情で吉宗の方に向き直って頭を下げた。
文蔵は一応直参であるが、御家人で町方同心に過ぎない。将軍に声をかけられるなど本来あり得ない。また、巳之吉や朱音は芸人である。社会の最下層と言っても良い立場なのだ。
将軍家に対する忠義など持ち合わせていなかった文蔵達であるが、この時ばかりは晴れがましい気持ちが胸を満たしていた。
この日の町入能の出来事は、退城した名主衆の口から江戸中に広まった。
病弱で暗愚と噂されていた家重が天下人の器であった事もであるし、文蔵達の活躍もである。これによって文蔵の所属する北町奉行所の評判も上がり、文蔵を採用する事を思いついた稲生はほくほく顔だ。元勘定奉行らしく諸事に細かい稲生であったが、この時ばかりは機嫌良く大らかであった。
だが、良い事も有れば悪い事もある。
広まった噂には尾ひれがついて、文蔵が動物を操って刺客を撃退した事になっていた。
おかげで市中見廻りの時にあれが忍者同心の服部文蔵よとひそひそ話されてしまい、気恥ずかしい思いをしている。先輩の粟口には何かと叱責される事が増えてしまった。それに、これまでも文蔵の事を忍者の何たるかを心得ぬ者だと怒りを抱いていた伊賀や甲賀の本物の忍者達が、更に敵視して来ることになったのだ。
しばらくの間彼らと市中で遭遇するたび、舌打ちや嫌味を浴びせかけられて気まずい思いをしたのであった。
24
お気に入りに追加
24
あなたにおすすめの小説

夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~
恩地玖
歴史・時代
位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。
一体、これまで成してきたことは何だったのか。
医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

仕合せ屋捕物控
綿涙粉緒
歴史・時代
「蕎麦しかできやせんが、よございますか?」
お江戸永代橋の袂。
草木も眠り、屋の棟も三寸下がろうかという刻限に夜な夜な店を出す屋台の蕎麦屋が一つ。
「仕合せ屋」なんぞという、どうにも優しい名の付いたその蕎麦屋には一人の親父と看板娘が働いていた。
ある寒い夜の事。
そばの香りに誘われて、ふらりと訪れた侍が一人。
お江戸の冷たい夜気とともに厄介ごとを持ち込んできた。
冷たい風の吹き荒れるその厄介ごとに蕎麦屋の親子とその侍で立ち向かう。

葉桜よ、もう一度 【完結】
五月雨輝
歴史・時代
【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。
謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

【完結】絵師の嫁取り
かずえ
歴史・時代
長屋シリーズ二作目。
第八回歴史・時代小説大賞で奨励賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
小鉢料理の店の看板娘、おふくは、背は低めで少しふくふくとした体格の十六歳。元気で明るい人気者。
ある日、昼も夜もご飯を食べに来ていた常連の客が、三日も姿を見せないことを心配して住んでいると聞いた長屋に様子を見に行ってみれば……?

三賢人の日本史
高鉢 健太
歴史・時代
とある世界線の日本の歴史。
その日本は首都は京都、政庁は江戸。幕末を迎えた日本は幕府が勝利し、中央集権化に成功する。薩摩?長州?負け組ですね。
なぜそうなったのだろうか。
※小説家になろうで掲載した作品です。
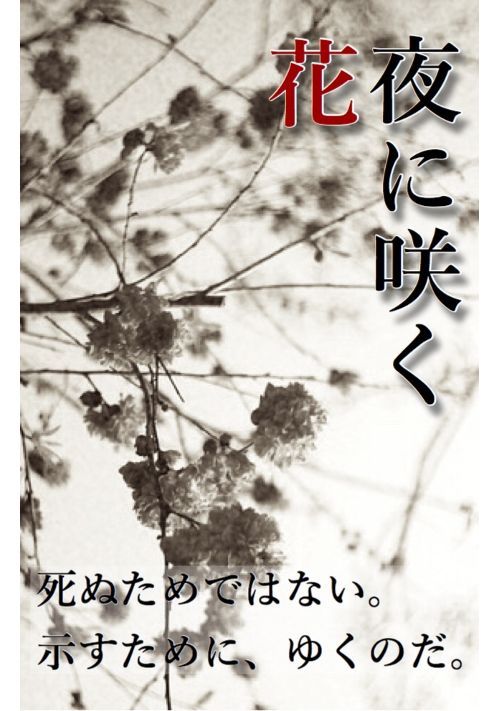
夜に咲く花
増黒 豊
歴史・時代
2017年に書いたものの改稿版を掲載します。
幕末を駆け抜けた新撰組。
その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。
よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















