12 / 21
11
しおりを挟む
陸上競技、日本選手権は六月最後の週末、三日間に開かれた。
百メートルは、一日目が予選、一回戦と二回戦、二日目が準決勝、そして三日目に決勝が予定されていた。
決勝レースは、夜のゴールデンタイムに生放送されることになっていた。
例年なら、午後五時頃には全ての競技は終わっていたのだが、今年は、テレビ局の都合が優先され、注目を集めている競技は、全て、夜の八時台に決勝が割り当てられていた。
スポーツは視聴率のとれるイベントだった。
勝者と敗者が分かりやすく、必死で闘う姿は、人々の感動を呼ぶ。思いがけぬアクシデントや、番狂わせ、筋書きのないドラマという言葉があるが、確かに、スポーツは安直なドラマよりもはるかに面白い番組だった。
今年は更にオリンピックイヤーだった。いやでも、国民の関心はスポーツに向けられる。 サッカーやバレーボールは、オリンピックの出場権を得るための予選からメディアは追いかけていた。
柔道、レスリング、水泳、出場選手を決める選考会は、いずれもテレビで放映されていた。
様々な競技で、オリンピック出場選手が決まっていった。最後に残ったのが陸上競技の選考会だった。メダルの可能性が低いとは言え、陸上競技はオリンピックの花形競技だ。注目度は高い。それに、今回は、マラソンや投擲競技で正真正銘、メダル候補がいた。
そして、百メートルだ。百メートルは、決勝に残るかさえ夢のような目標だったのだが、今回は沢田がアジア記録を、さらに大森が、非公式ながら、その記録を上回る好記録をだしている。
「オリンピックの決勝に二人残れば、日本陸上競技史上初めてのことです」
「二人で競い合えば、表彰台も夢ではありません」
マスコミは二人をオリンピックのメダル候補に持ち上げていた。
日本選手権の前日、大森は、軽い練習だけでグラウンドを上がった。
「リラックスして行こう」と高尾が声をかけると、「はい」と大森は力強く返事をした。
大森は、練習でもう一度、日本記録を切っていた。記録は九秒八三。伸びはまだ続いていた。あの夢を見た日に感じた足の違和感は消え、ドーピングの不安も無くなっていた。
「君ならだいじょうぶだから」
高尾は、大森の肩に手を置いて言った。
今の大森の力なら、故障や事故といったアクシデントさえなければ、八割の力で走っても、オリンピック出場は問題なかった。オリンピックの参加標準記録を突破しているのは、沢田と大森と須藤の三人だけなのだ。
沢田は、昨日、テレビでインタビューを受けていた。
「まあ、見ててよ。日本なんか通過点だから。日本選手権はウオーミングアップ。本番はオリンピックだから、俺が世界のスターになるのはさ」
どこかのラップミュージシャンのように、リズムをとって踊るようにしゃべっていた。沢田はいつもの沢田だ。どうやら、好調らしい。
須藤は春に痛めた左太股の肉離れが長引いて、満足な状態ではないようだ。噂では出場さえ迷っているらしい。
須藤の次ぎに記録が良いのは、中部大学職員の朝永だが、三十二歳という年齢を考えれば、急に記録が上がるとは考えられない。他の選手は、まだ0.2秒以上、標準記録から差がある。日本選手権の当日に、急に、残りの選手の記録が伸び、三人も四人も標準記録が突破できるとは考えられない。
無難に決勝に残り、確実に走り、四着以内に入れば百メートルとリレーの選手に決まる。オリンピック選手の誕生だ。
しかし、なにしろ百メートルだ。十秒あまりの戦いの中で、ほんのわずかな狂いが、全てを台無しにしてしまう。
体調を崩したらどうだ。当日、熱を出したら、下痢になったら、そんな例はいやほど見ている。
高熱を出し、朦朧となりながら、四百メートルを走り、準決勝で病院に運ばれた選手がいた。
レースの直前、トイレに駆け込み、便器に腰掛けながらピストルの音を聞いた選手もいる。笑い話ではない。大事な試合や試験の前に、決まって体調を崩す人間がいる、それが、大森でないとどうして言えるだろう。
予選のスタートでつまずいたら、靴が脱げたら、フライングをして失格になったら。オリンピックの決勝でさえ、フライングで失格になった選手がいた。
天気はどうだ。当日は晴れか、雨か。今は梅雨だ。雨の確率は高い。雨粒が目に入り、体のバランスを崩すことはないのか。トラックに水がたまり、足を滑らすことはないのか。
考えだすと、キリがなかった。悪い考えが次々に浮かんできては消え、また浮かんでくる。
平然とした態度をとってはいたが、高尾は、この一週間、眠りが浅く、夜中に何度も目を覚ましていた。
八年前の日本選手権。四百メートル決勝、ゴールテープの五メートル前で倒れた鈴木の姿が何度も夢に現れ、そのたびにうなされて、ベッドの上で起きあがり、薄ぼんやりとした、気の抜けたような暗さの、都会の闇の中で、冷や汗をかきながら目を見開いていた。
「楽にいこう。大森君。楽に。君なら大丈夫だから」
高尾は自分に言い聞かせるように、ゆっくりと言った。
明和大学のグラウンドに、日本人で初めて十秒の壁を破った沢田武志の姿はなかった。
「先生、隠さないでくださいよ」
沢田の取材に訪れた記者達は、当てが外れ、コーチの石嶺に文句を言っていた。
「沢田選手は、どちらですか。一言だけでもコメントをいただけませんか」
「試合は明日だから、沢田は、軽い練習だけで、今日は上がりました」
石嶺は、記者に囲まれ、何度も同じ言葉を繰り返していた。
「教えてくださいよ。子どもの使いじゃないんだから、何もなしじゃ、帰れませんよ」
「今日は、静かにしていたいという、本人の希望ですので、ご了承下さい。明日の予選の後には、コメントできると思いますから」
「先生、頼みますよ。一言だけでも」
「すいません。本当に今日は……」
「写真を一枚」
「すみません」
石嶺は記者の輪の中で髪の毛が薄くなった頭を下げ続けていた。
実は、沢田が今どこにいるのか、石嶺も知らなかった。昨日はグラウンドでいつものように練習したのだが、今日は、何の連絡もなく休んでいた。
「仕方ないな……」
記者たちは、舌打ちをし、沢田のコメントをあきらめて、一人一人、帰っていった。
記者の輪から解放され、
「ふー」と石嶺は息を吐いた。
「まったく、あいつは……」
どうせ、また女だろう。と、石嶺は思った。スポーツカーの助手席にアイドル歌手を乗せて試合に来るような男だ。
明日が日本選手権と言っても、緊張など無縁なのだろう。
「たいしたもんだよ」
自分は何日も前から、胃が痛く、食欲もないというのに、当の本人は練習をすっぽかし、女と遊んでいるらしい。
もし、自分に沢田の半分程のずうずうしさがあれば、オリンピックにも行けたかもしれない、と、石嶺は一瞬思った。大事な試合になればなるほど、緊張して足が動かなくなった。自己記録は、観客が誰もいないような小さな大会で出したものだ。
いや、違う、と石嶺はすぐに思い直した。自分のような平凡な男が、勘違いして思い上がったら、苦しい練習などしなかったに違いない。遊びを覚え、練習をさぼり、不摂生をし、記録はおろか、途中で陸上競技を止めていただろう。
自分の記録は、平凡な男が精一杯努力した結果だ。そして今、ここで好きな陸上のコーチをしていられるのも、努力した結果なのだ。
「ん? 雨か……」
石嶺の頬に雨粒が当たった。見上げると、空は、いつのまにか厚い雨雲で覆われていた。六月の末だった。梅雨明け宣言は、まだされていない。
ポツリ、ポツリと、大粒の雨がグラウンドに落ちだし、小さな土煙を立てて、黒い跡を残していった。
稲妻が光り、雷が鳴ると、大量の雨が地面に降り注いできた。
「ひどいなこれは」
叩きつける雨が水煙を上げ、夕方のような暗さに変わっていた。石嶺は、何の役にも立たないのに、手のひらを頭の上にかざしながら、走り出した。
石嶺の予想は半分当たっていた。
その日、沢田は、美里奈美という自称アイドルの子を車の助手席に乗せ、横浜に向かっていた。
横浜に特に目的はなかった。首都高に乗り、車を走らせているうちに、横浜に来てしまっただけだった。
沢田は、高速道路を下り、東京湾が一望できるホテルに車を入れ、最上階の部屋をとった。
石嶺が記者達に頭を下げているとき、沢田は、ベッドで他の運動に励んでいた。
ことが終わると、沢田は、すぐにイビキをかいて眠ってしまった。
「変な人」
奈美はあきれたように沢田の顔を見た。
今日は、朝の十時に急に沢田に呼び出され、車に乗せられ、ホテルに着き、沢田とセックスをした。
沢田はいつも、部屋に入ると、すぐに裸になり、「ウホウホ」とゴリラのマネをしながら、迫ってくる。
バカみたいだ。でも、嫌いじゃない。単純で明るいし、お金もある。それに、何を言っても沢田は有名人だ。
二ヶ月前、週刊誌に沢田と一緒にホテルに入る写真が載った。何だか自分が有名人になったみたいで良い気分だった。
奈美は、沢田の顔を手の平で軽く叩いてみた。沢田は、「うーん」と言って、その手を払ったが、目は開けなかった。
「ふわー」奈美は欠伸をした。朝の十時は、奈美にしては早い起床だった。奈美は沢田の隣で横になると、目を閉じて眠ってしまった。
一時間程して、奈美は目を覚ました。ベッドの横の時計を見ると、時間は二時を回っていた。
ベッドに沢田はいなかった。奈美は眠そうに欠伸をしながら、部屋の中を見回した。
窓際にシルエットが見えた。沢田だった。沢田は、何も着けず、裸のまま、立って海を見ていた。
「ねえぇ、何か食べに行こうよ」
奈美が鼻にかかった声で、けだるそうに言った。
「奈美、お腹空いちゃった」
舌足らずの声で言う。人気のあるアイドルのマネだった。
「……違うんだよな」
沢田が外を向いたままで呟いた。
「えっ?。なにぃ?」
「違うんだよ」
沢田は独り言を繰り返した。
「ねえ、何のこと?」
奈美が言うと、沢田は振り返り、
「おまえさ、もう、帰っていいよ」と言った。
「えっ、何?」
「帰っていいから」
「なによ。それ、ねえ。ここから、一人で帰れって言うの」
奈美が驚いて言うと、
「ああ、帰れるだろ」と沢田はあっさり言いった。
「ちょっと」
沢田は、また、海に向かい、
「……違うんだよな」と呟いた。
「もう」
やっぱり沢田は変わっている。沢田は、時々、自分だけの世界に入ってしまう。はしゃいでいたかと思うと、急に真剣な顔になる。こうなると、もう、周りのことには関心が無くなってしまう。
仕方がない、これが沢田武志だ、怒ってみても始まらない。何か急に思いつき、一人になって考えたいのだろう。明日になれば、また、電話をかけてくるに違いない。
「じゃあ、私、もう帰るから」
奈美は服を着た。
「ああ」沢田は振り返らずに答えた。
「またね」奈美は部屋を出た。
「ああ」沢田は右手を上げて答えた。
奈美がホテルを出ようとすると、外はどしゃ降りだった。
奈美はロビーに戻り、携帯電話を取り出し、
「ねえ、私、奈美。今、横浜なんだけど、急に会いたくなっちゃって」
と、迎えに来そうな男を選んで電話をかけた。
「久米ちゃん。うまいでしょ。ウチのトンカツ定食」
「ええ、まあ」
定食屋「さわだ」の店内はスポーツ新聞の記者達で結構繁盛していた。
「ちゃんとうちの名前も入れてよ。沢田選手は「さわだ」のトンカツ定食を食べて足が速くなりましたって」
日報スポーツの久米は苦笑しながら、トンカツを口に運んだ。
子が子なら、親も親だ。インタビューに来ると、話の前に、必ずトンカツ定食を注文させられる。
先月から、トンカツ定食は、ちゃっかり、二百円値上がりしていた。頼んでないのに、納豆と豆腐が追加が付き、しめて千五百円だ。
(経費で落ちるかな)
久米は衣の厚いトンカツを食べながら思った。
「お客さん、生卵はサービスだよ」
沢田似の母親ははりきっている。いや、沢田が母親に似ているというべきか、ともかく、沢田の実家は、東京の下町にある小さな定食屋だった。
昔ながらの八百屋や肉屋の並ぶ商店街には、アーケードに「祝 日本新記録 沢田選手」の横断幕が掲げられていた。オリンピック出場が決まれば、横断幕は「祝オリンピック出場 沢田選手」に掛け替えられる手はずが整っていた。
「……違うんだよな」
沢田の前には、雨に煙る東京湾の景色が広がっていたが、沢田の目には何も写っていなかった。
人から見れば、沢田は変人で天才だった。天才の定義はいろいろあるだろうが、日本人で初めて九秒九を切ったことを考えれば、彼を天才と言っても問題はないだろう。
横柄な口のききかたをし、派手な衣装を着て、両耳にピアスを付け、ダイヤの指輪をし、助手席にアイドル歌手を乗せて、スポーツカーで競技場に乗り付けてくる。
レースでは、アメリカの黒人選手のように、サングラスをかけ、金のネックレスをして走る。
大言壮語。沢田は、記録を作る二年も前から、「世界で勝つ」と、マスコミに言い続けてきた。
「おれはさ。天才だから、てっぺんに立つ男だから」
「日本なんて、考えてないから、おれは、世界のスターだから」
画家のダリのように、奇矯な行動をすることで、マスコミの過剰な関心に耐え、自分の脆い心の奥を隠す人間がいる。しかし、沢田は別に計算して、そのような態度をとっているわけではなかった。
全て、その時、その時、思ったままに行動し、しゃべってきただけだった。
「……違うんだよな」
沢田は何度も同じ言葉を繰り返していた。
明日から日本選手権が始まる。試合を明日に控えているというのに、気持ちが高ぶってこなかった。
試合前日には、いつも興奮して落ち着かなかった。不安ではない。ただ、ただ楽しいのだ。足の速い小学生が運動会を楽しみにするのと同じように、沢田は試合が楽しみでたまらなかった。
勝者は自分だ。両手を挙げてゴールラインを走りさるのは自分だ。フラッシュがたかれ、マイクが差し出され、周りの人間は羨望のまなざしで自分を見ている。快感だ。例えようも無いほどの快感だ。それなのに……今回は少し、違う。
沢田本人は自覚していなかったが、アジア記録を作って、マスコミに騒がれた後、ある種の達成感を感じ、記録や戦いへの飢餓感が薄れていた。闘争心が涌いてこない。記録を出して周りを驚かせてやるといった気持ちになれない。
しかし、沢田は確かに天才だった。自分に何が必要か本能が理解していた。
沢田は、立ったまま目をつぶった。
「位置について」
スターターの声を頭の中で呼び起こす。
弛緩した神経をもう一度研ぎ澄まなくてはだめだ。闘争本能をたたき起こすのだ。
「よーい」
頭の中で、沢田は腰を浮かした。スターターのピストルの音に神経を集中する。
「パン」
音が鳴った。かすかに硝煙の臭いを感じる。
スタート。
飛び出す。
腕を高く振る。体はまだ上げるな。
前を見る。頬に風を感じる。風景が左右に流れていく。
五十メートル。六十メートル。体の力を抜け、リラックスしろ。
ゴールラインが見える。体を前傾する。胸がラインを越えた。
ゴール。
よし、勝った。
沢田は息を吐く。
もう一度。
「位置について……」
同じことの繰り返しだ。
沢田は、何度も何度も、スタートからフィニッシュまでの九秒八八を正確に頭の中で繰り返していた。
イメージトレーニング。一流のアスリートは、イメージしただけで、筋肉が反応する。 部屋は冷房が効き過ぎるほど効き、冷えきっていた。しかし、動いてもいないのに、沢田の体は汗ばみ、白く湯気が立ち上っていくのが見えた。
東京に戻ってから、容子は大森とは会っていなかった。大森から二、三回連絡があったのだが、容子は用事があるからとウソをついて断っていた。
しばらくして、大森からアパートを替わるからと携帯電話に伝言が入っていたが、それ以来連絡はなかった。
急に道が分かれてしまった。大森の心は自分から離れてしまった。同じ道を歩いていると思っていたのに、相手は全く違う道を進んでいた。
いつからだろう。何が悪かったのだろう。
考えても分からなかった。いや、考えても仕方のないことだった。
自分が悪かったのなら謝ればいい。何か行き違いがあったのなら、話し会えば解決できるのかもしれない。
しかし、変わってしまったものは、もう元には戻せない。大森の目は自分を見ていないし、二人の将来を考えてもいないのだ。自分が何を言っても、元に戻ることはないだろう。
卒業すれば、遠くに離れる、前はそのことが不安だったが、今は救いだった。
就職試験を受けるために地元に帰った間、思いの外、寂しくなかった。大森との恋が終わったと考えても、胸をかきむしるような寂しさはなかった。
もういい。そんな感じだった。
あまりに彼は変わってしまった。木訥で素直で正直な彼はどこかへ行ってしまった。
初めて手が触れたときのあわてた表情や体を重ねた時の心臓の鼓動は今も鮮明に残っている。しかし、それもいつか、写真が色あせるように、記憶も淡く消えていき、秋風を頬に感じたときに、ふっと浮かんでくるだけの小さな思い出に変わってしまうのだろう。
携帯電話が鳴った。心臓の鼓動が速くなった。大森? 分けがない。でも……もしかして。
携帯電話を耳に当てる。
「はい、青井です」
「容子? ねえ、ちょっと出てこない? 今ね、友恵と千佳と飲んでるのよ」
電話は大学の同級生の由香からだった。
「ええ? 今から?」
「おいでよ。容子」
電話は友恵に代わっていた。
「そうね……」
友恵は飲み屋の名前を言った。知っている店だった。アパートからは歩いて十分ほどの場所にあった。
「ほら、容子。私の慰め会なんだから」
後ろで、「また振られたんだよ」と、千佳が言っていた。だいぶ出来上がっている。
容子は、「わかった、わかった」と、言って、電話を切り、立ち上がった。
夜。雨は止んだ。今年の梅雨は熱帯地方のスコールのように、短時間激しく降って、すぐに止んでしまう。
大森はマンションのベランダに出て、下を見下ろしていた。
雨で都会のチリが洗い流され、空気が澄んでいた。車のライトが赤やオレンジの星になって流れていく。目をかなたにやると、都心のビルの明かりが見えた。
明日、日本選手権が始まると言うのに、大森に不安はなかった。高ぶりも感じていなかった。高尾は、大森がオリンピックの代表に選ばれるかどうか心配していたが、大森本人は、日本選手権など、ただの通過点だという思いだった。
大森は深呼吸をして胸を張った。そして、雲の切れ間から顔を出した月に向かって、拳を突き上げた。
百メートルは、一日目が予選、一回戦と二回戦、二日目が準決勝、そして三日目に決勝が予定されていた。
決勝レースは、夜のゴールデンタイムに生放送されることになっていた。
例年なら、午後五時頃には全ての競技は終わっていたのだが、今年は、テレビ局の都合が優先され、注目を集めている競技は、全て、夜の八時台に決勝が割り当てられていた。
スポーツは視聴率のとれるイベントだった。
勝者と敗者が分かりやすく、必死で闘う姿は、人々の感動を呼ぶ。思いがけぬアクシデントや、番狂わせ、筋書きのないドラマという言葉があるが、確かに、スポーツは安直なドラマよりもはるかに面白い番組だった。
今年は更にオリンピックイヤーだった。いやでも、国民の関心はスポーツに向けられる。 サッカーやバレーボールは、オリンピックの出場権を得るための予選からメディアは追いかけていた。
柔道、レスリング、水泳、出場選手を決める選考会は、いずれもテレビで放映されていた。
様々な競技で、オリンピック出場選手が決まっていった。最後に残ったのが陸上競技の選考会だった。メダルの可能性が低いとは言え、陸上競技はオリンピックの花形競技だ。注目度は高い。それに、今回は、マラソンや投擲競技で正真正銘、メダル候補がいた。
そして、百メートルだ。百メートルは、決勝に残るかさえ夢のような目標だったのだが、今回は沢田がアジア記録を、さらに大森が、非公式ながら、その記録を上回る好記録をだしている。
「オリンピックの決勝に二人残れば、日本陸上競技史上初めてのことです」
「二人で競い合えば、表彰台も夢ではありません」
マスコミは二人をオリンピックのメダル候補に持ち上げていた。
日本選手権の前日、大森は、軽い練習だけでグラウンドを上がった。
「リラックスして行こう」と高尾が声をかけると、「はい」と大森は力強く返事をした。
大森は、練習でもう一度、日本記録を切っていた。記録は九秒八三。伸びはまだ続いていた。あの夢を見た日に感じた足の違和感は消え、ドーピングの不安も無くなっていた。
「君ならだいじょうぶだから」
高尾は、大森の肩に手を置いて言った。
今の大森の力なら、故障や事故といったアクシデントさえなければ、八割の力で走っても、オリンピック出場は問題なかった。オリンピックの参加標準記録を突破しているのは、沢田と大森と須藤の三人だけなのだ。
沢田は、昨日、テレビでインタビューを受けていた。
「まあ、見ててよ。日本なんか通過点だから。日本選手権はウオーミングアップ。本番はオリンピックだから、俺が世界のスターになるのはさ」
どこかのラップミュージシャンのように、リズムをとって踊るようにしゃべっていた。沢田はいつもの沢田だ。どうやら、好調らしい。
須藤は春に痛めた左太股の肉離れが長引いて、満足な状態ではないようだ。噂では出場さえ迷っているらしい。
須藤の次ぎに記録が良いのは、中部大学職員の朝永だが、三十二歳という年齢を考えれば、急に記録が上がるとは考えられない。他の選手は、まだ0.2秒以上、標準記録から差がある。日本選手権の当日に、急に、残りの選手の記録が伸び、三人も四人も標準記録が突破できるとは考えられない。
無難に決勝に残り、確実に走り、四着以内に入れば百メートルとリレーの選手に決まる。オリンピック選手の誕生だ。
しかし、なにしろ百メートルだ。十秒あまりの戦いの中で、ほんのわずかな狂いが、全てを台無しにしてしまう。
体調を崩したらどうだ。当日、熱を出したら、下痢になったら、そんな例はいやほど見ている。
高熱を出し、朦朧となりながら、四百メートルを走り、準決勝で病院に運ばれた選手がいた。
レースの直前、トイレに駆け込み、便器に腰掛けながらピストルの音を聞いた選手もいる。笑い話ではない。大事な試合や試験の前に、決まって体調を崩す人間がいる、それが、大森でないとどうして言えるだろう。
予選のスタートでつまずいたら、靴が脱げたら、フライングをして失格になったら。オリンピックの決勝でさえ、フライングで失格になった選手がいた。
天気はどうだ。当日は晴れか、雨か。今は梅雨だ。雨の確率は高い。雨粒が目に入り、体のバランスを崩すことはないのか。トラックに水がたまり、足を滑らすことはないのか。
考えだすと、キリがなかった。悪い考えが次々に浮かんできては消え、また浮かんでくる。
平然とした態度をとってはいたが、高尾は、この一週間、眠りが浅く、夜中に何度も目を覚ましていた。
八年前の日本選手権。四百メートル決勝、ゴールテープの五メートル前で倒れた鈴木の姿が何度も夢に現れ、そのたびにうなされて、ベッドの上で起きあがり、薄ぼんやりとした、気の抜けたような暗さの、都会の闇の中で、冷や汗をかきながら目を見開いていた。
「楽にいこう。大森君。楽に。君なら大丈夫だから」
高尾は自分に言い聞かせるように、ゆっくりと言った。
明和大学のグラウンドに、日本人で初めて十秒の壁を破った沢田武志の姿はなかった。
「先生、隠さないでくださいよ」
沢田の取材に訪れた記者達は、当てが外れ、コーチの石嶺に文句を言っていた。
「沢田選手は、どちらですか。一言だけでもコメントをいただけませんか」
「試合は明日だから、沢田は、軽い練習だけで、今日は上がりました」
石嶺は、記者に囲まれ、何度も同じ言葉を繰り返していた。
「教えてくださいよ。子どもの使いじゃないんだから、何もなしじゃ、帰れませんよ」
「今日は、静かにしていたいという、本人の希望ですので、ご了承下さい。明日の予選の後には、コメントできると思いますから」
「先生、頼みますよ。一言だけでも」
「すいません。本当に今日は……」
「写真を一枚」
「すみません」
石嶺は記者の輪の中で髪の毛が薄くなった頭を下げ続けていた。
実は、沢田が今どこにいるのか、石嶺も知らなかった。昨日はグラウンドでいつものように練習したのだが、今日は、何の連絡もなく休んでいた。
「仕方ないな……」
記者たちは、舌打ちをし、沢田のコメントをあきらめて、一人一人、帰っていった。
記者の輪から解放され、
「ふー」と石嶺は息を吐いた。
「まったく、あいつは……」
どうせ、また女だろう。と、石嶺は思った。スポーツカーの助手席にアイドル歌手を乗せて試合に来るような男だ。
明日が日本選手権と言っても、緊張など無縁なのだろう。
「たいしたもんだよ」
自分は何日も前から、胃が痛く、食欲もないというのに、当の本人は練習をすっぽかし、女と遊んでいるらしい。
もし、自分に沢田の半分程のずうずうしさがあれば、オリンピックにも行けたかもしれない、と、石嶺は一瞬思った。大事な試合になればなるほど、緊張して足が動かなくなった。自己記録は、観客が誰もいないような小さな大会で出したものだ。
いや、違う、と石嶺はすぐに思い直した。自分のような平凡な男が、勘違いして思い上がったら、苦しい練習などしなかったに違いない。遊びを覚え、練習をさぼり、不摂生をし、記録はおろか、途中で陸上競技を止めていただろう。
自分の記録は、平凡な男が精一杯努力した結果だ。そして今、ここで好きな陸上のコーチをしていられるのも、努力した結果なのだ。
「ん? 雨か……」
石嶺の頬に雨粒が当たった。見上げると、空は、いつのまにか厚い雨雲で覆われていた。六月の末だった。梅雨明け宣言は、まだされていない。
ポツリ、ポツリと、大粒の雨がグラウンドに落ちだし、小さな土煙を立てて、黒い跡を残していった。
稲妻が光り、雷が鳴ると、大量の雨が地面に降り注いできた。
「ひどいなこれは」
叩きつける雨が水煙を上げ、夕方のような暗さに変わっていた。石嶺は、何の役にも立たないのに、手のひらを頭の上にかざしながら、走り出した。
石嶺の予想は半分当たっていた。
その日、沢田は、美里奈美という自称アイドルの子を車の助手席に乗せ、横浜に向かっていた。
横浜に特に目的はなかった。首都高に乗り、車を走らせているうちに、横浜に来てしまっただけだった。
沢田は、高速道路を下り、東京湾が一望できるホテルに車を入れ、最上階の部屋をとった。
石嶺が記者達に頭を下げているとき、沢田は、ベッドで他の運動に励んでいた。
ことが終わると、沢田は、すぐにイビキをかいて眠ってしまった。
「変な人」
奈美はあきれたように沢田の顔を見た。
今日は、朝の十時に急に沢田に呼び出され、車に乗せられ、ホテルに着き、沢田とセックスをした。
沢田はいつも、部屋に入ると、すぐに裸になり、「ウホウホ」とゴリラのマネをしながら、迫ってくる。
バカみたいだ。でも、嫌いじゃない。単純で明るいし、お金もある。それに、何を言っても沢田は有名人だ。
二ヶ月前、週刊誌に沢田と一緒にホテルに入る写真が載った。何だか自分が有名人になったみたいで良い気分だった。
奈美は、沢田の顔を手の平で軽く叩いてみた。沢田は、「うーん」と言って、その手を払ったが、目は開けなかった。
「ふわー」奈美は欠伸をした。朝の十時は、奈美にしては早い起床だった。奈美は沢田の隣で横になると、目を閉じて眠ってしまった。
一時間程して、奈美は目を覚ました。ベッドの横の時計を見ると、時間は二時を回っていた。
ベッドに沢田はいなかった。奈美は眠そうに欠伸をしながら、部屋の中を見回した。
窓際にシルエットが見えた。沢田だった。沢田は、何も着けず、裸のまま、立って海を見ていた。
「ねえぇ、何か食べに行こうよ」
奈美が鼻にかかった声で、けだるそうに言った。
「奈美、お腹空いちゃった」
舌足らずの声で言う。人気のあるアイドルのマネだった。
「……違うんだよな」
沢田が外を向いたままで呟いた。
「えっ?。なにぃ?」
「違うんだよ」
沢田は独り言を繰り返した。
「ねえ、何のこと?」
奈美が言うと、沢田は振り返り、
「おまえさ、もう、帰っていいよ」と言った。
「えっ、何?」
「帰っていいから」
「なによ。それ、ねえ。ここから、一人で帰れって言うの」
奈美が驚いて言うと、
「ああ、帰れるだろ」と沢田はあっさり言いった。
「ちょっと」
沢田は、また、海に向かい、
「……違うんだよな」と呟いた。
「もう」
やっぱり沢田は変わっている。沢田は、時々、自分だけの世界に入ってしまう。はしゃいでいたかと思うと、急に真剣な顔になる。こうなると、もう、周りのことには関心が無くなってしまう。
仕方がない、これが沢田武志だ、怒ってみても始まらない。何か急に思いつき、一人になって考えたいのだろう。明日になれば、また、電話をかけてくるに違いない。
「じゃあ、私、もう帰るから」
奈美は服を着た。
「ああ」沢田は振り返らずに答えた。
「またね」奈美は部屋を出た。
「ああ」沢田は右手を上げて答えた。
奈美がホテルを出ようとすると、外はどしゃ降りだった。
奈美はロビーに戻り、携帯電話を取り出し、
「ねえ、私、奈美。今、横浜なんだけど、急に会いたくなっちゃって」
と、迎えに来そうな男を選んで電話をかけた。
「久米ちゃん。うまいでしょ。ウチのトンカツ定食」
「ええ、まあ」
定食屋「さわだ」の店内はスポーツ新聞の記者達で結構繁盛していた。
「ちゃんとうちの名前も入れてよ。沢田選手は「さわだ」のトンカツ定食を食べて足が速くなりましたって」
日報スポーツの久米は苦笑しながら、トンカツを口に運んだ。
子が子なら、親も親だ。インタビューに来ると、話の前に、必ずトンカツ定食を注文させられる。
先月から、トンカツ定食は、ちゃっかり、二百円値上がりしていた。頼んでないのに、納豆と豆腐が追加が付き、しめて千五百円だ。
(経費で落ちるかな)
久米は衣の厚いトンカツを食べながら思った。
「お客さん、生卵はサービスだよ」
沢田似の母親ははりきっている。いや、沢田が母親に似ているというべきか、ともかく、沢田の実家は、東京の下町にある小さな定食屋だった。
昔ながらの八百屋や肉屋の並ぶ商店街には、アーケードに「祝 日本新記録 沢田選手」の横断幕が掲げられていた。オリンピック出場が決まれば、横断幕は「祝オリンピック出場 沢田選手」に掛け替えられる手はずが整っていた。
「……違うんだよな」
沢田の前には、雨に煙る東京湾の景色が広がっていたが、沢田の目には何も写っていなかった。
人から見れば、沢田は変人で天才だった。天才の定義はいろいろあるだろうが、日本人で初めて九秒九を切ったことを考えれば、彼を天才と言っても問題はないだろう。
横柄な口のききかたをし、派手な衣装を着て、両耳にピアスを付け、ダイヤの指輪をし、助手席にアイドル歌手を乗せて、スポーツカーで競技場に乗り付けてくる。
レースでは、アメリカの黒人選手のように、サングラスをかけ、金のネックレスをして走る。
大言壮語。沢田は、記録を作る二年も前から、「世界で勝つ」と、マスコミに言い続けてきた。
「おれはさ。天才だから、てっぺんに立つ男だから」
「日本なんて、考えてないから、おれは、世界のスターだから」
画家のダリのように、奇矯な行動をすることで、マスコミの過剰な関心に耐え、自分の脆い心の奥を隠す人間がいる。しかし、沢田は別に計算して、そのような態度をとっているわけではなかった。
全て、その時、その時、思ったままに行動し、しゃべってきただけだった。
「……違うんだよな」
沢田は何度も同じ言葉を繰り返していた。
明日から日本選手権が始まる。試合を明日に控えているというのに、気持ちが高ぶってこなかった。
試合前日には、いつも興奮して落ち着かなかった。不安ではない。ただ、ただ楽しいのだ。足の速い小学生が運動会を楽しみにするのと同じように、沢田は試合が楽しみでたまらなかった。
勝者は自分だ。両手を挙げてゴールラインを走りさるのは自分だ。フラッシュがたかれ、マイクが差し出され、周りの人間は羨望のまなざしで自分を見ている。快感だ。例えようも無いほどの快感だ。それなのに……今回は少し、違う。
沢田本人は自覚していなかったが、アジア記録を作って、マスコミに騒がれた後、ある種の達成感を感じ、記録や戦いへの飢餓感が薄れていた。闘争心が涌いてこない。記録を出して周りを驚かせてやるといった気持ちになれない。
しかし、沢田は確かに天才だった。自分に何が必要か本能が理解していた。
沢田は、立ったまま目をつぶった。
「位置について」
スターターの声を頭の中で呼び起こす。
弛緩した神経をもう一度研ぎ澄まなくてはだめだ。闘争本能をたたき起こすのだ。
「よーい」
頭の中で、沢田は腰を浮かした。スターターのピストルの音に神経を集中する。
「パン」
音が鳴った。かすかに硝煙の臭いを感じる。
スタート。
飛び出す。
腕を高く振る。体はまだ上げるな。
前を見る。頬に風を感じる。風景が左右に流れていく。
五十メートル。六十メートル。体の力を抜け、リラックスしろ。
ゴールラインが見える。体を前傾する。胸がラインを越えた。
ゴール。
よし、勝った。
沢田は息を吐く。
もう一度。
「位置について……」
同じことの繰り返しだ。
沢田は、何度も何度も、スタートからフィニッシュまでの九秒八八を正確に頭の中で繰り返していた。
イメージトレーニング。一流のアスリートは、イメージしただけで、筋肉が反応する。 部屋は冷房が効き過ぎるほど効き、冷えきっていた。しかし、動いてもいないのに、沢田の体は汗ばみ、白く湯気が立ち上っていくのが見えた。
東京に戻ってから、容子は大森とは会っていなかった。大森から二、三回連絡があったのだが、容子は用事があるからとウソをついて断っていた。
しばらくして、大森からアパートを替わるからと携帯電話に伝言が入っていたが、それ以来連絡はなかった。
急に道が分かれてしまった。大森の心は自分から離れてしまった。同じ道を歩いていると思っていたのに、相手は全く違う道を進んでいた。
いつからだろう。何が悪かったのだろう。
考えても分からなかった。いや、考えても仕方のないことだった。
自分が悪かったのなら謝ればいい。何か行き違いがあったのなら、話し会えば解決できるのかもしれない。
しかし、変わってしまったものは、もう元には戻せない。大森の目は自分を見ていないし、二人の将来を考えてもいないのだ。自分が何を言っても、元に戻ることはないだろう。
卒業すれば、遠くに離れる、前はそのことが不安だったが、今は救いだった。
就職試験を受けるために地元に帰った間、思いの外、寂しくなかった。大森との恋が終わったと考えても、胸をかきむしるような寂しさはなかった。
もういい。そんな感じだった。
あまりに彼は変わってしまった。木訥で素直で正直な彼はどこかへ行ってしまった。
初めて手が触れたときのあわてた表情や体を重ねた時の心臓の鼓動は今も鮮明に残っている。しかし、それもいつか、写真が色あせるように、記憶も淡く消えていき、秋風を頬に感じたときに、ふっと浮かんでくるだけの小さな思い出に変わってしまうのだろう。
携帯電話が鳴った。心臓の鼓動が速くなった。大森? 分けがない。でも……もしかして。
携帯電話を耳に当てる。
「はい、青井です」
「容子? ねえ、ちょっと出てこない? 今ね、友恵と千佳と飲んでるのよ」
電話は大学の同級生の由香からだった。
「ええ? 今から?」
「おいでよ。容子」
電話は友恵に代わっていた。
「そうね……」
友恵は飲み屋の名前を言った。知っている店だった。アパートからは歩いて十分ほどの場所にあった。
「ほら、容子。私の慰め会なんだから」
後ろで、「また振られたんだよ」と、千佳が言っていた。だいぶ出来上がっている。
容子は、「わかった、わかった」と、言って、電話を切り、立ち上がった。
夜。雨は止んだ。今年の梅雨は熱帯地方のスコールのように、短時間激しく降って、すぐに止んでしまう。
大森はマンションのベランダに出て、下を見下ろしていた。
雨で都会のチリが洗い流され、空気が澄んでいた。車のライトが赤やオレンジの星になって流れていく。目をかなたにやると、都心のビルの明かりが見えた。
明日、日本選手権が始まると言うのに、大森に不安はなかった。高ぶりも感じていなかった。高尾は、大森がオリンピックの代表に選ばれるかどうか心配していたが、大森本人は、日本選手権など、ただの通過点だという思いだった。
大森は深呼吸をして胸を張った。そして、雲の切れ間から顔を出した月に向かって、拳を突き上げた。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

優秀賞受賞作【スプリンターズ】少女達の駆ける理由
棚丘えりん
青春
(2022/8/31)アルファポリス・第13回ドリーム小説大賞で優秀賞受賞、読者投票2位。
(2022/7/28)エブリスタ新作セレクション(編集部からオススメ作品をご紹介!)に掲載。
女子短距離界に突如として現れた、孤独な天才スプリンター瑠那。
彼女への大敗を切っ掛けに陸上競技を捨てた陽子。
高校入学により偶然再会した二人を中心に、物語は動き出す。
「一人で走るのは寂しいな」
「本気で走るから。本気で追いかけるからさ。勝負しよう」
孤独な中学時代を過ごし、仲間とリレーを知らない瑠那のため。
そして儚くも美しい瑠那の走りを間近で感じるため。
陽子は挫折を乗り越え、再び心を燃やして走り出す。
待ち受けるのは個性豊かなスプリンターズ(短距離選手達)。
彼女達にもまた『駆ける理由』がある。
想いと想いをスピードの世界でぶつけ合う、女子高生達のリレーを中心とした陸上競技の物語。
陸上部って結構メジャーな部活だし(プロスポーツとしてはマイナーだけど)昔やってたよ~って人も多そうですよね。
それなのに何故! どうして!
陸上部、特に短距離を舞台にした小説はこんなにも少ないんでしょうか!
というか少ないどころじゃなく有名作は『一瞬の風になれ』しかないような状況。
嘘だろ~全国の陸上ファンは何を読めばいいんだ。うわーん。
ということで、書き始めました。
陸上競技って、なかなか結構、面白いんですよ。ということが伝われば嬉しいですね。
表紙は荒野羊仔先生(https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/520209117)が描いてくれました。

美容師みみかの1日
coffee+
大衆娯楽
**「美容師みみかの1日」**は、
美容室 **YAIMY東和店の店長・岡島 公香(みみか)**が、
仕事と家庭を両立しようとするも、毎日トラブル続き!
✅ 朝が苦手でいつもギリギリ出勤!
✅ 仕事中にウトウト…でもお客様は待ってくれない!
✅ 新人アシスタントはミス連発!?
✅ 店長会議は毎回ピンチ!!
✅ 母親業と仕事の両立…でも、うまくいかない!?
時短に挑戦するも、結局「無理!」と断念し、開き直って毎日全力で奮闘するみみかの姿を描く、笑いあり、涙ありのリアル美容室ドキュメント小説!

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

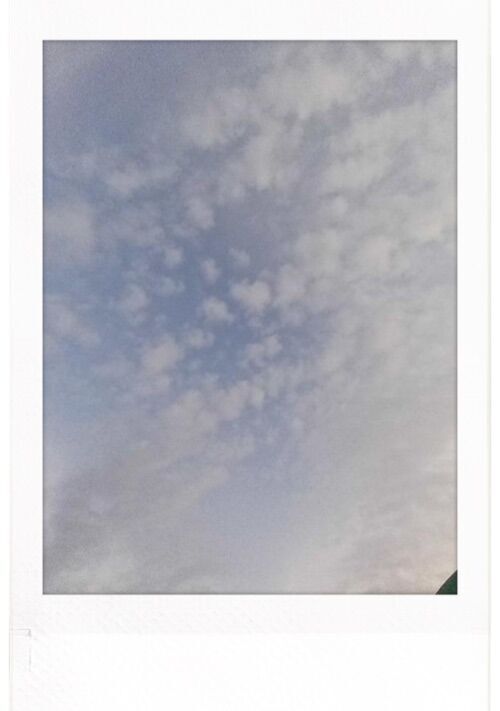
ファンファーレ!
ほしのことば
青春
♡完結まで毎日投稿♡
高校2年生の初夏、ユキは余命1年だと申告された。思えば、今まで「なんとなく」で生きてきた人生。延命治療も勧められたが、ユキは治療はせず、残りの人生を全力で生きることを決意した。
友情・恋愛・行事・学業…。
今まで適当にこなしてきただけの毎日を全力で過ごすことで、ユキの「生」に関する気持ちは段々と動いていく。
主人公のユキの心情を軸に、ユキが全力で生きることで起きる周りの心情の変化も描く。
誰もが感じたことのある青春時代の悩みや感動が、きっとあなたの心に寄り添う作品。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















