73 / 162
telepathy
しおりを挟む
※このお話はパラレルです。「たとえば」「もしも」設定です。彼らの現実で起こったお話ではありませんので、ご了承ください。
〈倉知編〉
「……ち、くらち、おい、起きろ」
揺り起こされて目を開けた。ハッとして、急いで体を起こす。
遠くに黒板が見えた。大学の教室だ。
教壇にはすでに教授の姿はなく、人もまばらだ。
「珍しいな、倉知が居眠りなんて」
橋場が言った。いつの間に寝たのか、記憶にない。
「寝不足?」
「え? いや、そんなことは」
――どうせ寝ないでイチャついてたとかだろ
「えっ」
驚いて声が出た。橋場が怪訝そうに俺を見下ろす。
「今、なんて」
橋場は普段、冗談でもこんな科白は言わない。
「何」
「何って、今、寝ないでイチャついてたって」
橋場が黙った。怒ったような顔に見えたが、次の瞬間、橋場の声が直接脳内に響いてきた。
――おかしいな、声に出てた?
「え? ええ? 何、何これ」
慌てて椅子から腰を上げた。今、橋場は口を真一文字に引き結んでいた。腹話術の名手でもなければ、声を出せるはずがない。
というよりも、明らかに、耳ではなく、頭の中に声が広がった。
「今日はもう講義もおしまいだし、帰って寝たら?」
――今夜はイチャついてないでちゃんと寝ろよ
またしても聞こえてくる、橋場らしからぬ軽口。
硬直する俺を置いて、橋場が去っていく。
おかしい、どうなっているのだろう。
寝ぼけているのだろうか。
頭を掻いて、教室を出た。
廊下を歩く。今日はやけに騒がしい。人の数に見合わない、やかましさだ。
「カラオケ行かない?」
「ごめんね、今日バイトだからパス」
――バイトなんてないけどね。こいつ、いつになったら音痴に気づくんだろ
俺の横を通り抜けた二人の会話がおかしい。
耳を塞いでみる。
すぐに意味がないと気づいた。
声は、やはり頭の中に直接流れ込んできている。
――おっぱいおっぱい。揉みたい、挟まりたいいい
――エロい目で見てんなよ、バレバレなんだよ、金玉蹴り上げるぞコラ
――あー、エッチしてえ
――今日は素人ナンパものか、人妻ものか、どっちにするかな
――あ、いい男。どんなチンコしてんのかな
耳を塞いだままで、絶句した。
脳内に侵入してくる独り言が、男女問わずほぼすべて下ネタだ。
俺は、走り出した。全力で大学の構内を脱出して、大急ぎで電車に乗り込んだ。
車内は混んでいた。満員というほどではなかったが、座れそうにない。手すりにつかまって、息をつく。
――なんであの子のほうがモテるの? あたしのほうが絶対可愛いのに
――テストだりい、学校燃えてなくならないかな
――五千兆円欲しい。そしたら今すぐ仕事辞めてやる
ネガティブなつぶやきが、あちこちから湧いてくる
口を閉ざしながら好き勝手わめく人たちの中で、電車に揺られ、耐えた。
マンションに着いた頃にはぐったりしていた。スーパーに寄るのを忘れるくらいに疲弊していて、冷蔵庫を覗いてみても、頭が回らない。何か作れる気はしなかった。
さっきから心臓がドキドキしている。
どうしてこうなったかはわからないが、多分、俺は、突然超能力に目覚めたのだ。
冷蔵庫を閉じて、後ずさる。そして、両手を突き出して、開け、と念じた。
冷蔵庫はビクともしない。
咳払いをして、手を下ろす。
物を動かしたりはできないにしても、人の心を読めるのは確かだ。
「加賀さん」
つぶやいた。
そうだ、当然、加賀さんの考えていることも、わかってしまう。
それはとても怖いことに思えた。
もし、加賀さんが変なことを考えていたら?
加賀さんの口から仕事の愚痴は聞いたことがない。仕事が楽しいし、好きだと言っている。でも、もし、違ったら? 加賀さんが愚痴るところなんて見たくない。
俺たちの間には、秘密がない。でも、何か重大なことを隠していたら。
本当は、俺のことを好きじゃなかったら。別れたいと考えていたら。
首を横に振る。
ない、ありえない。
ため息をついた。ソファに腰を下ろし、頭を抱える。
加賀さんの頭の中。
覗いてみたい気もする。でも、エロいことで溢れていたら、どうしよう。
……別に、どうもしない。
加賀さんがエロいことを考えていても、びっくりしないしがっかりしない。常日頃から下ネタも言うし、親父ギャグも言うし、エロいことを隠さないし我慢しない人だ。
じゃあいいか、と割り切ることにした。
前向きに気持ちを切り替え、とりあえず何かあるもので夕飯の用意をすることにした。
パスタくらいなら作れそうだ。冷凍のエビもあるし、常備野菜もある。簡単なサラダと、オニオンスープも準備した。一日くらい買い物しなくてもなんとかなるものだ。
「ただいま」
加賀さんが帰ってきた。洗い物をしながら、「おかえりなさい、お疲れ様です」と笑顔を向けた。
「あー、腹減った。すげえいい匂い、何?」
「エビのトマトクリームパスタです」
「うわ、美味そう」
答えてから、もし、と考えた。嫌いなものがないと言っている加賀さんが、実は好き嫌いがあったら?
「エビとかトマトとか、大丈夫ですか?」
「え? 何? 今さら?」
「加賀さん、嫌いな食べ物ないって言ってますけど、実は何かあるんじゃないですか?」
「どうした急に」
少し首をかしげて、加賀さんが笑った。
――なんかわかんねえけど、嫌いなものがあったほうがいいのか?
加賀さんの声が頭に響く。
――嫌いなもの? あったか?
考えている。すごく考えている。口がニヤニヤしてしまう。
――なんだ? にんじんとかピーマンって言えば可愛いのか?
ちょっとだけ吹き出してしまった。加賀さんが顔を上げる。そして俺をじっと見る。
――なんかあったな
「何もないです、あの、着替えてきてください。パスタ茹でますね」
「ん、おう」
――まあいっか
加賀さんは真から楽天家かもしれない。
着替えて戻ってきた加賀さんが、「あと何分?」と訊いた。
「あと五分くらいです」
答えると、加賀さんの声が頭の中に飛んできた。
――よし、ラッキー。五分間めっちゃ甘えよう
「え」
がし、と背中に抱きつかれた。すりすりとすり寄られているのがわかる。
「あの、あと五分かかるんで、ソファでゆっくりしてていいですよ」
「んー、このほうが落ち着くし安らぐんだよ」
――あー、すげえ癒される。倉知君大好き
「加賀さん」
俺の声は鼻声で、揺らいでいた。慌てて目元を拭う。
よかった、すごく、好かれている。
わかっている。疑うなんて失礼だった。でも、心の声を直接聞けて、本当にホッとした。
「あ、もしかして俺邪魔?」
「邪魔じゃないです、そこにいてください。ずっとくっついててください」
「はは」
――ほんと、ずっとこうしてたい。すっげえ好き
優しい本音がふわりと俺を包み込む。全身で、力いっぱいしがみついてくる、愛しい人。涙が堪えられなくなった。嬉しくて、幸せで、むせび泣く。
「え? なんで? どうした?」
――やっぱりなんかあったな
「すいません、俺、なんか、おかしくて、頭が、おかしいんです」
「よしよし、わかった。とにかく食おう」
加賀さんが俺の背中を撫でさすると、タイマーがパスタの茹で上がりを告げた。
温めなおしたソースをかけて、テーブルに置くと、向かい合って腰を下ろす。いただきますと手を合わせると、加賀さんがフォークにパスタを巻きつけながら、じっと俺を見てくる。
――ネガティブ、とは違うな
「はい、そうです」
「ん?」
「あ、いえ、なんでもないです」
つい、心の声に返事をしてしまった。目を落とし、パスタを口に運ぶ。
――頭がおかしいってどういう意味だ?
「あの、加賀さん、俺」
人の心が読めるようになったんです、とそのまま正直に言おうとして、ためらった。
種明かしする前に、試したいことがある。
「いえ、あの、美味しいですか?」
「うん、美味い」
――お前の料理はいつも美味いよ
「へへ」
にやける俺を、加賀さんが探るように見ている。
――なんか変だな
どうやら俺はわかりやすいらしい。
なるべくうつむいて、変なことを言わないように、妙な反応をしないように、無心で夕食を胃に詰め込んだ。その間の加賀さんの脳内はと言えば、「美味い」という誉め言葉と、「なんだ?」という疑問。それになぜかちょいちょい「可愛い」と「好き」を挟んでくるから、そのたびに顔が熱くなり、指が震えそうになった。
「加賀さん、お願いが」
食べ終わった食器をシンクに運ぶと、洗い物を開始しようとする加賀さんを止めた。
「何?」
「それは後回しにして、抱かせてくれませんか?」
「……はい?」
――いきなりどうした
「食後の軽い運動です」
「お、おう」
――本当に軽いのかよ
「大丈夫です、軽いです」
加賀さんの腰を抱き寄せて、首筋にキスをした。吸う。舐める。噛みつく。舌で耳たぶを転がしてから、耳を口中に含みながら、髪の中に指を差し入れた。
「ん……」
――やべえ、チンコ勃つ
勃ってもいいじゃないですか、と笑いそうになる。
「ちょっと、なあ、本当に今する?」
――食ったばっかだぞ。中身出たらどうすんだよ
ぐっ、と笑いを噛み殺す。笑ったら怪しまれる。堪えろ俺。
「今です。寝室行きます? それともここで?」
「寝室で」
即答した加賀さんの体を抱え上げて、寝室に飛び込んだ。ベッドに押し倒し、上から覗き込む。服の裾をめくり、手を入れる。丁寧に服を脱がせ、全裸にする。
「倉知君も脱いでよ」
――体、見たい
「わかりました」
勢いよく服を脱ぎ捨てた。加賀さんが、ふう、と短く息を吐く。
――めっちゃしたくなってきた
加賀さんの股間を確認した。すごく興奮してくれているのがわかる。愛しさが胸の内で倍増する。
「加賀さん、愛してます」
「うん、俺も」
――めちゃくちゃ愛してる
「抱いてもいいですか?」
「え? 今さら?」
「俺に抱かれたい?」
加賀さんが黙った。
――抱かれたいに決まってんだろ。なんでいちいち訊くんだ?
「よかった」
「何?」
「いえ、抱きます」
いつも以上に、優しく丁寧に扱った。
加賀さんの本音が聞きたくて、セックスを試したかった。
本当は嫌なんじゃないか。
本当は気持ちよくないんじゃないか。
俺に気を遣って、フリをしているんじゃないか。
馬鹿なことを考えた。
気持ちいい。
好き。
もっと。
七世、七世。
終わってみると、なんのことはない。嫌悪の瞬間など一度もなかった。本気で気持ちよくて、俺を好きでいてくれるのが痛いほど伝わった。
「加賀さん、俺、人の心が読めるようになったんです」
俺の上にまたがって、胸に頬をくっつけて体重を預けていた加賀さんが、「へえ」と気のない返事をした。
「疑ってますね?」
「え、超能力的な? 何、本気で言ってんの?」
「本気です。今から加賀さんが考えてること当ててみますから、なんでもいいから考えてください」
「なんでもいいの?」
「なんでもいいです。丸わかりですから。はい、どうぞ」
沈黙が落ちる。
静かだ。何も聞こえない。
おかしい。
もしやこれは、無の境地というやつか。
俺に心を読ませまいとして、無になっているに違いない。
「加賀さん、ちゃんと考えて」
「考えたよ?」
「え、本当に? 何も聞こえませんでしたよ」
「そりゃそうだよ、声に出してないからね」
「違うんです、俺、心が読めるから、言わなくても思うだけで」
「今めっちゃ心の中で叫んでるよ」
「えっ、嘘、何も聞こえない」
うろたえる俺の上で、加賀さんが笑い出した。
「信じてませんね?」
「いや、信じるよ。お前さっき、変だったもんな」
加賀さんはすごい。こんな馬鹿な話を簡単に信じてくれる。
「なんでいきなり聞こえなくなったんだろう」
「なんでいきなり聞こえるようになったんだろう、じゃない?」
加賀さんはおかしそうだ。
「あっ、セックスしたからかな?」
「ああ、射精したから? はは、うける」
「やっぱり信じてませんよね?」
「ていうかお前、俺が考えてることわかってたんだよな?」
「はい、帰ってきてからの頭の中、筒抜けでした」
そうだ、ちゃんと証明する方法があるじゃないか。
「嫌いな食べ物訊いたら、にんじんとかピーマンって言えば可愛いのかなって悩んでましたね」
「え」
「中身出たらどうするんだって、面白かったです」
「ちょ、待って、マジか」
加賀さんがようやく本気になってくれた。わたわたと、俺の上で体を起こす。
「えっ、あれ、待って、俺、なんか変なこと考えてなかった? やべえ、嘘だろ、なあ俺、恥ずかしいこと考えてなかった? 大丈夫?」
ものすごく可愛かったです。そしてうろたえる今の加賀さんも可愛いです。
ニヤニヤしながらあえて返事をしないでいると、加賀さんが殊勝な顔になり、俺を上目遣いで見て訊いた。
「エッチのとき、何考えてるか知りたかったとか?」
「そうですね、ちゃんと気持ちいいかなって。苦痛じゃないかなとか、嫌なことしてないかなって、確認です」
加賀さんが顔を覆う。
「すいません、なんか、あの、誘惑に勝てなくて」
「いいけど、あー、俺の頭ん中、ひどくなかった? ……幻滅した?」
俺の腹を指でつついてくる。
「すごく幸せでした。加賀さん、俺のこと大好きですよね」
加賀さんがホッとした様子で、肩で息をつく。
「当たり前だろ」
心が読めなくたって、わかる。
愛してる。
加賀さんが、優しく微笑んだ。
〈おわり〉
〈倉知編〉
「……ち、くらち、おい、起きろ」
揺り起こされて目を開けた。ハッとして、急いで体を起こす。
遠くに黒板が見えた。大学の教室だ。
教壇にはすでに教授の姿はなく、人もまばらだ。
「珍しいな、倉知が居眠りなんて」
橋場が言った。いつの間に寝たのか、記憶にない。
「寝不足?」
「え? いや、そんなことは」
――どうせ寝ないでイチャついてたとかだろ
「えっ」
驚いて声が出た。橋場が怪訝そうに俺を見下ろす。
「今、なんて」
橋場は普段、冗談でもこんな科白は言わない。
「何」
「何って、今、寝ないでイチャついてたって」
橋場が黙った。怒ったような顔に見えたが、次の瞬間、橋場の声が直接脳内に響いてきた。
――おかしいな、声に出てた?
「え? ええ? 何、何これ」
慌てて椅子から腰を上げた。今、橋場は口を真一文字に引き結んでいた。腹話術の名手でもなければ、声を出せるはずがない。
というよりも、明らかに、耳ではなく、頭の中に声が広がった。
「今日はもう講義もおしまいだし、帰って寝たら?」
――今夜はイチャついてないでちゃんと寝ろよ
またしても聞こえてくる、橋場らしからぬ軽口。
硬直する俺を置いて、橋場が去っていく。
おかしい、どうなっているのだろう。
寝ぼけているのだろうか。
頭を掻いて、教室を出た。
廊下を歩く。今日はやけに騒がしい。人の数に見合わない、やかましさだ。
「カラオケ行かない?」
「ごめんね、今日バイトだからパス」
――バイトなんてないけどね。こいつ、いつになったら音痴に気づくんだろ
俺の横を通り抜けた二人の会話がおかしい。
耳を塞いでみる。
すぐに意味がないと気づいた。
声は、やはり頭の中に直接流れ込んできている。
――おっぱいおっぱい。揉みたい、挟まりたいいい
――エロい目で見てんなよ、バレバレなんだよ、金玉蹴り上げるぞコラ
――あー、エッチしてえ
――今日は素人ナンパものか、人妻ものか、どっちにするかな
――あ、いい男。どんなチンコしてんのかな
耳を塞いだままで、絶句した。
脳内に侵入してくる独り言が、男女問わずほぼすべて下ネタだ。
俺は、走り出した。全力で大学の構内を脱出して、大急ぎで電車に乗り込んだ。
車内は混んでいた。満員というほどではなかったが、座れそうにない。手すりにつかまって、息をつく。
――なんであの子のほうがモテるの? あたしのほうが絶対可愛いのに
――テストだりい、学校燃えてなくならないかな
――五千兆円欲しい。そしたら今すぐ仕事辞めてやる
ネガティブなつぶやきが、あちこちから湧いてくる
口を閉ざしながら好き勝手わめく人たちの中で、電車に揺られ、耐えた。
マンションに着いた頃にはぐったりしていた。スーパーに寄るのを忘れるくらいに疲弊していて、冷蔵庫を覗いてみても、頭が回らない。何か作れる気はしなかった。
さっきから心臓がドキドキしている。
どうしてこうなったかはわからないが、多分、俺は、突然超能力に目覚めたのだ。
冷蔵庫を閉じて、後ずさる。そして、両手を突き出して、開け、と念じた。
冷蔵庫はビクともしない。
咳払いをして、手を下ろす。
物を動かしたりはできないにしても、人の心を読めるのは確かだ。
「加賀さん」
つぶやいた。
そうだ、当然、加賀さんの考えていることも、わかってしまう。
それはとても怖いことに思えた。
もし、加賀さんが変なことを考えていたら?
加賀さんの口から仕事の愚痴は聞いたことがない。仕事が楽しいし、好きだと言っている。でも、もし、違ったら? 加賀さんが愚痴るところなんて見たくない。
俺たちの間には、秘密がない。でも、何か重大なことを隠していたら。
本当は、俺のことを好きじゃなかったら。別れたいと考えていたら。
首を横に振る。
ない、ありえない。
ため息をついた。ソファに腰を下ろし、頭を抱える。
加賀さんの頭の中。
覗いてみたい気もする。でも、エロいことで溢れていたら、どうしよう。
……別に、どうもしない。
加賀さんがエロいことを考えていても、びっくりしないしがっかりしない。常日頃から下ネタも言うし、親父ギャグも言うし、エロいことを隠さないし我慢しない人だ。
じゃあいいか、と割り切ることにした。
前向きに気持ちを切り替え、とりあえず何かあるもので夕飯の用意をすることにした。
パスタくらいなら作れそうだ。冷凍のエビもあるし、常備野菜もある。簡単なサラダと、オニオンスープも準備した。一日くらい買い物しなくてもなんとかなるものだ。
「ただいま」
加賀さんが帰ってきた。洗い物をしながら、「おかえりなさい、お疲れ様です」と笑顔を向けた。
「あー、腹減った。すげえいい匂い、何?」
「エビのトマトクリームパスタです」
「うわ、美味そう」
答えてから、もし、と考えた。嫌いなものがないと言っている加賀さんが、実は好き嫌いがあったら?
「エビとかトマトとか、大丈夫ですか?」
「え? 何? 今さら?」
「加賀さん、嫌いな食べ物ないって言ってますけど、実は何かあるんじゃないですか?」
「どうした急に」
少し首をかしげて、加賀さんが笑った。
――なんかわかんねえけど、嫌いなものがあったほうがいいのか?
加賀さんの声が頭に響く。
――嫌いなもの? あったか?
考えている。すごく考えている。口がニヤニヤしてしまう。
――なんだ? にんじんとかピーマンって言えば可愛いのか?
ちょっとだけ吹き出してしまった。加賀さんが顔を上げる。そして俺をじっと見る。
――なんかあったな
「何もないです、あの、着替えてきてください。パスタ茹でますね」
「ん、おう」
――まあいっか
加賀さんは真から楽天家かもしれない。
着替えて戻ってきた加賀さんが、「あと何分?」と訊いた。
「あと五分くらいです」
答えると、加賀さんの声が頭の中に飛んできた。
――よし、ラッキー。五分間めっちゃ甘えよう
「え」
がし、と背中に抱きつかれた。すりすりとすり寄られているのがわかる。
「あの、あと五分かかるんで、ソファでゆっくりしてていいですよ」
「んー、このほうが落ち着くし安らぐんだよ」
――あー、すげえ癒される。倉知君大好き
「加賀さん」
俺の声は鼻声で、揺らいでいた。慌てて目元を拭う。
よかった、すごく、好かれている。
わかっている。疑うなんて失礼だった。でも、心の声を直接聞けて、本当にホッとした。
「あ、もしかして俺邪魔?」
「邪魔じゃないです、そこにいてください。ずっとくっついててください」
「はは」
――ほんと、ずっとこうしてたい。すっげえ好き
優しい本音がふわりと俺を包み込む。全身で、力いっぱいしがみついてくる、愛しい人。涙が堪えられなくなった。嬉しくて、幸せで、むせび泣く。
「え? なんで? どうした?」
――やっぱりなんかあったな
「すいません、俺、なんか、おかしくて、頭が、おかしいんです」
「よしよし、わかった。とにかく食おう」
加賀さんが俺の背中を撫でさすると、タイマーがパスタの茹で上がりを告げた。
温めなおしたソースをかけて、テーブルに置くと、向かい合って腰を下ろす。いただきますと手を合わせると、加賀さんがフォークにパスタを巻きつけながら、じっと俺を見てくる。
――ネガティブ、とは違うな
「はい、そうです」
「ん?」
「あ、いえ、なんでもないです」
つい、心の声に返事をしてしまった。目を落とし、パスタを口に運ぶ。
――頭がおかしいってどういう意味だ?
「あの、加賀さん、俺」
人の心が読めるようになったんです、とそのまま正直に言おうとして、ためらった。
種明かしする前に、試したいことがある。
「いえ、あの、美味しいですか?」
「うん、美味い」
――お前の料理はいつも美味いよ
「へへ」
にやける俺を、加賀さんが探るように見ている。
――なんか変だな
どうやら俺はわかりやすいらしい。
なるべくうつむいて、変なことを言わないように、妙な反応をしないように、無心で夕食を胃に詰め込んだ。その間の加賀さんの脳内はと言えば、「美味い」という誉め言葉と、「なんだ?」という疑問。それになぜかちょいちょい「可愛い」と「好き」を挟んでくるから、そのたびに顔が熱くなり、指が震えそうになった。
「加賀さん、お願いが」
食べ終わった食器をシンクに運ぶと、洗い物を開始しようとする加賀さんを止めた。
「何?」
「それは後回しにして、抱かせてくれませんか?」
「……はい?」
――いきなりどうした
「食後の軽い運動です」
「お、おう」
――本当に軽いのかよ
「大丈夫です、軽いです」
加賀さんの腰を抱き寄せて、首筋にキスをした。吸う。舐める。噛みつく。舌で耳たぶを転がしてから、耳を口中に含みながら、髪の中に指を差し入れた。
「ん……」
――やべえ、チンコ勃つ
勃ってもいいじゃないですか、と笑いそうになる。
「ちょっと、なあ、本当に今する?」
――食ったばっかだぞ。中身出たらどうすんだよ
ぐっ、と笑いを噛み殺す。笑ったら怪しまれる。堪えろ俺。
「今です。寝室行きます? それともここで?」
「寝室で」
即答した加賀さんの体を抱え上げて、寝室に飛び込んだ。ベッドに押し倒し、上から覗き込む。服の裾をめくり、手を入れる。丁寧に服を脱がせ、全裸にする。
「倉知君も脱いでよ」
――体、見たい
「わかりました」
勢いよく服を脱ぎ捨てた。加賀さんが、ふう、と短く息を吐く。
――めっちゃしたくなってきた
加賀さんの股間を確認した。すごく興奮してくれているのがわかる。愛しさが胸の内で倍増する。
「加賀さん、愛してます」
「うん、俺も」
――めちゃくちゃ愛してる
「抱いてもいいですか?」
「え? 今さら?」
「俺に抱かれたい?」
加賀さんが黙った。
――抱かれたいに決まってんだろ。なんでいちいち訊くんだ?
「よかった」
「何?」
「いえ、抱きます」
いつも以上に、優しく丁寧に扱った。
加賀さんの本音が聞きたくて、セックスを試したかった。
本当は嫌なんじゃないか。
本当は気持ちよくないんじゃないか。
俺に気を遣って、フリをしているんじゃないか。
馬鹿なことを考えた。
気持ちいい。
好き。
もっと。
七世、七世。
終わってみると、なんのことはない。嫌悪の瞬間など一度もなかった。本気で気持ちよくて、俺を好きでいてくれるのが痛いほど伝わった。
「加賀さん、俺、人の心が読めるようになったんです」
俺の上にまたがって、胸に頬をくっつけて体重を預けていた加賀さんが、「へえ」と気のない返事をした。
「疑ってますね?」
「え、超能力的な? 何、本気で言ってんの?」
「本気です。今から加賀さんが考えてること当ててみますから、なんでもいいから考えてください」
「なんでもいいの?」
「なんでもいいです。丸わかりですから。はい、どうぞ」
沈黙が落ちる。
静かだ。何も聞こえない。
おかしい。
もしやこれは、無の境地というやつか。
俺に心を読ませまいとして、無になっているに違いない。
「加賀さん、ちゃんと考えて」
「考えたよ?」
「え、本当に? 何も聞こえませんでしたよ」
「そりゃそうだよ、声に出してないからね」
「違うんです、俺、心が読めるから、言わなくても思うだけで」
「今めっちゃ心の中で叫んでるよ」
「えっ、嘘、何も聞こえない」
うろたえる俺の上で、加賀さんが笑い出した。
「信じてませんね?」
「いや、信じるよ。お前さっき、変だったもんな」
加賀さんはすごい。こんな馬鹿な話を簡単に信じてくれる。
「なんでいきなり聞こえなくなったんだろう」
「なんでいきなり聞こえるようになったんだろう、じゃない?」
加賀さんはおかしそうだ。
「あっ、セックスしたからかな?」
「ああ、射精したから? はは、うける」
「やっぱり信じてませんよね?」
「ていうかお前、俺が考えてることわかってたんだよな?」
「はい、帰ってきてからの頭の中、筒抜けでした」
そうだ、ちゃんと証明する方法があるじゃないか。
「嫌いな食べ物訊いたら、にんじんとかピーマンって言えば可愛いのかなって悩んでましたね」
「え」
「中身出たらどうするんだって、面白かったです」
「ちょ、待って、マジか」
加賀さんがようやく本気になってくれた。わたわたと、俺の上で体を起こす。
「えっ、あれ、待って、俺、なんか変なこと考えてなかった? やべえ、嘘だろ、なあ俺、恥ずかしいこと考えてなかった? 大丈夫?」
ものすごく可愛かったです。そしてうろたえる今の加賀さんも可愛いです。
ニヤニヤしながらあえて返事をしないでいると、加賀さんが殊勝な顔になり、俺を上目遣いで見て訊いた。
「エッチのとき、何考えてるか知りたかったとか?」
「そうですね、ちゃんと気持ちいいかなって。苦痛じゃないかなとか、嫌なことしてないかなって、確認です」
加賀さんが顔を覆う。
「すいません、なんか、あの、誘惑に勝てなくて」
「いいけど、あー、俺の頭ん中、ひどくなかった? ……幻滅した?」
俺の腹を指でつついてくる。
「すごく幸せでした。加賀さん、俺のこと大好きですよね」
加賀さんがホッとした様子で、肩で息をつく。
「当たり前だろ」
心が読めなくたって、わかる。
愛してる。
加賀さんが、優しく微笑んだ。
〈おわり〉
33
お気に入りに追加
530
あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

女装とメス調教をさせられ、担任だった教師の亡くなった奥さんの代わりをさせられる元教え子の男
湊戸アサギリ
BL
また女装メス調教です。見ていただきありがとうございます。
何も知らない息子視点です。今回はエロ無しです。他の作品もよろしくお願いします。

少年ペット契約
眠りん
BL
※少年売買契約のスピンオフ作品です。
↑上記作品を知らなくても読めます。
小山内文和は貧乏な家庭に育ち、教育上よろしくない環境にいながらも、幸せな生活を送っていた。
趣味は布団でゴロゴロする事。
ある日学校から帰ってくると、部屋はもぬけの殻、両親はいなくなっており、借金取りにやってきたヤクザの組員に人身売買で売られる事になってしまった。
文和を購入したのは堂島雪夜。四十二歳の優しい雰囲気のおじさんだ。
文和は雪夜の養子となり、学校に通ったり、本当の子供のように愛された。
文和同様人身売買で買われて、堂島の元で育ったアラサー家政婦の金井栞も、サバサバした性格だが、文和に親切だ。
三年程を堂島の家で、呑気に雪夜や栞とゴロゴロした生活を送っていたのだが、ある日雪夜が人身売買の罪で逮捕されてしまった。
文和はゴロゴロ生活を守る為、雪夜が出所するまでの間、ペットにしてくれる人を探す事にした。
※前作と違い、エロは最初の頃少しだけで、あとはほぼないです。
※前作がシリアスで暗かったので、今回は明るめでやってます。

少年野球で知り合ってやけに懐いてきた後輩のあえぎ声が頭から離れない
ベータヴィレッジ 現実沈殿村落
BL
少年野球で知り合い、やたら懐いてきた後輩がいた。
ある日、彼にちょっとしたイタズラをした。何気なく出したちょっかいだった。
だがそのときに発せられたあえぎ声が頭から離れなくなり、俺の行為はどんどんエスカレートしていく。


童貞が建設会社に就職したらメスにされちゃった
なる
BL
主人公の高梨優(男)は18歳で高校卒業後、小さな建設会社に就職した。しかし、そこはおじさんばかりの職場だった。
ストレスや性欲が溜まったおじさん達は、優にエッチな視線を浴びせ…
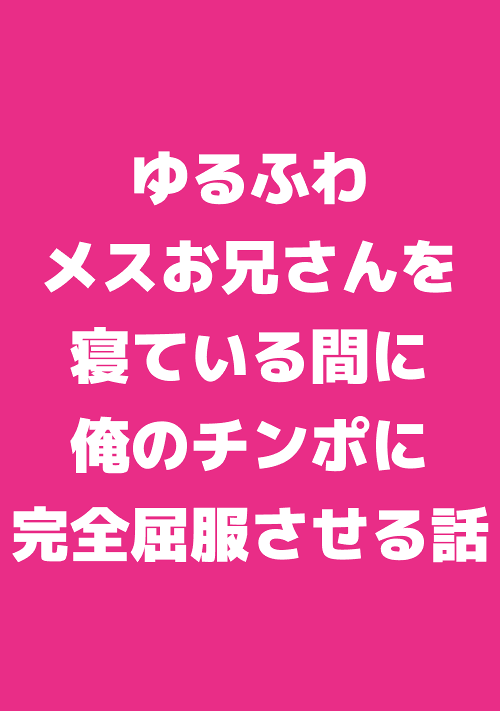
ゆるふわメスお兄さんを寝ている間に俺のチンポに完全屈服させる話
さくた
BL
攻め:浩介(こうすけ)
奏音とは大学の先輩後輩関係
受け:奏音(かなと)
同性と付き合うのは浩介が初めて
いつも以上に孕むだのなんだの言いまくってるし攻めのセリフにも♡がつく

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















