お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説



龍青学園GCSA
楓和
青春
学園都市の中にある学校の一つ、龍青学園。ここの中等部に、先生や生徒からの様々な依頼に対し、お金以外の報酬で請け負うお助け集団「GCSA」があった。
他学校とのスポーツ対決、謎の集団が絡む陰謀、大人の事情と子どもの事情…GCSAのリーダー「竜沢神侍」を中心に巻き起こる、ドタバタ青春ラブコメ爽快スポ根ストーリー。
※龍青学園GCSA 各話のちょっとした話しを書いた短編集「龍青学園GCSA -ぷち-」も宜しくお願い致します。
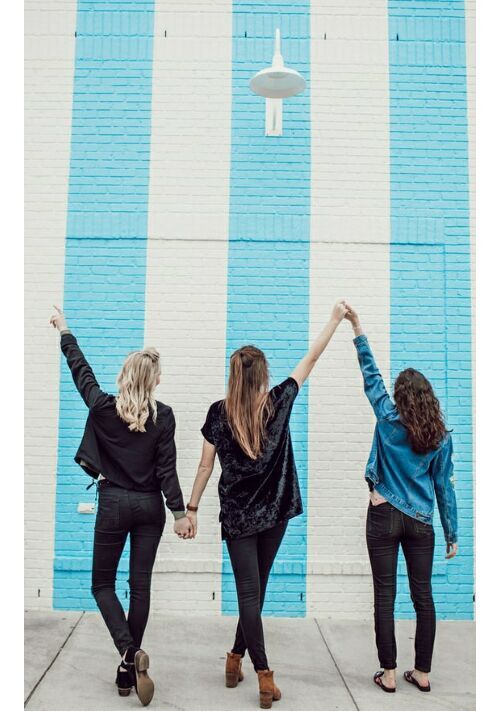
女子高生は小悪魔だ~教師のボクはこんな毎日送ってます
藤 ゆう
青春
ボクはある私立女子高の体育教師。大学をでて、初めての赴任だった。
「男子がいないからなぁ、ブリっ子もしないし、かなり地がでるぞ…おまえ食われるなよ(笑)」
先輩に聞いていたから少しは身構えていたけれど…
色んな(笑)事件がまきおこる。
どこもこんなものなのか?
新米のボクにはわからないけれど、ついにスタートした可愛い小悪魔たちとの毎日。


『器のちっちゃな、ふとちょ先輩』
小川敦人
青春
大学卒業後、スポーツジムで働き始めた蓮見吾一。彼は個性豊かな同僚たちに囲まれながら、仕事の楽しさと難しさを学んでいく。特に気分屋で繊細な「器の小さい」中田先輩に振り回される日々。ジム内の人間模様や恋愛模様が交錯しながらも、吾一は仲間との絆を深めていく。やがて訪れるイベントのトラブルを通じて、中田先輩の意外な一面が明らかになり、彼の成長を目の当たりにする。笑いあり、切なさありの職場青春ストーリー。

自称未来の妻なヤンデレ転校生に振り回された挙句、最終的に責任を取らされる話
水島紗鳥
青春
成績優秀でスポーツ万能な男子高校生の黒月拓馬は、学校では常に1人だった。
そんなハイスペックぼっちな拓馬の前に未来の妻を自称する日英ハーフの美少女転校生、十六夜アリスが現れた事で平穏だった日常生活が激変する。
凄まじくヤンデレなアリスは拓馬を自分だけの物にするためにありとあらゆる手段を取り、どんどん外堀を埋めていく。
「なあ、サインと判子欲しいって渡された紙が記入済婚姻届なのは気のせいか?」
「気にしない気にしない」
「いや、気にするに決まってるだろ」
ヤンデレなアリスから完全にロックオンされてしまった拓馬の運命はいかに……?(なお、もう一生逃げられない模様)
表紙はイラストレーターの谷川犬兎様に描いていただきました。
小説投稿サイトでの利用許可を頂いております。

転校して来た美少女が前幼なじみだった件。
ながしょー
青春
ある日のHR。担任の呼び声とともに教室に入ってきた子は、とてつもない美少女だった。この世とはかけ離れた美貌に、男子はおろか、女子すらも言葉を詰まらせ、何も声が出てこない模様。モデルでもやっていたのか?そんなことを思いながら、彼女の自己紹介などを聞いていると、担任の先生がふと、俺の方を……いや、隣の席を指差す。今朝から気になってはいたが、彼女のための席だったということに今知ったのだが……男子たちの目線が異様に悪意の籠ったものに感じるが気のせいか?とにもかくにも隣の席が学校一の美少女ということになったわけで……。
このときの俺はまだ気づいていなかった。この子を軸として俺の身の回りが修羅場と化すことに。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















