お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説


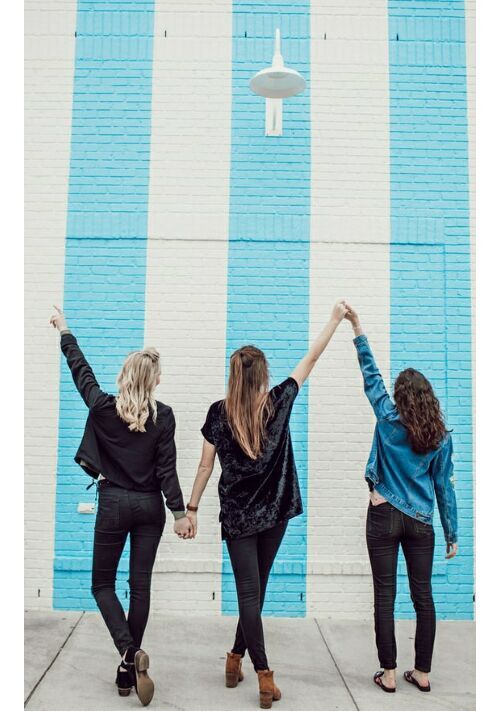
女子高生は小悪魔だ~教師のボクはこんな毎日送ってます
藤 ゆう
青春
ボクはある私立女子高の体育教師。大学をでて、初めての赴任だった。
「男子がいないからなぁ、ブリっ子もしないし、かなり地がでるぞ…おまえ食われるなよ(笑)」
先輩に聞いていたから少しは身構えていたけれど…
色んな(笑)事件がまきおこる。
どこもこんなものなのか?
新米のボクにはわからないけれど、ついにスタートした可愛い小悪魔たちとの毎日。

魔球オナラ球
ヨッシー@
青春
僕たちの青春は終わった。
カーン、
ボテ、ボテ、ボテ、
ゆる〜いボールが転がってくる。
学校のグランドの奥の奥。
パシッ、
一人の野球部員が、ボールを掴んで内野に投げる。
「ヘーイ」シュッ、
その背には、背番号は無い⋯⋯


三姉妹の姉達は、弟の俺に甘すぎる!
佐々木雄太
青春
四月——
新たに高校生になった有村敦也。
二つ隣町の高校に通う事になったのだが、
そこでは、予想外の出来事が起こった。
本来、いるはずのない同じ歳の三人の姉が、同じ教室にいた。
長女・唯【ゆい】
次女・里菜【りな】
三女・咲弥【さや】
この三人の姉に甘やかされる敦也にとって、
高校デビューするはずだった、初日。
敦也の高校三年間は、地獄の運命へと導かれるのであった。
カクヨム・小説家になろうでも好評連載中!

自称未来の妻なヤンデレ転校生に振り回された挙句、最終的に責任を取らされる話
水島紗鳥
青春
成績優秀でスポーツ万能な男子高校生の黒月拓馬は、学校では常に1人だった。
そんなハイスペックぼっちな拓馬の前に未来の妻を自称する日英ハーフの美少女転校生、十六夜アリスが現れた事で平穏だった日常生活が激変する。
凄まじくヤンデレなアリスは拓馬を自分だけの物にするためにありとあらゆる手段を取り、どんどん外堀を埋めていく。
「なあ、サインと判子欲しいって渡された紙が記入済婚姻届なのは気のせいか?」
「気にしない気にしない」
「いや、気にするに決まってるだろ」
ヤンデレなアリスから完全にロックオンされてしまった拓馬の運命はいかに……?(なお、もう一生逃げられない模様)
表紙はイラストレーターの谷川犬兎様に描いていただきました。
小説投稿サイトでの利用許可を頂いております。

龍青学園GCSA
楓和
青春
学園都市の中にある学校の一つ、龍青学園。ここの中等部に、先生や生徒からの様々な依頼に対し、お金以外の報酬で請け負うお助け集団「GCSA」があった。
他学校とのスポーツ対決、謎の集団が絡む陰謀、大人の事情と子どもの事情…GCSAのリーダー「竜沢神侍」を中心に巻き起こる、ドタバタ青春ラブコメ爽快スポ根ストーリー。
※龍青学園GCSA 各話のちょっとした話しを書いた短編集「龍青学園GCSA -ぷち-」も宜しくお願い致します。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















