112 / 170
【7】
君がいなくなった後で
しおりを挟む
蹴り上げる蹄の先から泥の飛沫が飛び散っているのが見える。粉袋のように乱暴に馬に乗せられたポルトは道標星を見上げることも出来ず、西へ向かっているのか東に向かっているのもわからなかった。
男達はポルト達の焚き火に辿り着く前に他の場所で仕事をしてきていたらしく、周りにいる他の馬の背にも見知らぬ荷物がいくつも積まれている。男達の身なりはその辺りの貧しい村民とさして変わりはない。典型的なゴロツキであるのだろうと察した。
シダやクランベリーの茂みを散らしながら一時間走った頃だろうか、小さな岩肌の前で馬の手綱が引かれた。風景に隠れるようにして開いていたのは馬が一頭入れるかどうか…という洞穴。男達は鞍から下ろした臀部の痛みや明日の天気のことなど他愛もない話をしながら、ゾロゾロとそこへ入っていった。
ポルトは身体をよじりながら周囲を見渡す。硬い岩盤の隙間から雑草がチラホラ顔を出す壁、そして湿気を帯びた土の臭いが強くした。所々に尖った石先はあるものの、足元は思っていたよりもなだらかだ。恐らく男たちが削って整えたのだろう。
狭いのは入り口だけだったようで、洞窟の中に入ると比較的広い通路が続き、道標のように点々と篝火が置いてある。奥は思っていたよりも開けていて、木箱や古いテーブルの上には沢山の荷物が乱雑に積んであった。
仕事に出てこなかった二人の男が頭領と仲間達を出迎える。
「よし、おめぇはこっちで大人しくしてろ」
「っ!」
そう言われ、強引に連れて行かれたのは荷物が山と積まれているテント、その支柱だ。比較的太い木で頑丈に作られていて、男はそこにポルトの手を縛り付けた。
若い男が片眉を歪ませながら見慣れぬ顔を睨む。
「親分、コイツなんですかぃ?どこでこんな小僧を?」
「ガキかもしれねぇが、女だとよ。こいつの兄貴が俺達に差し出して自分はトンズラこきやがったのさ」
「あっはっは!なんて腰抜けな野郎だ!俺達も相当のゲス野郎にゃ変わりねぇが、家族を…それも女を盾に使ったりはしねぇ!」
「しかも剣一本振らずによぉ!弱虫どころの話じゃねぇな!情けねぇっ!あーっはっはっは!!」
男たちは大笑いをしながら周りを取り囲む。その向こう側ではカールトンから奪ってきた荷物を並べ、ひとつひとつ手に取り品定めを始めていた。
荷物は黒パンやワイン、干し肉等、その殆が食料だ。そして替えのナイフが数本、砥石、ロープや調理道具がいくつか……。その中で男たちを一番喜ばせたのはズシリと重い革袋。大きさも男の掌に余るほどのものが二つもあった。目を輝かせた頭領がニヤけながら紐を解くと、汚れひとつ無い金貨と銀貨が顔を出し、湧いた男たちの野太い声が洞窟中に反響した。
「こりゃすげぇや!!王都に家が三つくらい買えるんじゃねぇか!?」
「娼館だ!!娼館を貸し切りにして、一週間はヤリまくってやる!!それもイイ女ばかり並べてなぁ!!」
ポルトはその様を驚いた様子で見ている。
平民は金貨を見ることすら稀。あれを一枚稼ぐのに家族が死に物狂いで働かなくてはならない程だというのに……。カールトンは何故あんな大金を持っているのだろうか。
(あれが…今回の依頼料ってこと……?)
国王の命を狙う程の首謀者。やはりカールトンの依頼主はかなりの有力者だったらしい。事件について彼からまだ何も聞けてはいないが、きっと自分でも顔がわかる位の人間の名が出てくるだろう。
「なぁ!お頭!!俺は酒が良い!!水で薄めてねぇ、濃いやつだ!貴族共が飲んでるような高級なワインを浴びながら飲みてぇぜ!」
「落ち着きやがれ、てめぇら!!分け前はくれてやる!その前に荷物を片付けやがれ!散らかし放題しやがって、足の踏み場もねぇ!!」
「この女はどうしましょうか?」
「そいつは今夜のお楽しみだ。おめぇらの好きにしろっ」
男たちの色づいた目が贄に注がれる。品性も理性もないその視線を、ポルトは睨みつけて返した。
◆◆◆
いくら探しても見つからなかった想い人が、じつは仕事仲間のポルトだと知ってから数日……。それは彼女が姿を消した日数と同じであった。隊で必死に探してた指輪は見つかったものの、ローガンの表情は前より一層暗い。
北牢にいたフォルカー王子は『侵入者がポルトを連れて行った』と話していた。しかし、その反応はあまりにも冷静…いや冷淡と言ってもいい程で、違和感を禁じ得ない。ロイター卿の時には鉄拳制裁をするほどの怒りを見せていたというのに、この差は一体……?
意図しない別れに動揺しているのだろうか?それとも他に何か言えない理由でもあったとか?
何にせよ、こんな形で彼女と分かれることになるとは思っていなかったのは自分も一緒だ。
晴れない胸中のまま作業用の服装に着替えると、一人で狼小屋へと顔を出す。
ポルトの不在で穴が空いた狼達の世話係を、臨時で担当することになった。
北牢に囚われる直前、ポルトから二匹の面倒を頼まれていたし、それ自体は構わない。人目を気にせず狼達と触れ合えるのは好機以外の何物でもない。しかし狼小屋ではひとつ問題が起きていた。
落ち着いた性格で誰をも惹き付ける白い毛の狼カロン、そして茶目っ気のある性格で遊び好きな黒い毛の狼シーザー。二匹とも暴れることもなく脱走することもなくちゃんと小屋の中にはいたが、こちらの声には一切応えることはない。いや、それどころか白狼のカロンはこちらの顔を見るやいなや白い歯を見せうなり始めるのだ。
もう何度も顔を合わせ、おやつだって時々手から食べてくれていた程の関係だったのに……。
(ポルトに手枷をつけた所を見ていたせいか?それとも…俺がポルトを連れ去った悪いやつの仲間だと思われたのか……)
どちらにせよ間違いではない。その事実は肩を落とさせる。間違いなく…嫌われてしまった……。
嫌われてしまったといえば、ポルトを連れて北国スキュラドへ逃げる計画も、本人が居なくなってしまったので中止になった。国を捨てる覚悟だったが…なんだか肩透かしを食らった気分だ。
見知らぬ土地で彼女と一緒にいる未来を何度か夢に見ていたが、本当に夢のまま終わってしまったらしい。
落ち込んでいるのは狼達も一緒なのだろう。ポルトが捕らえられて以来、すっかり食欲がなくなってしまい、与えた餌もその殆どを残している。最初はカロンだけだったのに、ポルトと離れている時間が増えるにつれてシーザーの食欲まで落ちてしまった。
高級な犬用おやつを持ってきても、使用人に頼んで新鮮な肉を分けて貰っても結果は変わらない。寝床に丸くなって、ただ寒さに耐えるような日を過ごしている。せめてゆっくり休めるようにと新しい藁や私邸から運ばせたクッション、そしてブランケットを側に置いてやったが、もれなく寝床の外へと放り出されてしまった。
やはり慣れない男の臭いがついているものでは駄目だったか……。
今日も二匹は寝床に丸くなったまま。動くにしても、こちらが近づいた時に唸るくらいだ。その様子にローガンは胸を痛めていた。自分の無力さを痛感する。
「せめて…フォルカー殿下がここに来てくれたらなぁ……」
彼らも少しは慰められるかもしれない。
しかし今の二匹を捕まえて城まで連れていける猛者はいない。いっそポルトの部屋からシーツの一枚でも持ってくることができれば…なんて考えていると、ふいに声をかけれた。
「――俺に何か用でもあるのか?」
「っ!?」
それは開けていた窓から。驚いて目を向けるとその人が戸板が開いている窓の縁に頬杖をついている。
王家の血を引く者の証、赤いルビーレッドの髪が陽に透けて輝く。
「フォ…フォルカー殿下……!?」
「――……」
エメラルドの瞳が狼達を見つめた。その姿、臭い、声で誰が来たのかはわかっているはずだ。しかしシーザーが首を少し持ち上げた程度で、反応は薄い。
「殿下…どうしてこちらに?今は会議中では……?」
「来年度の予算のことで『ウルム大聖堂に金をかけすぎだ』って大臣に追いかけられちまってな。城は最近声をかけてくる女が増えて落ち着かねぇし、面倒だからこっちに避難してきた」
「あ・あぁ……、なるほど……」
ポルトの小言が増える理由がわかる。
フォルカーは袖についた埃を軽く払いながら小屋の中へと入り、中を見回した。室内はあの者がいた頃と然程変化もないように思える。わかりやすく変わったと言えば……丸い個体と化してるこの二匹だろう。彼らの側に寄ると、厚い冬毛の中に手を埋めて撫でた。
「……元気が無いって言ってたけど、本当みたいだな」
「……はい……」
「飯は食ってるのか?」
「全くという程ではないのですが…そうですね、あまり食欲はないみたいで……」
「――……」
しばらく見ない間に随分と毛並みがゴワゴワになった。十分なブラッシングをされていないせいだろう。よく見れば毛艶も良いとは思えない。比較的慣れていたローガンですらこの状況なのだから仕方ない。「ブラシを」、そう言って彼から愛用の犬用ブラシを受け取ると、ゆっくりと毛をとかしはじめた。
「殿下…このままでは彼らの体力が衰えて何かの病にかかってしまうかもしれません。この寒さから身を守ることだって出来なくなるかもしれない。原因はポルトです。私が言うまでもないことだとはわかっていますが……。彼が…いや、彼女が居なくなったからこの子達は……。今からでもポルトを捜索に……」
「駄目だ。誰もあいつを追いかけることは許さん。勿論お前もだ」
「――……」
「つか、今お前が居なくなったら一番困るのはコイツらだぞ」
フォルカーの視線が狼達に向けられる。
「はい……」
フォルカーの持つブラシが狼の鼻筋から丸い頭へ、そして胴から尻尾まで……、簡単ではあるが白い毛並みを整えていく。久しぶりのふれあいにカロンも嬉しかったのだろう、今まで反応が無かった尻尾がゆっくりと左右に揺れた。
「お前に…ひとつ言いたいことがある」
フォルカーはカロンの寝顔を見ながら視線を上げることもない。しかし、その意識が自分にしっかりと向けられていることをローガンは察する。
「……?はい、いかがされましたか?」
今の提案…もしかして彼にとって口にしてはいけないものだったのだろうか?ローガンがゴクリと唾を飲む。
「あいつが…北棟で拷問官が呼ばれたって……。お前、知らせに来ただろ」
「――……」
「俺はその話を聞かされていなかった。陛下に伏せられていたんだろうな。……そうだろ?」
ローガンは口をつぐんだまま俯いた。王子の言うとおりだ。ポルトが牢の中でどうしているのか、どんな取り調べが行われているのかは口外しないように…特に王子には詳細を知らせていはならないと陛下から命じられていた。その理由は聞くまでもない。
ローガンはその場に膝を折り、深く深く頭を下げた。
「大変…申し訳ありません……!」
「いや、良い。陛下の命令じゃ仕方ない。俺が言いたいのはそこじゃねぇんだ」
「?」
それは何か?と問うようにローガンは顔を上げる。
「……お前がどんな思いで部屋に駆け込んで来たのか…わからない俺じゃないさ」
「――……」
「………助けられなくて、悪かったな」
「……っ」
ローガンの想いが何処に在るのかなど今更聞くまでもない。
感情的に行動を起こす者なら、成功の可能性を考えることもなく自ら飛び込んで行ったことだろう。しかしローガンは理性的に行動をした。より確実に彼女を救出できる手段をとったのだ。
男としてのプライドを抑え込んで、他の男に…それも恋敵とも言える相手に助けを求めた。
己の弱さを知り、受け入れる事ができる者は多くない。ローガンの行為は尊敬に値するものであり、同じ男として、同じ女を愛した男として…その思いに報いることが出来なかったことに、フォルカーは少なからず後ろめたさを感じていた。
「いえ……!そんな……!!殿下がお気にされるようなことは何も……っ」
「――……。俺がお前に聞いてほしかっただけかもしれねぇけどな」
フォルカーの表情を心配そうに見上げたシーザーにも、同じようにブラシをかける。そしてその額に唇を押し付けキスをする。「犬臭ぇ」、口ではそうは言っていたものの、エメラルドの目元は穏やかに下がりシーザーも嬉しそうに舌を出した。
「ほれ。お前らに良いもんやるよ」
フォルカーは懐から白い布を取り出した。
それは細い長い無地の布で、少しくたびれているようにも見えるが……。
「殿下、それは…?」
「秘密兵器」
「!」
カロンの黒い鼻先にそれを持っていくと、静かだった目が大きく開く。フンフンフンと次第に荒くなる鼻息。「ワンッ」と一声上げると、哀しいような甘えるような高い声をあげながら身体を何度もこすりつけた。シーザーも同じ様な叫び声をあげた後、室内をグルグルと走り回り、また布の匂いを嗅いでは鳴き騒ぎ走り回るという行動を繰り返す。
二匹の異変にローガンはただ驚くばかりだ。
「こ・こんなに活動的な二匹は初めて見ます。殿下、これは一体……」
「ポチが巻いてたさらし」
「!?」
「……なんか変な薬みてぇになっちまったな……」
呆れ気味のフォルカーの隣で、ローガンは目を真っ赤にして今にも泣き出しそうな顔……。
本当にこの二匹は賢いワンコ(狼)で、ポルトが精一杯注いだ愛情がちゃんと伝わっているのだと痛感する。飼い主から引き離されたワンコ(狼)の姿はいつだって胸をきつくきつく締め付け、目元を熱くさせるのだ。
「……っ!」
堪えきれず思わず口元を手で押さえた。
人間ならまだ言葉で理解させることも出来るだろう。でも、動物にはそれが出来ない。
突然いなくなった大切な人を恋しがり、心配しているのだ。会えなくて…寂しくて……、きっと彼らもこの太く強い足で駆け出して探しに行きたいに違いない。
もしかしたら、「ポルトと仲が良かったくせに何で探しに行かないんだ!」と、カロンは怒って牙を向いてきたのかもしれない。
(そうだ……。だって…カロンの前でポルトは抱きついてきたんだから……。カロンはちゃんとわかってるんだ……。それなのに…それなのに……!俺という男はなんと不甲斐ない……!)
狼を前にローガン目にキラリと光る涙。
「おい、ローガン……。まさかお前まで変なことになっちまうなんてことねーよな……?」
「殿下……、犬とはなんと情深き生き物なのでしょうか……。人も狼も同じ神から生まれたというのに、彼ら程の純粋な気持ちを…一体何処に落としてきてしまったのでしょう……」
いつも一緒に犬の話をしていた彼女。
一体何処で何をしているのか……。ローガンはただ、彼らと共に彼女が無事でいることを祈ることしか出来なかった。
男達はポルト達の焚き火に辿り着く前に他の場所で仕事をしてきていたらしく、周りにいる他の馬の背にも見知らぬ荷物がいくつも積まれている。男達の身なりはその辺りの貧しい村民とさして変わりはない。典型的なゴロツキであるのだろうと察した。
シダやクランベリーの茂みを散らしながら一時間走った頃だろうか、小さな岩肌の前で馬の手綱が引かれた。風景に隠れるようにして開いていたのは馬が一頭入れるかどうか…という洞穴。男達は鞍から下ろした臀部の痛みや明日の天気のことなど他愛もない話をしながら、ゾロゾロとそこへ入っていった。
ポルトは身体をよじりながら周囲を見渡す。硬い岩盤の隙間から雑草がチラホラ顔を出す壁、そして湿気を帯びた土の臭いが強くした。所々に尖った石先はあるものの、足元は思っていたよりもなだらかだ。恐らく男たちが削って整えたのだろう。
狭いのは入り口だけだったようで、洞窟の中に入ると比較的広い通路が続き、道標のように点々と篝火が置いてある。奥は思っていたよりも開けていて、木箱や古いテーブルの上には沢山の荷物が乱雑に積んであった。
仕事に出てこなかった二人の男が頭領と仲間達を出迎える。
「よし、おめぇはこっちで大人しくしてろ」
「っ!」
そう言われ、強引に連れて行かれたのは荷物が山と積まれているテント、その支柱だ。比較的太い木で頑丈に作られていて、男はそこにポルトの手を縛り付けた。
若い男が片眉を歪ませながら見慣れぬ顔を睨む。
「親分、コイツなんですかぃ?どこでこんな小僧を?」
「ガキかもしれねぇが、女だとよ。こいつの兄貴が俺達に差し出して自分はトンズラこきやがったのさ」
「あっはっは!なんて腰抜けな野郎だ!俺達も相当のゲス野郎にゃ変わりねぇが、家族を…それも女を盾に使ったりはしねぇ!」
「しかも剣一本振らずによぉ!弱虫どころの話じゃねぇな!情けねぇっ!あーっはっはっは!!」
男たちは大笑いをしながら周りを取り囲む。その向こう側ではカールトンから奪ってきた荷物を並べ、ひとつひとつ手に取り品定めを始めていた。
荷物は黒パンやワイン、干し肉等、その殆が食料だ。そして替えのナイフが数本、砥石、ロープや調理道具がいくつか……。その中で男たちを一番喜ばせたのはズシリと重い革袋。大きさも男の掌に余るほどのものが二つもあった。目を輝かせた頭領がニヤけながら紐を解くと、汚れひとつ無い金貨と銀貨が顔を出し、湧いた男たちの野太い声が洞窟中に反響した。
「こりゃすげぇや!!王都に家が三つくらい買えるんじゃねぇか!?」
「娼館だ!!娼館を貸し切りにして、一週間はヤリまくってやる!!それもイイ女ばかり並べてなぁ!!」
ポルトはその様を驚いた様子で見ている。
平民は金貨を見ることすら稀。あれを一枚稼ぐのに家族が死に物狂いで働かなくてはならない程だというのに……。カールトンは何故あんな大金を持っているのだろうか。
(あれが…今回の依頼料ってこと……?)
国王の命を狙う程の首謀者。やはりカールトンの依頼主はかなりの有力者だったらしい。事件について彼からまだ何も聞けてはいないが、きっと自分でも顔がわかる位の人間の名が出てくるだろう。
「なぁ!お頭!!俺は酒が良い!!水で薄めてねぇ、濃いやつだ!貴族共が飲んでるような高級なワインを浴びながら飲みてぇぜ!」
「落ち着きやがれ、てめぇら!!分け前はくれてやる!その前に荷物を片付けやがれ!散らかし放題しやがって、足の踏み場もねぇ!!」
「この女はどうしましょうか?」
「そいつは今夜のお楽しみだ。おめぇらの好きにしろっ」
男たちの色づいた目が贄に注がれる。品性も理性もないその視線を、ポルトは睨みつけて返した。
◆◆◆
いくら探しても見つからなかった想い人が、じつは仕事仲間のポルトだと知ってから数日……。それは彼女が姿を消した日数と同じであった。隊で必死に探してた指輪は見つかったものの、ローガンの表情は前より一層暗い。
北牢にいたフォルカー王子は『侵入者がポルトを連れて行った』と話していた。しかし、その反応はあまりにも冷静…いや冷淡と言ってもいい程で、違和感を禁じ得ない。ロイター卿の時には鉄拳制裁をするほどの怒りを見せていたというのに、この差は一体……?
意図しない別れに動揺しているのだろうか?それとも他に何か言えない理由でもあったとか?
何にせよ、こんな形で彼女と分かれることになるとは思っていなかったのは自分も一緒だ。
晴れない胸中のまま作業用の服装に着替えると、一人で狼小屋へと顔を出す。
ポルトの不在で穴が空いた狼達の世話係を、臨時で担当することになった。
北牢に囚われる直前、ポルトから二匹の面倒を頼まれていたし、それ自体は構わない。人目を気にせず狼達と触れ合えるのは好機以外の何物でもない。しかし狼小屋ではひとつ問題が起きていた。
落ち着いた性格で誰をも惹き付ける白い毛の狼カロン、そして茶目っ気のある性格で遊び好きな黒い毛の狼シーザー。二匹とも暴れることもなく脱走することもなくちゃんと小屋の中にはいたが、こちらの声には一切応えることはない。いや、それどころか白狼のカロンはこちらの顔を見るやいなや白い歯を見せうなり始めるのだ。
もう何度も顔を合わせ、おやつだって時々手から食べてくれていた程の関係だったのに……。
(ポルトに手枷をつけた所を見ていたせいか?それとも…俺がポルトを連れ去った悪いやつの仲間だと思われたのか……)
どちらにせよ間違いではない。その事実は肩を落とさせる。間違いなく…嫌われてしまった……。
嫌われてしまったといえば、ポルトを連れて北国スキュラドへ逃げる計画も、本人が居なくなってしまったので中止になった。国を捨てる覚悟だったが…なんだか肩透かしを食らった気分だ。
見知らぬ土地で彼女と一緒にいる未来を何度か夢に見ていたが、本当に夢のまま終わってしまったらしい。
落ち込んでいるのは狼達も一緒なのだろう。ポルトが捕らえられて以来、すっかり食欲がなくなってしまい、与えた餌もその殆どを残している。最初はカロンだけだったのに、ポルトと離れている時間が増えるにつれてシーザーの食欲まで落ちてしまった。
高級な犬用おやつを持ってきても、使用人に頼んで新鮮な肉を分けて貰っても結果は変わらない。寝床に丸くなって、ただ寒さに耐えるような日を過ごしている。せめてゆっくり休めるようにと新しい藁や私邸から運ばせたクッション、そしてブランケットを側に置いてやったが、もれなく寝床の外へと放り出されてしまった。
やはり慣れない男の臭いがついているものでは駄目だったか……。
今日も二匹は寝床に丸くなったまま。動くにしても、こちらが近づいた時に唸るくらいだ。その様子にローガンは胸を痛めていた。自分の無力さを痛感する。
「せめて…フォルカー殿下がここに来てくれたらなぁ……」
彼らも少しは慰められるかもしれない。
しかし今の二匹を捕まえて城まで連れていける猛者はいない。いっそポルトの部屋からシーツの一枚でも持ってくることができれば…なんて考えていると、ふいに声をかけれた。
「――俺に何か用でもあるのか?」
「っ!?」
それは開けていた窓から。驚いて目を向けるとその人が戸板が開いている窓の縁に頬杖をついている。
王家の血を引く者の証、赤いルビーレッドの髪が陽に透けて輝く。
「フォ…フォルカー殿下……!?」
「――……」
エメラルドの瞳が狼達を見つめた。その姿、臭い、声で誰が来たのかはわかっているはずだ。しかしシーザーが首を少し持ち上げた程度で、反応は薄い。
「殿下…どうしてこちらに?今は会議中では……?」
「来年度の予算のことで『ウルム大聖堂に金をかけすぎだ』って大臣に追いかけられちまってな。城は最近声をかけてくる女が増えて落ち着かねぇし、面倒だからこっちに避難してきた」
「あ・あぁ……、なるほど……」
ポルトの小言が増える理由がわかる。
フォルカーは袖についた埃を軽く払いながら小屋の中へと入り、中を見回した。室内はあの者がいた頃と然程変化もないように思える。わかりやすく変わったと言えば……丸い個体と化してるこの二匹だろう。彼らの側に寄ると、厚い冬毛の中に手を埋めて撫でた。
「……元気が無いって言ってたけど、本当みたいだな」
「……はい……」
「飯は食ってるのか?」
「全くという程ではないのですが…そうですね、あまり食欲はないみたいで……」
「――……」
しばらく見ない間に随分と毛並みがゴワゴワになった。十分なブラッシングをされていないせいだろう。よく見れば毛艶も良いとは思えない。比較的慣れていたローガンですらこの状況なのだから仕方ない。「ブラシを」、そう言って彼から愛用の犬用ブラシを受け取ると、ゆっくりと毛をとかしはじめた。
「殿下…このままでは彼らの体力が衰えて何かの病にかかってしまうかもしれません。この寒さから身を守ることだって出来なくなるかもしれない。原因はポルトです。私が言うまでもないことだとはわかっていますが……。彼が…いや、彼女が居なくなったからこの子達は……。今からでもポルトを捜索に……」
「駄目だ。誰もあいつを追いかけることは許さん。勿論お前もだ」
「――……」
「つか、今お前が居なくなったら一番困るのはコイツらだぞ」
フォルカーの視線が狼達に向けられる。
「はい……」
フォルカーの持つブラシが狼の鼻筋から丸い頭へ、そして胴から尻尾まで……、簡単ではあるが白い毛並みを整えていく。久しぶりのふれあいにカロンも嬉しかったのだろう、今まで反応が無かった尻尾がゆっくりと左右に揺れた。
「お前に…ひとつ言いたいことがある」
フォルカーはカロンの寝顔を見ながら視線を上げることもない。しかし、その意識が自分にしっかりと向けられていることをローガンは察する。
「……?はい、いかがされましたか?」
今の提案…もしかして彼にとって口にしてはいけないものだったのだろうか?ローガンがゴクリと唾を飲む。
「あいつが…北棟で拷問官が呼ばれたって……。お前、知らせに来ただろ」
「――……」
「俺はその話を聞かされていなかった。陛下に伏せられていたんだろうな。……そうだろ?」
ローガンは口をつぐんだまま俯いた。王子の言うとおりだ。ポルトが牢の中でどうしているのか、どんな取り調べが行われているのかは口外しないように…特に王子には詳細を知らせていはならないと陛下から命じられていた。その理由は聞くまでもない。
ローガンはその場に膝を折り、深く深く頭を下げた。
「大変…申し訳ありません……!」
「いや、良い。陛下の命令じゃ仕方ない。俺が言いたいのはそこじゃねぇんだ」
「?」
それは何か?と問うようにローガンは顔を上げる。
「……お前がどんな思いで部屋に駆け込んで来たのか…わからない俺じゃないさ」
「――……」
「………助けられなくて、悪かったな」
「……っ」
ローガンの想いが何処に在るのかなど今更聞くまでもない。
感情的に行動を起こす者なら、成功の可能性を考えることもなく自ら飛び込んで行ったことだろう。しかしローガンは理性的に行動をした。より確実に彼女を救出できる手段をとったのだ。
男としてのプライドを抑え込んで、他の男に…それも恋敵とも言える相手に助けを求めた。
己の弱さを知り、受け入れる事ができる者は多くない。ローガンの行為は尊敬に値するものであり、同じ男として、同じ女を愛した男として…その思いに報いることが出来なかったことに、フォルカーは少なからず後ろめたさを感じていた。
「いえ……!そんな……!!殿下がお気にされるようなことは何も……っ」
「――……。俺がお前に聞いてほしかっただけかもしれねぇけどな」
フォルカーの表情を心配そうに見上げたシーザーにも、同じようにブラシをかける。そしてその額に唇を押し付けキスをする。「犬臭ぇ」、口ではそうは言っていたものの、エメラルドの目元は穏やかに下がりシーザーも嬉しそうに舌を出した。
「ほれ。お前らに良いもんやるよ」
フォルカーは懐から白い布を取り出した。
それは細い長い無地の布で、少しくたびれているようにも見えるが……。
「殿下、それは…?」
「秘密兵器」
「!」
カロンの黒い鼻先にそれを持っていくと、静かだった目が大きく開く。フンフンフンと次第に荒くなる鼻息。「ワンッ」と一声上げると、哀しいような甘えるような高い声をあげながら身体を何度もこすりつけた。シーザーも同じ様な叫び声をあげた後、室内をグルグルと走り回り、また布の匂いを嗅いでは鳴き騒ぎ走り回るという行動を繰り返す。
二匹の異変にローガンはただ驚くばかりだ。
「こ・こんなに活動的な二匹は初めて見ます。殿下、これは一体……」
「ポチが巻いてたさらし」
「!?」
「……なんか変な薬みてぇになっちまったな……」
呆れ気味のフォルカーの隣で、ローガンは目を真っ赤にして今にも泣き出しそうな顔……。
本当にこの二匹は賢いワンコ(狼)で、ポルトが精一杯注いだ愛情がちゃんと伝わっているのだと痛感する。飼い主から引き離されたワンコ(狼)の姿はいつだって胸をきつくきつく締め付け、目元を熱くさせるのだ。
「……っ!」
堪えきれず思わず口元を手で押さえた。
人間ならまだ言葉で理解させることも出来るだろう。でも、動物にはそれが出来ない。
突然いなくなった大切な人を恋しがり、心配しているのだ。会えなくて…寂しくて……、きっと彼らもこの太く強い足で駆け出して探しに行きたいに違いない。
もしかしたら、「ポルトと仲が良かったくせに何で探しに行かないんだ!」と、カロンは怒って牙を向いてきたのかもしれない。
(そうだ……。だって…カロンの前でポルトは抱きついてきたんだから……。カロンはちゃんとわかってるんだ……。それなのに…それなのに……!俺という男はなんと不甲斐ない……!)
狼を前にローガン目にキラリと光る涙。
「おい、ローガン……。まさかお前まで変なことになっちまうなんてことねーよな……?」
「殿下……、犬とはなんと情深き生き物なのでしょうか……。人も狼も同じ神から生まれたというのに、彼ら程の純粋な気持ちを…一体何処に落としてきてしまったのでしょう……」
いつも一緒に犬の話をしていた彼女。
一体何処で何をしているのか……。ローガンはただ、彼らと共に彼女が無事でいることを祈ることしか出来なかった。
0
お気に入りに追加
2,265
あなたにおすすめの小説

【完結】お飾りの妻からの挑戦状
おのまとぺ
恋愛
公爵家から王家へと嫁いできたデイジー・シャトワーズ。待ちに待った旦那様との顔合わせ、王太子セオドア・ハミルトンが放った言葉に立ち会った使用人たちの顔は強張った。
「君はお飾りの妻だ。装飾品として慎ましく生きろ」
しかし、当のデイジーは不躾な挨拶を笑顔で受け止める。二人のドタバタ生活は心配する周囲を巻き込んで、やがて誰も予想しなかった展開へ……
◇表紙はノーコピーライトガール様より拝借しています
◇全18話で完結予定


アルバートの屈辱
プラネットプラント
恋愛
妻の姉に恋をして妻を蔑ろにするアルバートとそんな夫を愛するのを諦めてしまった妻の話。
『詰んでる不憫系悪役令嬢はチャラ男騎士として生活しています』の10年ほど前の話ですが、ほぼ無関係なので単体で読めます。


愛することをやめたら、怒る必要もなくなりました。今さら私を愛する振りなんて、していただかなくても大丈夫です。
石河 翠
恋愛
貴族令嬢でありながら、家族に虐げられて育ったアイビー。彼女は社交界でも人気者の恋多き侯爵エリックに望まれて、彼の妻となった。
ひとなみに愛される生活を夢見たものの、彼が欲していたのは、夫に従順で、家の中を取り仕切る女主人のみ。先妻の子どもと仲良くできない彼女をエリックは疎み、なじる。
それでもエリックを愛し、結婚生活にしがみついていたアイビーだが、彼の子どもに言われたたった一言で心が折れてしまう。ところが、愛することを止めてしまえばその生活は以前よりも穏やかで心地いいものになっていて……。
愛することをやめた途端に愛を囁くようになったヒーローと、その愛をやんわりと拒むヒロインのお話。
この作品は他サイトにも投稿しております。
扉絵は、写真ACよりチョコラテさまの作品(写真ID 179331)をお借りしております。

絶対に間違えないから
mahiro
恋愛
あれは事故だった。
けれど、その場には彼女と仲の悪かった私がおり、日頃の行いの悪さのせいで彼女を階段から突き落とした犯人は私だと誰もが思ったーーー私の初恋であった貴方さえも。
だから、貴方は彼女を失うことになった私を許さず、私を死へ追いやった………はずだった。
何故か私はあのときの記憶を持ったまま6歳の頃の私に戻ってきたのだ。
どうして戻ってこれたのか分からないが、このチャンスを逃すわけにはいかない。
私はもう彼らとは出会わず、日頃の行いの悪さを見直し、平穏な生活を目指す!そう決めたはずなのに...……。
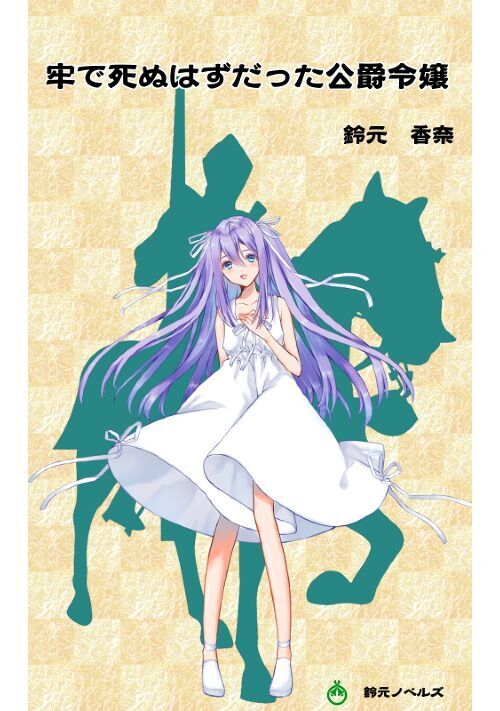
牢で死ぬはずだった公爵令嬢
鈴元 香奈
恋愛
婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。
表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。
小説家になろうさんにも投稿しています。

【改稿版・完結】その瞳に魅入られて
おもち。
恋愛
「——君を愛してる」
そう悲鳴にも似た心からの叫びは、婚約者である私に向けたものではない。私の従姉妹へ向けられたものだった——
幼い頃に交わした婚約だったけれど私は彼を愛してたし、彼に愛されていると思っていた。
あの日、二人の胸を引き裂くような思いを聞くまでは……
『最初から愛されていなかった』
その事実に心が悲鳴を上げ、目の前が真っ白になった。
私は愛し合っている二人を引き裂く『邪魔者』でしかないのだと、その光景を見ながらひたすら現実を受け入れるしかなかった。
『このまま婚姻を結んでも、私は一生愛されない』
『私も一度でいいから、あんな風に愛されたい』
でも貴族令嬢である立場が、父が、それを許してはくれない。
必死で気持ちに蓋をして、淡々と日々を過ごしていたある日。偶然見つけた一冊の本によって、私の運命は大きく変わっていくのだった。
私も、貴方達のように自分の幸せを求めても許されますか……?
※後半、壊れてる人が登場します。苦手な方はご注意下さい。
※このお話は私独自の設定もあります、ご了承ください。ご都合主義な場面も多々あるかと思います。
※『幸せは人それぞれ』と、いうような作品になっています。苦手な方はご注意下さい。
※こちらの作品は小説家になろう様でも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















