30 / 46
第八章
第八章 第二話
しおりを挟む
「向こうは陪臣だし、うちは小普請組だからイカだと思ったのかもね」
『陪臣』とは直接の家臣ではないと言う意味なので、例えば大名家の家臣が雇っている家臣も大名から見たら陪臣だし、大名の家臣でも他の大名から見たら陪臣である。
つまり陪臣とは自分の直接の家臣ではない者を指す。
ちなみに旗本が出世して石高が一万石を超えると大名となり直参とは呼ばれなくなるが、領地を子供達に分割して譲ったりして一万石以下になると旗本に戻る。
柳生宗矩は旗本から出世して一万二千五百石の大名となったが三人の息子に領地を分割して譲ったので一万石以下になったので柳生家は旗本に戻り、その後、宗冬の代でまた一万石以上になって大名に復帰している。
牢人は誰の家臣でもないので、大名とは別の意味で直参でも陪臣でもない。
ふと、花月が考え込むような表情になった。
「どうかしたか?」
「もしかしたら若様が公方様に拝謁する前に次丸様を跡継ぎにしたいのかも」
将軍は忙しいので大名や旗本の子息が元服する度に一々謁見などしていられない。
そのため旗本や小藩の大名の子息への謁見は一括して行われる。
大勢を集めたところに将軍が来てまとめて謁見するのだ。
直参でも御目見得以下の者や陪臣、牢人などはそれすら叶わないから光夜には無縁の話なので拝謁済みかどうかで何が違うのかよく分からないが。
「光夜、諱は考えたか」
夜、学問を教わるために居間へ行くと弦之丞が訊ねてきた。
「いえ、まだ……」
そういや考えとけって言われてたな……。
ササゲ豆が届くまでに思い付かなければ三厳にされかねない。
「では、この中から選ぶと良いだろう」
弦之丞が光夜に紙を渡した。
「私もいくつか書き出してみた」
宗祐もそう言って紙を出した。
「流石お父様とお兄様!」
紙を覗き込んだ花月が、はしゃいだ声を上げる。
えっ……。
なんか嫌な予感が……。
再度紙に目を落とすと弦之丞と宗祐が書き出したものは重複しているものが多かった。
しかも、いくつか聞き覚えのある名前が……。
「この名前って……」
「全員名だたる剣豪よ」
花月がにこやかに答えた。
やっぱり……。
てことは義輝って、もしかしなくても足利将軍……。
牢人風情が付けて良い名前じゃねぇだろ……!
「本当は宗祐も剣豪にあやかった名前にしたかったのだが、うちの通字である紘の字を使っている剣豪が見付からなくてな」
弦之丞の表情も声音もいつもと変わらないが無念さは十分に伝わってきた。
花月の剣豪好きは師匠の影響か……。
てか、若先生も……。
『通字』というのは一族で共通して使う字である。
武士の名前が似通っているのは通字を使うことが多いためである。
一族に通字がある場合、もう一字は既に居る者と被らないように避けた。
これを『偏諱』と言う。
徳川家なら『家』が通字で、『家康』の『康』が偏諱である。
家康以降は同じ『家康』という名前にならないように『康』の字が避けられた。
『光』なども同様に偏諱である。
『綱吉』の場合、兄の『家綱』が通字である『家』の字を使い、弟の綱吉は兄・家綱から偏諱である『綱』の字を賜ったから『綱吉』となった。
つまり『宗』が通字だったら若先生は宗厳か宗矩だったかもしれないのか……。
いくら滅多に使わないとは言え秘密ではないのだ。
そっと様子を窺うと花月が期待に満ちた表情で紙の一点を凝視している。
〝三厳〟
そうか、目上の者なら下の者を諱で呼べる。
つまり光夜の諱が『三厳』にした場合、花月は堂々と呼べるのだ。
町人ならいざ知らず、武士で三厳が柳生十兵衛の諱だと知らない者はいないだろう。
花月には悪いが人前で『三厳』などと呼ばれるのは御免被る。
しかし、ここには剣豪の名前しか書いてない。
弦之丞も宗祐も揃って剣豪の名前だけしか書いてこなかったのだから二人に任せたら剣豪の名前にされるのは目に見えている。
しかも二人揃って花月に弱い。
花月が『三厳』が良いと強く言ったら通ってしまうかもしれないのだ。
『三厳』などと付けられたらこの家を出奔するしかなくなる。
どうすりゃいいんだ……。
光夜は頭を抱えた。
そう言えば……。
「あの、師匠か若先生の名前の一字を頂けないでしょうか?」
紙に書かれた名前の中に『空』も『陽』もいない。
紘空か紘陽の偏諱を賜れば剣豪と同じ名前は避けられる。
「そうか」
弦之丞は頷くと、
「では『紘』の字を使いなさい」
あっさり言った。
「えっ! 『紘』は桜井家の通字では……」
偏諱でいいんだが……。
「通字を与えてはいけないという決まりはない」
確かに織田信長は通字である『信』を与えている。
いや、それはそれで恐れ多いし荷が重いんだが……。
藤孝辺りを選んでおけば良かった……。
細川幽斎で知られてるから剣豪にあやかったって分かる人は少ないだろうし……。
「じゃあ『紘』に『や』って言う字を付ければ今まで通り『こうや』って呼べるのね」
あっ……!
そうか……。
『紘』は『ひろ』だけではなく『こう』とも読む。
桜井家では『紘』を『ひろ』と読んでいると言うだけである。
『紘也』なり『紘矢』なりにしてしまえば『こうや』のままだから声で聞く分には今までと同じだ。
「じゃあ『紘』に『夜』で『紘夜』ね」
え……。
『や』は夜のままなのか……。
まぁ、剣豪と同じ名前じゃなきゃいいか……。
なんだか物凄く適当に決まってしまった気もするが、どうせ普段は使わないのだからと自分を納得させた。
『陪臣』とは直接の家臣ではないと言う意味なので、例えば大名家の家臣が雇っている家臣も大名から見たら陪臣だし、大名の家臣でも他の大名から見たら陪臣である。
つまり陪臣とは自分の直接の家臣ではない者を指す。
ちなみに旗本が出世して石高が一万石を超えると大名となり直参とは呼ばれなくなるが、領地を子供達に分割して譲ったりして一万石以下になると旗本に戻る。
柳生宗矩は旗本から出世して一万二千五百石の大名となったが三人の息子に領地を分割して譲ったので一万石以下になったので柳生家は旗本に戻り、その後、宗冬の代でまた一万石以上になって大名に復帰している。
牢人は誰の家臣でもないので、大名とは別の意味で直参でも陪臣でもない。
ふと、花月が考え込むような表情になった。
「どうかしたか?」
「もしかしたら若様が公方様に拝謁する前に次丸様を跡継ぎにしたいのかも」
将軍は忙しいので大名や旗本の子息が元服する度に一々謁見などしていられない。
そのため旗本や小藩の大名の子息への謁見は一括して行われる。
大勢を集めたところに将軍が来てまとめて謁見するのだ。
直参でも御目見得以下の者や陪臣、牢人などはそれすら叶わないから光夜には無縁の話なので拝謁済みかどうかで何が違うのかよく分からないが。
「光夜、諱は考えたか」
夜、学問を教わるために居間へ行くと弦之丞が訊ねてきた。
「いえ、まだ……」
そういや考えとけって言われてたな……。
ササゲ豆が届くまでに思い付かなければ三厳にされかねない。
「では、この中から選ぶと良いだろう」
弦之丞が光夜に紙を渡した。
「私もいくつか書き出してみた」
宗祐もそう言って紙を出した。
「流石お父様とお兄様!」
紙を覗き込んだ花月が、はしゃいだ声を上げる。
えっ……。
なんか嫌な予感が……。
再度紙に目を落とすと弦之丞と宗祐が書き出したものは重複しているものが多かった。
しかも、いくつか聞き覚えのある名前が……。
「この名前って……」
「全員名だたる剣豪よ」
花月がにこやかに答えた。
やっぱり……。
てことは義輝って、もしかしなくても足利将軍……。
牢人風情が付けて良い名前じゃねぇだろ……!
「本当は宗祐も剣豪にあやかった名前にしたかったのだが、うちの通字である紘の字を使っている剣豪が見付からなくてな」
弦之丞の表情も声音もいつもと変わらないが無念さは十分に伝わってきた。
花月の剣豪好きは師匠の影響か……。
てか、若先生も……。
『通字』というのは一族で共通して使う字である。
武士の名前が似通っているのは通字を使うことが多いためである。
一族に通字がある場合、もう一字は既に居る者と被らないように避けた。
これを『偏諱』と言う。
徳川家なら『家』が通字で、『家康』の『康』が偏諱である。
家康以降は同じ『家康』という名前にならないように『康』の字が避けられた。
『光』なども同様に偏諱である。
『綱吉』の場合、兄の『家綱』が通字である『家』の字を使い、弟の綱吉は兄・家綱から偏諱である『綱』の字を賜ったから『綱吉』となった。
つまり『宗』が通字だったら若先生は宗厳か宗矩だったかもしれないのか……。
いくら滅多に使わないとは言え秘密ではないのだ。
そっと様子を窺うと花月が期待に満ちた表情で紙の一点を凝視している。
〝三厳〟
そうか、目上の者なら下の者を諱で呼べる。
つまり光夜の諱が『三厳』にした場合、花月は堂々と呼べるのだ。
町人ならいざ知らず、武士で三厳が柳生十兵衛の諱だと知らない者はいないだろう。
花月には悪いが人前で『三厳』などと呼ばれるのは御免被る。
しかし、ここには剣豪の名前しか書いてない。
弦之丞も宗祐も揃って剣豪の名前だけしか書いてこなかったのだから二人に任せたら剣豪の名前にされるのは目に見えている。
しかも二人揃って花月に弱い。
花月が『三厳』が良いと強く言ったら通ってしまうかもしれないのだ。
『三厳』などと付けられたらこの家を出奔するしかなくなる。
どうすりゃいいんだ……。
光夜は頭を抱えた。
そう言えば……。
「あの、師匠か若先生の名前の一字を頂けないでしょうか?」
紙に書かれた名前の中に『空』も『陽』もいない。
紘空か紘陽の偏諱を賜れば剣豪と同じ名前は避けられる。
「そうか」
弦之丞は頷くと、
「では『紘』の字を使いなさい」
あっさり言った。
「えっ! 『紘』は桜井家の通字では……」
偏諱でいいんだが……。
「通字を与えてはいけないという決まりはない」
確かに織田信長は通字である『信』を与えている。
いや、それはそれで恐れ多いし荷が重いんだが……。
藤孝辺りを選んでおけば良かった……。
細川幽斎で知られてるから剣豪にあやかったって分かる人は少ないだろうし……。
「じゃあ『紘』に『や』って言う字を付ければ今まで通り『こうや』って呼べるのね」
あっ……!
そうか……。
『紘』は『ひろ』だけではなく『こう』とも読む。
桜井家では『紘』を『ひろ』と読んでいると言うだけである。
『紘也』なり『紘矢』なりにしてしまえば『こうや』のままだから声で聞く分には今までと同じだ。
「じゃあ『紘』に『夜』で『紘夜』ね」
え……。
『や』は夜のままなのか……。
まぁ、剣豪と同じ名前じゃなきゃいいか……。
なんだか物凄く適当に決まってしまった気もするが、どうせ普段は使わないのだからと自分を納得させた。
0
あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし
かずえ
歴史・時代
旧題:ふたり暮らし
長屋シリーズ一作目。
第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。
頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。
一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。
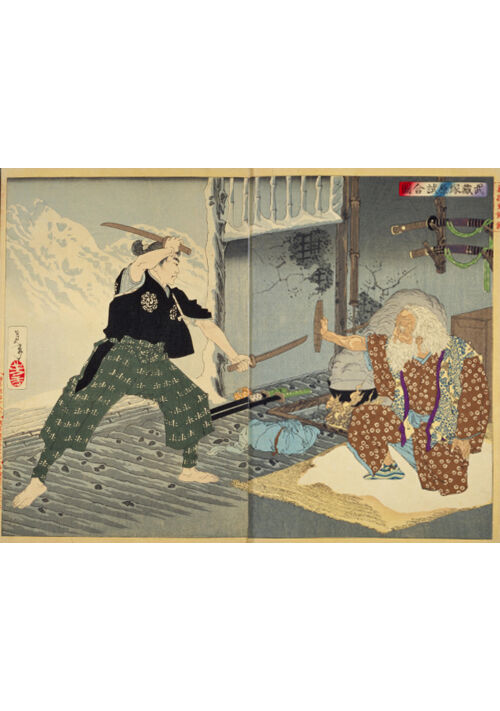
無用庵隠居清左衛門
蔵屋
歴史・時代
前老中田沼意次から引き継いで老中となった松平定信は、厳しい倹約令として|寛政の改革《かんせいのかいかく》を実施した。
第8代将軍徳川吉宗によって実施された|享保の改革《きょうほうのかいかく》、|天保の改革《てんぽうのかいかく》と合わせて幕政改革の三大改革という。
松平定信は厳しい倹約令を実施したのだった。江戸幕府は町人たちを中心とした貨幣経済の発達に伴い|逼迫《ひっぱく》した幕府の財政で苦しんでいた。
幕府の財政再建を目的とした改革を実施する事は江戸幕府にとって緊急の課題であった。
この時期、各地方の諸藩に於いても藩政改革が行われていたのであった。
そんな中、徳川家直参旗本であった緒方清左衛門は、己の出世の事しか考えない同僚に嫌気がさしていた。
清左衛門は無欲の徳川家直参旗本であった。
俸禄も入らず、出世欲もなく、ただひたすら、女房の千歳と娘の弥生と、三人仲睦まじく暮らす平穏な日々であればよかったのである。
清左衛門は『あらゆる欲を捨て去り、何もこだわらぬ無の境地になって千歳と弥生の幸せだけを願い、最後は無欲で死にたい』と思っていたのだ。
ある日、清左衛門に理不尽な言いがかりが同僚立花右近からあったのだ。
清左衛門は右近の言いがかりを相手にせず、
無視したのであった。
そして、松平定信に対して、隠居願いを提出したのであった。
「おぬし、本当にそれで良いのだな」
「拙者、一向に構いません」
「分かった。好きにするがよい」
こうして、清左衛門は隠居生活に入ったのである。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち
ヒロワークス
ライト文芸
女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。
クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。
それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。
そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!
その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

輿乗(よじょう)の敵 ~ 新史 桶狭間 ~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
美濃の戦国大名、斎藤道三の娘・帰蝶(きちょう)は、隣国尾張の織田信長に嫁ぐことになった。信長の父・信秀、信長の傅役(もりやく)・平手政秀など、さまざまな人々と出会い、別れ……やがて信長と帰蝶は尾張の国盗りに成功する。しかし、道三は嫡男の義龍に殺され、義龍は「一色」と称して、織田の敵に回る。一方、三河の方からは、駿河の国主・今川義元が、大軍を率いて尾張へと向かって来ていた……。
【登場人物】
帰蝶(きちょう):美濃の戦国大名、斎藤道三の娘。通称、濃姫(のうひめ)。
織田信長:尾張の戦国大名。父・信秀の跡を継いで、尾張を制した。通称、三郎(さぶろう)。
斎藤道三:下剋上(げこくじょう)により美濃の国主にのし上がった男。俗名、利政。
一色義龍:道三の息子。帰蝶の兄。道三を倒して、美濃の国主になる。幕府から、名門「一色家」を名乗る許しを得る。
今川義元:駿河の戦国大名。名門「今川家」の当主であるが、国盗りによって駿河の国主となり、「海道一の弓取り」の異名を持つ。
斯波義銀(しばよしかね):尾張の国主の家系、名門「斯波家」の当主。ただし、実力はなく、形だけの国主として、信長が「臣従」している。
【参考資料】
「国盗り物語」 司馬遼太郎 新潮社
「地図と読む 現代語訳 信長公記」 太田 牛一 (著) 中川太古 (翻訳) KADOKAWA
東浦町観光協会ホームページ
Wikipedia
【表紙画像】
歌川豊宣, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で
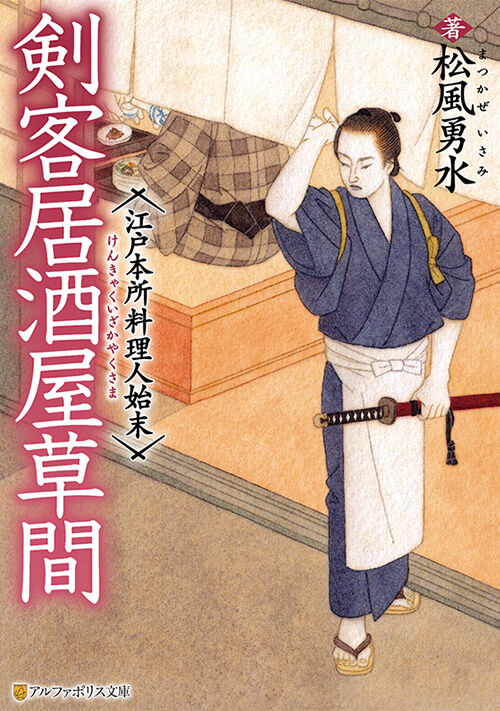
剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末
松風勇水(松 勇)
歴史・時代
旧題:剣客居酒屋 草間の陰
第9回歴史・時代小説大賞「読めばお腹がすく江戸グルメ賞」受賞作。
本作は『剣客居酒屋 草間の陰』から『剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末』と改題いたしました。
2025年11月28書籍刊行。
なお、レンタル部分は修正した書籍と同様のものとなっておりますが、一部の描写が割愛されたため、後続の話とは繋がりが悪くなっております。ご了承ください。
酒と肴と剣と闇
江戸情緒を添えて
江戸は本所にある居酒屋『草間』。
美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。
自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。
多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。
その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。
店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















