5 / 211
入団試験
しおりを挟む
「そんなことがあったんですか……」
ほんの一週間前、このS級パーティーで起こっていた追放劇……というのも少しおかしいか、正確に言うと追放未遂劇。
私はメッツァトルのリーダー、勇者アルグスさんからその一部始終を教えてもらって、ようやくこの異様な空気、ドラーガさんが喋るたびに微妙な雰囲気になる理由を知ることができた。
私がアルグスさんの目を見ると、アルグスさんも真っ直ぐに見返してくる。アルグスさんの端正な顔立ち、その中心にある真っ直ぐなまなざしが、それが冗談ではなく、事実であったのだと物語ってくる。
「つまり、『賢者』ドラーガ・ノートさんがパーティーの足を引っ張るため追放しようとしたんだけど、組合の力が強く、明確な背任行為などがないとそれができない、っていうことなんですよね?」
私がアルグスさんに尋ねると彼はこくりと頷いた。アンセさんとクオスさんも神妙な面持ちで静かに頷いた。
にわかには信じがたい話だけど、組合によって冒険者の生活が支えられるとともに、時としてこういう障りもあるのか。私はちらりと視線を外した。
そして、最も信じがたいのは……
「ハハハ、まあ過去の話だ。お前が気にすることじゃないさ、マッピ」
特に自室にこもったりして席を外すこともなく、普通に今の話を平気な顔してドラーガさんが横で聞いているということだ。どういうメンタルしてるんだこの人。ちょっとは気にしろ。
「ということでね。悪いけれど、いくら貴重なヒーラーと言っても、実技試験もなく仲間に入れることはできないのよ。『前例』があるからね! いくらかわいい女の子だからってそこはしっかりやるわよ、いいわね?」
憎々し気な視線をドラーガさんに向けながらアンセさんがそう言った。私は少し赤面してしまう。アンセさんみたいな綺麗な『大人の女性』に『かわいい』なんて言われると、言葉の綾だとしても照れてしまう。
「『かわいい』ってのは言葉の綾だからな?」
うるせーこのやろう。
即座にいらない補足を入れたドラーガさんに私は心の中で突っ込む。うん、まあ、ここまでの流れだけ見ても、この人ホントに『いらん一言』を言う人だな。
けど、そこでふと私の脳裏には一つの疑問が沸き上がった。
「あのぅ……ドラーガさんが加入した時には実技試験とかやらなかったんですか? 面接だけで加入を決めてしまったんですか?」
私がその質問を発すると、やはりまた一様に思い空気が場を支配した。しまった、聞いてはいけない質問だったんだろうか。でも気になる。それに命を預ける仲間を選ぶのに実力を全く見ないなんてことがあるんだろうか。
「まあ、いろいろあったんだよ……」
アルグスさんが重い口を開いてゆっくりと話し始めた。
それは、1年ほど前の事だったという。
――――――――――――――――
「えっと、じゃ、じゃあ、キミがドラーガ・ノートさんで間違いないんだね?」
緊張を隠しきれていない口調で僕、アルグスはメッツァトルの拠点を訪ねてきた男に訪ねた。声がかすれてしまう。
正直言ってこういった、全く知らない人をパーティーに迎えるのは初めてだ。今までのメンバーは元々知り合いだったり、そのメンバーが連れてきたり、知り合いの紹介だったりといったものだったので、こうしてギルドを通して面接をするなんてなかったからだ。
「いかにも」
その、バンダナをした長髪の男は腕を組んで椅子に座ったまま、落ち着いた態度で頷いた。面接される側なのにえらいデカい態度だとは思ったが、しかしむしろその時の僕にはこの堂々たる態度は頼もしくも感じたし、それだけの態度が許される人物だと思っていた。
なぜなら……
「その、ギルドの資料だとクラスが『賢者』とあるけど、これは本当なんだよね?」
その男、ドラーガは大げさに両手を広げて「ハッ」と笑って答えた。
「おいおい、ギルドの資料を疑うのか? それとも俺が文書偽造をしたとでも?」
そう、ギルドの文書は公文書ではないものの、偽造すれば重罪となる信憑性を持つ確かなものだし、『クラス』もまた偽ることはできない。なぜなら、クラスは自己申告でも試験があるわけでもない。自動で判別されるからだ。
各地のギルドの中でも比較的大きな拠点には『クラス判別』のための、魔力の込められた銅板が存在する。それは当然僕たちの滞在するカルゴシアの町にあるギルド拠点、『天文館』にも存在して、それが判別ミスをすることは決してないからだ。
銅板に手を当ててギルドの職員が呪文を唱えると判別が始まる。例えば賢者なら「格闘と魔法どちらが得意か」「攻撃魔法は使えるか」「回復魔法は使えるか」などをフローチャート式に次々と内部で自動的に判別されゆく。
賢者の主な特徴としては、『魔法を使って戦闘する』『攻撃魔法が使える』『回復魔法が使える』『補助魔法が使える』『複数の属性魔法を別々に同時に制御できる』などがある。
特に最後の条件が厳しく、これこそ『賢者の証明』であるとも言われる条件であり、これをクリアして『賢者』の称号を受けたものは歴史上数人しかいないとか。手前味噌で悪いが、僕の『勇者』と同じくらいレアなクラスだ。
「疑うわけじゃないけど、『勇者』がいるパーティーともなると寄生して甘い汁を吸おうなんて奴も多いのよ。気を悪くしないで」
隣にいたアンセがそう言った。まあ、本人の僕からは言いづらいけど、つまりそういうことだ。そして、このパーティーに迎える初めての回復職が賢者というのも正直言って少しできすぎた話だから、最初から疑ってかかってたのだ。
「ちっちっち……」
ドラーガがおどけるようにしながら右手の人差し指を立て、自分のこめかみのあたりで左右に振りながら目をつぶって話す。
「疑り深いねえ……実に臆病だ……」
一瞬バカにするようなことを言って言い逃れするつもりなのかと思ったが、違った。ドラーガが目を開けると人差し指の先にボッ、と火が灯った。
「だがその臆病さがいい! 死地で生き残るのは常に臆病者だ。俺から見て、あんたたちはどうやら合格のようだな」
その言葉を聞いた時、僕にはバカにするような話し方への怒りよりも、驚きの方が大きかった。
試していたのは僕たちの方だったはずなのに、実は僕たちが試されていたのか、という事態に畏怖の念すら覚えたからだ。
しかし魔法の炎は指先で小さく灯っているだけ。正直言ってこの程度の魔法ならちょっと優秀な子供でもできる。そう思って僕が口を開きかけた時だった。
ドラーガは次に中指を立てた。
「欲しいのは賢者の証か? それとも俺の力か?」
今度は中指の先に白銀の、球状の光が灯る。
「これは……間違いない、聖属性の魔法……ッ!!」
アンセが震えながらそう呟いた。攻撃魔法と回復魔法、そしてそれらを同時に扱える。賢者の証だ。しかも話に聞けば普通はもっと離れた場所、たとえば右手と左手で発動させるというのに、人差し指と中指という、極めて近い場所で同時に発動させている。こんな高等技術は伝承の中ですら聞いたことがない。
「アルグス、勇者と賢者が揃えばこの世界に解けない謎はない」
次に薬指を立てて、魔法を発動した。小さな風切り音と共に細かい塵やほこりが渦巻くのが見える。今度は風魔法だ。三属性の同時発動。こんなのは聞いたこともない。
「俺とお前で世界の謎を全て解き明かし、この世界をクソ退屈なものに変えてやろうぜ」
ドラーガは最後に小指を立てた。指の先にポツン、と小さい水の玉が現れ浮いている。水属性。
「うそ!? 火と水の属性を同時に発動させるなんて! 人間業じゃない!!」
アンセは冷や汗を流しながら恐怖に震えている。反対属性を同時に扱えるものなのか、その実力は魔法にあまり精通していない僕でも十分に理解できた。
ドラーガは全ての魔法を消すとパンパンと両手を叩いた。
「まっ、ざっとこんなもんさ」
ドラーガ・ノートは足を組んで座ったまま。汗一つかいていなかった。
ほんの一週間前、このS級パーティーで起こっていた追放劇……というのも少しおかしいか、正確に言うと追放未遂劇。
私はメッツァトルのリーダー、勇者アルグスさんからその一部始終を教えてもらって、ようやくこの異様な空気、ドラーガさんが喋るたびに微妙な雰囲気になる理由を知ることができた。
私がアルグスさんの目を見ると、アルグスさんも真っ直ぐに見返してくる。アルグスさんの端正な顔立ち、その中心にある真っ直ぐなまなざしが、それが冗談ではなく、事実であったのだと物語ってくる。
「つまり、『賢者』ドラーガ・ノートさんがパーティーの足を引っ張るため追放しようとしたんだけど、組合の力が強く、明確な背任行為などがないとそれができない、っていうことなんですよね?」
私がアルグスさんに尋ねると彼はこくりと頷いた。アンセさんとクオスさんも神妙な面持ちで静かに頷いた。
にわかには信じがたい話だけど、組合によって冒険者の生活が支えられるとともに、時としてこういう障りもあるのか。私はちらりと視線を外した。
そして、最も信じがたいのは……
「ハハハ、まあ過去の話だ。お前が気にすることじゃないさ、マッピ」
特に自室にこもったりして席を外すこともなく、普通に今の話を平気な顔してドラーガさんが横で聞いているということだ。どういうメンタルしてるんだこの人。ちょっとは気にしろ。
「ということでね。悪いけれど、いくら貴重なヒーラーと言っても、実技試験もなく仲間に入れることはできないのよ。『前例』があるからね! いくらかわいい女の子だからってそこはしっかりやるわよ、いいわね?」
憎々し気な視線をドラーガさんに向けながらアンセさんがそう言った。私は少し赤面してしまう。アンセさんみたいな綺麗な『大人の女性』に『かわいい』なんて言われると、言葉の綾だとしても照れてしまう。
「『かわいい』ってのは言葉の綾だからな?」
うるせーこのやろう。
即座にいらない補足を入れたドラーガさんに私は心の中で突っ込む。うん、まあ、ここまでの流れだけ見ても、この人ホントに『いらん一言』を言う人だな。
けど、そこでふと私の脳裏には一つの疑問が沸き上がった。
「あのぅ……ドラーガさんが加入した時には実技試験とかやらなかったんですか? 面接だけで加入を決めてしまったんですか?」
私がその質問を発すると、やはりまた一様に思い空気が場を支配した。しまった、聞いてはいけない質問だったんだろうか。でも気になる。それに命を預ける仲間を選ぶのに実力を全く見ないなんてことがあるんだろうか。
「まあ、いろいろあったんだよ……」
アルグスさんが重い口を開いてゆっくりと話し始めた。
それは、1年ほど前の事だったという。
――――――――――――――――
「えっと、じゃ、じゃあ、キミがドラーガ・ノートさんで間違いないんだね?」
緊張を隠しきれていない口調で僕、アルグスはメッツァトルの拠点を訪ねてきた男に訪ねた。声がかすれてしまう。
正直言ってこういった、全く知らない人をパーティーに迎えるのは初めてだ。今までのメンバーは元々知り合いだったり、そのメンバーが連れてきたり、知り合いの紹介だったりといったものだったので、こうしてギルドを通して面接をするなんてなかったからだ。
「いかにも」
その、バンダナをした長髪の男は腕を組んで椅子に座ったまま、落ち着いた態度で頷いた。面接される側なのにえらいデカい態度だとは思ったが、しかしむしろその時の僕にはこの堂々たる態度は頼もしくも感じたし、それだけの態度が許される人物だと思っていた。
なぜなら……
「その、ギルドの資料だとクラスが『賢者』とあるけど、これは本当なんだよね?」
その男、ドラーガは大げさに両手を広げて「ハッ」と笑って答えた。
「おいおい、ギルドの資料を疑うのか? それとも俺が文書偽造をしたとでも?」
そう、ギルドの文書は公文書ではないものの、偽造すれば重罪となる信憑性を持つ確かなものだし、『クラス』もまた偽ることはできない。なぜなら、クラスは自己申告でも試験があるわけでもない。自動で判別されるからだ。
各地のギルドの中でも比較的大きな拠点には『クラス判別』のための、魔力の込められた銅板が存在する。それは当然僕たちの滞在するカルゴシアの町にあるギルド拠点、『天文館』にも存在して、それが判別ミスをすることは決してないからだ。
銅板に手を当ててギルドの職員が呪文を唱えると判別が始まる。例えば賢者なら「格闘と魔法どちらが得意か」「攻撃魔法は使えるか」「回復魔法は使えるか」などをフローチャート式に次々と内部で自動的に判別されゆく。
賢者の主な特徴としては、『魔法を使って戦闘する』『攻撃魔法が使える』『回復魔法が使える』『補助魔法が使える』『複数の属性魔法を別々に同時に制御できる』などがある。
特に最後の条件が厳しく、これこそ『賢者の証明』であるとも言われる条件であり、これをクリアして『賢者』の称号を受けたものは歴史上数人しかいないとか。手前味噌で悪いが、僕の『勇者』と同じくらいレアなクラスだ。
「疑うわけじゃないけど、『勇者』がいるパーティーともなると寄生して甘い汁を吸おうなんて奴も多いのよ。気を悪くしないで」
隣にいたアンセがそう言った。まあ、本人の僕からは言いづらいけど、つまりそういうことだ。そして、このパーティーに迎える初めての回復職が賢者というのも正直言って少しできすぎた話だから、最初から疑ってかかってたのだ。
「ちっちっち……」
ドラーガがおどけるようにしながら右手の人差し指を立て、自分のこめかみのあたりで左右に振りながら目をつぶって話す。
「疑り深いねえ……実に臆病だ……」
一瞬バカにするようなことを言って言い逃れするつもりなのかと思ったが、違った。ドラーガが目を開けると人差し指の先にボッ、と火が灯った。
「だがその臆病さがいい! 死地で生き残るのは常に臆病者だ。俺から見て、あんたたちはどうやら合格のようだな」
その言葉を聞いた時、僕にはバカにするような話し方への怒りよりも、驚きの方が大きかった。
試していたのは僕たちの方だったはずなのに、実は僕たちが試されていたのか、という事態に畏怖の念すら覚えたからだ。
しかし魔法の炎は指先で小さく灯っているだけ。正直言ってこの程度の魔法ならちょっと優秀な子供でもできる。そう思って僕が口を開きかけた時だった。
ドラーガは次に中指を立てた。
「欲しいのは賢者の証か? それとも俺の力か?」
今度は中指の先に白銀の、球状の光が灯る。
「これは……間違いない、聖属性の魔法……ッ!!」
アンセが震えながらそう呟いた。攻撃魔法と回復魔法、そしてそれらを同時に扱える。賢者の証だ。しかも話に聞けば普通はもっと離れた場所、たとえば右手と左手で発動させるというのに、人差し指と中指という、極めて近い場所で同時に発動させている。こんな高等技術は伝承の中ですら聞いたことがない。
「アルグス、勇者と賢者が揃えばこの世界に解けない謎はない」
次に薬指を立てて、魔法を発動した。小さな風切り音と共に細かい塵やほこりが渦巻くのが見える。今度は風魔法だ。三属性の同時発動。こんなのは聞いたこともない。
「俺とお前で世界の謎を全て解き明かし、この世界をクソ退屈なものに変えてやろうぜ」
ドラーガは最後に小指を立てた。指の先にポツン、と小さい水の玉が現れ浮いている。水属性。
「うそ!? 火と水の属性を同時に発動させるなんて! 人間業じゃない!!」
アンセは冷や汗を流しながら恐怖に震えている。反対属性を同時に扱えるものなのか、その実力は魔法にあまり精通していない僕でも十分に理解できた。
ドラーガは全ての魔法を消すとパンパンと両手を叩いた。
「まっ、ざっとこんなもんさ」
ドラーガ・ノートは足を組んで座ったまま。汗一つかいていなかった。
0
お気に入りに追加
13
あなたにおすすめの小説


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

勇者一行から追放された二刀流使い~仲間から捜索願いを出されるが、もう遅い!~新たな仲間と共に魔王を討伐ス
R666
ファンタジー
アマチュアニートの【二龍隆史】こと36歳のおっさんは、ある日を境に実の両親達の手によって包丁で腹部を何度も刺されて地獄のような痛みを味わい死亡。
そして彼の魂はそのまま天界へ向かう筈であったが女神を自称する危ない女に呼び止められると、ギフトと呼ばれる最強の特典を一つだけ選んで、異世界で勇者達が魔王を討伐できるように手助けをして欲しいと頼み込まれた。
最初こそ余り乗り気ではない隆史ではあったが第二の人生を始めるのも悪くないとして、ギフトを一つ選び女神に言われた通りに勇者一行の手助けをするべく異世界へと乗り込む。
そして異世界にて真面目に勇者達の手助けをしていたらチキン野郎の役立たずという烙印を押されてしまい隆史は勇者一行から追放されてしまう。
※これは勇者一行から追放された最凶の二刀流使いの隆史が新たな仲間を自ら探して、自分達が新たな勇者一行となり魔王を討伐するまでの物語である※

システムバグで輪廻の輪から外れましたが、便利グッズ詰め合わせ付きで他の星に転生しました。
大国 鹿児
ファンタジー
輪廻転生のシステムのバグで輪廻の輪から外れちゃった!
でも神様から便利なチートグッズ(笑)の詰め合わせをもらって、
他の星に転生しました!特に使命も無いなら自由気ままに生きてみよう!
主人公はチート無双するのか!? それともハーレムか!?
はたまた、壮大なファンタジーが始まるのか!?
いえ、実は単なる趣味全開の主人公です。
色々な秘密がだんだん明らかになりますので、ゆっくりとお楽しみください。
*** 作品について ***
この作品は、真面目なチート物ではありません。
コメディーやギャグ要素やネタの多い作品となっております
重厚な世界観や派手な戦闘描写、ざまあ展開などをお求めの方は、
この作品をスルーして下さい。
*カクヨム様,小説家になろう様でも、別PNで先行して投稿しております。

妹が真の聖女だったので、偽りの聖女である私は追放されました。でも、聖女の役目はものすごく退屈だったので、最高に嬉しいです【完結】
小平ニコ
ファンタジー
「お姉様、よくも私から夢を奪ってくれたわね。絶対に許さない」
私の妹――シャノーラはそう言うと、計略を巡らし、私から聖女の座を奪った。……でも、私は最高に良い気分だった。だって私、もともと聖女なんかになりたくなかったから。
退職金を貰い、大喜びで国を出た私は、『真の聖女』として国を守る立場になったシャノーラのことを思った。……あの子、聖女になって、一日の休みもなく国を守るのがどれだけ大変なことか、ちゃんと分かってるのかしら?
案の定、シャノーラはよく理解していなかった。
聖女として役目を果たしていくのが、とてつもなく困難な道であることを……
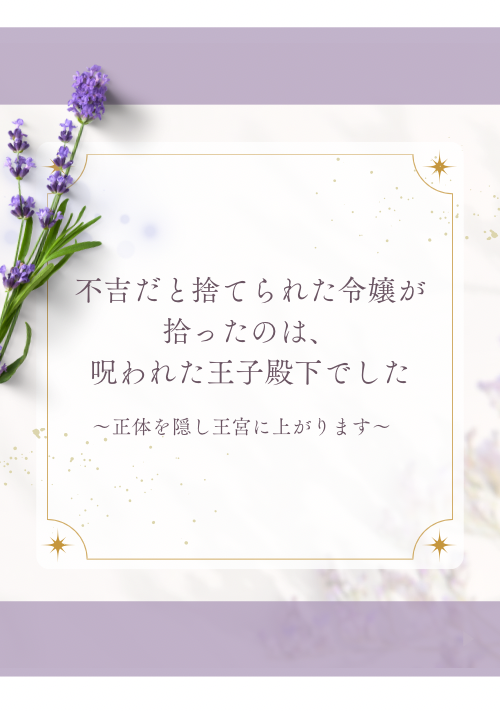
不吉だと捨てられた令嬢が拾ったのは、呪われた王子殿下でした ~正体を隠し王宮に上がります~
長井よる
恋愛
フローレス侯爵家の次女のレティシアは、この国で忌み嫌われる紫の髪と瞳を持って生まれたため、父親から疎まれ、ついには十歳の時に捨てられてしまう。
孤児となり、死にかけていたレティシアは、この国の高名な魔法使いに拾われ、彼の弟子として新たな人生を歩むことになる。
レティシアが十七歳になったある日、事故に遭い瀕死の王子アンドレアスを介抱する。アンドレアスの体には呪いがかけられており、成人まで生きられないという運命が待ち受けていた。レティシアは試行錯誤の末、何とか呪いの進行を止めることに成功する。
アンドレアスから、王宮に来てほしいと懇願されたレティシアは、正体を隠し王宮に上がることを決意するが……。
呪われた王子×秘密を抱えた令嬢(魔法使いの弟子)のラブストーリーです。
※残酷な描写注意
10/30:主要登場人物•事件設定をUPしました。

転生幼女の怠惰なため息
(◉ɷ◉ )〈ぬこ〉
ファンタジー
ひとり残業中のアラフォー、清水 紗代(しみず さよ)。異世界の神のゴタゴタに巻き込まれ、アッという間に死亡…( ºωº )チーン…
紗世を幼い頃から見守ってきた座敷わらしズがガチギレ⁉💢
座敷わらしズが異世界の神を脅し…ε=o(´ロ`||)ゴホゴホッ説得して異世界での幼女生活スタートっ!!
もう何番煎じかわからない異世界幼女転生のご都合主義なお話です。
全くの初心者となりますので、よろしくお願いします。
作者は極度のとうふメンタルとなっております…

子爵家の長男ですが魔法適性が皆無だったので孤児院に預けられました。変化魔法があれば魔法適性なんて無くても無問題!
八神
ファンタジー
主人公『リデック・ゼルハイト』は子爵家の長男として産まれたが、検査によって『魔法適性が一切無い』と判明したため父親である当主の判断で孤児院に預けられた。
『魔法適性』とは読んで字のごとく魔法を扱う適性である。
魔力を持つ人間には差はあれど基本的にみんな生まれつき様々な属性の魔法適性が備わっている。
しかし例外というのはどの世界にも存在し、魔力を持つ人間の中にもごく稀に魔法適性が全くない状態で産まれてくる人も…
そんな主人公、リデックが5歳になったある日…ふと前世の記憶を思い出し、魔法適性に関係の無い変化魔法に目をつける。
しかしその魔法は『魔物に変身する』というもので人々からはあまり好意的に思われていない魔法だった。
…はたして主人公の運命やいかに…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















