お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

深海の星空
柴野日向
青春
「あなたが、少しでも笑っていてくれるなら、ぼくはもう、何もいらないんです」
ひねくれた孤高の少女と、真面目すぎる新聞配達の少年は、深い海の底で出会った。誰にも言えない秘密を抱え、塞がらない傷を見せ合い、ただ求めるのは、歩む深海に差し込む光。
少しずつ縮まる距離の中、明らかになるのは、少女の最も嫌う人間と、望まれなかった少年との残酷な繋がり。
やがて立ち塞がる絶望に、一縷の希望を見出す二人は、再び手を繋ぐことができるのか。
世界の片隅で、小さな幸福へと手を伸ばす、少年少女の物語。

全力でおせっかいさせていただきます。―私はツンで美形な先輩の食事係―
入海月子
青春
佐伯優は高校1年生。カメラが趣味。ある日、高校の屋上で出会った超美形の先輩、久住遥斗にモデルになってもらうかわりに、彼の昼食を用意する約束をした。
遥斗はなぜか学校に住みついていて、衣食は女生徒からもらったものでまかなっていた。その報酬とは遥斗に抱いてもらえるというもの。
本当なの?遥斗が気になって仕方ない優は――。
優が薄幸の遥斗を笑顔にしようと頑張る話です。

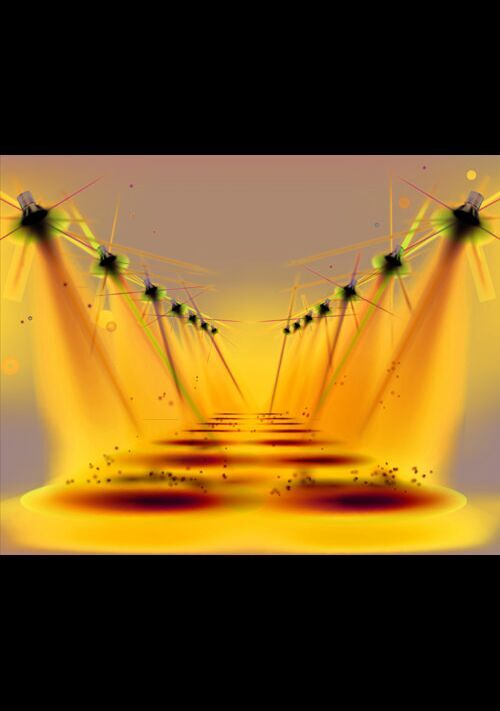
私のなかの、なにか
ちがさき紗季
青春
中学三年生の二月のある朝、川奈莉子の両親は消えた。叔母の曜子に引き取られて、大切に育てられるが、心に刻まれた深い傷は癒えない。そればかりか両親失踪事件をあざ笑う同級生によって、ネットに残酷な書きこみが連鎖し、対人恐怖症になって引きこもる。
やがて自分のなかに芽生える〝なにか〟に気づく莉子。かつては気持ちを満たす幸せの象徴だったそれが、不穏な負の象徴に変化しているのを自覚する。同時に両親が大好きだったビートルズの名曲『Something』を聴くことすらできなくなる。
春が訪れる。曜子の勧めで、独自の教育方針の私立高校に入学。修と咲南に出会い、音楽を通じてどこかに生きているはずの両親に想いを届けようと考えはじめる。
大学一年の夏、莉子は修と再会する。特別な歌声と特異の音域を持つ莉子の才能に気づいていた修の熱心な説得により、ふたたび歌うようになる。その後、修はネットの音楽配信サービスに楽曲をアップロードする。間もなく、二人の世界が動きはじめた。
大手レコード会社の新人発掘プロデューサー澤と出会い、修とともにライブに出演する。しかし、両親の失踪以来、莉子のなかに巣食う不穏な〝なにか〟が膨張し、大勢の観客を前にしてパニックに陥り、倒れてしまう。それでも奮起し、ぎりぎりのメンタルで歌いつづけるものの、さらに難題がのしかかる。音楽フェスのオープニングアクトの出演が決定した。直後、おぼろげに悟る両親の死によって希望を失いつつあった莉子は、プレッシャーからついに心が折れ、プロデビューを辞退するも、曜子から耳を疑う内容の電話を受ける。それは、両親が生きている、という信じがたい話だった。
歌えなくなった莉子は、葛藤や混乱と闘いながら――。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
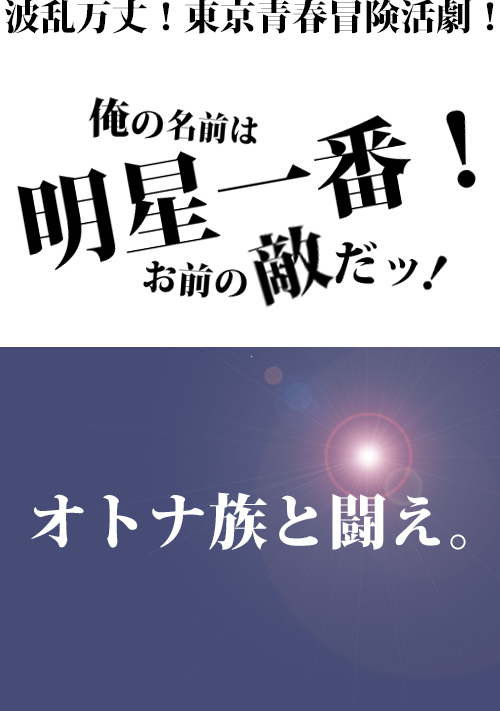
明星一番! オトナ族との闘い。
百夜
青春
波乱万丈、神出鬼没!
言葉遊びで展開する新感覚のハイテンション学園アクションコメディです。
明星一番は高校3年生。偶然隣りの席にいた三咲と共に、次々と襲い掛かかってくるオトナ族との闘いを「言葉遊び」で制していくーーー。
だが、この学園には重大な秘密が隠されていた。
それが「中二病」・・・。
超絶推理を駆使して、彼らはその謎を解けるのか?

君を救える夢を見た
冠つらら
青春
高校生の瀬名類香は、クラスメイト達から距離を置き、孤高を貫いている。
そんな類香にも最近は悩みがあった。
クラスメイトの一人が、やけに積極的に話しかけてくる。
類香はなんとか避けようとするが、相手はどうにも手強い。
クラスで一番の天真爛漫女子、日比和乃。
彼女は、類香の想像を超える強敵だった。

脅され彼女~可愛い女子の弱みを握ったので脅して彼女にしてみたが、健気すぎて幸せにしたいと思った~
みずがめ
青春
陰キャ男子が後輩の女子の弱みを握ってしまった。彼女いない歴=年齢の彼は後輩少女に彼女になってくれとお願いする。脅迫から生まれた恋人関係ではあったが、彼女はとても健気な女の子だった。
ゲス男子×健気女子のコンプレックスにまみれた、もしかしたら純愛になるかもしれないお話。
※この作品は別サイトにも掲載しています。
※表紙イラストは、あっきコタロウさんに描いていただきました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















