47 / 145
第四章 末路
第一回 初陣(前編)
しおりを挟む 春の夜だった。
城下の西、弁分町にある空き家の二階。平山雷蔵は、灯り一つない部屋で、一人息を殺して待っていた。
まだ夜は寒い。火の温もりが恋しくなるような気温だが、今の雷蔵には、それを必要としなかった。
寂とした闇と孤独。その中で緊張を強いられてはいるが、それが妙に心地よくあるのだ。身の内に燃える熱もある。
お役目である。勿論、それは殺しだった。
獲物とも呼べる標的の男は近くの料亭にいて、今はこうして出てくるのを待っている。何か動きがあれば、中にいる協力者から知らせが入る手筈になっていた。
料亭の名は、〔秀松〕という。分限者御用達の名店で、夜須二十六万石を代表する格式を有すると名高い。故に、藩政を揺るがすような陰謀が画策されて来た場所であると、まことしやかに囁かれている。
(予定ではもう少しか)
男が、中に入って一刻ぐらいは過ぎている。一刻と四半刻弱。それを目処に、男が秀松を出るという話を、協力者から聞いていた。
(あと四半刻……)
計算ではそうなる。ただ、果たして時間通りに出て来てくれるかどうかは判らない。
雷蔵は協力者というものを信用はしていない。そもそも、協力者という存在の素性を知らされていない。そのような胡乱な者を、簡単に信用する事は出来ない。信じられるのは、自らの耳目だけ。そう父である、平山清記に何度も言い聞かせられてきた。
雷蔵は喉の乾きを覚え、竹筒の水を一口だけ含んだ。
男の名は、真崎惣蔵という。武士である。三十五歳。身分は徒士組格と高くないが、下士や百姓を相手に尚武塾という私塾を谷村に開き、剣術と学問を教えている。家族は身分に釣り合った妻と、まだ幼い男児が一人。雷蔵は一度だけ、その暮し振りを覗いた事があるが、至極質素なものだ。
その真崎を殺す。それが年が明けた安永八年最初の、そして元服し小弥太から雷蔵に名を改めて初めて任されたお役目である。
ただ、真崎を殺すだけではない。殺した後に、少し細工を加える必要がある。殺すだけならいつでも出来るが、細工は今日というこの日にしか出来ない。それが上手く行かなければ、成功ではないと父に念を押されていた。面倒だと思うが、そうした手間を掛けざる得ない理由が、真崎という男にはある。
真崎は勤王の志士なのだ。それも、ただの志士ではない。武富陣内、館林簡陽、尚憲が亡き後に夜須勤王党の盟主に推された最後の大物なのである。剣は光当流の免許取りで、剣名が藩内外にも鳴り響く腕前。加えて学問も修めて、その人望は絶大だった。
「生かしておいては危うい男」
そう言った父の声が、耳に蘇った。
何故危ういのか? それを訊くと、黒河藩との関係と言われた。
黒河藩は東北最大の外様藩で、かつては陸奥の一部だった羽仙国を有する国持ちである。藩主の伊達蝦夷守は、勤王の志が篤く、東北近隣の志士を召し抱えては保護しているという。東北への藩屏として夜須に配された譜代の栄生家にとって、伊達家は仮想敵国であり、常に意識しなければならない相手であった。
その黒河藩と真崎は、親密な関係にある。何でも東北遊学の折には、蝦夷守に拝謁を賜ったらしく、現に今も夜須勤王党立て直しの為に、密かな支援をしているという報告があったそうだ。
故に表立って始末すると、真崎の信奉者の反発を招く結果となる。これを機に、黒河藩が何か仕掛ける口実を与えるかもしれない。藩としては、下火になった勤王運動を再燃させぬよう、秘密裏かつ確実に斬らねばならない厄介な男だった。
その真崎が、今まさに秀松で相賀舎人という男と密会していた。
相賀舎人は、夜須藩の中老である。藩校の学問師範をしていた所を、その学識を栄生利景によって見出されたという。
まず祐筆に取り立てられ、そこから町奉行で結果を出し若年寄を経て中老に昇進した。八艘飛びのような出世が出来たのも、利景の権力と威光が盤石だからだろう。抜擢に反対しそうな門閥も、今は日陰で鬱屈とした日々を過ごしている。
父も、この相賀については藩随一の切れ者と評していた。藩を支える吏僚になるとも。雷蔵が、相賀という男について知っている事は、このぐらいだった。一度窮地を救ったが、まともに会話もしていない。
しかし、真崎と相賀という取合せが、奇妙である事だけは理解していた。相賀は、真崎のような志士を取り締まる側の男なのだ。
(何か策略があるのだろうな)
それは、少し聞いてみたい気がした。そのくらいの権利を主張できるほど、自分は勤王派との争いに関わっている。
昨年の秋から、夜須勤王党の志士や夜須に流入する不逞浪士を斬っていた。それはもう反吐が出るほどで、その甲斐あってか、家業と呼ぶべき人生の幕引きに、些か慣れる事が出来た。
人を斬る。その行為が息をするように自然な行為となっても、夜な夜な苦しめる亡者の呻きが聞こえなくなったわけではない。日向峠で初めて人を殺して以来、夜は長くなる一方である。
だが、その勤王狩りも真崎を斬る事で粗方終わると父に言われた。橘民部の叛乱騒動も収束に向かいつつあり、夜須藩内に於いては、真崎さえ消せば勤王熱も冷めるとの見込みらしい。江戸でも、田沼が鎖国解禁を先送りにする方針を示しており、勤王派が騒ぐ理由も無くなっている。
雷蔵にとって、それは喜ばしい事だった。夜須から勤王派が消えるという事は、御上に叛き世を乱そうとする者を駆逐した事になる。それは、民の安寧を現している。その為にも、真崎を斬った後の工作が重要だという事だった。
(それにしてもだ……)
帝や朝廷を敬う。それは判る。開国に反対するのも判る。だが、その思想が人々を狂わせ世を乱し、人々を死に追いやっている。そこまでして、成したいものなのか。志士を斬る度に、雷蔵は無駄な争いに思えてしまう。
「勤王が何だというのだ」
夜の闇に映える桜を一瞥し、独り呟いていた。
本朝の中心には帝がいて、徳河将軍家が政事の頂点にある。志士達はそうした枠組みを壊し、再び帝を政事の頂点にした、即ち朝廷が政事を為す国にしようとしているらしい。
理解が出来ない。数百余年もの間、朝廷は乱世に背を向けずっと眠っていたのだ。そのような組織に国の裁量権を与えたところで、何が出来るというのだ。無駄な兵乱を招き、多くの民を苦しめるだけではないか。
それとも、今の朝廷には多くの民を幸せにできる力があるというのか。
そんなはずはない。そのような力があるのなら、勤王運動がこうも易々と潰されるはずはないはずだ。
(……結局は野心なのだ)
自分達が、思うように政事を成したいという野心。その為に、朝廷を担ぐ。下卑たる志である。その野望が故に、どれだけの人間が泣くのか、全く考えもしない。
尚憲も山藤助二郎も、そうした男だった。結構な志を説く割には、民の事は何も考えていない。自らの志や宿命に陶酔している節があった。だから斬った。
そう思索していると、あの男の顔が脳裏に浮かび、雷蔵の心を暗くさせた。
昨年の初冬。宇美津の湊で決闘し敗れた相手。滝沢求馬である。
この男も志士。だが、妻への想いを断ち切れず、情と志の間で揺れていた。雷蔵はその求馬と戦い、敗れたのだ。技倆で劣っていたと思わなかった。念真流の秘奥・落鳳が通じなかったとはいえ、戦いは終始押していた。それでも敗れたのは、支えていたものが違ったからだと、父に言われた。
海に引き摺り込まれた時、雷蔵は焦りを覚えた。想定していなかった事態だった。それでもすぐに次の手を考え、求馬の首を絞めて殺そうとした。勝利を確信した。しかし、求馬は平然としていた。再び焦った。そして求馬の目を見た時、勝てないと悟った。求馬は涅槃の域に達していたのだ。
案の定、先に息が切れて、意識を失った。本来そこで死ぬはずだったが、あろう事か敵である求馬に命を救われた。
その敗北に、父は平然としていた。厳しい言葉一つ、投げ掛けてくれなかった。それが雷蔵の心を余計に暗くさせた。
一方生き残った求馬は、妻と共に西国に落ち延びたという。同僚であった辻村と父が、何やら手引きをしたらしいのだ。それもまた、雷蔵の心を苦しめた。
(兎に角、今は真崎を殺す事を考えねば)
雷蔵は気持ちを切り替え、無銘の刀を引き寄せた。そして、抜いてみる。反りが浅く、身が厚い。父に与えられた、新しい刀である。使い慣れた刀は、自信と共に宇美津の海深くに沈んでしまったのだ。
自信は無いが、畏れも無い。そして、気負いも無いつもりだった。しかし、自然と喉は渇く。また水を飲み、水筒は空になってしまった。
この春に、元服をした。父に、雷蔵の他に経玄という諱も与えられた。だが、何かが変わったわけではなかった。夜須藩士たる覚悟も、御手先役たる覚悟も、昨年の旅で固めた。名が変わっただけだとしか思わない。それでも無意識の気負いが、心のどこかにある。
それは、無理もないのかもしれない。今夜が、一人前の武士としての初陣なのだ。そして、求馬に敗れた失態の挽回は、今夜の働きにかかっている。
城下の西、弁分町にある空き家の二階。平山雷蔵は、灯り一つない部屋で、一人息を殺して待っていた。
まだ夜は寒い。火の温もりが恋しくなるような気温だが、今の雷蔵には、それを必要としなかった。
寂とした闇と孤独。その中で緊張を強いられてはいるが、それが妙に心地よくあるのだ。身の内に燃える熱もある。
お役目である。勿論、それは殺しだった。
獲物とも呼べる標的の男は近くの料亭にいて、今はこうして出てくるのを待っている。何か動きがあれば、中にいる協力者から知らせが入る手筈になっていた。
料亭の名は、〔秀松〕という。分限者御用達の名店で、夜須二十六万石を代表する格式を有すると名高い。故に、藩政を揺るがすような陰謀が画策されて来た場所であると、まことしやかに囁かれている。
(予定ではもう少しか)
男が、中に入って一刻ぐらいは過ぎている。一刻と四半刻弱。それを目処に、男が秀松を出るという話を、協力者から聞いていた。
(あと四半刻……)
計算ではそうなる。ただ、果たして時間通りに出て来てくれるかどうかは判らない。
雷蔵は協力者というものを信用はしていない。そもそも、協力者という存在の素性を知らされていない。そのような胡乱な者を、簡単に信用する事は出来ない。信じられるのは、自らの耳目だけ。そう父である、平山清記に何度も言い聞かせられてきた。
雷蔵は喉の乾きを覚え、竹筒の水を一口だけ含んだ。
男の名は、真崎惣蔵という。武士である。三十五歳。身分は徒士組格と高くないが、下士や百姓を相手に尚武塾という私塾を谷村に開き、剣術と学問を教えている。家族は身分に釣り合った妻と、まだ幼い男児が一人。雷蔵は一度だけ、その暮し振りを覗いた事があるが、至極質素なものだ。
その真崎を殺す。それが年が明けた安永八年最初の、そして元服し小弥太から雷蔵に名を改めて初めて任されたお役目である。
ただ、真崎を殺すだけではない。殺した後に、少し細工を加える必要がある。殺すだけならいつでも出来るが、細工は今日というこの日にしか出来ない。それが上手く行かなければ、成功ではないと父に念を押されていた。面倒だと思うが、そうした手間を掛けざる得ない理由が、真崎という男にはある。
真崎は勤王の志士なのだ。それも、ただの志士ではない。武富陣内、館林簡陽、尚憲が亡き後に夜須勤王党の盟主に推された最後の大物なのである。剣は光当流の免許取りで、剣名が藩内外にも鳴り響く腕前。加えて学問も修めて、その人望は絶大だった。
「生かしておいては危うい男」
そう言った父の声が、耳に蘇った。
何故危ういのか? それを訊くと、黒河藩との関係と言われた。
黒河藩は東北最大の外様藩で、かつては陸奥の一部だった羽仙国を有する国持ちである。藩主の伊達蝦夷守は、勤王の志が篤く、東北近隣の志士を召し抱えては保護しているという。東北への藩屏として夜須に配された譜代の栄生家にとって、伊達家は仮想敵国であり、常に意識しなければならない相手であった。
その黒河藩と真崎は、親密な関係にある。何でも東北遊学の折には、蝦夷守に拝謁を賜ったらしく、現に今も夜須勤王党立て直しの為に、密かな支援をしているという報告があったそうだ。
故に表立って始末すると、真崎の信奉者の反発を招く結果となる。これを機に、黒河藩が何か仕掛ける口実を与えるかもしれない。藩としては、下火になった勤王運動を再燃させぬよう、秘密裏かつ確実に斬らねばならない厄介な男だった。
その真崎が、今まさに秀松で相賀舎人という男と密会していた。
相賀舎人は、夜須藩の中老である。藩校の学問師範をしていた所を、その学識を栄生利景によって見出されたという。
まず祐筆に取り立てられ、そこから町奉行で結果を出し若年寄を経て中老に昇進した。八艘飛びのような出世が出来たのも、利景の権力と威光が盤石だからだろう。抜擢に反対しそうな門閥も、今は日陰で鬱屈とした日々を過ごしている。
父も、この相賀については藩随一の切れ者と評していた。藩を支える吏僚になるとも。雷蔵が、相賀という男について知っている事は、このぐらいだった。一度窮地を救ったが、まともに会話もしていない。
しかし、真崎と相賀という取合せが、奇妙である事だけは理解していた。相賀は、真崎のような志士を取り締まる側の男なのだ。
(何か策略があるのだろうな)
それは、少し聞いてみたい気がした。そのくらいの権利を主張できるほど、自分は勤王派との争いに関わっている。
昨年の秋から、夜須勤王党の志士や夜須に流入する不逞浪士を斬っていた。それはもう反吐が出るほどで、その甲斐あってか、家業と呼ぶべき人生の幕引きに、些か慣れる事が出来た。
人を斬る。その行為が息をするように自然な行為となっても、夜な夜な苦しめる亡者の呻きが聞こえなくなったわけではない。日向峠で初めて人を殺して以来、夜は長くなる一方である。
だが、その勤王狩りも真崎を斬る事で粗方終わると父に言われた。橘民部の叛乱騒動も収束に向かいつつあり、夜須藩内に於いては、真崎さえ消せば勤王熱も冷めるとの見込みらしい。江戸でも、田沼が鎖国解禁を先送りにする方針を示しており、勤王派が騒ぐ理由も無くなっている。
雷蔵にとって、それは喜ばしい事だった。夜須から勤王派が消えるという事は、御上に叛き世を乱そうとする者を駆逐した事になる。それは、民の安寧を現している。その為にも、真崎を斬った後の工作が重要だという事だった。
(それにしてもだ……)
帝や朝廷を敬う。それは判る。開国に反対するのも判る。だが、その思想が人々を狂わせ世を乱し、人々を死に追いやっている。そこまでして、成したいものなのか。志士を斬る度に、雷蔵は無駄な争いに思えてしまう。
「勤王が何だというのだ」
夜の闇に映える桜を一瞥し、独り呟いていた。
本朝の中心には帝がいて、徳河将軍家が政事の頂点にある。志士達はそうした枠組みを壊し、再び帝を政事の頂点にした、即ち朝廷が政事を為す国にしようとしているらしい。
理解が出来ない。数百余年もの間、朝廷は乱世に背を向けずっと眠っていたのだ。そのような組織に国の裁量権を与えたところで、何が出来るというのだ。無駄な兵乱を招き、多くの民を苦しめるだけではないか。
それとも、今の朝廷には多くの民を幸せにできる力があるというのか。
そんなはずはない。そのような力があるのなら、勤王運動がこうも易々と潰されるはずはないはずだ。
(……結局は野心なのだ)
自分達が、思うように政事を成したいという野心。その為に、朝廷を担ぐ。下卑たる志である。その野望が故に、どれだけの人間が泣くのか、全く考えもしない。
尚憲も山藤助二郎も、そうした男だった。結構な志を説く割には、民の事は何も考えていない。自らの志や宿命に陶酔している節があった。だから斬った。
そう思索していると、あの男の顔が脳裏に浮かび、雷蔵の心を暗くさせた。
昨年の初冬。宇美津の湊で決闘し敗れた相手。滝沢求馬である。
この男も志士。だが、妻への想いを断ち切れず、情と志の間で揺れていた。雷蔵はその求馬と戦い、敗れたのだ。技倆で劣っていたと思わなかった。念真流の秘奥・落鳳が通じなかったとはいえ、戦いは終始押していた。それでも敗れたのは、支えていたものが違ったからだと、父に言われた。
海に引き摺り込まれた時、雷蔵は焦りを覚えた。想定していなかった事態だった。それでもすぐに次の手を考え、求馬の首を絞めて殺そうとした。勝利を確信した。しかし、求馬は平然としていた。再び焦った。そして求馬の目を見た時、勝てないと悟った。求馬は涅槃の域に達していたのだ。
案の定、先に息が切れて、意識を失った。本来そこで死ぬはずだったが、あろう事か敵である求馬に命を救われた。
その敗北に、父は平然としていた。厳しい言葉一つ、投げ掛けてくれなかった。それが雷蔵の心を余計に暗くさせた。
一方生き残った求馬は、妻と共に西国に落ち延びたという。同僚であった辻村と父が、何やら手引きをしたらしいのだ。それもまた、雷蔵の心を苦しめた。
(兎に角、今は真崎を殺す事を考えねば)
雷蔵は気持ちを切り替え、無銘の刀を引き寄せた。そして、抜いてみる。反りが浅く、身が厚い。父に与えられた、新しい刀である。使い慣れた刀は、自信と共に宇美津の海深くに沈んでしまったのだ。
自信は無いが、畏れも無い。そして、気負いも無いつもりだった。しかし、自然と喉は渇く。また水を飲み、水筒は空になってしまった。
この春に、元服をした。父に、雷蔵の他に経玄という諱も与えられた。だが、何かが変わったわけではなかった。夜須藩士たる覚悟も、御手先役たる覚悟も、昨年の旅で固めた。名が変わっただけだとしか思わない。それでも無意識の気負いが、心のどこかにある。
それは、無理もないのかもしれない。今夜が、一人前の武士としての初陣なのだ。そして、求馬に敗れた失態の挽回は、今夜の働きにかかっている。
0
お気に入りに追加
33
あなたにおすすめの小説
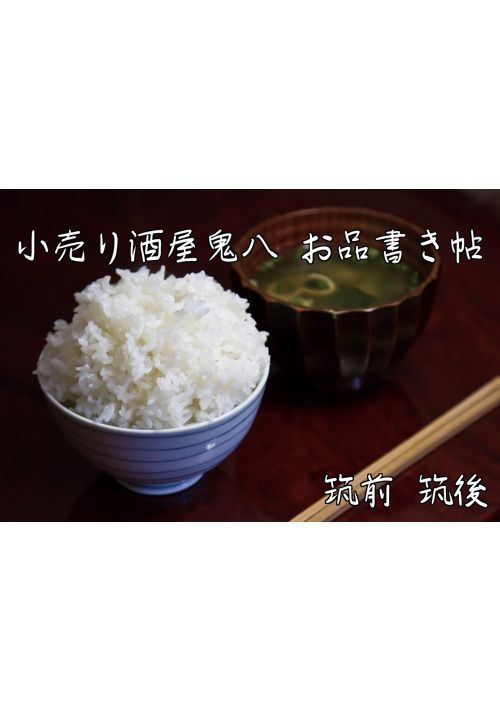
【受賞作】小売り酒屋鬼八 人情お品書き帖
筑前助広
歴史・時代
幸せとちょっぴりの切なさを感じるお品書き帖です――
野州夜須藩の城下・蔵前町に、昼は小売り酒屋、夜は居酒屋を営む鬼八という店がある。父娘二人で切り盛りするその店に、六蔵という料理人が現れ――。
アルファポリス歴史時代小説大賞特別賞「狼の裔」、同最終候補「天暗の星」ともリンクする、「夜須藩もの」人情ストーリー。

南町奉行所お耳役貞永正太郎の捕物帳
勇内一人
歴史・時代
第9回歴史・時代小説大賞奨励賞受賞作品に2024年6月1日より新章「材木商桧木屋お七の訴え」を追加しています(続きではなく途中からなので、わかりづらいかもしれません)
南町奉行所吟味方与力の貞永平一郎の一人息子、正太郎はお多福風邪にかかり両耳の聴覚を失ってしまう。父の跡目を継げない彼は吟味方書物役見習いとして南町奉行所に勤めている。ある時から聞こえない正太郎の耳が死者の声を拾うようになる。それは犯人や証言に不服がある場合、殺された本人が異議を唱える声だった。声を頼りに事件を再捜査すると、思わぬ真実が発覚していく。やがて、平一郎が喧嘩の巻き添えで殺され、正太郎の耳に亡き父の声が届く。
表紙はパブリックドメインQ 著作権フリー絵画:小原古邨 「月と蝙蝠」を使用しております。
2024年10月17日〜エブリスタにも公開を始めました。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

仇討ちの娘
サクラ近衛将監
歴史・時代
父の仇を追う姉弟と従者、しかしながらその行く手には暗雲が広がる。藩の闇が仇討ちを様々に妨害するが、仇討の成否や如何に?娘をヒロインとして思わぬ人物が手助けをしてくれることになる。
毎週木曜日22時の投稿を目指します。

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)
三矢由巳
歴史・時代
時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。
佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。
幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。
ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。
又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。
海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。
一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。
事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。
果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。
シロの鼻が真実を追い詰める!
別サイトで発表した作品のR15版です。

剣客逓信 ―明治剣戟郵便録―
三條すずしろ
歴史・時代
【第9回歴史・時代小説大賞:痛快! エンタメ剣客賞受賞】
明治6年、警察より早くピストルを装備したのは郵便配達員だった――。
維新の動乱で届くことのなかった手紙や小包。そんな残された思いを配達する「御留郵便御用」の若者と老剣士が、時に不穏な明治の初めをひた走る。
密書や金品を狙う賊を退け大切なものを届ける特命郵便配達人、通称「剣客逓信(けんかくていしん)」。
武装する必要があるほど危険にさらされた初期の郵便時代、二人はやがてさらに大きな動乱に巻き込まれ――。
※エブリスタでも連載中

旅路ー元特攻隊員の願いと希望ー
ぽんた
歴史・時代
舞台は1940年代の日本。
軍人になる為に、学校に入学した
主人公の田中昴。
厳しい訓練、激しい戦闘、苦しい戦時中の暮らしの中で、色んな人々と出会い、別れ、彼は成長します。
そんな彼の人生を、年表を辿るように物語りにしました。
※この作品は、残酷な描写があります。
※直接的な表現は避けていますが、性的な表現があります。
※「小説家になろう」「ノベルデイズ」でも連載しています。

大絶滅 2億年後 -原付でエルフの村にやって来た勇者たち-
半道海豚
SF
200万年後の姉妹編です。2億年後への移住は、誰もが思いもよらない結果になってしまいました。推定2億人の移住者は、1年2カ月の間に2億年後へと旅立ちました。移住者2億人は11万6666年という長い期間にばらまかれてしまいます。結果、移住者個々が独自に生き残りを目指さなくてはならなくなります。本稿は、移住最終期に2億年後へと旅だった5人の少年少女の奮闘を描きます。彼らはなんと、2億年後の移動手段に原付を選びます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















