19 / 24
Risoluto 〔決然と〕
19
しおりを挟む
「あーやばいかも」朝、目が覚めたその瞬間。奏始は自分の体の熱っぽさを感じて一人ごちた。抑制剤を使わないヒートは人生で2回目のことだ。初めてヒートを経験して以来になる。市販の薬では発情期のフェロモンや性衝動を完全に抑えることはできない。だからこれまで行きずりの関係に頼ってきたわけだが、今回は話が違う。奏始は初めて、自らの意思でαに体を差し出す。
のろのろと準備をしている間にも、体内にこもる熱はひどくなる。「こんなにきつかったっけ」と初めてのヒートを思い返しながら、奏始は家を出た。
この状態で電車に乗るわけにはいかない。Ω専用のタクシーを呼んで、真尋の家まで乗車することにした。Ω専用タクシーはヒート時など、公共交通機関を使用できない時に使える交通手段だ。奏始も何度か利用したことはある。料金は通常に比べて高いが、その分、運転手は必ずΩであることや、緊急抑制剤が常備されていること、またシートは多少汚れても大丈夫な仕様になっている。タクシーに乗ってすぐ、奏始は己のαに連絡を入れた。太陽が高く昇り始めた時間。すでに起きていたのだろう、真尋は1コールで通話に応じた。
「何かあったか?」
「ふふ、一言目がそれ?」
「朝弱いお前がこんな時間に連絡してくるのが異常だろ」
「確かに」
「で? どうした?」
「ヒート始まったから今すぐそっち行くね。というかもう向かってる」
「は!? お前、いや、向かってる? どうやって? まさか電車じゃないだろうな」
「まさか。Ωタクシーに乗ってる。後20分くらいで着くから」
「……わかった。待ってる」
常に無い焦った声を出す真尋に笑いながら通話を終える。こんなにも自分を案じてくれる存在がいることがくすぐったい。
ずっと迷っていた。想いを伝えて、通じ合って、その先は? αとΩである以上、番になるのが自然なんだろう。互いのバース性の相性も良いという確信もあった。初めて会ったときにそのフェロモンを不快に感じなかったことが何よりの証拠。でも、と臆病な自分が囁く。
真尋は本当は自分なんかが関わり合えないような地位のαだろう。ちょっと調べればわかることだ。宮瀬真尋。日本屈指の医療系グループの御曹司。家を飛び出して音楽に進んだと語るインタビュー記事も読んだ。だからといって親兄弟との交流が途絶えているということもなく、時折食事しに帰ったりもしているようだ。
じゃあ自分は? 父親が誰かもわからない。母親ももういない。高卒でΩ雇用の工場働き。奏始には何もない。
端的に言えば奏始は怯んでいた。偶然、あの夜真尋が奏始のピアノを聞いた。そこから余りにも自分に都合の良いように何もかもが進んでいっている。上手くいっているのに、こんなことを考えるのはわがままだと思う。勝手に卑屈になって、勝手に怯えている。番というのはΩにとって一生に一度の契約だ。αが多数のΩと契約できるのに対して、Ωからは唯一無二。破棄されれば気が狂う苦しみを味わうし、破棄されなくてもヒートを慰められるのは番のαだけになるから、冷遇されればそれもまた苦しむことになる。真尋がそういうことをする人間だとは思っていない。でも、どこかで信じ切れていなかったのかもしれない。自分の音楽に自信はある。でもそれを失くせば、奏始はそこらにいる人間と大差ない。いや、それよりも、もっと、何も持たない人間で。それが露わになることが怖いのだ。でも、真尋はそんな奏始を急かすことなくじっと待っていてくれた。慈しみ、ゆっくりと愛を与えてくれた。αにとってΩなんか取るに足らない存在なはずなのに。でも、真尋はそんな奏始に選択権をくれた。
だからもういいかと思ったのだ。自分の音楽を見つけてくれて、自分のことも愛すると言ってくれた。そんな真尋に返せるものはなんだってあげたい、なんて考えた時点で奏始もきっと真尋を手放す気なんてなかった。
見慣れたマンションの外には真尋が立っていた。タクシーを降りて、人目も気にせずその胸に飛び込む。息を吸い込むと、体の中に真尋の香りが広がった。白檀のような少しオリエンタルな匂い。うっとりと目を細めると、それに呼応して自らのフェロモンが濃くなったのがわかった。真尋が一つ舌打ちをする。
ほとんど抱えられるようにして、真尋の部屋までたどり着き、そのままベッドに放り込まれた。
「お前な、全部急すぎるんだよ。準備ギリギリだったぞ」
「準備?」
「ヒート中は何もできなくなるだろ。すぐに食べれるものとか、タオルとか、必要なもの揃えずにおっぱじめて見ろよ。死体を二つ作りたいか?」
「……何か詳しいね」
「調べたんだよ。言っとくけど、ヒート中のΩを相手にすんのは俺も初めてだからな。自分がどうなるかなんてわからん」
仰向けの奏始に覆い被さる体勢の真尋の顔は、暗がりになってよく見えない。でも目がギラギラと光っているのはわかって、奏始はごくりと唾をのみ込んだ。
「俺も。抑制剤無しにヒート過ごすの初めてだから。……引かないでね」
奏始の気弱な付け加えを鼻で笑って、真尋の唇が降ってくる。額に、頬に、鼻先に、唇に。いつの間にか服が取り払われ、剥き出しなった肩に、鎖骨に。触れられるたびにそこがじんと熱くなる。でも決定的な刺激は与えられない。 ベッドの上でもどかしく身をよじる奏始に覆いかぶさってくる真尋の体から、むせ返るようなフェロモンが発されて肺に染み込んでいく。冷たいシーツの感触が気持ちいい。でも、足りない。
「まひろ」
「噛んでいいか?」
項に指が這わされて、何度もそこもなぞる。その感覚がたまらなくて、もうそれだけでイッてしまいそうだ。前戯も何もない。キスだってまだ。でも早く噛んでもらわないと気が狂いそうだ。お互いにお互いを番にしたくて、もう限界だった。
「はやく、はやくして」
言い終わるや否や、唇が項に触れた。熱い舌が、一度そこを舐めて、そして鋭い犬歯が深く突き立てられた。
「っっっぁッ」
声にならない声を発して、のけ反る。体が作り変わる感覚が気持ち良すぎて、それから逃れたいのに更に深く項を差し出すような格好で自分を無意識に苦しめる。真尋が噛み跡に滲む血を丹念に舐めとる度に、そこがピリピリと痛んで、その痛みが否応なしに番になったのだとに奏始に伝えた。
「っは、ん、これで、もう真尋は俺のものだな」
「ふ、そうだな。まあ、お前も俺のだけどな」
頭の芯がじんと痺れる。いろんな感情が溢れて、入り混じって、ぐちゃぐちゃになった。なんだかわからないのに、涙が止まらない。
「なんで泣くんだ」
困ったように笑って、真尋が俺の涙に唇を寄せる。
「だって、だってぇ」
一層止まらなくなって子どものように泣きじゃくる奏始を、力強い腕があやすように抱き寄せる。肌と肌が重なるのが気持ちよくて、思わず声が漏れた。
「泣くのか感じるのかどっちかにしろ」
ふ、と真尋が笑って、俺の肌に手を這わせ始めた。首から始まり、背を通り、いたずらに胸の尖りをくすぐり、腰を撫で、先走りを零すモノの先端を掠めて、足まで余すことなく撫で下ろされる。骨ばった手の感触に、体が震えた。
「ふ、あ」
「奏始」
熱の籠もった声で名前を呼ばれる。唇にキスが降ってきた。食むように何度も重ね合わされて、そのうちに熱い舌が割り入ってくる。我が物顔で口内を蹂躪して、歯列をなぞり、舌を吸われる。体を這っていた指が、しとどに濡れた秘所へ至った。つぷりと指が侵入する。入り口を広げるようにかき回してから、内壁をなぞって奥へ奥へ、長い指が進む。器用な指はすぐに感じるしこりを探り当てて、重点的にそこを擦った。その刺激に背がのけ反る。
「ぅあ、は、まひろ」
「ん?」
「もっと。ね、はやく」
ヒートで高まった体には、指一本の感覚はもどかしい。もっと激しく。強烈な快感が欲しい。
漏れ出る声の合間で強請れば、指がもう一本増やされた。でも足りない。
「煽るな。優しくしたい」
「やだ、もっと強くして、まひろ」
優しい刺激がもはや辛い。ぐずぐずと溶けた声で何度も名前を呼べば、覆い被さった真尋がぐっと息を詰めたのがわかった。フェロモンが密度を増して奏始を包む。窒息しそうなくらい、甘くむせ返る。
「馬鹿だな。もう知らないぞ」
腰を強く掴んで、真尋が熱を俺の中に押し込んだ。待ちわびた刺激に、喉を曝け出して身をよじる。掴まれた手に逃げは許されない。
「っあ、ん、ひぅ」
馴染ませるようにゆっくりと腰が動かされて、そうかと思えば、急に奥まで突き入れられる。
「ん、あ、あ」
壊れたおもちゃのように、掠れた声がひっきりなしに出る。前立腺を突かれれば、その刺激は耐えられるものではなくて、真尋の背中に縋り付いた。そうすれば一層深く自分から引き寄せることになって、より快感を拾ってしまう。こんこんと最奥を突かれるのも気持ち良すぎて、もう訳がわからない。
「っふ、あ、んン、や」
熱の先端が降りてきた子宮の入り口を破って、先へ進もうとする。頭のどこかではダメだと言っているのに、溶けた思考はそれに酷く喜んで、きゅうきゅうとナカが収縮する。
「や、だめ、ぅぁあ、ん」
「気持ちいいな」
「ぁ、や、きもち、きもちからだめ」
「ダメじゃないだろ」
もうただ快感を求めて喘ぐ事しかできない。涙が滲んで霞む視界に、歪んだ表情の真尋が映る。掠れた声と、荒い呼吸を零す軽く開いた唇に、視線が囚われる。ダメだ、どこもかしこも気持ちがいい。「だめになる」なんて無意識に発していたらしい。「ダメになればいい。時間はたっぷりあるんだから」という真尋の言葉を最後に、奏始の思考は完全にヒートに飲まれた。
のろのろと準備をしている間にも、体内にこもる熱はひどくなる。「こんなにきつかったっけ」と初めてのヒートを思い返しながら、奏始は家を出た。
この状態で電車に乗るわけにはいかない。Ω専用のタクシーを呼んで、真尋の家まで乗車することにした。Ω専用タクシーはヒート時など、公共交通機関を使用できない時に使える交通手段だ。奏始も何度か利用したことはある。料金は通常に比べて高いが、その分、運転手は必ずΩであることや、緊急抑制剤が常備されていること、またシートは多少汚れても大丈夫な仕様になっている。タクシーに乗ってすぐ、奏始は己のαに連絡を入れた。太陽が高く昇り始めた時間。すでに起きていたのだろう、真尋は1コールで通話に応じた。
「何かあったか?」
「ふふ、一言目がそれ?」
「朝弱いお前がこんな時間に連絡してくるのが異常だろ」
「確かに」
「で? どうした?」
「ヒート始まったから今すぐそっち行くね。というかもう向かってる」
「は!? お前、いや、向かってる? どうやって? まさか電車じゃないだろうな」
「まさか。Ωタクシーに乗ってる。後20分くらいで着くから」
「……わかった。待ってる」
常に無い焦った声を出す真尋に笑いながら通話を終える。こんなにも自分を案じてくれる存在がいることがくすぐったい。
ずっと迷っていた。想いを伝えて、通じ合って、その先は? αとΩである以上、番になるのが自然なんだろう。互いのバース性の相性も良いという確信もあった。初めて会ったときにそのフェロモンを不快に感じなかったことが何よりの証拠。でも、と臆病な自分が囁く。
真尋は本当は自分なんかが関わり合えないような地位のαだろう。ちょっと調べればわかることだ。宮瀬真尋。日本屈指の医療系グループの御曹司。家を飛び出して音楽に進んだと語るインタビュー記事も読んだ。だからといって親兄弟との交流が途絶えているということもなく、時折食事しに帰ったりもしているようだ。
じゃあ自分は? 父親が誰かもわからない。母親ももういない。高卒でΩ雇用の工場働き。奏始には何もない。
端的に言えば奏始は怯んでいた。偶然、あの夜真尋が奏始のピアノを聞いた。そこから余りにも自分に都合の良いように何もかもが進んでいっている。上手くいっているのに、こんなことを考えるのはわがままだと思う。勝手に卑屈になって、勝手に怯えている。番というのはΩにとって一生に一度の契約だ。αが多数のΩと契約できるのに対して、Ωからは唯一無二。破棄されれば気が狂う苦しみを味わうし、破棄されなくてもヒートを慰められるのは番のαだけになるから、冷遇されればそれもまた苦しむことになる。真尋がそういうことをする人間だとは思っていない。でも、どこかで信じ切れていなかったのかもしれない。自分の音楽に自信はある。でもそれを失くせば、奏始はそこらにいる人間と大差ない。いや、それよりも、もっと、何も持たない人間で。それが露わになることが怖いのだ。でも、真尋はそんな奏始を急かすことなくじっと待っていてくれた。慈しみ、ゆっくりと愛を与えてくれた。αにとってΩなんか取るに足らない存在なはずなのに。でも、真尋はそんな奏始に選択権をくれた。
だからもういいかと思ったのだ。自分の音楽を見つけてくれて、自分のことも愛すると言ってくれた。そんな真尋に返せるものはなんだってあげたい、なんて考えた時点で奏始もきっと真尋を手放す気なんてなかった。
見慣れたマンションの外には真尋が立っていた。タクシーを降りて、人目も気にせずその胸に飛び込む。息を吸い込むと、体の中に真尋の香りが広がった。白檀のような少しオリエンタルな匂い。うっとりと目を細めると、それに呼応して自らのフェロモンが濃くなったのがわかった。真尋が一つ舌打ちをする。
ほとんど抱えられるようにして、真尋の部屋までたどり着き、そのままベッドに放り込まれた。
「お前な、全部急すぎるんだよ。準備ギリギリだったぞ」
「準備?」
「ヒート中は何もできなくなるだろ。すぐに食べれるものとか、タオルとか、必要なもの揃えずにおっぱじめて見ろよ。死体を二つ作りたいか?」
「……何か詳しいね」
「調べたんだよ。言っとくけど、ヒート中のΩを相手にすんのは俺も初めてだからな。自分がどうなるかなんてわからん」
仰向けの奏始に覆い被さる体勢の真尋の顔は、暗がりになってよく見えない。でも目がギラギラと光っているのはわかって、奏始はごくりと唾をのみ込んだ。
「俺も。抑制剤無しにヒート過ごすの初めてだから。……引かないでね」
奏始の気弱な付け加えを鼻で笑って、真尋の唇が降ってくる。額に、頬に、鼻先に、唇に。いつの間にか服が取り払われ、剥き出しなった肩に、鎖骨に。触れられるたびにそこがじんと熱くなる。でも決定的な刺激は与えられない。 ベッドの上でもどかしく身をよじる奏始に覆いかぶさってくる真尋の体から、むせ返るようなフェロモンが発されて肺に染み込んでいく。冷たいシーツの感触が気持ちいい。でも、足りない。
「まひろ」
「噛んでいいか?」
項に指が這わされて、何度もそこもなぞる。その感覚がたまらなくて、もうそれだけでイッてしまいそうだ。前戯も何もない。キスだってまだ。でも早く噛んでもらわないと気が狂いそうだ。お互いにお互いを番にしたくて、もう限界だった。
「はやく、はやくして」
言い終わるや否や、唇が項に触れた。熱い舌が、一度そこを舐めて、そして鋭い犬歯が深く突き立てられた。
「っっっぁッ」
声にならない声を発して、のけ反る。体が作り変わる感覚が気持ち良すぎて、それから逃れたいのに更に深く項を差し出すような格好で自分を無意識に苦しめる。真尋が噛み跡に滲む血を丹念に舐めとる度に、そこがピリピリと痛んで、その痛みが否応なしに番になったのだとに奏始に伝えた。
「っは、ん、これで、もう真尋は俺のものだな」
「ふ、そうだな。まあ、お前も俺のだけどな」
頭の芯がじんと痺れる。いろんな感情が溢れて、入り混じって、ぐちゃぐちゃになった。なんだかわからないのに、涙が止まらない。
「なんで泣くんだ」
困ったように笑って、真尋が俺の涙に唇を寄せる。
「だって、だってぇ」
一層止まらなくなって子どものように泣きじゃくる奏始を、力強い腕があやすように抱き寄せる。肌と肌が重なるのが気持ちよくて、思わず声が漏れた。
「泣くのか感じるのかどっちかにしろ」
ふ、と真尋が笑って、俺の肌に手を這わせ始めた。首から始まり、背を通り、いたずらに胸の尖りをくすぐり、腰を撫で、先走りを零すモノの先端を掠めて、足まで余すことなく撫で下ろされる。骨ばった手の感触に、体が震えた。
「ふ、あ」
「奏始」
熱の籠もった声で名前を呼ばれる。唇にキスが降ってきた。食むように何度も重ね合わされて、そのうちに熱い舌が割り入ってくる。我が物顔で口内を蹂躪して、歯列をなぞり、舌を吸われる。体を這っていた指が、しとどに濡れた秘所へ至った。つぷりと指が侵入する。入り口を広げるようにかき回してから、内壁をなぞって奥へ奥へ、長い指が進む。器用な指はすぐに感じるしこりを探り当てて、重点的にそこを擦った。その刺激に背がのけ反る。
「ぅあ、は、まひろ」
「ん?」
「もっと。ね、はやく」
ヒートで高まった体には、指一本の感覚はもどかしい。もっと激しく。強烈な快感が欲しい。
漏れ出る声の合間で強請れば、指がもう一本増やされた。でも足りない。
「煽るな。優しくしたい」
「やだ、もっと強くして、まひろ」
優しい刺激がもはや辛い。ぐずぐずと溶けた声で何度も名前を呼べば、覆い被さった真尋がぐっと息を詰めたのがわかった。フェロモンが密度を増して奏始を包む。窒息しそうなくらい、甘くむせ返る。
「馬鹿だな。もう知らないぞ」
腰を強く掴んで、真尋が熱を俺の中に押し込んだ。待ちわびた刺激に、喉を曝け出して身をよじる。掴まれた手に逃げは許されない。
「っあ、ん、ひぅ」
馴染ませるようにゆっくりと腰が動かされて、そうかと思えば、急に奥まで突き入れられる。
「ん、あ、あ」
壊れたおもちゃのように、掠れた声がひっきりなしに出る。前立腺を突かれれば、その刺激は耐えられるものではなくて、真尋の背中に縋り付いた。そうすれば一層深く自分から引き寄せることになって、より快感を拾ってしまう。こんこんと最奥を突かれるのも気持ち良すぎて、もう訳がわからない。
「っふ、あ、んン、や」
熱の先端が降りてきた子宮の入り口を破って、先へ進もうとする。頭のどこかではダメだと言っているのに、溶けた思考はそれに酷く喜んで、きゅうきゅうとナカが収縮する。
「や、だめ、ぅぁあ、ん」
「気持ちいいな」
「ぁ、や、きもち、きもちからだめ」
「ダメじゃないだろ」
もうただ快感を求めて喘ぐ事しかできない。涙が滲んで霞む視界に、歪んだ表情の真尋が映る。掠れた声と、荒い呼吸を零す軽く開いた唇に、視線が囚われる。ダメだ、どこもかしこも気持ちがいい。「だめになる」なんて無意識に発していたらしい。「ダメになればいい。時間はたっぷりあるんだから」という真尋の言葉を最後に、奏始の思考は完全にヒートに飲まれた。
41
お気に入りに追加
117
あなたにおすすめの小説

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。

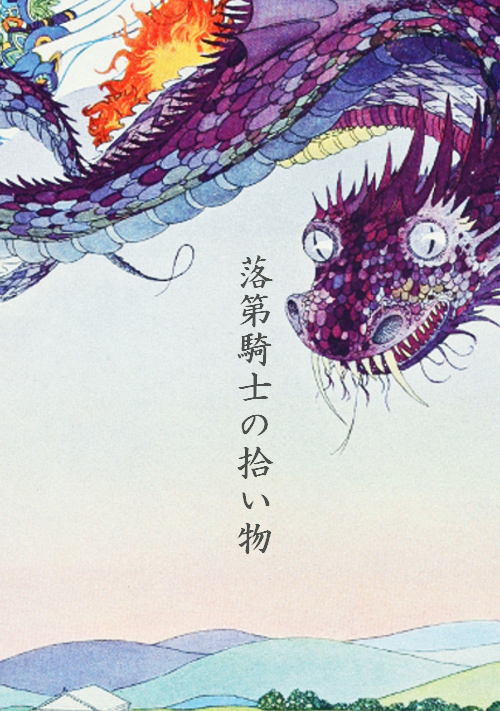
落第騎士の拾い物
深山恐竜
BL
「オメガでございます」
ひと月前、セレガは医者から第三の性別を告知された。将来は勇猛な騎士になることを夢見ていたセレガは、この診断に絶望した。
セレガは絶望の末に”ドラゴンの巣”へ向かう。そこで彼は騎士見習いとして最期の戦いをするつもりであった。しかし、巣にはドラゴンに育てられたという男がいた。男は純粋で、無垢で、彼と交流するうちに、セレガは未来への希望を取り戻す。
ところがある日、発情したセレガは男と関係を持ってしまって……?
オメガバースの設定をお借りしています。
ムーンライトノベルズにも掲載中

実力を隠し「例え長男でも無能に家は継がせん。他家に養子に出す」と親父殿に言われたところまでは計算通りだったが、まさかハーレム生活になるとは
竹井ゴールド
ライト文芸
日本国内トップ5に入る異能力者の名家、東条院。
その宗家本流の嫡子に生まれた東条院青夜は子供の頃に実母に「16歳までに東条院の家を出ないと命を落とす事になる」と予言され、無能を演じ続け、父親や後妻、異母弟や異母妹、親族や許嫁に馬鹿にされながらも、念願適って中学卒業の春休みに東条院家から田中家に養子に出された。
青夜は4月が誕生日なのでギリギリ16歳までに家を出た訳だが。
その後がよろしくない。
青夜を引き取った田中家の義父、一狼は53歳ながら若い妻を持ち、4人の娘の父親でもあったからだ。
妻、21歳、一狼の8人目の妻、愛。
長女、25歳、皇宮警察の異能力部隊所属、弥生。
次女、22歳、田中流空手道場の師範代、葉月。
三女、19歳、離婚したフランス系アメリカ人の3人目の妻が産んだハーフ、アンジェリカ。
四女、17歳、死別した4人目の妻が産んだ中国系ハーフ、シャンリー。
この5人とも青夜は家族となり、
・・・何これ? 少し想定外なんだけど。
【2023/3/23、24hポイント26万4600pt突破】
【2023/7/11、累計ポイント550万pt突破】
【2023/6/5、お気に入り数2130突破】
【アルファポリスのみの投稿です】
【第6回ライト文芸大賞、22万7046pt、2位】
【2023/6/30、メールが来て出版申請、8/1、慰めメール】
【未完】

キンモクセイは夏の記憶とともに
広崎之斗
BL
弟みたいで好きだった年下αに、外堀を埋められてしまい意を決して番になるまでの物語。
小山悠人は大学入学を機に上京し、それから実家には帰っていなかった。
田舎故にΩであることに対する風当たりに我慢できなかったからだ。
そして10年の月日が流れたある日、年下で幼なじみの六條純一が突然悠人の前に現われる。
純一はずっと好きだったと告白し、10年越しの想いを伝える。
しかし純一はαであり、立派に仕事もしていて、なにより見た目だって良い。
「俺になんてもったいない!」
素直になれない年下Ωと、執着系年下αを取り巻く人達との、ハッピーエンドまでの物語。
性描写のある話は【※】をつけていきます。

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!
灯璃
BL
家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。
何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。
仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。
思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。
みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。
※完結しました!ありがとうございました!

美貌の騎士候補生は、愛する人を快楽漬けにして飼い慣らす〜僕から逃げないで愛させて〜
飛鷹
BL
騎士養成学校に在席しているパスティには秘密がある。
でも、それを誰かに言うつもりはなく、目的を達成したら静かに自国に戻るつもりだった。
しかし美貌の騎士候補生に捕まり、快楽漬けにされ、甘く喘がされてしまう。
秘密を抱えたまま、パスティは幸せになれるのか。
美貌の騎士候補生のカーディアスは何を考えてパスティに付きまとうのか……。
秘密を抱えた二人が幸せになるまでのお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















