18 / 24
Calando 〔和らいで〕
18
しおりを挟む
奏始はあまり酒に強くない。それがわかったのは最近のことだ。思考を飛ばすということは余りないが、その代わり足元がおぼつかなくなる。それが心配で飲み会、コンサートの後にはよくある、の日は真尋のマンションに泊めるのが常だ。
今日もその予定だった。演奏家が数名集められた今回のコンサートだったが、間違いなく真尋たちが一番良い演奏をしていたと言える。奏始もそうだったのだろうか、いつもより速いペースで飲んでいたようだった。
「帰るぞ。俺ん家でいいだろ?」
「……いや、自分の家に帰る」
「は?」
いつもと異なる返答に真尋は眉を寄せた。ふらふらのくせして何を言い出すんだ。いや、それよりも、この表情はなんだ。
「ついてきて」
「は? ああ、いや、元から送っていくつもりではあるが」
「よし」
真面目くさった顔で頷いて、奏始はさっさと歩きだす。その足取りは確かだ。
「お前、酔ってたんじゃないのかよ」
「醒めた」
「なんで」
「タクシー? 電車?」
「……タクシー」
「おし」
理由は言わないつもりらしい。不自然に目が合わない。
真尋は今まで奏始の家に行ったことはない。愛しい男の家だ。行ってみたいという気持ちがないわけではなかった。しかし、狭いし楽器も弾けない、何にもない。そう言って困ったように笑うのを押し切ってまで行くのも気が引けた。それが、今夜急に真尋を招く気になったらしい。一体何を考えているのだろうか。
先導されて辿り着いたのは、なんと言うか、率直に言ってかなり古びたアパートだった。錆ついたむき出しの鉄階段が月明かりに鈍く浮かんでいる。その階段をカンカンと音を立てて登って、奏始は後ろを歩く真尋を振り返った。その表情はやはり真面目くさっている。
「何にもないからね」
念押しするようにそう言って、奏始は鍵をカチリと回した。
奏始の部屋に足を踏み入れて、ぐるりと中を見渡して真尋は「へえ」と呟いた。
「なんだよ、言えよ」
「じゃあ遠慮なく。散らかってんな、この部屋」
「うるせえよ!」
「お前が言えって言ったんだろ。……お前ってもしかして片付け苦手なタイプ? そういえばうち来てる時も整理整頓してなかったか……」
何か知らないが緊張している奏始を緩ませたくて、軽口を叩いてみる。電気をつけても薄暗い小さな部屋。キッチンも、ダイニングも、ベッドも。全てが小さな1つの空間に収まっている。築何年なんだろうか。古びた水道からは、ぽつりぽつりとゆっくりと水滴が滲みだしていた。ぶつぶつ言いながらエアコンを操作する奏始を窺う。夏宵の熱のこもった空気が動き始める。
なぜ自分は今夜、ここに案内されたのか。何か伝えたいことがあるからの行動だろうとは思う。口を開くまで待つのが吉か。それとも敢えてつっこんでみるのが吉か。思案しながら、真尋はもう一度ぐるりと部屋を見渡して、はたと気がつく。よくよく見てみれば、物自体は何もない。必要最低限のものがぎゅっと並んでいるだけで、例えば本だとか、写真だとか。そういう生存に必要のない、でも大多数の生活の中に普通にあるようなものは少しもなかった。散らかっているように見えたのは、床に無数の紙が散乱していたからだ。真っ白い紙もあれば、広告のようなものもある。一枚、近所のスーパーだろうチラシを拾い上げて、何気なく裏返して、そこにあったものに真尋は思わず息を飲んだ。更に一枚、もう一枚と手の届く範囲のものを拾い集める。それらにびっしりと書かれていたのは音符。几帳面に定規か何かで引かれた線に、適当に塗りつぶされた音部が並んでいる。まるで書く手が追いつかないというように殴り書きにされたそれらは楽譜だった。
「お前これ……」
隅の方にページ番号が書かれているのに気が付いて、手の中の楽譜を床に並べてみる。気が急いて、思うように手が動かない。ピアノとヴァイオリンの譜面が並んでいく。ざっと目で追いながら、自分の呼吸が浅くなるのがわかった。早く弾きたいと思った。この曲を弾くならどんな表現にするだろうか。今までの演奏を超えるものになるという確信があった。
「これ全部お前が書いた楽譜か?」
「うん。……生きてると、ずっと曲が聞こえるんだ。生活の全てに音がある。譜面に起こして、自分で弾いて。弾き終わったら捨ててをずっと繰り返してきたんだけど、最近はさ、ヴァイオリンの音も聞こえるようになったんだ。前まではピアノだけだった。だから、ああ香坂に弾いてほしいなって思って。そっから……」
思わず目の前の男をかき抱いた。心臓が痛い。何もないこの部屋で、奏始はただ己の音を孤独に追っていたのだろう。そこにお前を受け入れたのだと言われて、それを差し出されて、何も感じない者なんかいるか。こみ上げてくるのが涙だか、愛しさだか分からなくなって、真尋はたまらなくなった。
「俺さ、ずっと自分のこと嫌いだったんだ。Ωでいるのってしんどいんだよ。フェロモンとかヒートのことはもちろん。コンクールには出られないし、スポーツの大会だってエントリーすらできない。働けるのはΩ雇用があるところか風俗がほとんど。いくら頭が良くたって、運動が出来たって何にもできない。何かが得意だとか、好きだとか、そういうことって自分を苦しめる要素にしかならない」
真尋の胸元をぐっと握りしめて、奏始はくぐもった声で語った。
「音楽が好きで、ピアノが好き。ずっとそれだけで生きていきたいと思ってたけど、そんなの叶いっこないって。でも……お前に会った」
「うん」
「無理だって言ってんのに一緒に世界一目指そうとか意味わかんないこと言って、でも本当にコンサートとか出れるようになってさ。挙句の果てに俺のこと好きだとか言い出すし。俺はΩもαも大嫌いで誰とも恋なんかしないし、番にもならないとか密かに覚悟決めてたのに、そんなん全部ぶっとばされたし」
「……うん」
「Ωにとって自分のテリトリーにαを入れるってマジのマジに信頼してないとできないことなのわかってる?」
「……すまん。わかってなかった」
「だろうな。不思議そうな顔してついてきやがって」
「ごめん」
「責任とって俺と番になって」
「うん……うん?」
「だからあ、俺のモンになれって言ってんの!」
思わず体を離そうとすると、奏始が反対にぐっと真尋にしがみついてくる。何が何でも顔を上げないつもりらしい。それでも赤く染まった頬を耳が見えて、真尋は思い切りそこに噛り付きたいような心地を覚えた。
「あーだめだ。俺、ちょっとおかしくなりそう」
「は?」
「お前が可愛くて変になる」
「壊れた?」
「なんでそんな男前なんだ? あー、一生適う気がしない」
「何と戦ってんだよ」
「過去の話とか、バースについていろいろ思ってることとか。追々聞いていこうとか思ってた訳だよ、俺は。で、いろいろ整理がついたら番にしてほしいって改めてプロポーズするかとか考えてた訳。反省してる。俺は甘かった。相手はお前だもんなあ。のんきにそんなこと考えてる暇なんか無いって」
「ディスってる?」
「愛してるっていってんだよ」
腕の中の存在を抱え直して、真尋はうなじに唇を触れさせた。ぴくりと奏始の体が揺れる。それでも真尋の拘束から抜け出そうとはせず、むしろ甘えるようにすり、と額が擦りつけられた。そのことに自分が満たされていくのがわかる。
「……俺はお前と番になりたい。一生そばにいさせてほしい。でも番になったら、何があっても離せない。離れようもんならお前を殺して俺も死ぬくらいは、たぶんする」
「物騒だな」
「俺と番になってくれないか?」
「それを聞いて躊躇いなく番になりたいって思う俺も大概物騒だから、いいよ」
目が熱くなるのを感じて、真尋はゆっくりと息を吐いた。ふわりと奏始から香るレモンが身を包む。甘く優しい、でもさっぱりとしたフェロモンの香り。意識すればあちこちから漂うそれに、体に熱が灯りそうになって、真尋はそっと自らの気を反らした。
「……なんで急にその気になったんだ? ついこの前まで番の話は避けてたくせに」
「……待ってくれてたから。踏み込まずに待ってくれてただろ。いろんなこと。音楽のことに関しては強引なくせにさ。いや、けっこう滲みでてたというか、駄々洩れではあったけど。やたらとうなじ触りたがるし、俺にマーキングで匂いつけるし」
「あー、すまん」
意識的にやっていた部分と、無意識にやってしまっていた部分と。半々ぐらいだろうか。αはその本能的な性質として執着心が強い。これと定めたΩが自分の番になっていないのは実はかなり精神的に負荷がかかる状況だったりする。
「うん。分かってたから。α的にはけっこうストレスだったんだろ。だから申し訳ないなってずっと思ってたんだけど、心の整理がつかなくて。でもそんなストレスかかってまで俺の意思を大事にしてくれるんだなって思ったら、なんかもうどうでもよくなった」
「投げやりだな」
「いや、最高にプラスの投げやりだから。なんか悩んでんの馬鹿らしくなったんだよ。これでも初恋だったし、お前の横に立つのが俺みたいなクソ底辺出身のΩでいいのかとかぐるぐる考えてたんだけどさ」
「待て、初恋? 俺が?」
「今そこどうでもいい! ともかく! お互いに好きなんだったらもう番になればいいじゃんって思ったの! 以上!」
いつまでだって待つつもりだった。自分の意思で真尋を番にしたいと思ってくれるまで何度だって愛を伝えようと思っていたし、信頼してもらえるように過ごしていこうと思っていた。それがきちんと伝わっていたことに、体から力が抜けるようだった。いつだって真尋は己のΩには勝てないようだ。抱きかかえたまま後ろに体を倒すと、抵抗なく奏始は真尋の隣に横たわった。そのことに、また言葉にし得ないこそばゆさを感じる。
「次のヒートいつだ?」
「んー。3日後」
「は!?」
うなじを噛むことでαとΩは番になれる。いつでも出来るのだが、確実なのは発情期の性交時だ。次のヒートに備えるか、と思ったら爆弾が落とされた。ああ、もう、ほんとうに気が抜けない。最初から確信犯だったのだろう。奏始はいたずらが成功したという顔で笑っている。その肩を引っ掴んで、真尋は首筋に歯を立てた。ぎゃあと色気のない声があがる。顔を話すと、そこにはくっきりと歯型がついていた。少し満足して眺めていると、思い切り頭突きをくらって、真尋は呻く羽目になった。
今日もその予定だった。演奏家が数名集められた今回のコンサートだったが、間違いなく真尋たちが一番良い演奏をしていたと言える。奏始もそうだったのだろうか、いつもより速いペースで飲んでいたようだった。
「帰るぞ。俺ん家でいいだろ?」
「……いや、自分の家に帰る」
「は?」
いつもと異なる返答に真尋は眉を寄せた。ふらふらのくせして何を言い出すんだ。いや、それよりも、この表情はなんだ。
「ついてきて」
「は? ああ、いや、元から送っていくつもりではあるが」
「よし」
真面目くさった顔で頷いて、奏始はさっさと歩きだす。その足取りは確かだ。
「お前、酔ってたんじゃないのかよ」
「醒めた」
「なんで」
「タクシー? 電車?」
「……タクシー」
「おし」
理由は言わないつもりらしい。不自然に目が合わない。
真尋は今まで奏始の家に行ったことはない。愛しい男の家だ。行ってみたいという気持ちがないわけではなかった。しかし、狭いし楽器も弾けない、何にもない。そう言って困ったように笑うのを押し切ってまで行くのも気が引けた。それが、今夜急に真尋を招く気になったらしい。一体何を考えているのだろうか。
先導されて辿り着いたのは、なんと言うか、率直に言ってかなり古びたアパートだった。錆ついたむき出しの鉄階段が月明かりに鈍く浮かんでいる。その階段をカンカンと音を立てて登って、奏始は後ろを歩く真尋を振り返った。その表情はやはり真面目くさっている。
「何にもないからね」
念押しするようにそう言って、奏始は鍵をカチリと回した。
奏始の部屋に足を踏み入れて、ぐるりと中を見渡して真尋は「へえ」と呟いた。
「なんだよ、言えよ」
「じゃあ遠慮なく。散らかってんな、この部屋」
「うるせえよ!」
「お前が言えって言ったんだろ。……お前ってもしかして片付け苦手なタイプ? そういえばうち来てる時も整理整頓してなかったか……」
何か知らないが緊張している奏始を緩ませたくて、軽口を叩いてみる。電気をつけても薄暗い小さな部屋。キッチンも、ダイニングも、ベッドも。全てが小さな1つの空間に収まっている。築何年なんだろうか。古びた水道からは、ぽつりぽつりとゆっくりと水滴が滲みだしていた。ぶつぶつ言いながらエアコンを操作する奏始を窺う。夏宵の熱のこもった空気が動き始める。
なぜ自分は今夜、ここに案内されたのか。何か伝えたいことがあるからの行動だろうとは思う。口を開くまで待つのが吉か。それとも敢えてつっこんでみるのが吉か。思案しながら、真尋はもう一度ぐるりと部屋を見渡して、はたと気がつく。よくよく見てみれば、物自体は何もない。必要最低限のものがぎゅっと並んでいるだけで、例えば本だとか、写真だとか。そういう生存に必要のない、でも大多数の生活の中に普通にあるようなものは少しもなかった。散らかっているように見えたのは、床に無数の紙が散乱していたからだ。真っ白い紙もあれば、広告のようなものもある。一枚、近所のスーパーだろうチラシを拾い上げて、何気なく裏返して、そこにあったものに真尋は思わず息を飲んだ。更に一枚、もう一枚と手の届く範囲のものを拾い集める。それらにびっしりと書かれていたのは音符。几帳面に定規か何かで引かれた線に、適当に塗りつぶされた音部が並んでいる。まるで書く手が追いつかないというように殴り書きにされたそれらは楽譜だった。
「お前これ……」
隅の方にページ番号が書かれているのに気が付いて、手の中の楽譜を床に並べてみる。気が急いて、思うように手が動かない。ピアノとヴァイオリンの譜面が並んでいく。ざっと目で追いながら、自分の呼吸が浅くなるのがわかった。早く弾きたいと思った。この曲を弾くならどんな表現にするだろうか。今までの演奏を超えるものになるという確信があった。
「これ全部お前が書いた楽譜か?」
「うん。……生きてると、ずっと曲が聞こえるんだ。生活の全てに音がある。譜面に起こして、自分で弾いて。弾き終わったら捨ててをずっと繰り返してきたんだけど、最近はさ、ヴァイオリンの音も聞こえるようになったんだ。前まではピアノだけだった。だから、ああ香坂に弾いてほしいなって思って。そっから……」
思わず目の前の男をかき抱いた。心臓が痛い。何もないこの部屋で、奏始はただ己の音を孤独に追っていたのだろう。そこにお前を受け入れたのだと言われて、それを差し出されて、何も感じない者なんかいるか。こみ上げてくるのが涙だか、愛しさだか分からなくなって、真尋はたまらなくなった。
「俺さ、ずっと自分のこと嫌いだったんだ。Ωでいるのってしんどいんだよ。フェロモンとかヒートのことはもちろん。コンクールには出られないし、スポーツの大会だってエントリーすらできない。働けるのはΩ雇用があるところか風俗がほとんど。いくら頭が良くたって、運動が出来たって何にもできない。何かが得意だとか、好きだとか、そういうことって自分を苦しめる要素にしかならない」
真尋の胸元をぐっと握りしめて、奏始はくぐもった声で語った。
「音楽が好きで、ピアノが好き。ずっとそれだけで生きていきたいと思ってたけど、そんなの叶いっこないって。でも……お前に会った」
「うん」
「無理だって言ってんのに一緒に世界一目指そうとか意味わかんないこと言って、でも本当にコンサートとか出れるようになってさ。挙句の果てに俺のこと好きだとか言い出すし。俺はΩもαも大嫌いで誰とも恋なんかしないし、番にもならないとか密かに覚悟決めてたのに、そんなん全部ぶっとばされたし」
「……うん」
「Ωにとって自分のテリトリーにαを入れるってマジのマジに信頼してないとできないことなのわかってる?」
「……すまん。わかってなかった」
「だろうな。不思議そうな顔してついてきやがって」
「ごめん」
「責任とって俺と番になって」
「うん……うん?」
「だからあ、俺のモンになれって言ってんの!」
思わず体を離そうとすると、奏始が反対にぐっと真尋にしがみついてくる。何が何でも顔を上げないつもりらしい。それでも赤く染まった頬を耳が見えて、真尋は思い切りそこに噛り付きたいような心地を覚えた。
「あーだめだ。俺、ちょっとおかしくなりそう」
「は?」
「お前が可愛くて変になる」
「壊れた?」
「なんでそんな男前なんだ? あー、一生適う気がしない」
「何と戦ってんだよ」
「過去の話とか、バースについていろいろ思ってることとか。追々聞いていこうとか思ってた訳だよ、俺は。で、いろいろ整理がついたら番にしてほしいって改めてプロポーズするかとか考えてた訳。反省してる。俺は甘かった。相手はお前だもんなあ。のんきにそんなこと考えてる暇なんか無いって」
「ディスってる?」
「愛してるっていってんだよ」
腕の中の存在を抱え直して、真尋はうなじに唇を触れさせた。ぴくりと奏始の体が揺れる。それでも真尋の拘束から抜け出そうとはせず、むしろ甘えるようにすり、と額が擦りつけられた。そのことに自分が満たされていくのがわかる。
「……俺はお前と番になりたい。一生そばにいさせてほしい。でも番になったら、何があっても離せない。離れようもんならお前を殺して俺も死ぬくらいは、たぶんする」
「物騒だな」
「俺と番になってくれないか?」
「それを聞いて躊躇いなく番になりたいって思う俺も大概物騒だから、いいよ」
目が熱くなるのを感じて、真尋はゆっくりと息を吐いた。ふわりと奏始から香るレモンが身を包む。甘く優しい、でもさっぱりとしたフェロモンの香り。意識すればあちこちから漂うそれに、体に熱が灯りそうになって、真尋はそっと自らの気を反らした。
「……なんで急にその気になったんだ? ついこの前まで番の話は避けてたくせに」
「……待ってくれてたから。踏み込まずに待ってくれてただろ。いろんなこと。音楽のことに関しては強引なくせにさ。いや、けっこう滲みでてたというか、駄々洩れではあったけど。やたらとうなじ触りたがるし、俺にマーキングで匂いつけるし」
「あー、すまん」
意識的にやっていた部分と、無意識にやってしまっていた部分と。半々ぐらいだろうか。αはその本能的な性質として執着心が強い。これと定めたΩが自分の番になっていないのは実はかなり精神的に負荷がかかる状況だったりする。
「うん。分かってたから。α的にはけっこうストレスだったんだろ。だから申し訳ないなってずっと思ってたんだけど、心の整理がつかなくて。でもそんなストレスかかってまで俺の意思を大事にしてくれるんだなって思ったら、なんかもうどうでもよくなった」
「投げやりだな」
「いや、最高にプラスの投げやりだから。なんか悩んでんの馬鹿らしくなったんだよ。これでも初恋だったし、お前の横に立つのが俺みたいなクソ底辺出身のΩでいいのかとかぐるぐる考えてたんだけどさ」
「待て、初恋? 俺が?」
「今そこどうでもいい! ともかく! お互いに好きなんだったらもう番になればいいじゃんって思ったの! 以上!」
いつまでだって待つつもりだった。自分の意思で真尋を番にしたいと思ってくれるまで何度だって愛を伝えようと思っていたし、信頼してもらえるように過ごしていこうと思っていた。それがきちんと伝わっていたことに、体から力が抜けるようだった。いつだって真尋は己のΩには勝てないようだ。抱きかかえたまま後ろに体を倒すと、抵抗なく奏始は真尋の隣に横たわった。そのことに、また言葉にし得ないこそばゆさを感じる。
「次のヒートいつだ?」
「んー。3日後」
「は!?」
うなじを噛むことでαとΩは番になれる。いつでも出来るのだが、確実なのは発情期の性交時だ。次のヒートに備えるか、と思ったら爆弾が落とされた。ああ、もう、ほんとうに気が抜けない。最初から確信犯だったのだろう。奏始はいたずらが成功したという顔で笑っている。その肩を引っ掴んで、真尋は首筋に歯を立てた。ぎゃあと色気のない声があがる。顔を話すと、そこにはくっきりと歯型がついていた。少し満足して眺めていると、思い切り頭突きをくらって、真尋は呻く羽目になった。
42
お気に入りに追加
117
あなたにおすすめの小説

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない
月島日向
ライト文芸
俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。
人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。
2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)
。
誰も俺に気付いてはくれない。そう。
2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。
もう、全部どうでもよく感じた。

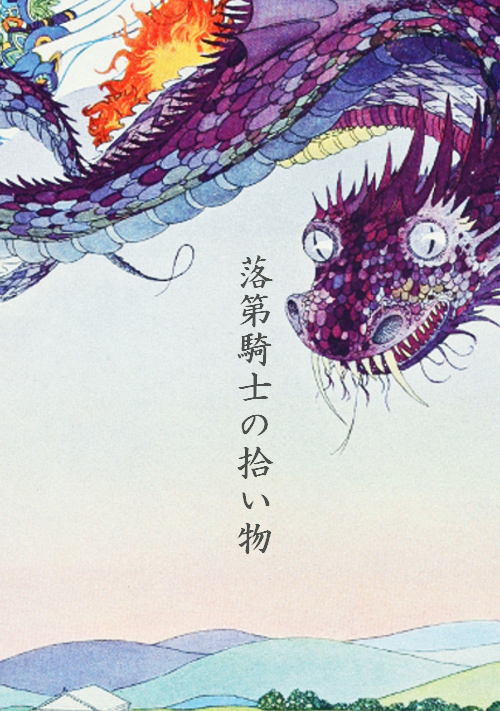
落第騎士の拾い物
深山恐竜
BL
「オメガでございます」
ひと月前、セレガは医者から第三の性別を告知された。将来は勇猛な騎士になることを夢見ていたセレガは、この診断に絶望した。
セレガは絶望の末に”ドラゴンの巣”へ向かう。そこで彼は騎士見習いとして最期の戦いをするつもりであった。しかし、巣にはドラゴンに育てられたという男がいた。男は純粋で、無垢で、彼と交流するうちに、セレガは未来への希望を取り戻す。
ところがある日、発情したセレガは男と関係を持ってしまって……?
オメガバースの設定をお借りしています。
ムーンライトノベルズにも掲載中

実力を隠し「例え長男でも無能に家は継がせん。他家に養子に出す」と親父殿に言われたところまでは計算通りだったが、まさかハーレム生活になるとは
竹井ゴールド
ライト文芸
日本国内トップ5に入る異能力者の名家、東条院。
その宗家本流の嫡子に生まれた東条院青夜は子供の頃に実母に「16歳までに東条院の家を出ないと命を落とす事になる」と予言され、無能を演じ続け、父親や後妻、異母弟や異母妹、親族や許嫁に馬鹿にされながらも、念願適って中学卒業の春休みに東条院家から田中家に養子に出された。
青夜は4月が誕生日なのでギリギリ16歳までに家を出た訳だが。
その後がよろしくない。
青夜を引き取った田中家の義父、一狼は53歳ながら若い妻を持ち、4人の娘の父親でもあったからだ。
妻、21歳、一狼の8人目の妻、愛。
長女、25歳、皇宮警察の異能力部隊所属、弥生。
次女、22歳、田中流空手道場の師範代、葉月。
三女、19歳、離婚したフランス系アメリカ人の3人目の妻が産んだハーフ、アンジェリカ。
四女、17歳、死別した4人目の妻が産んだ中国系ハーフ、シャンリー。
この5人とも青夜は家族となり、
・・・何これ? 少し想定外なんだけど。
【2023/3/23、24hポイント26万4600pt突破】
【2023/7/11、累計ポイント550万pt突破】
【2023/6/5、お気に入り数2130突破】
【アルファポリスのみの投稿です】
【第6回ライト文芸大賞、22万7046pt、2位】
【2023/6/30、メールが来て出版申請、8/1、慰めメール】
【未完】


キンモクセイは夏の記憶とともに
広崎之斗
BL
弟みたいで好きだった年下αに、外堀を埋められてしまい意を決して番になるまでの物語。
小山悠人は大学入学を機に上京し、それから実家には帰っていなかった。
田舎故にΩであることに対する風当たりに我慢できなかったからだ。
そして10年の月日が流れたある日、年下で幼なじみの六條純一が突然悠人の前に現われる。
純一はずっと好きだったと告白し、10年越しの想いを伝える。
しかし純一はαであり、立派に仕事もしていて、なにより見た目だって良い。
「俺になんてもったいない!」
素直になれない年下Ωと、執着系年下αを取り巻く人達との、ハッピーエンドまでの物語。
性描写のある話は【※】をつけていきます。

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜
きよひ
BL
無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員
Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。
そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。
初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。
甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。
第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。
※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)
※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り
初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!
灯璃
BL
家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。
何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。
仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。
思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。
みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。
※完結しました!ありがとうございました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















