お気に入りに追加
505
あなたにおすすめの小説

願いの守護獣 チートなもふもふに転生したからには全力でペットになりたい
戌葉
ファンタジー
気付くと、もふもふに生まれ変わって、誰もいない森の雪の上に寝ていた。
人恋しさに森を出て、途中で魔物に間違われたりもしたけど、馬に助けられ騎士に保護してもらえた。正体はオレ自身でも分からないし、チートな魔法もまだ上手く使いこなせないけど、全力で可愛く頑張るのでペットとして飼ってください!
チートな魔法のせいで狙われたり、自分でも分かっていなかった正体のおかげでとんでもないことに巻き込まれちゃったりするけど、オレが目指すのはぐーたらペット生活だ!!
※「1-7」で正体が判明します。「精霊の愛し子編」や番外編、「美食の守護獣」ではすでに正体が分かっていますので、お気を付けください。
番外編「美食の守護獣 ~チートなもふもふに転生したからには全力で食い倒れたい」
「冒険者編」と「精霊の愛し子編」の間の食い倒れツアーのお話です。
https://www.alphapolis.co.jp/novel/2227451/394680824


子ども扱いしないでください! 幼女化しちゃった完璧淑女は、騎士団長に甘やかされる
佐崎咲
恋愛
旧題:完璧すぎる君は一人でも生きていけると婚約破棄されたけど、騎士団長が即日プロポーズに来た上に甘やかしてきます
「君は完璧だ。一人でも生きていける。でも、彼女には私が必要なんだ」
なんだか聞いたことのある台詞だけれど、まさか現実で、しかも貴族社会に生きる人間からそれを聞くことになるとは思ってもいなかった。
彼の言う通り、私ロゼ=リンゼンハイムは『完璧な淑女』などと称されているけれど、それは努力のたまものであって、本質ではない。
私は幼い時に我儘な姉に追い出され、開き直って自然溢れる領地でそれはもうのびのびと、野を駆け山を駆け回っていたのだから。
それが、今度は跡継ぎ教育に嫌気がさした姉が自称病弱設定を作り出し、代わりに私がこの家を継ぐことになったから、王都に移って血反吐を吐くような努力を重ねたのだ。
そして今度は腐れ縁ともいうべき幼馴染みの友人に婚約者を横取りされたわけだけれど、それはまあ別にどうぞ差し上げますよというところなのだが。
ただ。
婚約破棄を告げられたばかりの私をその日訪ねた人が、もう一人いた。
切れ長の紺色の瞳に、長い金髪を一つに束ね、男女問わず目をひく美しい彼は、『微笑みの貴公子』と呼ばれる第二騎士団長のユアン=クラディス様。
彼はいつもとは違う、改まった口調で言った。
「どうか、私と結婚してください」
「お返事は急ぎません。先程リンゼンハイム伯爵には手紙を出させていただきました。許可が得られましたらまた改めさせていただきますが、まずはロゼ嬢に私の気持ちを知っておいていただきたかったのです」
私の戸惑いたるや、婚約破棄を告げられた時の比ではなかった。
彼のことはよく知っている。
彼もまた、私のことをよく知っている。
でも彼は『それ』が私だとは知らない。
まったくの別人に見えているはずなのだから。
なのに、何故私にプロポーズを?
しかもやたらと甘やかそうとしてくるんですけど。
どういうこと?
============
番外編は思いついたら追加していく予定です。
<レジーナ公式サイト番外編>
「番外編 相変わらずな日常」
レジーナ公式サイトにてアンケートに答えていただくと、書き下ろしweb番外編をお読みいただけます。
いつも攻め込まれてばかりのロゼが居眠り中のユアンを見つけ、この機会に……という話です。
※転載・複写はお断りいたします。

社畜だけど異世界では推し騎士の伴侶になってます⁈
めがねあざらし
BL
気がつくと、そこはゲーム『クレセント・ナイツ』の世界だった。
しかも俺は、推しキャラ・レイ=エヴァンスの“伴侶”になっていて……⁈
記憶喪失の俺に課されたのは、彼と共に“世界を救う鍵”として戦う使命。
しかし、レイとの誓いに隠された真実や、迫りくる敵の陰謀が俺たちを追い詰める――。
異世界で見つけた愛〜推し騎士との奇跡の絆!
推しとの距離が近すぎる、命懸けの異世界ラブファンタジー、ここに開幕!

【完結】冷酷眼鏡とウワサされる副騎士団長様が、一直線に溺愛してきますっ!
楠結衣
恋愛
触ると人の心の声が聞こえてしまう聖女リリアンは、冷酷と噂の副騎士団長のアルバート様に触ってしまう。
(リリアン嬢、かわいい……。耳も小さくて、かわいい。リリアン嬢の耳、舐めたら甘そうだな……いや寧ろ齧りたい……)
遠くで見かけるだけだったアルバート様の思わぬ声にリリアンは激しく動揺してしまう。きっと聞き間違えだったと結論付けた筈が、聖女の試験で必須な魔物についてアルバート様から勉強を教わることに──!
(かわいい、好きです、愛してます)
(誰にも見せたくない。執務室から出さなくてもいいですよね?)
二人きりの勉強会。アルバート様に触らないように気をつけているのに、リリアンのうっかりで毎回触れられてしまう。甘すぎる声にリリアンのドキドキが止まらない!
ところが、ある日、リリアンはアルバート様の声にうっかり反応してしまう。
(まさか。もしかして、心の声が聞こえている?)
リリアンの秘密を知ったアルバート様はどうなる?
二人の恋の結末はどうなっちゃうの?!
心の声が聞こえる聖女リリアンと変態あまあまな声がダダ漏れなアルバート様の、甘すぎるハッピーエンドラブストーリー。
✳︎表紙イラストは、さらさらしるな。様の作品です。
✳︎小説家になろうにも投稿しています♪

【第1章完結】悪役令息に転生して絶望していたら王国至宝のエルフ様にヨシヨシしてもらえるので、頑張って生きたいと思います!
梻メギ
BL
「あ…もう、駄目だ」プツリと糸が切れるように限界を迎え死に至ったブラック企業に勤める主人公は、目覚めると悪役令息になっていた。どのルートを辿っても断罪確定な悪役令息に生まれ変わったことに絶望した主人公は、頑張る意欲そして生きる気力を失い床に伏してしまう。そんな、人生の何もかもに絶望した主人公の元へ王国お抱えのエルフ様がやってきて───!?
【王国至宝のエルフ様×元社畜のお疲れ悪役令息】
▼第2章2025年1月18日より投稿予定
▼この作品と出会ってくださり、ありがとうございます!初投稿になります、どうか温かい目で見守っていただけますと幸いです。
▼こちらの作品はムーンライトノベルズ様にも投稿しております。
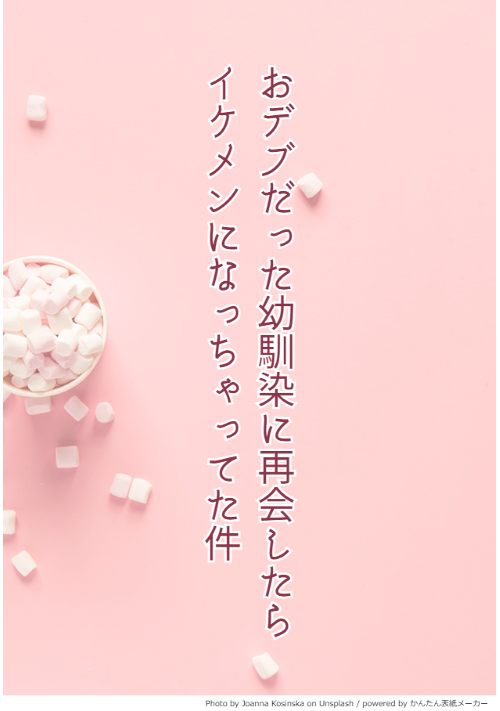
おデブだった幼馴染に再会したら、イケメンになっちゃってた件
実川えむ
恋愛
子供のころチビでおデブちゃんだったあの子が、王子様みたいなイケメン俳優になって現れました。
ちょっと、聞いてないんですけど。
※以前、エブリスタで別名義で書いていたお話です(現在非公開)。
※不定期更新
※カクヨム・ベリーズカフェでも掲載中

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします
文野多咲
恋愛
秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。
夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。
エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。
「ゲルハルトさま、愛しています」
ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。
「エレーヌ、俺はあなたが憎い」
エレーヌは凍り付いた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















