70 / 73
69.アリシア
しおりを挟む
「消えた…………のですか?」
ルイス卿が呆然と呟く。私もすぐには信じられない。
「アベル!」
デラクルス嬢が喜びの声をあげ、レオポルド殿下の外套を羽織っただけの姿で、忠実な下僕に駆け寄った。殿下も慌ててあとを追う。
「ありがとう、アベル。わたくし達を助けてくれたのね」
「セレスティナお嬢様…………」
アベルはふらふらで、立っているのもやっと、という様子だ。
「私からも礼を言う、アベル。そなたとソル聖神官がいなければ、あの危険な男は倒せなかった。よく、ティナと我々を守ってくれた」
「礼には、及びません。私は、セレスティナお嬢様の、望みを叶えるため…………」
アベルの体がぐらり、と、かしぐ。
「アベル!」
反射的にレオポルド殿下がアベルへ手を出した。
その殿下の手を、アベルががっちり、つかむ。
そのまま、にぎっていた緋と黒に染まった短剣を、レオポルド殿下の心臓に突き立てた。
悲鳴があがる。
「レオ様!! なにをするの、アベル!!」
アベルは主君の問いには答えず、どさり、とレオポルド殿下の長身が地面に倒れる。
「レオ様! レオ様っ!!」
デラクルス嬢が半泣きで倒れた殿下にすがる。
レオポルド殿下の心臓に突き立った短剣の刃からは、殿下の心臓に飲み干されるかのように色が、緋と黒が抜けていき、最初の水晶のような透明感をとり戻す。
アベルは一息に短剣を引き抜いた。鮮血は一滴も流れない。
「え…………アベル、これはいったい、どういう…………」
しきりに瞬きするデラクルス嬢の目の前で、レオポルド殿下は変化していく。
「あれは…………まさか」
教皇猊下が瞠目し、呆然と見守る私達の前で、レオポルド殿下の全身から緋と黒の光が放たれ、まぶしさに目をつぶる。
そろそろと目を開くと、レオポルド殿下は両足で立っていた。
上着の、心臓の部分に刃の大きさの穴が開いている。
そして陽光のごとく輝いていた金色の髪は緋色に、澄んだ紫水晶のようだった二つの瞳は漆黒に変化していた。
「レオ様…………? いったい、これは…………」
困惑するデラクルス嬢の前で、髪と瞳の色が変わったレオポルド殿下は周囲を見渡し、自身の手と体を見下ろす。
「ティナ…………? アベル…………どういうことだ、これは………すさまじい力がみなぎるような…………」
アベルは恭しく答える。
「あの邪竜の魔力を移植しました。ご自身の名がわかりますか? 殿下」
「私の名…………私の名は、ブルガトリオ…………いや、レオポルド…………?」
自分の内側をさぐるように、殿下は名を口に出す。自分でも明確でないようだ。
「私は、レオポルド…………けれど、ブルガトリオでもある…………?」
「成功したようです」
アベルは満足げにうなずき、デラクルス嬢に向き直った。
「ご安心ください、セレスティナお嬢様。魔術は成功しました。レオポルド殿下は邪竜ブルガトリオの魔力を宿しました。殿下は人間でありながら、竜の力を継ぐ存在となったのです。人間として、これ以上の強さがありましょうか。今の殿下は、人間でありながら神の力を手に入れた、まさに伝説に語られる数多の英雄のごとく、半神半人となられたのです」
「アベル!?」
デラクルス嬢が青玉の目をみはり、私も驚愕と共に教皇猊下をふりかえる。
「そんなことができるんですか? 人が神の力を、って…………」
「――――本来は不可能にちかい技です。神を降ろす巫の資質を持ち、修行を修めた者でさえ、神の力の一部をお借りするだけ…………ただ、あの竜はソル聖神官の聖魔力でかなり弱っていましたし、その上で、優れた術者が優れた道具を用いたなら、あるいは…………」
「じゃあ、本当に…………?」
呆然と三人を見守る私達にかまわず、アベルはレオポルド殿下に提案する。
「殿下。魔力の使い方はおわかりですか? 試しに一度、お使いになってはいかがでしょう」
アベルは空を指さす。
「ふむ…………」とかなんとか呟いたレオポルド殿下は、大きな手を天空へ向けた。
その手の平から、先ほど見たばかりの緋と黒の炎が噴き出し、柱のようにそそり立つ。
「っ!!」
私達の間に緊張が走る。
逆にアベルは、ますます満足そうに笑みを深めた。
「お見事にございます。もう魔力を使いこなしておられる」
「魔力…………これが?」
「邪竜ブルガトリオの魔力です。これからは殿下の御力です」
「私の…………」
両の拳をにぎったり開いたりするレオポルド殿下が、ゆっくり笑みを浮かべていく。
「レオ様!!」
明るい声が響いて、デラクルス嬢がレオポルド殿下に抱きつくように問うた。
「レオ様! わたくしがわかりますか!? セレスティナですわ!」
「ああ。むろんだとも、ティナ」
レオポルド殿下が優しくほほ笑み、一気にこれまでの殿下の印象が強くなる。
「貴女はセレスティナ・デラクルス。私の愛する、ただ一人の婚約者。未来の妃。喜んでくれ、ティナ。私は今度こそ、君を守る力を手に入れた。ヒルベルト皇子からも邪竜からも、君を傷つけるすべてのものから、君を守ってみせる――――!!」
「レオ様…………っ!!」
デラクルス嬢は歓喜の涙と共にレオポルド殿下にすがりつき、彼の胸に頬を寄せる。
「嬉しい…………嬉しいですわ、レオ様。やはりわたくしの真の運命の相手は、レオ様だったのですね…………っ」
「ティナ…………!!」
レオポルド殿下とデラクルス嬢はかたくかたく抱き合って、ここだけ見れば、二人の様子はデラクルス嬢がノベーラを出る前と、なんの違いもない。
「ヒルベルト皇子やブルガトリオの妃と言っていたのは、どうなったのよ…………」
私は思わず、ぼそっ、と呟かずにはいられなかったし、うんうん、とルイス卿も首を上下にふっている。教皇猊下とエルネスト候子も、詳しい経緯は知らないまでも、つい先ほどまで邪竜を『夫』と呼んでいたデラクルス嬢が当たり前のようにレオポルド殿下と抱き合う姿に、驚きと呆れの視線を送っていた。
だが恋人達は、どんどん二人の世界を展開している。
「ノベーラに帰ろう、ティナ。陛下にも大臣達にも、誰にもいっさい反対はさせない。私の妻になるのは君だけ、君こそ私の愛するただ一人の女性だ。私はこの竜の魔力を用いて、君もノベーラもすべて守り抜いてみせる。セルバ侵攻をもくろむイストリアも、この力で倒して、ノベーラをこの大陸の覇者としてみせよう――――!!」
「レオ様…………っ、なんて凛々しく頼もしい。ああ、こんなに輝かしいレオ様は初めて。まさに、伝説に語られる神の血を引く英雄の生まれ変わり。レオ様、レオ様こそは、この世界の新たな英雄、新たな王、いえ皇帝ですわ。千年先の未来にだって、その名が語り継がれましょう」
「そして君が、その英雄の皇帝の皇后だ」
「レオ様…………っ!! 嬉しいですわ、わたくしの真の運命…………っ!!」
恋人達はひし、と抱き合う。
「聞けば聞くほどしらけます」
普段、冷静沈着なルイス卿が、珍しく私情を露わにする。私も、
「まったく同感」
と返した。
「まあ、無事にまとまったのなら、結果としては問題ないのかも」
「無事、でしょうか?」
肩をすくめた私に、ルイス卿が懐疑的に応じる。
私は頭を切り替えた。
先ほど殿下が述べた『セルバ』という単語に、本来の目的の片方を思い出したのだ。
「教皇猊下。デラクルス嬢は、教皇猊下にお任せします。レオポルド殿下も、責任もってデラクルス嬢に罪を償わせる、と約束されたのですから、文句はおっしゃらないでしょう。私達は、もう王宮に向かわないと――――」
日が暮れはじめている。
裾の埃を叩く私に、ルイス卿が慌てて言った。
「お忘れですか、アリシア様。クエント侯への謁見には、レオポルド殿下も同行しなければ。大公陛下から親書を託され、同盟を申し込む役目を仰せつかった使者は、公太子殿下です」
「あ、そうか」
すっかり忘れていた。
「じゃあ、殿下…………」
私はお邪魔虫になる覚悟を決めて、殿下に呼びかける。
と。
デラクルス嬢が私を見ていた。
不気味なくらい、じっと。まばたきもせず。
けれど突然、視線をそらすと、愛する恋人の胸にふたたび顔をうずめる。
「レオ様。愛していますわ、レオ様。わたくしの願い、聞いてくださいますか?」
「むろんだとも、ティナ。なにが望みなんだ?」
デラクルス嬢は殿下の胸から顔をあげ、私を見て、にっこり笑う。
「あの女を殺してくださいませ」
白い指の先を、私にむかって突きつける。
「あの女、アリシア・ソルは悪女です。大勢の人々をたぶらかして、わたくしを散々に苦しめた、希代の魔女ですわ。あの女が生きている限り、わたくしは自分の幸せを信じられないし、安心して生きることができないのです」
「なにを、っ!」
ルイス卿が私を背にかばい、教皇猊下とエルネスト候子の表情も険しくなる。
レオポルド殿下は少し躊躇した。
「しかし、ティナ」
「お願いです、レオ様。わたくしを救ってくださいませ。あの女がノベーラに帰るなら、わたくしはノベーラに戻りません。あの女が生きている限り、わたくしは幸せにはなれないのです」
「いい加減になさいませ」
教皇猊下の声が飛ぶ。
「この期に及んで、まだ貴女は、ソル聖神官に助けられたことも理解できないのですか? ソル聖神官は瀕死の貴女を癒し、貴女をだまして捨てた邪竜からも、貴女の命を守った。その返礼が、それですか? あなたが聖女と認められないのは、あなた自身のその態度が遠ざけているからだと、いい加減、理解できませんか?」
「聖女なんていりませんわ」
デラクルス嬢は吐き捨てた。
「聖女の称号なんて、もう要りません。《聖印》も、どうでもいい。わたくしの高貴や神聖さを理解できぬ愚かな教皇や世間など、認めてもらいたいとも思いません。わたくしはセレスティナ・デラクルス。この世界の悪役令嬢で、レオ様の妃です。ノベーラはいずれ、レオ様のお力でイストリアをも超える大帝国となります。レオ様はその大帝国の帝王で、わたくしは帝后。世間がなにを言っても、聞こえませんわ。わたくしはレオ様だけがわたくしを愛し、守り、認めてくださるなら、それでいいのです。レオ様はわたくしのもの。そしてわたくしのすべては、レオ様のもの――――…………」
「ティナ…………」
デラクルス嬢が甘く切なく潤んだ瞳で、レオポルド殿下を見上げる。
「お願いです、レオ様。わたくし達が永遠に共に在るために――――わたくしとあの女は、永久に相容れぬ存在なのです」
「私めからもお願いいたします、レオポルド殿下。どうかセレスティナお嬢様の願いをお聞き届けください。デラクルス公爵閣下にもヒルベルト皇子にも、私めにも、それは叶いませんでした。セレスティナお嬢様のために、なにとぞアリシア・ソルを…………!!」
黙って見守っていたアベルも膝をついて頭を垂れる。
「世迷いごとを!! アリシア様、すぐに避難なさってください!!」
ルイス卿が私の背を押し、エルネスト候子も教皇の手を引いて、中庭から出ようとする。
しかし数秒、遅かった。
「――――致し方ない」
レオポルド殿下は心を決められたようだった。
「許せ、アリシア・ソル。私はティナのためなら、竜にも悪魔にもなれる男なのだ」
「要らないでしょ、そんな覚悟!!」
「せめて、君が私やティナを助けたこと、大公陛下には必ず報告しよう。『アリシア・ソル聖神官は、教皇にアンブロシアと認められたものの、不幸な事故で帰国が叶わなかった』、そう伝える。助けられた礼だ、命は守れないが、名誉だけは守ろう―――――」
「逆ですよ、名誉は最低限でいいから、命を守ってください!!」
レオポルド殿下がこちらへ腕を突き出し、その手の平から、邪竜の緋と黒の炎が放たれる。
私は立ち止まってふりむき、星銀の聖魔力で盾を作った。
が、もう力が尽きかけているのだろう、白銀色の光の盾は、薄いガラスのようにヒビが入っていく。
回廊の石の床や柱、壁が黒く焦げていき、頬も髪も熱風で炙られて肺の中まで熱い。背後からも咳き込む音が聞こえる。
(お願い、もって)
音高く破壊音が響いて、光の盾が真っ二つに割れる。
その割れ目の向こうから、炎が私達に迫る様が、妙にゆっくり、鮮明に視認できた。
緋と黒と灼熱に包まれる。
どおん、と激しい爆発に似た音が響いた気がしたが、はっきりしなかった。
あまりに轟音すぎて、人間の聴覚では聞きとれなかったのかもしれない。
気づくと、覚悟していた熱も炎も襲ってきてはいなかった。むしろ涼しい。
びりびりしていた耳の奥が静まっていき、周囲の音が戻ってくる。
「貴様…………何者だ!?」
レオポルド殿下の鋭い誰何の声が聞こえ、私はそっとまぶたを開いた。
聞き覚えある、むしろずっと聞きたかった声が、頭の上から降ってくる。
「図書館の魔王ビブロス。召喚はされていないが、星の要請に従い推参した。アンブロシアは殺させないよ」
「ビブロス――――!!」
白い髪と漆黒の瞳の魔王が、私の肩を抱いて立っていた。
ルイス卿が呆然と呟く。私もすぐには信じられない。
「アベル!」
デラクルス嬢が喜びの声をあげ、レオポルド殿下の外套を羽織っただけの姿で、忠実な下僕に駆け寄った。殿下も慌ててあとを追う。
「ありがとう、アベル。わたくし達を助けてくれたのね」
「セレスティナお嬢様…………」
アベルはふらふらで、立っているのもやっと、という様子だ。
「私からも礼を言う、アベル。そなたとソル聖神官がいなければ、あの危険な男は倒せなかった。よく、ティナと我々を守ってくれた」
「礼には、及びません。私は、セレスティナお嬢様の、望みを叶えるため…………」
アベルの体がぐらり、と、かしぐ。
「アベル!」
反射的にレオポルド殿下がアベルへ手を出した。
その殿下の手を、アベルががっちり、つかむ。
そのまま、にぎっていた緋と黒に染まった短剣を、レオポルド殿下の心臓に突き立てた。
悲鳴があがる。
「レオ様!! なにをするの、アベル!!」
アベルは主君の問いには答えず、どさり、とレオポルド殿下の長身が地面に倒れる。
「レオ様! レオ様っ!!」
デラクルス嬢が半泣きで倒れた殿下にすがる。
レオポルド殿下の心臓に突き立った短剣の刃からは、殿下の心臓に飲み干されるかのように色が、緋と黒が抜けていき、最初の水晶のような透明感をとり戻す。
アベルは一息に短剣を引き抜いた。鮮血は一滴も流れない。
「え…………アベル、これはいったい、どういう…………」
しきりに瞬きするデラクルス嬢の目の前で、レオポルド殿下は変化していく。
「あれは…………まさか」
教皇猊下が瞠目し、呆然と見守る私達の前で、レオポルド殿下の全身から緋と黒の光が放たれ、まぶしさに目をつぶる。
そろそろと目を開くと、レオポルド殿下は両足で立っていた。
上着の、心臓の部分に刃の大きさの穴が開いている。
そして陽光のごとく輝いていた金色の髪は緋色に、澄んだ紫水晶のようだった二つの瞳は漆黒に変化していた。
「レオ様…………? いったい、これは…………」
困惑するデラクルス嬢の前で、髪と瞳の色が変わったレオポルド殿下は周囲を見渡し、自身の手と体を見下ろす。
「ティナ…………? アベル…………どういうことだ、これは………すさまじい力がみなぎるような…………」
アベルは恭しく答える。
「あの邪竜の魔力を移植しました。ご自身の名がわかりますか? 殿下」
「私の名…………私の名は、ブルガトリオ…………いや、レオポルド…………?」
自分の内側をさぐるように、殿下は名を口に出す。自分でも明確でないようだ。
「私は、レオポルド…………けれど、ブルガトリオでもある…………?」
「成功したようです」
アベルは満足げにうなずき、デラクルス嬢に向き直った。
「ご安心ください、セレスティナお嬢様。魔術は成功しました。レオポルド殿下は邪竜ブルガトリオの魔力を宿しました。殿下は人間でありながら、竜の力を継ぐ存在となったのです。人間として、これ以上の強さがありましょうか。今の殿下は、人間でありながら神の力を手に入れた、まさに伝説に語られる数多の英雄のごとく、半神半人となられたのです」
「アベル!?」
デラクルス嬢が青玉の目をみはり、私も驚愕と共に教皇猊下をふりかえる。
「そんなことができるんですか? 人が神の力を、って…………」
「――――本来は不可能にちかい技です。神を降ろす巫の資質を持ち、修行を修めた者でさえ、神の力の一部をお借りするだけ…………ただ、あの竜はソル聖神官の聖魔力でかなり弱っていましたし、その上で、優れた術者が優れた道具を用いたなら、あるいは…………」
「じゃあ、本当に…………?」
呆然と三人を見守る私達にかまわず、アベルはレオポルド殿下に提案する。
「殿下。魔力の使い方はおわかりですか? 試しに一度、お使いになってはいかがでしょう」
アベルは空を指さす。
「ふむ…………」とかなんとか呟いたレオポルド殿下は、大きな手を天空へ向けた。
その手の平から、先ほど見たばかりの緋と黒の炎が噴き出し、柱のようにそそり立つ。
「っ!!」
私達の間に緊張が走る。
逆にアベルは、ますます満足そうに笑みを深めた。
「お見事にございます。もう魔力を使いこなしておられる」
「魔力…………これが?」
「邪竜ブルガトリオの魔力です。これからは殿下の御力です」
「私の…………」
両の拳をにぎったり開いたりするレオポルド殿下が、ゆっくり笑みを浮かべていく。
「レオ様!!」
明るい声が響いて、デラクルス嬢がレオポルド殿下に抱きつくように問うた。
「レオ様! わたくしがわかりますか!? セレスティナですわ!」
「ああ。むろんだとも、ティナ」
レオポルド殿下が優しくほほ笑み、一気にこれまでの殿下の印象が強くなる。
「貴女はセレスティナ・デラクルス。私の愛する、ただ一人の婚約者。未来の妃。喜んでくれ、ティナ。私は今度こそ、君を守る力を手に入れた。ヒルベルト皇子からも邪竜からも、君を傷つけるすべてのものから、君を守ってみせる――――!!」
「レオ様…………っ!!」
デラクルス嬢は歓喜の涙と共にレオポルド殿下にすがりつき、彼の胸に頬を寄せる。
「嬉しい…………嬉しいですわ、レオ様。やはりわたくしの真の運命の相手は、レオ様だったのですね…………っ」
「ティナ…………!!」
レオポルド殿下とデラクルス嬢はかたくかたく抱き合って、ここだけ見れば、二人の様子はデラクルス嬢がノベーラを出る前と、なんの違いもない。
「ヒルベルト皇子やブルガトリオの妃と言っていたのは、どうなったのよ…………」
私は思わず、ぼそっ、と呟かずにはいられなかったし、うんうん、とルイス卿も首を上下にふっている。教皇猊下とエルネスト候子も、詳しい経緯は知らないまでも、つい先ほどまで邪竜を『夫』と呼んでいたデラクルス嬢が当たり前のようにレオポルド殿下と抱き合う姿に、驚きと呆れの視線を送っていた。
だが恋人達は、どんどん二人の世界を展開している。
「ノベーラに帰ろう、ティナ。陛下にも大臣達にも、誰にもいっさい反対はさせない。私の妻になるのは君だけ、君こそ私の愛するただ一人の女性だ。私はこの竜の魔力を用いて、君もノベーラもすべて守り抜いてみせる。セルバ侵攻をもくろむイストリアも、この力で倒して、ノベーラをこの大陸の覇者としてみせよう――――!!」
「レオ様…………っ、なんて凛々しく頼もしい。ああ、こんなに輝かしいレオ様は初めて。まさに、伝説に語られる神の血を引く英雄の生まれ変わり。レオ様、レオ様こそは、この世界の新たな英雄、新たな王、いえ皇帝ですわ。千年先の未来にだって、その名が語り継がれましょう」
「そして君が、その英雄の皇帝の皇后だ」
「レオ様…………っ!! 嬉しいですわ、わたくしの真の運命…………っ!!」
恋人達はひし、と抱き合う。
「聞けば聞くほどしらけます」
普段、冷静沈着なルイス卿が、珍しく私情を露わにする。私も、
「まったく同感」
と返した。
「まあ、無事にまとまったのなら、結果としては問題ないのかも」
「無事、でしょうか?」
肩をすくめた私に、ルイス卿が懐疑的に応じる。
私は頭を切り替えた。
先ほど殿下が述べた『セルバ』という単語に、本来の目的の片方を思い出したのだ。
「教皇猊下。デラクルス嬢は、教皇猊下にお任せします。レオポルド殿下も、責任もってデラクルス嬢に罪を償わせる、と約束されたのですから、文句はおっしゃらないでしょう。私達は、もう王宮に向かわないと――――」
日が暮れはじめている。
裾の埃を叩く私に、ルイス卿が慌てて言った。
「お忘れですか、アリシア様。クエント侯への謁見には、レオポルド殿下も同行しなければ。大公陛下から親書を託され、同盟を申し込む役目を仰せつかった使者は、公太子殿下です」
「あ、そうか」
すっかり忘れていた。
「じゃあ、殿下…………」
私はお邪魔虫になる覚悟を決めて、殿下に呼びかける。
と。
デラクルス嬢が私を見ていた。
不気味なくらい、じっと。まばたきもせず。
けれど突然、視線をそらすと、愛する恋人の胸にふたたび顔をうずめる。
「レオ様。愛していますわ、レオ様。わたくしの願い、聞いてくださいますか?」
「むろんだとも、ティナ。なにが望みなんだ?」
デラクルス嬢は殿下の胸から顔をあげ、私を見て、にっこり笑う。
「あの女を殺してくださいませ」
白い指の先を、私にむかって突きつける。
「あの女、アリシア・ソルは悪女です。大勢の人々をたぶらかして、わたくしを散々に苦しめた、希代の魔女ですわ。あの女が生きている限り、わたくしは自分の幸せを信じられないし、安心して生きることができないのです」
「なにを、っ!」
ルイス卿が私を背にかばい、教皇猊下とエルネスト候子の表情も険しくなる。
レオポルド殿下は少し躊躇した。
「しかし、ティナ」
「お願いです、レオ様。わたくしを救ってくださいませ。あの女がノベーラに帰るなら、わたくしはノベーラに戻りません。あの女が生きている限り、わたくしは幸せにはなれないのです」
「いい加減になさいませ」
教皇猊下の声が飛ぶ。
「この期に及んで、まだ貴女は、ソル聖神官に助けられたことも理解できないのですか? ソル聖神官は瀕死の貴女を癒し、貴女をだまして捨てた邪竜からも、貴女の命を守った。その返礼が、それですか? あなたが聖女と認められないのは、あなた自身のその態度が遠ざけているからだと、いい加減、理解できませんか?」
「聖女なんていりませんわ」
デラクルス嬢は吐き捨てた。
「聖女の称号なんて、もう要りません。《聖印》も、どうでもいい。わたくしの高貴や神聖さを理解できぬ愚かな教皇や世間など、認めてもらいたいとも思いません。わたくしはセレスティナ・デラクルス。この世界の悪役令嬢で、レオ様の妃です。ノベーラはいずれ、レオ様のお力でイストリアをも超える大帝国となります。レオ様はその大帝国の帝王で、わたくしは帝后。世間がなにを言っても、聞こえませんわ。わたくしはレオ様だけがわたくしを愛し、守り、認めてくださるなら、それでいいのです。レオ様はわたくしのもの。そしてわたくしのすべては、レオ様のもの――――…………」
「ティナ…………」
デラクルス嬢が甘く切なく潤んだ瞳で、レオポルド殿下を見上げる。
「お願いです、レオ様。わたくし達が永遠に共に在るために――――わたくしとあの女は、永久に相容れぬ存在なのです」
「私めからもお願いいたします、レオポルド殿下。どうかセレスティナお嬢様の願いをお聞き届けください。デラクルス公爵閣下にもヒルベルト皇子にも、私めにも、それは叶いませんでした。セレスティナお嬢様のために、なにとぞアリシア・ソルを…………!!」
黙って見守っていたアベルも膝をついて頭を垂れる。
「世迷いごとを!! アリシア様、すぐに避難なさってください!!」
ルイス卿が私の背を押し、エルネスト候子も教皇の手を引いて、中庭から出ようとする。
しかし数秒、遅かった。
「――――致し方ない」
レオポルド殿下は心を決められたようだった。
「許せ、アリシア・ソル。私はティナのためなら、竜にも悪魔にもなれる男なのだ」
「要らないでしょ、そんな覚悟!!」
「せめて、君が私やティナを助けたこと、大公陛下には必ず報告しよう。『アリシア・ソル聖神官は、教皇にアンブロシアと認められたものの、不幸な事故で帰国が叶わなかった』、そう伝える。助けられた礼だ、命は守れないが、名誉だけは守ろう―――――」
「逆ですよ、名誉は最低限でいいから、命を守ってください!!」
レオポルド殿下がこちらへ腕を突き出し、その手の平から、邪竜の緋と黒の炎が放たれる。
私は立ち止まってふりむき、星銀の聖魔力で盾を作った。
が、もう力が尽きかけているのだろう、白銀色の光の盾は、薄いガラスのようにヒビが入っていく。
回廊の石の床や柱、壁が黒く焦げていき、頬も髪も熱風で炙られて肺の中まで熱い。背後からも咳き込む音が聞こえる。
(お願い、もって)
音高く破壊音が響いて、光の盾が真っ二つに割れる。
その割れ目の向こうから、炎が私達に迫る様が、妙にゆっくり、鮮明に視認できた。
緋と黒と灼熱に包まれる。
どおん、と激しい爆発に似た音が響いた気がしたが、はっきりしなかった。
あまりに轟音すぎて、人間の聴覚では聞きとれなかったのかもしれない。
気づくと、覚悟していた熱も炎も襲ってきてはいなかった。むしろ涼しい。
びりびりしていた耳の奥が静まっていき、周囲の音が戻ってくる。
「貴様…………何者だ!?」
レオポルド殿下の鋭い誰何の声が聞こえ、私はそっとまぶたを開いた。
聞き覚えある、むしろずっと聞きたかった声が、頭の上から降ってくる。
「図書館の魔王ビブロス。召喚はされていないが、星の要請に従い推参した。アンブロシアは殺させないよ」
「ビブロス――――!!」
白い髪と漆黒の瞳の魔王が、私の肩を抱いて立っていた。
120
お気に入りに追加
296
あなたにおすすめの小説

婚約破棄されて辺境へ追放されました。でもステータスがほぼMAXだったので平気です!スローライフを楽しむぞっ♪
naturalsoft
恋愛
シオン・スカーレット公爵令嬢は転生者であった。夢だった剣と魔法の世界に転生し、剣の鍛錬と魔法の鍛錬と勉強をずっとしており、攻略者の好感度を上げなかったため、婚約破棄されました。
「あれ?ここって乙女ゲーの世界だったの?」
まっ、いいかっ!
持ち前の能天気さとポジティブ思考で、辺境へ追放されても元気に頑張って生きてます!

無一文で追放される悪女に転生したので特技を活かしてお金儲けを始めたら、聖女様と呼ばれるようになりました
結城芙由奈@2/28コミカライズ発売
恋愛
スーパームーンの美しい夜。仕事帰り、トラックに撥ねらてしまった私。気づけば草の生えた地面の上に倒れていた。目の前に見える城に入れば、盛大なパーティーの真っ最中。目の前にある豪華な食事を口にしていると見知らぬ男性にいきなり名前を呼ばれて、次期王妃候補の資格を失ったことを聞かされた。理由も分からないまま、家に帰宅すると「お前のような恥さらしは今日限り、出ていけ」と追い出されてしまう。途方に暮れる私についてきてくれたのは、私の専属メイドと御者の青年。そこで私は2人を連れて新天地目指して旅立つことにした。無一文だけど大丈夫。私は前世の特技を活かしてお金を稼ぐことが出来るのだから――
※ 他サイトでも投稿中

お兄様、冷血貴公子じゃなかったんですか?~7歳から始める第二の聖女人生~
みつまめ つぼみ
ファンタジー
17歳で偽りの聖女として処刑された記憶を持つ7歳の女の子が、今度こそ世界を救うためにエルメーテ公爵家に引き取られて人生をやり直します。
記憶では冷血貴公子と呼ばれていた公爵令息は、義妹である主人公一筋。
そんな義兄に戸惑いながらも甘える日々。
「お兄様? シスコンもほどほどにしてくださいね?」
恋愛ポンコツと冷血貴公子の、コミカルでシリアスな救世物語開幕!

異世界に落ちたら若返りました。
アマネ
ファンタジー
榊原 チヨ、87歳。
夫との2人暮らし。
何の変化もないけど、ゆっくりとした心安らぐ時間。
そんな普通の幸せが側にあるような生活を送ってきたのにーーー
気がついたら知らない場所!?
しかもなんかやたらと若返ってない!?
なんで!?
そんなおばあちゃんのお話です。
更新は出来れば毎日したいのですが、物語の時間は割とゆっくり進むかもしれません。

ボロボロになるまで働いたのに見た目が不快だと追放された聖女は隣国の皇子に溺愛される。……ちょっと待って、皇子が三つ子だなんて聞いてません!
沙寺絃
恋愛
ルイン王国の神殿で働く聖女アリーシャは、早朝から深夜まで一人で激務をこなしていた。
それなのに聖女の力を理解しない王太子コリンから理不尽に追放を言い渡されてしまう。
失意のアリーシャを迎えに来たのは、隣国アストラ帝国からの使者だった。
アリーシャはポーション作りの才能を買われ、アストラ帝国に招かれて病に臥せった皇帝を助ける。
帝国の皇子は感謝して、アリーシャに深い愛情と敬意を示すようになる。
そして帝国の皇子は十年前にアリーシャと出会った事のある初恋の男の子だった。
再会に胸を弾ませるアリーシャ。しかし、衝撃の事実が発覚する。
なんと、皇子は三つ子だった!
アリーシャの幼馴染の男の子も、三人の皇子が入れ替わって接していたと判明。
しかも病から復活した皇帝は、アリーシャを皇子の妃に迎えると言い出す。アリーシャと結婚した皇子に、次の皇帝の座を譲ると宣言した。
アリーシャは個性的な三つ子の皇子に愛されながら、誰と結婚するか決める事になってしまう。
一方、アリーシャを追放したルイン王国では暗雲が立ち込め始めていた……。

トカゲ令嬢とバカにされて聖女候補から外され辺境に追放されましたが、トカゲではなく龍でした。
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
リバコーン公爵家の長女ソフィアは、全貴族令嬢10人の1人の聖獣持ちに選ばれたが、その聖獣がこれまで誰も持ったことのない小さく弱々しいトカゲでしかなかった。それに比べて側室から生まれた妹は有名な聖獣スフィンクスが従魔となった。他にもグリフォンやペガサス、ワイバーンなどの実力も名声もある従魔を従える聖女がいた。リバコーン公爵家の名誉を重んじる父親は、ソフィアを正室の領地に追いやり第13王子との婚約も辞退しようとしたのだが……
王立聖女学園、そこは爵位を無視した弱肉強食の競争社会。だがどれだけ努力しようとも神の気紛れで全てが決められてしまう。まず従魔が得られるかどうかで貴族令嬢に残れるかどうかが決まってしまう。

冤罪で殺された聖女、生まれ変わって自由に生きる
みおな
恋愛
聖女。
女神から選ばれし、世界にたった一人の存在。
本来なら、誰からも尊ばれ大切に扱われる存在である聖女ルディアは、婚約者である王太子から冤罪をかけられ処刑されてしまう。
愛し子の死に、女神はルディアの時間を巻き戻す。
記憶を持ったまま聖女認定の前に戻ったルディアは、聖女にならず自由に生きる道を選択する。
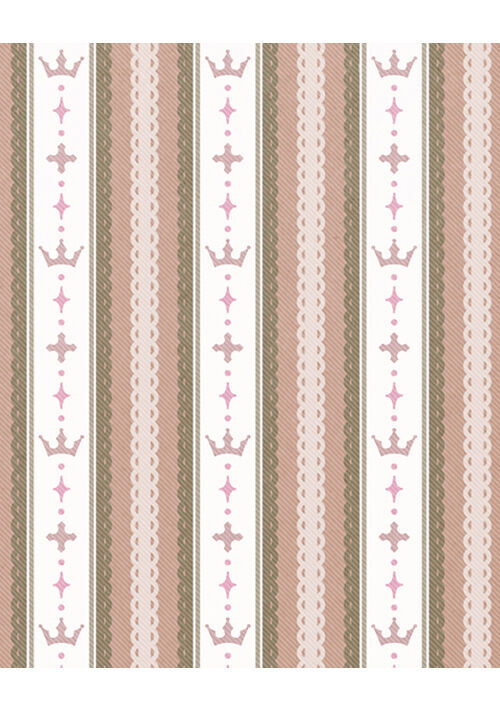
【完結】「神様、辞めました〜竜神の愛し子に冤罪を着せ投獄するような人間なんてもう知らない」
まほりろ
恋愛
王太子アビー・シュトースと聖女カーラ・ノルデン公爵令嬢の結婚式当日。二人が教会での誓いの儀式を終え、教会の扉を開け外に一歩踏み出したとき、国中の壁や窓に不吉な文字が浮かび上がった。
【本日付けで神を辞めることにした】
フラワーシャワーを巻き王太子と王太子妃の結婚を祝おうとしていた参列者は、突然現れた文字に驚きを隠せず固まっている。
国境に壁を築きモンスターの侵入を防ぎ、結界を張り国内にいるモンスターは弱体化させ、雨を降らせ大地を潤し、土地を豊かにし豊作をもたらし、人間の体を強化し、生活が便利になるように魔法の力を授けた、竜神ウィルペアトが消えた。
人々は三カ月前に冤罪を着せ、|罵詈雑言《ばりぞうごん》を浴びせ、石を投げつけ投獄した少女が、本物の【竜の愛し子】だと分かり|戦慄《せんりつ》した。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
アルファポリスに先行投稿しています。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
2021/12/13、HOTランキング3位、12/14総合ランキング4位、恋愛3位に入りました! ありがとうございます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















