あなたにおすすめの小説



どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

照と二人の夫
三矢由巳
歴史・時代
江戸時代中期、家老の娘照(てる)は、十も年上の吝嗇な男孫右衛門と祝言を挙げる。だが、実家の事情で離縁せざるを得なくなる。そんな彼女に思いを寄せていたのは幼馴染の清兵衛だった。
ムーンライトノベルズの「『香田角の人々』拾遺」のエピソードを増補改訂したものです。

ふたりの旅路
三矢由巳
歴史・時代
第三章開始しました。以下は第一章のあらすじです。
志緒(しお)のいいなずけ駒井幸之助は文武両道に秀でた明るく心優しい青年だった。祝言を三カ月後に控え幸之助が急死した。幸せの絶頂から奈落の底に突き落とされた志緒と駒井家の人々。一周忌の後、家の存続のため駒井家は遠縁の山中家から源治郎を養子に迎えることに。志緒は源治郎と幸之助の妹佐江が結婚すると思っていたが、駒井家の人々は志緒に嫁に来て欲しいと言う。
無口で何を考えているかわからない源治郎との結婚に不安を感じる志緒。果たしてふたりの運命は……。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
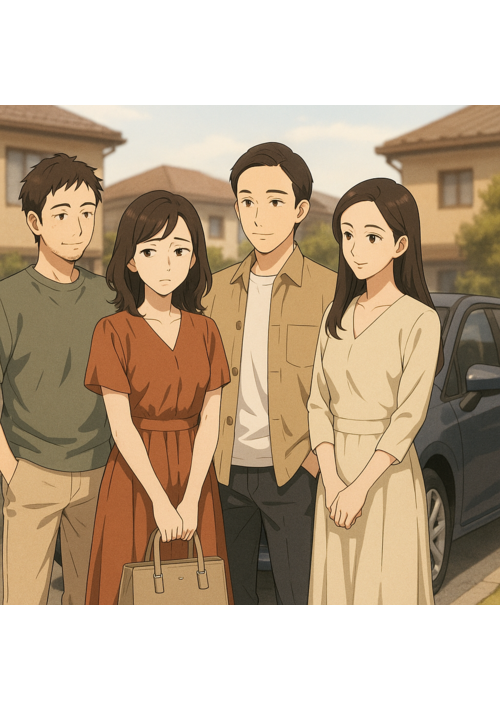
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















