お気に入りに追加
14
あなたにおすすめの小説

クラス転移で無能判定されて追放されたけど、努力してSSランクのチートスキルに進化しました~【生命付与】スキルで異世界を自由に楽しみます~
いちまる
ファンタジー
ある日、クラスごと異世界に召喚されてしまった少年、天羽イオリ。
他のクラスメートが強力なスキルを発現させてゆく中、イオリだけが最低ランクのEランクスキル【生命付与】の持ち主だと鑑定される。
「無能は不要だ」と判断した他の生徒や、召喚した張本人である神官によって、イオリは追放され、川に突き落とされた。
しかしそこで、川底に沈んでいた謎の男の力でスキルを強化するチャンスを得た――。
1千年の努力とともに、イオリのスキルはSSランクへと進化!
自分を拾ってくれた田舎町のアイテムショップで、チートスキルをフル稼働!
「転移者が世界を良くする?」
「知らねえよ、俺は異世界を自由気ままに楽しむんだ!」
追放された少年の第2の人生が、始まる――!
※本作品は他サイト様でも掲載中です。

【完結】【勇者】の称号が無かった美少年は王宮を追放されたのでのんびり異世界を謳歌する
雪雪ノ雪
ファンタジー
ある日、突然学校にいた人全員が【勇者】として召喚された。
その召喚に巻き込まれた少年柊茜は、1人だけ【勇者】の称号がなかった。
代わりにあったのは【ラグナロク】という【固有exスキル】。
それを見た柊茜は
「あー....このスキルのせいで【勇者】の称号がなかったのかー。まぁ、ス・ラ・イ・厶・に【勇者】って称号とか合わないからなぁ…」
【勇者】の称号が無かった柊茜は、王宮を追放されてしまう。
追放されてしまった柊茜は、特に慌てる事もなくのんびり異世界を謳歌する..........たぶん…....
主人公は男の娘です 基本主人公が自分を表す時は「私」と表現します

【R18】スライムにマッサージされて絶頂しまくる女の話
白木 白亜
ファンタジー
突如として異世界転移した日本の大学生、タツシ。
世界にとって致命的な抜け穴を見つけ、召喚士としてあっけなく魔王を倒してしまう。
その後、一緒に旅をしたスライムと共に、マッサージ店を開くことにした。卑猥な目的で。
裏があるとも知れず、王都一番の人気になるマッサージ店「スライム・リフレ」。スライムを巧みに操って体のツボを押し、角質を取り、リフレッシュもできる。
だがそこは三度の飯よりも少女が絶頂している瞬間を見るのが大好きなタツシが経営する店。
そんな店では、膣に媚薬100%の粘液を注入され、美少女たちが「気持ちよくなって」いる!!!
感想大歓迎です!
※1グロは一切ありません。登場人物が圧倒的な不幸になることも(たぶん)ありません。今日も王都は平和です。異種姦というよりは、スライムは主人公の補助ツールとして扱われます。そっち方面を期待していた方はすみません。

凡人がおまけ召喚されてしまった件
根鳥 泰造
ファンタジー
勇者召喚に巻き込まれて、異世界にきてしまった祐介。最初は勇者の様に大切に扱われていたが、ごく普通の才能しかないので、冷遇されるようになり、ついには王宮から追い出される。
仕方なく冒険者登録することにしたが、この世界では希少なヒーラー適正を持っていた。一年掛けて治癒魔法を習得し、治癒剣士となると、引く手あまたに。しかも、彼は『強欲』という大罪スキルを持っていて、倒した敵のスキルを自分のものにできるのだ。
それらのお蔭で、才能は凡人でも、数多のスキルで能力を補い、熟練度は飛びぬけ、高難度クエストも熟せる有名冒険者となる。そして、裏では気配消去や不可視化スキルを活かして、暗殺という裏の仕事も始めた。
異世界に来て八年後、その暗殺依頼で、召喚勇者の暗殺を受けたのだが、それは祐介を捕まえるための罠だった。祐介が暗殺者になっていると知った勇者が、改心させよう企てたもので、その後は勇者一行に加わり、魔王討伐の旅に同行することに。
最初は脅され渋々同行していた祐介も、勇者や仲間の思いをしり、どんどん勇者が好きになり、勇者から告白までされる。
だが、魔王を討伐を成し遂げるも、魔王戦で勇者は祐介を庇い、障害者になる。
祐介は、勇者の嘘で、病院を作り、医師の道を歩みだすのだった。

【R18】異世界転生したら投獄されたけど美少女を絶頂テイムしてハーレム作って無双!最強勇者に!国に戻れとかもう遅いこのまま俺は魔王になる!
金国佐門
ファンタジー
憧れのマドンナを守るために車にひかれて死んだ主人公天原翔は異世界召喚に巻き添こまれて転生した。
神っぽいサムシングはお詫びとして好きなスキルをくれると言う。
未使用のまま終わってしまった愚息で無双できるよう不死身でエロスな能力を得た翔だが。
「なんと破廉恥な!」
鑑定の結果、クソの役にも立たない上に女性に害が出かねないと王の命令により幽閉されてしまった。
だが幽閉先に何も知らずに男勝りのお転婆ボクっ娘女騎士がやってきて……。
魅力Sランク性的魅了Sクラス性技Sクラスによる攻めで哀れ連続アクメに堕ちる女騎士。
性行為時スキル奪取の能力で騎士のスキルを手に入れた翔は壁を破壊して空へと去っていくのだった。
そして様々な美少女を喰らい(性的な意味で)勇者となった翔の元に王から「戻ってきて力を貸してくれと」懇願の手紙が。
今更言われてももう遅い。知らんがな!
このままもらった領土広げてって――。
「俺、魔王になりまーす」
喰えば喰うほどに強くなる!(性的な意味で) 強くなりたくば喰らえッッ!! *:性的な意味で。
美少女達を連続絶頂テイムしてレベルアップ!
どんどん強くなっていく主人公! 無双! 最強!
どんどん増えていく美少女ヒロインたち。 エロス! アダルト!
R18なシーンあり!
男のロマンと売れ筋爆盛りでお贈りするノンストレスご都合主義ライトファンタジー英雄譚!

復讐完遂者は吸収スキルを駆使して成り上がる 〜さあ、自分を裏切った初恋の相手へ復讐を始めよう〜
サイダーボウイ
ファンタジー
「気安く私の名前を呼ばないで! そうやってこれまでも私に付きまとって……ずっと鬱陶しかったのよ!」
孤児院出身のナードは、初恋の相手セシリアからそう吐き捨てられ、パーティーを追放されてしまう。
淡い恋心を粉々に打ち砕かれたナードは失意のどん底に。
だが、ナードには、病弱な妹ノエルの生活費を稼ぐために、冒険者を続けなければならないという理由があった。
1人決死の覚悟でダンジョンに挑むナード。
スライム相手に死にかけるも、その最中、ユニークスキル【アブソープション】が覚醒する。
それは、敵のLPを吸収できるという世界の掟すらも変えてしまうスキルだった。
それからナードは毎日ダンジョンへ入り、敵のLPを吸収し続けた。
増やしたLPを消費して、魔法やスキルを習得しつつ、ナードはどんどん強くなっていく。
一方その頃、セシリアのパーティーでは仲間割れが起こっていた。
冒険者ギルドでの評判も地に落ち、セシリアは徐々に追いつめられていくことに……。
これは、やがて勇者と呼ばれる青年が、チートスキルを駆使して最強へと成り上がり、自分を裏切った初恋の相手に復讐を果たすまでの物語である。
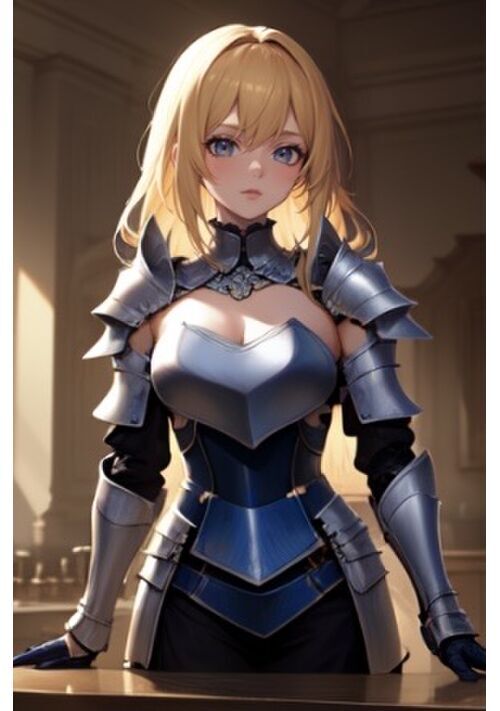
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















