22 / 46
第二話 因縁
噂の真相
しおりを挟む
その晩、雲雀には求馬と会っていたことを明かした。もちろん、上様がお美津の件を求馬に探らせようとしていることも。
「そうですか。上様がそのようなことを」
上様がすでにお美津の件を把握していたことに驚きを隠せない雲雀は、外した前掛けを乱雑に置くと、宗次郎の目の前に座った。
「それにしても、まさか宗次郎さんが尾張の弟君とお知り合いだとは。というよりも、その方の正体もわからずにご一緒していたなんて」
「まさか、尾張の家の者だとは思いもしなかったんだ。今日、身分を明かされて肝を冷やした」
「でしょうね」
呆れたような、冷ややかな目で睨まれる。
「私の方は、読売屋(かわら版屋)に聞き込んでみたのですが、巷の噂の出どころだけはわかりました」
巷の噂――武家の娘が道ならざる恋をして身投げをした。
面白半分に流された風聞ではなかったようだ。
雲雀が宗次郎の前に置いたのは、先日の*読売。お美津の身投げが記事になっていた。それを手に取る。
「この挿絵が余計に哀れで涙を誘うのでしょうね。飛ぶように売れておりました」
華やかな花模様の振袖を着た寝顔のような美しい娘が描かれていた。
「ご近所の話では、大奥を退いてからほとんど出歩くことはなかったらしいのですが、月に一度か二度、市ヶ谷八幡で縁日のある日に、お一人で出かけることがあったそうです」
「その時、誰かと会っていたとか言うのか?」
「ええ。ちょっとした噂になるほど、目立っていらしたようです」
月に一、二度、人と逢うだけで噂になるとは、宗次郎には信じがたい。
「しかしよく憶えているというか、見ているもんだな。他人が誰と会っていたとか」
「その相手が相手ですから」
「有名な奴なのか」
宗次郎はてっきり、安房守の手の者だと思っていた。だから、それ如きで噂になるとは信じられなかったのだ。
「あの辺りでは有名な寺小姓です」
「寺小姓……」
「ですから、お美津さんの身投げを、『享保のお七』だなんて噂する人もいたらしいですわね」
寺小姓というのは、寺の雑用係のようなものであるが、旗本など武家の次男坊以下が多い。
彼らは手習い学問習得という名目のもとに寺入りするのだが、その本質は口減らしである。主な仕事は和尚の身の回りの世話であるが、女人禁制である仏門において、身の回りの世話というのは、慰み者になることを指していた。
言い換えれば、寺小姓には美しい少年が多いのである。
「乙八……恵光寺の乙八と言えば、誰もが振り向く美男だそうですよ」
「その乙八を雲雀が見たことは?」
「いいえ、ないわ。でも八幡宮の縁日に、乙八が女連れでいるのを見たと言う人は確かにいるらしいのです」
人の口に戸は立てられぬ――とはよく言ったものだ。
この噂を、浅井殿は知っていたのだろうか。乙八の相手が自分の娘だと知って、婚姻を進めたのであろうか。
考えれば考えるほど、残された両親が哀れに思えた。
「立花の亭主は、月光院様の遣いが自分の店で誰かと逢っていたことを憶えていたようだった。でも、ここ最近は使っていない」
「お美津さんが使い版をしていた頃、くノ一を立花楼の女中として送り込み、探らせたことがありました。その時の相手は、お美津さんと不必要な言葉を交わすことがなかったらしいので、その相手と恋に落ちたと考えるには無理がありますね」
「そいつは確かに尾張の遣いの者だったのか」
「それは間違いございません。ただ……」
「ただ?」
「いえ、武士と中間者の二人連れだったのですが、武士のなりをした方が供侍のようで、書簡を受け取ったのが中間者だったと。身なりと立場がちぐはぐで妙な印象だった、との報告を受けたことを思い出しました。まあ、正体がばれないように変装をしたとも考えられますが」
ふと、宗次郎の頭に九鬼丸が浮かんだ。彼も中間なのに、やたらと求馬に近しい。安房守にも、そのように近しい中間や小者が側にいたのだろうかと、考えてしまった。
「父は、お抱えの忍びではないかと疑っていたようでしたが、それ以上の動きもなかったので、その時はそれっきり……」
「その、月光院様の企みとは、いったい何だったんだ」
「そうね」と小声でささやくように言うと、雲雀はうつむき、そして下からうかがうように宗次郎を見た。大奥という閉鎖された社会の中で、いったい何を見て来たのだろうかと思わせる視線だ。
「お前は知っているのか」
「いえ」
さらりと否定されたが、「でも」とその顔を宗次郎に向いて近づけた。さらに声を小さくして答える。
「証拠はつかんでおりませぬ。ですが多分……竹姫様の暗殺ではと勘ぐっておりました」
「暗殺」という不穏な言葉にぎょっとした。
「将軍様とはいえ腹を痛めて産んだ御子。さらに思い人同然のような関係の間部様。その御二方を同時に喪い、吹上御殿で独り孤独に老いて行くには、月光院様は若すぎたのです」
「だが、間部氏を裏切ったのは月光院様の方じゃないのか」
声が大きくなった宗次郎の唇に、雲雀の人差し指が立てられた。
「いえ。間部様がそうするよう仕向けたというのが真相でございます。そうでもしないと、下手をすれば月光院様は御城を追い出されてしまうやも知れませんでしたからね。ですが、ことが終わってからの喪失感は耐えらえぬものだったのでしょう」
月光院様とて、一人の女だったということか……
「そこへ我が殿はさらなる石をお投げになりました」
「節倹のことか?」
「それもありますが」
とうとう、雲雀の唇は宗次郎の耳元まで近づく。
「将軍職に就くや、五代目将軍様……綱吉様の養女でいらしたわずか十歳の竹姫様をご寵愛なすったのですよ」
これにはあきれた。殿も殿だが……
「まさか、そんな幼子に嫉妬したのか」
「例え五つの幼児でも将軍職に就けます。同じく例え十の少女でも側室になれまする」
「つまり、大奥での力関係が変わるということか」
「いえ、そんな単純には変わりませぬ。今も大奥の頂点には天英院様が君臨しておられます。それに殿には他にも御側室がおられますゆえ」
「それでも……」
「ええ。ですが、月光院様が頼りとする男を城から追い出しておきながら、その城で、系図上とはいえ大叔母にあたる娘を寵愛する。許せなかったのでありましょう」
「その企てを上様は」
「もちろん知りませぬ。全て私の想像の範疇。何も証拠になる物などございませぬ。私が監察してそう判断だけにございますから、内緒ごとなのですよ。怪しい動きはあった……ですが結局何も起こらなかった――というのが、私が父上に報告した内容です」
(しかし、一年以上も経って、何で今頃)
恋の相手も、尾張とはまるで関係の無い寺小姓だった。それを考えると、一見、浅井の娘の身投げと尾張家とは無関係のようにも思える。
「ですが、お美津さんのことを尾張家の求馬様に話したとなると、上様は、求馬様に御家の内情を探らせようと目論んでいるのではないでしょうか」
雲雀と同じことを宗次郎も考えていた。だから、わざわざ求馬を呼び出し、身投げの件を探らせるような話を持ち掛けたのではないか……と。
「確かにそうかもしれんが、求さんは、お美津さんが立花で逢った相手を、尾張家の者だとは思ってもいなかったぞ。そこは上様から知らされて……なんや、その顔は」
奇妙なしかめ面をした雲雀の表情に、話の腰が折れる。
「いえ、だって、何ですか、その『求さん』って」
「求さんは求さんだ。町の皆もそう呼んでいる」
「ああ、そうでした。確かに尾張家の末の弟君は、身分の分別がないとのお噂。それはまことだったのですね」
そう嫌味を言うと、鼻から息を吐いた。
「でもね、それを宗次郎さんまで。いいですか、あなたは上様お抱えの殺生人であるという身分を隠すために、町人餌差のふりをなさっているんですよ」
説教じみた雲雀の言い草に、憮然として答える。
「わかっている。ちゃんと町人らしく振舞っている。素性も明かしてはいない」
しかし、きっぱりと否定され、叱責された。
「そうではありません。むやみに情を持ってしまいますと、真実を見誤ってしまうということを言いたいのです。相手の懐に入っても、情を移されてはなりませぬ。いつ、その御方が上様に謀反しないとも限らないでしょう。そもそも上様と将軍職の座を争った尾張家なのですよ」
バン!
板の間を叩く音が、台所に響き渡った。打った拳がジンジンと痺れる。
「わかり切ったことをいちいち言わんでもええ! 仕事と情の区別くらい、俺にかてわかっとる!」
床を蹴るようにして立ち上がると、振り向きもせず、まっすぐ仕事部屋へと向かった。
雲雀の態度に腹が立った。
求馬が正体を明かそうとしなかったのは、その身分の高さではないと、今更理解した。
紀州と尾張は、将軍の座を争った間柄だと世間では知れている。しかも兄君は上様に反発して国に送り返されたという事情がある。
――「こんな俺でも、今までと同じように接してくれるか」
求馬の心の声が聞こえるようだ。
――「宗次郎は和歌山の出か?」
(それでも俺は……)
自分の立場と求馬への友情を天秤に掛けたところで、その先を考えることは止めた。信頼するもしないも、求馬の行動次第なのだ。
そして、それはきっと上様も同じ思いなのだろうと、思い至る。
上様は、求馬がお美津の件をどのように受け止めるのか。正直に兄との接点を報告するのか否か。それに賭けているのではなかろうか、と。
たわいのない話を交わす間柄なのだ。
鼠を使って見張らせているくせに、それでもきっと上様は求馬のことが好きなのだと、己の勝手な思いつきに可笑しくなって、少しだけ笑った。
-------------
*江戸の瓦版*
*読売――時代劇でおなじみの瓦版。大火や殺人、天変地異、心中、果ては妖怪出没など、庶民の関心を引く記事を読み上げながら売っていた速報性の高い印刷物です。ガセネタや政治批判ぽいものも多く、売り子はほっかむりや笠で顔を隠していることが多かったようです。
粘土板を用いたという説もありますが、木版刷りが主流。近代になってもメディアは安価で売りやすい瓦版を発行していたそうです。
かわら版という記述は、幕末の書物に初めて登場していることから、ここでは「読売」という呼び方をさせています。
「そうですか。上様がそのようなことを」
上様がすでにお美津の件を把握していたことに驚きを隠せない雲雀は、外した前掛けを乱雑に置くと、宗次郎の目の前に座った。
「それにしても、まさか宗次郎さんが尾張の弟君とお知り合いだとは。というよりも、その方の正体もわからずにご一緒していたなんて」
「まさか、尾張の家の者だとは思いもしなかったんだ。今日、身分を明かされて肝を冷やした」
「でしょうね」
呆れたような、冷ややかな目で睨まれる。
「私の方は、読売屋(かわら版屋)に聞き込んでみたのですが、巷の噂の出どころだけはわかりました」
巷の噂――武家の娘が道ならざる恋をして身投げをした。
面白半分に流された風聞ではなかったようだ。
雲雀が宗次郎の前に置いたのは、先日の*読売。お美津の身投げが記事になっていた。それを手に取る。
「この挿絵が余計に哀れで涙を誘うのでしょうね。飛ぶように売れておりました」
華やかな花模様の振袖を着た寝顔のような美しい娘が描かれていた。
「ご近所の話では、大奥を退いてからほとんど出歩くことはなかったらしいのですが、月に一度か二度、市ヶ谷八幡で縁日のある日に、お一人で出かけることがあったそうです」
「その時、誰かと会っていたとか言うのか?」
「ええ。ちょっとした噂になるほど、目立っていらしたようです」
月に一、二度、人と逢うだけで噂になるとは、宗次郎には信じがたい。
「しかしよく憶えているというか、見ているもんだな。他人が誰と会っていたとか」
「その相手が相手ですから」
「有名な奴なのか」
宗次郎はてっきり、安房守の手の者だと思っていた。だから、それ如きで噂になるとは信じられなかったのだ。
「あの辺りでは有名な寺小姓です」
「寺小姓……」
「ですから、お美津さんの身投げを、『享保のお七』だなんて噂する人もいたらしいですわね」
寺小姓というのは、寺の雑用係のようなものであるが、旗本など武家の次男坊以下が多い。
彼らは手習い学問習得という名目のもとに寺入りするのだが、その本質は口減らしである。主な仕事は和尚の身の回りの世話であるが、女人禁制である仏門において、身の回りの世話というのは、慰み者になることを指していた。
言い換えれば、寺小姓には美しい少年が多いのである。
「乙八……恵光寺の乙八と言えば、誰もが振り向く美男だそうですよ」
「その乙八を雲雀が見たことは?」
「いいえ、ないわ。でも八幡宮の縁日に、乙八が女連れでいるのを見たと言う人は確かにいるらしいのです」
人の口に戸は立てられぬ――とはよく言ったものだ。
この噂を、浅井殿は知っていたのだろうか。乙八の相手が自分の娘だと知って、婚姻を進めたのであろうか。
考えれば考えるほど、残された両親が哀れに思えた。
「立花の亭主は、月光院様の遣いが自分の店で誰かと逢っていたことを憶えていたようだった。でも、ここ最近は使っていない」
「お美津さんが使い版をしていた頃、くノ一を立花楼の女中として送り込み、探らせたことがありました。その時の相手は、お美津さんと不必要な言葉を交わすことがなかったらしいので、その相手と恋に落ちたと考えるには無理がありますね」
「そいつは確かに尾張の遣いの者だったのか」
「それは間違いございません。ただ……」
「ただ?」
「いえ、武士と中間者の二人連れだったのですが、武士のなりをした方が供侍のようで、書簡を受け取ったのが中間者だったと。身なりと立場がちぐはぐで妙な印象だった、との報告を受けたことを思い出しました。まあ、正体がばれないように変装をしたとも考えられますが」
ふと、宗次郎の頭に九鬼丸が浮かんだ。彼も中間なのに、やたらと求馬に近しい。安房守にも、そのように近しい中間や小者が側にいたのだろうかと、考えてしまった。
「父は、お抱えの忍びではないかと疑っていたようでしたが、それ以上の動きもなかったので、その時はそれっきり……」
「その、月光院様の企みとは、いったい何だったんだ」
「そうね」と小声でささやくように言うと、雲雀はうつむき、そして下からうかがうように宗次郎を見た。大奥という閉鎖された社会の中で、いったい何を見て来たのだろうかと思わせる視線だ。
「お前は知っているのか」
「いえ」
さらりと否定されたが、「でも」とその顔を宗次郎に向いて近づけた。さらに声を小さくして答える。
「証拠はつかんでおりませぬ。ですが多分……竹姫様の暗殺ではと勘ぐっておりました」
「暗殺」という不穏な言葉にぎょっとした。
「将軍様とはいえ腹を痛めて産んだ御子。さらに思い人同然のような関係の間部様。その御二方を同時に喪い、吹上御殿で独り孤独に老いて行くには、月光院様は若すぎたのです」
「だが、間部氏を裏切ったのは月光院様の方じゃないのか」
声が大きくなった宗次郎の唇に、雲雀の人差し指が立てられた。
「いえ。間部様がそうするよう仕向けたというのが真相でございます。そうでもしないと、下手をすれば月光院様は御城を追い出されてしまうやも知れませんでしたからね。ですが、ことが終わってからの喪失感は耐えらえぬものだったのでしょう」
月光院様とて、一人の女だったということか……
「そこへ我が殿はさらなる石をお投げになりました」
「節倹のことか?」
「それもありますが」
とうとう、雲雀の唇は宗次郎の耳元まで近づく。
「将軍職に就くや、五代目将軍様……綱吉様の養女でいらしたわずか十歳の竹姫様をご寵愛なすったのですよ」
これにはあきれた。殿も殿だが……
「まさか、そんな幼子に嫉妬したのか」
「例え五つの幼児でも将軍職に就けます。同じく例え十の少女でも側室になれまする」
「つまり、大奥での力関係が変わるということか」
「いえ、そんな単純には変わりませぬ。今も大奥の頂点には天英院様が君臨しておられます。それに殿には他にも御側室がおられますゆえ」
「それでも……」
「ええ。ですが、月光院様が頼りとする男を城から追い出しておきながら、その城で、系図上とはいえ大叔母にあたる娘を寵愛する。許せなかったのでありましょう」
「その企てを上様は」
「もちろん知りませぬ。全て私の想像の範疇。何も証拠になる物などございませぬ。私が監察してそう判断だけにございますから、内緒ごとなのですよ。怪しい動きはあった……ですが結局何も起こらなかった――というのが、私が父上に報告した内容です」
(しかし、一年以上も経って、何で今頃)
恋の相手も、尾張とはまるで関係の無い寺小姓だった。それを考えると、一見、浅井の娘の身投げと尾張家とは無関係のようにも思える。
「ですが、お美津さんのことを尾張家の求馬様に話したとなると、上様は、求馬様に御家の内情を探らせようと目論んでいるのではないでしょうか」
雲雀と同じことを宗次郎も考えていた。だから、わざわざ求馬を呼び出し、身投げの件を探らせるような話を持ち掛けたのではないか……と。
「確かにそうかもしれんが、求さんは、お美津さんが立花で逢った相手を、尾張家の者だとは思ってもいなかったぞ。そこは上様から知らされて……なんや、その顔は」
奇妙なしかめ面をした雲雀の表情に、話の腰が折れる。
「いえ、だって、何ですか、その『求さん』って」
「求さんは求さんだ。町の皆もそう呼んでいる」
「ああ、そうでした。確かに尾張家の末の弟君は、身分の分別がないとのお噂。それはまことだったのですね」
そう嫌味を言うと、鼻から息を吐いた。
「でもね、それを宗次郎さんまで。いいですか、あなたは上様お抱えの殺生人であるという身分を隠すために、町人餌差のふりをなさっているんですよ」
説教じみた雲雀の言い草に、憮然として答える。
「わかっている。ちゃんと町人らしく振舞っている。素性も明かしてはいない」
しかし、きっぱりと否定され、叱責された。
「そうではありません。むやみに情を持ってしまいますと、真実を見誤ってしまうということを言いたいのです。相手の懐に入っても、情を移されてはなりませぬ。いつ、その御方が上様に謀反しないとも限らないでしょう。そもそも上様と将軍職の座を争った尾張家なのですよ」
バン!
板の間を叩く音が、台所に響き渡った。打った拳がジンジンと痺れる。
「わかり切ったことをいちいち言わんでもええ! 仕事と情の区別くらい、俺にかてわかっとる!」
床を蹴るようにして立ち上がると、振り向きもせず、まっすぐ仕事部屋へと向かった。
雲雀の態度に腹が立った。
求馬が正体を明かそうとしなかったのは、その身分の高さではないと、今更理解した。
紀州と尾張は、将軍の座を争った間柄だと世間では知れている。しかも兄君は上様に反発して国に送り返されたという事情がある。
――「こんな俺でも、今までと同じように接してくれるか」
求馬の心の声が聞こえるようだ。
――「宗次郎は和歌山の出か?」
(それでも俺は……)
自分の立場と求馬への友情を天秤に掛けたところで、その先を考えることは止めた。信頼するもしないも、求馬の行動次第なのだ。
そして、それはきっと上様も同じ思いなのだろうと、思い至る。
上様は、求馬がお美津の件をどのように受け止めるのか。正直に兄との接点を報告するのか否か。それに賭けているのではなかろうか、と。
たわいのない話を交わす間柄なのだ。
鼠を使って見張らせているくせに、それでもきっと上様は求馬のことが好きなのだと、己の勝手な思いつきに可笑しくなって、少しだけ笑った。
-------------
*江戸の瓦版*
*読売――時代劇でおなじみの瓦版。大火や殺人、天変地異、心中、果ては妖怪出没など、庶民の関心を引く記事を読み上げながら売っていた速報性の高い印刷物です。ガセネタや政治批判ぽいものも多く、売り子はほっかむりや笠で顔を隠していることが多かったようです。
粘土板を用いたという説もありますが、木版刷りが主流。近代になってもメディアは安価で売りやすい瓦版を発行していたそうです。
かわら版という記述は、幕末の書物に初めて登場していることから、ここでは「読売」という呼び方をさせています。
10
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

忍者同心 服部文蔵
大澤伝兵衛
歴史・時代
八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。
服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。
忍者同心の誕生である。
だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。
それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。
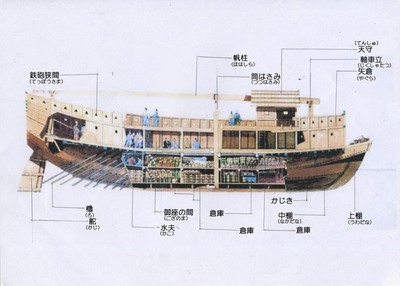

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)
三矢由巳
歴史・時代
時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。
佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。
幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。
ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。
又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。
海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。
一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。
事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。
果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。
シロの鼻が真実を追い詰める!
別サイトで発表した作品のR15版です。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















