5 / 46
第一話 吉宗の隠密
津田越前守助広
しおりを挟む
半平太の部屋に戻るなり、宗次郎は奥側の一番広い座敷にこもって鳥刺し棒をこしらえ始めた。
さりさりと小刀で竹竿の先を平らに削る。少し削っては重さを確かめ、再び削っては均衡がとれているか竿先を振る。この微妙な調整が、道具を自分の手足として扱うためには必要不可欠であった。
適当な竿でも宗次郎の腕ならば刺せぬことはない。それでも宗次郎が竿にこだわるには理由があった。
じっくりと拵えながら、この先のことを考えていた。
竿を削ってしばらくした頃、襖が開いた。いつまで経っても出てこない宗次郎に痺れを切らしたのであろう。
「おい、今日は鳥を追わねえのか」
竿を削っていることに気が付いた半平太が問うた。
「おい、竿ならまだあるだろう」
「これでなきゃ駄目なんですよ」
いつもの竿よりも短いが、代わりにとり餅が塗られるはずの先端は薄く鋭く削られていた。
「俺が郷里で習ったのはこれでしてね」
そう言うと、削った先端を半平太の目の先に突きつける。
「それで雀を刺すのか」
一歩下がった半平太が問い返した。
「だから『鳥刺し』と言うのですよ」
ごくりと半平太が唾を飲んだ。
「ならば、雀は殺すのか」
「まさか! この先で羽の付け根を狙って突くんです。殺しやしません」
「……いったい、親父さんから何の話があったってんだ」
剣呑な面の半平太を見上げる。
「半平太さん、旅支度をしてください。少し遠出します。明朝出立しましょう。得物(武器)はこの鳥刺し棒です。これで仕留められるようになれば一人前ですから」
にこりと微笑んで見せた。
◇
杢右衛門から受け取ったのは、御紋入りの餌差札だけではなかった。
旅支度をしながら、刀掛けに目をやる。目線の先には未だ刀袋に入れたままの長脇差。
――津田越前守助広一尺八寸。
大業物と言われる名刀である。
一見、地味な拵えは、実用しやすいよう、わざと質素に徹したのではないかと思えるほどだった。鞘は無地で艶のない石目塗り、柄の糸巻きもくすんだ黒。どこにも装飾らしい装飾もなく、なんなら兄のお下がりである無銘の脇差の方が意匠は凝っている。
地味な意匠は嫌ではない。むしろ好みだ。糸巻の握り具合に加え、重さも良かった。
それなのに鯉口を切った途端、宗次郎の胃の腑の石ころがさらに増えた。
(こんなけ地味にするんやったら、この御紋は勘弁してくれ……)
鈍い鉄色の縁金に見えたのは、丸に三つ葉葵。
これを見た時、如何にも「すぐでも身に着けよ。わしは良い働きをして見せよう」とせがんでいそうな実直さを見せつつ、実は徳川幕府の密偵であった――というような、裏切りにも似た落胆を覚えた。
おまけに助広の波紋は濤乱である。大波のごとく派手に揺れる煌めきに、「早く血を吸わせてくれ」と、催促されているようで、気持ちが萎えてしまった。
平坦に言うならば、この刀は嫌いである。すぐに鞘に収め、刀袋に仕舞って、さっさと刀掛けに鎮座させた。
「これで何を斬らせるつもりや」
つい、声に出してしまった答えのわかり切っている愚問。
御目見でもない餌差役人が、この様な御紋を身に着ける意味はただ一つ。
幼少の頃から相賀の父の手で鍛錬されてきた。
修験道の厳しい修行に加え、鉄砲を含む、あらゆる武術を仕込まれた。宮井の養子となった後には、鷹師ではなく鳥刺しとしての技を教え込まれた。江戸に来てからは、いざという時に国元がばれないよう江戸前の言葉を覚え、江戸の地を知るために市内だけでなく江戸郊外も歩き回った……。
どれもこれも、「いずれは殿様の御役に立つ」という目的のためである。そのために自分は生かされてきたとすら思っている。
下賜された脇差を眺めながら、宗次郎はつい、和歌山での暮らしを思い出していた。
相賀の父の元で修行をしていた幼い頃……その技が人を殺めるための技術だとは知らず、ただ上達が楽しくて修業を重ねていた時の思い出。
養父による鍛錬は剣術や柔術といった単純な武芸稽古ではなかった。山を駆け抜け、木々を渡り、川を泳ぐ。時には山の奥に入り、鳥や獣を鉄砲で撃つこともあった。
技の上達も嬉しかったが、一つ技を会得すると褒めてくれる、普段は厳しい父のほころぶ顔が一番嬉しかった。
いつからだろう、人を殺める覚悟を背負わされたのは。
全て、人殺しをする技だとわかってから、己の技に磨きがかかった。
瞬殺――それがせめてもの情けだと思い至ったからだ。
そしてそれが、「いずれ」訪れる戦いにおいて、己が生き残るためにも最良の術だということも……
しかし、その「いずれ」は、いっそ来んといてほしかった――それが本音だ。
そう……誰にも言えぬ本心。
それを腹の奥に押し込むように、深く息を吸い、いらぬ雑念を追い出すように、大きく息を吐き出す。
(けど、此度はええよな。半平太さんを連れて派手な人斬りなんぞ出来やん)
と、自分に言い訳をした挙句、助広は刀袋に入れたまま置いておく。
そして腰には普段使いしている無銘の大小を差した。
さりさりと小刀で竹竿の先を平らに削る。少し削っては重さを確かめ、再び削っては均衡がとれているか竿先を振る。この微妙な調整が、道具を自分の手足として扱うためには必要不可欠であった。
適当な竿でも宗次郎の腕ならば刺せぬことはない。それでも宗次郎が竿にこだわるには理由があった。
じっくりと拵えながら、この先のことを考えていた。
竿を削ってしばらくした頃、襖が開いた。いつまで経っても出てこない宗次郎に痺れを切らしたのであろう。
「おい、今日は鳥を追わねえのか」
竿を削っていることに気が付いた半平太が問うた。
「おい、竿ならまだあるだろう」
「これでなきゃ駄目なんですよ」
いつもの竿よりも短いが、代わりにとり餅が塗られるはずの先端は薄く鋭く削られていた。
「俺が郷里で習ったのはこれでしてね」
そう言うと、削った先端を半平太の目の先に突きつける。
「それで雀を刺すのか」
一歩下がった半平太が問い返した。
「だから『鳥刺し』と言うのですよ」
ごくりと半平太が唾を飲んだ。
「ならば、雀は殺すのか」
「まさか! この先で羽の付け根を狙って突くんです。殺しやしません」
「……いったい、親父さんから何の話があったってんだ」
剣呑な面の半平太を見上げる。
「半平太さん、旅支度をしてください。少し遠出します。明朝出立しましょう。得物(武器)はこの鳥刺し棒です。これで仕留められるようになれば一人前ですから」
にこりと微笑んで見せた。
◇
杢右衛門から受け取ったのは、御紋入りの餌差札だけではなかった。
旅支度をしながら、刀掛けに目をやる。目線の先には未だ刀袋に入れたままの長脇差。
――津田越前守助広一尺八寸。
大業物と言われる名刀である。
一見、地味な拵えは、実用しやすいよう、わざと質素に徹したのではないかと思えるほどだった。鞘は無地で艶のない石目塗り、柄の糸巻きもくすんだ黒。どこにも装飾らしい装飾もなく、なんなら兄のお下がりである無銘の脇差の方が意匠は凝っている。
地味な意匠は嫌ではない。むしろ好みだ。糸巻の握り具合に加え、重さも良かった。
それなのに鯉口を切った途端、宗次郎の胃の腑の石ころがさらに増えた。
(こんなけ地味にするんやったら、この御紋は勘弁してくれ……)
鈍い鉄色の縁金に見えたのは、丸に三つ葉葵。
これを見た時、如何にも「すぐでも身に着けよ。わしは良い働きをして見せよう」とせがんでいそうな実直さを見せつつ、実は徳川幕府の密偵であった――というような、裏切りにも似た落胆を覚えた。
おまけに助広の波紋は濤乱である。大波のごとく派手に揺れる煌めきに、「早く血を吸わせてくれ」と、催促されているようで、気持ちが萎えてしまった。
平坦に言うならば、この刀は嫌いである。すぐに鞘に収め、刀袋に仕舞って、さっさと刀掛けに鎮座させた。
「これで何を斬らせるつもりや」
つい、声に出してしまった答えのわかり切っている愚問。
御目見でもない餌差役人が、この様な御紋を身に着ける意味はただ一つ。
幼少の頃から相賀の父の手で鍛錬されてきた。
修験道の厳しい修行に加え、鉄砲を含む、あらゆる武術を仕込まれた。宮井の養子となった後には、鷹師ではなく鳥刺しとしての技を教え込まれた。江戸に来てからは、いざという時に国元がばれないよう江戸前の言葉を覚え、江戸の地を知るために市内だけでなく江戸郊外も歩き回った……。
どれもこれも、「いずれは殿様の御役に立つ」という目的のためである。そのために自分は生かされてきたとすら思っている。
下賜された脇差を眺めながら、宗次郎はつい、和歌山での暮らしを思い出していた。
相賀の父の元で修行をしていた幼い頃……その技が人を殺めるための技術だとは知らず、ただ上達が楽しくて修業を重ねていた時の思い出。
養父による鍛錬は剣術や柔術といった単純な武芸稽古ではなかった。山を駆け抜け、木々を渡り、川を泳ぐ。時には山の奥に入り、鳥や獣を鉄砲で撃つこともあった。
技の上達も嬉しかったが、一つ技を会得すると褒めてくれる、普段は厳しい父のほころぶ顔が一番嬉しかった。
いつからだろう、人を殺める覚悟を背負わされたのは。
全て、人殺しをする技だとわかってから、己の技に磨きがかかった。
瞬殺――それがせめてもの情けだと思い至ったからだ。
そしてそれが、「いずれ」訪れる戦いにおいて、己が生き残るためにも最良の術だということも……
しかし、その「いずれ」は、いっそ来んといてほしかった――それが本音だ。
そう……誰にも言えぬ本心。
それを腹の奥に押し込むように、深く息を吸い、いらぬ雑念を追い出すように、大きく息を吐き出す。
(けど、此度はええよな。半平太さんを連れて派手な人斬りなんぞ出来やん)
と、自分に言い訳をした挙句、助広は刀袋に入れたまま置いておく。
そして腰には普段使いしている無銘の大小を差した。
10
お気に入りに追加
37
あなたにおすすめの小説


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

忍者同心 服部文蔵
大澤伝兵衛
歴史・時代
八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。
服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。
忍者同心の誕生である。
だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。
それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。
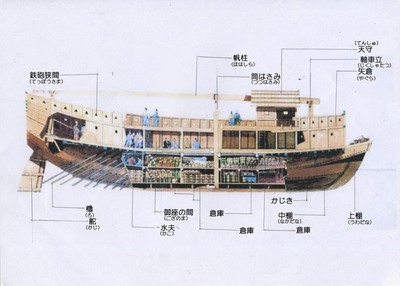

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)
三矢由巳
歴史・時代
時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。
佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。
幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。
ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。
又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。
海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。
一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。
事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。
果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。
シロの鼻が真実を追い詰める!
別サイトで発表した作品のR15版です。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















