38 / 49
七
坊ちゃんの正体
しおりを挟む
藤田にとって、蟲の存在は怪異そのものなのだろうな。あいつにとっては昔話や言い伝えとさほど変わらぬ。
ああ、俺だってそうさ。
ただ信じられるか信じられないかと問われたら、信じるに決まっている。下手な神や仏の教えよりも、坊ちゃんの言う言葉を信じる。だが、それをまざまざと現実に見せつけられるとなると違ってくるのだということが、よぉくわかった。
信じるかどうかと、目の前の事実を認めるとかどうかは、別の感覚なんだよ。
――だから、豆千代が疑わしいと頭の片隅では感じていたのに、認めることができなかった。
それらを差し置いても、坊ちゃんに特別な力があるということは事実だ。なぜそうなのかという理由も、今となってははっきりと理解できる。
なぜならば…………
「坊ちゃんも、体に二匹の蟲を飼っている。そのせいで、坊ちゃんには、そういった奇怪な現象の類いが俺たちよりもよく見えるんだろう。だから俺は坊ちゃんの力を信じられるんだ」
「なんだと」
目の前の男が目を見張るのを見て、俺は藤田と同じように両手を机の上で組み、自分の手を睨んだまま遠い過去を思い出していた。
「これには、坊ちゃんの産まれから話さねばならねえ……」
坊ちゃん自身にも、亡き主君にも話したことのない――いや、話せなかった禁秘事項だ。
それを、ついこの間出逢ったばかりの男に打ち明ける。怪異体験を共有する同志として……
「俺が元服する前に坊ちゃんは産まれた。妾を取らず、しかし長く世継ぎができなかった酒井家の殿様は、三十俵二人扶持貧乏御家人の次男であった俺を、剣の腕を見込んで小姓見習いにして下すった。さらに養子にという話まで出ていた矢先のことだった」
ギシリと木のきしむ音がした。
俺の昔話をじっくりと聞く気になってくれたのか、藤田が組んでいた手を解き、椅子の背もたれに体を預けていた。
「奥様がご懐妊……当然俺は、養子の話を白紙に戻して欲しいと申し出たが、それは保留という形でお産の日を迎えることになったのだ」
唾を飲み込み、俺はあの日の出来事をもう一度頭の中で再現した。
「難産だった……双子だったからだ」
「双子? あいつに兄弟がいたのか。今も生きているのか」
「まあ聞け。……お産の部屋に男が立ち入っちゃあいけねえのは百も承知だった。ガキの俺にだってわかっていた。だがあの時、俺は誰かに呼ばれた気がして、取り上げ婆やら屋敷の女衆が騒いでいる奥の部屋を開けちまった」
お産は慶び事ではあるが、血を流す忌事でもある。産婦となった女は奥の部屋をあてがわれ、そこは男子禁制と決まっていた。農村では離れの小屋に隔離される習わしが今も続いている。
「俺がのぞいた時、ちょうど一人目が取り上げられたところで、俺はそこにいたお絹さんと目が合った。『急いでたらいをもう一つ持っておいで』――そう言われ、赤子が双子だと気付いた俺は、急ぎ、たらいと湯を用意した。だが奥の部屋へ戻った時には、二人目がすでに赤く染まった古い湯で洗われているところだった」
自分の手を見ていた顔を上げ、信じろと懇願する意味を込め、藤田を見たが、奴は相変わらずの無表情だった。
そのまま、嘘のような本当の話を続ける。
「その時、見たんだよ。すでに布に包まれていた、先に産まれた赤子の口から小さい蟲が這い出たのを」
「むし……あの古書に描かれていた蟲か」
「形は……そこまで憶えていねえ。だが、あの本に描かれていたような恐ろしい雰囲気ではなかった。もっと小さくて……油虫にも満たない大きさで、儚げに見えた。そう、ちょうどこいつみてえな」
机の上に置かれた帳面の上を、五分(1.5㎝)ほどの長さまで育った紙魚が這っていた。それを藤田がプツリと潰すと、ばらばらに砕けた紙魚の銀粉が紙の上に残った。
「そいつよりは大きかったが、何しろ産まれたての赤子の口から出るくらいの大きさだ。怖くもなけりゃ、気味悪いとも思わなかった。だが、そいつがもう一人の赤子に向かって這って行くのを見た時、急にぞっと寒気が襲ってきたんだ。真冬のことだ。坊ちゃんの名前の由来の一つだ。正月朔日のことだったからな、寒いのは当たりめえだと言われたらそうかもしれねえ」
ありゃあ、冬の寒さとは違っていたんだよ。どう言やぁ、伝わるだろうなあ。あん時の怖気を……
「だがな、部屋は火鉢をいくつも並べてあって、何よりも人いきれで暑いくれえだったんだ。なのに寒気を感じている俺の目の前で、その蟲は、湯の中でくったりとしていた赤子の口に滑り込んで行きやがった」
「お前のほかに、誰もそれを見ていないのか」
首を縦に振る。
見ていないと言うよりも、俺にしか見えていなかったのだ。
いつまでもぼんやりと眺めていたせいだろう。早く出ていけだとか、男の子が来る場所じゃねえとか、散々女たちが大声で叫んでいたと思うんだが、あの蟲の光景が強烈過ぎて、そのほかのことはほとんど憶えていねえ。
「あとからお絹さんに聞いた話だ。初めに産まれた赤ん坊は間もなく息を引き取って、死にかけていた赤子を新しい湯で洗ってやったら、息を吹き返したのだと」
「……その生き残った弟の方がてめえの今の御主人ということか」
「ああ。坊ちゃんは何も知らない。一人息子としか知らされていねえ……だから、名前も一を表す『朔』の字を付けられた」
「だが、あの小さな店主の中身は別人というわけだ」
「それは! ……いや、わからん」
力なく頭を振る。
あの蟲が、弟と兄の生死を分けたのだということを、ぼんやりとだが感じてはいた。だが、あれが魂の化身だと知らなかった今までは、坊ちゃんの中身が別人の魂だなどと考えたこともなかった。
「……わからん」
同じ言葉を二度繰り返した。
しかし、大石の念を持つ〈魂の蟲〉が別人へと次々乗り換えていったのだとすれば、すでに坊ちゃんも別人の魂だということになる。
(どう考えりゃあいいんだ。)
俺のぼんくらな頭じゃあ、到底わからねえ。
机の上の自分の手を開いたり閉じたりする。この手は己の意志で動かせているように思えるが、〈大石〉に乗っ取られ人を次々と殺した三井や佐々木のことを考えると、己の意志と体は別物で、体なんぞただの肉の器にすぎない気がした。
だが、こうも考えられる。
「蟲が人の念を運ぶのだとすれば、もしかしたら死にかけていた弟の体を、兄が救おうとしたのかもしれねえ」
結果、蟲が出て行ってしまった兄の体は死んでしまったのだから。
だが、藤田の考え方は違うようだ。
「逆かもしれねえぜ」
「なに」
「実は元気そうに見えて、兄の方は既に死にかけていたのかもしれぬ。自分が産まれて早速死ぬことを予感しちまった兄は、弟の体を奪ってでも生き延びたかったんじゃあねえか。ついでに言うと、三井にしろ、佐々木にしろ、蟲を二匹飼っていた奴らは、恐ろしく強い。佐々木はまるで痛みを感じていないかのようだった」
新選組の組長として死線を潜り抜け、維新後も生き続けている藤田の言葉は重い。おまけに、佐々木を追ったが逃がしているという事実が、さらにその言葉を正解だと思わせるに十分の重みを加えていた。
蟲は強い念を持つと他人の体を乗っ取れるほどの力を持つ――この概念が真実だとすれば、藤田の言うことの方が正解だ。
「しかし、お前の話が事実だとすれば……そりゃあ、他人の蟲も見えちまうだろうな。二匹の蟲を飼い馴らして今の今まで生きてきたのだ。神通力ぐれえ、使えても不思議じゃねえな」
言い方はひねくれて小馬鹿にしているようだが、藤田の目は真剣で、むしろ思いつめている風にも見えた。
『二匹を飼い馴らす』――いや、あの蟲が魂であり人の念そのものだとすれば、二匹が共存しているのではなく、兄の蟲が弟を蹂躙していると考えるべきか。
「坊ちゃんが言うには、普通ならば他人の蟲に乗っ取られると、元居た本人の蟲は食われちまうと考えるのが妥当らしい……」
坊ちゃんの正体を説明するために自分から始めた昔話であったが、今まで考えたこともなかった正体の見解に、俺は動揺していた。
ああ、俺だってそうさ。
ただ信じられるか信じられないかと問われたら、信じるに決まっている。下手な神や仏の教えよりも、坊ちゃんの言う言葉を信じる。だが、それをまざまざと現実に見せつけられるとなると違ってくるのだということが、よぉくわかった。
信じるかどうかと、目の前の事実を認めるとかどうかは、別の感覚なんだよ。
――だから、豆千代が疑わしいと頭の片隅では感じていたのに、認めることができなかった。
それらを差し置いても、坊ちゃんに特別な力があるということは事実だ。なぜそうなのかという理由も、今となってははっきりと理解できる。
なぜならば…………
「坊ちゃんも、体に二匹の蟲を飼っている。そのせいで、坊ちゃんには、そういった奇怪な現象の類いが俺たちよりもよく見えるんだろう。だから俺は坊ちゃんの力を信じられるんだ」
「なんだと」
目の前の男が目を見張るのを見て、俺は藤田と同じように両手を机の上で組み、自分の手を睨んだまま遠い過去を思い出していた。
「これには、坊ちゃんの産まれから話さねばならねえ……」
坊ちゃん自身にも、亡き主君にも話したことのない――いや、話せなかった禁秘事項だ。
それを、ついこの間出逢ったばかりの男に打ち明ける。怪異体験を共有する同志として……
「俺が元服する前に坊ちゃんは産まれた。妾を取らず、しかし長く世継ぎができなかった酒井家の殿様は、三十俵二人扶持貧乏御家人の次男であった俺を、剣の腕を見込んで小姓見習いにして下すった。さらに養子にという話まで出ていた矢先のことだった」
ギシリと木のきしむ音がした。
俺の昔話をじっくりと聞く気になってくれたのか、藤田が組んでいた手を解き、椅子の背もたれに体を預けていた。
「奥様がご懐妊……当然俺は、養子の話を白紙に戻して欲しいと申し出たが、それは保留という形でお産の日を迎えることになったのだ」
唾を飲み込み、俺はあの日の出来事をもう一度頭の中で再現した。
「難産だった……双子だったからだ」
「双子? あいつに兄弟がいたのか。今も生きているのか」
「まあ聞け。……お産の部屋に男が立ち入っちゃあいけねえのは百も承知だった。ガキの俺にだってわかっていた。だがあの時、俺は誰かに呼ばれた気がして、取り上げ婆やら屋敷の女衆が騒いでいる奥の部屋を開けちまった」
お産は慶び事ではあるが、血を流す忌事でもある。産婦となった女は奥の部屋をあてがわれ、そこは男子禁制と決まっていた。農村では離れの小屋に隔離される習わしが今も続いている。
「俺がのぞいた時、ちょうど一人目が取り上げられたところで、俺はそこにいたお絹さんと目が合った。『急いでたらいをもう一つ持っておいで』――そう言われ、赤子が双子だと気付いた俺は、急ぎ、たらいと湯を用意した。だが奥の部屋へ戻った時には、二人目がすでに赤く染まった古い湯で洗われているところだった」
自分の手を見ていた顔を上げ、信じろと懇願する意味を込め、藤田を見たが、奴は相変わらずの無表情だった。
そのまま、嘘のような本当の話を続ける。
「その時、見たんだよ。すでに布に包まれていた、先に産まれた赤子の口から小さい蟲が這い出たのを」
「むし……あの古書に描かれていた蟲か」
「形は……そこまで憶えていねえ。だが、あの本に描かれていたような恐ろしい雰囲気ではなかった。もっと小さくて……油虫にも満たない大きさで、儚げに見えた。そう、ちょうどこいつみてえな」
机の上に置かれた帳面の上を、五分(1.5㎝)ほどの長さまで育った紙魚が這っていた。それを藤田がプツリと潰すと、ばらばらに砕けた紙魚の銀粉が紙の上に残った。
「そいつよりは大きかったが、何しろ産まれたての赤子の口から出るくらいの大きさだ。怖くもなけりゃ、気味悪いとも思わなかった。だが、そいつがもう一人の赤子に向かって這って行くのを見た時、急にぞっと寒気が襲ってきたんだ。真冬のことだ。坊ちゃんの名前の由来の一つだ。正月朔日のことだったからな、寒いのは当たりめえだと言われたらそうかもしれねえ」
ありゃあ、冬の寒さとは違っていたんだよ。どう言やぁ、伝わるだろうなあ。あん時の怖気を……
「だがな、部屋は火鉢をいくつも並べてあって、何よりも人いきれで暑いくれえだったんだ。なのに寒気を感じている俺の目の前で、その蟲は、湯の中でくったりとしていた赤子の口に滑り込んで行きやがった」
「お前のほかに、誰もそれを見ていないのか」
首を縦に振る。
見ていないと言うよりも、俺にしか見えていなかったのだ。
いつまでもぼんやりと眺めていたせいだろう。早く出ていけだとか、男の子が来る場所じゃねえとか、散々女たちが大声で叫んでいたと思うんだが、あの蟲の光景が強烈過ぎて、そのほかのことはほとんど憶えていねえ。
「あとからお絹さんに聞いた話だ。初めに産まれた赤ん坊は間もなく息を引き取って、死にかけていた赤子を新しい湯で洗ってやったら、息を吹き返したのだと」
「……その生き残った弟の方がてめえの今の御主人ということか」
「ああ。坊ちゃんは何も知らない。一人息子としか知らされていねえ……だから、名前も一を表す『朔』の字を付けられた」
「だが、あの小さな店主の中身は別人というわけだ」
「それは! ……いや、わからん」
力なく頭を振る。
あの蟲が、弟と兄の生死を分けたのだということを、ぼんやりとだが感じてはいた。だが、あれが魂の化身だと知らなかった今までは、坊ちゃんの中身が別人の魂だなどと考えたこともなかった。
「……わからん」
同じ言葉を二度繰り返した。
しかし、大石の念を持つ〈魂の蟲〉が別人へと次々乗り換えていったのだとすれば、すでに坊ちゃんも別人の魂だということになる。
(どう考えりゃあいいんだ。)
俺のぼんくらな頭じゃあ、到底わからねえ。
机の上の自分の手を開いたり閉じたりする。この手は己の意志で動かせているように思えるが、〈大石〉に乗っ取られ人を次々と殺した三井や佐々木のことを考えると、己の意志と体は別物で、体なんぞただの肉の器にすぎない気がした。
だが、こうも考えられる。
「蟲が人の念を運ぶのだとすれば、もしかしたら死にかけていた弟の体を、兄が救おうとしたのかもしれねえ」
結果、蟲が出て行ってしまった兄の体は死んでしまったのだから。
だが、藤田の考え方は違うようだ。
「逆かもしれねえぜ」
「なに」
「実は元気そうに見えて、兄の方は既に死にかけていたのかもしれぬ。自分が産まれて早速死ぬことを予感しちまった兄は、弟の体を奪ってでも生き延びたかったんじゃあねえか。ついでに言うと、三井にしろ、佐々木にしろ、蟲を二匹飼っていた奴らは、恐ろしく強い。佐々木はまるで痛みを感じていないかのようだった」
新選組の組長として死線を潜り抜け、維新後も生き続けている藤田の言葉は重い。おまけに、佐々木を追ったが逃がしているという事実が、さらにその言葉を正解だと思わせるに十分の重みを加えていた。
蟲は強い念を持つと他人の体を乗っ取れるほどの力を持つ――この概念が真実だとすれば、藤田の言うことの方が正解だ。
「しかし、お前の話が事実だとすれば……そりゃあ、他人の蟲も見えちまうだろうな。二匹の蟲を飼い馴らして今の今まで生きてきたのだ。神通力ぐれえ、使えても不思議じゃねえな」
言い方はひねくれて小馬鹿にしているようだが、藤田の目は真剣で、むしろ思いつめている風にも見えた。
『二匹を飼い馴らす』――いや、あの蟲が魂であり人の念そのものだとすれば、二匹が共存しているのではなく、兄の蟲が弟を蹂躙していると考えるべきか。
「坊ちゃんが言うには、普通ならば他人の蟲に乗っ取られると、元居た本人の蟲は食われちまうと考えるのが妥当らしい……」
坊ちゃんの正体を説明するために自分から始めた昔話であったが、今まで考えたこともなかった正体の見解に、俺は動揺していた。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

白雉の微睡
葛西秋
歴史・時代
中大兄皇子と中臣鎌足による古代律令制度への政治改革、大化の改新。乙巳の変前夜から近江大津宮遷都までを辿る古代飛鳥の物語。
――馬が足りない。兵が足りない。なにもかも、戦のためのものが全て足りない。
飛鳥の宮廷で中臣鎌子が受け取った葛城王の木簡にはただそれだけが書かれていた。唐と新羅の連合軍によって滅亡が目前に迫る百済。その百済からの援軍要請を満たすための数千騎が揃わない。百済が完全に滅亡すれば唐は一気に倭国に攻めてくるだろう。だがその唐の軍勢を迎え撃つだけの戦力を倭国は未だ備えていなかった。古代に起きた国家存亡の危機がどのように回避されたのか、中大兄皇子と中臣鎌足の視点から描く古代飛鳥の歴史物語。
主要な登場人物:
葛城王(かつらぎおう)……中大兄皇子。のちの天智天皇、中臣鎌子(なかとみ かまこ)……中臣鎌足。藤原氏の始祖。王族の祭祀を司る中臣連を出自とする

夜に咲く花
増黒 豊
歴史・時代
2017年に書いたものの改稿版を掲載します。
幕末を駆け抜けた新撰組。
その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。
よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

田楽屋のぶの店先日記〜殿ちびちゃん参るの巻〜
皐月なおみ
歴史・時代
わけあり夫婦のところに、わけあり子どもがやってきた!?
冨岡八幡宮の門前町で田楽屋を営む「のぶ」と亭主「安居晃之進」は、奇妙な駆け落ちをして一緒になったわけあり夫婦である。
あれから三年、子ができないこと以外は順調だ。
でもある日、晃之進が見知らぬ幼子「朔太郎」を、連れて帰ってきたからさあ、大変!
『これおかみ、わしに気安くさわるでない』
なんだか殿っぽい喋り方のこの子は何者?
もしかして、晃之進の…?
心穏やかではいられないながらも、一生懸命面倒をみるのぶに朔太郎も心を開くようになる。
『うふふ。わし、かかさまの抱っこだいすきじゃ』
そのうちにのぶは彼の尋常じゃない能力に気がついて…?
近所から『殿ちびちゃん』と呼ばれるようになった朔太郎とともに、田楽屋の店先で次々に起こる事件を解決する。
亭主との関係
子どもたちを振り回す理不尽な出来事に対する怒り
友人への複雑な思い
たくさんの出来事を乗り越えた先に、のぶが辿り着いた答えは…?
※田楽屋を営む主人公が、わけありで預かることになった朔太郎と、次々と起こる事件を解決する物語です!
※歴史・時代小説コンテストエントリー作品です。もしよろしければ応援よろしくお願いします。
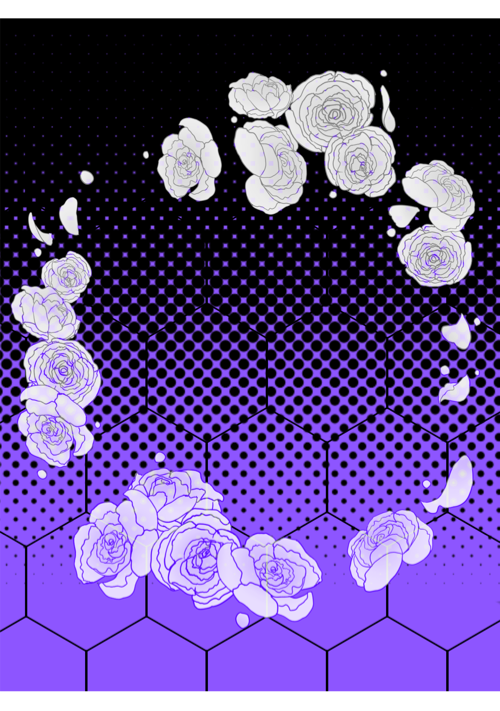
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?

新選組の漢達
宵月葵
歴史・時代
オトコマエな新選組の漢たちでお魅せしましょう。
新選組好きさんに贈る、一話完結の短篇集。
別途連載中のジャンル混合型長編小説『碧恋の詠―貴方さえ護れるのなら、許されなくても浅はかに。』から、
歴史小説の要素のみを幾つか抽出したスピンオフ的短篇小説です。もちろん、本編をお読みいただいている必要はありません。
恋愛等の他要素は無くていいから新選組の歴史小説が読みたい、そんな方向けに書き直した短篇集です。
(ちなみに、一話完結ですが流れは作ってあります)
楽しんでいただけますように。
★ 本小説では…のかわりに・を好んで使用しております ―もその場に応じ個数を変えて並べてます

壬生狼の戦姫
天羽ヒフミ
歴史・時代
──曰く、新撰組には「壬生狼の戦姫」と言われるほどの強い女性がいたと言う。
土方歳三には最期まで想いを告げられなかった許嫁がいた。名を君菊。幼馴染であり、歳三の良き理解者であった。だが彼女は喧嘩がとんでもなく強く美しい女性だった。そんな彼女にはある秘密があって──?
激動の時代、誠を貫いた新撰組の歴史と土方歳三の愛と人生、そして君菊の人生を描いたおはなし。
参考・引用文献
土方歳三 新撰組の組織者<増補新版>新撰組結成150年
図説 新撰組 横田淳
新撰組・池田屋事件顛末記 冨成博

湖水のかなた
優木悠
歴史・時代
6/7完結しました。
新選組を脱走した川井信十郎。傷ついた彼は、心を失った少女おゆいに助けられる。そして始まる彼と彼女の逃避行。
信十郎を追う藤堂平助。襲い来る刺客たち。
ふたりの道ゆきの果てに、安息は訪れるのか。
琵琶湖岸を舞台に繰り広げられる、男と幼女の逃亡劇。

鬼嫁物語
楠乃小玉
歴史・時代
織田信長家臣筆頭である佐久間信盛の弟、佐久間左京亮(さきょうのすけ)。
自由奔放な兄に加え、きっつい嫁に振り回され、
フラフラになりながらも必死に生き延びようとする彼にはたして
未来はあるのか?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















