10 / 49
二
手掛かりは「ムシ」
しおりを挟む
少し話すだけでわかってしまった。この藤田という男も、維新前はこちら側の人間であったのだろうと。
今は新政府の狗と成り下がった男を睨みつける。
俺は坊ちゃんの側にいると決めていた。だからこそ、商売人に成り下がることになっても、何ら卑屈な想いはない。だがな、一つ心に誓ったことだけはあった。
(ぜってえ、新政府の狗にはならねえ。あいつらの下で働くくれえなら、首を刎ねられた方がましだ!)
これが俺の武士としての矜持だ。
「なあ、藤田さんも亡霊の側の人間だったんじゃあねえんですかい」
藤田の左の眉がひくりと上がり、太い指がサーベルの柄をなぞる。
「何が言いたい」
「今だから言えますがね、坊ちゃんの家も直参でしてね。そりゃあ、御一新の折には苦汁を舐めさせられたもんでさ。だから『維新』なんてぇ言葉は死んでも使いたかねえが、だからと言って今更、恨みを晴らしたいとも思ってはいねえ。いねえが、恨む気持ちはわかるんだよ。……安易に分かるとか言うのもなんだがな」
江戸の名が東京府などという胡散臭い名前に変わり、文明開化とやらで西洋化が進み、暮らしがどれほど便利になろうとも、新政府軍のやったことを、俺は一生、許さねえだろう。
「ふん、どれだけ恨みが強かろうが、亡霊などおらぬ。いるのはただの人殺しだ」
つまらなさそうに、帳場机に肘をついて俺たちの会話を聞いていた坊ちゃんが、おもむろに口を開いた。
「ねえ、藤田さん、僕に仕事を頼む気になった? 亡霊探しなら、警視庁よりもうまくやれると思うよ。何しろ僕には、そういう失せ物を見つける神通力があるからね」
「坊ちゃん!」
「相手は生きた人間だ!」
俺と藤田が二人して大きな声を上げた。
だが坊ちゃんは何食わぬ顔でへらりと答える。
「神通力を貸すだけだよ。それに、この事件にうちの客が関わっている可能性も無きにしも非ず……だろ」
珠緒のことを言っているのか、それとも石川か、伊勢屋か菱屋か……。関わっているというのは、殺しに関与しているということなのか、ただ単に巻き込まれそうだということなのか。
いずれにせよ、坊ちゃんの物騒な思いつきに狼狽した。
「神通力だと、馬鹿々々しい……」と、まるで相手にしないと思われた藤田だったが、
「とりあえず俺は伊勢屋の珠緒が誰に本を又貸ししたのか、裏を取るところから始めよう」
立ち上がると、ズボンのポケットに手を突っ込んだ。そして紅葉の生け花の手前に畳んだ紙幣を置きやがった。
「おい、藤田さん!」
つまり、仕事を依頼するということじゃねえかよ!
「ああ、そういや、上野の事件に遭遇した巡査が気になることを言っていたな。『ムシ』がどうとか」
藤田が思い出したように振り返って言った。
言っている意味が分からない。「ムシ」だと?
「ムシ? どういう意味だ。ムシとは蝉とか蠅といった虫のことか」
「わからん。斬られた巡査が死ぬ間際に言い残した言葉が『ムシ』だったらしい。俺が直接聞いたわけじゃねえからわからんが、『ムシ、ムシ』と呻きながら死んだそうだ」
瞬間、俺の頭に、ある風景が蘇っていた……
――累々と散らばる死体から湧く様に現れた蟲……。
今思い返してみても、夢か現か、未だに分からぬ光景。
続々と死体の陰から現れたのは鱗をまとった節のある平たい蟲で、大きさはまちまちだが、どれも土蔵の隅を這っている太った油虫より一回り以上は大きい。その気味の悪い蟲の、長々とした触角と何本あるのか分からない足と大きな顎が、ざわざわとそれぞれ別々の意志でも持つかのように蠢いているのを見たことがある。
それらは現れてしばらくすると丸まってしまって、次々その背中が割れていった。
(なるほど、天へと昇るのか……)
漠然とそう感じた。あれは魂の化身だ――と。
一つの死体に一つの蟲が沸いている。
その蟲の背中から現れたのは無数の細かな羽虫で、まるで蜻蛉のように儚く、焼野に立ち昇る細い黒い煙に乗って、ふわりふわりと空へ舞い上がって行った。
幽玄であり、かつ不気味なその光景を、平和な生活の中でいつしか忘れていた。
「どうしたんだい。ぼんやりして」
坊ちゃんの声が聞こえた時、すでに藤田はいなかった。
「明日、行くよ」
さっそくか――げんなりとして尋ねる。
「菱屋さんですか、それとも辻斬りがあったという四谷ですかい」
いよいよ危険な『亡霊探し』の始まりだ――と覚悟を決めたのだが、意外な場所を指定してきた。
「その前に上野だ」
「へ?」
「ムシ……三四郎も気になるんだろ。新聞で詳しい場所を確認しろ」
『三四郎も』ということは、坊ちゃんもあの『ムシ』の話が気になったらしい。
言われたまま、上野の事件が載っていた新聞を取り出し、事件現場についてもう一度確認をする。
「新聞によると……上野は谷中となっていますね。『谷中ハ一乗寺ノ近ク辻ニテ見廻リノ巡査一名斬殺』……と。ここへ行って何をなさる気ですか。あまり危ういことには首を突っ込まない方が」
俺の苦言は、あっさり遮られた。
「心配は無用だ。件の辻斬りが同じ人物の仕業だとすると、既に奴は四谷あたりに潜んでいるということになる。今更上野には戻らないだろう」
「もし、それぞれの事件が同じ人間の仕業でなかったらどうするんですかい」
複数人の人殺しを相手取って探索するなんぞ、無謀としか思えない。
「いや、これは同じ人間の仕業だ。ただし、辻斬りだけだ。厠の殺しは殺し方が違いすぎる」
「……」
何かを確信しているような坊ちゃんの言い方に、再び顔を見返した。
冴えた黒い眼の奥で、既にこの事件に関する様々な……俺には見えることのない物を見ているのだと、改めて感心する。
それは目に見えないもの。『念の色』といった類の現象だけではなく、人間の行動の機微とでも言うか、誰しもが見逃すようなほんのわずかな矛盾や歪みを彼は見ているのだ。そしてそれらをばらして意味を考察したのち、正しく組み立てていく。
(そう、いつだって坊ちゃんは正しい)
酒井家の現当主とはいえ、一回り以上も若い坊ちゃんにおとなしく仕えている理由の一つである。
未だかつて、坊ちゃんの判断が誤っていたことは無かった。
◇◇
早朝……本来なら明け六つの鐘が鳴る時刻。
生活に馴染んでいた〈時の鐘〉は四年も前に廃止となった。それなのに未だ明け六つの鐘が鳴る時刻になると、洋時計を見るよりも先に耳を澄ましてしまう。
貸本屋の朝は早い。お絹さんが店へ出てくる前に、開店の準備に取り掛からなくてはならない。何しろ、俺は『丁稚』であり、『手代』であり、『行商人』だからな。
坊ちゃんの乳母だったお絹さんは、酒井家が没落してしまった後も坊ちゃんの元を離れず、今も通いで店の手伝いや家事や、身の回りのあれこれを請け負ってくれていた。
この時間、坊ちゃんはまだ寝ている。
通用口と庭、二か所の木戸の閂を開け、桶とたらいに水を汲んでおく。そのうちお絹さんがやって来て、店の奥に位置する台所で、簡単な朝食を作ってくれる。
おみおつけのふくよかな香りを感じながら、台所と隣り合った作業部屋にて背負子の準備をしていると、ガタガタと賑やかな木の音が近付いて来た。
坊ちゃんが起きたのだ。
坊ちゃんは通り土間の向こうにある離れで寝起きをしている。そのため裸足で行き来できるよう、土間の端には隙間なく、すのこを並べていた。
起きてから厠で用を足し、あらかじめ用意しておいた桶の水で顔を清め、髪を撫でつける。服だけはお絹さんが前の晩に明くる日に身に着ける下着から着流しから靴下まで準備しているが、全ての身支度は、誰の手も借りず全て自分で済ませるよう、幼いころから躾けられていた。
家の中でも使えるように先端を皮で覆った杖を突きながら、すのこの上を渡って台所まで来ると、半分寝ぼけまなこでお絹さんに朝の挨拶をした。
「おはよ」
「はい、おはようございます。朔様」
お絹さんは今でも朔太郎ではなく『朔様』という呼び方のままだ。
壁伝いに作業部屋まで来た坊ちゃんが、挨拶もせずいきなり念を押す。
「行くよね」
作業の手を止め、見上げる。
「新橋から京橋までの間を人力車が通っておりまする。あれに乗って良いのなら」
「別にいいよ。そのくらいの贅沢なら許す」
「有難き幸せ」
いやはや小柄だとはいえ、ほぼ成人に近い坊ちゃんを背負って歩くのだ。御城(今は皇居だが)を挟んで反対方角にある上野まで歩くとなると中々きついものがある。少しくらい楽をしても良いだろう。――と考えながら支度を進めた。
(どうせなら浅草で旨い鰻でも食いたいな)
などと思う。
今は新政府の狗と成り下がった男を睨みつける。
俺は坊ちゃんの側にいると決めていた。だからこそ、商売人に成り下がることになっても、何ら卑屈な想いはない。だがな、一つ心に誓ったことだけはあった。
(ぜってえ、新政府の狗にはならねえ。あいつらの下で働くくれえなら、首を刎ねられた方がましだ!)
これが俺の武士としての矜持だ。
「なあ、藤田さんも亡霊の側の人間だったんじゃあねえんですかい」
藤田の左の眉がひくりと上がり、太い指がサーベルの柄をなぞる。
「何が言いたい」
「今だから言えますがね、坊ちゃんの家も直参でしてね。そりゃあ、御一新の折には苦汁を舐めさせられたもんでさ。だから『維新』なんてぇ言葉は死んでも使いたかねえが、だからと言って今更、恨みを晴らしたいとも思ってはいねえ。いねえが、恨む気持ちはわかるんだよ。……安易に分かるとか言うのもなんだがな」
江戸の名が東京府などという胡散臭い名前に変わり、文明開化とやらで西洋化が進み、暮らしがどれほど便利になろうとも、新政府軍のやったことを、俺は一生、許さねえだろう。
「ふん、どれだけ恨みが強かろうが、亡霊などおらぬ。いるのはただの人殺しだ」
つまらなさそうに、帳場机に肘をついて俺たちの会話を聞いていた坊ちゃんが、おもむろに口を開いた。
「ねえ、藤田さん、僕に仕事を頼む気になった? 亡霊探しなら、警視庁よりもうまくやれると思うよ。何しろ僕には、そういう失せ物を見つける神通力があるからね」
「坊ちゃん!」
「相手は生きた人間だ!」
俺と藤田が二人して大きな声を上げた。
だが坊ちゃんは何食わぬ顔でへらりと答える。
「神通力を貸すだけだよ。それに、この事件にうちの客が関わっている可能性も無きにしも非ず……だろ」
珠緒のことを言っているのか、それとも石川か、伊勢屋か菱屋か……。関わっているというのは、殺しに関与しているということなのか、ただ単に巻き込まれそうだということなのか。
いずれにせよ、坊ちゃんの物騒な思いつきに狼狽した。
「神通力だと、馬鹿々々しい……」と、まるで相手にしないと思われた藤田だったが、
「とりあえず俺は伊勢屋の珠緒が誰に本を又貸ししたのか、裏を取るところから始めよう」
立ち上がると、ズボンのポケットに手を突っ込んだ。そして紅葉の生け花の手前に畳んだ紙幣を置きやがった。
「おい、藤田さん!」
つまり、仕事を依頼するということじゃねえかよ!
「ああ、そういや、上野の事件に遭遇した巡査が気になることを言っていたな。『ムシ』がどうとか」
藤田が思い出したように振り返って言った。
言っている意味が分からない。「ムシ」だと?
「ムシ? どういう意味だ。ムシとは蝉とか蠅といった虫のことか」
「わからん。斬られた巡査が死ぬ間際に言い残した言葉が『ムシ』だったらしい。俺が直接聞いたわけじゃねえからわからんが、『ムシ、ムシ』と呻きながら死んだそうだ」
瞬間、俺の頭に、ある風景が蘇っていた……
――累々と散らばる死体から湧く様に現れた蟲……。
今思い返してみても、夢か現か、未だに分からぬ光景。
続々と死体の陰から現れたのは鱗をまとった節のある平たい蟲で、大きさはまちまちだが、どれも土蔵の隅を這っている太った油虫より一回り以上は大きい。その気味の悪い蟲の、長々とした触角と何本あるのか分からない足と大きな顎が、ざわざわとそれぞれ別々の意志でも持つかのように蠢いているのを見たことがある。
それらは現れてしばらくすると丸まってしまって、次々その背中が割れていった。
(なるほど、天へと昇るのか……)
漠然とそう感じた。あれは魂の化身だ――と。
一つの死体に一つの蟲が沸いている。
その蟲の背中から現れたのは無数の細かな羽虫で、まるで蜻蛉のように儚く、焼野に立ち昇る細い黒い煙に乗って、ふわりふわりと空へ舞い上がって行った。
幽玄であり、かつ不気味なその光景を、平和な生活の中でいつしか忘れていた。
「どうしたんだい。ぼんやりして」
坊ちゃんの声が聞こえた時、すでに藤田はいなかった。
「明日、行くよ」
さっそくか――げんなりとして尋ねる。
「菱屋さんですか、それとも辻斬りがあったという四谷ですかい」
いよいよ危険な『亡霊探し』の始まりだ――と覚悟を決めたのだが、意外な場所を指定してきた。
「その前に上野だ」
「へ?」
「ムシ……三四郎も気になるんだろ。新聞で詳しい場所を確認しろ」
『三四郎も』ということは、坊ちゃんもあの『ムシ』の話が気になったらしい。
言われたまま、上野の事件が載っていた新聞を取り出し、事件現場についてもう一度確認をする。
「新聞によると……上野は谷中となっていますね。『谷中ハ一乗寺ノ近ク辻ニテ見廻リノ巡査一名斬殺』……と。ここへ行って何をなさる気ですか。あまり危ういことには首を突っ込まない方が」
俺の苦言は、あっさり遮られた。
「心配は無用だ。件の辻斬りが同じ人物の仕業だとすると、既に奴は四谷あたりに潜んでいるということになる。今更上野には戻らないだろう」
「もし、それぞれの事件が同じ人間の仕業でなかったらどうするんですかい」
複数人の人殺しを相手取って探索するなんぞ、無謀としか思えない。
「いや、これは同じ人間の仕業だ。ただし、辻斬りだけだ。厠の殺しは殺し方が違いすぎる」
「……」
何かを確信しているような坊ちゃんの言い方に、再び顔を見返した。
冴えた黒い眼の奥で、既にこの事件に関する様々な……俺には見えることのない物を見ているのだと、改めて感心する。
それは目に見えないもの。『念の色』といった類の現象だけではなく、人間の行動の機微とでも言うか、誰しもが見逃すようなほんのわずかな矛盾や歪みを彼は見ているのだ。そしてそれらをばらして意味を考察したのち、正しく組み立てていく。
(そう、いつだって坊ちゃんは正しい)
酒井家の現当主とはいえ、一回り以上も若い坊ちゃんにおとなしく仕えている理由の一つである。
未だかつて、坊ちゃんの判断が誤っていたことは無かった。
◇◇
早朝……本来なら明け六つの鐘が鳴る時刻。
生活に馴染んでいた〈時の鐘〉は四年も前に廃止となった。それなのに未だ明け六つの鐘が鳴る時刻になると、洋時計を見るよりも先に耳を澄ましてしまう。
貸本屋の朝は早い。お絹さんが店へ出てくる前に、開店の準備に取り掛からなくてはならない。何しろ、俺は『丁稚』であり、『手代』であり、『行商人』だからな。
坊ちゃんの乳母だったお絹さんは、酒井家が没落してしまった後も坊ちゃんの元を離れず、今も通いで店の手伝いや家事や、身の回りのあれこれを請け負ってくれていた。
この時間、坊ちゃんはまだ寝ている。
通用口と庭、二か所の木戸の閂を開け、桶とたらいに水を汲んでおく。そのうちお絹さんがやって来て、店の奥に位置する台所で、簡単な朝食を作ってくれる。
おみおつけのふくよかな香りを感じながら、台所と隣り合った作業部屋にて背負子の準備をしていると、ガタガタと賑やかな木の音が近付いて来た。
坊ちゃんが起きたのだ。
坊ちゃんは通り土間の向こうにある離れで寝起きをしている。そのため裸足で行き来できるよう、土間の端には隙間なく、すのこを並べていた。
起きてから厠で用を足し、あらかじめ用意しておいた桶の水で顔を清め、髪を撫でつける。服だけはお絹さんが前の晩に明くる日に身に着ける下着から着流しから靴下まで準備しているが、全ての身支度は、誰の手も借りず全て自分で済ませるよう、幼いころから躾けられていた。
家の中でも使えるように先端を皮で覆った杖を突きながら、すのこの上を渡って台所まで来ると、半分寝ぼけまなこでお絹さんに朝の挨拶をした。
「おはよ」
「はい、おはようございます。朔様」
お絹さんは今でも朔太郎ではなく『朔様』という呼び方のままだ。
壁伝いに作業部屋まで来た坊ちゃんが、挨拶もせずいきなり念を押す。
「行くよね」
作業の手を止め、見上げる。
「新橋から京橋までの間を人力車が通っておりまする。あれに乗って良いのなら」
「別にいいよ。そのくらいの贅沢なら許す」
「有難き幸せ」
いやはや小柄だとはいえ、ほぼ成人に近い坊ちゃんを背負って歩くのだ。御城(今は皇居だが)を挟んで反対方角にある上野まで歩くとなると中々きついものがある。少しくらい楽をしても良いだろう。――と考えながら支度を進めた。
(どうせなら浅草で旨い鰻でも食いたいな)
などと思う。
3
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説
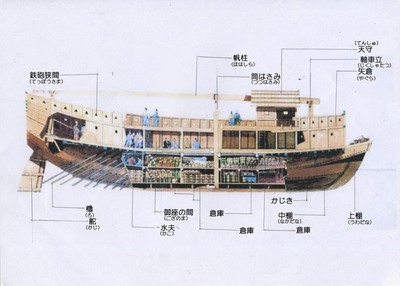

白雉の微睡
葛西秋
歴史・時代
中大兄皇子と中臣鎌足による古代律令制度への政治改革、大化の改新。乙巳の変前夜から近江大津宮遷都までを辿る古代飛鳥の物語。
――馬が足りない。兵が足りない。なにもかも、戦のためのものが全て足りない。
飛鳥の宮廷で中臣鎌子が受け取った葛城王の木簡にはただそれだけが書かれていた。唐と新羅の連合軍によって滅亡が目前に迫る百済。その百済からの援軍要請を満たすための数千騎が揃わない。百済が完全に滅亡すれば唐は一気に倭国に攻めてくるだろう。だがその唐の軍勢を迎え撃つだけの戦力を倭国は未だ備えていなかった。古代に起きた国家存亡の危機がどのように回避されたのか、中大兄皇子と中臣鎌足の視点から描く古代飛鳥の歴史物語。
主要な登場人物:
葛城王(かつらぎおう)……中大兄皇子。のちの天智天皇、中臣鎌子(なかとみ かまこ)……中臣鎌足。藤原氏の始祖。王族の祭祀を司る中臣連を出自とする

夜に咲く花
増黒 豊
歴史・時代
2017年に書いたものの改稿版を掲載します。
幕末を駆け抜けた新撰組。
その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。
よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

田楽屋のぶの店先日記〜殿ちびちゃん参るの巻〜
皐月なおみ
歴史・時代
わけあり夫婦のところに、わけあり子どもがやってきた!?
冨岡八幡宮の門前町で田楽屋を営む「のぶ」と亭主「安居晃之進」は、奇妙な駆け落ちをして一緒になったわけあり夫婦である。
あれから三年、子ができないこと以外は順調だ。
でもある日、晃之進が見知らぬ幼子「朔太郎」を、連れて帰ってきたからさあ、大変!
『これおかみ、わしに気安くさわるでない』
なんだか殿っぽい喋り方のこの子は何者?
もしかして、晃之進の…?
心穏やかではいられないながらも、一生懸命面倒をみるのぶに朔太郎も心を開くようになる。
『うふふ。わし、かかさまの抱っこだいすきじゃ』
そのうちにのぶは彼の尋常じゃない能力に気がついて…?
近所から『殿ちびちゃん』と呼ばれるようになった朔太郎とともに、田楽屋の店先で次々に起こる事件を解決する。
亭主との関係
子どもたちを振り回す理不尽な出来事に対する怒り
友人への複雑な思い
たくさんの出来事を乗り越えた先に、のぶが辿り着いた答えは…?
※田楽屋を営む主人公が、わけありで預かることになった朔太郎と、次々と起こる事件を解決する物語です!
※歴史・時代小説コンテストエントリー作品です。もしよろしければ応援よろしくお願いします。
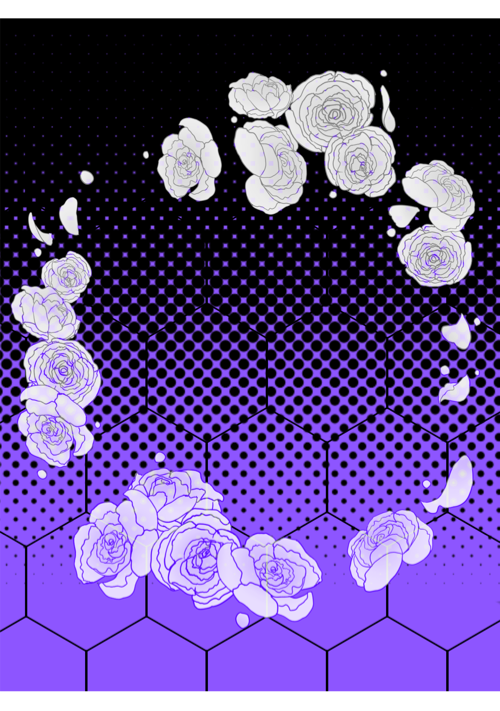
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?

新選組の漢達
宵月葵
歴史・時代
オトコマエな新選組の漢たちでお魅せしましょう。
新選組好きさんに贈る、一話完結の短篇集。
別途連載中のジャンル混合型長編小説『碧恋の詠―貴方さえ護れるのなら、許されなくても浅はかに。』から、
歴史小説の要素のみを幾つか抽出したスピンオフ的短篇小説です。もちろん、本編をお読みいただいている必要はありません。
恋愛等の他要素は無くていいから新選組の歴史小説が読みたい、そんな方向けに書き直した短篇集です。
(ちなみに、一話完結ですが流れは作ってあります)
楽しんでいただけますように。
★ 本小説では…のかわりに・を好んで使用しております ―もその場に応じ個数を変えて並べてます

壬生狼の戦姫
天羽ヒフミ
歴史・時代
──曰く、新撰組には「壬生狼の戦姫」と言われるほどの強い女性がいたと言う。
土方歳三には最期まで想いを告げられなかった許嫁がいた。名を君菊。幼馴染であり、歳三の良き理解者であった。だが彼女は喧嘩がとんでもなく強く美しい女性だった。そんな彼女にはある秘密があって──?
激動の時代、誠を貫いた新撰組の歴史と土方歳三の愛と人生、そして君菊の人生を描いたおはなし。
参考・引用文献
土方歳三 新撰組の組織者<増補新版>新撰組結成150年
図説 新撰組 横田淳
新撰組・池田屋事件顛末記 冨成博

湖水のかなた
優木悠
歴史・時代
6/7完結しました。
新選組を脱走した川井信十郎。傷ついた彼は、心を失った少女おゆいに助けられる。そして始まる彼と彼女の逃避行。
信十郎を追う藤堂平助。襲い来る刺客たち。
ふたりの道ゆきの果てに、安息は訪れるのか。
琵琶湖岸を舞台に繰り広げられる、男と幼女の逃亡劇。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















