お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

陸のくじら侍 -元禄の竜-
陸 理明
歴史・時代
元禄時代、江戸に「くじら侍」と呼ばれた男がいた。かつて武士であるにも関わらず鯨漁に没頭し、そして誰も知らない理由で江戸に流れてきた赤銅色の大男――権藤伊佐馬という。海の巨獣との命を削る凄絶な戦いの果てに会得した正確無比な投げ銛術と、苛烈なまでの剛剣の使い手でもある伊佐馬は、南町奉行所の戦闘狂の美貌の同心・青碕伯之進とともに江戸の悪を討ちつつ、日がな一日ずっと釣りをして生きていくだけの暮らしを続けていた……

教皇の獲物(ジビエ) 〜コンスタンティノポリスに角笛が響く時〜
H・カザーン
歴史・時代
西暦一四五一年。
ローマ教皇の甥レオナルド・ディ・サヴォイアは、十九歳の若さでヴァティカンの枢機卿に叙階(任命)された。
西ローマ帝国を始め広大な西欧の上に立つローマ教皇。一方、その当時の東ローマ帝国は、かつての栄華も去り首都コンスタンティノポリスのみを城壁で囲まれた地域に縮小され、若きオスマンの新皇帝メフメト二世から圧迫を受け続けている都市国家だった。
そんなある日、メフメトと同い年のレオナルドは、ヴァティカンから東ローマとオスマン両帝国の和平大使としての任務を受ける。行方不明だった王女クラウディアに幼い頃から心を寄せていたレオナルドだが、彼女が見つかったかもしれない可能性を西欧に残したまま、遥か東の都コンスタンティノポリスに旅立つ。
教皇はレオナルドを守るため、オスマンとの戦争勃発前には必ず帰還せよと固く申付ける。
交渉後に帰国しようと教皇勅使の船が出港した瞬間、オスマンの攻撃を受け逃れてきたヴェネツィア商船を救い、レオナルドらは東ローマ帝国に引き返すことになった。そのままコンスタンティノポリスにとどまった彼らは、四月、ついにメフメトに城壁の周囲を包囲され、籠城戦に巻き込まれてしまうのだった。
史実に基づいた創作ヨーロッパ史!
わりと大手による新人賞の三次通過作品を改稿したものです。四次の壁はテオドシウス城壁より高いので、なかなか……。
表紙のイラストは都合により主人公じゃなくてユージェニオになってしまいました(スマソ)レオナルドは、もう少し孤独でストイックなイメージのつもり……だったり(*´-`)

永遠より長く
横山美香
歴史・時代
戦国時代の安芸国、三入高松城主熊谷信直の娘・沙紀は「天下の醜女」と呼ばれていた。そんな彼女の前にある日、次郎と名乗る謎の若者が現れる。明るく快活で、しかし素性を明かさない次郎に対し沙紀は反発するが、それは彼女の運命を変える出会いだった。
全五話 完結済み。

隠密同心艶遊記
Peace
歴史・時代
花のお江戸で巻き起こる、美女を狙った怪事件。
隠密同心・和田総二郎が、女の敵を討ち果たす!
女岡っ引に男装の女剣士、甲賀くノ一を引き連れて、舞うは刀と恋模様!
往年の時代劇テイストたっぷりの、血湧き肉躍る痛快エンタメ時代小説を、ぜひお楽しみください!

あの日、自遊長屋にて
灰色テッポ
歴史・時代
幕末の江戸の片隅で、好まざる仕事をしながら暮らす相楽遼之進。彼は今日も酒臭いため息を吐いて、独り言の様に愚痴を云う。
かつては天才剣士として誇りある武士であったこの男が、生活に疲れたつまらない浪人者に成り果てたのは何時からだったか。
わたしが妻を死なせてしまった様なものだ────
貧しく苦労の絶えない浪人生活の中で、病弱だった妻を逝かせてしまった。その悔恨が相楽の胸を締め付ける。
だがせめて忘れ形見の幼い娘の前では笑顔でありたい……自遊長屋にて暮らす父と娘、二人は貧しい住人たちと共に今日も助け合いながら生きていた。
世話焼きな町娘のお花、一本気な錺り職人の夜吉、明けっ広げな棒手振の八助。他にも沢山の住人たち。
迷い苦しむときの方が多くとも、大切なものからは目を逸らしてはならないと──ただ愚直なまでの彼らに相楽は心を寄せ、彼らもまた相楽を思い遣る。
ある日、相楽の幸せを願った住人は相楽に寺子屋の師匠になってもらおうと計画するのだが……
そんな誰もが一生懸命に生きる日々のなか、相楽に思いもよらない凶事が降りかかるのであった────
◆全24話

クロワッサン物語
コダーマ
歴史・時代
1683年、城塞都市ウィーンはオスマン帝国の大軍に包囲されていた。
第二次ウィーン包囲である。
戦況厳しいウィーンからは皇帝も逃げ出し、市壁の中には守備隊の兵士と市民軍、避難できなかった市民ら一万人弱が立て籠もった。
彼らをまとめ、指揮するウィーン防衛司令官、その名をシュターレンベルクという。
敵の数は三十万。
戦況は絶望的に想えるものの、シュターレンベルクには策があった。
ドナウ河の水運に恵まれたウィーンは、ドナウ艦隊を蔵している。
内陸に位置するオーストリア唯一の海軍だ。
彼らをウィーンの切り札とするのだ。
戦闘には参加させず、外界との唯一の道として、連絡も補給も彼等に依る。
そのうち、ウィーンには厳しい冬が訪れる。
オスマン帝国軍は野営には耐えられまい。
そんなシュターレンベルクの元に届いた報は『ドナウ艦隊の全滅』であった。
もはや、市壁の中にこもって救援を待つしかないウィーンだが、敵軍のシャーヒー砲は、連日、市に降り注いだ。
戦闘、策略、裏切り、絶望──。
シュターレンベルクはウィーンを守り抜けるのか。
第二次ウィーン包囲の二か月間を描いた歴史小説です。
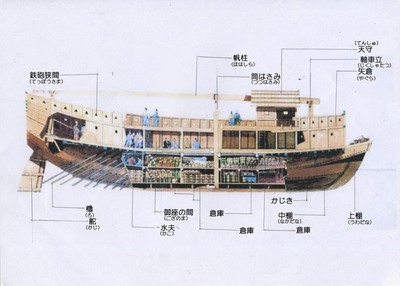

武田信玄救出作戦
みるく
歴史・時代
領土拡大を目指す武田信玄は三増峠での戦を終え、駿河侵攻を再開しようと準備をしていた。
しかしある日、謎の刺客によって信玄は連れ去られてしまう。
望月千代女からの報告により、武田家重臣たちは主人を助けに行こうと立ち上がる。
信玄を捕らえた目的は何なのか。そして彼らを待ち受ける困難を乗り越え、無事に助けることはできるのか!?
※極力史実に沿うように進めていますが、細々としたところは筆者の創作です。物語の内容は歴史改変ですのであしからず。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















