3 / 38
3
しおりを挟む
白で統一された部屋に漂うコーヒーの匂いは嫌いじゃない。
まだ授業中じゃないのか?と呆れた顔で聞かれたので、追い出されないための賄賂として、さっき買ったパンを差し出した。賄賂と解っていながら迷わずに受け取る姿は清々しい。
白衣を椅子の背凭れに掛け、無精髭を生やしたヤル気ゼロの三十八才の保健医は母さんの兄で僕の伯父にあたる。見た目は悪いが腕は良い。母さんには、僕は伯父さんに似ていると言われた事があるが、それはなんだか複雑だ。僕はここまでだらしない人間ではない。何が似ていると言うんだ。全然じゃないか。
「自習なので勉強をしに来ました。課題はちゃんと終わらせたし問題無いだろ」
伯父さんを座る椅子ごと机の前から動かし、その場所に丸椅子を置いて腰をおろす。
「ここは怪我人や病人が来る場所だ。何も無いなら教室に戻って勉強しろ」
「だから、こうしてわからないところを理解しようと多木崎先生に聞きに来てるんです」
そう言ってパソコンをずらし、古文の教科書を机に置いてノートを開く。
「そもそも保健医に古文教えろって言うことが間違ってると思うぞ」
もっともな事をいう伯父さんはコーヒーを飲みながらパソコンと向き合ってしまう。
「あんな噛み噛みの授業で理解しろなんて時間の無駄」
「噛み噛み?それは無いだろ。解りやすくて評判なのに」
「不良が二人居るだけでボロボロ。未来を証人にしても良い」
「不良……あの二人か。校内では大きな問題起こして無いだろ。何で怖がるんだ?」
校内では、と、言うことは、校外では何かしらをやらかしている、と、とらえて問題ないんだよな。未来は大丈夫だろうか。いや、僕と居るよりはマシになるか、同じくらいかの違いでしかないだろうから、心配するのは止めよう。
「知らないよ。居ることすら知らなかった僕に聞くな」
大きな問題を起こしたことが無いなら、これから起こされる可能性を危惧して、何もない様にと身構えた結果があの授業だろうな。本当に下らない。こっちはお金を払って授業を受けているんだ。中途半端にやられるのは迷惑でしかない。
「我が甥っ子ながらどうやってこの数ヵ月を過ごしてきたんだか」
「その可愛い甥っ子が必死に頼んでいるのに駄目だなんて、伯父さんがそんなに冷たい人だとは知らなかった」
「そんな心にもない台詞を真顔でペラペラと言う奴には絶対に教えん。今すぐ教室帰れ」
「これの動詞なんだけど」
「あー、これは……」
なんだかんだ教えてくれる伯父さんの優しさと博識に頼ってしまうのは今日が初めてではない。未来もそれを知っているからこそ、俺を咎めることはしないし、咎めるとしたら伯父さんも一緒になる。優しい未来にはそれが出来ない。少し卑怯だが、これも大事な策の一つ。伯父さんが教えてくれた部分を書き留め終わるのと同時に保健室のドアがバンッと勢いよく開いた。何事かと身構えた僕と伯父さんはドアへ体を向ける。視線の先には、教室に居るはずの金髪の不良が肩で息をしながら立っていて眉をしかめた。なんで、ここに不良が来んの?
「はー、はー、ど、どっか怪我した?」
「は?」
不良は何を言っているんだ。
「それとも病気?」
状況が飲み込めない僕と伯父さんは顔を見合わせた後でもう一度不良に視線を戻す。どこで何を勘違いする事になったのかは興味ないが、伯父さんに余計な迷惑がかかるのは避けたい。
「まぁ、落ち着きなさい。この子は怪我一つ無く健康だ」
伯父さんはコーヒーの入ったコップを机に置いて、僕が健康だという事を勘違い男に伝える。
「まぁ、普通は怪我とかで来る場所だから、檜山くんが心配するのも当然だな」
その言葉にトゲを感じるのは気のせいだろうか。伯父さんの言葉に不良はキョトンとした顔で俺と先生を見比べる。
「あれ?じゃー、なんで保健室?」
首を傾げながら聞いてくる不良の質問に答えるのが面倒でノートに視線を戻す。
「幸慈、友達が心配してきてくれたのにその態度はないだろ。悪いな、こんなんだからよく誤解されやすいんだけど、本当は繊細で優しい子なんだ」
「……はぁ(何で多木崎くんの事を名前で呼んでんの?教師のくせに)」
曖昧な返事をする奴と親しくさせようとする伯父さんを睨みつけ、間違いを訂正する為に口を開く。
「違う」
「照れるなって」
頭をガシガシと撫でてくる伯父さんの手を退けながら僕はノートを閉じた。
「どっちも違う」
「?」
どういう意味だという顔をしている伯父さんを軽く睨んで机の上の物を片す。
「僕の性格は見たまんまで、不良は友達じゃない」
そう言いながら、僕はノートで不良を指す。不良が少し寂しそうに笑ったような気がしたけど、それは絶対に気のせいだ。
「こらっ」
「デッ!」
久しぶりに伯父さんのチョップをくらった。加減無しの本気のチョップが残した痛みの余韻が辛い。
「全く、口の悪さは誰に似たんだか」
誰にも似てないなら、一人しかいないだろ。
「はっ、アイツに似たんじゃねぇの?」
吐き捨てるように言って、立ち上がる。
「幸慈っ!」
「説教する暇があるなら女心でも勉強しなよ」
伯父さんの説教を聞かされる前に勉強道具と飲み物を持って、チョップの仕返しに奥さんを怒らせた事を突っつくと、伯父さんは青冷めた顔をして固まった。その隙に保健室から撤退する。ドアのところで不良に止められるかと思ったけど、そんなことは無かった。まぁ、その本人は僕の後ろにいるんだけど。
「謝んないでいいのぉ?ケンカみたいな感じだったけどー」
うるさい。てか、喧嘩じゃない。そう言い返すのが面倒で口を閉ざす。
「多木崎くーん」
うるさい。
「無視しないでー」
「うるさいな。アンタには関係ないだろ」
俺が伯父さん夫婦に首を突っ込むのも無責任だろうな。まぁ、今回は八つ当たりだけど。ごめん、伯父さん。心の中だけで謝っとく。
「やっと返事してくれたー」
その嬉しそうな声に余計イライラが増す。何か別の事を考えよう。そうだ、さっき教わった動詞の復習をすれば気が紛れるかも。頭を冷やそうと別の事に思考を巡らせていたせいで、後ろとの距離が狭まっていることに気がつかなかった。
「っ!」
突然腕を引っ張られた事に対応出来ず、足を止めるしかなかった僕は、何のつもりだ、と、後ろの人物を睨む。だが、睨んだ先には怖いくらい真っ直ぐな目が僕を待ち受けていた。この目、嫌いだ。
「アンタじゃない」
意味の解らない言葉に眉をしかめる。
「俺の名前は檜山茜」
それがどうした。僕と何の関係があるって言うんだ。掴まれた左腕に視線を向けて不良を睨む。
「離せ」
「これから俺のこと名前で呼んでくれるなら離してあげる(こんな風に睨まれるのも初めてだな)」
「断る」
そう言うと、俺の腕を掴む力が少し強くなった。
「なんで?俺だってあの保健医みたいに下の名前で呼びたいの我慢してるんだからそれくらい良いでしょ?(何で名前で呼びたいんだろう)」
意味が解らない。なんでそこで伯父さんが出てくるんだ。親戚なんだから当たり前の事じゃないか。
「クラスの奴の言葉には返事したくせに何で俺の言葉は無視なの?(何でこんなにイライラしないといけないのさ)」
今度はクラスの奴かよ。とことん意味が和からない。何、コイツ。今日会ったばかりのくせに馴れ馴れしい。所詮は未来の恋人の友人でしかないくせに。
「はっ、未来達が羨ましくなったからって僕を使って恋人ごっこ?それでヤキモチ焼いた振りでもしてるわけ?」
嫌味を込めて言った言葉に、男は眉間に皺を作った。
「俺だって好きで食べれないモチ焼いてるんじゃない!」
コイツ、今なんて言った?本人も自分で言ったことが信じられないといったような顔をしている。緑の瞳が揺れて、左手で口元を覆い難しい顔をして、数秒後に息を吐く。吐き終わった息の変わりに、迷いが消え何かが吹っ切れたような顔をした後、さっきよりも強く僕の嫌いな目をぶつけてきた。危機感を感じた僕は、手に持っていた教科書や飲み物を投げつけて、腕の拘束が緩くなったのを見計らって不良から離れる。
「冗談じゃない!僕が感情の中で一番嫌いなのは、オマエが僕に向けてる気持ちそのものなんだよ!二度と僕を好きだと思うな!」
そう言い捨てて、僕はその場から逃げ出した。頼むから追ってくるな。僕を呼ぶな。誤解だと、勘違いだと騒ぎ立てろ。その願って、無我夢中で走って、走り続けて、授業の終わりを告げるチャイムを聞いた。いつもは通らない場所で足を止め、後ろから追いかけてこない事を確認して壁に寄り掛かる。
「はっ、はっ、くそ、なんだよあの不良」
いつもとは違う走り方をしたせいで息がうるさく耳に届く。未来も面倒なのを連れてきたものだ。巻き込むなと言ったのに、結局は巻き込まれている自分に嫌気が差す。教室に戻るのは嫌だが授業の事を考えると、逃げ続けたところで未来のところへ戻れば不良が待っているのは目に見えている。
「好き?ははっ、冗談じゃない」
同じになってたまるか。僕はアイツにはならない。絶対に。あんなのは、二度とごめんだ。
息が整って、改めて周りを見回す。見覚えのない光景にストレスが溜まる。逃げることだけを考えていたせいか、気がつけば迷子になっていたらしい。早速ろくなことがない。たかが男子校の癖になんでこうも無駄に広いんだよ。全力疾走したせいで必要以上に疲れたし、熱いし、喉乾いたし、少しだけ腹が減った錯覚すらする始末。はっ、としてズボンのポケットに手を入れると、五百円玉まみれの財布が出てきて息を吐く。助かった。幸い、近くに自販機があったので、そこで水のペットボトルを買って半分ほど飲んで喉を潤す。二度目のチャイムを聞いて、初めて授業をサボったのだと認識する。こうなったらかなり早いが一人でプール掃除始めるとするか。僕は意地でもそこへ辿り着くと心に決めペットボトルを手に歩き始めた。
……
…………
………………
奇跡だ。目の前にあるプールの存在に何度も瞬きをする。掃除を始める前からやりきった感が半端ない。とは言え、やらないと帰れないもんな。未来のためにも自分のためにも頑張ってみるか。水泳部の部室から掃除道具を一通り取り出してプールサイドに置いて、ブレザーを脱いだ後ワイシャツの袖を捲くり、靴と靴下を脱いでズボンの裾が濡れないよう膝まで折ってからホースとデッキブラシ片手にしたくもない掃除を始めた。足元は結構泥が溜まってて予想以上に歩き難い。未来だったら絶対転ぶな。しかもプールが無駄に広い。これ何メートルあるんだろう。
ホースを固定してから両手でデッキブラシをしっかり持ち掃除を始める。泥がある程度なくなったのは六時間目の授業終了を告げるチャイムが鳴ってからだった。これ、放課後から始めてたら大変だったな。額から流れる汗を乾かす風が気持ち良くて目を閉じる。鞄、どうしよう。まぁ、自分の状況を考えると持ってきてもらうしかないんだが、面倒事の臭いしかしない。背に腹は代えられないか。一応連絡しておくことにした僕は、プールサイドに上がってブレザーから携帯を取り出す。
「……こわ」
携帯には未来からの着信とメールがたくさん来ていた。僕はそれを見なかったことにして携帯をブレザーのポケットに戻す。さて、あともう一頑張りするか。
そうだ、確か無くなったネクタイの変わりに封筒が入れられてたっけ。内ポケットから封筒を取り出して中身を見た。あぁ、やっぱり。封筒の中に書かれた予想通りの内容に軽く笑ってポケットに突っ込んだ。ぬるくなったペットボトルの水を飲み干して息を吐く。
「くだらない」
デッキブラシを水切りに持ち換えて掃除を再開した。ここのプールは大きいほうだが掃除が早く終わったように感じる。僕の手際が良すぎるからなのか、未来の心配をしながら作業していないからなのか考えて、後者の可能性が高いのかもしれないと思い頷く。ま、何はともあれ、早く帰れるに越したことはない。水切りといってもどうせ水を溜めるし、水泳部がまた掃除するだろうから適当に終わらせて平気だと判断してプールサイドに上がる。
「後は水溜めて終わりだな」
一仕事終えて固まった筋肉を解すのに伸びをした僕の背中に、よく知った声が届く。
「幸慈ーーーーー!」
来た。近くなる声と足音に肩をすくめて振り返ると、未来が走ってくる姿が見えてゆっくりと息を吐き出す。僕の鞄は持ってきてくれなかったらしい。プールサイドに来た未来は、荒れた息を整えてから自分の携帯画面を僕に見せてきて眉間に皺を作る。
「何度も携帯に連絡入れたのに何で返事くれないの!?」
携帯画面を僕に近付けながら怒ってきたが、こちらには正当な理由がある。僕は携帯を押し返してプールを顎で差す。
「そんなの掃除してたんだから気付くわけないだろ」
「そ、掃除?」
プールを見るなり驚いた表情を隠せない未来は信じられないといった顔をして僕を見る。
「まさか一人でやったの!?」
他に誰がいるんだよ。誰かとやるような人間じゃないのは解ってるだろ。
「わかったら掃除道具片してこい。僕はプールに水入れる方やるから」
「……はい」
掃除を僕が全部やってしまったせいか、未来は少し落ち込みながら荷物をプールサイドの隅に置いて掃除用具を片しに行く。僕は水道管をひねり、水を流し込む。片し終わった未来が戻ってきた時、鞄を取りに行きたいから暫く留守番を頼みたい事を伝えると全力で止められた。何か、すごく嫌な予感がする。
「何を企んでるか是非聞かせて頂きたい」
「俺は何も企んでないから!」
ほう。
「俺は?」
てことは、他のやつが企んでるって事か。
「や、やだなー。誰も企んでないってばー」
「何故目を逸らす」
顔ごと視線を逸らす未来の顔を覗き込もうとした時、ガシャンとフェンスが音をたてた。
「たーきーざーきーくーん」
何故不良がここにいる。しかも不良が持ってるのって、もしかしなくても僕の鞄じゃないか。未来に視線を向けると誤魔化すように笑いかけられた。眼は口ほどに物を言うとは本当らしい。頭痛に頭を抱えた僕は盛大に息を吐いて捲っていた袖を元に戻しながら靴下を取りに向かう。
「だ、だって、ヒーくんが、幸慈の事が好きだから協力してって」
「迷惑だ」
「ご、ごめん」
背中に未来の声を受け止めながら、靴下を履いたりと服装を整えた。その間にも不良はフェンスを登ってこっち側に来ようとしている。
「ミーちゃんは悪くないよ。ごめんね。嫌な思いさせちゃったね」
そう言いながらガシャンと音を立ててプールサイドに来た不良の顔を見る限りでは一応反省しているみたいだった。
「そ、そんなことないよ」
あるだろうが。仲良くなるのは未来の自由だが、俺の気持ちを無視しないでほしい。だが、今までだったら未来は俺の嫌な事はしなかった。この行動にも何か意味があるのか?
「なんだ、綺麗じゃねぇか」
「秋谷おっそーい」
「フェンスのところまでは一緒だっただろうが。つーか、これオマエ一人でやったわけ?」
「そうだけど。いっ!」
右腕に痛みを感じて振り向くと不機嫌な顔をした不良が居た。
「秋谷とは普通に話すんだね」
言葉の意味が解らなくて無視しようとしたら、腕の痛みが強くなった。この馬鹿力!
「秋谷とは普通に話すんだね、の返事は?」
笑顔と腕の痛みが比例しないのは何故だろうな。
「僕に害がないからな」
「へぇ」
納得がいかない顔をして、不良は俺を見下ろす。
「その辺にしとけ、腕折れるぞ」
鹿沼の言葉で力が弱まり痛みは無くなったが、腕は今もつかまれたまま。コイツ、本気で嫌いだ。
「ミーちゃん、後どれくらいで掃除終わる?」
「え、えっと、水溜めて終わり?」
未来は困惑しながら鹿沼に聞くと、頷き返され安心していた。その後、何故か未来は僕に向かって頷いてきたので、なんとなく頷き返す。
「じゃあ、後お願いね。きちんと家まで送らないとダメだよー、秋谷」
「わかってる」
何言ってんだコイツ。僕の知らない所で僕に関係する話が纏まってるのが気に入らない。
「幸慈」
「!?」
いきなり呼び捨てにされて肩が跳ねた。
「デートするよ」
は?
「もう、答えは聞かないことにしたから」
「ぉわっ!ちょっ!」
言うよりも早く僕を肩に担いだ不良は走り出した。冗談じゃないっ。未来は兎も角、僕は一般高校生位には身長があるんだ。こんな俵みたいに担がれるのは屈辱以外の何物でもない!
「レッツゴー!」
「待て!降ろせ馬鹿!!」
「あははは、聞こえませーん」
聞こえてるじゃないか!結局校門まで担がれた僕は、渋々不良の事を苗字で呼ぶのを条件に自分で歩く権利を手に入れたが、それでも鞄は返してもらえず、逃げることが出来ない環境に舌打ちをする。笑顔で下駄箱にあるはずの僕の外靴を出された時には目眩すらした。あの時、体育教師を蹴るんじゃなかった、と、先にたたない後悔をして深く息を吐く。鼻歌混じりに僕の右手を掴んで歩く人間を追い払う術があるなら教えてほしい。
和風ハンバーグ・海鮮丼・きのこパスタ・シーフードドリア・日替わりランチ。メニューには美味そうな写真が大量で、昼飯を食い損ねた僕としては食欲を微かにそそられるが、どれも食べきれないと解っているせいか、まともに見るのを止めて窓の外へ目を向ける。これ食べたら帰れるのかな。宿題は出たんだろうか。帰ったら未来に確認しないと。
「幸慈は何食べるか決めた?」
目の前に檜山さえいなかったらとっくに軽食を頼んでいただろう。
「要らん」
「んー、よしっ」
頼む気のない僕は、呼び出しボタンを押す檜山の指先を他人事のように見ていた。店が空いていたからか店員はすぐにやって来て、注文を聞いてくる。
「お待たせ致しました。ご注文をお伺い致します」
「オムライスとドリンクバーを二つずつとー、イチゴパフェとチョコレートパフェを一つずつ。デザートは後から持ってきてね」
オムライスとデザートを二人分頼む檜山に呆れる。オムライス二人分なんて僕だったら絶対に無理だ。パフェだって一つ食べれるかどうか。考えただけで吐き気がする。
「ご注文繰り返させていただきます。オムライスを……」
この店員は随分と丁寧な対応をするんだな。僕も高校生になったわけだし、そろそろバイトしようか悩んではいる。母さんは必要ないって言うけど、一人息子としてはやっぱり力になりたいわけで……まぁ、医者の月給に比べれば可愛い金額しか稼げないだろうけどな。
「幸慈」
「イッ!」
檜山の事忘れてた。でも、無理やりファミレスに連れてきておきながら、僕がチョット考え事してただけで足を踏んでくるのはどうなんだ。保護者の教育方針を盛大に疑う。
「隙だらけだよ。本当に廊下で俺を殺そうとした人と同一人物?つか、俺と一緒にいるのに考え事とかどうなの?サイテー」
なら今すぐ帰らせろ。
「で、何飲む?」
「要らん」
「オレンジジュースねー、りょーかーい」
人の話を聞け!席を立ってドリンクバーへ向かう男に頭痛がした。未来の彼氏とは正反対だな。まぁ、まともに話していないから今評価するのはどうかと思うが、身勝手な事をしまくる檜山と比べると一般常識は備わっていると解る。プール掃除はどうなっただろうか。あの彼氏はちゃんと家まで送ってくれるだろうけど。そう考えていると携帯が震えだした。何かと思って僕はポケットから携帯を取り出し待ち受けを見る。未来からの電話に少し安心した後、通話ボタンを押す。
「はい」
『あ、幸慈?』
僕かどうかを確認する未来の言葉に眉をしかめる。
「僕以外の誰がこの携帯を使うんだ?」
『ヒーくんが出るかもしれないじゃん』
どうしたらその考えにたどり着くんだ。
「勘弁してくれ」
未来の言葉にどっと疲れた僕は机に突っ伏した。
「で、掃除は終わったのか?」
『うん。それを伝えたかったのと……明日の弁当』
自習でのやり取りが脳を過り未来の言葉を遮る。
「却下」
『まだ言い終わってない』
「ピクニックなんてアホなもの誰がするか」
「えーしようよー」
「……」
顔を上げ前を見ると、思っていたよりも近くに檜山の顔があった。
「チョット貸して」
「ちょ、おいっ」
「もしもし、ミーちゃん?」
僕の許可を得ないまま携帯を奪い未来と話始めた。通話代は誰が払うと思ってるんだ。こういうところが非常識だというのが何故解らない。
「ねー、俺もしたいなー。ピクニック」
勝手にしてろ。ピクニックは無しにしても買出しはしないとだな。明日の未来と母さんの弁当が作れない。今冷蔵庫にあるのは……。
「だいじょーぶ!俺に任せなさい!」
檜山のヤル気に溢れた声に思考を呼び戻され、僕の知らないところで話がまとまりつつあるらしい事が解った。高校生にもなってピクニックって、どんだけ子供なんだよ。
「弁当箱?チョット待ってねー。幸慈、ミーちゃんが弁当箱返し忘れたから明日返すって」
忘れてた。
「僕に返すくらいならその弁当箱を彼氏のためのおかずで埋め尽くしてみろ」
「ミーちゃんってそんなに料理ダメなの?」
「卵の殻を割るところから始めないとダメだな」
「ぶっ、あっはははははは……ひー、く、くるしぃー。マ、マジみーちゃん最高!あー、ミーちゃんごめんね。拗ねないでよー」
なにを暢気に話してるんだ僕は。檜山は僕に対して最悪な感情を抱いてるってのに。早く別のことを考えよう。えーっと……。
「お待たせしました。オムライスになります」
「あぁ、どーも」
自然と僕の前にも置かれたオムライスを見て、最近作ってないな、と懐かしくなった。
「はい」
やっと電話が終わったらしく、檜山は携帯を僕に返した。それを受け取った僕に、今度はスプーンを差し出してくる。何で僕に渡してくるんだ。
「あ、フォークの方が良かった?」
まさか、檜山、僕の分も頼んでたのか。スプーンを受け取ると、自分もスプーンを持ってオムライスに指した。
「いっただきまーす」
檜山どんだけ自由なんだ。それに、なに勝手に僕の分も頼んでんだよ。
「食べないの?もしかしてアレルギーとか?」
「……なにが楽しいんだ」
「幸慈とご飯食べれること」
馬鹿馬鹿しい。
僕は出来るだけ男を視界に入れないようにオムライスを食べ始めた。あ、美味い。
「ここのオムライス美味しいでしょ?」
檜山に言われるとムカつく。
「むー、ふりだしに戻っちゃった感じかなー」
最初から一歩も進んてない。
「明日ってさー、四時間目の家庭科って自習になったでしょ」
何それ。僕は購買が休みになることしか知らないぞ。
「あー、そっか、幸慈は午後サボったから知らないんだっけ」
誰かさんのお陰でな。個人的意見を言えば、プール掃除やってたんだからプラスマイナス0だ。
「ねぇねぇ、自習でピクニック用の弁当作ってよー。家庭科室は使えるようにしておくからさ」
簡単に許可が出るわけない。脅しでもするつもりか?それで使えるって、学校が生徒に負けてどうする。
「ここの金も俺が払うしー、材料費も出すからさー。ミーちゃんの料理教室ってことで、どう?」
僕が首を縦に振るまで家に帰す気ないな。料理教室ってのは意外と良い案だが、発案者が檜山じゃな。どうしたもんか。
「檜山くん?」
「「?」」
突然の声に僕と檜山は同時にその方へ顔を向ける。僕達の座るテーブルの近くの通路に若さと化粧の力を借りて可愛らしく化けているであろう女が立っていて、笑顔で近付いて来た。距離がなくなるにつれて届く匂いに眉をしかめて息を止める。かなり香水臭い。それにこの女、スッピンはブスっぽいな。
「久しぶりー!半月前のホテル以来だねー!」
年頃の女が恥じらいも無く大きな声でホテルと口に出来るほどこの世の教育は腐ってきているのか。この女と知り合いという事は目の前の男もまともではないってことだな。解ってはいたが、目の当たりにすると嫌悪感が増すというものだ。まとも、か。僕にそんなこと言う権利は無いな。自己否定する考えに反吐が出るが、当然なのだから仕方がない。味のしなくなったオムライスは一口食べたきり、スプーンが進まずほとんど残っていた。
「ねぇ、これから遊びに行かない?二人で」
おぉ、僕は邪魔者か。このまま二人で何処かに行ってくれればすごく助かる。今すぐそうしろ。なんならここの金は僕が払う。だから早くどこかに行け。
「んー、ごめんねー。今はこの子といる方が大事なんだ」
期待とは正反対の言葉に眉間に皺を作ってしまった。
「なにそれー。ねぇ、檜山くんの優しさに漬け込むとか最悪なんだけど」
今やオマエの脳みそが最悪だ。
「そんなふうに言わないでよ。俺が無理言って付き合ってもらってるんだよ」
自分が無理矢理連れ回してる自覚はあるのか。
「檜山くん優し過ぎだよ!嫌なら嫌って言わなくちゃ!」
キャンキャンとうるさいなー。最悪だがこの男は未だに僕に惚れてるらしく、飽きるまでは他からの誘惑には絶対頷く事は無いと認識させられる位の会話に頭を抱える。本当、最悪。そんな事を考えていると、男と目が合った。申し訳なさそうな顔をしてる暇があるなら馬鹿女を何とかしろよ。
「アンタも少しは気を利かして帰るなりしなさいよ!」
そう言って、女はコップに入った水を僕にぶっかけた。
「ちょっと!何してんのさ!」
焦る檜山の声と女を非難する他の客の声が聞こえたが、当の本人には届いていない。なんで僕ばっかり!僕はコップを掴んで立ち上がり中身のオレンジジュースをぶっかけた。その瞬間耳にチラホラと拍手の音が聞こえ、檜山は驚いた顔をして僕を見てくる。
「ちょっと!なにすんのよ!」
女の声に店員と客の視線がさらにこっちのテーブルに集まる。
「それはこっちの台詞だ。自分の気持ち押し付けてキャンキャンと犬みたいに吠えて五月蝿いんだよ。僕は静かに飯食ってただけだろ。なのに水かけてくるとか最低」
「だからってジュースは無いじゃん!ベタベタして気持ち悪いー!クリーニング代出してよ!」
「だったら僕の分アンタが払ってくれんの?当然ここの飯代も払ってくれるんだよな?」
そう言って僕は水まみれになったオムライスを指差した。
「冗談じゃないわよ!」
「なら早くどっかに行ってくれないかな?まぁ、ジュースまみれでメイクの剥がれた汚い顔を好きな人に見られても平気だって言うなら、話は別だけど」
見下すように笑う僕の言葉にハッとした顔で檜山に視線を向けた女は、すぐに顔を真っ赤にして店を出て行った。また敵を作ってしまった事に頭を抱えて盛大に溜め息を吐く。絶対どこかで闇討ちに合うの確定だな。
「幸慈、カッコイイ」
真顔で男が男に言う事じゃないだろ。
「人見る目なさすぎ」
「ごめん」
僕は座っていた場所に腰を下ろし、濡れたブレザーを脱いで全部止めていたシャツのボタンを二つ目まで外す。濡れた眼鏡をワイシャツのポケットに入れた後、髪から滴り落ちる水滴が邪魔で軽く後ろに流した。
「……エロ」
はぁ?
「でも、このままじゃ風邪ひかしちゃうね」
そう言って男は立ち上がって僕の手を引いて歩き出した。僕は慌てて鞄を持って立ち上がり、バランスを崩しながら歩き始める。僕のは食べれないが、オマエのオムライスはまだ残ってんだろ。店で騒いだ罪悪感からオムライスの金を払うために財布を取り出そうとしたら、驚いたことに男はレジに行くことなく食い逃げ状態で店を出た。
「お、おいっ、金!」
「この店、オジイが経営してっから平気」
オマエは何者だ。まさか金持ちの坊ちゃんか?ま、金持ちと解っても態度を変えるつもりは無いけど。てか、どこまで行くんだ?僕は食料を買って今すぐにでも帰りたいんだが、それが叶う雰囲気にも思えない。檜山は店を出て、すぐに足を止めて僕を見てきた、と思う。眼鏡が無いから全てがボヤけて見えて判断がしにくい。
「嫌いになった?」
最初から嫌いだ。いや、違うな。
「嫌いなのは恋愛感情」
「それ、遠回しに嫌いって言ってるようなもんだよ」
ふーん。檜山が僕にとって不必要なことに変わりないけどな。それからはお互いに無言で歩く。せめて眼鏡を掛けたいと思って足を止めたら最初より強く手を引っ張られて腕を引かれた。むかつくのは身長が俺の方が低く相手の歩くペースに合わせると少し小走りになることだ。お陰で鞄と上着を持ちながら歩く僕は今にも転びそうな状況だが、全く気付いてもらえない。すれ違う人間の視線が雰囲気で伝わってきて僕の神経を逆撫でする。
「着いたよ」
ようやく足を止めることが出来た僕は、すこし前屈みになって息を整えた。
「幸慈?」
暢気に首を傾げてそうなところが更にムカつく。
「もう少しゆっくり歩け!僕の歩幅はオマエ……じゃなくて、檜山みたいにでかくないんだよ!それに、眼鏡が無いとほとんど見えないから危ないんだ」
言って満足した僕は、ポケットから眼鏡を取り出す。眼鏡を掛けて視界がはっきりと見えて安堵した僕の体は、五月の冷たい風に軽く身震いした。
「ごめん、寒かったよね」
水ぶっかけられたから余計に寒いんだよ!
「行こ、本当に風邪ひくよ」
誰のせいだ!
檜山に連れられて入ったのは、僕の知っているスーパーと縁の無さそうなファッションセンターだった。建物の中にはファッションブランドと呼ばれる店ばかりがずらりと並んでいて気が重くなる。なんだここ。メチャクチャ居づらい。
「か、帰りたい」
僕は鞄を抱き締めて項垂れた。
「買い物したらね」
僕の気持ちなんて知らない檜山は一つのブランド店へ迷うことなく入っていく。まさかこの店も檜山の爺さんが経営してるなんて言わないよな!?
「いらっしゃいませ、檜山様。本日はどのようなものをお探しですか?」
檜山様!?やっぱしここも爺さんが絡んでるに違いない。
「今日は俺じゃなくて、この子の服が欲しいんだ」
は?何で僕?
「どのような服がお好みでしょうか?」
「幸慈、服にこだわりある?」
店員と檜山の質問が理解できなくて少し首を傾げた。どのようなって、服は服だろ。着れれば何でも良いし。
「めちゃくちゃ安いやつ」
気にするといったら値段くらい。
「却下。俺好みでよろしく」
何の為に聞いてきたんだよ。
「ちょっ、おい!」
店員は礼儀正しく一礼してから背中を向けてどこかに行ってしまうし、僕はまた腕を引っ張られて歩かないといけないわけで。なんかもう、今日一日で色々ありすぎて疲れた。
「着いたよ」
その言葉に足元を見ていた顔をあげると、いつの間にか個室っぽい場所の入口に連れて来られていた事に気付く。
「何、ここ」
「んー、VIPルーム?」
僕の呟きに返ってきた言葉に改めてドアの向こうの部屋を見回す。部屋は白・ベージュ・茶でバランスよく統一されてて、入り口のすぐ横には大きめの試着室、前の中央スペースにはソファーとテーブル、それを覗いても無駄に広いスペースがあったりで、もう、訳がわからない。全身の血の気が引くという感覚を味わった僕は、ゆっくり後退した。
「はい、逃げない(こんな反応されたの初めてだな)」
僕の手を引いて中に入る背中に言葉が出ない。
「何か飲む?」
「帰りたい」
肉食動物に囲まれた草食動物の気持ちを、今なら少しだけ理解できる気がした。人生でこんなにも家が恋しく感じるのは初めてだ。
「ホットココアにしようかー、身体だいぶ冷えちゃったもんね」
誰のせいだ。声には出さなくても、僕は檜山に対してかなり怒ってるんだからな。
「ひっくしょん!」
やばい、このままじゃマジで風邪ひく。
「暖房入れようか?」
「要らん」
冷暖房まで完備してんのか、この部屋。
「ごめんね。あの場で俺がはっきり断ってれば……」
「アンタ……檜山がどんだけ断ってもあのての女は簡単には引きさがらねぇだろうが」
「まぁ、そうなんだけどさ」
「日頃の行いが……ひっくしゅっ!悪いんだよ」
「看病は任せてね」
「アンタが……檜山が僕の周りをウロチョロしてる間はぶっ倒れねぇよ」
「そっか、よかった」
そう言って檜山は僕の頭をポンポンっと撫でてきた。僕はその手を払ってソファーの真ん中に座る。鞄をテーブルに置いた後、濡れたブレザーをその上に乗せた。それと同時にノックの音が聞こえて、店員が何着か服の掛かったハンガーラックを押して入ってきた。あれ全部買うとか言いださないよな。僕の気持ちとは裏腹に、檜山は店員の持ってきた服を吟味している。
「あ、これ俺も欲しいかも。色はここにあるだけ?」
俺も、の意味が解らない。
「此方にある色以外には、グレー・紺・ホワイトがございます。後は似たデザインの物で裾のほうに……」
目の前で繰り広げられる会話についていけず、僕は考える事を放棄して膝を抱えた。
「(膝抱えてる。可愛いなぁ)」
寒くて腕を擦ると、会話が途切れているのに気が付いて顔を上げる。
「良かった。起きてた」
僕の前髪を横に流して笑顔を向けてくる姿を迷わず睨み付けた。檜山の前で寝るわけないだろ。
「幸慈、立って。試着するよ」
手を引かれて渋々立ち上がると、ハンガーラックの服を整える店員と目が合う。
「試着って……全部?」
僕の言葉に檜山はハンガーを揺らしながら服に触れる。
「全部じゃないけど、デザインによってサイズが違ったりするから、その確認くらいかな」
それって、結局全部じゃないか。
「僕としては、古着屋ので良いんだけど」
「古着?」
ポロっと出た本音に、しまった、と唇を引き締める。
「幸慈、古着って何?兄弟のお下がり?(その顔は可愛いけど、ちょっと無視出来ないかなぁ)」
言わないと帰れない雰囲気だと察した僕は盛大に溜め息を吐いた。
「自慢じゃないけど、僕の持ってる服は未来と母さんがくれたやつ以外は全部古着屋で買ったやつだから、こういう所のはちょっと……」
馴染みがないどころか関わりたくない。
「へぇ……予定変更」
なんかボソッと聞こえたと思ったら力尽くで試着室に押し込められた。
「ちょっ」
「とりあえずコレ着て」
そう言って僕に服を押し付けカーテンを閉めた男は店員に何かを言っているようだったが、なんか嫌な予感がして盗み聞きする気になれなかった。手元の服を見て溜め息を吐き、無駄にでかい鏡を見て、自分の髪が濡れている事を思い出す。
「おいっ」
「もう着たの!?」
「まだ脱いですらない。そうじゃなくて、髪濡れてるからズボンだけ試着とか駄目なのか?」
「買うんだし、気にしなくていいのに」
やっぱ買うのか、って違う、今はそういう問題じゃない。
「サイズ合わなくて買わなかったらどうするんだよ」
「それは無いと思うから大丈夫」
「色とか」
「絶対似合うよ」
「ありえない」
檜山の頭の中は自分中心に回ってるに違いない。僕は心の中で店員に謝りながら制服を脱ぎだした。
「幸慈」
なんだ?と聞くのが面倒で返事をしなかったが、今更そんなことで凹む奴ではないだろう。
「今持ってる私服全部捨てて」
ん?
「……は!?何だそれ!」
「ちょっ!!なんつー格好してんだよ!」
試着室のカーテンを開けて抗議する僕の姿に慌てる男を無視して言葉を続けようとしたが、無理やりカーテンを閉められた。
「やべー、マジ焦った」
それはこっちの台詞だ!
「捨てろってどういう意味だよ」
「古着屋って、着なくなった服を売りに行く場所でしょ」
当たり前だろ。
「幸慈が誰か解らない奴が着てた服を身につけてるとかありえない」
「それはオマエの価値観だろうが」
「檜山」
「うっ……檜山」
こんな時まで名前にこだわるなよ。
「未来ちゃんが古着を着てたら秋谷だって同じこと言うよ」
例えを出されても理解できない。
「僕は全然平気だけど」
「(でしょうね。じゃないと古着屋で買って着ようなんてしないからね)」
何かさっきから肌寒い。早いとこ着替えよう。僕はとっとと制服を脱いで渡された服を着た。はぁ、この作業を何回やれば帰れるんだろうか。着替え終わった僕はカーテンを開けて、男を捜したが店員以外は居なかった。よし、今のうちに試着を全部終わらせて帰ろう。
「良くお似合いです!」
そうですか。お決まりの台詞を有り難うございます。一応カーテンを開ける前に鏡を見たが全然お似合いでなかったぞ店員さん。だがサイズは恐ろしくピッタリだ。
「たっだいまー、着替えお……」
うるさいのが帰ってきてしまった。
「……」
黙って見てくる視線を不快に感じて睨み返す。
「何だよ。ジロジロ見るな気持ち悪い」
「……完璧」
なんて言ったのかは聞き取れなかったけど、大して興味もなくサイズを確認する店員に後何回試着しないといけないのか聞くと、最低でも後三回は頼みたいと言われゲッゾリした。
「やっぱその色にして正解だったな。サイズもピッタリだし」
僕の手を取って満足そうに見下ろす笑顔に披露が増す。
「紫が僕に合うとは思えないがな」
「ラベンダー色ね」
紫だろ。
「俺も色違いの買おうかなー」
この服は一生着ないな。
「帰りたい」
「次これね」
人の話し聞きやがれ。このくたびれた体で料理の材料を買いに行かないといけないのかと思うと眩暈がする。
「幸慈ー、俺何色が似合うかな?」
知るか。
「言わないと帰れないよ」
言ったって試着が終わらないと帰れないくせに。
「……じゃあ青で」
「却下」
聞いといて速効で却下ってなんだ!今ここを殺人現場にしない自分を心から称賛したい。
「何色かな?」
今自分で却下したばかりだろうが。
「何でも良いだろ、色なんか」
「良くないよ!」
良くない、の感覚が僕には理解出来ない。
「幸慈の好きな色は?」
「ない」
「自然と目で追う色とか」
「ない」
「……じゃあ、好きな季節は?」
「……強いて言えば……秋?」
「これオレンジある?」
店員に色を催促して持ってきてもらった服を試着する姿は、ここの常連なんだと改めて認識させられる。おかわりのココアを持ってきてくれたので、黙ってそれを口にした。
「幸慈、どう?」
「知らん」
「えー(せっかくのペアルックなのに)」
ココアのお陰で体が少しだけ温まって、小さく息を吐いた。
「何で秋が好きなの?」
強いて言えば、の返答に質問してくるなよ。
「ねぇ、何で?」
「答えたら帰れるのか?」
「試着終わったらね」
「黙秘する」
「何で!?」
駄々を捏ねる高校生男子に頭を抱えながら、僕は試着をするために店員の所へ向かった。結局あれから四回試着をした後、いつの間にか用意されていたココアのおかわりを飲んでようやく男とおさらば出来ると思い心から喜んだ。ココアなんて久々だな。
行き付けのスーパーに入って割引野菜等が入ってるワゴンには殆ど食材は無く、定価で買う事にした。今日は散々だ。あんな思いをした結果、安売り品を買い逃してしまった。野菜が高騰してるから、割引はありがたかったが無いものは仕方がない。無いものは何をしても買えないんだから。それもこれも全部檜山のせいだ。
「幸慈ー、タコさんウインナー食べたーい」
なのに、そいつはまだ僕の横に居る。
「なんか新婚みたいだよねー」
そう言いながらウインナーを二袋買い物かごに入れる姿は恐ろしく上機嫌だった。金の心配をしたことが無いような買い物の仕方に腹が立つ。
「……」
「そんな照れなくてもいいじゃーん」
死ね。
「いつまでついてくるつもりだ」
「家まで」
ありえねぇ。家まで、の一言に足が勢いよく重くなり立ち止まる。
「だって、幸慈一人でこんなに持てないでしょ」
そう言って両手に持ってる紙袋をわざとらしく鳴らす。結局、檜山は僕の意見なんて聞かないで店員の用意した服の八割を買った。金を稼ぐ大変さを知るべきだ。右手に持ってる紙袋は檜山の個人的な買い物らしいが、そんなのは知ったことじゃない。そもそも一着で良いじゃないか。僕が何を着ようと関係ないだろ。
「僕を馬鹿にするな、それくらい平気だ」
「やー、でもー、かごの中身が大量すぎて、説得力が……」
僕の返事も聞かないで次々と増やしていったのは檜山だろうが。今回は作る量が多いから仕方ないと自分に言い聞かせる。荷物を減らすなら服を返品してこいと言わない自分を誉めたい。
「仕方ないだろ、普段の飯と一週間分のピクニックの材料考えたら自然とこれくらいの量になるんだよ」
「……えっ!弁当作ってくれんの!?マジ!?やったーー!!」
声がでかい。
まぁ、飯も服も檜山の爺さんの店ではあるけど、かなり金を出してくれてるのは確かだし、このままじゃ不公平というか対等じゃない気がして、それが嫌なだけだ。
「弁当箱買わないと!」
飛び跳ねそうなくらいに喜んでた顔は一変して、すぐにでも弁当箱を買いに店の外へ走りだそうな勢いでソワソワし始めた。頼むから面倒事を起こすなよ。周りの視線が痛くて棚に向き合う様にして立つ。
「弁当箱は家にある」
「水筒!」
「ある」
「レジャーシート!」
「ある」
「……なんか、どうしよう」
何がだよ。面倒臭い男だな。頼むから声のボリュームを下げてくれ。
「すげー楽しみ」
「そうかよ」
人の笑顔というものは嫌いじゃない。
調子に乗ってリクエストをし続ける高校生男子を無視して買いたいものをかごに入れていく。お菓子にまで手を伸ばそうとしたのを止めて、これ以上増える前にレジへ足を動かす。後ろから何かをねだってくる声は全部無視だ。でないと一生帰れない。セルフレジの前に立った僕に、檜山は何をしているのか聞いてきた。予想通りセルフレジを知らないらしい。無人レジだと説明すると、目を輝かせてやりたいと言ってきたので社会経験としてやらせることにした。
「幸慈、これメチャクチャ楽しい!」
「そうか」
計りハンガーにセットしたレジ袋にスキャンした商品を入れていく。
「バーコードのない生魚はどうすれば良いの?」
「項目から探すんだ。ここを選択して……」
「おっ、あった。買った魚覚えてないと出来ないね」
「必要で買ってるんだから忘れないだろ」
「ミーちゃん相手に同じこと言える?俺は言えない」
確かに未来はメモを持って買い物に行かせても、メモを持っている事を忘れるから意味がない。ここは未来を例外として考えて発言した方が良いな。
「もしかして肉も魚と同じ?」
「肉はパックに入ってるの買ったから問題ない」
「本当だ。良かったー」
初めてのおつかいじゃないだろうに。会計を無事に済ませた後、余程セルフレジが気に入ったのか、また買いに来たいと言い出した。一人で買いにくる分には問題ない為、放っておくことにして店を出る。有言実行というやつだろうか。檜山は荷物の殆どを持って僕の横を歩き始める。重そうな素振りも一切なく終始笑顔のまま僕に話し掛けてくる姿は今にもスキップしそうなほど浮き足だっていた。僕の足は正反対に、地面にめり込んでいるのかと思うほどに重い。何で未来の彼氏はこんなのと友人なんだろうか。こんなのが毎日横に居たらストレスが貯まって仕方ないと思う僕の方がおかしいのかもしれない。人と人の繋がりなんて、曖昧でしかないんだから。
結局この日、檜山は制止する僕の言葉を無視して家まで荷物を運んだ。運んで終わりならまだ良かったが、図々しく家に上がり込んだあげく、御丁寧にも僕が今まで着てた服を、未来と母さんから貰ったやつ以外全部を処分し始める始末。帰る頃には何故か母さんとすごく仲良しになっていたのも気に入らない。母さんに言われて大通りまで見送るはめになった僕は、自転車の前かごに男の荷物を入れ、とぼとぼと歩き出す。何で僕がここまでしないといけないんだ。
「今から楽しみすぎて寝れる気がしなーいっ」
そうか。僕は疲労が貯まりすぎて今すぐにでも寝れそうだ。
「幸慈の手料理楽しみだなー。ミーちゃんのお弁当を横取りするのを我慢して良かった」
昼休みの時の話か。
「未来なら言えば分けてくれただろ」
「ミーちゃんは良いよって言ってくれたんだけど、秋谷が駄目だって睨んできてさー。マジで鬼に見えた」
あぁ、そういうことか。
昼の前に教室で購買の話を聞いたから未来に栄養を摂らせようと必要以上に神経質になったのかもな。明日は別の意味で神経質になりそうだが。
時間帯のせいか社会人が多く、すれ違った女の人からは甘い匂いがして眉をしかめる。日頃の行い、か。檜山は足を止めた僕を不思議そうに見てきて、どうしたのかと聞いてきた。嫌な奴だと思われるだろうか。友人を非難されるのは、誰でも嫌な気持ちになるものだ。それを口にしたら、未来はどう思うだろうか。放れて、しまうだろうか。それでも、知りたい事があった。
「鹿沼は良い奴か?」
僕の質問を聞いて、檜山の顔は不機嫌に歪む。やっぱり、友人を悪く言われるのは、嫌な奴だと決めつけられるのは不愉快だよな。
「何で、秋谷の名前が出てくるわけ?」
「友達を悪く言われるのは嫌だろうけど、でも大事な事なんだ」
「違くてさー」
「っ!」
自転車が倒れる頃には、僕は両手首を掴まれた状態でコンクリートの塀に背中を押し付けられていた。どうにか逃げられないかと腕に力を入れたが、更に強い力で塀に押し付けられ手首が悲鳴を上げただけに終わる。意外にも友達思いな一面に少し驚く。もう少しサバサバした関係かとも思っていたが、そうではないらしい。
「俺と二人でいるんだよね?」
そう聞かれて、一応辺りを見回す。綺麗に誰も居ないな。
「幽霊でもいない限りはそうなるな」
「なら、秋谷の事なんて考えてんじゃねぇよ」
予想してたのとは全く違う返答に眉をしかめる。鹿沼を疑ったことに怒ってるんじゃないのか?更に強くなる力に苛立ちながらも、ここで引きたくは無かった。僕は目の前の苛立つ顔を睨み付け口を開く。
「未来の側で鹿沼を否定出来るわけないだろ!」
僕の言葉に男の怒りは引っ込んだ。
「は?……ミーちゃん?否定?」
力が少し緩んだ事を考えると、少しは冷静に話が出来ると思って良いだろう。
「日頃の行いはアンタ……じゃなくて、檜山と一緒だったんだろ」
「んー……俺ほどではないかなー」
だろうな。
「秋谷は後腐れない女選ぶの上手かったし」
でも、やってる事は同じじゃないか。好きってなんだよ。本気ってなんだよ。子供の戯言を、どう信じろって言うんだ。縁を切ることが前提にある関係が当たり前だった奴が、本当に、本気で好きだなんて、信じられるわけない。
「僕はそれが怖いんだ。もし遊びの罰ゲームとか気紛れならすぐにでも手を引いてくれるように……」
「駄目だよ」
言い終わる前に重ねられた言葉に込められた意味は、どっちだ。
「それは、死ねに等しい言葉だよ」
なんだよ、それ。
「それくらいまでに、秋谷はミーちゃんを求めてるんだ」
そんなの今だけじゃないか。一時の感情じゃないか。大人が失敗するものを子供が貫き通せるわけないだろ。
「いらなくなってからじゃ駄目なんだ」
それじゃ遅すぎる。
「傷ついてからじゃ駄目なんだ」
遅すぎるんだ。
「……ミーちゃんが大事なのは解ったけど、少しは信じてあげようよ」
信じてるさ。未来の事は誰よりも信じてる。鹿沼の事だって友達になったって紹介なら今よりも穏やかでいられたさ。でも、これだけは駄目だ。恋だの愛だの夢を見て、現実に打ちのめされた先には何も無い。俺はそれを知ってる。嫌って位に思い知らされた。
「幸慈は、何が不安なの?」
「……先が、解らない事かもな」
「そっか。……本気で、ごめんね」
慣れた手付きで僕を抱きしめながらごめんと言った男に反発心を抱く事はなかった。それは多分、遠慮がちに動く事無く背中を擦り慣れた手に、僕の代わりは他に沢山いると言われている様な気がしたからだろう。
いつか未来が誰かに恋をする事くらい解っていた事じゃないか。だから僕は、これから先ずっと未来の涙を覚悟して生きていかないといけないってだけの事。それだけの事だ。
オレンジ色の空に、秋を重ねる。
葉の色を変えて、寂しさをまとわせるくせに、どこかで暖かさをちらつかせるオレンジは、大嫌いだ。
まだ授業中じゃないのか?と呆れた顔で聞かれたので、追い出されないための賄賂として、さっき買ったパンを差し出した。賄賂と解っていながら迷わずに受け取る姿は清々しい。
白衣を椅子の背凭れに掛け、無精髭を生やしたヤル気ゼロの三十八才の保健医は母さんの兄で僕の伯父にあたる。見た目は悪いが腕は良い。母さんには、僕は伯父さんに似ていると言われた事があるが、それはなんだか複雑だ。僕はここまでだらしない人間ではない。何が似ていると言うんだ。全然じゃないか。
「自習なので勉強をしに来ました。課題はちゃんと終わらせたし問題無いだろ」
伯父さんを座る椅子ごと机の前から動かし、その場所に丸椅子を置いて腰をおろす。
「ここは怪我人や病人が来る場所だ。何も無いなら教室に戻って勉強しろ」
「だから、こうしてわからないところを理解しようと多木崎先生に聞きに来てるんです」
そう言ってパソコンをずらし、古文の教科書を机に置いてノートを開く。
「そもそも保健医に古文教えろって言うことが間違ってると思うぞ」
もっともな事をいう伯父さんはコーヒーを飲みながらパソコンと向き合ってしまう。
「あんな噛み噛みの授業で理解しろなんて時間の無駄」
「噛み噛み?それは無いだろ。解りやすくて評判なのに」
「不良が二人居るだけでボロボロ。未来を証人にしても良い」
「不良……あの二人か。校内では大きな問題起こして無いだろ。何で怖がるんだ?」
校内では、と、言うことは、校外では何かしらをやらかしている、と、とらえて問題ないんだよな。未来は大丈夫だろうか。いや、僕と居るよりはマシになるか、同じくらいかの違いでしかないだろうから、心配するのは止めよう。
「知らないよ。居ることすら知らなかった僕に聞くな」
大きな問題を起こしたことが無いなら、これから起こされる可能性を危惧して、何もない様にと身構えた結果があの授業だろうな。本当に下らない。こっちはお金を払って授業を受けているんだ。中途半端にやられるのは迷惑でしかない。
「我が甥っ子ながらどうやってこの数ヵ月を過ごしてきたんだか」
「その可愛い甥っ子が必死に頼んでいるのに駄目だなんて、伯父さんがそんなに冷たい人だとは知らなかった」
「そんな心にもない台詞を真顔でペラペラと言う奴には絶対に教えん。今すぐ教室帰れ」
「これの動詞なんだけど」
「あー、これは……」
なんだかんだ教えてくれる伯父さんの優しさと博識に頼ってしまうのは今日が初めてではない。未来もそれを知っているからこそ、俺を咎めることはしないし、咎めるとしたら伯父さんも一緒になる。優しい未来にはそれが出来ない。少し卑怯だが、これも大事な策の一つ。伯父さんが教えてくれた部分を書き留め終わるのと同時に保健室のドアがバンッと勢いよく開いた。何事かと身構えた僕と伯父さんはドアへ体を向ける。視線の先には、教室に居るはずの金髪の不良が肩で息をしながら立っていて眉をしかめた。なんで、ここに不良が来んの?
「はー、はー、ど、どっか怪我した?」
「は?」
不良は何を言っているんだ。
「それとも病気?」
状況が飲み込めない僕と伯父さんは顔を見合わせた後でもう一度不良に視線を戻す。どこで何を勘違いする事になったのかは興味ないが、伯父さんに余計な迷惑がかかるのは避けたい。
「まぁ、落ち着きなさい。この子は怪我一つ無く健康だ」
伯父さんはコーヒーの入ったコップを机に置いて、僕が健康だという事を勘違い男に伝える。
「まぁ、普通は怪我とかで来る場所だから、檜山くんが心配するのも当然だな」
その言葉にトゲを感じるのは気のせいだろうか。伯父さんの言葉に不良はキョトンとした顔で俺と先生を見比べる。
「あれ?じゃー、なんで保健室?」
首を傾げながら聞いてくる不良の質問に答えるのが面倒でノートに視線を戻す。
「幸慈、友達が心配してきてくれたのにその態度はないだろ。悪いな、こんなんだからよく誤解されやすいんだけど、本当は繊細で優しい子なんだ」
「……はぁ(何で多木崎くんの事を名前で呼んでんの?教師のくせに)」
曖昧な返事をする奴と親しくさせようとする伯父さんを睨みつけ、間違いを訂正する為に口を開く。
「違う」
「照れるなって」
頭をガシガシと撫でてくる伯父さんの手を退けながら僕はノートを閉じた。
「どっちも違う」
「?」
どういう意味だという顔をしている伯父さんを軽く睨んで机の上の物を片す。
「僕の性格は見たまんまで、不良は友達じゃない」
そう言いながら、僕はノートで不良を指す。不良が少し寂しそうに笑ったような気がしたけど、それは絶対に気のせいだ。
「こらっ」
「デッ!」
久しぶりに伯父さんのチョップをくらった。加減無しの本気のチョップが残した痛みの余韻が辛い。
「全く、口の悪さは誰に似たんだか」
誰にも似てないなら、一人しかいないだろ。
「はっ、アイツに似たんじゃねぇの?」
吐き捨てるように言って、立ち上がる。
「幸慈っ!」
「説教する暇があるなら女心でも勉強しなよ」
伯父さんの説教を聞かされる前に勉強道具と飲み物を持って、チョップの仕返しに奥さんを怒らせた事を突っつくと、伯父さんは青冷めた顔をして固まった。その隙に保健室から撤退する。ドアのところで不良に止められるかと思ったけど、そんなことは無かった。まぁ、その本人は僕の後ろにいるんだけど。
「謝んないでいいのぉ?ケンカみたいな感じだったけどー」
うるさい。てか、喧嘩じゃない。そう言い返すのが面倒で口を閉ざす。
「多木崎くーん」
うるさい。
「無視しないでー」
「うるさいな。アンタには関係ないだろ」
俺が伯父さん夫婦に首を突っ込むのも無責任だろうな。まぁ、今回は八つ当たりだけど。ごめん、伯父さん。心の中だけで謝っとく。
「やっと返事してくれたー」
その嬉しそうな声に余計イライラが増す。何か別の事を考えよう。そうだ、さっき教わった動詞の復習をすれば気が紛れるかも。頭を冷やそうと別の事に思考を巡らせていたせいで、後ろとの距離が狭まっていることに気がつかなかった。
「っ!」
突然腕を引っ張られた事に対応出来ず、足を止めるしかなかった僕は、何のつもりだ、と、後ろの人物を睨む。だが、睨んだ先には怖いくらい真っ直ぐな目が僕を待ち受けていた。この目、嫌いだ。
「アンタじゃない」
意味の解らない言葉に眉をしかめる。
「俺の名前は檜山茜」
それがどうした。僕と何の関係があるって言うんだ。掴まれた左腕に視線を向けて不良を睨む。
「離せ」
「これから俺のこと名前で呼んでくれるなら離してあげる(こんな風に睨まれるのも初めてだな)」
「断る」
そう言うと、俺の腕を掴む力が少し強くなった。
「なんで?俺だってあの保健医みたいに下の名前で呼びたいの我慢してるんだからそれくらい良いでしょ?(何で名前で呼びたいんだろう)」
意味が解らない。なんでそこで伯父さんが出てくるんだ。親戚なんだから当たり前の事じゃないか。
「クラスの奴の言葉には返事したくせに何で俺の言葉は無視なの?(何でこんなにイライラしないといけないのさ)」
今度はクラスの奴かよ。とことん意味が和からない。何、コイツ。今日会ったばかりのくせに馴れ馴れしい。所詮は未来の恋人の友人でしかないくせに。
「はっ、未来達が羨ましくなったからって僕を使って恋人ごっこ?それでヤキモチ焼いた振りでもしてるわけ?」
嫌味を込めて言った言葉に、男は眉間に皺を作った。
「俺だって好きで食べれないモチ焼いてるんじゃない!」
コイツ、今なんて言った?本人も自分で言ったことが信じられないといったような顔をしている。緑の瞳が揺れて、左手で口元を覆い難しい顔をして、数秒後に息を吐く。吐き終わった息の変わりに、迷いが消え何かが吹っ切れたような顔をした後、さっきよりも強く僕の嫌いな目をぶつけてきた。危機感を感じた僕は、手に持っていた教科書や飲み物を投げつけて、腕の拘束が緩くなったのを見計らって不良から離れる。
「冗談じゃない!僕が感情の中で一番嫌いなのは、オマエが僕に向けてる気持ちそのものなんだよ!二度と僕を好きだと思うな!」
そう言い捨てて、僕はその場から逃げ出した。頼むから追ってくるな。僕を呼ぶな。誤解だと、勘違いだと騒ぎ立てろ。その願って、無我夢中で走って、走り続けて、授業の終わりを告げるチャイムを聞いた。いつもは通らない場所で足を止め、後ろから追いかけてこない事を確認して壁に寄り掛かる。
「はっ、はっ、くそ、なんだよあの不良」
いつもとは違う走り方をしたせいで息がうるさく耳に届く。未来も面倒なのを連れてきたものだ。巻き込むなと言ったのに、結局は巻き込まれている自分に嫌気が差す。教室に戻るのは嫌だが授業の事を考えると、逃げ続けたところで未来のところへ戻れば不良が待っているのは目に見えている。
「好き?ははっ、冗談じゃない」
同じになってたまるか。僕はアイツにはならない。絶対に。あんなのは、二度とごめんだ。
息が整って、改めて周りを見回す。見覚えのない光景にストレスが溜まる。逃げることだけを考えていたせいか、気がつけば迷子になっていたらしい。早速ろくなことがない。たかが男子校の癖になんでこうも無駄に広いんだよ。全力疾走したせいで必要以上に疲れたし、熱いし、喉乾いたし、少しだけ腹が減った錯覚すらする始末。はっ、としてズボンのポケットに手を入れると、五百円玉まみれの財布が出てきて息を吐く。助かった。幸い、近くに自販機があったので、そこで水のペットボトルを買って半分ほど飲んで喉を潤す。二度目のチャイムを聞いて、初めて授業をサボったのだと認識する。こうなったらかなり早いが一人でプール掃除始めるとするか。僕は意地でもそこへ辿り着くと心に決めペットボトルを手に歩き始めた。
……
…………
………………
奇跡だ。目の前にあるプールの存在に何度も瞬きをする。掃除を始める前からやりきった感が半端ない。とは言え、やらないと帰れないもんな。未来のためにも自分のためにも頑張ってみるか。水泳部の部室から掃除道具を一通り取り出してプールサイドに置いて、ブレザーを脱いだ後ワイシャツの袖を捲くり、靴と靴下を脱いでズボンの裾が濡れないよう膝まで折ってからホースとデッキブラシ片手にしたくもない掃除を始めた。足元は結構泥が溜まってて予想以上に歩き難い。未来だったら絶対転ぶな。しかもプールが無駄に広い。これ何メートルあるんだろう。
ホースを固定してから両手でデッキブラシをしっかり持ち掃除を始める。泥がある程度なくなったのは六時間目の授業終了を告げるチャイムが鳴ってからだった。これ、放課後から始めてたら大変だったな。額から流れる汗を乾かす風が気持ち良くて目を閉じる。鞄、どうしよう。まぁ、自分の状況を考えると持ってきてもらうしかないんだが、面倒事の臭いしかしない。背に腹は代えられないか。一応連絡しておくことにした僕は、プールサイドに上がってブレザーから携帯を取り出す。
「……こわ」
携帯には未来からの着信とメールがたくさん来ていた。僕はそれを見なかったことにして携帯をブレザーのポケットに戻す。さて、あともう一頑張りするか。
そうだ、確か無くなったネクタイの変わりに封筒が入れられてたっけ。内ポケットから封筒を取り出して中身を見た。あぁ、やっぱり。封筒の中に書かれた予想通りの内容に軽く笑ってポケットに突っ込んだ。ぬるくなったペットボトルの水を飲み干して息を吐く。
「くだらない」
デッキブラシを水切りに持ち換えて掃除を再開した。ここのプールは大きいほうだが掃除が早く終わったように感じる。僕の手際が良すぎるからなのか、未来の心配をしながら作業していないからなのか考えて、後者の可能性が高いのかもしれないと思い頷く。ま、何はともあれ、早く帰れるに越したことはない。水切りといってもどうせ水を溜めるし、水泳部がまた掃除するだろうから適当に終わらせて平気だと判断してプールサイドに上がる。
「後は水溜めて終わりだな」
一仕事終えて固まった筋肉を解すのに伸びをした僕の背中に、よく知った声が届く。
「幸慈ーーーーー!」
来た。近くなる声と足音に肩をすくめて振り返ると、未来が走ってくる姿が見えてゆっくりと息を吐き出す。僕の鞄は持ってきてくれなかったらしい。プールサイドに来た未来は、荒れた息を整えてから自分の携帯画面を僕に見せてきて眉間に皺を作る。
「何度も携帯に連絡入れたのに何で返事くれないの!?」
携帯画面を僕に近付けながら怒ってきたが、こちらには正当な理由がある。僕は携帯を押し返してプールを顎で差す。
「そんなの掃除してたんだから気付くわけないだろ」
「そ、掃除?」
プールを見るなり驚いた表情を隠せない未来は信じられないといった顔をして僕を見る。
「まさか一人でやったの!?」
他に誰がいるんだよ。誰かとやるような人間じゃないのは解ってるだろ。
「わかったら掃除道具片してこい。僕はプールに水入れる方やるから」
「……はい」
掃除を僕が全部やってしまったせいか、未来は少し落ち込みながら荷物をプールサイドの隅に置いて掃除用具を片しに行く。僕は水道管をひねり、水を流し込む。片し終わった未来が戻ってきた時、鞄を取りに行きたいから暫く留守番を頼みたい事を伝えると全力で止められた。何か、すごく嫌な予感がする。
「何を企んでるか是非聞かせて頂きたい」
「俺は何も企んでないから!」
ほう。
「俺は?」
てことは、他のやつが企んでるって事か。
「や、やだなー。誰も企んでないってばー」
「何故目を逸らす」
顔ごと視線を逸らす未来の顔を覗き込もうとした時、ガシャンとフェンスが音をたてた。
「たーきーざーきーくーん」
何故不良がここにいる。しかも不良が持ってるのって、もしかしなくても僕の鞄じゃないか。未来に視線を向けると誤魔化すように笑いかけられた。眼は口ほどに物を言うとは本当らしい。頭痛に頭を抱えた僕は盛大に息を吐いて捲っていた袖を元に戻しながら靴下を取りに向かう。
「だ、だって、ヒーくんが、幸慈の事が好きだから協力してって」
「迷惑だ」
「ご、ごめん」
背中に未来の声を受け止めながら、靴下を履いたりと服装を整えた。その間にも不良はフェンスを登ってこっち側に来ようとしている。
「ミーちゃんは悪くないよ。ごめんね。嫌な思いさせちゃったね」
そう言いながらガシャンと音を立ててプールサイドに来た不良の顔を見る限りでは一応反省しているみたいだった。
「そ、そんなことないよ」
あるだろうが。仲良くなるのは未来の自由だが、俺の気持ちを無視しないでほしい。だが、今までだったら未来は俺の嫌な事はしなかった。この行動にも何か意味があるのか?
「なんだ、綺麗じゃねぇか」
「秋谷おっそーい」
「フェンスのところまでは一緒だっただろうが。つーか、これオマエ一人でやったわけ?」
「そうだけど。いっ!」
右腕に痛みを感じて振り向くと不機嫌な顔をした不良が居た。
「秋谷とは普通に話すんだね」
言葉の意味が解らなくて無視しようとしたら、腕の痛みが強くなった。この馬鹿力!
「秋谷とは普通に話すんだね、の返事は?」
笑顔と腕の痛みが比例しないのは何故だろうな。
「僕に害がないからな」
「へぇ」
納得がいかない顔をして、不良は俺を見下ろす。
「その辺にしとけ、腕折れるぞ」
鹿沼の言葉で力が弱まり痛みは無くなったが、腕は今もつかまれたまま。コイツ、本気で嫌いだ。
「ミーちゃん、後どれくらいで掃除終わる?」
「え、えっと、水溜めて終わり?」
未来は困惑しながら鹿沼に聞くと、頷き返され安心していた。その後、何故か未来は僕に向かって頷いてきたので、なんとなく頷き返す。
「じゃあ、後お願いね。きちんと家まで送らないとダメだよー、秋谷」
「わかってる」
何言ってんだコイツ。僕の知らない所で僕に関係する話が纏まってるのが気に入らない。
「幸慈」
「!?」
いきなり呼び捨てにされて肩が跳ねた。
「デートするよ」
は?
「もう、答えは聞かないことにしたから」
「ぉわっ!ちょっ!」
言うよりも早く僕を肩に担いだ不良は走り出した。冗談じゃないっ。未来は兎も角、僕は一般高校生位には身長があるんだ。こんな俵みたいに担がれるのは屈辱以外の何物でもない!
「レッツゴー!」
「待て!降ろせ馬鹿!!」
「あははは、聞こえませーん」
聞こえてるじゃないか!結局校門まで担がれた僕は、渋々不良の事を苗字で呼ぶのを条件に自分で歩く権利を手に入れたが、それでも鞄は返してもらえず、逃げることが出来ない環境に舌打ちをする。笑顔で下駄箱にあるはずの僕の外靴を出された時には目眩すらした。あの時、体育教師を蹴るんじゃなかった、と、先にたたない後悔をして深く息を吐く。鼻歌混じりに僕の右手を掴んで歩く人間を追い払う術があるなら教えてほしい。
和風ハンバーグ・海鮮丼・きのこパスタ・シーフードドリア・日替わりランチ。メニューには美味そうな写真が大量で、昼飯を食い損ねた僕としては食欲を微かにそそられるが、どれも食べきれないと解っているせいか、まともに見るのを止めて窓の外へ目を向ける。これ食べたら帰れるのかな。宿題は出たんだろうか。帰ったら未来に確認しないと。
「幸慈は何食べるか決めた?」
目の前に檜山さえいなかったらとっくに軽食を頼んでいただろう。
「要らん」
「んー、よしっ」
頼む気のない僕は、呼び出しボタンを押す檜山の指先を他人事のように見ていた。店が空いていたからか店員はすぐにやって来て、注文を聞いてくる。
「お待たせ致しました。ご注文をお伺い致します」
「オムライスとドリンクバーを二つずつとー、イチゴパフェとチョコレートパフェを一つずつ。デザートは後から持ってきてね」
オムライスとデザートを二人分頼む檜山に呆れる。オムライス二人分なんて僕だったら絶対に無理だ。パフェだって一つ食べれるかどうか。考えただけで吐き気がする。
「ご注文繰り返させていただきます。オムライスを……」
この店員は随分と丁寧な対応をするんだな。僕も高校生になったわけだし、そろそろバイトしようか悩んではいる。母さんは必要ないって言うけど、一人息子としてはやっぱり力になりたいわけで……まぁ、医者の月給に比べれば可愛い金額しか稼げないだろうけどな。
「幸慈」
「イッ!」
檜山の事忘れてた。でも、無理やりファミレスに連れてきておきながら、僕がチョット考え事してただけで足を踏んでくるのはどうなんだ。保護者の教育方針を盛大に疑う。
「隙だらけだよ。本当に廊下で俺を殺そうとした人と同一人物?つか、俺と一緒にいるのに考え事とかどうなの?サイテー」
なら今すぐ帰らせろ。
「で、何飲む?」
「要らん」
「オレンジジュースねー、りょーかーい」
人の話を聞け!席を立ってドリンクバーへ向かう男に頭痛がした。未来の彼氏とは正反対だな。まぁ、まともに話していないから今評価するのはどうかと思うが、身勝手な事をしまくる檜山と比べると一般常識は備わっていると解る。プール掃除はどうなっただろうか。あの彼氏はちゃんと家まで送ってくれるだろうけど。そう考えていると携帯が震えだした。何かと思って僕はポケットから携帯を取り出し待ち受けを見る。未来からの電話に少し安心した後、通話ボタンを押す。
「はい」
『あ、幸慈?』
僕かどうかを確認する未来の言葉に眉をしかめる。
「僕以外の誰がこの携帯を使うんだ?」
『ヒーくんが出るかもしれないじゃん』
どうしたらその考えにたどり着くんだ。
「勘弁してくれ」
未来の言葉にどっと疲れた僕は机に突っ伏した。
「で、掃除は終わったのか?」
『うん。それを伝えたかったのと……明日の弁当』
自習でのやり取りが脳を過り未来の言葉を遮る。
「却下」
『まだ言い終わってない』
「ピクニックなんてアホなもの誰がするか」
「えーしようよー」
「……」
顔を上げ前を見ると、思っていたよりも近くに檜山の顔があった。
「チョット貸して」
「ちょ、おいっ」
「もしもし、ミーちゃん?」
僕の許可を得ないまま携帯を奪い未来と話始めた。通話代は誰が払うと思ってるんだ。こういうところが非常識だというのが何故解らない。
「ねー、俺もしたいなー。ピクニック」
勝手にしてろ。ピクニックは無しにしても買出しはしないとだな。明日の未来と母さんの弁当が作れない。今冷蔵庫にあるのは……。
「だいじょーぶ!俺に任せなさい!」
檜山のヤル気に溢れた声に思考を呼び戻され、僕の知らないところで話がまとまりつつあるらしい事が解った。高校生にもなってピクニックって、どんだけ子供なんだよ。
「弁当箱?チョット待ってねー。幸慈、ミーちゃんが弁当箱返し忘れたから明日返すって」
忘れてた。
「僕に返すくらいならその弁当箱を彼氏のためのおかずで埋め尽くしてみろ」
「ミーちゃんってそんなに料理ダメなの?」
「卵の殻を割るところから始めないとダメだな」
「ぶっ、あっはははははは……ひー、く、くるしぃー。マ、マジみーちゃん最高!あー、ミーちゃんごめんね。拗ねないでよー」
なにを暢気に話してるんだ僕は。檜山は僕に対して最悪な感情を抱いてるってのに。早く別のことを考えよう。えーっと……。
「お待たせしました。オムライスになります」
「あぁ、どーも」
自然と僕の前にも置かれたオムライスを見て、最近作ってないな、と懐かしくなった。
「はい」
やっと電話が終わったらしく、檜山は携帯を僕に返した。それを受け取った僕に、今度はスプーンを差し出してくる。何で僕に渡してくるんだ。
「あ、フォークの方が良かった?」
まさか、檜山、僕の分も頼んでたのか。スプーンを受け取ると、自分もスプーンを持ってオムライスに指した。
「いっただきまーす」
檜山どんだけ自由なんだ。それに、なに勝手に僕の分も頼んでんだよ。
「食べないの?もしかしてアレルギーとか?」
「……なにが楽しいんだ」
「幸慈とご飯食べれること」
馬鹿馬鹿しい。
僕は出来るだけ男を視界に入れないようにオムライスを食べ始めた。あ、美味い。
「ここのオムライス美味しいでしょ?」
檜山に言われるとムカつく。
「むー、ふりだしに戻っちゃった感じかなー」
最初から一歩も進んてない。
「明日ってさー、四時間目の家庭科って自習になったでしょ」
何それ。僕は購買が休みになることしか知らないぞ。
「あー、そっか、幸慈は午後サボったから知らないんだっけ」
誰かさんのお陰でな。個人的意見を言えば、プール掃除やってたんだからプラスマイナス0だ。
「ねぇねぇ、自習でピクニック用の弁当作ってよー。家庭科室は使えるようにしておくからさ」
簡単に許可が出るわけない。脅しでもするつもりか?それで使えるって、学校が生徒に負けてどうする。
「ここの金も俺が払うしー、材料費も出すからさー。ミーちゃんの料理教室ってことで、どう?」
僕が首を縦に振るまで家に帰す気ないな。料理教室ってのは意外と良い案だが、発案者が檜山じゃな。どうしたもんか。
「檜山くん?」
「「?」」
突然の声に僕と檜山は同時にその方へ顔を向ける。僕達の座るテーブルの近くの通路に若さと化粧の力を借りて可愛らしく化けているであろう女が立っていて、笑顔で近付いて来た。距離がなくなるにつれて届く匂いに眉をしかめて息を止める。かなり香水臭い。それにこの女、スッピンはブスっぽいな。
「久しぶりー!半月前のホテル以来だねー!」
年頃の女が恥じらいも無く大きな声でホテルと口に出来るほどこの世の教育は腐ってきているのか。この女と知り合いという事は目の前の男もまともではないってことだな。解ってはいたが、目の当たりにすると嫌悪感が増すというものだ。まとも、か。僕にそんなこと言う権利は無いな。自己否定する考えに反吐が出るが、当然なのだから仕方がない。味のしなくなったオムライスは一口食べたきり、スプーンが進まずほとんど残っていた。
「ねぇ、これから遊びに行かない?二人で」
おぉ、僕は邪魔者か。このまま二人で何処かに行ってくれればすごく助かる。今すぐそうしろ。なんならここの金は僕が払う。だから早くどこかに行け。
「んー、ごめんねー。今はこの子といる方が大事なんだ」
期待とは正反対の言葉に眉間に皺を作ってしまった。
「なにそれー。ねぇ、檜山くんの優しさに漬け込むとか最悪なんだけど」
今やオマエの脳みそが最悪だ。
「そんなふうに言わないでよ。俺が無理言って付き合ってもらってるんだよ」
自分が無理矢理連れ回してる自覚はあるのか。
「檜山くん優し過ぎだよ!嫌なら嫌って言わなくちゃ!」
キャンキャンとうるさいなー。最悪だがこの男は未だに僕に惚れてるらしく、飽きるまでは他からの誘惑には絶対頷く事は無いと認識させられる位の会話に頭を抱える。本当、最悪。そんな事を考えていると、男と目が合った。申し訳なさそうな顔をしてる暇があるなら馬鹿女を何とかしろよ。
「アンタも少しは気を利かして帰るなりしなさいよ!」
そう言って、女はコップに入った水を僕にぶっかけた。
「ちょっと!何してんのさ!」
焦る檜山の声と女を非難する他の客の声が聞こえたが、当の本人には届いていない。なんで僕ばっかり!僕はコップを掴んで立ち上がり中身のオレンジジュースをぶっかけた。その瞬間耳にチラホラと拍手の音が聞こえ、檜山は驚いた顔をして僕を見てくる。
「ちょっと!なにすんのよ!」
女の声に店員と客の視線がさらにこっちのテーブルに集まる。
「それはこっちの台詞だ。自分の気持ち押し付けてキャンキャンと犬みたいに吠えて五月蝿いんだよ。僕は静かに飯食ってただけだろ。なのに水かけてくるとか最低」
「だからってジュースは無いじゃん!ベタベタして気持ち悪いー!クリーニング代出してよ!」
「だったら僕の分アンタが払ってくれんの?当然ここの飯代も払ってくれるんだよな?」
そう言って僕は水まみれになったオムライスを指差した。
「冗談じゃないわよ!」
「なら早くどっかに行ってくれないかな?まぁ、ジュースまみれでメイクの剥がれた汚い顔を好きな人に見られても平気だって言うなら、話は別だけど」
見下すように笑う僕の言葉にハッとした顔で檜山に視線を向けた女は、すぐに顔を真っ赤にして店を出て行った。また敵を作ってしまった事に頭を抱えて盛大に溜め息を吐く。絶対どこかで闇討ちに合うの確定だな。
「幸慈、カッコイイ」
真顔で男が男に言う事じゃないだろ。
「人見る目なさすぎ」
「ごめん」
僕は座っていた場所に腰を下ろし、濡れたブレザーを脱いで全部止めていたシャツのボタンを二つ目まで外す。濡れた眼鏡をワイシャツのポケットに入れた後、髪から滴り落ちる水滴が邪魔で軽く後ろに流した。
「……エロ」
はぁ?
「でも、このままじゃ風邪ひかしちゃうね」
そう言って男は立ち上がって僕の手を引いて歩き出した。僕は慌てて鞄を持って立ち上がり、バランスを崩しながら歩き始める。僕のは食べれないが、オマエのオムライスはまだ残ってんだろ。店で騒いだ罪悪感からオムライスの金を払うために財布を取り出そうとしたら、驚いたことに男はレジに行くことなく食い逃げ状態で店を出た。
「お、おいっ、金!」
「この店、オジイが経営してっから平気」
オマエは何者だ。まさか金持ちの坊ちゃんか?ま、金持ちと解っても態度を変えるつもりは無いけど。てか、どこまで行くんだ?僕は食料を買って今すぐにでも帰りたいんだが、それが叶う雰囲気にも思えない。檜山は店を出て、すぐに足を止めて僕を見てきた、と思う。眼鏡が無いから全てがボヤけて見えて判断がしにくい。
「嫌いになった?」
最初から嫌いだ。いや、違うな。
「嫌いなのは恋愛感情」
「それ、遠回しに嫌いって言ってるようなもんだよ」
ふーん。檜山が僕にとって不必要なことに変わりないけどな。それからはお互いに無言で歩く。せめて眼鏡を掛けたいと思って足を止めたら最初より強く手を引っ張られて腕を引かれた。むかつくのは身長が俺の方が低く相手の歩くペースに合わせると少し小走りになることだ。お陰で鞄と上着を持ちながら歩く僕は今にも転びそうな状況だが、全く気付いてもらえない。すれ違う人間の視線が雰囲気で伝わってきて僕の神経を逆撫でする。
「着いたよ」
ようやく足を止めることが出来た僕は、すこし前屈みになって息を整えた。
「幸慈?」
暢気に首を傾げてそうなところが更にムカつく。
「もう少しゆっくり歩け!僕の歩幅はオマエ……じゃなくて、檜山みたいにでかくないんだよ!それに、眼鏡が無いとほとんど見えないから危ないんだ」
言って満足した僕は、ポケットから眼鏡を取り出す。眼鏡を掛けて視界がはっきりと見えて安堵した僕の体は、五月の冷たい風に軽く身震いした。
「ごめん、寒かったよね」
水ぶっかけられたから余計に寒いんだよ!
「行こ、本当に風邪ひくよ」
誰のせいだ!
檜山に連れられて入ったのは、僕の知っているスーパーと縁の無さそうなファッションセンターだった。建物の中にはファッションブランドと呼ばれる店ばかりがずらりと並んでいて気が重くなる。なんだここ。メチャクチャ居づらい。
「か、帰りたい」
僕は鞄を抱き締めて項垂れた。
「買い物したらね」
僕の気持ちなんて知らない檜山は一つのブランド店へ迷うことなく入っていく。まさかこの店も檜山の爺さんが経営してるなんて言わないよな!?
「いらっしゃいませ、檜山様。本日はどのようなものをお探しですか?」
檜山様!?やっぱしここも爺さんが絡んでるに違いない。
「今日は俺じゃなくて、この子の服が欲しいんだ」
は?何で僕?
「どのような服がお好みでしょうか?」
「幸慈、服にこだわりある?」
店員と檜山の質問が理解できなくて少し首を傾げた。どのようなって、服は服だろ。着れれば何でも良いし。
「めちゃくちゃ安いやつ」
気にするといったら値段くらい。
「却下。俺好みでよろしく」
何の為に聞いてきたんだよ。
「ちょっ、おい!」
店員は礼儀正しく一礼してから背中を向けてどこかに行ってしまうし、僕はまた腕を引っ張られて歩かないといけないわけで。なんかもう、今日一日で色々ありすぎて疲れた。
「着いたよ」
その言葉に足元を見ていた顔をあげると、いつの間にか個室っぽい場所の入口に連れて来られていた事に気付く。
「何、ここ」
「んー、VIPルーム?」
僕の呟きに返ってきた言葉に改めてドアの向こうの部屋を見回す。部屋は白・ベージュ・茶でバランスよく統一されてて、入り口のすぐ横には大きめの試着室、前の中央スペースにはソファーとテーブル、それを覗いても無駄に広いスペースがあったりで、もう、訳がわからない。全身の血の気が引くという感覚を味わった僕は、ゆっくり後退した。
「はい、逃げない(こんな反応されたの初めてだな)」
僕の手を引いて中に入る背中に言葉が出ない。
「何か飲む?」
「帰りたい」
肉食動物に囲まれた草食動物の気持ちを、今なら少しだけ理解できる気がした。人生でこんなにも家が恋しく感じるのは初めてだ。
「ホットココアにしようかー、身体だいぶ冷えちゃったもんね」
誰のせいだ。声には出さなくても、僕は檜山に対してかなり怒ってるんだからな。
「ひっくしょん!」
やばい、このままじゃマジで風邪ひく。
「暖房入れようか?」
「要らん」
冷暖房まで完備してんのか、この部屋。
「ごめんね。あの場で俺がはっきり断ってれば……」
「アンタ……檜山がどんだけ断ってもあのての女は簡単には引きさがらねぇだろうが」
「まぁ、そうなんだけどさ」
「日頃の行いが……ひっくしゅっ!悪いんだよ」
「看病は任せてね」
「アンタが……檜山が僕の周りをウロチョロしてる間はぶっ倒れねぇよ」
「そっか、よかった」
そう言って檜山は僕の頭をポンポンっと撫でてきた。僕はその手を払ってソファーの真ん中に座る。鞄をテーブルに置いた後、濡れたブレザーをその上に乗せた。それと同時にノックの音が聞こえて、店員が何着か服の掛かったハンガーラックを押して入ってきた。あれ全部買うとか言いださないよな。僕の気持ちとは裏腹に、檜山は店員の持ってきた服を吟味している。
「あ、これ俺も欲しいかも。色はここにあるだけ?」
俺も、の意味が解らない。
「此方にある色以外には、グレー・紺・ホワイトがございます。後は似たデザインの物で裾のほうに……」
目の前で繰り広げられる会話についていけず、僕は考える事を放棄して膝を抱えた。
「(膝抱えてる。可愛いなぁ)」
寒くて腕を擦ると、会話が途切れているのに気が付いて顔を上げる。
「良かった。起きてた」
僕の前髪を横に流して笑顔を向けてくる姿を迷わず睨み付けた。檜山の前で寝るわけないだろ。
「幸慈、立って。試着するよ」
手を引かれて渋々立ち上がると、ハンガーラックの服を整える店員と目が合う。
「試着って……全部?」
僕の言葉に檜山はハンガーを揺らしながら服に触れる。
「全部じゃないけど、デザインによってサイズが違ったりするから、その確認くらいかな」
それって、結局全部じゃないか。
「僕としては、古着屋ので良いんだけど」
「古着?」
ポロっと出た本音に、しまった、と唇を引き締める。
「幸慈、古着って何?兄弟のお下がり?(その顔は可愛いけど、ちょっと無視出来ないかなぁ)」
言わないと帰れない雰囲気だと察した僕は盛大に溜め息を吐いた。
「自慢じゃないけど、僕の持ってる服は未来と母さんがくれたやつ以外は全部古着屋で買ったやつだから、こういう所のはちょっと……」
馴染みがないどころか関わりたくない。
「へぇ……予定変更」
なんかボソッと聞こえたと思ったら力尽くで試着室に押し込められた。
「ちょっ」
「とりあえずコレ着て」
そう言って僕に服を押し付けカーテンを閉めた男は店員に何かを言っているようだったが、なんか嫌な予感がして盗み聞きする気になれなかった。手元の服を見て溜め息を吐き、無駄にでかい鏡を見て、自分の髪が濡れている事を思い出す。
「おいっ」
「もう着たの!?」
「まだ脱いですらない。そうじゃなくて、髪濡れてるからズボンだけ試着とか駄目なのか?」
「買うんだし、気にしなくていいのに」
やっぱ買うのか、って違う、今はそういう問題じゃない。
「サイズ合わなくて買わなかったらどうするんだよ」
「それは無いと思うから大丈夫」
「色とか」
「絶対似合うよ」
「ありえない」
檜山の頭の中は自分中心に回ってるに違いない。僕は心の中で店員に謝りながら制服を脱ぎだした。
「幸慈」
なんだ?と聞くのが面倒で返事をしなかったが、今更そんなことで凹む奴ではないだろう。
「今持ってる私服全部捨てて」
ん?
「……は!?何だそれ!」
「ちょっ!!なんつー格好してんだよ!」
試着室のカーテンを開けて抗議する僕の姿に慌てる男を無視して言葉を続けようとしたが、無理やりカーテンを閉められた。
「やべー、マジ焦った」
それはこっちの台詞だ!
「捨てろってどういう意味だよ」
「古着屋って、着なくなった服を売りに行く場所でしょ」
当たり前だろ。
「幸慈が誰か解らない奴が着てた服を身につけてるとかありえない」
「それはオマエの価値観だろうが」
「檜山」
「うっ……檜山」
こんな時まで名前にこだわるなよ。
「未来ちゃんが古着を着てたら秋谷だって同じこと言うよ」
例えを出されても理解できない。
「僕は全然平気だけど」
「(でしょうね。じゃないと古着屋で買って着ようなんてしないからね)」
何かさっきから肌寒い。早いとこ着替えよう。僕はとっとと制服を脱いで渡された服を着た。はぁ、この作業を何回やれば帰れるんだろうか。着替え終わった僕はカーテンを開けて、男を捜したが店員以外は居なかった。よし、今のうちに試着を全部終わらせて帰ろう。
「良くお似合いです!」
そうですか。お決まりの台詞を有り難うございます。一応カーテンを開ける前に鏡を見たが全然お似合いでなかったぞ店員さん。だがサイズは恐ろしくピッタリだ。
「たっだいまー、着替えお……」
うるさいのが帰ってきてしまった。
「……」
黙って見てくる視線を不快に感じて睨み返す。
「何だよ。ジロジロ見るな気持ち悪い」
「……完璧」
なんて言ったのかは聞き取れなかったけど、大して興味もなくサイズを確認する店員に後何回試着しないといけないのか聞くと、最低でも後三回は頼みたいと言われゲッゾリした。
「やっぱその色にして正解だったな。サイズもピッタリだし」
僕の手を取って満足そうに見下ろす笑顔に披露が増す。
「紫が僕に合うとは思えないがな」
「ラベンダー色ね」
紫だろ。
「俺も色違いの買おうかなー」
この服は一生着ないな。
「帰りたい」
「次これね」
人の話し聞きやがれ。このくたびれた体で料理の材料を買いに行かないといけないのかと思うと眩暈がする。
「幸慈ー、俺何色が似合うかな?」
知るか。
「言わないと帰れないよ」
言ったって試着が終わらないと帰れないくせに。
「……じゃあ青で」
「却下」
聞いといて速効で却下ってなんだ!今ここを殺人現場にしない自分を心から称賛したい。
「何色かな?」
今自分で却下したばかりだろうが。
「何でも良いだろ、色なんか」
「良くないよ!」
良くない、の感覚が僕には理解出来ない。
「幸慈の好きな色は?」
「ない」
「自然と目で追う色とか」
「ない」
「……じゃあ、好きな季節は?」
「……強いて言えば……秋?」
「これオレンジある?」
店員に色を催促して持ってきてもらった服を試着する姿は、ここの常連なんだと改めて認識させられる。おかわりのココアを持ってきてくれたので、黙ってそれを口にした。
「幸慈、どう?」
「知らん」
「えー(せっかくのペアルックなのに)」
ココアのお陰で体が少しだけ温まって、小さく息を吐いた。
「何で秋が好きなの?」
強いて言えば、の返答に質問してくるなよ。
「ねぇ、何で?」
「答えたら帰れるのか?」
「試着終わったらね」
「黙秘する」
「何で!?」
駄々を捏ねる高校生男子に頭を抱えながら、僕は試着をするために店員の所へ向かった。結局あれから四回試着をした後、いつの間にか用意されていたココアのおかわりを飲んでようやく男とおさらば出来ると思い心から喜んだ。ココアなんて久々だな。
行き付けのスーパーに入って割引野菜等が入ってるワゴンには殆ど食材は無く、定価で買う事にした。今日は散々だ。あんな思いをした結果、安売り品を買い逃してしまった。野菜が高騰してるから、割引はありがたかったが無いものは仕方がない。無いものは何をしても買えないんだから。それもこれも全部檜山のせいだ。
「幸慈ー、タコさんウインナー食べたーい」
なのに、そいつはまだ僕の横に居る。
「なんか新婚みたいだよねー」
そう言いながらウインナーを二袋買い物かごに入れる姿は恐ろしく上機嫌だった。金の心配をしたことが無いような買い物の仕方に腹が立つ。
「……」
「そんな照れなくてもいいじゃーん」
死ね。
「いつまでついてくるつもりだ」
「家まで」
ありえねぇ。家まで、の一言に足が勢いよく重くなり立ち止まる。
「だって、幸慈一人でこんなに持てないでしょ」
そう言って両手に持ってる紙袋をわざとらしく鳴らす。結局、檜山は僕の意見なんて聞かないで店員の用意した服の八割を買った。金を稼ぐ大変さを知るべきだ。右手に持ってる紙袋は檜山の個人的な買い物らしいが、そんなのは知ったことじゃない。そもそも一着で良いじゃないか。僕が何を着ようと関係ないだろ。
「僕を馬鹿にするな、それくらい平気だ」
「やー、でもー、かごの中身が大量すぎて、説得力が……」
僕の返事も聞かないで次々と増やしていったのは檜山だろうが。今回は作る量が多いから仕方ないと自分に言い聞かせる。荷物を減らすなら服を返品してこいと言わない自分を誉めたい。
「仕方ないだろ、普段の飯と一週間分のピクニックの材料考えたら自然とこれくらいの量になるんだよ」
「……えっ!弁当作ってくれんの!?マジ!?やったーー!!」
声がでかい。
まぁ、飯も服も檜山の爺さんの店ではあるけど、かなり金を出してくれてるのは確かだし、このままじゃ不公平というか対等じゃない気がして、それが嫌なだけだ。
「弁当箱買わないと!」
飛び跳ねそうなくらいに喜んでた顔は一変して、すぐにでも弁当箱を買いに店の外へ走りだそうな勢いでソワソワし始めた。頼むから面倒事を起こすなよ。周りの視線が痛くて棚に向き合う様にして立つ。
「弁当箱は家にある」
「水筒!」
「ある」
「レジャーシート!」
「ある」
「……なんか、どうしよう」
何がだよ。面倒臭い男だな。頼むから声のボリュームを下げてくれ。
「すげー楽しみ」
「そうかよ」
人の笑顔というものは嫌いじゃない。
調子に乗ってリクエストをし続ける高校生男子を無視して買いたいものをかごに入れていく。お菓子にまで手を伸ばそうとしたのを止めて、これ以上増える前にレジへ足を動かす。後ろから何かをねだってくる声は全部無視だ。でないと一生帰れない。セルフレジの前に立った僕に、檜山は何をしているのか聞いてきた。予想通りセルフレジを知らないらしい。無人レジだと説明すると、目を輝かせてやりたいと言ってきたので社会経験としてやらせることにした。
「幸慈、これメチャクチャ楽しい!」
「そうか」
計りハンガーにセットしたレジ袋にスキャンした商品を入れていく。
「バーコードのない生魚はどうすれば良いの?」
「項目から探すんだ。ここを選択して……」
「おっ、あった。買った魚覚えてないと出来ないね」
「必要で買ってるんだから忘れないだろ」
「ミーちゃん相手に同じこと言える?俺は言えない」
確かに未来はメモを持って買い物に行かせても、メモを持っている事を忘れるから意味がない。ここは未来を例外として考えて発言した方が良いな。
「もしかして肉も魚と同じ?」
「肉はパックに入ってるの買ったから問題ない」
「本当だ。良かったー」
初めてのおつかいじゃないだろうに。会計を無事に済ませた後、余程セルフレジが気に入ったのか、また買いに来たいと言い出した。一人で買いにくる分には問題ない為、放っておくことにして店を出る。有言実行というやつだろうか。檜山は荷物の殆どを持って僕の横を歩き始める。重そうな素振りも一切なく終始笑顔のまま僕に話し掛けてくる姿は今にもスキップしそうなほど浮き足だっていた。僕の足は正反対に、地面にめり込んでいるのかと思うほどに重い。何で未来の彼氏はこんなのと友人なんだろうか。こんなのが毎日横に居たらストレスが貯まって仕方ないと思う僕の方がおかしいのかもしれない。人と人の繋がりなんて、曖昧でしかないんだから。
結局この日、檜山は制止する僕の言葉を無視して家まで荷物を運んだ。運んで終わりならまだ良かったが、図々しく家に上がり込んだあげく、御丁寧にも僕が今まで着てた服を、未来と母さんから貰ったやつ以外全部を処分し始める始末。帰る頃には何故か母さんとすごく仲良しになっていたのも気に入らない。母さんに言われて大通りまで見送るはめになった僕は、自転車の前かごに男の荷物を入れ、とぼとぼと歩き出す。何で僕がここまでしないといけないんだ。
「今から楽しみすぎて寝れる気がしなーいっ」
そうか。僕は疲労が貯まりすぎて今すぐにでも寝れそうだ。
「幸慈の手料理楽しみだなー。ミーちゃんのお弁当を横取りするのを我慢して良かった」
昼休みの時の話か。
「未来なら言えば分けてくれただろ」
「ミーちゃんは良いよって言ってくれたんだけど、秋谷が駄目だって睨んできてさー。マジで鬼に見えた」
あぁ、そういうことか。
昼の前に教室で購買の話を聞いたから未来に栄養を摂らせようと必要以上に神経質になったのかもな。明日は別の意味で神経質になりそうだが。
時間帯のせいか社会人が多く、すれ違った女の人からは甘い匂いがして眉をしかめる。日頃の行い、か。檜山は足を止めた僕を不思議そうに見てきて、どうしたのかと聞いてきた。嫌な奴だと思われるだろうか。友人を非難されるのは、誰でも嫌な気持ちになるものだ。それを口にしたら、未来はどう思うだろうか。放れて、しまうだろうか。それでも、知りたい事があった。
「鹿沼は良い奴か?」
僕の質問を聞いて、檜山の顔は不機嫌に歪む。やっぱり、友人を悪く言われるのは、嫌な奴だと決めつけられるのは不愉快だよな。
「何で、秋谷の名前が出てくるわけ?」
「友達を悪く言われるのは嫌だろうけど、でも大事な事なんだ」
「違くてさー」
「っ!」
自転車が倒れる頃には、僕は両手首を掴まれた状態でコンクリートの塀に背中を押し付けられていた。どうにか逃げられないかと腕に力を入れたが、更に強い力で塀に押し付けられ手首が悲鳴を上げただけに終わる。意外にも友達思いな一面に少し驚く。もう少しサバサバした関係かとも思っていたが、そうではないらしい。
「俺と二人でいるんだよね?」
そう聞かれて、一応辺りを見回す。綺麗に誰も居ないな。
「幽霊でもいない限りはそうなるな」
「なら、秋谷の事なんて考えてんじゃねぇよ」
予想してたのとは全く違う返答に眉をしかめる。鹿沼を疑ったことに怒ってるんじゃないのか?更に強くなる力に苛立ちながらも、ここで引きたくは無かった。僕は目の前の苛立つ顔を睨み付け口を開く。
「未来の側で鹿沼を否定出来るわけないだろ!」
僕の言葉に男の怒りは引っ込んだ。
「は?……ミーちゃん?否定?」
力が少し緩んだ事を考えると、少しは冷静に話が出来ると思って良いだろう。
「日頃の行いはアンタ……じゃなくて、檜山と一緒だったんだろ」
「んー……俺ほどではないかなー」
だろうな。
「秋谷は後腐れない女選ぶの上手かったし」
でも、やってる事は同じじゃないか。好きってなんだよ。本気ってなんだよ。子供の戯言を、どう信じろって言うんだ。縁を切ることが前提にある関係が当たり前だった奴が、本当に、本気で好きだなんて、信じられるわけない。
「僕はそれが怖いんだ。もし遊びの罰ゲームとか気紛れならすぐにでも手を引いてくれるように……」
「駄目だよ」
言い終わる前に重ねられた言葉に込められた意味は、どっちだ。
「それは、死ねに等しい言葉だよ」
なんだよ、それ。
「それくらいまでに、秋谷はミーちゃんを求めてるんだ」
そんなの今だけじゃないか。一時の感情じゃないか。大人が失敗するものを子供が貫き通せるわけないだろ。
「いらなくなってからじゃ駄目なんだ」
それじゃ遅すぎる。
「傷ついてからじゃ駄目なんだ」
遅すぎるんだ。
「……ミーちゃんが大事なのは解ったけど、少しは信じてあげようよ」
信じてるさ。未来の事は誰よりも信じてる。鹿沼の事だって友達になったって紹介なら今よりも穏やかでいられたさ。でも、これだけは駄目だ。恋だの愛だの夢を見て、現実に打ちのめされた先には何も無い。俺はそれを知ってる。嫌って位に思い知らされた。
「幸慈は、何が不安なの?」
「……先が、解らない事かもな」
「そっか。……本気で、ごめんね」
慣れた手付きで僕を抱きしめながらごめんと言った男に反発心を抱く事はなかった。それは多分、遠慮がちに動く事無く背中を擦り慣れた手に、僕の代わりは他に沢山いると言われている様な気がしたからだろう。
いつか未来が誰かに恋をする事くらい解っていた事じゃないか。だから僕は、これから先ずっと未来の涙を覚悟して生きていかないといけないってだけの事。それだけの事だ。
オレンジ色の空に、秋を重ねる。
葉の色を変えて、寂しさをまとわせるくせに、どこかで暖かさをちらつかせるオレンジは、大嫌いだ。
0
お気に入りに追加
18
あなたにおすすめの小説

【完結】俺はずっと、おまえのお嫁さんになりたかったんだ。
ペガサスサクラ
BL
※あらすじ、後半の内容にやや二章のネタバレを含みます。
幼なじみの悠也に、恋心を抱くことに罪悪感を持ち続ける楓。
逃げるように東京の大学に行き、田舎故郷に二度と帰るつもりもなかったが、大学三年の夏休みに母親からの電話をきっかけに帰省することになる。
見慣れた駅のホームには、悠也が待っていた。あの頃と変わらない無邪気な笑顔のままー。
何年もずっと連絡をとらずにいた自分を笑って許す悠也に、楓は戸惑いながらも、そばにいたい、という気持ちを抑えられず一緒に過ごすようになる。もう少し今だけ、この夏が終わったら今度こそ悠也のもとを去るのだと言い聞かせながら。
しかしある夜、悠也が、「ずっと親友だ」と自分に無邪気に伝えてくることに耐えきれなくなった楓は…。
お互いを大切に思いながらも、「すき」の色が違うこととうまく向き合えない、不器用な少年二人の物語。
主人公楓目線の、片思いBL。
プラトニックラブ。
いいね、感想大変励みになっています!読んでくださって本当にありがとうございます。
2024.11.27 無事本編完結しました。感謝。
最終章投稿後、第四章 3.5話を追記しています。
(この回は箸休めのようなものなので、読まなくても次の章に差し支えはないです。)
番外編は、2人の高校時代のお話。

【完結】ぎゅって抱っこして
かずえ
BL
幼児教育学科の短大に通う村瀬一太。訳あって普通の高校に通えなかったため、働いて貯めたお金で二年間だけでもと大学に入学してみたが、学費と生活費を稼ぎつつ学校に通うのは、考えていたよりも厳しい……。
でも、頼れる者は誰もいない。
自分で頑張らなきゃ。
本気なら何でもできるはず。
でも、ある日、金持ちの坊っちゃんと心の中で呼んでいた松島晃に苦手なピアノの課題で助けてもらってから、どうにも自分の心がコントロールできなくなって……。

美人に告白されたがまたいつもの嫌がらせかと思ったので適当にOKした
亜桜黄身
BL
俺の学校では俺に付き合ってほしいと言う罰ゲームが流行ってる。
カースト底辺の卑屈くんがカースト頂点の強気ド美人敬語攻めと付き合う話。
(悪役モブ♀が出てきます)
(他サイトに2021年〜掲載済)
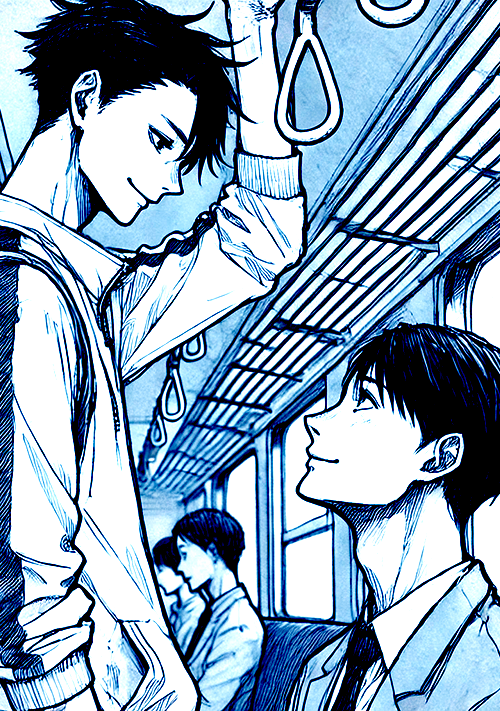
たまにはゆっくり、歩きませんか?
隠岐 旅雨
BL
大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。
よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。
世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

告白ゲームの攻略対象にされたので面倒くさい奴になって嫌われることにした
雨宮里玖
BL
《あらすじ》
昼休みに乃木は、イケメン三人の話に聞き耳を立てていた。そこで「それぞれが最初にぶつかった奴を口説いて告白する。それで一番早く告白オッケーもらえた奴が勝ち」という告白ゲームをする話を聞いた。
その直後、乃木は三人のうちで一番のモテ男・早坂とぶつかってしまった。
その日の放課後から早坂は乃木にぐいぐい近づいてきて——。
早坂(18)モッテモテのイケメン帰国子女。勉強運動なんでもできる。物静か。
乃木(18)普通の高校三年生。
波田野(17)早坂の友人。
蓑島(17)早坂の友人。
石井(18)乃木の友人。

モテる兄貴を持つと……(三人称改訂版)
夏目碧央
BL
兄、海斗(かいと)と同じ高校に入学した城崎岳斗(きのさきやまと)は、兄がモテるがゆえに様々な苦難に遭う。だが、カッコよくて優しい兄を実は自慢に思っている。兄は弟が大好きで、少々過保護気味。
ある日、岳斗は両親の血液型と自分の血液型がおかしい事に気づく。海斗は「覚えてないのか?」と驚いた様子。岳斗は何を忘れているのか?一体どんな秘密が?

後輩に嫌われたと思った先輩と その先輩から突然ブロックされた後輩との、その後の話し…
まゆゆ
BL
澄 真広 (スミ マヒロ) は、高校三年の卒業式の日から。
5年に渡って拗らせた恋を抱えていた。
相手は、後輩の久元 朱 (クモト シュウ) 5年前の卒業式の日、想いを告げるか迷いながら待って居たが、シュウは現れず。振られたと思い込む。
一方で、シュウは、澄が急に自分をブロックしてきた事にショックを受ける。
唯一自分を、励ましてくれた先輩からのブロックを時折思い出しては、辛くなっていた。
それは、澄も同じであの日、来てくれたら今とは違っていたはずで仮に振られたとしても、ここまで拗らせることもなかったと考えていた。
そんな5年後の今、シュウは住み込み先で失敗して追い出された途方に暮れていた。
そこへ社会人となっていた澄と再会する。
果たして5年越しの恋は、動き出すのか?
表紙のイラストは、Daysさんで作らせていただきました。

夢では溺愛騎士、現実ではただのクラスメイト
春音優月
BL
真面目でおとなしい性格の藤村歩夢は、武士と呼ばれているクラスメイトの大谷虎太郎に密かに片想いしている。
クラスではほとんど会話も交わさないのに、なぜか毎晩歩夢の夢に出てくる虎太郎。しかも夢の中での虎太郎は、歩夢を守る騎士で恋人だった。
夢では溺愛騎士、現実ではただのクラスメイト。夢と現実が交錯する片想いの行方は――。
2024.02.23〜02.27
イラスト:かもねさま
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















