お気に入りに追加
32
あなたにおすすめの小説

性奴隷を飼ったのに
お小遣い月3万
ファンタジー
10年前に俺は日本から異世界に転移して来た。
異世界に転移して来たばかりの頃、辿り着いた冒険者ギルドで勇者認定されて、魔王を討伐したら家族の元に帰れるのかな、っと思って必死になって魔王を討伐したけど、日本には帰れなかった。
異世界に来てから10年の月日が流れてしまった。俺は魔王討伐の報酬として特別公爵になっていた。ちなみに領地も貰っている。
自分の領地では奴隷は禁止していた。
奴隷を売買している商人がいるというタレコミがあって、俺は出向いた。
そして1人の奴隷少女と出会った。
彼女は、お風呂にも入れられていなくて、道路に落ちている軍手のように汚かった。
彼女は幼いエルフだった。
それに魔力が使えないように処理されていた。
そんな彼女を故郷に帰すためにエルフの村へ連れて行った。
でもエルフの村は魔力が使えない少女を引き取ってくれなかった。それどころか魔力が無いエルフは処分する掟になっているらしい。
俺の所有物であるなら彼女は処分しない、と村長が言うから俺はエルフの女の子を飼うことになった。
孤児になった魔力も無いエルフの女の子。年齢は14歳。
エルフの女の子を見捨てるなんて出来なかった。だから、この世界で彼女が生きていけるように育成することに決めた。
※エルフの少女以外にもヒロインは登場する予定でございます。
※帰る場所を無くした女の子が、美しくて強い女性に成長する物語です。

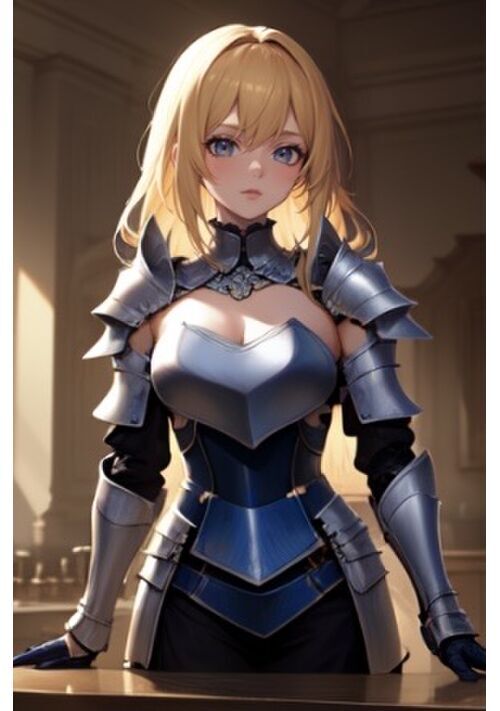
【R18】童貞のまま転生し悪魔になったけど、エロ女騎士を救ったら筆下ろしを手伝ってくれる契約をしてくれた。
飼猫タマ
ファンタジー
訳あって、冒険者をしている没落騎士の娘、アナ·アナシア。
ダンジョン探索中、フロアーボスの付き人悪魔Bに捕まり、恥辱を受けていた。
そんな折、そのダンジョンのフロアーボスである、残虐で鬼畜だと巷で噂の悪魔Aが復活してしまい、アナ·アナシアは死を覚悟する。
しかし、その悪魔は違う意味で悪魔らしくなかった。
自分の前世は人間だったと言い張り、自分は童貞で、SEXさせてくれたらアナ·アナシアを殺さないと言う。
アナ·アナシアは殺さない為に、童貞チェリーボーイの悪魔Aの筆下ろしをする契約をしたのだった!

大好きな彼女を学校一のイケメンに寝取られた。そしたら陰キャの僕が突然モテ始めた件について
ねんごろ
恋愛
僕の大好きな彼女が寝取られた。学校一のイケメンに……
しかし、それはまだ始まりに過ぎなかったのだ。
NTRは始まりでしか、なかったのだ……

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました
フルーツパフェ
大衆娯楽
とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。
曰く、全校生徒はパンツを履くこと。
生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?
史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。

アリスと女王
ちな
ファンタジー
迷い込んだ謎の森。何故かその森では“ アリス”と呼ばれ、“蜜”を求める動物たちの餌食に!
謎の青年に導かれながら“アリス”は森の秘密を知る物語──
クリ責め中心のファンタジーえろ小説!ちっちゃなクリを吊ったり舐めたり叩いたりして、発展途上の“ アリス“をゆっくりたっぷり調教しちゃいます♡通常では有り得ない責め苦に喘ぐかわいいアリスを存分に堪能してください♡
☆その他タグ:ロリ/クリ責め/股縄/鬼畜/凌辱/アナル/浣腸/三角木馬/拘束/スパンキング/羞恥/異種姦/折檻/快楽拷問/強制絶頂/コブ渡り/クンニ/☆
※完結しました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















