51 / 178
陳蔡之厄黒炎山(黒炎山での災難)
049:狐死首丘(七)
しおりを挟む
「これは……うっ、なんだ!? 地面から翳炎が……」
「翳炎の力を返せって言ってたけど……まず先にこの黒炎山の中で燃えているお前の力を先に戻してやるよ!」
地面からあふれ出す翳炎の力が黒冥翳魔の体を包み込む。しかし、ほどなくして黒冥翳魔の右手首がぼろりと落ちた。次いで左手首、足も綻びはじめてじきに立っていることすらできずに膝をつく。
本来ならば彼が欲しがっている力そのものだ、喜びこそすれ困ることは何もなかっただろう。しかし、いまの黒冥翳魔は実体がなく死体に宿って動いている存在だ。受け止められる力にも限りがある。どうやら凰黎の読みは当たったらしい。
それでも、器が壊れるだけで本体は簡単には消えることはないのだろうが。
「やってくれたな……! 許さないぞ!」
「許さないも何も、力を返せっていって殴り掛かってきたのはお前だろう。簡単に返せないことはさっき話した。それでも返せっていうなら俺は抵抗するだけだ。俺には俺の人生があるし、お前に好き勝手にできるもんじゃないからな」
「くそっ……!」
黒冥翳魔が煬鳳を睨む。既に崩れつつある体のため、煬鳳に飛び掛かることもできないが、それでも瞳の中の怒りは消えてはいない。
呪符とは本来呪文を唱えて術を使うべきところを、あらかじめ呪符に記すことでその手順を使用時に簡略化することが可能となる。先ほど煬鳳が使った呪符もごく一般的な呪文のひとつだが、あらかじめ霊力を込めてあるので、いざという時に発動に使うだけの最小限の霊力のみで、手早く術を発動させることが可能なのだ。
できるだけ使用時の負担が少ないようにと凰黎が考えてくれた作戦だったが、翳炎の力が満ちたこの黒炎山において、この作戦はとても効果的だった。お陰で煬鳳は倒れることもなく、次の呪符を使うことができるのだから。
「そろそろ頃合いか」
煬鳳はもう一枚の呪符を取り出すと剣訣を按ずる。体を失えば黒冥翳魔もさほど強力な力を行使することはできないだろう。捕まえて五行盟に渡すことができれば、煬鳳への風当たりも弱まるかもしれない。
「黒冥翳魔! 私の体を使うがいい!」
突然の声に煬鳳たちは驚いて振り返る。足を引きずりながら走ってきたのは、先ほどまで小黄と遊んでいた、彩藍方の兄弟子、彩菫青だ。その後ろからは彩藍方が追いかけている。
「師兄! 止めるんだ!」
「煩い! お前に分かるか! あの噴火によって私の足は使い物にならなくなってしまったんだ! もう二度と戦うことができない! こんな理不尽なことがあるか!? 私は一番だったんだぞ!? なのに、いまとなっては戦いの場に出ることすら許されず、憐憫の目を向けられながら足を引きずって子供の相手をすることくらいしかできない! こんな世界くそくらえだ! 全て無くなってしまえばいい! だから私は、黒冥翳魔にこの体を捧げて存分に全てを破壊して貰うんだ!」
あまりの剣幕に、みな呆然として立ち尽くしてしまった。当の黒冥翳魔ですら一瞬何が起きたのか理解できず、反応するまでしばらくかかったほどだ。
しかし、すぐさま自分の体がもう持たないと見るや否や、彩菫青に向き直り「良いのか? 遠慮はしないぞ」と問いかける。
「師兄! 馬鹿なことは止すんだ! それがどういうことをもたらすのか、分かってるだろ!?」
彩藍方の言葉を受け、彩菫青の顔からは一切の表情が消えた。次の瞬間薄く微笑みを浮かべると、大きな声で叫んだ。
「分かってるから、喜んで差し出すんだよ!!」
彩菫青は黒冥翳魔に向き直り、迎え入れるように手を広げた。
黒い熱風があたりに吹き荒れる。その風に煽られて危うく煬鳳はよろけかけそうになった。そんな煬鳳を支えてくれたのは凰黎の腕だ。
「煬鳳、あれを」
凰黎の視線の先に黒冥翳魔がいる。
もうほとんど上半身しか残っていなかった黒冥翳魔だったが、炎の中で何か呪文を唱え、赤い瞳が怪しく光った。
「気に入った」
言い終えた黒冥翳魔の体がくすんだ色へと変化して、灰のようにぼろぼろと崩れ落ちる。代わりに彩菫青の手が荒ぶる炎に向けられて、吹き荒れる翳炎を吸収した。
――どうやら彩菫青の体に乗り換えることに成功してしまったらしい。
にやりと笑った彩菫青の体は、まだ朱く輝いている。彩菫青――いや、黒冥翳魔はその手を空に掲げ、先ほどよりも二回り大きな炎の渦を空に作り出した。
咄嗟に前に出た凰黎が、神侯で防御陣を展開させる。堪らず煬鳳は「凰黎!」と叫んだが、次に起こった衝撃があまりにも凄まじくて目を開けていられなかった。
「黒冥翳魔は去ったようですね」
「凰黎!?」
凰黎の声が間近で聞こえる。その声を開くや否や、煬鳳は目を開いた。すぐさま凰黎を探そうとしたが、抱きしめているのが凰黎であることに気づいて煬鳳はほっと胸をなでおろす。しかし、凰黎の視線は一瞬だけ煬鳳を見て細められたあと、すぐに煬鳳たちの前にいる巨大なものに向けられた。
「なんだ、あれ!?」
目の前にいるのは石の巨人だ。古今東西そんなけったいなものを見たのは生まれて初めてのことだった。恐らくはこの巨人が、あの炎の渦を防いでくれたのだ。
煬鳳は凰黎の腕の中から岩の巨人をまじまじと見上げる。
「恐らく、彩鉱門の鉄鉱力士でしょう」
「なんだそりゃ!?」
「金行使いである彼らは、鉱物の声を聞き、呼びかける力を持っています。あれは仙人たちが使う宝器を模したものなのだと思います」
彩鉱門は五十年近く前に五行盟を始めとする他の門派の前から姿を消した。当時の蓬静嶺嶺主は彩鉱門の掌門に相談を打ち明けられ、彩鉱門の門弟たちが脱出するのを手伝ったそうだ。それで、公にはできないものの、いまでも蓬静嶺と彩鉱門とは内密に交流を続けている。だから、これは彼らと交流のある蓬静嶺と一部の門派しか知らないことなのだと凰黎は言う。
「あーほら、彩鉱門の門辺や中庭に大きな石が沢山置いてあっただろ? あれ全部、実は鉄鉱力士なんだ。非常事態にすぐに動かせるようにしてるんだぜ」
黒冥翳魔の去ったあとを彩藍方は見ている。
「しっかし、まさか師兄があんなことすると思わなかったよ……」
溜め息交じりに肩を落としながらそう呟いた。
彩鉱門に戻ったあと、彩藍方は煬鳳たちと共に掌門に彩菫青がどうなったかを包み隠さず話した。変に何か言い訳をしても、却って誤解を生むことになったら厄介だと思ったのだ。ただでさえ五行盟とは少し拗れかけている。ここで彩鉱門とも拗れるのは避けたかった。
――とはいっても、彩菫青がああなってしまった以上、拗れずに終わるかも不安だった。
彩菫青が黒冥翳魔に体を明け渡してしまったことを知り、彩鉱門の掌門は悲しむよりも彼の不甲斐なさを嘆いた。
そもそも彩菫青は掌門の息子であり、かつてはもっとも有能な弟子であったのだ。彩藍方が彩鉱門に助けられ、掌門に引き取られる以前は足の怪我もなく素晴らしい実力を持っていたのだという。
ただ、少し自分を過信しすぎるところ、向こう見ずなところがあって、それが運悪く噴火の際に発揮されてしまった。黒炎山の噴火のさなか、彼は掌門が止めるのも聞かず、火口近くまで様子を見に行ったのだ。その結果、彩菫青は燃え盛る岩の下敷きになり、生きるか死ぬかの瀬戸際のさなかで弟子たちに助けられた。
それからの彼がどうなったかは、煬鳳たちが見たとおりだ。
以前は周囲の期待を一身に受けていた彼が、二度とその高みに登ることはできなくなってしまった。噴火から十五年経ち、燻っていた不満が爆発してしまったのだろう。
「息子には気を使いすぎるほど気を使ったつもりでしたが、却ってそれが良くない結果に繋がったのか……。いや、元々調子に乗りやすく、自信過剰な部分もありましたから、これは必然の運命であったのやもしれませんな」
恐らく彩菫青が戻ることは二度とないだろう。
別れの言葉もなかった息子を想う掌門の横顔は寂し気だった。
「翳炎の力を返せって言ってたけど……まず先にこの黒炎山の中で燃えているお前の力を先に戻してやるよ!」
地面からあふれ出す翳炎の力が黒冥翳魔の体を包み込む。しかし、ほどなくして黒冥翳魔の右手首がぼろりと落ちた。次いで左手首、足も綻びはじめてじきに立っていることすらできずに膝をつく。
本来ならば彼が欲しがっている力そのものだ、喜びこそすれ困ることは何もなかっただろう。しかし、いまの黒冥翳魔は実体がなく死体に宿って動いている存在だ。受け止められる力にも限りがある。どうやら凰黎の読みは当たったらしい。
それでも、器が壊れるだけで本体は簡単には消えることはないのだろうが。
「やってくれたな……! 許さないぞ!」
「許さないも何も、力を返せっていって殴り掛かってきたのはお前だろう。簡単に返せないことはさっき話した。それでも返せっていうなら俺は抵抗するだけだ。俺には俺の人生があるし、お前に好き勝手にできるもんじゃないからな」
「くそっ……!」
黒冥翳魔が煬鳳を睨む。既に崩れつつある体のため、煬鳳に飛び掛かることもできないが、それでも瞳の中の怒りは消えてはいない。
呪符とは本来呪文を唱えて術を使うべきところを、あらかじめ呪符に記すことでその手順を使用時に簡略化することが可能となる。先ほど煬鳳が使った呪符もごく一般的な呪文のひとつだが、あらかじめ霊力を込めてあるので、いざという時に発動に使うだけの最小限の霊力のみで、手早く術を発動させることが可能なのだ。
できるだけ使用時の負担が少ないようにと凰黎が考えてくれた作戦だったが、翳炎の力が満ちたこの黒炎山において、この作戦はとても効果的だった。お陰で煬鳳は倒れることもなく、次の呪符を使うことができるのだから。
「そろそろ頃合いか」
煬鳳はもう一枚の呪符を取り出すと剣訣を按ずる。体を失えば黒冥翳魔もさほど強力な力を行使することはできないだろう。捕まえて五行盟に渡すことができれば、煬鳳への風当たりも弱まるかもしれない。
「黒冥翳魔! 私の体を使うがいい!」
突然の声に煬鳳たちは驚いて振り返る。足を引きずりながら走ってきたのは、先ほどまで小黄と遊んでいた、彩藍方の兄弟子、彩菫青だ。その後ろからは彩藍方が追いかけている。
「師兄! 止めるんだ!」
「煩い! お前に分かるか! あの噴火によって私の足は使い物にならなくなってしまったんだ! もう二度と戦うことができない! こんな理不尽なことがあるか!? 私は一番だったんだぞ!? なのに、いまとなっては戦いの場に出ることすら許されず、憐憫の目を向けられながら足を引きずって子供の相手をすることくらいしかできない! こんな世界くそくらえだ! 全て無くなってしまえばいい! だから私は、黒冥翳魔にこの体を捧げて存分に全てを破壊して貰うんだ!」
あまりの剣幕に、みな呆然として立ち尽くしてしまった。当の黒冥翳魔ですら一瞬何が起きたのか理解できず、反応するまでしばらくかかったほどだ。
しかし、すぐさま自分の体がもう持たないと見るや否や、彩菫青に向き直り「良いのか? 遠慮はしないぞ」と問いかける。
「師兄! 馬鹿なことは止すんだ! それがどういうことをもたらすのか、分かってるだろ!?」
彩藍方の言葉を受け、彩菫青の顔からは一切の表情が消えた。次の瞬間薄く微笑みを浮かべると、大きな声で叫んだ。
「分かってるから、喜んで差し出すんだよ!!」
彩菫青は黒冥翳魔に向き直り、迎え入れるように手を広げた。
黒い熱風があたりに吹き荒れる。その風に煽られて危うく煬鳳はよろけかけそうになった。そんな煬鳳を支えてくれたのは凰黎の腕だ。
「煬鳳、あれを」
凰黎の視線の先に黒冥翳魔がいる。
もうほとんど上半身しか残っていなかった黒冥翳魔だったが、炎の中で何か呪文を唱え、赤い瞳が怪しく光った。
「気に入った」
言い終えた黒冥翳魔の体がくすんだ色へと変化して、灰のようにぼろぼろと崩れ落ちる。代わりに彩菫青の手が荒ぶる炎に向けられて、吹き荒れる翳炎を吸収した。
――どうやら彩菫青の体に乗り換えることに成功してしまったらしい。
にやりと笑った彩菫青の体は、まだ朱く輝いている。彩菫青――いや、黒冥翳魔はその手を空に掲げ、先ほどよりも二回り大きな炎の渦を空に作り出した。
咄嗟に前に出た凰黎が、神侯で防御陣を展開させる。堪らず煬鳳は「凰黎!」と叫んだが、次に起こった衝撃があまりにも凄まじくて目を開けていられなかった。
「黒冥翳魔は去ったようですね」
「凰黎!?」
凰黎の声が間近で聞こえる。その声を開くや否や、煬鳳は目を開いた。すぐさま凰黎を探そうとしたが、抱きしめているのが凰黎であることに気づいて煬鳳はほっと胸をなでおろす。しかし、凰黎の視線は一瞬だけ煬鳳を見て細められたあと、すぐに煬鳳たちの前にいる巨大なものに向けられた。
「なんだ、あれ!?」
目の前にいるのは石の巨人だ。古今東西そんなけったいなものを見たのは生まれて初めてのことだった。恐らくはこの巨人が、あの炎の渦を防いでくれたのだ。
煬鳳は凰黎の腕の中から岩の巨人をまじまじと見上げる。
「恐らく、彩鉱門の鉄鉱力士でしょう」
「なんだそりゃ!?」
「金行使いである彼らは、鉱物の声を聞き、呼びかける力を持っています。あれは仙人たちが使う宝器を模したものなのだと思います」
彩鉱門は五十年近く前に五行盟を始めとする他の門派の前から姿を消した。当時の蓬静嶺嶺主は彩鉱門の掌門に相談を打ち明けられ、彩鉱門の門弟たちが脱出するのを手伝ったそうだ。それで、公にはできないものの、いまでも蓬静嶺と彩鉱門とは内密に交流を続けている。だから、これは彼らと交流のある蓬静嶺と一部の門派しか知らないことなのだと凰黎は言う。
「あーほら、彩鉱門の門辺や中庭に大きな石が沢山置いてあっただろ? あれ全部、実は鉄鉱力士なんだ。非常事態にすぐに動かせるようにしてるんだぜ」
黒冥翳魔の去ったあとを彩藍方は見ている。
「しっかし、まさか師兄があんなことすると思わなかったよ……」
溜め息交じりに肩を落としながらそう呟いた。
彩鉱門に戻ったあと、彩藍方は煬鳳たちと共に掌門に彩菫青がどうなったかを包み隠さず話した。変に何か言い訳をしても、却って誤解を生むことになったら厄介だと思ったのだ。ただでさえ五行盟とは少し拗れかけている。ここで彩鉱門とも拗れるのは避けたかった。
――とはいっても、彩菫青がああなってしまった以上、拗れずに終わるかも不安だった。
彩菫青が黒冥翳魔に体を明け渡してしまったことを知り、彩鉱門の掌門は悲しむよりも彼の不甲斐なさを嘆いた。
そもそも彩菫青は掌門の息子であり、かつてはもっとも有能な弟子であったのだ。彩藍方が彩鉱門に助けられ、掌門に引き取られる以前は足の怪我もなく素晴らしい実力を持っていたのだという。
ただ、少し自分を過信しすぎるところ、向こう見ずなところがあって、それが運悪く噴火の際に発揮されてしまった。黒炎山の噴火のさなか、彼は掌門が止めるのも聞かず、火口近くまで様子を見に行ったのだ。その結果、彩菫青は燃え盛る岩の下敷きになり、生きるか死ぬかの瀬戸際のさなかで弟子たちに助けられた。
それからの彼がどうなったかは、煬鳳たちが見たとおりだ。
以前は周囲の期待を一身に受けていた彼が、二度とその高みに登ることはできなくなってしまった。噴火から十五年経ち、燻っていた不満が爆発してしまったのだろう。
「息子には気を使いすぎるほど気を使ったつもりでしたが、却ってそれが良くない結果に繋がったのか……。いや、元々調子に乗りやすく、自信過剰な部分もありましたから、これは必然の運命であったのやもしれませんな」
恐らく彩菫青が戻ることは二度とないだろう。
別れの言葉もなかった息子を想う掌門の横顔は寂し気だった。
10
お気に入りに追加
116
あなたにおすすめの小説

【完結・BL】俺をフッた初恋相手が、転勤して上司になったんだが?【先輩×後輩】
彩華
BL
『俺、そんな目でお前のこと見れない』
高校一年の冬。俺の初恋は、見事に玉砕した。
その後、俺は見事にDTのまま。あっという間に25になり。何の変化もないまま、ごくごくありふれたサラリーマンになった俺。
そんな俺の前に、運命の悪戯か。再び初恋相手は現れて────!?

好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

Ωの不幸は蜜の味
grotta
BL
俺はΩだけどαとつがいになることが出来ない。うなじに火傷を負ってフェロモン受容機能が損なわれたから噛まれてもつがいになれないのだ――。
Ωの川西望はこれまで不幸な恋ばかりしてきた。
そんな自分でも良いと言ってくれた相手と結婚することになるも、直前で婚約は破棄される。
何もかも諦めかけた時、望に同居を持ちかけてきたのはマンションのオーナーである北条雪哉だった。
6千文字程度のショートショート。
思いついてダダっと書いたので設定ゆるいです。
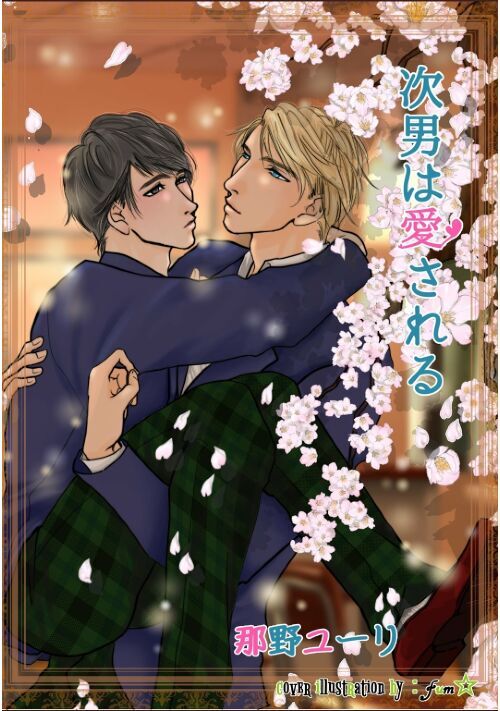
次男は愛される
那野ユーリ
BL
ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男
佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。
素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡
無断転載は厳禁です。
【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】
12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。
近況ボードをご覧下さい。


【完結】I adore you
ひつじのめい
BL
幼馴染みの蒼はルックスはモテる要素しかないのに、性格まで良くて羨ましく思いながらも夏樹は蒼の事を1番の友達だと思っていた。
そんな時、夏樹に彼女が出来た事が引き金となり2人の関係に変化が訪れる。
※小説家になろうさんでも公開しているものを修正しています。

【完結】愛執 ~愛されたい子供を拾って溺愛したのは邪神でした~
綾雅(ヤンデレ攻略対象、電子書籍化)
BL
「なんだ、お前。鎖で繋がれてるのかよ! ひでぇな」
洞窟の神殿に鎖で繋がれた子供は、愛情も温もりも知らずに育った。
子供が欲しかったのは、自分を抱き締めてくれる腕――誰も与えてくれない温もりをくれたのは、人間ではなくて邪神。人間に害をなすとされた破壊神は、純粋な子供に絆され、子供に名をつけて溺愛し始める。
人のフリを長く続けたが愛情を理解できなかった破壊神と、初めての愛情を貪欲に欲しがる物知らぬ子供。愛を知らぬ者同士が徐々に惹かれ合う、ひたすら甘くて切ない恋物語。
「僕ね、セティのこと大好きだよ」
【注意事項】BL、R15、性的描写あり(※印)
【重複投稿】アルファポリス、カクヨム、小説家になろう、エブリスタ
【完結】2021/9/13
※2020/11/01 エブリスタ BLカテゴリー6位
※2021/09/09 エブリスタ、BLカテゴリー2位

虐げられている魔術師少年、悪魔召喚に成功したところ国家転覆にも成功する
あかのゆりこ
BL
主人公のグレン・クランストンは天才魔術師だ。ある日、失われた魔術の復活に成功し、悪魔を召喚する。その悪魔は愛と性の悪魔「ドーヴィ」と名乗り、グレンに契約の代償としてまさかの「口づけ」を提示してきた。
領民を守るため、王家に囚われた姉を救うため、グレンは致し方なく自分の唇(もちろん未使用)を差し出すことになる。
***
王家に虐げられて不遇な立場のトラウマ持ち不幸属性主人公がスパダリ系悪魔に溺愛されて幸せになるコメディの皮を被ったそこそこシリアスなお話です。
・ハピエン
・CP左右固定(リバありません)
・三角関係及び当て馬キャラなし(相手違いありません)
です。
べろちゅーすらないキスだけの健全ピュアピュアなお付き合いをお楽しみください。
***
2024.10.18 第二章開幕にあたり、第一章の2話~3話の間に加筆を行いました。小数点付きの話が追加分ですが、別に読まなくても問題はありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















