5 / 6
8月15日
しおりを挟む
ちょうど腕時計が十二時を指したとき、ラジオのノイズが一段と酷くなった。努さんは腹ただしげにラジオを切り、
「山道は電波が悪いんだな…」
と独り言のように呟いていた。
その一連の動作を眺めながら、僕は不意にある事を思い出した。
「ねぇ、努さん。その事故があったのって、今僕と努さんが使ってる道じゃあないよね?」
努さんの顔が強張るのを、僕ははっきりと見た。そのはずなのに、もう一度しっかり見てみるとその顔は、いつもの努さんの顔だった。
「さぁ?俺もあまり詳しくないからわかんないな。」
努さんの声は、顔と同じでいつもの彼のままだった。
それからしばらくは、また二人とも黙ったままだった。助手席から山道を眺めながら、僕はまた三年前の事故について考え始めていた。
努さんは、この話を避けているんじゃないだろうか…。避けているとして、何故だろうか?何か僕に隠しておきたい事があるのだろうか?
そんな風に答えの出ない自問自答を繰り返していると、道を覆っていた木々が一瞬途切れて、月明かりが差した。
ちょうどその時だった、青白い明かりの中に、赤い影が見えたのは。
僕がとっさに振り返った時には、影はどこにも見えなかった。目の錯覚か何かとはとても思えないような鮮やかな赤だったのに、何故消えてしまったのだろう…。僕はそう思ったが、車が再び暗闇の中に入ってしまったため確認のしようがなかった。
「努さん、今何か赤いものが見えなかった?」
影のあったはずの方を向きながら僕がそう言っても、横からは相変わらずいつも通りの努さんの返事しか聞こえない。何かと見間違えたのだろうか…。気の無い努さんの返事からして、努さんには見えなかったのかもしれないし…。
悩む僕をよそに、車は低い音を立てながら山道を進んでいった。
ふと気がつくと、道路を走る音が増えているように感じた。何かが自分達の後ろを走っているのだろうか…、サイドミラー越しに後ろを見てみても何もない。そうこうしているうちにも、もう一つの低い音は確実に近づいているようだった。そしてついにその音は、正体がはっきりとわかるところまで近づいて来たのだ。
その音は、バイクのエンジン音だった。"バイク…?" そう意識した瞬間、今までの様々な事が繋がった。
三年前の事故、赤い影、さっきからずっと聞こえるエンジン音…。
ふと、僕は祖母の言葉を思い出した。
「お盆に死んだ人が帰ってくるっていうのは本当だって、そう思うようになったよ。」
嘘だろ…?じゃあこの音って…僕達を追っているものって…。
もう一度振り返ってみても、そこにはやはり道路と木立しか広がっていない。けれども音は益々近くなっている。たとえ耳を塞ぎこんでも、エンジン音は頭の中から聞こえているかのように段々と大きくなってゆく。
「ねぇ…努さんには聞こえてる…?」
できるだけ平静を装ってそう聞くと、
「いいや?」
という気の無い返事。…そうなのか?この音は僕にしか聞こえていないのか?だとしたら、きっと錯覚なんだ。良かった、これは現実のことじゃ……。
僕は、ある事に気づく。彼の、努さんの顔は、この音が聞こえない人間の顔ではなかった。無理に笑おうとしている口元、額からこぼれる冷や汗。そして何よりその目が、助けがそこにあると信じているかのように、必死に前だけを見ているその目が、彼の恐怖を表していた。
"この人は音が聞こえないんじゃない、聞こえないと自分に言い聞かせているんだ…" 反射的に僕はそう思った。
なら何故彼は、先程聞こえないふりを、知らないふりをしたのだろうか。そもそも何故アレが僕達を追ってくるのだろうか。…そんなこと今はどうでも良い。とにかくこの音から逃げなければいけない。
努さんも同じことを考えたのか、僕達を乗せた車は速度を上げて、凄まじい速さで山道を進んで行った。
ガードレールで車体をこすり、せり出た枝が窓を打っても、車は速度を落とすことはなかった。それなのに、音は更に近づいてくる。いくら速度を上げても、バイクの激しいエンジンの音は大きくなるばかりだ。
そう思っていた矢先、突然音が止んだ。理由は分からないが、逃げ切れたのだろうか?それとも、追いつかれた…?
それを考える暇は、僕達二人にはなかった。突然目の前に葉の茂った大木が姿を現した。
その刹那、僕達はハンドルを切るのもブレーキを踏むのも考えられなかった。
夜闇を引き裂くその音は、何かが壊れる音にも悲鳴にも聞こえた。
「山道は電波が悪いんだな…」
と独り言のように呟いていた。
その一連の動作を眺めながら、僕は不意にある事を思い出した。
「ねぇ、努さん。その事故があったのって、今僕と努さんが使ってる道じゃあないよね?」
努さんの顔が強張るのを、僕ははっきりと見た。そのはずなのに、もう一度しっかり見てみるとその顔は、いつもの努さんの顔だった。
「さぁ?俺もあまり詳しくないからわかんないな。」
努さんの声は、顔と同じでいつもの彼のままだった。
それからしばらくは、また二人とも黙ったままだった。助手席から山道を眺めながら、僕はまた三年前の事故について考え始めていた。
努さんは、この話を避けているんじゃないだろうか…。避けているとして、何故だろうか?何か僕に隠しておきたい事があるのだろうか?
そんな風に答えの出ない自問自答を繰り返していると、道を覆っていた木々が一瞬途切れて、月明かりが差した。
ちょうどその時だった、青白い明かりの中に、赤い影が見えたのは。
僕がとっさに振り返った時には、影はどこにも見えなかった。目の錯覚か何かとはとても思えないような鮮やかな赤だったのに、何故消えてしまったのだろう…。僕はそう思ったが、車が再び暗闇の中に入ってしまったため確認のしようがなかった。
「努さん、今何か赤いものが見えなかった?」
影のあったはずの方を向きながら僕がそう言っても、横からは相変わらずいつも通りの努さんの返事しか聞こえない。何かと見間違えたのだろうか…。気の無い努さんの返事からして、努さんには見えなかったのかもしれないし…。
悩む僕をよそに、車は低い音を立てながら山道を進んでいった。
ふと気がつくと、道路を走る音が増えているように感じた。何かが自分達の後ろを走っているのだろうか…、サイドミラー越しに後ろを見てみても何もない。そうこうしているうちにも、もう一つの低い音は確実に近づいているようだった。そしてついにその音は、正体がはっきりとわかるところまで近づいて来たのだ。
その音は、バイクのエンジン音だった。"バイク…?" そう意識した瞬間、今までの様々な事が繋がった。
三年前の事故、赤い影、さっきからずっと聞こえるエンジン音…。
ふと、僕は祖母の言葉を思い出した。
「お盆に死んだ人が帰ってくるっていうのは本当だって、そう思うようになったよ。」
嘘だろ…?じゃあこの音って…僕達を追っているものって…。
もう一度振り返ってみても、そこにはやはり道路と木立しか広がっていない。けれども音は益々近くなっている。たとえ耳を塞ぎこんでも、エンジン音は頭の中から聞こえているかのように段々と大きくなってゆく。
「ねぇ…努さんには聞こえてる…?」
できるだけ平静を装ってそう聞くと、
「いいや?」
という気の無い返事。…そうなのか?この音は僕にしか聞こえていないのか?だとしたら、きっと錯覚なんだ。良かった、これは現実のことじゃ……。
僕は、ある事に気づく。彼の、努さんの顔は、この音が聞こえない人間の顔ではなかった。無理に笑おうとしている口元、額からこぼれる冷や汗。そして何よりその目が、助けがそこにあると信じているかのように、必死に前だけを見ているその目が、彼の恐怖を表していた。
"この人は音が聞こえないんじゃない、聞こえないと自分に言い聞かせているんだ…" 反射的に僕はそう思った。
なら何故彼は、先程聞こえないふりを、知らないふりをしたのだろうか。そもそも何故アレが僕達を追ってくるのだろうか。…そんなこと今はどうでも良い。とにかくこの音から逃げなければいけない。
努さんも同じことを考えたのか、僕達を乗せた車は速度を上げて、凄まじい速さで山道を進んで行った。
ガードレールで車体をこすり、せり出た枝が窓を打っても、車は速度を落とすことはなかった。それなのに、音は更に近づいてくる。いくら速度を上げても、バイクの激しいエンジンの音は大きくなるばかりだ。
そう思っていた矢先、突然音が止んだ。理由は分からないが、逃げ切れたのだろうか?それとも、追いつかれた…?
それを考える暇は、僕達二人にはなかった。突然目の前に葉の茂った大木が姿を現した。
その刹那、僕達はハンドルを切るのもブレーキを踏むのも考えられなかった。
夜闇を引き裂くその音は、何かが壊れる音にも悲鳴にも聞こえた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説




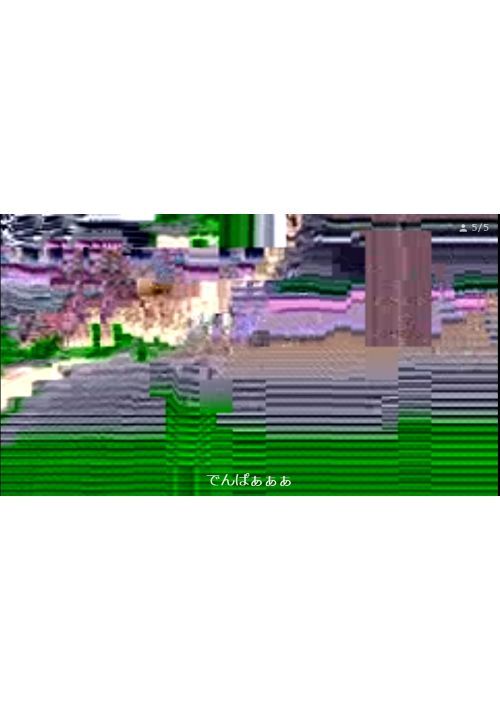


カゲムシ
倉澤 環(タマッキン)
ホラー
幼いころ、陰口を言う母の口から不気味な蟲が這い出てくるのを見た男。
それから男はその蟲におびえながら生きていく。
そんな中、偶然出会った女性は、男が唯一心を許せる「蟲を吐かない女性」だった。
徐々に親しくなり、心を奪われていく男。
しかし、清らかな女性にも蟲は襲いかかる。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















