2 / 5
2
しおりを挟む
翌日。夜の7時に、駅のローターリーにいた。一昨日も訪れた場所だ。この駅で降りるのは二度目だったが、通学途中の駅の一つで、アパートからそう遠い場所ではなかった。一臣の指定した場所は、またも同じ噴水の前だった。平日とあってか、帰路につく人々の足は速く、自分を気にとめる人はいないようだった。
待ち合わせは7時。一臣は遅れているようだった。ポケットの中でケータイに触れる。
だるい。それに悪寒がした。熱があるようだった。
今日、始業式には行かなかった。体が思うように動かず、そんな気にはなれなかったからだ。相変わらず、動くたび傷が痛かった。心なしか、酷くなっているようにすら思う。どうしていいかわからずに、ただ癒えるのを待つことしかできなかった。
食事も、一臣とホテルでしたのを最後に、なにも口にしていない。かろうじて水分だけはとっていたが、そうでなければ、この暑さだ。熱中症で今頃本当に死んでいる。
それほどまでに具合が悪くても、足は何故かここに来ることを選んだ。一臣に会いたかった。秘密を知りたいと思ったのだ。一人で家にいる間に思ったことは一つだ。
『秘密の共有』
なんと甘美的な響きだろう。
一臣に、死ぬことと、その理由を明かした自分。それは、胸の内に秘めて持って逝くだろうものだった。そして、秘密を教えてくれると言った一臣。それを聞いた時、何かが変わる予感がした。秘密だと言うからには、一臣の話も、誰にでもするような話ではないだろう。それならば、自分と一臣はお互いの秘密を交換し、共有する不思議な関係になる。体のつながりだけの、お金のつながりだけの関係ではなくなるということだ。それはとても魅力的だった。
しかし、一臣は待ち合わせの時間を三十分過ぎても現れなかった。ケータイも鳴らない。場所と時間を指定してきたのは一臣からで、三時を過ぎた頃にメールでのことだった。まさか、今更会いたくなくなったということはないだろうが、否定しきれないのも確かだった。自分だったら、こんな自殺志願者、放っておくだろう。
結局、あの夜提示された金を、自分は受け取った。それで終わりだったとしても、何ら問題はなかった。
それからしばらくして、時計が8時を指そうかというころ、ケータイが震えた。手にすると、一臣からの着信だった。通話ボタンを押すと、別れて以来の一臣の声が耳に飛び込んできた。
『よかった。出てくれた。』
『え?』
『ごめん。仕事がちょっと。もうすぐ着くけど、まだそこにいる?』
遅れた理由は、仕事がおしたらしかった。
『はい。』
『ごめんね。連絡もできなくて。暑いだろう?見えるところにコンビニあるよね。そこで待っててくれないか。もう、本当にすぐ着くから。』
言われて、視線を巡らすと、カフェとコンビニが並んで立っていた。一臣の言うコンビニとはおそらくそこだろう。
『わかりました。』
『ごめんね。じゃぁ。』
再度謝罪の言葉を残して、通話が切れる。
歩くも立っているのも辛かったから、本当はここから動きたくなかったが、言われたとおりにコンビニで待つことにした。そういえば、喉が渇いている。
水、買おう・・・。
レジで会計を済ませていると、一臣が現れた。
今日も、ワイシャツ姿だった。仕事だったと言うからには当然かも知れなかったが。
「ごめん。遅くなった。・・・なに買ったの?」
謝罪の言葉を口にしつつ、視線はレジ袋の中身を気にしたようだった。
「水。」
「そっか・・・。お腹空いたよね。ちょっと路駐してるから、急いでもらってもいい?」
路駐?車で来たのか。
一臣に腕を引かれ、よろめいた。
「っ・・・!」
「え?」
小さく漏れた悲鳴を、一臣は聞き逃さなかった。
「痛かった?」
びくりと体が竦む。一臣に与えられた傷ではあったが、そのことを悟られたくなかった。気に病んで欲しくなかったからだ。しかし、一臣は確信したようだった。
「ちょっと・・・。」
先ほどよりはゆっくりだったが、足は店の奥のトイレに向かって歩き出す。引きずられるようにして、個室に押し込まれた。
「お尻・・・痛いの?」
じ、っと視線を合わされる。否定したかったが、沈黙を肯定と受け取ったようだった。
「ごめん。ちょっと見ても良い?」
「や!駄目です!」
こんなところで?いや、それどころではない。情事の後でも前でもないのだ。秘部を見せるなんてとんでもない話だ。
「まだ、出血してる?」
ふるふると首を横に振る。
「すばる。見せて。」
再度強く言われ、観念した。
頷くと、ベルトを外され、ボタンを外され、ファスナーを下ろし、ズボンを腿まで下げられる。そして、くるりと後ろを向かされて、壁に手をつくように言われた。従うと、下着を下ろされる。両手で肉を掴まれ、左右に割られた。一臣が息をのむ気配がした。
「・・・ごめん。ちゃんと手当てしたつもりだったけど・・・。」
一臣は、状態を確認して、すぐに着衣を整えてくれた。
「とりあえず、車。停めておけないから移動しよう。」
一臣は、店を出ると、急ぎながらも気遣うようにして歩を進めた。送迎の車の列の端に、申し訳なさそうに白のインプレッサが停めてある。一臣は助手席のドアを開くと、乗るように言って、自分は運転席へと回った。乗り込むと、エンジンをかけ、すぐに出られるようにしつつ、ケータイを取り出した。どこかに電話し、ややあってから出ただろう相手と何かやりとりをする。頼むよ、と通話を終わらせると、タクシーが行きすぎるのを待って、車を発進させた。
いくつ目かの赤信号で、意を決して口を開いた。
「・・・どこに、行くんですか?」
車の中は居心地が悪い。どこに連れ去られるかわからない不安感と、逃げ出せない圧迫感がある。普段あまり車に乗らない自分には地の利がない。交差点ごとに地名を確認しているが、ここで一人下ろされたとして、帰れる自信がない。
「・・・病院。」
信号が青に変わる。交差点を右折して、車線を変える。
「病院って、こんな時間に?」
8時過ぎだ。普通の病院はもうとっくに閉まっている。
「すばる、熱あるでしょ。呼吸も速い。」
それはそうかも知れないが、救急指定に駆け込むほど悪くはない。
それ以前に、病院は困る。保険証を使いたくないからだ。そうなると、手持ちのお金も足りない。
「一臣さん・・・あの。困ります。僕なら大丈夫ですから・・・。」
「大丈夫かどうかは俺が決める。」
妙にはっきりとそう言い切ると、大通りから一本裏道に入った。少し進んだところに、四階建てのビルがある。一階部分が駐車場になっていて、一臣は慣れた様子でそこに車を停めた。入り口は通りに面していて、ここが目的の病院だとわかったが、その標榜に絶句した。
肛門科、消化器科、内科。普通、標榜というのは、その病院の医者が最も得意とする科を頭にのせるものだと聞いたことがある。と言うことはつまり、ここは尻を見せるための病院だと言うことだ。頭の中が、「嫌だ」の二文字で埋め尽くされる。一臣にされるのならまだしも、それ以外の人間にまで見られたくない。たとえ相手が医者でもだ。
一臣は、車から降りると助手席に回り、ドアを開けて降りるように言う。当然のように、足は固まって動けない。
「すばる。だだこねてる場合じゃない。」
口調が厳しい。
でも、だけど、だ。
「か、一臣さん・・・。保険証、使ったら親に知れる!ヤダよ!」
嫌な理由はそれだけではないが。
一臣は、ふーっとため息をついた。
「・・・知り合いの医者なんだ。大丈夫。誰にも知られないよ。」
知り合い・・・?
そう言われてしまうと、断る理由がなくなってしまう。
「すばる。」
再度促されて、しぶしぶ車から降りた。たったこれだけの動きが、傷に響く。立ち上がると、くらりとした。熱も上がっているのかも知れなかった。確かに、だだをこねている場合ではないような気がする。
手を引かれて連れて行かれたのは、正面の入り口ではなく、駐車場から出入りできる通用口だった。一臣はインターホンを押した。
ほどなくして、「はーい。」とスピーカーから声がした。男の声だ。
「俺だ。」と一臣が短く言うと、相手の方も「開いてるよ。」と返した。言われたとおり、ドアには鍵がかかっていなかった。一臣は、勝手知ったる様子で、中に入っていく。すぐに階段になっていて、どうやら二階が病院施設らしかった。夜の9時少し前。非常灯の明かりを頼りに、廊下を抜けて、院内を突っ切り、待合室に出る。ちょっと待ってて、と長いすに座らされた。
一臣は、壁際をなぞると、スイッチを入れた。広くはない待合室に明かりが点る。
スイッチの場所まで知っているとは、よほどここに出入りしたことがあるのだろう。なんのために・・・?疑問は、すぐに嫌な予感に変わった。もしかしなくても、自分と同じような理由で、急患を連れて来た過去があると言うことではないだろうか。自分の考えに、手をきつく握りしめた。17人目。自分には一臣が初めての相手だが、一臣にはそうでないことを思い知らされる。
「久しぶりだな。・・・葬式以来か?」
不意に、廊下から声をかけられた。野太い男の声だ。顔を上げると、背丈は一臣ほどの、どっしりと体格のいい男が、ポロシャツに白衣を羽織って立っていた。
「あぁ。あれ以来か・・・。久しぶり。榊。」
久しぶり?
「おまえ・・・まだ悪いあそび止めらんねーの?」
悪いあそびって、僕のことだろうか?と思う。白衣の男が、品定めでもするように見ていた。
「未成年じゃん。なにやってんの?犯罪だよー。ハンザイ。」
「ちが・・・。」
言いかけた口を、一臣が制した。
「わかってるよ。」
「わかってるなら、やめろ。バカが。」
さっきから聞いていると、どうやらこの医者・・・相当に口が悪い。いつもこうなんだろうか?それとも一臣が相手だから?
「・・・やめてもいいかと思ってるんだよ。・・・診てやってくれないか。」
一臣はため息混じりにいった。相手の乱暴な言葉に取り合うつもりはないらしかった。榊と呼ばれた男は、舌打ちすると、診察室の方へと歩いて行き、明かりをつけた。
「おまえの頼みだから、特別に診てやるんだからな。」
「わかってるよ。ちゃんと礼はする。」
おいで、と呼ばれて、おそるおそる診察室に足を踏み入れる。パソコンと書類の載ったデスクに、カーテンで仕切られたベッド。薬品棚。血圧計や身長体重計などがある、普通の診察室と同じように思えた。
「来な。ズボン腿まで下ろして、ベッドに上がって。尻こっち向けて、横向きに。」
指示されるが、緊張で足が竦む。一臣が手を引いた。たたらを踏みつつ、ベッドに上がる。
榊は、手袋をするとワゴンにいくつかの薬品を載せて、ベッドの足下に立った。
「じゃ、お尻見せようね。膝抱えて、お尻突き出すように体丸めて。」
言うなり、下着を下ろされそうになり、慌てて履き口のゴム部分を掴んでしまった。
「やることやっといて、今更恥ずかしいもないだろ。しょうがないな・・・ほら。」
腰のあたりに、大判のタオルを掛けられた。
「尻しか見ないから、パンツ下ろして。」
言いぐさに、一臣に目で訴えてみたが、一臣は小さく頷いただけだった。言われたとおりにしろということだ。仕方なく、下着を下ろした。
「はい。ごめんね~。」
腰を片手で押さえられ、尻を割り開かれる。恥ずかしさよりも、痛みの方が勝った。悲鳴をかみ殺す。
「痛そう。・・・やったのいつ?」
「一昨日の晩。」
「やりっぱなしかよ。」
忌々しげに、傷を指でなぞられる。
「一応手当はしたんだけどね。」
「これだけ深くちゃな。・・・縫うほどじゃない。けど、しばらく痛いぞ。炎症が酷い。」
縫う?たかが切れ痔ではないのか?そんな処置をするほどのこともあるのか。
今更ながらぞっとする。
「中も見るから。・・・暴れんなよ。」
「麻酔は!?」
一臣が慌てたように声を上げた。
「するよ。」
カチカチとワゴンの上で音がする。何かの準備をしているのだろうが、怖くてとても見られなかった。
「すばる、ちょっと我慢。」
背中と腰を押さえられた。次の瞬間、秘部に激痛が走る。
「っくぅ・・・。」
何かを入れられて、ぐるりとかき回された。それが抜けると、ひやりとした感覚と、ずきずきとした痛みが残る。
「麻酔効いたら中見るから。」
麻酔?今のがそうだったのだろうか。目尻に涙がにじんでいる。それを、そっと一臣が拭ってくれた。乱れた呼吸を背中をさすってなだめてくれる。
「薬が効けば楽になるからね。」
言われたとおり、痛みはだんだん遠くなっている。感覚が麻痺していくのがわかった。
カチャリ。
金属音に、なにをされるのかと思わず足下に目をやると、榊が見慣れない金属の器具を手にしたところだった。
「初めて?」
「?」
「肛門科。」
頷く。
「あっそ。覚えておきな。指突っ込まれて触診と、肛門鏡使って中見られるのセットだから。」
指を突っ込まれる、とはさっきのアレのことか。では肛門鏡というのはあの器具のことだろうか。くちばしのような形状にハンドルが付いている。
「これ、今から入れるんだよ。」
「えっ!?」
そんなものが入る?ただでさえ傷ついて痛い部分に?
思わず泣きそうな顔をしたのだと思う。一臣は眉根を寄せて苦笑すると、頭をぽんぽんと叩いた。
「あんまり脅かさないでやって。・・・普通の子なんだよ。」
「脅しじゃないだろ。・・・はい。力抜いてねー。」
ぐっと一瞬圧迫感があった。が、それ以外の感覚はない。麻酔のせいだろうか。恐れていた痛みはなかった。
「口で短く呼吸して。」
言われたとおり、はっはっと呼吸する。顎が上がった。
「出血痕あるな・・・生傷は無し。はい終わり。機械抜くよ。」
言われて、器具が抜かれたのがわかったが、感覚は全くなかった。麻酔の効果とはこれほどのものなのか。しばらくの間だろうが、体を苛んでいた痛みから解放されるのだろう。
榊はもう一度タオルをめくると、感覚のない秘部にまた何かしたようだった。
「解熱鎮痛剤入れて、炎症抑える薬塗ったから。しばらくすれば楽になるだろ。」
服を整えるように言われ、ほっとする。ベッドから降りるのを、一臣が手を添えて気遣ってくれた。
「メシ、食えてないんだろう。水分は?時間があるなら点滴一本入れてくか?」
榊の言葉に、一臣をうかがう。
「頼む。」
一臣は、どうやらそれも頼むことにしたらしかった。
「じゃぁ隣のベッドで横になってて。暑いな。ちょっとエアコンいじってくるわ。」
言い置いて、榊はどこかへ消えていった。
一臣に付き添われ、診察室の隣、処置室とプレートのかかった部屋に入った。ベッドが三台おいてある。入り口側のベッドに横になるよう言われ、仰向けに横になると、一臣はシャツのボタンとベルトを緩めてから、横にあった丸椅子に座った。
「ごめん。辛かったろう。」
辛かったようにも思うが、あえて首を横に振った。
「明日も学校だろう?早く帰してやるつもりだったんだけど。少し時間かかるね。・・・家に連絡入れておく?」
「あ・・・一人だから大丈夫・・・です。」
「一人、って?」
「アパートに一人で住んでるんです。」
家に連絡されるよりはマシ、とプライバシーを少し明かす。
「高校生なのに?」
「・・・家、居づらいから。」
答えると、一臣はあぁ、と頷いた。
そこに榊が点滴のパックを持って現れる。
「温度下げてきたから、涼しくなるだろ。一時間くらいか・・・。」
言いながら、点滴台にパックをセットし、準備をする。
「あーもー・・・。メシまだなんだよ俺。腹減ったわ。」
そんなことを言いながら、右腕の肘の内側をアルコール綿で消毒した。血管に針が刺さるのをじっと見つめる。
「珍しいね。」
「え?」
「男はたいがい見ないもんなんだけどね。針とか、血とか。」
そう言われると、そうかも知れない。
「そんなんだから悪い男に喰われたりするんだよ。」
腕に針が入るのを見ていただけで、そんなんだからと決めつけられ、むっとした。それに、一臣は悪い男のようには思えなかったし、喰われた覚えもない。悪い男というのなら、榊の口の方が余程悪かった。
「・・・いじめないでやってくれよ。ほんとに、普通の子なんだ。それ、何が入ってる?」
それ、と一臣が点滴のパックを指した。
「ブドウ糖とビタミンと抗生剤。」
見ればわかるだろ。藪医者。と榊が悪態をつく。
「抗生剤はわからないだろう。藪で悪かったな。」
え?
思わず一臣を見上げた。一瞬目が合う。が、すぐに反らされた。
「後で話すから。少し眠るといいよ。」
さら、と前髪を撫でられる。
「寝とけ。・・・俺はこいつと話があるからな。終わる頃見に来てやるから心配するな。」
榊は、こいつ、と一臣を指し、立つように促した。
「あ、メシ、買ってこさせるけど、食えるか?牛丼かコンビニだけど。」
振り返りざま、榊が言う。食欲は正直なかったが、答えないと出て行きそうになかった。
「なにか軽いもの・・・。」
「わかった。食べやすそうなもの買ってくるから。」
返事は一臣がした。
二人はそろって処置室を出て行った。
誰もいない夜の病院。ぽたり、ぽたりと落ちる点滴を見ているうちに、どうやら眠ったようだった。
人の気配に目を覚ます。目をやると、一臣が点滴の処理をしていた。慣れた手つきで針を抜き、一瞬あふれた血液を脱脂綿で拭き取ると、テープで止める。
点滴のパックにルートを巻き付けると、起きられる?と小首をかしげた。頷いて、ベッドから降りる。薬が効いたのか、傷の痛みは大分引いていた。
「おいで。サンドイッチとプリン買ってきた。」
連れられて、奥の廊下へと誘われる。途中、点滴のパックを廃棄物のゴミ箱に捨てる。関係者以外立ち入り禁止と書かれた扉を開けると階段があり、一臣は先に登るよう言った。登った先は、病院のそれとは雰囲気が違っていた。
「榊の家なんだよ。三階から上。」
なるほど。それで四階建てなのか。妙に納得していると、リビングへと通された。ソファーとテーブルが目に入る。二人は食事を終えたのだろう。レジ袋と、飲み物のグラスが二つ置かれていた。
「なに飲む?・・・あ、トイレ大丈夫?」
「あ。お願いします。」
こっちだよ、とトイレに案内される。一臣は、病院の中だけでなく、家の中のことも良く知っているようだった。
トイレから戻ると、テーブルの上はきれいに片付けられていた。代わりに、パッケージに包まれたサンドイッチと、プリンとお茶が置かれている。どうやらこれが今日の夕食というところだろう。ソファに座ると、居心地悪く腰が沈んだ。その横に一臣がやはり腰を沈める。向かいに、榊が座った。新しいグラスを持っている。
「ビール、開けて良いだろ?」
問いかけに、一臣があぁと頷いた。自分は差し出されたお茶に口をつける。
気まずい。
視線を目の前の食べ物に移すと、榊がすかさず口を開いた。
「どっちか無理にでも口に入れな。」
「・・・はい。」
渋々、プリンのふたを剥がしにかかる。プラスチックのスプーンで口に運ぶと、その甘さが妙に美味しく感じられた。やはり、お腹が空いていたのだろうか。点滴のおかげか、薬のおかげかわからなかったが、熱が下がって、食欲が湧いたのかも知れなかった。体はずいぶんと軽くなっていた。
「うまい?」
問われて頷いた。
「良かった。本当はもっとまともな食事をしに行こうと思っていたんだけど・・・。悪かったね。」
「いえ。僕の方が・・・すみませんでした。」
具合が悪かったのなら、断れば良かったのだ。いらない手間をかけさせたと、うなだれる。
「あのなぁ。諸悪の根源はこいつだろ。なんでおまえが謝るの!」
榊が煽ったグラスをテーブルに置いて口を挟む。
「・・・一臣さんは・・・悪くないんです。」
どうしても一臣を悪人にしたいらしい榊に、そうではないと訴える。しかし、こちらの言い分は聞く耳持たないといった風だった。
「悪いのはこいつ。大人が子供に何してるんだって話なの!同意の上でも大人が悪いの!金がらみならなお悪い!」
言い切って、二本目のビールをグラスに注ぐ。
そりゃ・・・未成年だけど。だけど・・・。
横に座る一臣を見やると、いいんだよ、と苦笑した。
「それよりすばる。今夜、うちに泊まらないか?一人の家に帰すのは心配なんだ。」
時計を見ると、10時をとうに回っていた。
「大丈夫です。具合、大分いいし。」
「今は薬が効いてるだけだよ。また熱が上がるかも知れない。」
そうかもしれないが。学校もあるし。
学校がある、と思ったところで、はっとした。今日は休んだが、普通の顔をして学校に行き、授業を受けようとしていたのだ自分は。それが何だか急に馬鹿馬鹿しくなった。笑った自分を、一臣が怪訝そうに見つめてくる。
「学校、行かなきゃって、思って。なにやってるんだろう・・・僕。」
「すばる・・・。」
一昨日の晩、死にたいのだと打ち明けたその口で、学校の話など。滑稽なことだった。
「そうだね。一度アパートに寄ってあげるから、必要なものを持ってきなさい。客間が空いてるから、そこで寝るといい。朝、駅まで送るから。」
一臣の申し出に、首を横に振ると、榊がまた口を挟む。
「そーしとけ。藪でも医者だからな。一人よりはマシだろ。」
医者?それに、駅、って・・・。疑問がいろいろとわき上がる。
「一臣さん・・・?」
伺うと、一臣は曖昧な笑みを浮かべた。
「うちにくるなら話してあげるよ。・・・秘密、知りたいんだろう?」
あ、と思った。そうだ。自分は今日、そのために一臣と会う約束をしたのだ。こんな事にはなったが、やはり秘密という単語は魅力的だった。
「わかりました。じゃぁ・・・お願いします。」
了承すると、一臣は優しげに微笑んだ。
結局、サンドイッチも食べ終えて、榊の家を出たのは11時を少し過ぎたころだった。
「すばるの家って、あの駅の沿線?」
「あ・・・はい。」
車に乗り込み、シートベルトを締めると、一臣がカーナビに触れた。
「住所、教えて。電話番号でもいいけど。」
「電話、ケータイしかないから。」
住所を口にするのは少々抵抗があったが、これから一臣の家も知ることになるのだと思うと、案外すんなりと言えた。
「思ったより近いな・・・。」
入力し終えると、一臣がつぶやく。
「え?」
「うちと。頑張れば歩いていけるくらいの距離だよ。今の季節ちょっと厳しいけど。」
それってけっこうな近所じゃ。
「12時までには帰れそうかも。ちょっと急ぐね。」
急ぐね、と言った割に、車は滑らかに走り出した。程なくして、見覚えのある町並みに出る。どうやら一臣の家と、榊の病院とアパートは、本当に近い位置関係にあるらしかった。車はアパートの横に停まった。学生用のアパートで、近くに駐車場はない。こんな時間とは言え、路上駐車は気がとがめた。急いで階段を上がると、二階の角部屋の鍵を開ける。今夜、と明日必要なものだけ、とスポーツバッグに詰め込んだ。しかしながら、着替えに制服、教科書などを持って行こうとすると、結構な量になった。
「着替えとかは、俺の使えばいいよ。」
玄関口から声をかけられる。一臣が上がってきたらしかった。
「運ぶの手伝ってあげるから。」
はい、と手を伸ばされて、どうしようかと躊躇う。持てない量ではないけれど。
「すばる。急ごう?」
再度言われて、制服を渡した。近所だというなら、これで学校も知られただろう。思えば、自分は一臣のことは名前しか知らないも同然なのに、フェアじゃないとため息する。自分ばかりが身ぐるみを剥がされるように暴かれていく。
「荷物、それだけ?」
スポーツバッグと、教科書の入った鞄を手に頷いた。
「行こう。時間も遅いし、迷惑になるといけないから。」
もう、住人は寝ている時間だろう。普段なら自分だってそうだ。言われるまま、扉に鍵をかけた。
一臣の家には本当に12時前に着いた。住宅街に建つ一戸建てだ。半地下の駐車場に車を入れると、玄関に案内される。表札には『佐伯』とあった。榊とは違い、どうやら病院兼住居というわけではなかった。しかし、まさかここに一人暮らしというわけではないだろう。こんな時間に、迷惑だ。荷物を持って先に扉を開けた一臣の後ろで、立ち止まってしまう。
「すばる?」
「・・・こんな時間に・・・。家の人、寝てるでしょう?」
ここまで来ておいて今更だが、そう思わずにはいられない。
「大丈夫。俺も一人。」
「え?」
こんな立派な一軒家に?
いいから早く入りなさい、と促され、玄関をくぐった。
「おいで。客間に荷物を運ぼうね。」
一臣が先を歩く。階段を上がってすぐの扉がどうやら客間のようだった。ベッドと、机が一つ置いてある。
「クローゼット、使っていいから。制服、しわになるといけないからね。」
一臣は、手にした制服を丁寧にハンガーに掛けた。荷物を下ろす。
「とりあえずは風呂・・・かな。すばるはどうしようか?でも汗かいたよね。シャワーくらいにしておいたほうがいいんだけど、かまわない?」
どうしようかとは、たぶん発熱したことを指しているのだろう。しかし、今日は嫌な汗をたくさんかいた。借りられるものなら、使わせてもらいたかった。
「お願いします。」
「うん。タオル用意するね。」
こっちだよ、と浴室に案内される。
「タオルと、歯ブラシ、これね。・・・傷、しみるかもしれないけど清潔にした方が治りが早いから、きちんと洗ってね。」
済んだら手当てするから、と脱衣所の扉を閉められた。
手当?って・・・またあの夜のようなことをするのだろうか。普通の傷ならこんなに抵抗はないのだろうが、場所が場所だ。何度も見られるのはさすがにきつかった。けれど、一臣になら、もうなにを晒してもいいような気にもなっていた。こうして、家に上げてもらい、浴室を使わせてもらい、寝る場所を与えられる。
一臣の意図がわからなかった。自分とのことは、あの夜済んだことで、今のこの状況は理解に苦しむべきことだった。なぜなら、自分にそうまで手をかけてもらえる理由がないからだ。一臣との事が原因で体調を崩したとしても、それを含めての報酬だ。医者に掛かりたければ、その金で掛かるべきだっただろう。一臣や、榊の手を煩わせた罪悪感は大きい。
自分に価値が見いだせない。そうなると、一臣がもし自分になにか望むことがあるのなら、それを全て叶えなくてはいけないような気になっていた。
シャワーを済ませ、身支度を調えると、脱衣所の扉がノックされた。
「すばる。いい?」
「あ、はい。」
扉を開くと、部屋着に着替えた一臣が立っていた。
「手当、しようね。・・・洗面台に手をついて、ちょっと足開いてくれる?」
どうやら、一臣は本当に手当てするつもりのようだった。しかも、ここで、だ。
言うとおりにすると、今身につけたばかりの下着を下ろされた。
「痛いと思うけど、少しだから頑張って。」
一臣は、薬袋から白いチューブのようなものを取り出すと、中身をたっぷりと指先にとった。それを、秘部に塗り込む。
「ぃ・・・っ。」
痛みに、声が漏れた。
「ごめんね。」
一臣はそれが済むと、先ほどのチューブをまた手にした。
「薬、中にも入れるから。」
つ、とチューブの口が差し込まれる。中に薬が出される感覚があった。
「痛みと腫れに効く軟膏だよ。榊のところで出してもらったんだ。市販薬より効くから、朝にはかなり楽になると思うよ。」
言いながら、下着とパジャマを整えてくれる。一臣は、そのままその紙袋を手渡した。
「二週間分入ってる。お風呂上がりに使って。それくらいで落ち着くと思うんだけど・・・。」
もしかして、あとは自分でしろ、と言うことだろうか。さっきのは、使い方の説明と言ったところか。
戸惑っていると、一臣が申し訳なさそうに首をかしげた。
「ごめんね。毎日、俺がしてあげられたら良いんだけど・・・。」
「そんな!いいです。できます!」
毎日、こんな事のためにここに通うことなどできなかった。
「・・・ねぇ。あとでちゃんと話そうと思うけど・・・。すばる、うちにこない?」
とっさに、言われたことに意味がわからなかった。頭の中で、何度も反芻する。
「・・・それって、どういう・・・?」
結局、わからなくて問いかけた。
「距離的に考えて、うちから学校行くの、そんなに苦じゃないだろう?親御さんとも相談して・・・うちで一緒に住まない?」
一臣は丁寧に言い直した。
ここに、一臣と一緒に住む!?
一臣の言いたいことはわかったが、意図が全く理解できなかった。なんのために?どうして?
ぐるぐると頭の中が混乱する。
「ちょっと考えてみてくれる?」
考えるって、そんなの。答えは決まっている。「無理」だ。あの親が、他人に迷惑をかけることを許すはずがない。が、一臣は本気のようだった。
「まぁ、答えは俺の秘密を聞いたあとでいいから。」
遅いからおやすみ、と一臣は脱衣所を出て行った。
翌日、微熱はあったものの、さして辛くもなかったので、学校へ行くことにした。一臣は言ったとおり駅まで送ってくれ、辛かったら休ませてもらうように、と強く言って出勤していった。
昨夜は、風呂から上がると、時間が遅かったこともあり、すぐに客間へと押し込まれた。約束の秘密の話は、また今度、とはぐらかされた。
ベッドの中で、一日のことを振り返る。色々あったように思う。中でも、最後に一臣の言ったことは、眠れなくさせるのには十分の内容だった。
一緒に暮らす。
つい先日会ったばかりの他人だ。しかも普通の関係とは言いがたい。どうしてそんなことを言うのか、全くわからなかった。ただ、一臣は、こうも言った。秘密を聞いたあとでもいい。一臣の秘密とはそれほど重いものなのか・・・。優しく微笑む姿からは、想像することができなかった。それ以前に、一臣についての情報が少なすぎた。職業はどうやら医者で、年は28歳。名字は佐伯。金に不自由しているそぶりがないことが、年齢からいえば不自然のような気がした。不自由していないのではない。無駄な使い方をしていると言っていいだろう。男を買うのに一人30万。しかも、17人目だと言っていた。買ってもらっておいて言うのもなんだが、馬鹿げていると思う。
持ってきた荷物の中には、あの夜一臣から手渡された白い封筒が入っていた。中身に手はつけていない。使う気もなかった。欲しいものなどなにもなかった。
そんなことを考えて、眠りについた。ベッドの寝心地は良く、ケータイのアラームをセットしておかなければ、危うく寝過ごすところだった。
放課後、駅に向かって歩いていると、ケータイが震えた。一臣からのメールだった。『アパートに迎えに行く。待ってて。』荷物の半分は一臣の家に置いて来てしまっていて、どうしようかと思っていた矢先だった。傷の痛みは大分引いていたが、歩いて一臣の家に行くには駅からの道がわからなかったし、なにより家には鍵が掛かっている。一臣が帰ってくるまで外で待つには、まだまだ気温が高すぎた。病み上がりの自分には過酷な環境だった。メールにほっとしている自分がいた。いつも通りに、アパートに帰ることにした。
7時を回った頃、夕ご飯をどうしようかと思っていると、チャイムが鳴った。扉を開けると、一臣だった。一臣の定時は、7時前後らしいことが察せられた。
「こんばんは。・・・具合どう?」
「こんばんは・・・。悪くないです。」
答えて、ここで話していていいのかと迷う。上がってもらうべきか、それとも。その気配を感じ取ったのか、一臣は少し笑うと、ご飯食べに行こうよ、と言った。そしてどういうわけか、明日の着替えを用意するように言う。
「今夜も、お泊まり・・・ですか?」
「うん。悪いけど、ちょっと長い話をするから。」
長い話とは、秘密のことだろうか。それとも一緒に住む、というあれだろうか。アパートから登校しない、ということにも少々の抵抗があった。万が一にもないだろうが、親に知れたら何を言われるかわからないからだ。黙っていれば、わからないことだろうが。
意を決して従うことにした。
ファミレスで夕食をとった後、一臣はまっすぐ帰路についた。昨日と同じく、家の中へと招かれ、客間に荷物を置いてくるようにと言われた。それが済むと、リビングへと通される。明るい色の家具で統一された部屋の奥には、カウンターキッチンが見えた。清潔感があると言えば聞こえがいいが、使っているのかどうかあやしい感じだった。生活感がないと言ってもいい。リビングには他に、大型のテレビと、コレクションボードがあった。様々な形のグラスと、何種類かの琥珀色の酒の瓶が置いてあった。自分の前では、アルコールをとらない彼の意外な一面を見た気がした。
「お風呂、先に済ませようか。今日も暑かったものね。・・・長い話になるし。」
一臣はそう言うと、風呂の支度をしに行ってしまった。ソファーに座っていいものかと立ち尽くしていると、ややあって一臣は戻ってきた。
「座ったらいいのに。」
苦笑されて、うなだれる。他人のテリトリーで、くつろげる性格ではないのだ。自分は。
「何か飲む?」
座るよう言い置いて、一臣は冷蔵庫を開ける。
「おまかせします。」
「なんて・・・君用に買っておいたよ。はい、どうぞ。」
一臣の手にはグラスと、オレンジジュースの紙パックがあった。最初に会った日に、レストランで何を頼んだか覚えていたのだ。子供みたいな注文をしたと恥ずかしく思ったが、一臣の気遣いがくすぐったかった。
「ありがとう。」
グラスに注がれるオレンジジュースに、素直に礼を言う。
「あぁ。やっと笑ったね。」
一臣は、向かいのソファーに腰を下ろすと、微笑んだ。
「ずっと緊張してたり、具合悪かったりだったろう。・・・よかった。」
言われて、そうかと思う。初めて会った日は酷く緊張していたし、その後も居心地が悪いばかりで、笑う余裕などなかった。一臣は、ずっと笑いかけてくれていたのに。
「ごめんなさい・・・。」
「いいよ。無理もない。・・・あんなこと平気でするような相手と一緒にいて、緊張しないわけがないものね。」
あんなこと、とはあの夜の事だろう。一臣はそのことを口にする時だけ、酷く自分を卑下した。
「でも・・・僕の体にはもう、興味がないでしょう?」
バージンを抱くのが好きだと言っていた。嗜虐を好む、と。
一臣は曖昧に笑い、今はね、と答えた。それなら、一臣のすること、とりわけ性的なことや暴力的なことに関しては、恐れる必要はなかった。それがいいことなのか悪いことなのかはかりかねたが。
「あぁ。お風呂沸いたね。飲み終わったら入っておいで。・・・傷に障るから、あまり温まらない方がいいよ。」
頷いて、グラスの中身を飲み干した。
二日続けて、風呂を借りる。二度目ともなれば、少々の慣れもあった。髪を洗い、体を洗い・・・特に傷のあたりは丁寧に洗った。石けんが少し滲みる程度で、我慢できない痛みはなかった。湯船に少しだけつかる。白い浴槽は広く、半身浴ができるように段差になっていた。実家の風呂を思い出す。広さも同じようだった。普段、アパートの狭い風呂に、膝を抱えて入っていることを思うと、足を伸ばしてゆうゆうと入れるこの風呂は、気持ちが良かった。この広さなら、一臣が一緒でも大丈夫なように思う。ふと、髪を洗ってもらったことを思い出した。髪どころか、全身を余すとことなく丁寧に洗ってくれた。その後の情事を思えばこそのことだろうが、決して嫌なことではなかった。むしろ、心のどこかで、あの行為を望んでいる自分がいた。
風呂から上がり体を拭くと、試練が待っていた。自分で、秘部の手当をしなければならないのだ。昨日手渡された軟膏は持ってきていたが、自分でするのは抵抗があった。しばらく悩んだが、どうしてもできずに、薬をパジャマのポケットにしまって、脱衣所を出た。
リビングに戻ると、一臣がミネラルウォーターのボトルを差し出してくれた。
「お湯の温度大丈夫だった?」
「はい・・・。」
「・・・手当、ちゃんとできた?」
どき、と動きが止まる。視線は軟膏を忍ばせたパジャマのポケットのあたりを見てしまっていた。
「してあげようね。」
一臣はいったんキッチンに行き、手を洗って戻ってきた。
「ソファーに後ろ向きに上がって。足開いてね。体は背もたれに預けると楽だよ。」
言われたとおりに体が動く。何故か、一臣の指示に従ってしまう自分を不思議に思いながら、軟膏を手渡した。パジャマごと下着を下ろされてから、なかなかに恥ずかしいポーズをとらされていることに気がついたが、遅かった。一臣は素早く昨夜と同じ手当を施すと、なにごともなかったようにパジャマを元に戻してくれた。
「今日は泣かなかったね。痛み、大分引いたの?」
頷く。
「よかった。やっぱり、榊に頼んで正解だった。」
一臣は苦笑すると、入れ違いに風呂へと向かったようだった。
一人残されたリビングで、ぼんやりとテレビを見ながら、渡された水に時々口をつけ、一臣を待つ。ニュース番組が流れていた。天気予報によると、明日も暑いようだった。今年は残暑が厳しい。この暑さも、今頃はもう感じている予定ではなかったのだが。自分の立てた計画がフイになった今、少々投げやりな気持ちになっているのは否めなかった。そうでなければ、おそらく自分は今ここにはいないだろう。どうにでもなれ。そう思う自分が、一臣の帰りを待っていた。
テレビの番組が変わる頃、一臣が部屋着に着替えて戻ってきた。冷蔵庫に行き、ミネラルウォーターのボトルを手に、ソファーの向かいに座る。振り向いて、背後のテレビを消した。
いよいよ、だ。
一臣はながながとため息すると、わずかに首を傾けて、目をじっと見つめてきた。
「君・・・まだ死にたいと思ってる?」
一度はその覚悟を決めたのだ。揺らいではいるが、全くないとは言い切れなかった。
「一臣さんの・・・言うことが確かなら。早く寿命がこないかな・・・って思ってます。」
輪廻の話。自殺者は生まれ変われないのだと。それならば、一日でも早くその日が来ることを祈らずにはいられない。
「そう・・・。」
一臣はまたため息をついた。
「秘密の話、長くなるけど・・・聞いてくれる?」
頷いた。
一臣は、水を一口含むと、ゆっくりと飲み下した。
「・・・この家はね、俺と妻と、生まれてくる子供のために用意したものなんだよ。」
一臣の話は、出だしから衝撃的だった。結婚しているとは思わなかったからだ。一臣の年なら、ありえなくはないだろうが、その気配は少しも感じられなかった。
「俺の性癖を知ってるだろう?母は知らなかったけど、父は、そのことを酷く心配していてね。仕事が決まるとすぐに、何度か見合いをしたんだ。大体の相手は、俺が女は相手にできない、と話せば納得してくれたんだけどね。それでもいい、って言った人がいて。両親の手前、結婚することになったんだ。それで、家を買って・・・。少しして彼女は妊娠したんだ。両親とも喜んでね。特に父は、俺の子供を見られると思っていなかったみたいで。だから検診の付き添いとか、かって出てくれていたりしたんだよ。俺は、仕事が忙しかったから、ついていてやれなくて。・・・お腹の子が6ヶ月の時だった。その日も検診で、両親が病院に付き添いで車を出したんだけど・・・。途中でね、交通事故に遭って。助かったのは妻だけだった。両親は即死。お腹の子は流産した。それが、三年くらい前。」
こくり、と喉が鳴った。あまりに過酷な内容で、どんな顔をしていいかわからなかった。ただ黙って頷く。
「以来、妻は病んでしまってね。気分がふさぐとか、眠れないとか・・・。当然だろうけど。・・・専門の病院を紹介する、って言ったんだけど、嫌だって言うものだから、俺が睡眠薬を処方したんだ。専門は内科だけど、それくらいのことはできたから。あぁ・・・その頃は、ちょっと大きい病院に勤めていてね。」
榊が医者だと言っていたのは、どうやら本当のことだったらしい。
「その頃からかな。学生時代につきあってた彼と、時々会うようになって。うちの両親に世話になったから、って葬儀の時にわざわざ来てくれてね。それがきっかけで・・・。妻は、それに気がついたんだと思う。俺が会っている相手が、ただの友達じゃないって事。だから、あの日、彼女は試したんだ。俺が、彼と彼女のどちらを選ぶか。彼女は、貯めた睡眠薬を大量に飲んで、自殺を図ったんだ。幸い命は助かったけど、重い後遺症が残ってね。発見が遅かったから・・・。
俺がその日、彼を選んだから。」
一臣はまた、深いため息をついた。その頃のことは、思い出したくないのだろう。
「その後、彼女は実家で療養することになって、彼女の両親の意向で離婚することになった。俺は、それに従ったんだ。
俺は、俺の処方した薬で、人を一人殺しかけたんだよ。彼女の人生を駄目にしたことを思えば、殺したも同じだね。それが俺の秘密。」
殺した。そう言って、一臣は自嘲した。
「酷い男だろう?・・・そのことが原因で、当時の病院にいられなくなってね。今は企業の産業医をしてる。会社の保健室の先生みたいなもんだよ。勘が鈍るから、時々当直のバイトを入れてるけど、それくらいじゃ医療現場には追いつけない。榊が藪医者だって言ったのは、彼女のこともあるけど、実際なまった俺の腕のことを言ってるんだよ。」
一臣の話が、嘘や作り話の類いでないことは、雰囲気で察せられた。
「・・・その・・・彼氏・・・さん?とは・・・?」
おそるおそる聞いてみる。
「彼女の自殺未遂を期に、縁を切ったよ。後悔したから。彼も納得してくれた。学生時代つきあってた、俺の最初の男だったんだ。一番長くつきあった。いろいろあって別れたけど、両親がいっぺんに亡くなって、気を使わせたんだろうな。時々悪い酒につきあってくれたんだ。それだけだったのに・・・。」
かける言葉もなかった。酷い話だと思った。どんなことが起きたら、男を17人も買うような人生を送ることになるのだろうかと思っていたが、納得せざるを得なかった。
「実家は、兄夫婦が継いでね。遺産が少し入ったから、この家のローンにあてて。それで終わり。あとはもう・・・何にも残ってなかったから・・・荒れてね。月に一度、君としたみたいなことをして、給料をドブに捨てる生活をしてるんだよ。」
ドブ・・・。
一臣は自分のしている行為が退廃的なものだとわかっているのだ。それでもなお止められないほどの、深い傷を負ったのだ。たぶん、元奥さんの『自殺』で。
だから、あんなに「死なれたくない。」と繰り返したのか。
今なら、彼の言動が少し理解できる気がした。
医者だからとか、身近な人の自殺未遂を経験したからとか、そんな複雑な思いが、今ここに自分を置いているのだろう。そして、秘密を打ち明けた。
けれど、腑に落ちないことが一つあった。
どうして、自分なんかのために、大切な秘密を口にしてまで、つなぎ止めようとするのか。それがわからなかった。一臣にとって、命とは等しく平等なものだということだろうか。自分には、そうは思えなかった。
「秘密の話は、これで終わり。・・・さて、どうする?すばる。」
どうする?とは、ここで一臣と一緒に暮らすかどうか、についてだ。
一臣がどうしてこんな広い家に一人で住んでいるのか知ってしまった今、なぜか心に強く思う気持ちがあった。
このまま、一人でいちゃいけない気がする。一臣も。自分も。
おそらくは、一臣もそう思ったのだろう。
これ以上、自分に関わった人間が、命を縮めないために。
けれど・・・両親を説得できるだろうか?話を聞いた限り、社会的な身分は申し分ないだろう。働いているのが病院ではないだけで、一臣は医者だ。母親に関して言えば、そういう肩書きに弱いところがある。だが父親は?どこの誰とも知らない男に、いらないとはいえ息子を預けるだろうか。世間体を重んじる人間だ。一臣が万が一同性愛者だと知れれば、許されることはまずない。けれど・・・高校生の一人息子をアパートで一人暮らしさせておくよりは、マシかもしれないと思うかも知れない。天秤の針は微妙なラインで揺れているように思えた。
「父を・・・説得できれば・・・。」
自分の気持ちは決まっていた。一臣のそばにいたい。一人にしておきたくないと思った。
「・・・こういうのはどう?俺は忙しい医者じゃないけけど、肩書きは役に立つだろう。君の勉強を見ることにして。これでも医学部ストレートで入って卒業してるからね。君の進学先が文系だと、ちょっと厳しい言い訳になるけど。」
なるほど、と思った。しかし、決定打に欠ける気がする。
「・・・すばる、名字、早乙女って言ったっけ?」
一度、身分証を見せたのを覚えていたらしかった。
「うん。」
「もしかして、お父さん学校の先生だったりする?高校の。」
確かに父はこのあたりでは有名な私立高校の教師をしている。それだけに、融通が利かない。しかし、なぜそれを一臣が知っているのか。
「ひょっとして、俺のこと覚えているかも。」
「え?」
一臣が、父の学校の卒業生??そんな偶然って。
「ちょっと待ってて。アルバムとってくる。」
だが一臣は確信があるらしく、階段を上がって行ってしまった。ややあって、卒業アルバムを持って戻ってくる。10年ほど前のものだ。その高校の名前は、確かに父の勤めている学校だった。
「ちょっと古いけど・・・主席だったから記憶にあるんじゃないかな?授業は受けたことないけど。生徒会にいたし。お父さんって、今も学生指導部にいたりする?」
そう言われても。父親がどんな仕事をしているかなど、漠然としか知らない。
「わかりません・・・。」
「そう。」
それにしても、主席、って・・・。医学部にストレートならそれもそうかと思うが。人は見かけによらない。
「でも・・・もし、覚えてたら、説得できるかも。」
「一人じゃ難しいかも知れないね。日曜日の都合が良ければ、俺がきちんと挨拶しにいくよ。大丈夫。猫をかぶるのは得意だから。」
少しいたずらっぽく笑う一臣に、苦笑する。
あの優しげな微笑みは、もしかしてかぶった猫だったのかと思った。
日曜の午後。久しぶりの自宅は、すこぶる居心地が悪かった。滅多に入ることのない客間に通され、冷たい麦茶を差し出される。そのグラスも、時間を追うごとに汗をかいていた。まるで背中を伝う冷や汗のようだ。
隣には一臣が座っていて、両親を前にとうとうと、まさに立て板に水といった調子で嘘を並べていた。
なんでも、自分と一臣が出会ったのは七月、夏休みの初めで、補講の帰りに駅で気分が悪くなったところに偶然居合わせ、医務室へと送り届けたのだそうで。その際に、どうしても後でお礼がしたいからと自分が強引に連絡先を聞き、以来時々連絡を取り合っているのだという。そして、先日も体調を崩し、アパートで一人暮らしをしていることが知れ、そのことを心配した一臣が、同居を申し出た。産業医とはいえ医師免許は持っているし、勉強も見てやれる。家事のできる自分が、家にいてくれると非常に助かる。・・・と言うようなことを、あの温和な声音、真面目な顔で平然と言ってのけたのだった。たいした猫をかぶっている。この時点で、母親は「落ちた」。だが父親は納得していないようだった。一臣が、自分の勤める高校の卒業生であると言うことは、自己紹介をした時に明かしている。良い印象を持っていることは確かだったが、なかなか首を縦には振らなかった。
「すばるくんのお姉さん、ご結婚の予定がおありだとか。おめでとうございます。だだ・・・そのことをすばるくんが気にかけているようで。自分が家にいたら、お姉さんの迷惑になるのでは、と。そんなこと、あるはずないと話したんですが・・・どうも。多感な時期ですからね、なにか思うところがあるのでしょう。僕は、カウンセラーの資格も持っていますから、しばらく彼を預けてみてはもらえないでしょうか?」
僕?・・・カウンセラー・・・??初耳だ。
「気持ちが落ち着いたら自宅に戻れば良いのではないかと・・・。」
一臣はどうやら「同居」から「一時預かり」に戦略を組み替えたらしかった。この言い方なら、世間体を重んじる父の印象も変わるかも知れない。そしてそれは、当たりだった。
「わかりました。・・・娘の結婚の話も、まだまとまってはいませんが・・・そうまで言ってくれるなら。ただし・・・。」
ただし?
「期限を設けましょうか。いつまでもだらだらとというわけにもいかないでしょう。あなただってまだ若い。これから再婚の話もあるでしょう。この子の進学先が決まるまで、ということで。」
再婚・・・。
父親の言った言葉に、思わず一臣の顔を仰ぐ。
「高校を卒業するまで・・・ということですか?」
「大学に進学するなら、そういうこともあり得るでしょう。ただうちは、この子を医学部にやるつもりはありません。」
もとよりそのつもりはないが、「そんな金は出せない。」そう言っているのだ。何しろ、自分が勤める私立の高校ではなく、公立の高校に通わせているくらいだ。学費は最小限に抑えたいのだろう。
「・・・わかりました。」
父親の出した条件を、一臣は了承した。
その後、今住んでいるアパートをどうするか、引っ越しはいつするのかなどをざっと話した。全ての話がすむ頃には、西日がきつい時間になっていた。
一臣に連れられて、自宅を後にする。とりあえず、今日帰るのはアパートだ。整理はできていたが、引っ越すとなれば話は別だ。持って行けないものを処分したりしなくてはいけない。
それにしても。
一臣の運転する車の助手席で、ちらりと顔を伺う。
頭がいい、というのを前提にしたとしても、あぁもすらすら嘘がつけるものだろうか。
「一臣さん、嘘は嫌いって・・・。」
自分には何度も、嘘はつかないで、と言ってきた一臣だ。言葉尻がどうしたって嫌みのニュアンスだ。
「時と場合によるでしょ。おかげで何とか丸め込めました、っと。」
一臣は満足げだ。
「でも、卒業までって・・・。」
ずっと一緒にいられるとは思っていなかったが、切られた期限はあまりにも短いような気がした。
「って言ってたね。・・・まぁ帰すつもりはないよ。」
「え?」
「あの家に、君の居場所はないだろう。」
言い切られて、俯く。
あの場で、一臣が感じたことを、そのまま口にしただけだろう。だが、他人にそう言われるのは、自分で思うのとはわけが違った。
「やっぱり・・・そう見えるんですね。」
「見えるね・・・。まぁ俺のうちは二人兄弟だけど・・・進学先くらい好きにさせてくれたしね。高校も、好きで通ってるんじゃないんだろ?・・・愛情はないのにレールには乗せておきたいなんて、エゴだね。」
「・・・でも、親だし。」
二十歳までは、自分の人生は親のものだと思う。その前に、リタイヤしようとしたわけだけれど。
「俺は鈍い方じゃないからね。・・・あの部屋、お姉さんの写真や賞状なんかは飾ってあるのに、君のは一つもなかった。・・・君の話を信じていなかったわけじゃないけど、あそこまであからさまだとは・・・。」
一臣は忌々しげに言った。そして、口調を緩めると、車線から視線をそらさぬままに言葉をつなげた。
「あそこにいたら、君は本当につぶれてしまうよ。・・・そんな風にはさせない。」
何故?
「一臣さん・・・なんでそんなに僕にかまうの?」
「・・・なんでだろうね?」
問いは、問いで返された。
翌週。引っ越しは思ったより早く片付いた。アパートで使っていたベッドや机を処分すると、案外身軽だったからだ。しかしながら一臣の車では、何度も往復させることになりそうだったので、業者を手配した。金は、あの日一臣から手渡された封筒から出した。その使い道なら、間違っていないような気がしたからだ。
一臣の家で与えられたのは、最初に通された客間だった。衣類をクローゼットにしまい、教科書などの本を棚に収め、パソコンの環境を整えると、ほぼ作業は終わりだった。新たに買い足したものは特になかった。一臣は、カーテンや寝具も自分好みに変えて良いと言ったが、期限があることを思うと、とりあえずはこのままでいいように思った。
遅めの昼食を、ダイニングキッチンで二人、向き合って食べていると、一臣が口を開いた。
「駅までの道順、後で確認しなきゃね。あー・・・自転車いるかな。歩きだとちょっと厳しいかも。雨の日は送るけど、毎日はちょっと難しい。」
「そう・・・ですか。わかりました。お金、まだ余ってるし。大丈夫です。」
「お金・・・ってあのお金使ったの?」
引っ越し費用も出さないのかあの親は。と一臣が憤る。
「いいんです。だって、僕のわがままだし・・・。」
「わがままとは少し違うと思う。俺は了解を得て君をここに連れてきたんだ。悪いけど、おかしいと思ったら、俺は口に出しちゃうかもしれない。」
口角を下げて不機嫌になる一臣が、なんだか可笑しかった。他人の親のことなど、どうでもいいだろうに。けれど、心のどこかで、「おかしい」と肯定されることが嬉しかった。違和感を感じているのが自分だけではないと知れたからだ。もしかしたら、思い込みなんじゃないかと思っていた時期もあった。けれど現実は、やはりそうではないらしかった。
「自転車は俺が買ってあげるよ。引っ越しのお祝い。・・・それから、あのお金はなるべく使わないようにしなさい。必要なものがあれば、用意するから。」
「そんな・・・。おいてもらえるだけでもありがたいのに。」
一臣に迷惑をかけたくなかった。
「大家なんだから、世話をするのは当たり前なの。」
いいんだよ。とカップ麺のスープを飲み干す。
「それに、あのお金は君にとって大切なお金でしょう?」
バージンと引き替えにした金だ。それが大切と呼ぶに値するのかわからなかった。二度と手にすることのない金ではあったが。
「・・・そうだ。すばる、今までは自炊だったんだよね?」
問われて頷く。たいがいの家事はこなせた。
「ご両親の手前、家事ができる人が欲しいって言ったけど、あれ半分は本音なんだ。余裕のある時でいいから、掃除とか洗濯とか、任せてもいいだろうか?」
「そんな・・・。やらせてもらえるなら何でもします。」
ただでおいてもらって、衣食住まかなってもらうことなど、無理な相談だった。できることがあるのなら、させてもらいたかった。それを仕事と呼んで、対価を得ることが果たして等価と呼べるかどうかは謎だったが。
「よかった。じゃぁ、あとで家の中案内するから。あ、あとこれ。」
小さな白い封筒を差し出される。開けてみると、それは鍵だった。
「すばるのだよ。」
「・・・・・・。」
ここに住む以上、必要だとは思うが。荷物も運び込んでしまっているのに、『鍵』の重さに緊張した。
「あの・・・。今更ですけど。本当に、いいんですか?」
「いいの。もらってね。」
「・・・はい。」
一臣はペットボトルの水を口にする。
「それから・・・少しずつでいいんだけど。・・・敬語、やめられないかな?」
え?
「敬語・・・ですか?」
「うん。そうそれ。」
10も年の離れた大人を相手に、敬語で話すな・・・とは。どうしたものか。
一臣の見た目は若く、いつか本人が言っていたように、年の離れた兄弟のように見えなくもないかも知れない。けれど、知り合ってまだ間もない。距離の取り方がわからなかった。
「どんな風にすればいいですか?」
敬語を使わない関係と言ってもいろいろあるだろう。友達とか・・・恋人・・・とか。
「もう少しリラックスできないかなって。まぁ・・・君は野良猫みたいなものだから、急に懐いて見せろって言っても無理か。」
一臣は苦笑する。
そうか。一臣の中で、自分は拾われた野良猫ということか。
その表現が、妙に自分には合っているような気がして、笑ってしまった。
「僕、猫ですか?犬っぽいと思うんですけど。」
主人の命令には忠実だ。この家での主人は一臣ということになる。言われれば何でもするだろう。
「犬?・・・そうか。犬か。」
一臣も笑う。
「猫なのは一臣さんでしょう?ものすごい猫かぶり。びっくりしちゃった。」
先週の早乙女家のことだ。あの演技力たるや拍手喝采もいいところだ。おかげで今自分はこうしてここにいられる。少しの偶然も手助けしてくれたけど、そこはやはり、一臣の肩書きと、かぶった猫の皮の厚みのなせるわざと言えよう。
「すばる・・・笑ってな。笑うと可愛い。」
「えっ?」
かぁっと顔が熱くなるのを感じた。可愛い、なんて言われるのは初めてだった。なにしろ女の子ではないというだけで、姿形などどうでもいい家に育っている。正直、自分の顔は他人から見てどうなのか、まったく興味がなかった。今までは。
一臣は同性愛者だ。その彼の好みに、少しでも近かったらいいと思った。野良猫でも、器量が良ければ可愛がられるかも知れない。
自分はまた、彼に両親からは得られなかったものを求めようとしているのかも知れなかった。
愛情がなんだかも、よくわからなかったが。
「僕、可愛いですか?」
箸を置き、膝の上に両手をそろえる。
「可愛いよ。線が細くて、色白いし。髪も栗色。その長さもよく似合ってるしね。」
引きこもりのもやしっ子なだけなんだけど。
「あの・・・。一臣さんの好みとは、どうですか?」
おそるおそる、上目遣いに尋ねる。
一臣は苦笑して、右手で口元を隠した。
「可愛い・・・と思ってるよ。」
良かった。
しかし一臣は、真面目な顔をしてこう続けた。
「君はゲイじゃないだろう。普通の男の子だ。特別俺の好みである必要はないんだよ。」
何を言われたのか理解するのに、数分の時間を要した。
一臣は、自分を性的な対象としては見ていない。それどころか恋人としても不適格だと言っているのだ。
自分は、一臣の声も、笑う顔も、指も・・・仕草の全てにこんなに惹かれているのに。
一臣が言うように、自分はゲイではないかもしれない。でも、そうじゃないとも言い切れない。何しろ自分は、一臣に抱かれて、嫌悪感を抱くことはなかったし、少なからず満足したのだ。
いや・・・そうじゃなくて。
もしかして。
それは相手が、一臣だから・・・?
「僕・・・ゲイじゃないの?」
「・・・女の子になりたい願望を持ってるだけの・・・普通の男の子だよ。」
「でも・・・。」
「前にも言ったろう?まだ自分の性癖なんてはっきりしてないよ。」
「でも・・・。」
そうなんだろうか。一臣の言うことが正しくて、自分は間違っているのだろうか。
一臣にされるのは嫌じゃない。そう思うのに、確かめる術がなかった。一臣はもう、自分の体には興味がない、と言っていたのを思いだしたのだ。
「僕は、一臣さんのこと・・・。」
なんと続けようとしたのだろう。
「すばる。俺は悪い大人だから、それ以上言わない方がいい。考えない方がいい。つけあげるよ。なにをしてしまうかわからない。」
今度こそ、一臣の言っていることがわからなかった。
「すばるのそれは、インプリンティングだよ。・・・今日の課題だ。調べておいて。」
一臣はそう言うと、二人分のカップ麺の容器をキッチンへと運んでいった。
食事の後、家の中を案内された。一階にはLDKと書斎。バスルームと洗濯スペース、納戸があった。キッチンにはパントリーもあったが、食材はほとんど置かれていなかった。二階は、与えられた客間と、一臣の寝室、そのほかに二部屋あった。今は使っていないとかで、一部屋は鍵が掛かっており、もう一部屋は物置として使っているらしかった。物置と言っても、スペースには十分余裕があったが。
バルコニーはサンルームになっていて、洗濯はそこに干すように言われた。ガラス張りのそこは、風雨の心配なく一年中洗濯が干せるとのことだった。間取りや導線を見る限り、やはりこの家は将来的に家族で住むことを前提に立てられたのだと察せされる。トイレも当然のように一階と二階にあった。だから、キッチンの説明を受けている時も、もやもやとした気持ちになった。きっとこのスペースは、元奥さんが使いやすいように設計されたものなのだろう。シンクの高さが少し低かった。IHのコンロを使うのは初めてだったが、それはそれで面白そうだった。それよりも、驚いたのは冷蔵庫の中身だった。食材はほぼ空で、あるのはミネラルウォーターのペットボトル。野菜庫には数本のビール。家で食事をしていないのは明白だった。
「一臣さん・・・。近くにスーパーとか・・・ある?」
語尾に気をつけつつ、話しかける。
「あるよ。二軒。自転車を買ったらいける範囲に三軒あるかな。」
そんな立地でこの冷蔵庫とは。呆れてため息をついていると、一臣は悪びれもせずに言い切った。
「一人のご飯は淋しいの。言っておくけど、俺は乱れた生活してるからね。」
そうだった。離婚してから、荒れている、と言っていた。それは性生活のことだけではなく、日常生活のことでもあるようだった。その割に、家の中は整然としていたが、それは、一臣がほとんど寝るためだけにこの家に帰っていることの証だった。
「じゃぁ、できる限りご飯作りますから・・・。作るから、帰る時メールくださいね。」
「毎日?それじゃ君の負担になるよ。たまには外食しよう?あぁそうだ。二、三約束事も作っておかないとね。」
「約束?」
「朝早いから、11時には寝ること。金曜の夜は、俺の部屋で一緒に寝ること。・・・月に二回、土曜の夜に当直のバイト入れてるから、帰るのは日曜の朝になる。だから、日曜日は昼まで起きないから。」
どうやら、一臣の生活のサイクルを乱すなと言うことらしい。当然と言えば当然だ。病院勤務でないにしても、仕事は医者なのだ。寝不足で仕事をさせるわけにはいかないだろう。
「定時は6時半だから、だいたい7時すぎには帰れるよ。」
すばるの学校は?と聞かれる。
「僕は、5時の電車には乗れてるから・・・。それから夕食の買い物して、じゃぁ帰る頃にはごはん間に合いそうですね。」
「朝はこの間と同じでいいの?」
この間、とは泊めてもらった翌日、駅まで送ってもらった時のことだ。
「一本遅くても大丈夫です。」
「それだと俺が間に合わない。・・・自転車買うまで我慢してくれる?」
「わかりました。」
しかし。さらりと聞き流したが。一臣は約束事の中に、一つ不可解なものを混ぜ込んだように思う。
「あの・・・金曜の夜って?」
「あぁ。休みの前日くらい、君とゆっくり話がしたいでしょう?大丈夫だよ。なにもしないから。」
一臣は苦笑した。怖がらなくていいからね、と。
その後、近い方だというスーパーに二人歩いて買い物に行った。米がないことに気がついたのは店に入ってからで、こんな事なら車で来るべきだったと後悔した。仕方なしに、冷や麦と、トマトとキュウリを買った。出来合いの唐揚げと豆腐を買って、つまみはこれでいいかと思う。そういえば、一臣は自分といる時に酒を飲まない。たまたまかもしれないが。冷蔵庫には冷えたビールがあった。このメニューなら、飲みたければ飲むだろう。調味料の在庫と賞味期限が不安だったので、めんつゆは出来合いのものを買うことにした。
これから、徐々に整えていけばいいよ、と一臣は笑う。それがどこか嬉しそうで、気恥ずかしかった。
一臣は、もう割り切っているのだろう。あのキッチンを使っていた人はもういないのだということを。その人の残した痕跡に、いちいちうろたえているのは自分の方だった。好きなようにしていい、と言われたが、難しいことのように思えた。
夕食と風呂を終えると、時刻は10時半を回っていた。一臣はもう寝るというので、自分も部屋に戻った。引っ越しの疲れがないわけではなかったが、一臣の課題が気になって、パソコンを立ち上げた。『インプリンティング』検索する。どうやら、鳥の刷り込み現象のことらしかった。卵からかえる時に、親鳥以外の生物が目に入ると、それを親だと思い込んでしまうと言うものだった。また、人間の心理学用語でもあるらしかった。初めて好感を抱いたものに対しての執着に似た感情・・・といったところか。一臣が、自分と彼の関係に対して、何故その言葉を使ったのか、よくわからなかった。自分は一臣に好感を持っている。一臣は、それを思い込みだと言いたいのかもしれなかった。それなのに、突き放すでもなくそばに置き、それこそ親鳥のように世話を焼く。一臣が、自分にどうなって欲しいのか、見当がつかなかった。死にたい気持ちがなくなればいいと思っているのは確かだろうが。あるいは野良猫が人に懐くかどうかを、ゲームのように楽しんでいるのだろうか?だが、それは違うように思う。自分は特に、一臣に対して敵意も警戒心も持ち合わせていないといっていいからだ。聡い一臣ならば、それくらいのことはわかっているだろう。ならばなぜ・・・。
一臣の気持ちがわからない。
ぐるぐると彼とのやりとりを思い出す。どれも、自分に好意的に接してくれていたように思う。それとも、そもそもそれが間違いなのだろうか?実家でついた嘘のように。全てが一臣の優しい嘘で。「愛してるよ。」と口にした彼だ。もしかしたら、自分に見せる表情のそこかしこに、嘘が紛れているのかもしれない。それならば、何が嘘で、何が本当なのか・・・。
疑い出すと切りがなかった。自分はあまりにも彼のことを知らないからだ。
自分に向けられる全てを信じたいけれど。一臣には、その背負った過去のせいか、暗い影を負っていて、時々そぐわない言動や表情を見せる。もともとの一臣を知らない自分が、それをそぐわない、と感じることも、またおかしな事なのだろうが。
今まで、こんなに誰かのことを考えたことがあっただろうか。眠れないほど・・・。
とにかく、一臣へのこの感情が「思い込み」だと彼が言うのには、それなりの理由があると言うことなのだ。自分には確信があるのに、彼にそう言われると揺らぐ。
一臣は、繰り返し、自分のことを「普通の男の子」だと言った。まるで、自分を恋愛対象に入れたくないとでもいうように。
けれど・・・。一臣の全てが虚構だったとしても、自分はもう、たぶん、きっと・・・。
これがおそらく、恋愛感情というものだ。刷り込みによるものだとしても、これは恋なのだろうと思えた。
一臣のことが知りたい。
待ち合わせは7時。一臣は遅れているようだった。ポケットの中でケータイに触れる。
だるい。それに悪寒がした。熱があるようだった。
今日、始業式には行かなかった。体が思うように動かず、そんな気にはなれなかったからだ。相変わらず、動くたび傷が痛かった。心なしか、酷くなっているようにすら思う。どうしていいかわからずに、ただ癒えるのを待つことしかできなかった。
食事も、一臣とホテルでしたのを最後に、なにも口にしていない。かろうじて水分だけはとっていたが、そうでなければ、この暑さだ。熱中症で今頃本当に死んでいる。
それほどまでに具合が悪くても、足は何故かここに来ることを選んだ。一臣に会いたかった。秘密を知りたいと思ったのだ。一人で家にいる間に思ったことは一つだ。
『秘密の共有』
なんと甘美的な響きだろう。
一臣に、死ぬことと、その理由を明かした自分。それは、胸の内に秘めて持って逝くだろうものだった。そして、秘密を教えてくれると言った一臣。それを聞いた時、何かが変わる予感がした。秘密だと言うからには、一臣の話も、誰にでもするような話ではないだろう。それならば、自分と一臣はお互いの秘密を交換し、共有する不思議な関係になる。体のつながりだけの、お金のつながりだけの関係ではなくなるということだ。それはとても魅力的だった。
しかし、一臣は待ち合わせの時間を三十分過ぎても現れなかった。ケータイも鳴らない。場所と時間を指定してきたのは一臣からで、三時を過ぎた頃にメールでのことだった。まさか、今更会いたくなくなったということはないだろうが、否定しきれないのも確かだった。自分だったら、こんな自殺志願者、放っておくだろう。
結局、あの夜提示された金を、自分は受け取った。それで終わりだったとしても、何ら問題はなかった。
それからしばらくして、時計が8時を指そうかというころ、ケータイが震えた。手にすると、一臣からの着信だった。通話ボタンを押すと、別れて以来の一臣の声が耳に飛び込んできた。
『よかった。出てくれた。』
『え?』
『ごめん。仕事がちょっと。もうすぐ着くけど、まだそこにいる?』
遅れた理由は、仕事がおしたらしかった。
『はい。』
『ごめんね。連絡もできなくて。暑いだろう?見えるところにコンビニあるよね。そこで待っててくれないか。もう、本当にすぐ着くから。』
言われて、視線を巡らすと、カフェとコンビニが並んで立っていた。一臣の言うコンビニとはおそらくそこだろう。
『わかりました。』
『ごめんね。じゃぁ。』
再度謝罪の言葉を残して、通話が切れる。
歩くも立っているのも辛かったから、本当はここから動きたくなかったが、言われたとおりにコンビニで待つことにした。そういえば、喉が渇いている。
水、買おう・・・。
レジで会計を済ませていると、一臣が現れた。
今日も、ワイシャツ姿だった。仕事だったと言うからには当然かも知れなかったが。
「ごめん。遅くなった。・・・なに買ったの?」
謝罪の言葉を口にしつつ、視線はレジ袋の中身を気にしたようだった。
「水。」
「そっか・・・。お腹空いたよね。ちょっと路駐してるから、急いでもらってもいい?」
路駐?車で来たのか。
一臣に腕を引かれ、よろめいた。
「っ・・・!」
「え?」
小さく漏れた悲鳴を、一臣は聞き逃さなかった。
「痛かった?」
びくりと体が竦む。一臣に与えられた傷ではあったが、そのことを悟られたくなかった。気に病んで欲しくなかったからだ。しかし、一臣は確信したようだった。
「ちょっと・・・。」
先ほどよりはゆっくりだったが、足は店の奥のトイレに向かって歩き出す。引きずられるようにして、個室に押し込まれた。
「お尻・・・痛いの?」
じ、っと視線を合わされる。否定したかったが、沈黙を肯定と受け取ったようだった。
「ごめん。ちょっと見ても良い?」
「や!駄目です!」
こんなところで?いや、それどころではない。情事の後でも前でもないのだ。秘部を見せるなんてとんでもない話だ。
「まだ、出血してる?」
ふるふると首を横に振る。
「すばる。見せて。」
再度強く言われ、観念した。
頷くと、ベルトを外され、ボタンを外され、ファスナーを下ろし、ズボンを腿まで下げられる。そして、くるりと後ろを向かされて、壁に手をつくように言われた。従うと、下着を下ろされる。両手で肉を掴まれ、左右に割られた。一臣が息をのむ気配がした。
「・・・ごめん。ちゃんと手当てしたつもりだったけど・・・。」
一臣は、状態を確認して、すぐに着衣を整えてくれた。
「とりあえず、車。停めておけないから移動しよう。」
一臣は、店を出ると、急ぎながらも気遣うようにして歩を進めた。送迎の車の列の端に、申し訳なさそうに白のインプレッサが停めてある。一臣は助手席のドアを開くと、乗るように言って、自分は運転席へと回った。乗り込むと、エンジンをかけ、すぐに出られるようにしつつ、ケータイを取り出した。どこかに電話し、ややあってから出ただろう相手と何かやりとりをする。頼むよ、と通話を終わらせると、タクシーが行きすぎるのを待って、車を発進させた。
いくつ目かの赤信号で、意を決して口を開いた。
「・・・どこに、行くんですか?」
車の中は居心地が悪い。どこに連れ去られるかわからない不安感と、逃げ出せない圧迫感がある。普段あまり車に乗らない自分には地の利がない。交差点ごとに地名を確認しているが、ここで一人下ろされたとして、帰れる自信がない。
「・・・病院。」
信号が青に変わる。交差点を右折して、車線を変える。
「病院って、こんな時間に?」
8時過ぎだ。普通の病院はもうとっくに閉まっている。
「すばる、熱あるでしょ。呼吸も速い。」
それはそうかも知れないが、救急指定に駆け込むほど悪くはない。
それ以前に、病院は困る。保険証を使いたくないからだ。そうなると、手持ちのお金も足りない。
「一臣さん・・・あの。困ります。僕なら大丈夫ですから・・・。」
「大丈夫かどうかは俺が決める。」
妙にはっきりとそう言い切ると、大通りから一本裏道に入った。少し進んだところに、四階建てのビルがある。一階部分が駐車場になっていて、一臣は慣れた様子でそこに車を停めた。入り口は通りに面していて、ここが目的の病院だとわかったが、その標榜に絶句した。
肛門科、消化器科、内科。普通、標榜というのは、その病院の医者が最も得意とする科を頭にのせるものだと聞いたことがある。と言うことはつまり、ここは尻を見せるための病院だと言うことだ。頭の中が、「嫌だ」の二文字で埋め尽くされる。一臣にされるのならまだしも、それ以外の人間にまで見られたくない。たとえ相手が医者でもだ。
一臣は、車から降りると助手席に回り、ドアを開けて降りるように言う。当然のように、足は固まって動けない。
「すばる。だだこねてる場合じゃない。」
口調が厳しい。
でも、だけど、だ。
「か、一臣さん・・・。保険証、使ったら親に知れる!ヤダよ!」
嫌な理由はそれだけではないが。
一臣は、ふーっとため息をついた。
「・・・知り合いの医者なんだ。大丈夫。誰にも知られないよ。」
知り合い・・・?
そう言われてしまうと、断る理由がなくなってしまう。
「すばる。」
再度促されて、しぶしぶ車から降りた。たったこれだけの動きが、傷に響く。立ち上がると、くらりとした。熱も上がっているのかも知れなかった。確かに、だだをこねている場合ではないような気がする。
手を引かれて連れて行かれたのは、正面の入り口ではなく、駐車場から出入りできる通用口だった。一臣はインターホンを押した。
ほどなくして、「はーい。」とスピーカーから声がした。男の声だ。
「俺だ。」と一臣が短く言うと、相手の方も「開いてるよ。」と返した。言われたとおり、ドアには鍵がかかっていなかった。一臣は、勝手知ったる様子で、中に入っていく。すぐに階段になっていて、どうやら二階が病院施設らしかった。夜の9時少し前。非常灯の明かりを頼りに、廊下を抜けて、院内を突っ切り、待合室に出る。ちょっと待ってて、と長いすに座らされた。
一臣は、壁際をなぞると、スイッチを入れた。広くはない待合室に明かりが点る。
スイッチの場所まで知っているとは、よほどここに出入りしたことがあるのだろう。なんのために・・・?疑問は、すぐに嫌な予感に変わった。もしかしなくても、自分と同じような理由で、急患を連れて来た過去があると言うことではないだろうか。自分の考えに、手をきつく握りしめた。17人目。自分には一臣が初めての相手だが、一臣にはそうでないことを思い知らされる。
「久しぶりだな。・・・葬式以来か?」
不意に、廊下から声をかけられた。野太い男の声だ。顔を上げると、背丈は一臣ほどの、どっしりと体格のいい男が、ポロシャツに白衣を羽織って立っていた。
「あぁ。あれ以来か・・・。久しぶり。榊。」
久しぶり?
「おまえ・・・まだ悪いあそび止めらんねーの?」
悪いあそびって、僕のことだろうか?と思う。白衣の男が、品定めでもするように見ていた。
「未成年じゃん。なにやってんの?犯罪だよー。ハンザイ。」
「ちが・・・。」
言いかけた口を、一臣が制した。
「わかってるよ。」
「わかってるなら、やめろ。バカが。」
さっきから聞いていると、どうやらこの医者・・・相当に口が悪い。いつもこうなんだろうか?それとも一臣が相手だから?
「・・・やめてもいいかと思ってるんだよ。・・・診てやってくれないか。」
一臣はため息混じりにいった。相手の乱暴な言葉に取り合うつもりはないらしかった。榊と呼ばれた男は、舌打ちすると、診察室の方へと歩いて行き、明かりをつけた。
「おまえの頼みだから、特別に診てやるんだからな。」
「わかってるよ。ちゃんと礼はする。」
おいで、と呼ばれて、おそるおそる診察室に足を踏み入れる。パソコンと書類の載ったデスクに、カーテンで仕切られたベッド。薬品棚。血圧計や身長体重計などがある、普通の診察室と同じように思えた。
「来な。ズボン腿まで下ろして、ベッドに上がって。尻こっち向けて、横向きに。」
指示されるが、緊張で足が竦む。一臣が手を引いた。たたらを踏みつつ、ベッドに上がる。
榊は、手袋をするとワゴンにいくつかの薬品を載せて、ベッドの足下に立った。
「じゃ、お尻見せようね。膝抱えて、お尻突き出すように体丸めて。」
言うなり、下着を下ろされそうになり、慌てて履き口のゴム部分を掴んでしまった。
「やることやっといて、今更恥ずかしいもないだろ。しょうがないな・・・ほら。」
腰のあたりに、大判のタオルを掛けられた。
「尻しか見ないから、パンツ下ろして。」
言いぐさに、一臣に目で訴えてみたが、一臣は小さく頷いただけだった。言われたとおりにしろということだ。仕方なく、下着を下ろした。
「はい。ごめんね~。」
腰を片手で押さえられ、尻を割り開かれる。恥ずかしさよりも、痛みの方が勝った。悲鳴をかみ殺す。
「痛そう。・・・やったのいつ?」
「一昨日の晩。」
「やりっぱなしかよ。」
忌々しげに、傷を指でなぞられる。
「一応手当はしたんだけどね。」
「これだけ深くちゃな。・・・縫うほどじゃない。けど、しばらく痛いぞ。炎症が酷い。」
縫う?たかが切れ痔ではないのか?そんな処置をするほどのこともあるのか。
今更ながらぞっとする。
「中も見るから。・・・暴れんなよ。」
「麻酔は!?」
一臣が慌てたように声を上げた。
「するよ。」
カチカチとワゴンの上で音がする。何かの準備をしているのだろうが、怖くてとても見られなかった。
「すばる、ちょっと我慢。」
背中と腰を押さえられた。次の瞬間、秘部に激痛が走る。
「っくぅ・・・。」
何かを入れられて、ぐるりとかき回された。それが抜けると、ひやりとした感覚と、ずきずきとした痛みが残る。
「麻酔効いたら中見るから。」
麻酔?今のがそうだったのだろうか。目尻に涙がにじんでいる。それを、そっと一臣が拭ってくれた。乱れた呼吸を背中をさすってなだめてくれる。
「薬が効けば楽になるからね。」
言われたとおり、痛みはだんだん遠くなっている。感覚が麻痺していくのがわかった。
カチャリ。
金属音に、なにをされるのかと思わず足下に目をやると、榊が見慣れない金属の器具を手にしたところだった。
「初めて?」
「?」
「肛門科。」
頷く。
「あっそ。覚えておきな。指突っ込まれて触診と、肛門鏡使って中見られるのセットだから。」
指を突っ込まれる、とはさっきのアレのことか。では肛門鏡というのはあの器具のことだろうか。くちばしのような形状にハンドルが付いている。
「これ、今から入れるんだよ。」
「えっ!?」
そんなものが入る?ただでさえ傷ついて痛い部分に?
思わず泣きそうな顔をしたのだと思う。一臣は眉根を寄せて苦笑すると、頭をぽんぽんと叩いた。
「あんまり脅かさないでやって。・・・普通の子なんだよ。」
「脅しじゃないだろ。・・・はい。力抜いてねー。」
ぐっと一瞬圧迫感があった。が、それ以外の感覚はない。麻酔のせいだろうか。恐れていた痛みはなかった。
「口で短く呼吸して。」
言われたとおり、はっはっと呼吸する。顎が上がった。
「出血痕あるな・・・生傷は無し。はい終わり。機械抜くよ。」
言われて、器具が抜かれたのがわかったが、感覚は全くなかった。麻酔の効果とはこれほどのものなのか。しばらくの間だろうが、体を苛んでいた痛みから解放されるのだろう。
榊はもう一度タオルをめくると、感覚のない秘部にまた何かしたようだった。
「解熱鎮痛剤入れて、炎症抑える薬塗ったから。しばらくすれば楽になるだろ。」
服を整えるように言われ、ほっとする。ベッドから降りるのを、一臣が手を添えて気遣ってくれた。
「メシ、食えてないんだろう。水分は?時間があるなら点滴一本入れてくか?」
榊の言葉に、一臣をうかがう。
「頼む。」
一臣は、どうやらそれも頼むことにしたらしかった。
「じゃぁ隣のベッドで横になってて。暑いな。ちょっとエアコンいじってくるわ。」
言い置いて、榊はどこかへ消えていった。
一臣に付き添われ、診察室の隣、処置室とプレートのかかった部屋に入った。ベッドが三台おいてある。入り口側のベッドに横になるよう言われ、仰向けに横になると、一臣はシャツのボタンとベルトを緩めてから、横にあった丸椅子に座った。
「ごめん。辛かったろう。」
辛かったようにも思うが、あえて首を横に振った。
「明日も学校だろう?早く帰してやるつもりだったんだけど。少し時間かかるね。・・・家に連絡入れておく?」
「あ・・・一人だから大丈夫・・・です。」
「一人、って?」
「アパートに一人で住んでるんです。」
家に連絡されるよりはマシ、とプライバシーを少し明かす。
「高校生なのに?」
「・・・家、居づらいから。」
答えると、一臣はあぁ、と頷いた。
そこに榊が点滴のパックを持って現れる。
「温度下げてきたから、涼しくなるだろ。一時間くらいか・・・。」
言いながら、点滴台にパックをセットし、準備をする。
「あーもー・・・。メシまだなんだよ俺。腹減ったわ。」
そんなことを言いながら、右腕の肘の内側をアルコール綿で消毒した。血管に針が刺さるのをじっと見つめる。
「珍しいね。」
「え?」
「男はたいがい見ないもんなんだけどね。針とか、血とか。」
そう言われると、そうかも知れない。
「そんなんだから悪い男に喰われたりするんだよ。」
腕に針が入るのを見ていただけで、そんなんだからと決めつけられ、むっとした。それに、一臣は悪い男のようには思えなかったし、喰われた覚えもない。悪い男というのなら、榊の口の方が余程悪かった。
「・・・いじめないでやってくれよ。ほんとに、普通の子なんだ。それ、何が入ってる?」
それ、と一臣が点滴のパックを指した。
「ブドウ糖とビタミンと抗生剤。」
見ればわかるだろ。藪医者。と榊が悪態をつく。
「抗生剤はわからないだろう。藪で悪かったな。」
え?
思わず一臣を見上げた。一瞬目が合う。が、すぐに反らされた。
「後で話すから。少し眠るといいよ。」
さら、と前髪を撫でられる。
「寝とけ。・・・俺はこいつと話があるからな。終わる頃見に来てやるから心配するな。」
榊は、こいつ、と一臣を指し、立つように促した。
「あ、メシ、買ってこさせるけど、食えるか?牛丼かコンビニだけど。」
振り返りざま、榊が言う。食欲は正直なかったが、答えないと出て行きそうになかった。
「なにか軽いもの・・・。」
「わかった。食べやすそうなもの買ってくるから。」
返事は一臣がした。
二人はそろって処置室を出て行った。
誰もいない夜の病院。ぽたり、ぽたりと落ちる点滴を見ているうちに、どうやら眠ったようだった。
人の気配に目を覚ます。目をやると、一臣が点滴の処理をしていた。慣れた手つきで針を抜き、一瞬あふれた血液を脱脂綿で拭き取ると、テープで止める。
点滴のパックにルートを巻き付けると、起きられる?と小首をかしげた。頷いて、ベッドから降りる。薬が効いたのか、傷の痛みは大分引いていた。
「おいで。サンドイッチとプリン買ってきた。」
連れられて、奥の廊下へと誘われる。途中、点滴のパックを廃棄物のゴミ箱に捨てる。関係者以外立ち入り禁止と書かれた扉を開けると階段があり、一臣は先に登るよう言った。登った先は、病院のそれとは雰囲気が違っていた。
「榊の家なんだよ。三階から上。」
なるほど。それで四階建てなのか。妙に納得していると、リビングへと通された。ソファーとテーブルが目に入る。二人は食事を終えたのだろう。レジ袋と、飲み物のグラスが二つ置かれていた。
「なに飲む?・・・あ、トイレ大丈夫?」
「あ。お願いします。」
こっちだよ、とトイレに案内される。一臣は、病院の中だけでなく、家の中のことも良く知っているようだった。
トイレから戻ると、テーブルの上はきれいに片付けられていた。代わりに、パッケージに包まれたサンドイッチと、プリンとお茶が置かれている。どうやらこれが今日の夕食というところだろう。ソファに座ると、居心地悪く腰が沈んだ。その横に一臣がやはり腰を沈める。向かいに、榊が座った。新しいグラスを持っている。
「ビール、開けて良いだろ?」
問いかけに、一臣があぁと頷いた。自分は差し出されたお茶に口をつける。
気まずい。
視線を目の前の食べ物に移すと、榊がすかさず口を開いた。
「どっちか無理にでも口に入れな。」
「・・・はい。」
渋々、プリンのふたを剥がしにかかる。プラスチックのスプーンで口に運ぶと、その甘さが妙に美味しく感じられた。やはり、お腹が空いていたのだろうか。点滴のおかげか、薬のおかげかわからなかったが、熱が下がって、食欲が湧いたのかも知れなかった。体はずいぶんと軽くなっていた。
「うまい?」
問われて頷いた。
「良かった。本当はもっとまともな食事をしに行こうと思っていたんだけど・・・。悪かったね。」
「いえ。僕の方が・・・すみませんでした。」
具合が悪かったのなら、断れば良かったのだ。いらない手間をかけさせたと、うなだれる。
「あのなぁ。諸悪の根源はこいつだろ。なんでおまえが謝るの!」
榊が煽ったグラスをテーブルに置いて口を挟む。
「・・・一臣さんは・・・悪くないんです。」
どうしても一臣を悪人にしたいらしい榊に、そうではないと訴える。しかし、こちらの言い分は聞く耳持たないといった風だった。
「悪いのはこいつ。大人が子供に何してるんだって話なの!同意の上でも大人が悪いの!金がらみならなお悪い!」
言い切って、二本目のビールをグラスに注ぐ。
そりゃ・・・未成年だけど。だけど・・・。
横に座る一臣を見やると、いいんだよ、と苦笑した。
「それよりすばる。今夜、うちに泊まらないか?一人の家に帰すのは心配なんだ。」
時計を見ると、10時をとうに回っていた。
「大丈夫です。具合、大分いいし。」
「今は薬が効いてるだけだよ。また熱が上がるかも知れない。」
そうかもしれないが。学校もあるし。
学校がある、と思ったところで、はっとした。今日は休んだが、普通の顔をして学校に行き、授業を受けようとしていたのだ自分は。それが何だか急に馬鹿馬鹿しくなった。笑った自分を、一臣が怪訝そうに見つめてくる。
「学校、行かなきゃって、思って。なにやってるんだろう・・・僕。」
「すばる・・・。」
一昨日の晩、死にたいのだと打ち明けたその口で、学校の話など。滑稽なことだった。
「そうだね。一度アパートに寄ってあげるから、必要なものを持ってきなさい。客間が空いてるから、そこで寝るといい。朝、駅まで送るから。」
一臣の申し出に、首を横に振ると、榊がまた口を挟む。
「そーしとけ。藪でも医者だからな。一人よりはマシだろ。」
医者?それに、駅、って・・・。疑問がいろいろとわき上がる。
「一臣さん・・・?」
伺うと、一臣は曖昧な笑みを浮かべた。
「うちにくるなら話してあげるよ。・・・秘密、知りたいんだろう?」
あ、と思った。そうだ。自分は今日、そのために一臣と会う約束をしたのだ。こんな事にはなったが、やはり秘密という単語は魅力的だった。
「わかりました。じゃぁ・・・お願いします。」
了承すると、一臣は優しげに微笑んだ。
結局、サンドイッチも食べ終えて、榊の家を出たのは11時を少し過ぎたころだった。
「すばるの家って、あの駅の沿線?」
「あ・・・はい。」
車に乗り込み、シートベルトを締めると、一臣がカーナビに触れた。
「住所、教えて。電話番号でもいいけど。」
「電話、ケータイしかないから。」
住所を口にするのは少々抵抗があったが、これから一臣の家も知ることになるのだと思うと、案外すんなりと言えた。
「思ったより近いな・・・。」
入力し終えると、一臣がつぶやく。
「え?」
「うちと。頑張れば歩いていけるくらいの距離だよ。今の季節ちょっと厳しいけど。」
それってけっこうな近所じゃ。
「12時までには帰れそうかも。ちょっと急ぐね。」
急ぐね、と言った割に、車は滑らかに走り出した。程なくして、見覚えのある町並みに出る。どうやら一臣の家と、榊の病院とアパートは、本当に近い位置関係にあるらしかった。車はアパートの横に停まった。学生用のアパートで、近くに駐車場はない。こんな時間とは言え、路上駐車は気がとがめた。急いで階段を上がると、二階の角部屋の鍵を開ける。今夜、と明日必要なものだけ、とスポーツバッグに詰め込んだ。しかしながら、着替えに制服、教科書などを持って行こうとすると、結構な量になった。
「着替えとかは、俺の使えばいいよ。」
玄関口から声をかけられる。一臣が上がってきたらしかった。
「運ぶの手伝ってあげるから。」
はい、と手を伸ばされて、どうしようかと躊躇う。持てない量ではないけれど。
「すばる。急ごう?」
再度言われて、制服を渡した。近所だというなら、これで学校も知られただろう。思えば、自分は一臣のことは名前しか知らないも同然なのに、フェアじゃないとため息する。自分ばかりが身ぐるみを剥がされるように暴かれていく。
「荷物、それだけ?」
スポーツバッグと、教科書の入った鞄を手に頷いた。
「行こう。時間も遅いし、迷惑になるといけないから。」
もう、住人は寝ている時間だろう。普段なら自分だってそうだ。言われるまま、扉に鍵をかけた。
一臣の家には本当に12時前に着いた。住宅街に建つ一戸建てだ。半地下の駐車場に車を入れると、玄関に案内される。表札には『佐伯』とあった。榊とは違い、どうやら病院兼住居というわけではなかった。しかし、まさかここに一人暮らしというわけではないだろう。こんな時間に、迷惑だ。荷物を持って先に扉を開けた一臣の後ろで、立ち止まってしまう。
「すばる?」
「・・・こんな時間に・・・。家の人、寝てるでしょう?」
ここまで来ておいて今更だが、そう思わずにはいられない。
「大丈夫。俺も一人。」
「え?」
こんな立派な一軒家に?
いいから早く入りなさい、と促され、玄関をくぐった。
「おいで。客間に荷物を運ぼうね。」
一臣が先を歩く。階段を上がってすぐの扉がどうやら客間のようだった。ベッドと、机が一つ置いてある。
「クローゼット、使っていいから。制服、しわになるといけないからね。」
一臣は、手にした制服を丁寧にハンガーに掛けた。荷物を下ろす。
「とりあえずは風呂・・・かな。すばるはどうしようか?でも汗かいたよね。シャワーくらいにしておいたほうがいいんだけど、かまわない?」
どうしようかとは、たぶん発熱したことを指しているのだろう。しかし、今日は嫌な汗をたくさんかいた。借りられるものなら、使わせてもらいたかった。
「お願いします。」
「うん。タオル用意するね。」
こっちだよ、と浴室に案内される。
「タオルと、歯ブラシ、これね。・・・傷、しみるかもしれないけど清潔にした方が治りが早いから、きちんと洗ってね。」
済んだら手当てするから、と脱衣所の扉を閉められた。
手当?って・・・またあの夜のようなことをするのだろうか。普通の傷ならこんなに抵抗はないのだろうが、場所が場所だ。何度も見られるのはさすがにきつかった。けれど、一臣になら、もうなにを晒してもいいような気にもなっていた。こうして、家に上げてもらい、浴室を使わせてもらい、寝る場所を与えられる。
一臣の意図がわからなかった。自分とのことは、あの夜済んだことで、今のこの状況は理解に苦しむべきことだった。なぜなら、自分にそうまで手をかけてもらえる理由がないからだ。一臣との事が原因で体調を崩したとしても、それを含めての報酬だ。医者に掛かりたければ、その金で掛かるべきだっただろう。一臣や、榊の手を煩わせた罪悪感は大きい。
自分に価値が見いだせない。そうなると、一臣がもし自分になにか望むことがあるのなら、それを全て叶えなくてはいけないような気になっていた。
シャワーを済ませ、身支度を調えると、脱衣所の扉がノックされた。
「すばる。いい?」
「あ、はい。」
扉を開くと、部屋着に着替えた一臣が立っていた。
「手当、しようね。・・・洗面台に手をついて、ちょっと足開いてくれる?」
どうやら、一臣は本当に手当てするつもりのようだった。しかも、ここで、だ。
言うとおりにすると、今身につけたばかりの下着を下ろされた。
「痛いと思うけど、少しだから頑張って。」
一臣は、薬袋から白いチューブのようなものを取り出すと、中身をたっぷりと指先にとった。それを、秘部に塗り込む。
「ぃ・・・っ。」
痛みに、声が漏れた。
「ごめんね。」
一臣はそれが済むと、先ほどのチューブをまた手にした。
「薬、中にも入れるから。」
つ、とチューブの口が差し込まれる。中に薬が出される感覚があった。
「痛みと腫れに効く軟膏だよ。榊のところで出してもらったんだ。市販薬より効くから、朝にはかなり楽になると思うよ。」
言いながら、下着とパジャマを整えてくれる。一臣は、そのままその紙袋を手渡した。
「二週間分入ってる。お風呂上がりに使って。それくらいで落ち着くと思うんだけど・・・。」
もしかして、あとは自分でしろ、と言うことだろうか。さっきのは、使い方の説明と言ったところか。
戸惑っていると、一臣が申し訳なさそうに首をかしげた。
「ごめんね。毎日、俺がしてあげられたら良いんだけど・・・。」
「そんな!いいです。できます!」
毎日、こんな事のためにここに通うことなどできなかった。
「・・・ねぇ。あとでちゃんと話そうと思うけど・・・。すばる、うちにこない?」
とっさに、言われたことに意味がわからなかった。頭の中で、何度も反芻する。
「・・・それって、どういう・・・?」
結局、わからなくて問いかけた。
「距離的に考えて、うちから学校行くの、そんなに苦じゃないだろう?親御さんとも相談して・・・うちで一緒に住まない?」
一臣は丁寧に言い直した。
ここに、一臣と一緒に住む!?
一臣の言いたいことはわかったが、意図が全く理解できなかった。なんのために?どうして?
ぐるぐると頭の中が混乱する。
「ちょっと考えてみてくれる?」
考えるって、そんなの。答えは決まっている。「無理」だ。あの親が、他人に迷惑をかけることを許すはずがない。が、一臣は本気のようだった。
「まぁ、答えは俺の秘密を聞いたあとでいいから。」
遅いからおやすみ、と一臣は脱衣所を出て行った。
翌日、微熱はあったものの、さして辛くもなかったので、学校へ行くことにした。一臣は言ったとおり駅まで送ってくれ、辛かったら休ませてもらうように、と強く言って出勤していった。
昨夜は、風呂から上がると、時間が遅かったこともあり、すぐに客間へと押し込まれた。約束の秘密の話は、また今度、とはぐらかされた。
ベッドの中で、一日のことを振り返る。色々あったように思う。中でも、最後に一臣の言ったことは、眠れなくさせるのには十分の内容だった。
一緒に暮らす。
つい先日会ったばかりの他人だ。しかも普通の関係とは言いがたい。どうしてそんなことを言うのか、全くわからなかった。ただ、一臣は、こうも言った。秘密を聞いたあとでもいい。一臣の秘密とはそれほど重いものなのか・・・。優しく微笑む姿からは、想像することができなかった。それ以前に、一臣についての情報が少なすぎた。職業はどうやら医者で、年は28歳。名字は佐伯。金に不自由しているそぶりがないことが、年齢からいえば不自然のような気がした。不自由していないのではない。無駄な使い方をしていると言っていいだろう。男を買うのに一人30万。しかも、17人目だと言っていた。買ってもらっておいて言うのもなんだが、馬鹿げていると思う。
持ってきた荷物の中には、あの夜一臣から手渡された白い封筒が入っていた。中身に手はつけていない。使う気もなかった。欲しいものなどなにもなかった。
そんなことを考えて、眠りについた。ベッドの寝心地は良く、ケータイのアラームをセットしておかなければ、危うく寝過ごすところだった。
放課後、駅に向かって歩いていると、ケータイが震えた。一臣からのメールだった。『アパートに迎えに行く。待ってて。』荷物の半分は一臣の家に置いて来てしまっていて、どうしようかと思っていた矢先だった。傷の痛みは大分引いていたが、歩いて一臣の家に行くには駅からの道がわからなかったし、なにより家には鍵が掛かっている。一臣が帰ってくるまで外で待つには、まだまだ気温が高すぎた。病み上がりの自分には過酷な環境だった。メールにほっとしている自分がいた。いつも通りに、アパートに帰ることにした。
7時を回った頃、夕ご飯をどうしようかと思っていると、チャイムが鳴った。扉を開けると、一臣だった。一臣の定時は、7時前後らしいことが察せられた。
「こんばんは。・・・具合どう?」
「こんばんは・・・。悪くないです。」
答えて、ここで話していていいのかと迷う。上がってもらうべきか、それとも。その気配を感じ取ったのか、一臣は少し笑うと、ご飯食べに行こうよ、と言った。そしてどういうわけか、明日の着替えを用意するように言う。
「今夜も、お泊まり・・・ですか?」
「うん。悪いけど、ちょっと長い話をするから。」
長い話とは、秘密のことだろうか。それとも一緒に住む、というあれだろうか。アパートから登校しない、ということにも少々の抵抗があった。万が一にもないだろうが、親に知れたら何を言われるかわからないからだ。黙っていれば、わからないことだろうが。
意を決して従うことにした。
ファミレスで夕食をとった後、一臣はまっすぐ帰路についた。昨日と同じく、家の中へと招かれ、客間に荷物を置いてくるようにと言われた。それが済むと、リビングへと通される。明るい色の家具で統一された部屋の奥には、カウンターキッチンが見えた。清潔感があると言えば聞こえがいいが、使っているのかどうかあやしい感じだった。生活感がないと言ってもいい。リビングには他に、大型のテレビと、コレクションボードがあった。様々な形のグラスと、何種類かの琥珀色の酒の瓶が置いてあった。自分の前では、アルコールをとらない彼の意外な一面を見た気がした。
「お風呂、先に済ませようか。今日も暑かったものね。・・・長い話になるし。」
一臣はそう言うと、風呂の支度をしに行ってしまった。ソファーに座っていいものかと立ち尽くしていると、ややあって一臣は戻ってきた。
「座ったらいいのに。」
苦笑されて、うなだれる。他人のテリトリーで、くつろげる性格ではないのだ。自分は。
「何か飲む?」
座るよう言い置いて、一臣は冷蔵庫を開ける。
「おまかせします。」
「なんて・・・君用に買っておいたよ。はい、どうぞ。」
一臣の手にはグラスと、オレンジジュースの紙パックがあった。最初に会った日に、レストランで何を頼んだか覚えていたのだ。子供みたいな注文をしたと恥ずかしく思ったが、一臣の気遣いがくすぐったかった。
「ありがとう。」
グラスに注がれるオレンジジュースに、素直に礼を言う。
「あぁ。やっと笑ったね。」
一臣は、向かいのソファーに腰を下ろすと、微笑んだ。
「ずっと緊張してたり、具合悪かったりだったろう。・・・よかった。」
言われて、そうかと思う。初めて会った日は酷く緊張していたし、その後も居心地が悪いばかりで、笑う余裕などなかった。一臣は、ずっと笑いかけてくれていたのに。
「ごめんなさい・・・。」
「いいよ。無理もない。・・・あんなこと平気でするような相手と一緒にいて、緊張しないわけがないものね。」
あんなこと、とはあの夜の事だろう。一臣はそのことを口にする時だけ、酷く自分を卑下した。
「でも・・・僕の体にはもう、興味がないでしょう?」
バージンを抱くのが好きだと言っていた。嗜虐を好む、と。
一臣は曖昧に笑い、今はね、と答えた。それなら、一臣のすること、とりわけ性的なことや暴力的なことに関しては、恐れる必要はなかった。それがいいことなのか悪いことなのかはかりかねたが。
「あぁ。お風呂沸いたね。飲み終わったら入っておいで。・・・傷に障るから、あまり温まらない方がいいよ。」
頷いて、グラスの中身を飲み干した。
二日続けて、風呂を借りる。二度目ともなれば、少々の慣れもあった。髪を洗い、体を洗い・・・特に傷のあたりは丁寧に洗った。石けんが少し滲みる程度で、我慢できない痛みはなかった。湯船に少しだけつかる。白い浴槽は広く、半身浴ができるように段差になっていた。実家の風呂を思い出す。広さも同じようだった。普段、アパートの狭い風呂に、膝を抱えて入っていることを思うと、足を伸ばしてゆうゆうと入れるこの風呂は、気持ちが良かった。この広さなら、一臣が一緒でも大丈夫なように思う。ふと、髪を洗ってもらったことを思い出した。髪どころか、全身を余すとことなく丁寧に洗ってくれた。その後の情事を思えばこそのことだろうが、決して嫌なことではなかった。むしろ、心のどこかで、あの行為を望んでいる自分がいた。
風呂から上がり体を拭くと、試練が待っていた。自分で、秘部の手当をしなければならないのだ。昨日手渡された軟膏は持ってきていたが、自分でするのは抵抗があった。しばらく悩んだが、どうしてもできずに、薬をパジャマのポケットにしまって、脱衣所を出た。
リビングに戻ると、一臣がミネラルウォーターのボトルを差し出してくれた。
「お湯の温度大丈夫だった?」
「はい・・・。」
「・・・手当、ちゃんとできた?」
どき、と動きが止まる。視線は軟膏を忍ばせたパジャマのポケットのあたりを見てしまっていた。
「してあげようね。」
一臣はいったんキッチンに行き、手を洗って戻ってきた。
「ソファーに後ろ向きに上がって。足開いてね。体は背もたれに預けると楽だよ。」
言われたとおりに体が動く。何故か、一臣の指示に従ってしまう自分を不思議に思いながら、軟膏を手渡した。パジャマごと下着を下ろされてから、なかなかに恥ずかしいポーズをとらされていることに気がついたが、遅かった。一臣は素早く昨夜と同じ手当を施すと、なにごともなかったようにパジャマを元に戻してくれた。
「今日は泣かなかったね。痛み、大分引いたの?」
頷く。
「よかった。やっぱり、榊に頼んで正解だった。」
一臣は苦笑すると、入れ違いに風呂へと向かったようだった。
一人残されたリビングで、ぼんやりとテレビを見ながら、渡された水に時々口をつけ、一臣を待つ。ニュース番組が流れていた。天気予報によると、明日も暑いようだった。今年は残暑が厳しい。この暑さも、今頃はもう感じている予定ではなかったのだが。自分の立てた計画がフイになった今、少々投げやりな気持ちになっているのは否めなかった。そうでなければ、おそらく自分は今ここにはいないだろう。どうにでもなれ。そう思う自分が、一臣の帰りを待っていた。
テレビの番組が変わる頃、一臣が部屋着に着替えて戻ってきた。冷蔵庫に行き、ミネラルウォーターのボトルを手に、ソファーの向かいに座る。振り向いて、背後のテレビを消した。
いよいよ、だ。
一臣はながながとため息すると、わずかに首を傾けて、目をじっと見つめてきた。
「君・・・まだ死にたいと思ってる?」
一度はその覚悟を決めたのだ。揺らいではいるが、全くないとは言い切れなかった。
「一臣さんの・・・言うことが確かなら。早く寿命がこないかな・・・って思ってます。」
輪廻の話。自殺者は生まれ変われないのだと。それならば、一日でも早くその日が来ることを祈らずにはいられない。
「そう・・・。」
一臣はまたため息をついた。
「秘密の話、長くなるけど・・・聞いてくれる?」
頷いた。
一臣は、水を一口含むと、ゆっくりと飲み下した。
「・・・この家はね、俺と妻と、生まれてくる子供のために用意したものなんだよ。」
一臣の話は、出だしから衝撃的だった。結婚しているとは思わなかったからだ。一臣の年なら、ありえなくはないだろうが、その気配は少しも感じられなかった。
「俺の性癖を知ってるだろう?母は知らなかったけど、父は、そのことを酷く心配していてね。仕事が決まるとすぐに、何度か見合いをしたんだ。大体の相手は、俺が女は相手にできない、と話せば納得してくれたんだけどね。それでもいい、って言った人がいて。両親の手前、結婚することになったんだ。それで、家を買って・・・。少しして彼女は妊娠したんだ。両親とも喜んでね。特に父は、俺の子供を見られると思っていなかったみたいで。だから検診の付き添いとか、かって出てくれていたりしたんだよ。俺は、仕事が忙しかったから、ついていてやれなくて。・・・お腹の子が6ヶ月の時だった。その日も検診で、両親が病院に付き添いで車を出したんだけど・・・。途中でね、交通事故に遭って。助かったのは妻だけだった。両親は即死。お腹の子は流産した。それが、三年くらい前。」
こくり、と喉が鳴った。あまりに過酷な内容で、どんな顔をしていいかわからなかった。ただ黙って頷く。
「以来、妻は病んでしまってね。気分がふさぐとか、眠れないとか・・・。当然だろうけど。・・・専門の病院を紹介する、って言ったんだけど、嫌だって言うものだから、俺が睡眠薬を処方したんだ。専門は内科だけど、それくらいのことはできたから。あぁ・・・その頃は、ちょっと大きい病院に勤めていてね。」
榊が医者だと言っていたのは、どうやら本当のことだったらしい。
「その頃からかな。学生時代につきあってた彼と、時々会うようになって。うちの両親に世話になったから、って葬儀の時にわざわざ来てくれてね。それがきっかけで・・・。妻は、それに気がついたんだと思う。俺が会っている相手が、ただの友達じゃないって事。だから、あの日、彼女は試したんだ。俺が、彼と彼女のどちらを選ぶか。彼女は、貯めた睡眠薬を大量に飲んで、自殺を図ったんだ。幸い命は助かったけど、重い後遺症が残ってね。発見が遅かったから・・・。
俺がその日、彼を選んだから。」
一臣はまた、深いため息をついた。その頃のことは、思い出したくないのだろう。
「その後、彼女は実家で療養することになって、彼女の両親の意向で離婚することになった。俺は、それに従ったんだ。
俺は、俺の処方した薬で、人を一人殺しかけたんだよ。彼女の人生を駄目にしたことを思えば、殺したも同じだね。それが俺の秘密。」
殺した。そう言って、一臣は自嘲した。
「酷い男だろう?・・・そのことが原因で、当時の病院にいられなくなってね。今は企業の産業医をしてる。会社の保健室の先生みたいなもんだよ。勘が鈍るから、時々当直のバイトを入れてるけど、それくらいじゃ医療現場には追いつけない。榊が藪医者だって言ったのは、彼女のこともあるけど、実際なまった俺の腕のことを言ってるんだよ。」
一臣の話が、嘘や作り話の類いでないことは、雰囲気で察せられた。
「・・・その・・・彼氏・・・さん?とは・・・?」
おそるおそる聞いてみる。
「彼女の自殺未遂を期に、縁を切ったよ。後悔したから。彼も納得してくれた。学生時代つきあってた、俺の最初の男だったんだ。一番長くつきあった。いろいろあって別れたけど、両親がいっぺんに亡くなって、気を使わせたんだろうな。時々悪い酒につきあってくれたんだ。それだけだったのに・・・。」
かける言葉もなかった。酷い話だと思った。どんなことが起きたら、男を17人も買うような人生を送ることになるのだろうかと思っていたが、納得せざるを得なかった。
「実家は、兄夫婦が継いでね。遺産が少し入ったから、この家のローンにあてて。それで終わり。あとはもう・・・何にも残ってなかったから・・・荒れてね。月に一度、君としたみたいなことをして、給料をドブに捨てる生活をしてるんだよ。」
ドブ・・・。
一臣は自分のしている行為が退廃的なものだとわかっているのだ。それでもなお止められないほどの、深い傷を負ったのだ。たぶん、元奥さんの『自殺』で。
だから、あんなに「死なれたくない。」と繰り返したのか。
今なら、彼の言動が少し理解できる気がした。
医者だからとか、身近な人の自殺未遂を経験したからとか、そんな複雑な思いが、今ここに自分を置いているのだろう。そして、秘密を打ち明けた。
けれど、腑に落ちないことが一つあった。
どうして、自分なんかのために、大切な秘密を口にしてまで、つなぎ止めようとするのか。それがわからなかった。一臣にとって、命とは等しく平等なものだということだろうか。自分には、そうは思えなかった。
「秘密の話は、これで終わり。・・・さて、どうする?すばる。」
どうする?とは、ここで一臣と一緒に暮らすかどうか、についてだ。
一臣がどうしてこんな広い家に一人で住んでいるのか知ってしまった今、なぜか心に強く思う気持ちがあった。
このまま、一人でいちゃいけない気がする。一臣も。自分も。
おそらくは、一臣もそう思ったのだろう。
これ以上、自分に関わった人間が、命を縮めないために。
けれど・・・両親を説得できるだろうか?話を聞いた限り、社会的な身分は申し分ないだろう。働いているのが病院ではないだけで、一臣は医者だ。母親に関して言えば、そういう肩書きに弱いところがある。だが父親は?どこの誰とも知らない男に、いらないとはいえ息子を預けるだろうか。世間体を重んじる人間だ。一臣が万が一同性愛者だと知れれば、許されることはまずない。けれど・・・高校生の一人息子をアパートで一人暮らしさせておくよりは、マシかもしれないと思うかも知れない。天秤の針は微妙なラインで揺れているように思えた。
「父を・・・説得できれば・・・。」
自分の気持ちは決まっていた。一臣のそばにいたい。一人にしておきたくないと思った。
「・・・こういうのはどう?俺は忙しい医者じゃないけけど、肩書きは役に立つだろう。君の勉強を見ることにして。これでも医学部ストレートで入って卒業してるからね。君の進学先が文系だと、ちょっと厳しい言い訳になるけど。」
なるほど、と思った。しかし、決定打に欠ける気がする。
「・・・すばる、名字、早乙女って言ったっけ?」
一度、身分証を見せたのを覚えていたらしかった。
「うん。」
「もしかして、お父さん学校の先生だったりする?高校の。」
確かに父はこのあたりでは有名な私立高校の教師をしている。それだけに、融通が利かない。しかし、なぜそれを一臣が知っているのか。
「ひょっとして、俺のこと覚えているかも。」
「え?」
一臣が、父の学校の卒業生??そんな偶然って。
「ちょっと待ってて。アルバムとってくる。」
だが一臣は確信があるらしく、階段を上がって行ってしまった。ややあって、卒業アルバムを持って戻ってくる。10年ほど前のものだ。その高校の名前は、確かに父の勤めている学校だった。
「ちょっと古いけど・・・主席だったから記憶にあるんじゃないかな?授業は受けたことないけど。生徒会にいたし。お父さんって、今も学生指導部にいたりする?」
そう言われても。父親がどんな仕事をしているかなど、漠然としか知らない。
「わかりません・・・。」
「そう。」
それにしても、主席、って・・・。医学部にストレートならそれもそうかと思うが。人は見かけによらない。
「でも・・・もし、覚えてたら、説得できるかも。」
「一人じゃ難しいかも知れないね。日曜日の都合が良ければ、俺がきちんと挨拶しにいくよ。大丈夫。猫をかぶるのは得意だから。」
少しいたずらっぽく笑う一臣に、苦笑する。
あの優しげな微笑みは、もしかしてかぶった猫だったのかと思った。
日曜の午後。久しぶりの自宅は、すこぶる居心地が悪かった。滅多に入ることのない客間に通され、冷たい麦茶を差し出される。そのグラスも、時間を追うごとに汗をかいていた。まるで背中を伝う冷や汗のようだ。
隣には一臣が座っていて、両親を前にとうとうと、まさに立て板に水といった調子で嘘を並べていた。
なんでも、自分と一臣が出会ったのは七月、夏休みの初めで、補講の帰りに駅で気分が悪くなったところに偶然居合わせ、医務室へと送り届けたのだそうで。その際に、どうしても後でお礼がしたいからと自分が強引に連絡先を聞き、以来時々連絡を取り合っているのだという。そして、先日も体調を崩し、アパートで一人暮らしをしていることが知れ、そのことを心配した一臣が、同居を申し出た。産業医とはいえ医師免許は持っているし、勉強も見てやれる。家事のできる自分が、家にいてくれると非常に助かる。・・・と言うようなことを、あの温和な声音、真面目な顔で平然と言ってのけたのだった。たいした猫をかぶっている。この時点で、母親は「落ちた」。だが父親は納得していないようだった。一臣が、自分の勤める高校の卒業生であると言うことは、自己紹介をした時に明かしている。良い印象を持っていることは確かだったが、なかなか首を縦には振らなかった。
「すばるくんのお姉さん、ご結婚の予定がおありだとか。おめでとうございます。だだ・・・そのことをすばるくんが気にかけているようで。自分が家にいたら、お姉さんの迷惑になるのでは、と。そんなこと、あるはずないと話したんですが・・・どうも。多感な時期ですからね、なにか思うところがあるのでしょう。僕は、カウンセラーの資格も持っていますから、しばらく彼を預けてみてはもらえないでしょうか?」
僕?・・・カウンセラー・・・??初耳だ。
「気持ちが落ち着いたら自宅に戻れば良いのではないかと・・・。」
一臣はどうやら「同居」から「一時預かり」に戦略を組み替えたらしかった。この言い方なら、世間体を重んじる父の印象も変わるかも知れない。そしてそれは、当たりだった。
「わかりました。・・・娘の結婚の話も、まだまとまってはいませんが・・・そうまで言ってくれるなら。ただし・・・。」
ただし?
「期限を設けましょうか。いつまでもだらだらとというわけにもいかないでしょう。あなただってまだ若い。これから再婚の話もあるでしょう。この子の進学先が決まるまで、ということで。」
再婚・・・。
父親の言った言葉に、思わず一臣の顔を仰ぐ。
「高校を卒業するまで・・・ということですか?」
「大学に進学するなら、そういうこともあり得るでしょう。ただうちは、この子を医学部にやるつもりはありません。」
もとよりそのつもりはないが、「そんな金は出せない。」そう言っているのだ。何しろ、自分が勤める私立の高校ではなく、公立の高校に通わせているくらいだ。学費は最小限に抑えたいのだろう。
「・・・わかりました。」
父親の出した条件を、一臣は了承した。
その後、今住んでいるアパートをどうするか、引っ越しはいつするのかなどをざっと話した。全ての話がすむ頃には、西日がきつい時間になっていた。
一臣に連れられて、自宅を後にする。とりあえず、今日帰るのはアパートだ。整理はできていたが、引っ越すとなれば話は別だ。持って行けないものを処分したりしなくてはいけない。
それにしても。
一臣の運転する車の助手席で、ちらりと顔を伺う。
頭がいい、というのを前提にしたとしても、あぁもすらすら嘘がつけるものだろうか。
「一臣さん、嘘は嫌いって・・・。」
自分には何度も、嘘はつかないで、と言ってきた一臣だ。言葉尻がどうしたって嫌みのニュアンスだ。
「時と場合によるでしょ。おかげで何とか丸め込めました、っと。」
一臣は満足げだ。
「でも、卒業までって・・・。」
ずっと一緒にいられるとは思っていなかったが、切られた期限はあまりにも短いような気がした。
「って言ってたね。・・・まぁ帰すつもりはないよ。」
「え?」
「あの家に、君の居場所はないだろう。」
言い切られて、俯く。
あの場で、一臣が感じたことを、そのまま口にしただけだろう。だが、他人にそう言われるのは、自分で思うのとはわけが違った。
「やっぱり・・・そう見えるんですね。」
「見えるね・・・。まぁ俺のうちは二人兄弟だけど・・・進学先くらい好きにさせてくれたしね。高校も、好きで通ってるんじゃないんだろ?・・・愛情はないのにレールには乗せておきたいなんて、エゴだね。」
「・・・でも、親だし。」
二十歳までは、自分の人生は親のものだと思う。その前に、リタイヤしようとしたわけだけれど。
「俺は鈍い方じゃないからね。・・・あの部屋、お姉さんの写真や賞状なんかは飾ってあるのに、君のは一つもなかった。・・・君の話を信じていなかったわけじゃないけど、あそこまであからさまだとは・・・。」
一臣は忌々しげに言った。そして、口調を緩めると、車線から視線をそらさぬままに言葉をつなげた。
「あそこにいたら、君は本当につぶれてしまうよ。・・・そんな風にはさせない。」
何故?
「一臣さん・・・なんでそんなに僕にかまうの?」
「・・・なんでだろうね?」
問いは、問いで返された。
翌週。引っ越しは思ったより早く片付いた。アパートで使っていたベッドや机を処分すると、案外身軽だったからだ。しかしながら一臣の車では、何度も往復させることになりそうだったので、業者を手配した。金は、あの日一臣から手渡された封筒から出した。その使い道なら、間違っていないような気がしたからだ。
一臣の家で与えられたのは、最初に通された客間だった。衣類をクローゼットにしまい、教科書などの本を棚に収め、パソコンの環境を整えると、ほぼ作業は終わりだった。新たに買い足したものは特になかった。一臣は、カーテンや寝具も自分好みに変えて良いと言ったが、期限があることを思うと、とりあえずはこのままでいいように思った。
遅めの昼食を、ダイニングキッチンで二人、向き合って食べていると、一臣が口を開いた。
「駅までの道順、後で確認しなきゃね。あー・・・自転車いるかな。歩きだとちょっと厳しいかも。雨の日は送るけど、毎日はちょっと難しい。」
「そう・・・ですか。わかりました。お金、まだ余ってるし。大丈夫です。」
「お金・・・ってあのお金使ったの?」
引っ越し費用も出さないのかあの親は。と一臣が憤る。
「いいんです。だって、僕のわがままだし・・・。」
「わがままとは少し違うと思う。俺は了解を得て君をここに連れてきたんだ。悪いけど、おかしいと思ったら、俺は口に出しちゃうかもしれない。」
口角を下げて不機嫌になる一臣が、なんだか可笑しかった。他人の親のことなど、どうでもいいだろうに。けれど、心のどこかで、「おかしい」と肯定されることが嬉しかった。違和感を感じているのが自分だけではないと知れたからだ。もしかしたら、思い込みなんじゃないかと思っていた時期もあった。けれど現実は、やはりそうではないらしかった。
「自転車は俺が買ってあげるよ。引っ越しのお祝い。・・・それから、あのお金はなるべく使わないようにしなさい。必要なものがあれば、用意するから。」
「そんな・・・。おいてもらえるだけでもありがたいのに。」
一臣に迷惑をかけたくなかった。
「大家なんだから、世話をするのは当たり前なの。」
いいんだよ。とカップ麺のスープを飲み干す。
「それに、あのお金は君にとって大切なお金でしょう?」
バージンと引き替えにした金だ。それが大切と呼ぶに値するのかわからなかった。二度と手にすることのない金ではあったが。
「・・・そうだ。すばる、今までは自炊だったんだよね?」
問われて頷く。たいがいの家事はこなせた。
「ご両親の手前、家事ができる人が欲しいって言ったけど、あれ半分は本音なんだ。余裕のある時でいいから、掃除とか洗濯とか、任せてもいいだろうか?」
「そんな・・・。やらせてもらえるなら何でもします。」
ただでおいてもらって、衣食住まかなってもらうことなど、無理な相談だった。できることがあるのなら、させてもらいたかった。それを仕事と呼んで、対価を得ることが果たして等価と呼べるかどうかは謎だったが。
「よかった。じゃぁ、あとで家の中案内するから。あ、あとこれ。」
小さな白い封筒を差し出される。開けてみると、それは鍵だった。
「すばるのだよ。」
「・・・・・・。」
ここに住む以上、必要だとは思うが。荷物も運び込んでしまっているのに、『鍵』の重さに緊張した。
「あの・・・。今更ですけど。本当に、いいんですか?」
「いいの。もらってね。」
「・・・はい。」
一臣はペットボトルの水を口にする。
「それから・・・少しずつでいいんだけど。・・・敬語、やめられないかな?」
え?
「敬語・・・ですか?」
「うん。そうそれ。」
10も年の離れた大人を相手に、敬語で話すな・・・とは。どうしたものか。
一臣の見た目は若く、いつか本人が言っていたように、年の離れた兄弟のように見えなくもないかも知れない。けれど、知り合ってまだ間もない。距離の取り方がわからなかった。
「どんな風にすればいいですか?」
敬語を使わない関係と言ってもいろいろあるだろう。友達とか・・・恋人・・・とか。
「もう少しリラックスできないかなって。まぁ・・・君は野良猫みたいなものだから、急に懐いて見せろって言っても無理か。」
一臣は苦笑する。
そうか。一臣の中で、自分は拾われた野良猫ということか。
その表現が、妙に自分には合っているような気がして、笑ってしまった。
「僕、猫ですか?犬っぽいと思うんですけど。」
主人の命令には忠実だ。この家での主人は一臣ということになる。言われれば何でもするだろう。
「犬?・・・そうか。犬か。」
一臣も笑う。
「猫なのは一臣さんでしょう?ものすごい猫かぶり。びっくりしちゃった。」
先週の早乙女家のことだ。あの演技力たるや拍手喝采もいいところだ。おかげで今自分はこうしてここにいられる。少しの偶然も手助けしてくれたけど、そこはやはり、一臣の肩書きと、かぶった猫の皮の厚みのなせるわざと言えよう。
「すばる・・・笑ってな。笑うと可愛い。」
「えっ?」
かぁっと顔が熱くなるのを感じた。可愛い、なんて言われるのは初めてだった。なにしろ女の子ではないというだけで、姿形などどうでもいい家に育っている。正直、自分の顔は他人から見てどうなのか、まったく興味がなかった。今までは。
一臣は同性愛者だ。その彼の好みに、少しでも近かったらいいと思った。野良猫でも、器量が良ければ可愛がられるかも知れない。
自分はまた、彼に両親からは得られなかったものを求めようとしているのかも知れなかった。
愛情がなんだかも、よくわからなかったが。
「僕、可愛いですか?」
箸を置き、膝の上に両手をそろえる。
「可愛いよ。線が細くて、色白いし。髪も栗色。その長さもよく似合ってるしね。」
引きこもりのもやしっ子なだけなんだけど。
「あの・・・。一臣さんの好みとは、どうですか?」
おそるおそる、上目遣いに尋ねる。
一臣は苦笑して、右手で口元を隠した。
「可愛い・・・と思ってるよ。」
良かった。
しかし一臣は、真面目な顔をしてこう続けた。
「君はゲイじゃないだろう。普通の男の子だ。特別俺の好みである必要はないんだよ。」
何を言われたのか理解するのに、数分の時間を要した。
一臣は、自分を性的な対象としては見ていない。それどころか恋人としても不適格だと言っているのだ。
自分は、一臣の声も、笑う顔も、指も・・・仕草の全てにこんなに惹かれているのに。
一臣が言うように、自分はゲイではないかもしれない。でも、そうじゃないとも言い切れない。何しろ自分は、一臣に抱かれて、嫌悪感を抱くことはなかったし、少なからず満足したのだ。
いや・・・そうじゃなくて。
もしかして。
それは相手が、一臣だから・・・?
「僕・・・ゲイじゃないの?」
「・・・女の子になりたい願望を持ってるだけの・・・普通の男の子だよ。」
「でも・・・。」
「前にも言ったろう?まだ自分の性癖なんてはっきりしてないよ。」
「でも・・・。」
そうなんだろうか。一臣の言うことが正しくて、自分は間違っているのだろうか。
一臣にされるのは嫌じゃない。そう思うのに、確かめる術がなかった。一臣はもう、自分の体には興味がない、と言っていたのを思いだしたのだ。
「僕は、一臣さんのこと・・・。」
なんと続けようとしたのだろう。
「すばる。俺は悪い大人だから、それ以上言わない方がいい。考えない方がいい。つけあげるよ。なにをしてしまうかわからない。」
今度こそ、一臣の言っていることがわからなかった。
「すばるのそれは、インプリンティングだよ。・・・今日の課題だ。調べておいて。」
一臣はそう言うと、二人分のカップ麺の容器をキッチンへと運んでいった。
食事の後、家の中を案内された。一階にはLDKと書斎。バスルームと洗濯スペース、納戸があった。キッチンにはパントリーもあったが、食材はほとんど置かれていなかった。二階は、与えられた客間と、一臣の寝室、そのほかに二部屋あった。今は使っていないとかで、一部屋は鍵が掛かっており、もう一部屋は物置として使っているらしかった。物置と言っても、スペースには十分余裕があったが。
バルコニーはサンルームになっていて、洗濯はそこに干すように言われた。ガラス張りのそこは、風雨の心配なく一年中洗濯が干せるとのことだった。間取りや導線を見る限り、やはりこの家は将来的に家族で住むことを前提に立てられたのだと察せされる。トイレも当然のように一階と二階にあった。だから、キッチンの説明を受けている時も、もやもやとした気持ちになった。きっとこのスペースは、元奥さんが使いやすいように設計されたものなのだろう。シンクの高さが少し低かった。IHのコンロを使うのは初めてだったが、それはそれで面白そうだった。それよりも、驚いたのは冷蔵庫の中身だった。食材はほぼ空で、あるのはミネラルウォーターのペットボトル。野菜庫には数本のビール。家で食事をしていないのは明白だった。
「一臣さん・・・。近くにスーパーとか・・・ある?」
語尾に気をつけつつ、話しかける。
「あるよ。二軒。自転車を買ったらいける範囲に三軒あるかな。」
そんな立地でこの冷蔵庫とは。呆れてため息をついていると、一臣は悪びれもせずに言い切った。
「一人のご飯は淋しいの。言っておくけど、俺は乱れた生活してるからね。」
そうだった。離婚してから、荒れている、と言っていた。それは性生活のことだけではなく、日常生活のことでもあるようだった。その割に、家の中は整然としていたが、それは、一臣がほとんど寝るためだけにこの家に帰っていることの証だった。
「じゃぁ、できる限りご飯作りますから・・・。作るから、帰る時メールくださいね。」
「毎日?それじゃ君の負担になるよ。たまには外食しよう?あぁそうだ。二、三約束事も作っておかないとね。」
「約束?」
「朝早いから、11時には寝ること。金曜の夜は、俺の部屋で一緒に寝ること。・・・月に二回、土曜の夜に当直のバイト入れてるから、帰るのは日曜の朝になる。だから、日曜日は昼まで起きないから。」
どうやら、一臣の生活のサイクルを乱すなと言うことらしい。当然と言えば当然だ。病院勤務でないにしても、仕事は医者なのだ。寝不足で仕事をさせるわけにはいかないだろう。
「定時は6時半だから、だいたい7時すぎには帰れるよ。」
すばるの学校は?と聞かれる。
「僕は、5時の電車には乗れてるから・・・。それから夕食の買い物して、じゃぁ帰る頃にはごはん間に合いそうですね。」
「朝はこの間と同じでいいの?」
この間、とは泊めてもらった翌日、駅まで送ってもらった時のことだ。
「一本遅くても大丈夫です。」
「それだと俺が間に合わない。・・・自転車買うまで我慢してくれる?」
「わかりました。」
しかし。さらりと聞き流したが。一臣は約束事の中に、一つ不可解なものを混ぜ込んだように思う。
「あの・・・金曜の夜って?」
「あぁ。休みの前日くらい、君とゆっくり話がしたいでしょう?大丈夫だよ。なにもしないから。」
一臣は苦笑した。怖がらなくていいからね、と。
その後、近い方だというスーパーに二人歩いて買い物に行った。米がないことに気がついたのは店に入ってからで、こんな事なら車で来るべきだったと後悔した。仕方なしに、冷や麦と、トマトとキュウリを買った。出来合いの唐揚げと豆腐を買って、つまみはこれでいいかと思う。そういえば、一臣は自分といる時に酒を飲まない。たまたまかもしれないが。冷蔵庫には冷えたビールがあった。このメニューなら、飲みたければ飲むだろう。調味料の在庫と賞味期限が不安だったので、めんつゆは出来合いのものを買うことにした。
これから、徐々に整えていけばいいよ、と一臣は笑う。それがどこか嬉しそうで、気恥ずかしかった。
一臣は、もう割り切っているのだろう。あのキッチンを使っていた人はもういないのだということを。その人の残した痕跡に、いちいちうろたえているのは自分の方だった。好きなようにしていい、と言われたが、難しいことのように思えた。
夕食と風呂を終えると、時刻は10時半を回っていた。一臣はもう寝るというので、自分も部屋に戻った。引っ越しの疲れがないわけではなかったが、一臣の課題が気になって、パソコンを立ち上げた。『インプリンティング』検索する。どうやら、鳥の刷り込み現象のことらしかった。卵からかえる時に、親鳥以外の生物が目に入ると、それを親だと思い込んでしまうと言うものだった。また、人間の心理学用語でもあるらしかった。初めて好感を抱いたものに対しての執着に似た感情・・・といったところか。一臣が、自分と彼の関係に対して、何故その言葉を使ったのか、よくわからなかった。自分は一臣に好感を持っている。一臣は、それを思い込みだと言いたいのかもしれなかった。それなのに、突き放すでもなくそばに置き、それこそ親鳥のように世話を焼く。一臣が、自分にどうなって欲しいのか、見当がつかなかった。死にたい気持ちがなくなればいいと思っているのは確かだろうが。あるいは野良猫が人に懐くかどうかを、ゲームのように楽しんでいるのだろうか?だが、それは違うように思う。自分は特に、一臣に対して敵意も警戒心も持ち合わせていないといっていいからだ。聡い一臣ならば、それくらいのことはわかっているだろう。ならばなぜ・・・。
一臣の気持ちがわからない。
ぐるぐると彼とのやりとりを思い出す。どれも、自分に好意的に接してくれていたように思う。それとも、そもそもそれが間違いなのだろうか?実家でついた嘘のように。全てが一臣の優しい嘘で。「愛してるよ。」と口にした彼だ。もしかしたら、自分に見せる表情のそこかしこに、嘘が紛れているのかもしれない。それならば、何が嘘で、何が本当なのか・・・。
疑い出すと切りがなかった。自分はあまりにも彼のことを知らないからだ。
自分に向けられる全てを信じたいけれど。一臣には、その背負った過去のせいか、暗い影を負っていて、時々そぐわない言動や表情を見せる。もともとの一臣を知らない自分が、それをそぐわない、と感じることも、またおかしな事なのだろうが。
今まで、こんなに誰かのことを考えたことがあっただろうか。眠れないほど・・・。
とにかく、一臣へのこの感情が「思い込み」だと彼が言うのには、それなりの理由があると言うことなのだ。自分には確信があるのに、彼にそう言われると揺らぐ。
一臣は、繰り返し、自分のことを「普通の男の子」だと言った。まるで、自分を恋愛対象に入れたくないとでもいうように。
けれど・・・。一臣の全てが虚構だったとしても、自分はもう、たぶん、きっと・・・。
これがおそらく、恋愛感情というものだ。刷り込みによるものだとしても、これは恋なのだろうと思えた。
一臣のことが知りたい。
10
お気に入りに追加
156
あなたにおすすめの小説



好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」


噛痕に思う
阿沙🌷
BL
αのイオに執着されているβのキバは最近、思うことがある。じゃれ合っているとイオが噛み付いてくるのだ。痛む傷跡にどことなく関係もギクシャクしてくる。そんななか、彼の悪癖の理由を知って――。
✿オメガバースもの掌編二本作。
(『ride』は2021年3月28日に追加します)

初恋はおしまい
佐治尚実
BL
高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。
高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。
※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。
今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

多分前世から続いているふたりの追いかけっこ
雨宮里玖
BL
執着ヤバめの美形攻め×絆されノンケ受け
《あらすじ》
高校に入って初日から桐野がやたらと蒼井に迫ってくる。うわ、こいつヤバい奴だ。関わってはいけないと蒼井は逃げる——。
桐野柊(17)高校三年生。風紀委員。芸能人。
蒼井(15)高校一年生。あだ名『アオ』。
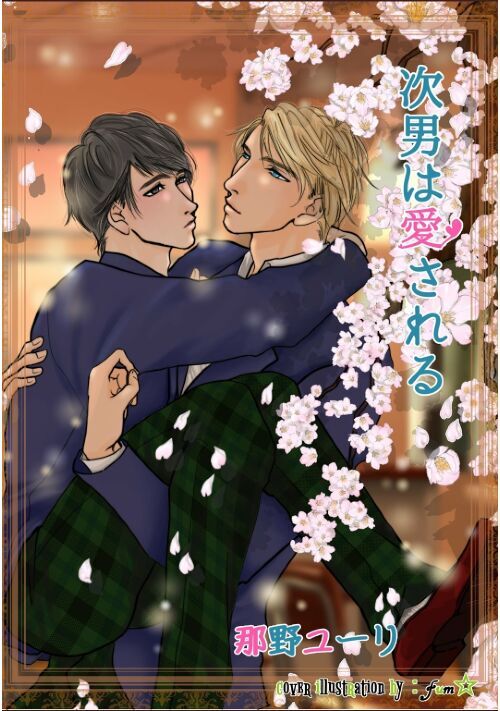
次男は愛される
那野ユーリ
BL
ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男
佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。
素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡
無断転載は厳禁です。
【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】
12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。
近況ボードをご覧下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















